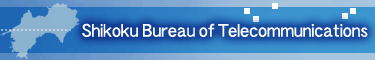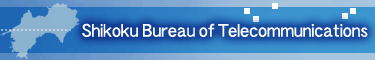<< 1つ前のページへ戻る
(別紙)
「情報通信を活用した防災・減災対策の現状・動向等に関するアンケート調査」の結果
アンケート実施時期:平成24年11月15日から12月末まで
アンケート対象:四国管内95市町村(回収率97%)
1 防災対策全般について
質問1:貴団体の地域防災計画において強調するなど特に重要視している防災・減災対策にはどのようなものがありますか。以下のうち該当するものに印を付けてください。(いくつでも可。)
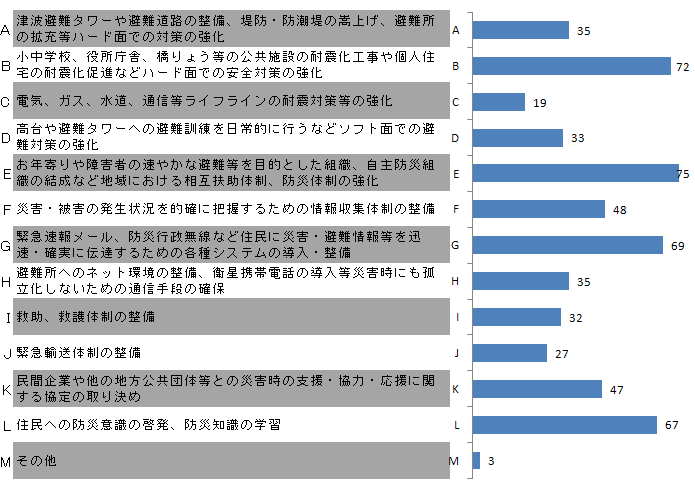
【コメント】
最も重要視されているのは、Eの「地域における相互扶助体制、防災体制の強化」で、Lの「住民への防災意識の啓発等」と併せて、住民を中心とした地域の防災体制を強化しようとする姿勢が見て取れる。
ハード整備の面では、Bの「建物の耐震化等地震対策」が重要視されている。一方、同じハード整備でもAの「津波対策」は、回答数を見る限りそれほど重要視されていないように見えるが、これは、多くの市町村で地域防災計画の中に津波対策を盛り込むための改定作業に時間を要していることが関係していると思われる。
質問2:貴団体がこれまで取り組んできた防災・減災対策のうち、特に取組が遅れていると思われるものは何ですか。以下のうち該当するものに印を付けてください。(いくつでも可。)
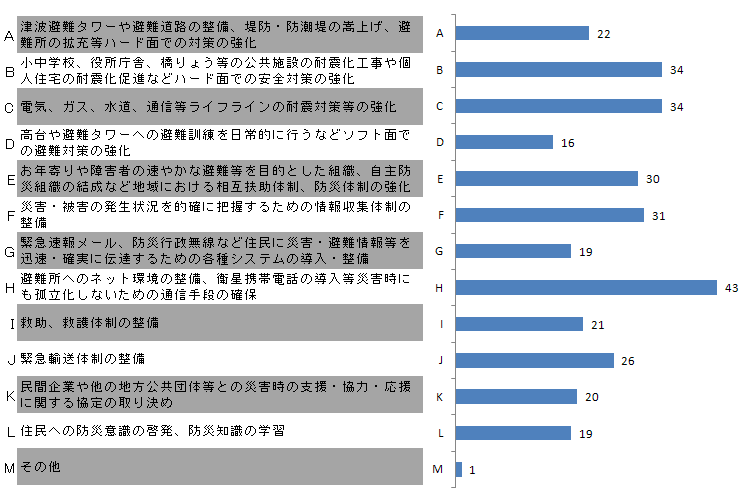
【コメント】
特に取組が遅れている対策として、Hの「避難所へのネット環境整備等通信手段の確保」を挙げたところが最も多い。通信手段確保の推奨は当局の所管でもあるので、今後の積極的な働きかけが必要だと考えられる。
2 防災行政無線の整備状況について
質問3-1:同報系防災行政無線を整備していますか。
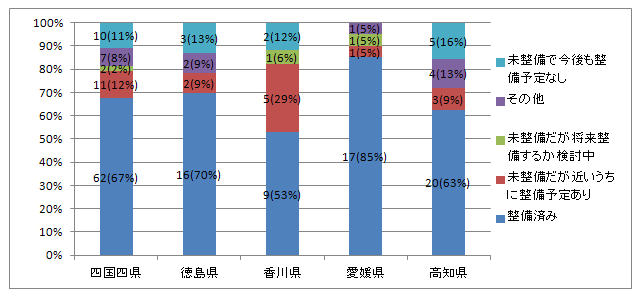
【コメント】
「整備済み」との回答が62件(67%)と大半を占めている。県別に見ると、愛媛県が最も整備が進んでいる。「整備予定あり」や「整備検討中」を含めると、全体の81%に達するが、災害時における住民への情報伝達手段としての同報系防災行政無線の重要性を勘案すると、より一層の整備の進展が望まれる。
※「その他」は、「一部地域でのみ整備済み」などである。
質問3-2:前問で「整備予定なし」と回答の場合、その理由は何ですか。
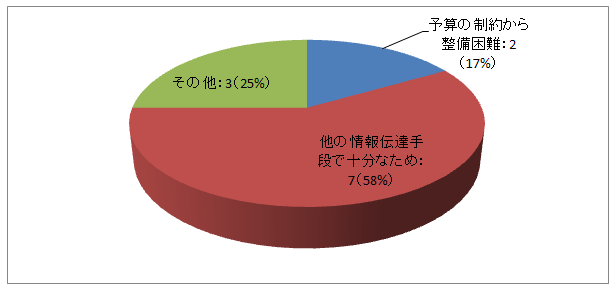
【コメント】
整備する予定がない理由としては、「CATV、MCA無線、緊急速報メール等他の情報伝達手段で十分」との回答が7件と最も多い。住民への情報伝達手段が多様化していることを反映した結果と思われるが、他の手段があったとしても、同報系防災行政無線は情報伝達手段の基盤であることから一層の整備が望まれる。
※「その他」の主なものは以下のとおりである。
- IP告知放送という手段が既にある中、二重整備するのは財政上困難であるため。
- 以前整備していたものを老朽化で廃止したため。
質問4-1:同報系防災行政無線を整備している場合、各戸に戸別受信機を配備していますか。
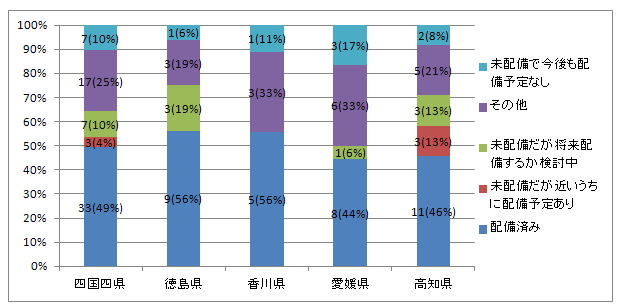
【コメント】
「配備済み」との回答が33件(49%)と約半数である。「その他」の回答が17件と多いが、一部配備済みのことを指しており、これを含めると全体の74%に達するので、戸別受信機が屋外拡声器と相互補完しながら役割を果たしているものと考えられる。
質問4-2:前問で「今後も配備予定なし」と回答の場合、その理由は何ですか。
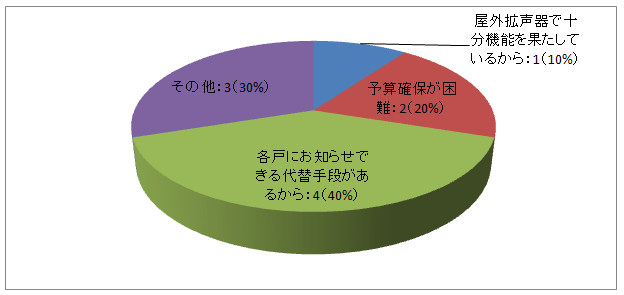
【コメント】
配備する予定がない理由としては、「代替手段があるから」との回答が4件と最も多く、質問3−2と同様、情報伝達手段が多様化していることを現している。なお、代替手段の具体例として回答があったのは、IP告知端末と及び緊急速報メールである。
※「その他」の理由の主なものは以下のとおりである。
- 配備しても、世帯によっては受信機の電源をオフにしたり、音量を絞ることが懸念され、運用の担保が完全には取れないため。
- 代替手段として防災ラジオを検討しているため。
質問5:同報系防災行政無線を整備している場合、J−ALERTの信号を受信して同無線機を自動起動できる装置を導入していますか。
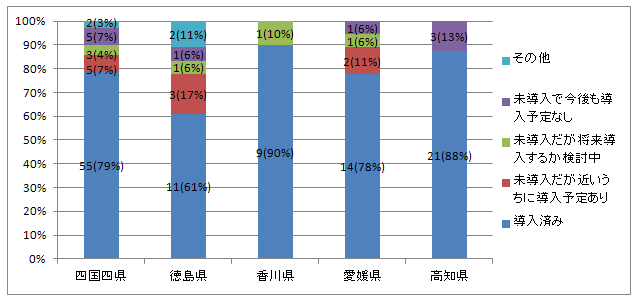
【コメント】
「導入済み」との回答が55件(79%)と大半を占めている。平成24年度補正予算案に自動起動装置等の整備に対する支援施策が盛り込まれていることから、今後導入が一層拡大することが期待される。
※「今後も導入予定なし」の理由としては以下のようなものが挙げられている。
- 支所毎に装置を導入する必要があるため費用がかさみ、予算確保が困難なため。
- IP告知端末を自動起動できるようにしているため。
- メール配信システムを整備しているため。
質問6-1:整備している同報系防災行政無線はアナログ方式ですかデジタル方式ですか。(アナログ方式の場合、デジタル方式への更改予定の有無についても質問。)
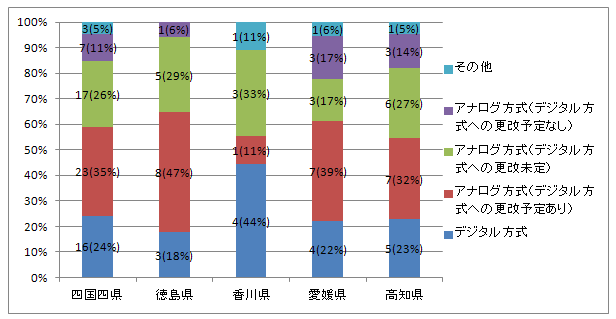
【コメント】
アナログ方式が合計47件(72%)、デジタル方式が16件(24%)であり、国の方針としてデジタル化推奨を掲げているものの、その進捗は十分とは言えない状況である。県別に見ると、香川県のデジタル方式が44%で、四県の中では最もデジタル化が進んでいる。
デジタル方式への更改意向に関しては、「更改予定あり」が23件(35%)と最も多く、今後のデジタル化の進展が期待される。一方、「予定なし」、「未定」の合計も24件(37%)に及んでいる。
質問6-2:デジタル方式に更改する予定がない場合、その理由は何ですか。
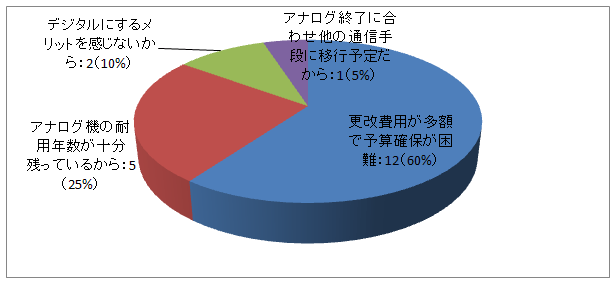
【コメント】
「予算確保が困難」との理由が12件(60%)と最も多く、デジタル化は財政上の負担と市町村が感じていることが分かる。一方、「メリットを感じないから」との回答は2件と少ないため、デジタル化のメリット自体は各市町村にある程度浸透しているものと推測できる。
質問7-1:移動系防災行政無線を整備していますか。
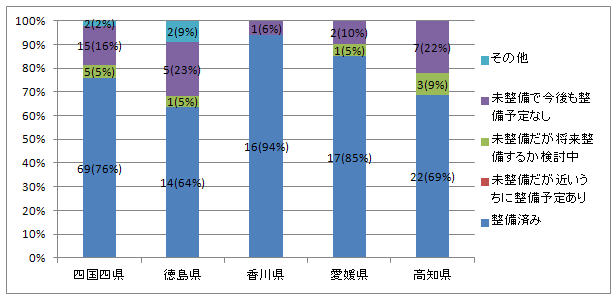
【コメント】
「整備済み」との回答は69件(76%)で、同報系防災行政無線(整備割合67%)以上に整備が進んでいる。県別に見ると、香川県における整備が特に進んでおり、「整備済み」が94%となっている。
大半の市町村で整備されていることから、災害時等における情報伝達手段として、移動系防災行政無線が重要視されていることが分かる。
質問7-2:前問で「今後も整備予定なし」と回答の場合、その理由は何ですか。
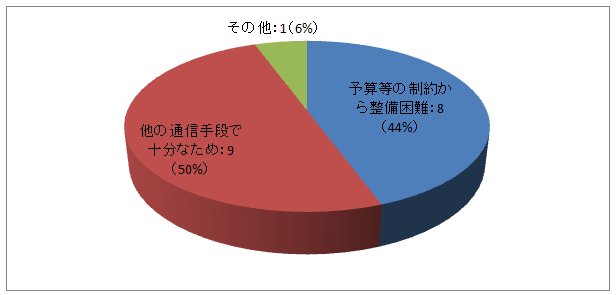
【コメント】
整備予定なしの理由としては、「他の通信手段で十分」との回答が9件と最も多く、通信手段の多様化が見て取れる。
なお、他の通信手段の例として回答があったのは、デジタル簡易無線と消防無線である。
また、予算上の制約を理由として挙げた市町村も8件と多く、移動系防災行政無線の整備に多額の財政支出が必要であることが分かる。
質問8-1:整備している移動系防災行政無線はアナログ方式ですかデジタル方式ですか。(アナログ方式の場合、デジタル方式への更改予定の有無についても質問。)
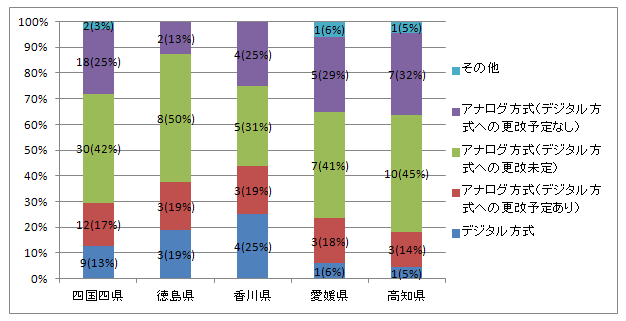
【コメント】
アナログ方式が合計60件(84%)、デジタル方式が9件(13%)と圧倒的にアナログ方式が多く、デジタル化の進捗は、同報系防災行政無線よりも遅れていることが分かる。県別に見ると、香川県のデジタル方式が25%で、四県の中では最もデジタル化が進んでいる。
デジタル方式への更改意向に関しても、「予定あり」は12件(17%)と少なく、「ない」と「未定」の合計が48件(67%)と大半を占めている。
質問8-2:デジタル方式に更改する予定がない場合、その理由は何ですか。
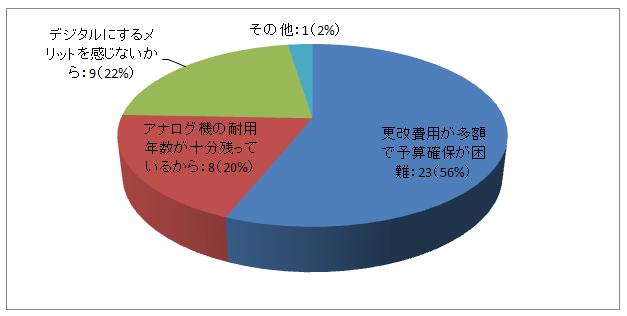
【コメント】
「予算確保が困難」との理由が23件(56%)と最も多く、同報系防災行政無線の場合と同様、デジタル化は財政上の負担と市町村が感じていることが分かる。一方、「メリットを感じないから」との回答は9件(22%)と比較的少ないため、デジタル化のメリット自体は各市町村にある程度浸透しているものと推測できる。
3 四国総合通信局の防災支援策について
質問9-1:四国総合通信局では災害発生時の電源供給確保のため、地方公共団体に対して無償で移動電源車(5.5キロボルトアンペア)の貸出をおこなっています。このことを知っていますか。
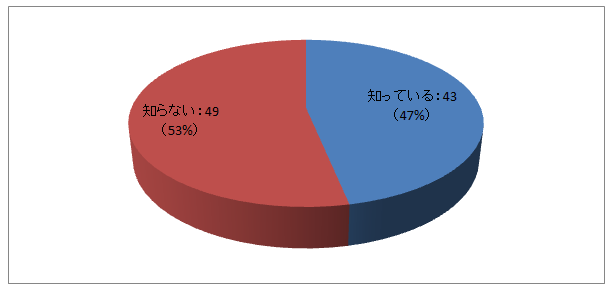
質問9-2:災害発生時に電源供給が途絶えたような場合、前記の移動電源車の貸出を希望しますか。
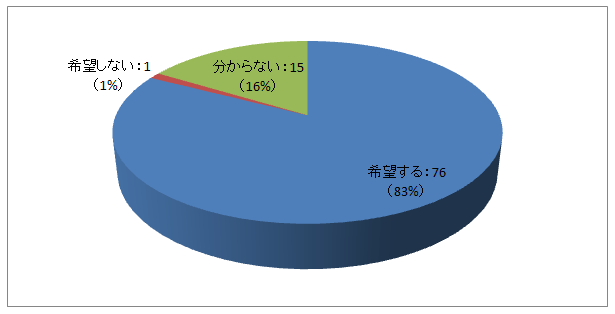
質問9-3:移動電源車の貸出に関してご質問や改善意見等があればご自由にお書きください。
- 自治体主催の総合防災訓練でデモをおこなうなど、住民が直接見られる機会を作ってほしい。
- 要望が重複した場合の貸出優先順位を教えてほしい。
- 1台のみでは、多くの需要に対応できないと考える。台数を増やしてほしい。
- 災害時に遠方まで搬送するのは困難だと考える。
- 試験的な貸出は可能か知りたい。
質問10-1:四国総合通信局では災害発生時の通信手段確保のため、現地災害対策本部等に対して無償で移動通信機器(衛星携帯電話、MCA無線機、簡易無線機)の貸出をおこなっています。このことを知っていますか。
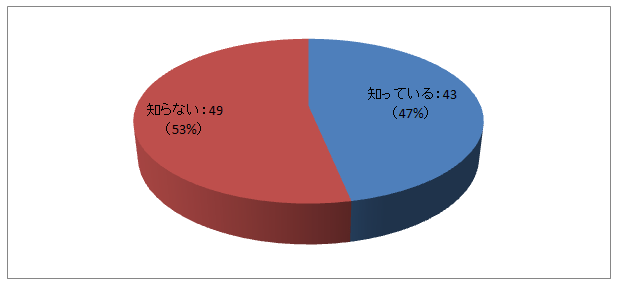
質問10-2:災害発生時に必要な場合には、前記の移動通信機器の貸出を希望しますか。
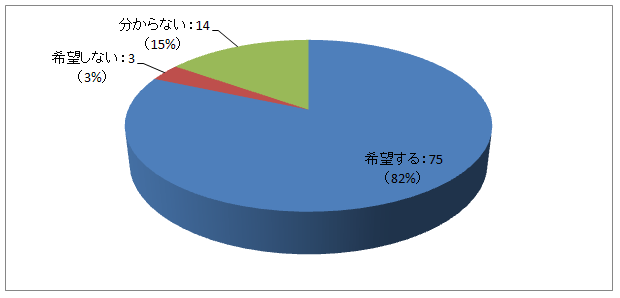
質問10-3:移動通信機器の貸出に関してご質問や改善意見等があればご自由にお書きください。
- 自治体主催の総合防災訓練でデモをおこなうなど、住民が直接見られる機会を作ってほしい。
- 要望が重複した場合の貸出優先順位を教えてほしい。
- 災害時に遠方まで搬送するのは困難だと考える。
4 その他情報通信システムの導入状況等について
質問11:東日本大震災では、多くの地方公共団体が臨時災害放送局(臨時に開局するFMラジオ放送局)を開局し、地域住民に対して適切に安否情報、救援情報、復興情報等を届けるなど被害の軽減、被災者の生活安定に大いに貢献しました。大規模災害発生時に貴団体では、こうした臨時災害放送局を開局する意向がありますか。
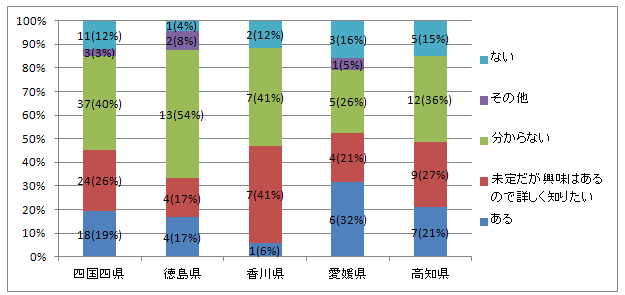
【コメント】
「開局意向がある」との回答は18件(19%)と必ずしも高くはない。「分からない」という回答が37件(40%)と多いことからも、臨時災害放送局に対する理解がまだ十分浸透していないのではないかと思われる。
※「開局意向がない」理由の主なものは以下のとおりである。
- 人員不足、準備不足のため。
- 防災行政無線で十分なため。
- 地域のコミュニティFMと災害時の協定を締結しており、緊急割込放送も可能なため。
- 既設コミュニティFMが無いので新規開設が困難なため。
※「その他」の主なものは以下のとおりである。
- 既設コミュニティFMとの協議の結果次第。
- 各戸への防災ラジオの配備も検討しているが、臨時災害放送局とどちらが有用かを比較しているところ。
質問12-1:携帯電話事業者は、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報に加え、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を対象エリア内の携帯電話に一斉にお知らせする緊急速報メール(エリアメール)のサービスをおこなっています。貴団体では災害・避難情報を緊急速報メールでお知らせするための契約を携帯電話事業者とおこなっていますか。
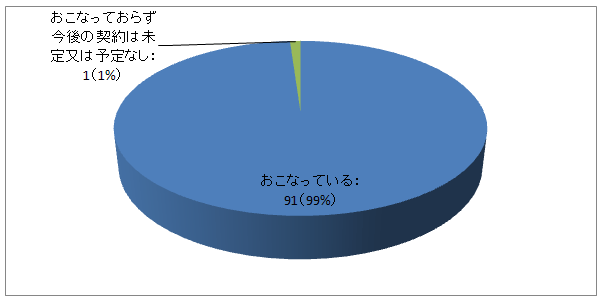
【コメント】
ほぼ100%が「契約をおこなっている」と回答しており、緊急速報メールが、災害時に有効な情報伝達手段と認識されていることがうかがえる。
質問12-2:前問で「契約をおこなっている」とお答えの場合、契約は緊急速報メールを提供している全携帯電話事業者(NTTドコモ、KDDI及びソフトバンクモバイル)と締結していますか。(又は締結する予定ですか。)
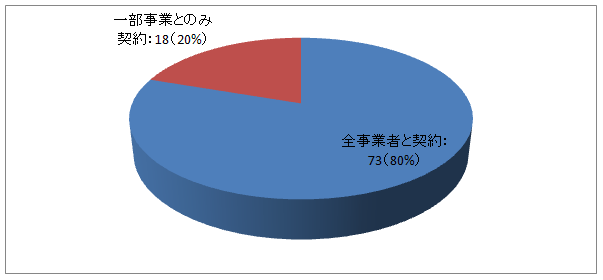
【コメント】
「全事業者と契約」との回答が73件(80%)と非常に多いが、「一部事業者とのみ契約」との回答も18件(20%)ある。
質問12-3:前問で「一部事業者とのみ契約」とお答えの場合、今後全事業者と契約する予定はありますか。
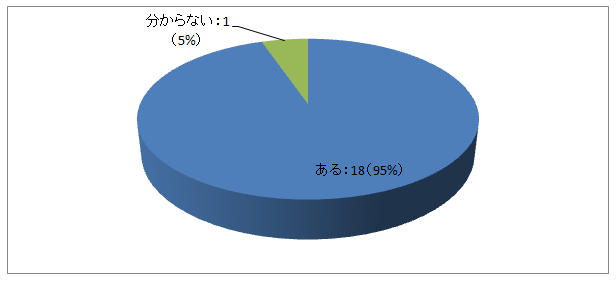
【コメント】
前問のコメントのとおり、現段階で一部事業者としか契約していない場合も、大半は今後全事業者と契約する予定となっているため、近いうちにほとんどの市町村が全ての事業者と契約を結ぶことになると考えられる。
質問13:災害時には通信の途絶を防ぐため、多様な連絡手段の確保が必要だと言われています。こうした観点から災害に強いと言われる「衛星携帯電話」を導入していますか。
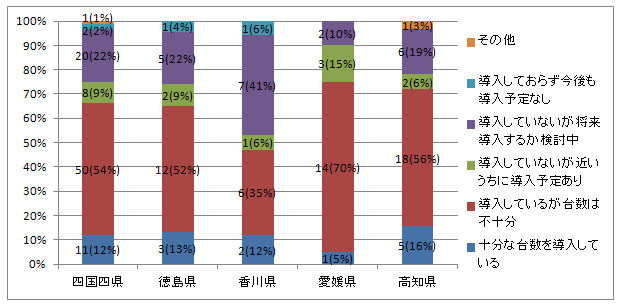
【コメント】
「台数は不十分」との回答が多いものの、導入済みの合計は61件(66%)に達しており、緊急速報メール及び防災行政無線に次いで普及が進んでいるメディアである。
質問14:避難所等非常災害時に拠点となる施設へ平時からのインターネットアクセス環境の整備をおこなっていますか。
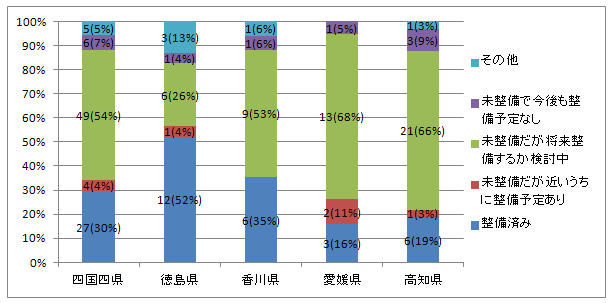
【コメント】
「将来整備するかどうか検討中」との回答が49件(54%)と最も多い。県別に見ると、最も整備が進んでいるのは徳島県であり、「整備済み」が52%となっている。今後、インターネットアクセス環境整備が進展することが望まれる。
質問15:堅牢なデータセンターを利用して行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業務継続を確保する観点から自治体クラウドが注目されています。自治体クラウドを導入していますか。
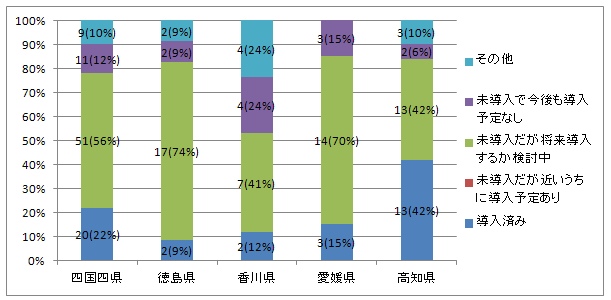
【コメント】
「導入済み」はまだ20件(22%)と数は少ない。県別に見ると、最も導入が進んでいるのは高知県であり、「導入済み」が42%となっている。
「将来導入するかどうか検討中」との回答が51件(56%)と最も多いが、クラウドという概念やその普及が最近のことであることを考えると、自治体クラウドに対する市町村の評価・関心は高く、今後の導入の進展が望まれる。
※「今後も導入予定なし」の理由の主なものは以下のとおりである。
- セキュリティ面での不安や通信回線途絶時に使用不可となる懸念があるため。
- 予算確保が困難なため。
5 国や事業者に対するニーズについて
質問16:情報通信技術・システムを利活用した防災対策を進める上で何か困っていること、詳しく知りたいこと等があれば記載してください。
- 防災行政無線等の整備には多額の財政支出が必要なので、国等の財政支援を希望。
- デジタル無線機器の低廉化を希望。
- 衛星携帯電話は利用料が高額なため、必要とする台数が保有できない。
- 市町村合併の後、アナログ、デジタル等異なる規格の無線設備が併存しているため、運用に支障をきたす場合がある。そのため総デジタル化等の規格統一が急務である。
- 防災行政無線の屋外拡声器は、風水害発生時の音声伝達の確実性が不安。今後は、防災ラジオや携帯メール等住民へのより確実な情報伝達手段が必要。
- 各種の防災関係システムが独立して存在しているため、システム毎の個別データ入力が必要となり、発災時に業務量が増大するという問題を抱えている。
質問17:電気通信事業者又は放送事業者に望むことがあれば記載してください。
- 災害による電話線の寸断、携帯電話基地局の倒壊等が発生した場合の早期復旧。(特に離島において)
- 災害時の情報伝達等の体制強化。
- MCA無線の伝搬範囲の拡大。
- 避難施設へ設置した電話、テレビ等の通信料等の無償化。
- 商用電源断でない場合は、テレビを利用した自治体からの情報発信が出来るようにしていただきたい。
- 夜間におけるAMラジオの外国波混信対策。
質問18:四国総合通信局に望むことがあれば記載してください。
- コミュニティFM施設を整備し、災害時に活用する計画を検討中のため、参考となる情報を提供いただきたい。
- 現在運用しているアナログ防災行政無線(移動系)は、他市町村のデジタル無線と比較しても使い勝手が良い。デジタル移行が推進されているが、整備コストがかかることもあり、使用期限を設けないでほしい。
- 出来るだけ早期にアナログ防災行政無線(移動系)の終了時期を知らせてほしい。
- デジタル防災行政無線の整備に関する指導、具体的なノウハウの助言、財政支援(特に補助金)をお願いしたい。
- 各自治体がどのような情報通信技術・システムを導入しているかといった情報提供や優良事例の紹介。
- 各種の無線システムが個別に親局、中継局等の鉄塔建設をおこなっているが、せめて都道府県と市町村は共同鉄塔を建設し、効率的な無線局運用が可能となることを希望。
- 山間地域で孤立の恐れがある自治体との連絡協議会を作るなど、災害時に備えた連携を深める場を設けてほしい。また、そうした場を活用して日頃から情報交換、研修、交流会等をおこなってほしい。
<< 1つ前のページへ戻る
|