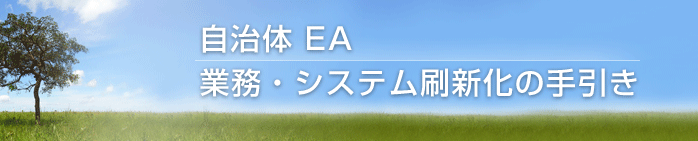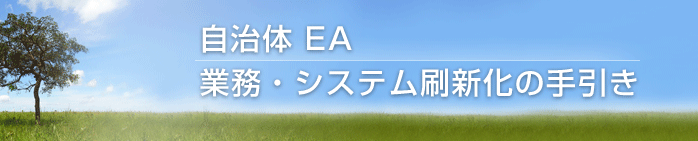| ■作業名 |
基幹業務 住民情報関連業務 住民基本台帳 現状分析(業務分析)作業(第2回) |
| ■日時 |
平成 17年11月17日(木)
9:00〜11:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
市民課 大山主査、岩本主事 |
企業:【基幹】
日立製作所 小松崎、大谷 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 第1回業務分析の成果物に対し、さらに業務の流れを意識した機能分割となるように再度見直し、その結果を参加者間で確認した上で、機能間の情報の流れ、流れる情報名等を明確にします。
【当日の流れ】
9:00〜9:05 本日の作業についての説明(5分)
9:05〜10:45 機能分析表(DMM:以下「DMM」という)、機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)の確認(100分)
10:45〜10:55 業務説明表の記入・確認(主に根拠法令等について)(10分)
10:55〜11:00 業務要件定義表の説明(5分)
【作業内容】
- 第1回業務分析のDMMは、階層2を業務の場合分けによる分割(転出、転入、出生、死亡等)で表現し、階層3を各場合分けの作業の流れ(受付→審査→記載・・・)で表現していました。しかし、DMMについては、まず階層2までを業務の流れが見える形で整理する必要があったため、第2回業務分析の実施前に、参加者間でDMMの見直しを行いました。
- 見直しにあたっては、階層3で表現されていた機能のうち、各場合分けに共通している機能(受付、審査等)を、階層2の機能として纏めていきました。この結果、各場合分けは抽象化されてDMM上には表現されなくなり、階層2は業務の流れに基づく機能分割で表現されるようになりました。
- また、DMMの階層1は、住民基本台帳への新規登録処理から始まり、台帳の登録内容に基づく処理(住民票の写し交付、閲覧等)、台帳の変更、消除に至るという、台帳の状態遷移を表現するように整理しました。
- さらに見直したDMMに基づいて、DFDも事前に整理しました。DFD上を流れる情報名を記載する際には、場合分け毎に情報を分類しておくことによって、各機能が含む場合分けの種類を表現するようにしました。
- 上記を踏まえて、第2回業務分析では、まずDMMの機能構成を第1回業務分析のDMMと比較しながら確認することにしました。しかし、DMMだけでは具体的な情報の流れが見えず、比較が困難との意見が職員より出されたため、1つ1つの機能が含む場合分けを表現したDFDの確認から開始しました。
- その際、参加者全員が見えやすいように拡大しておいたDFD(A3用紙)を机の中央に置き、確認事項をそこに直接追記しながら作業を進めていきました。
- DFDの確認では、当初、多様な処理の場合分けが職員より示されたため、確認に時間を要しました。しかし、職員はこれまで市民課所管業務の分析作業に全て参加しており、業務の中心的な流れを表現すべきであることが念頭にあったため、後半になるにつれて、確認作業は円滑に進んでいきました。
- DFD階層1の「3 住民票・証明書等発行」について、当初は住民基本台帳カードの発行機能を含むものとして整理していました。しかし、住民基本台帳カード発行は、住民基本台帳の管理そのものに関わる業務ではなく、処理の性質が異なるとの意見が出たため、「住民基本台帳カード発行」機能として個別に切り出すことにしました。
- また、電算処理機能については、第1回業務分析で「市民課内でシステム運用を行っており、作業量がかなり多いので入れておきたい」という意見が出ていました。しかし、電算処理は住民基本台帳の中心的な業務を円滑に進めるための副次的な業務と捉えられるので、DMM上には表現されないものであることを職員に説明した上で、DMMからは除くことにしました。
- 続いて、業務説明表については、「根拠法令等」「所管課」の項目を確認、追記しました。
- 最後に、業務要件定義表について記載内容を簡単に説明しましたが、具体的な記載例が欲しいとのことでしたので、別途電子メールで連絡することとしました。
【出てきた意見】
- 業務要件定義表について、業務量を記載する旨を説明したところ、DMMから除いた「電算処理」は作業量としてはかなり多いので、本来ならば記載したいとの意見がありました。
- 業務説明表の「成果指標」について職員に確認しましたが、特にないとのことでした。
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「根拠法令等」「所管課」欄について確認しました。
- DMM(1枚)・・・階層1、2について確認しました。
- DFD(8枚)・・・階層1について確認しました。
|
| ■ポイント |
- 現行の住民基本台帳業務は、ほとんどシステムを用いての処理となっています。そのため、システム化されている部分の機能を原課職員はあまり意識することがなく、業務機能を洗い出す際に抜け漏れが生じる可能性があります。今回の業務分析では、業務・情報システムの双方に詳しい職員が参加したことが、必要な機能を漏れなく洗い出すことに寄与しました。したがってシステム化された業務の現状分析を行う際には、実際の業務に携わっている職員に加え、情報システムを熟知した職員が参加するとよいと考えます。
- DMM、DFDを用いた業務分析では、細かい作業はあまり表現されないことになります。しかし、職員にとっては、どんなに細かい作業であっても、実際の業務遂行には必要であり、抽象化した機能の中にそれらがきちんと含まれているのか、不安に感じるようです。このような不安感を軽減するためには、職員が業務の流れを意識しやすい単位(「転出時の処理」「転入時の処理」といった業務の場合分けの1つ等)で一旦機能分割を行い、そこで出てきた同じ機能を抽象化するという進め方が有効だと考えられます。
- 住民基本台帳業務は、戸籍と連携する部分(例えば、戸籍係から出生届等を受け取り、住民基本台帳へ登録する等)があるので、戸籍の業務分析成果物(DFD)と照らし合わせることによって、情報の受け渡し関係が業務間で矛盾しないように留意する必要があります。他業務の分析についても、業務間の整合(機能分割の単位、情報連携の関係等)を取りながら、分析を進めることが望ましいと考えられます。
|