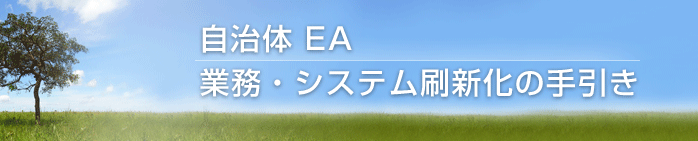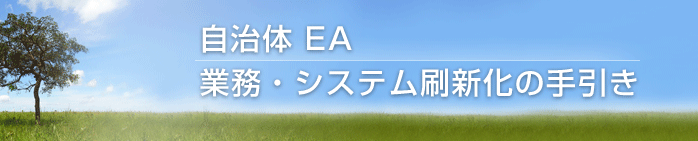| ■作業名 |
基幹業務 住民情報関連業務 印鑑登録 現状分析(業務分析)作業(第2回) |
| ■日時 |
平成17年11月24日(木)
13:00〜14:30 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
市民課 大山主査、坂口主事 |
企業:【基幹】
日立製作所 小松崎、榎本、大谷 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 第1回業務分析の成果物を基に事前に整理した機能分析表(DMM:以下「DMM」という)および機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)について、機能間のつながりや流れる情報の実体等を明らかにします。
【当日の流れ】
13:00〜13:05 本日の作業目標等の説明(5分)
13:05〜14:15 DFDの確認(70分)
14:15〜14:20 業務説明表の説明(「業務規模」「成果指標」「投入資源」欄)(10分)
14:20〜14:30 業務要件定義表の説明(10分)
【作業内容】
- 第1回業務分析の成果物は、DMMとDFDの間に不整合(機能名称が一致していない、DFD上に機能が8つ以上ある等)が生じていました。そこで、第2回業務分析の実施前に、DMMとDFDを整理し直すことにしました。
- 具体的には、DMMについて、業務の流れがほぼ同じである「印鑑登録」機能と「引替交付」機能を1つに纏める等、DMM階層1の機能分割を見直しました。また、整理したDMMと整合を取るようにDFDも改めて整理しました。
- なお、市民課の主管業務(住民基本台帳、外国人登録、戸籍)については、業務間の連携を考慮し、分析成果を調整しながら進められるようにするため、今回からは他の市民課業務の分析に参加していた企業が対応することにしました。
- 今回の業務分析は、まず第1回業務分析の成果物(DMM)と、事前に整理したDMMの対応関係を確認することから開始しました。その後の確認作業は、DMMだけでは情報の流れが見えないため、DFDを中心に進めていきました。
- 初めに議論になったのは、登録印鑑の情報を管理する台帳の表記でした。整理したDFDには「印鑑登録原票」と記載していましたが、この表記だと印鑑登録原票の現物を想起してしまうとのことでした。したがって、印鑑登録原票は現物を示す表現とし、台帳の名称は「印鑑登録原票情報」に変更することにしました。
- 次に、被後見人該当時の印鑑登録禁止または廃止について議論しました。まずは第1回業務分析のDFD階層1「成年後見人」を基に、具体的な処理の流れを確認しました。すると、被後見人となった場合には、戸籍係から登記事項記載通知を受け取り、対象者の印鑑登録の有無によって登録禁止あるいは廃止処理を行う、という処理の流れが明らかになりました。そこで、「後見人登録」機能を新設した上で、対象者が印鑑登録をしている場合のみDFDの階層1「登録廃止」機能に情報を受け渡すという流れで整理することにしました。
- 続いて、職権回復時の印鑑登録原票(現物)について議論しました。「登録廃止」機能の中には、廃止する原票を引き抜き、印鑑登録原票(廃鑑)として保管する流れを記載していましたが、職権回復時には印鑑登録原票(現物)に関する処理を記載していませんでした。そこで、機能間の記載の詳細度を合わせるために、印鑑登録原票(廃鑑)から回復対象者の原票を引き抜き、印鑑登録原票として保管するという流れを「職権回復」機能に追記することにしました。
- また「証明書交付指定」については、印鑑登録証明書の交付を指定した対象者のみに行うようにする処理であり、機能名としては「交付指定登録」の方が適切であるという意見が出たので、変更することにしました。
- なお、「発行停止」機能については、住民から印鑑登録証明書の発行を停止してほしい旨の連絡を受け、その内容を台帳等へ記録する処理であることが分かりました。したがって、新規に機能を設けるのではなく、「印鑑登録証明書交付」の中の一機能として「発行停止」を追記する形で整理することにしました。
【出てきた意見】
- 住民基本台帳カードの多目的利用を検討する中で、印鑑登録証の情報を住民基本台帳カードに持つとよいのではないか、といった考え方がありますが、氏名、住所、生年月日に加え、顔写真までの情報が搭載される住民基本台帳カードの中に、印鑑登録といった重要な情報を同一に管理するのは、セキュリティ面で危険ではないか、との意見がありました。
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「根拠法令等」欄を確認、記入しました。
- DMM(1枚)・・・整理したDMMを基に、階層1、2を全て確認しました。
- DFD(7枚)・・・整理したDFDを基に、階層1を全て確認しました。
※業務要件定義表は内容説明が中心となり、具体的な作成作業まで行うことはできませんでしたが、DFD確認を通じて各機能の作業内容、入出力情報等を把握しています。
|
| ■ポイント |
- 事前にDMM、DFDを整理した際に、再度検討が必要な点を明確にしていたため、それらについて抜け漏れなく議論できました。正式な帳票名等は電子メールのやり取りで確認できますが、機能分割の考え方、各機能が含む作業の範囲は参加者が直接議論した方が分かりやすいです。そこで、事前に確認すべき点を明確にし、それを参加者全員が共有できるようにしておいた方がよいと思います。
- 「手数料徴収」機能のように、複数業務間に共通して存在する機能については、DFDの表現(記載の詳細度等)を当該業務間で統一しておくべきです。そこで、ある業務での分析成果が確定した段階で、他業務の成果物はその分析成果の表記に合わせ、表現の統一を図るとよいと考えられます。
|