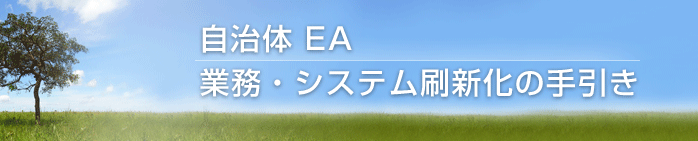| ■作業名 |
内部管理業務:財務会計 現状分析(業務分析)作業 |
| ■日時 |
平成18年1月19日(木)
13:30 〜 16:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所 本庁舎五階大会議室
|
| ■参加者 |
職員:
財政課 岩城課長補佐、会計課 田村副主幹、妹尾主任、園田主任、山本主事、契約課 荒井主任、管財課 相原課長補佐、室井主査、買田主査、森主査、総合政策課 永井係長、行政管理課 板倉主査 |
企業:
大和総研 堀井、
京都電子計算鶴衛、行政システム 渡辺、
NTTデータ 角田 他
|
| ■使った資料 |
なし |
| ■概要 |
【作業の目標】
- 作業前に当日の作業(業務機能の論理化・抽象化)の主旨、手順を確認した後、業務分析第2回目までに作成した機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という。)を使って、業務機能の論理化(一筆書き)・抽象化の作業を行いました。まず、財務会計全体を対象に階層1のDFDの機能間を流れる情報を確認し、一筆書きを行いました。ただし、政策事業評価と情報公開は業務として独立しており、個別の作業となりました。その後、財政課、会計課、契約課を一つのグループ、管財課を一つのグループ、総合政策課、行政管理課を一つのグループとしてさらに詳細化した階層2のDFDを材料に論理化(一筆書き)を行いました。一筆書きが終わった後、課題と注釈も入れました。次に、論理化した階層2のDFDを対象に、企業で用意した用紙に機能の抽象化の作業をしました。最後に機能を記入した業務をパターン分けし、分析作業を終了しました。
- 業務を「機能」と「機能間の情報の流れ」としてとらえた時に、どこまでを一つのくくりとしてまとめることができるか確認すること、また機能を類型化し基本機能の組み合わせでパターン化することを目的としました。
【当日の流れ】
13:30〜13:55 業務分析作業手順についての説明(25分)
13:55〜14:55 論理化(一筆書き)作業(60分)
14:55〜15:55 抽象化作業(60分)
15:55〜16:00 作業全体についての説明(5分)
【作業内容】
(1)論理化(一筆書き)
- 作業機能間の連携を想定して、情報の流れを記述しました。財務会計の予算、歳入歳出の範囲については、情報の流れがお金の流れになるので想定し易く作業は順調に進みました。逆に、財産管理については、情報を財産自体とするか、それに関する契約または金銭とするかで議論になりましたが、情報自体は複数あってもかまわないとし作業を進めました。作業は違う色のペンを使い情報の違いを明確にしました。業務間(歳出執行管理と契約管理)についても論理化を行いました。
(2)抽象化作業
- 企業で事前に第2回目までの業務分析で作成したDFDから機能名を抽出してシートを作成していたため、当日職員はそのシートに個別の業務につき、どの機能が該当するか印をつけていきました。シート上の機能の名称は複数ある機能を抽象化したものであり作業の開始時点では理解しにくく感じましたが、企業に確認するうちに、順調に全ての機能について印付けを行っていきました。その後、印をつけた機能について、違う色のペンなどを使って表にパターン分けの作業をしました。
【出てきた意見】
主な意見は以下のとおりです。
- 類型化は、階層の分け方が難しい。
- 全ての機能は同じではない。(財産管理は)独自性が高いと感じている。
- 各市によって違うと思うが、パターン化できるものばかりではない。業務により、向き、不向きがある。
|
| ■成果物 |
|
| ■ポイント |
【作業を実施して気付いた点】
- 論理化(一筆書き)においては、主たる情報を何にし、展開するかによって作業の進み方が違ってくると感じました。主たる情報の選定自体もばらつきがあると感じました。主たる情報については、事前に絞りこみを行っておくと作業が進めやすいと感じました。
- 各課によって、今回の業務分析の類型化に対する反応は分かれました。特に類型化しにくい計画策定を内容とする業務では1年を期間として展開していく必要があるので、その中から類型するものを探すこと自体に違和感を覚えました。
- 一筆書きをすることによって、組織間での情報のやりとりが目に見える形で表わされ、改めて情報の流れを認識することができました。
- パターン分けについては、担当者によって意見が分かれることもあると感じました。
【作業をうまく進めるための助言】
- 部署やシステムなどの枠を取り払って考えるとスムーズに進むと思います。
|