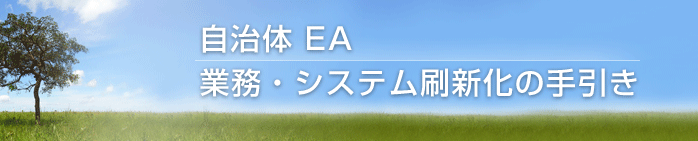【作業の目標】
- 作業前に当日の作業(業務機能の論理化・抽象化)の主旨、手順の説明を受けた後、業務分析第2回目までに作成した機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という。)を使って、業務機能の論理化(一筆書き)・抽象化の作業を行いました。作業は、参加した職員の担当業務に応じて、人事関連・研修・福利厚生の3つのグループに分かれて行いました。
- 業務を「機能」と「機能間の情報の流れ」としてとらえた時に、一つのくくりとしてまとめなおした形を作ること、また機能を類型化し基本機能の組み合わせでパターンを作ることを目的としました。
【当日の流れ】
13:30〜13:55 業務分析作業手順についての説明(25分)
13:55〜14:30 論理化(一筆書き)作業(35分)
14:30〜15:55 抽象化作業(85分)
15:55〜16:00 作業についての説明(5分)
【作業内容】
(1)論理化(一筆書き)作業
- 階層1の全体的なDFDで一筆書きを始めました。最初はどこから書き始めたらよいか戸惑いましたが、代表的な業務を想定して書くことで整理していったところ、書き始めることができました。一度書き始めると業務の流れに応じた機能をDFD上に捜すことが出来るようになり、さらさらと書けるようになってきました。階層1のDFDで主要な業務の一筆書きが終ったあと、それぞれの一筆書きが階層2のDFDでどう書けるかという観点で、詳細な一筆書きを行いました。
- また、研修業務については、外部機関による研修、啓蒙活動、役所内での研修等複数の切り口から情報の流れを整理する形で、作業を進めていきました。さらに、機能ごとの作業時期の違いを区別するために、日次、月次、年次、随時の区別を色分けしました。
(2)抽象化作業
- 抽象化作業用のシートを使用して、抽象化作業を行いました。予め作業シートに記載した「抽象化後のくくり」(抽象化した機能の呼称)の意味を随時確認しながら、業務ごとに該当する抽象化後のくくりに印をつけていきました。業務内容は熟知しているため、極めて順調に印をつけていくことができました。ひととおり印をつけた後に、時間が余ったグループは、類似した機能をもつ業務の分類(パターン分け)を行いました。パターンの数は業務によって異なり、少ない業務は5パターン程度、多いところは業務の数とパターンの数がほぼ同じという状況でした。
【出てきた意見】
主な意見は以下のとおりです。
- DFD上で、情報がシステムに入ると業務の流れがそこで途切れてしまう。
- 研修業務では、原課における研修情報の確認から研修申込
- 供覧、実績管理までの一連の手続がシステム化されていない状況である。一連の流れをシステム化することにより原課作業が効率化されるとともに、研修課においても省力化され計画策定等の主要な業務に専従する時間を作りだせると思う。
- 抽象化作業後パターン化したが、パターンに少しずつ違いがあり完全なパターン化が難しいと感じた。業務によって、パターン化できるものとできないものがあるのではないかと思う。
- 給与関連の業務においては、受理・認定・登録が基本的な機能パターンであり、そこにどんな機能が追加されるかによって機能のパターンが分かれてくる。
- 一筆書きの起点を職員にするのか、システムにするのか戸惑っていたが業務的な流れで整理するとできると感じた。