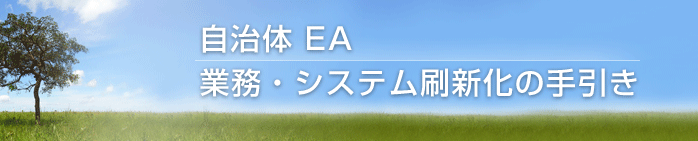| ■作業名 |
基幹業務 税関連業務 現状分析(業務分析・情報分析)作業(第4回) |
| ■日時 |
平成18年2月16日(木)
9:30〜12:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所2F第3会議室 |
| ■参加者 |
職員:
【市民税課】 中村主事、漆山主事、佐藤主事
【固定資産税課】 内座課長補佐、柳沢課長補佐、清水主任、神田主任、斎藤主事
【国民健康保険課】 池田主任、加来主事
【収滞納促進課】 堀江主任、小林(悠)主事
【税制課】 矢作主査、舟津主査、飯盛主任 |
企業:【基幹】
三菱電機 古宮、栗林
アイシーエス 藤原 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 第3回業務分析で作成した業務機能の論理化(一筆書き)の結果を受け、今回はそこで流れる情報の分析(抽象化)を職員自らが実施し、税業務が基本的な機能と情報の組み合わせで実現できることを確認します。
【当日の流れ】
9:30〜 9:45 作業方法の説明(15分)
9:45〜10:50 論理化(一筆書き)による現状との変更点確認(65分)
9:50〜11:00 休憩
11:00〜11:15 抽象化整理表、取引パターン明細表の結果確認(15分)
11:15〜11:35 イベントエンテティ表の作成(20分)
11:35〜11:45 情報体系整理図の作成(10分)
11:45〜12:00 業務分析全体に関する感想・意見交換(15分)
【作業内容】
- 今回の作業では、前回実施した論理化作業(一筆書き)の結果について各業務で確認を行いました。また、現状の機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)上において、業務機能をくくり直す箇所がないか討議することで、組織や機能の枠を越えた、将来のあるべき姿について意見交換を行いました。さらに、前回の抽象化作業により抽出した各業務パターンの上を流れる情報について、実際の帳票から情報を採取することにより、税業務活動に関わる、ヒト・モノ・カネの資源について整理しました。
- 前回に続き、各税業務より1名以上の職員が出席し、税業務として1つの島を作りました。
- 前半の論理化作業の確認では、収滞納管理の収納業務と、税制で行っている市税収納、還付・充当処理が一筆でつながることから、これらを一つのくくりとしてまとめることを試みました。討議の結果、業務的には一筆でつなぐことは可能であると判断できました。その一方で、審査部門と処理部門が一つのくくりになるため、これらを同一の組織で行うことは公正が保てなくなる、との意見もありました。
- 休憩を挟んで、後半作業では、前回作成した抽象化整理表を確認しました。この中から、減免業務、および税証明発行業務において、実際に業務上を流れる帳票(減免申請書、減免決定通知書、市民税証明申請書、市・県民税納税証明書)を用いて、ヒト・モノ・カネで区別した情報名を採取し、イベントエンテティ表に並べていきました。
- 上記以外の業務パターンについても、イベントエンテティ表で確認したのち、これらを図に描いて体系化した情報体系整理図について確認しました。この結果、税業務活動全般に関わる、ヒト・モノ・カネの資源と情報名を整理することができました。
【出てきた意見】
- 論理化作業から将来のあるべき姿を討議する過程で、以下のような意見がありました。
- 今回の論理化作業によって、組織を越えた業務のつながりを確認できた。ただし、実際には、審査部門と処理部門などの権限分離の必要性により、組織を分けざるを得ない状況にある。しかしながら、権限分離の公正を保つために非効率な組織体系をとることは、かえって住民サービス低下にもつながりかねない。改めて、今後のあるべき姿について議論する必要がある。少なくとも、このような課題を税業務に携わる職員で共有認識できたことは価値があったと言える。
- 現状では、国民健康保険税の収納業務は課内で個別に行っており、他税の収納業務とは別管理となっている(ただし、督促や催告などについては収滞納管理にて一元されている)。この理由としては、国民健康保険税にて、収納管理を含めた個別システムを持っている、という要因が一番大きい。一方で、資格・給付といった他税とは異なる業務を抱える中で、国民健康保険税として収納状況を個別に把握する必要があり、業務として複雑に絡み合うため、結果的に組織として分かれざるを得ない状況にもなった。ただし、今回の論理化作業による討議の中で、本来ならば収納管理も一元できるという共有認識が持てた。今後どのように改善していくのか、改めて検討する必要があると感じた。
- 第1回目から第4回目までの分析作業を通じて感じたことについて、以下のような意見がありました。
- これまでは自部門の税業務しか把握できなかったが、今回の分析作業を通じて、他部門の税業務についても理解することができた。・これまでに自分の業務を他人に伝えるような資料がほとんど存在しなかったが、今回の業務分析で作成した資料は、業務の引継ぎや後輩などに教える場合にも有効に使える資料であると言える。
- 今回の分析結果を、今後どのように活用していけば、より具体的な業務改革となって効果につながるのか見えにくい。(これについては、今回の成果物の活用事例として、別途、分科会にて川口市の個別課題を選定しており、基幹系としては住民の窓口処理時間の実体を計測し、一回の申請で複数証明書を発行する場合の効果の試行と、課題解決の方向性を検証していることを伝えました。)
|
| ■成果物 |
- DFD(一筆書き)・・・業務毎に、機能と機能が一筆でつながることを確認しました。
個人住民税、
法人住民税、
固定資産税(土地)、
固定資産税(家屋)、
固定資産税(償却資産)、
軽自動車税、
国民健康保険税、
収滞納管理(消込・還付・充当)、
収滞納管理、
税制
- DFD(論理化)・・・業務毎に、論理化後のDFDを確認しました。
個人住民税、
法人住民税、
固定資産税(土地)、
固定資産税(家屋)、
固定資産税(償却資産)、
軽自動車税、
国民健康保険税、
収滞納管理、
税制
- 抽象化整理表・・・第3回で実施した抽象化作業に基づき、税業務全般における業務パターンを抽出し確認しました。
- 取引パターン明細表・・・抽象化整理表に基づき、各業務の上を流れる帳票の取引パターンを確認しました。
- イベントエンテティ表・・・取引パターン明細表に記載された各種帳票から、ヒト・モノ・カネで分類した情報名を採取し一覧表に整理しました。
- 情報体系整理図・・・イベントエンテティ表に記載された情報名に基づき、具体的な図を描いて体系的に整理できることを確認しました。
|
| ■ポイント |
- 今回の業務分析を、今後どのように活用していけば良いのか見えづらい、といった意見がありました。これについては、刷新化の方向性と各業務の分析結果とのつながりを踏まえて、今回の成果物の活用事例を説明する機会を設ける必要があると考えます。
- 今回のように、各税課が一同に集まって討議する際に、自部門以外の税業務を知らないことが多くあります。この場合、機能分析表(DMM)を用いることで、1枚の紙面上で各税業務の機能全体を見渡すことができるので、職員同士の共有認識が図りやすくなります。
|