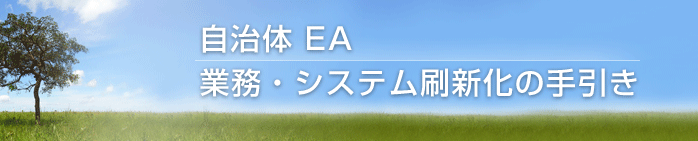| ■作業名 |
基幹業務 福祉関連業務 介護保険 現状分析(業務分析)作業(第2回) |
| ■日時 |
平成17年11月17日(木)
13:00〜15:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
介護保険課 柳原主任、上田主事、河内主事、井上主事補、早川主査、都鳥主任、宮内主査 |
企業:【基幹】
日立製作所 前田
三菱電機 栗林 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 第1回業務分析およびその後の電子メールでのやり取りで作成した成果物をもとに、現行業務の機能のつながり、流れる情報を確認します。
【当日の流れ】
13:00〜13:05 本日の作業内容の説明(5分)
13:05〜13:10 業務説明表、機能分析表(DMM:以下「DMM」という)の確認(5分)
13:10〜14:40 機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)の確認、業務要件定義表の作成(90分)
14:40〜14:50 情報実体一覧表の記述内容の説明(事例を利用)(10分)
【作業内容】
- 第1回業務分析で作成したDMM、DFD(認定)と、その後作成したDFD(各担当職員がDFDを作成し、企業が整理したもの)を事前に用意しました。
- 最初に、事前に用意したDMM、DFDについて、上記変更に際しての考え方を説明すると共に、本日の検討作業全体の流れを簡単に説明しました。
- 業務説明表については、根拠法令等および所管部署の部分のみを確認しました。
- DMMについては、1点追加した機能があったので、その部分のみ確認しました。
- DFDの確認は、各職員にDFDを配付し、それを見て進めることにしました。
- DFDの確認は、事前に抜き出した確認項目を中心に、情報名や情報の流れを確認しました。
- また、業務要件定義表を平行して作成しました。
- DFDの確認では出てこないが、業務要件定義表の作成で出てきた機能・情報については、他のDFDとの粒度をあわせるという観点で、取捨選択しました。例えば、「認定」の主治医意見書の報酬支払い等は職員2名で実施しているのですが、他のDFDでは同様の機能は省略しているので、機能として追加することは見合わせました。
- 情報実体一覧表は、例として、給付の「介護給付費通知書」について作成し、作り方を確認しました。残りは、今後電子メール等のやり取りで完成することとしました。
【出てきた意見】
- 業務要件定義表の作業時間・作業量等は、記載方法が業務により変わるため、宿題になると記載方法で悩んでしまうという意見があり、正しい数字がわからなくても、とりあえずの数字・書き方を記入してもらいました(正しい数字を埋めるだけであれば、宿題にしても、負担はないが、記載方法まで考えるのは負担という意見でした)。
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「根拠法令等」「所管課」欄を確認しました。
- DMM(1枚)・・・階層1、2を確認しました。
- DFD(8枚)・・・階層1をすべて確認しました。
- 業務要件定義表(7枚)・・・作業名、作業内容、実施方法、担当部署、作業者を記入しました。
- 情報実体一覧表(1枚)・・・「介護給付費通知書」他について記入しました。
|
| ■ポイント |
- DFDの確認作業では、事前に確認項目を抜き出し・送付しておくこと、最初にDMM、DFDの修正の考え方を説明しておくことで、抜け漏れなく効率的に進めることができました。
- DFDの確認は、各自手元のDFDを修正、加筆したので、個人の理解は進んだと思いますが、共通認識ができにくい場面もありました。やはり、多少窮屈でも、みんなで1つのDFDを見て、それに直接書き込んでいくほうが、作業の正確性、効率性の観点から、望ましいと感じました。
- DFDの確認作業と並行して、業務要件定義表を作成していくことで、業務の流れが明確になり、確認作業を効率的に進めることができました。
- 業務要件定義表の作業時間・作業量等は、正しい数字がわからなくても、とりあえずの数字・書き方を確認して記入してもらうことで、考え方の統一と宿題の負担感をなくすことができました。
- 情報実体一覧表は、例として一部実施することで、具体的な作業内容について共通認識を図ることができました。
|