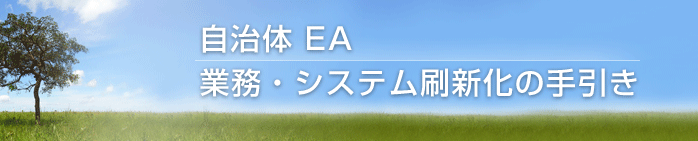| ■作業名 |
基幹業務 福祉関連業務 障害者福祉 現状分析(業務分析)作業(第2回) |
| ■日時 |
平成17年11月17日(木)
13:00〜15:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
障害福祉課 金杉主任、宮川主任 片岡主任、松崎主事 |
企業:【基幹】
日立製作所 大谷、岩崎 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 第1回業務分析の成果を踏まえて、機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)における機能間のつながり、流れる情報名等を明確化することによって、現行業務処理の流れを整理します。
【当日の流れ】
13:00〜13:05 本日の作業についての説明(5分)
13:05〜14:50 DFDの確認(105分)
14:50〜15:00 業務説明表の確認、業務要件定義表の説明(10分)
【作業内容】
- 第1回業務分析で機能分析表(DMM:以下「DMM」という)を作成した後に、DMM作成過程で確認できた情報に基づいて、参加者間でDFDの整理作業を事前に行いました。
- 第2回業務分析では、そのDFDについて、機能間の情報の流れ、流れる情報名等を確認していきました。その際、障害者福祉のDFDは、1つの機能が多くの場合分け(事業)を含んでいるため、職員が分かりやすいように1つずつ順に確認していきました。
- DFD確認の具体的な方法としては、参加者が共通の認識を持ちながら進められるように、机の中央に大き目のDFD(A3版)を置き、そこに確認事項を記載していくようにしました。
- しかし、障害者福祉業務は非常に広範な内容を含んでいるため、確認対象となる事業によって担当職員が変わり、それに伴って議論が分散することがありました。結果として、作業全体を通して参加者全員が常に認識を共有することが困難でした。
- DFD確認の途中で、残り時間が少なくなっていたため、DFDの確認を中断し、業務説明表の確認作業に移りました。業務説明表の「根拠法令等」欄については、事前に職員が確認していたため、即座に記載することができました。その他の「業務規模」「成果指標」等については、具体的な記載例を別途連絡した上で、職員が記載することとしました。
- 業務要件定義表については、記載内容の大まかな説明を行い、今後参加者間の電子メールでのやりとりを通じて整理していくこととしました。
【出てきた意見】
- 業務説明表の「根拠法令等」欄について、条例・規則に加えて、要綱を記載することになっていますが、障害者福祉に関する要綱はたくさんあり、どの程度記載すればよいのか判断に迷うとのことでした。今回は、条例・規則の中でも、代表的なもののみを記載することとしました。
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「根拠法令等」「所管課」欄の確認を行いました。
- DMM(1枚)・・・階層1、2を確認しました。
- DFD(6枚)・・・階層1の8機能中6機能まで確認しました。(ただし「6 自立支援給付」については途中)
|
| ■ポイント |
- DFDを事前に調整し、情報名が分からない箇所を明確にしていたことによって、一部の情報については職員が予め正式名称を確認することができました。その結果、即座にDFDへ反映することができる等、作業の進捗に寄与しました。
- 情報の滞留を考える際に、職員にとっては情報システムが最も身近な存在であり、そこに全ての情報を蓄積するものと捉える傾向がありました。実際に確認作業を進める過程では、滞留する情報の内容を職員に確認し、その内容と適合する名称をつけた台帳として記載しましたが、職員の十分な理解を得ることは難しいように感じました。DFDの記法については、職員が十分に理解できるような説明および試作の経験が必要であると思います。
- DFD上で場合分けを記載する場合、線の色を場合分けに応じて変える等の工夫が考えられますが、障害者福祉のように5つ以上の事業を含む場合には、情報の滞留や台帳等の記載が複数混在することになり、かなり複雑な表記になります。そこで、情報名や情報の流れを確認する段階では、1つの事業単位にDFDを記載しておき、最終的に機能毎に集約したDFDを作成すると分かりやすいと考えます。
|