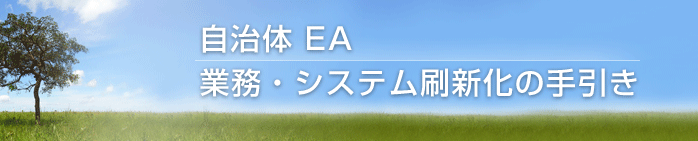| ■作業名 |
基幹業務 福祉関連業務 生活保護 現状分析(業務分析)作業(第2回) |
| ■日時 |
平成17年11月17日(木)
13:00〜15:00 |
 |
| ■場所 |
川口市役所5F大会議室 |
| ■参加者 |
職員:
福祉課 石井課長補佐、加藤主事、青羽主事 |
企業:【基幹】
日立製作所 榎本 |
| ■使った資料 |
|
| ■概要 |
【作業の目標】
- 前回作成した業務分析結果およびその後の電子メールでやり取りし整理した成果物に対し、各機能が指し示す作業内容(働き)の確認、機能間で流れる情報の論理性(機能が働くために情報が正しく繋がっているか)、情報の実体(各種情報が具体的にどのような内容を示すのか)を確認します。
【当日の流れ】
13:00〜13:05 業務説明表の確認(5分)
13:05〜14:20 機能情報関連図(DFD:以下「DFD」という)の確認(75分)
14:20〜14:50 業務要件定義表の作成(30分)
14:50〜15:00 今後の作業に関する調整(10分)
【作業内容】
- 第2回の業務分析に入るまでに、前回確認できた機能分析表(DMM:以下「DMM」という)をもとに、参加者にてDFDの素案を整理し、さらに流れる情報について事前に調査・記入しておくことにしました。参加者間での確認方法としては、電子メールを活用し、成果物(素案)のやり取りを行いました。
- その結果、第2回での業務分析は、対面での確認が可能なため、さらに詳細な部分について意見交換を行い、DFDを固めていく作業となりました。
- DFDの確認では、参加者が同じものを見て議論および意思疎通が図れるよう、議論の対象を一つの用紙に絞り、そこに赤いペンで議論の内容(指摘・修正事項)を記録していきました。
- DFDの確認作業が想定より早く終わったこともあり、その後の作業として残っている、業務要件定義表、情報実体一覧表の作成方法およびDFDとの関係性を説明し、どの部分から取りかかるか議論しました。
- その結果、業務要件定義表の「作業内容」「入出力情報」および情報実体一覧表はDFDをもととすればある程度想定できるため、これについては別途作成することとし、ここでは参加者間で協議が必要と思われる、業務要件定義表の「作業場所」「作業者」「作業時間」欄を記入していくことにしました。(上の写真はその時の様子です。)
- なお、ここで作成できなかった部分については、引き続き、今回協議した方針(作業時間は停滞時間を含むこと等)に沿って、後日記入することにしました。
【出てきた意見】
- 業務説明表の業務規模について、生活保護業務は、業務の繁忙期・閑散期があまりなく記述の仕方に困る、といったことや、規模を表す数値として被保護世帯数を記載したいが「年間総数」といった表記にそぐわない(総計となる)、との意見がありました。
|
| ■成果物 |
- 業務説明表(1枚)・・・「根拠法令等」「所管課」「業務規模」欄を記入しました。
- DMM(1枚)・・・階層1、2を確認しました。
- DFD(8枚)・・・階層1を一通り確認しました。
- 業務要件定義表(4枚)・・・一部の機能について「作業場所」「作業者」「作業量」を記入しました。
※業務要件定義表および情報実体一覧表については、本時間内で完了することはできませんでしたが、DFD確認時に、情報の実体(具体的な帳票名、紙、データ等の区分)について確認しています。
|
| ■ポイント |
- 今回は参加者が4名ということで、紙(A3用紙)の資料にて議論の対象を一つに集中させ、議論の共有化を図る工夫をしましたが、参加者の人数によっては、パソコンと投射機等を使って協議する方法も有効かと思われます。そこで協議した結果が、即座に電子的な成果物として残すことができます。
- 業務要件定義表と情報実体一覧表は、個人で作業ができる部分(成果物の素案作成、入出力情報欄の記入等)と、ある程度協議したうえで埋めるべき部分(成果物の内容確認、作業時間欄の記入等)があります。時間がない中で作業を進める場合は、この切り分けを明確にしながら始めることが効率的だと考えます。
|