2 国際協力
(1)開発途上国に対する国際協力
開発途上国に対する国際協力を大別すると,研修員の受入れ,専門家の派遣等を行う技術協力と,開発プロジェクトに対して資金を供与する資金協力との二つに分けられる。
ア.技術協力
技術協力の形態には,研修員の受入れ,専門家の派遣,機材供与,開発調査,プロジェクト方式技術協力等があり,これら政府ベースの技術協力は,主として国際協力事業団(JICA)を通じて実施されている。
(ア)研修員の受入れ
研修員の受入れは,開発途上国の通信・放送関係技術者等を我が国に受け入れて,我が国の進んだ技術の習得を目的とするもので,受入れ方式には,大別して集団研修と個別研修とがある。
集団研修は,開発途上国におけるニーズの高い分野を選定し,あらかじめ研修コースを設定し,集団的に研修を行うものである。
個別研修は,開発途上国から個々に要請される専門分野について研修を行うもので,単発要請,特定地域あるいは特定国を対象とする特設コースヘの参加,カウンターパートの受入れ,UPU,ITU等の国際機関からの要請による受入れが含まれる。研修対象者は,開発途上国の政府機関,公共機関及び民間の通信・放送関係の技術者,行政官,研究者等で,当該国政府から推薦された者である。
A 郵政事業関係
郵政事業分野における研修員の受入れは,郵政幹部セミナーの開催,APPU職員交換計画に基づく郵政職員の受入れ及び個別研修員の受入れにより実施している。
60年度は,アジア及びオセアニア地域等を対象とする郵政幹部セミナーを開催し,地域内に共通する郵便業務の管理,運営等の諸問題とその解決策をテーマとして,14か国から14名が参加した。60年度に個別研修員として受け入れた13名の内訳は,APPU職員交換計画で11名,郵便切手のデザイン,郵便訓練制度の分野でそれぞれ1名ずつである。
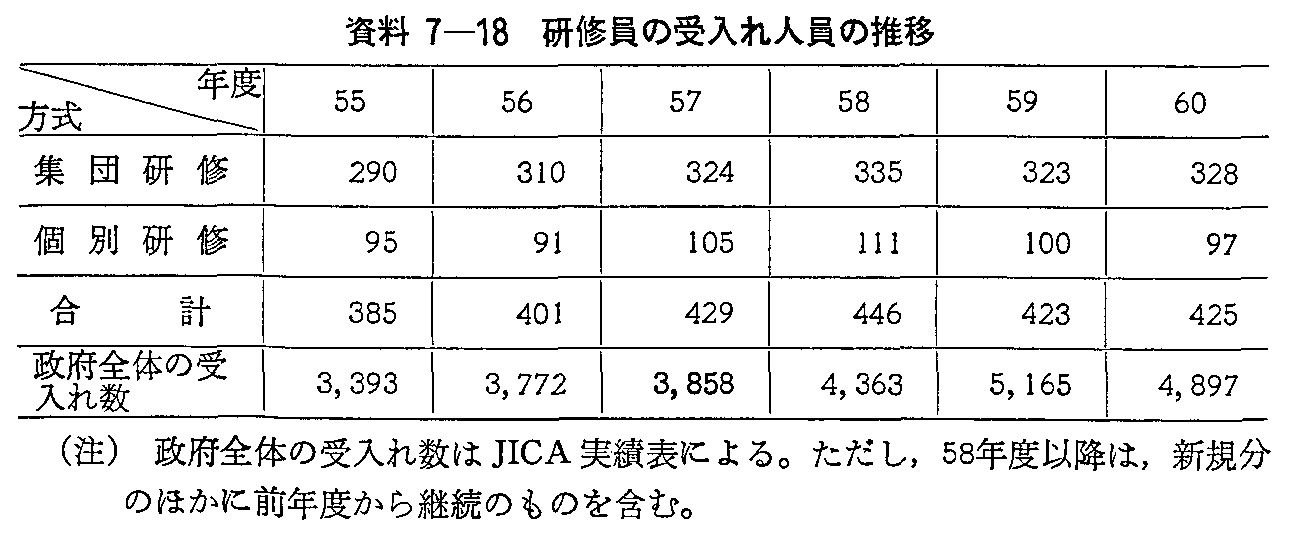
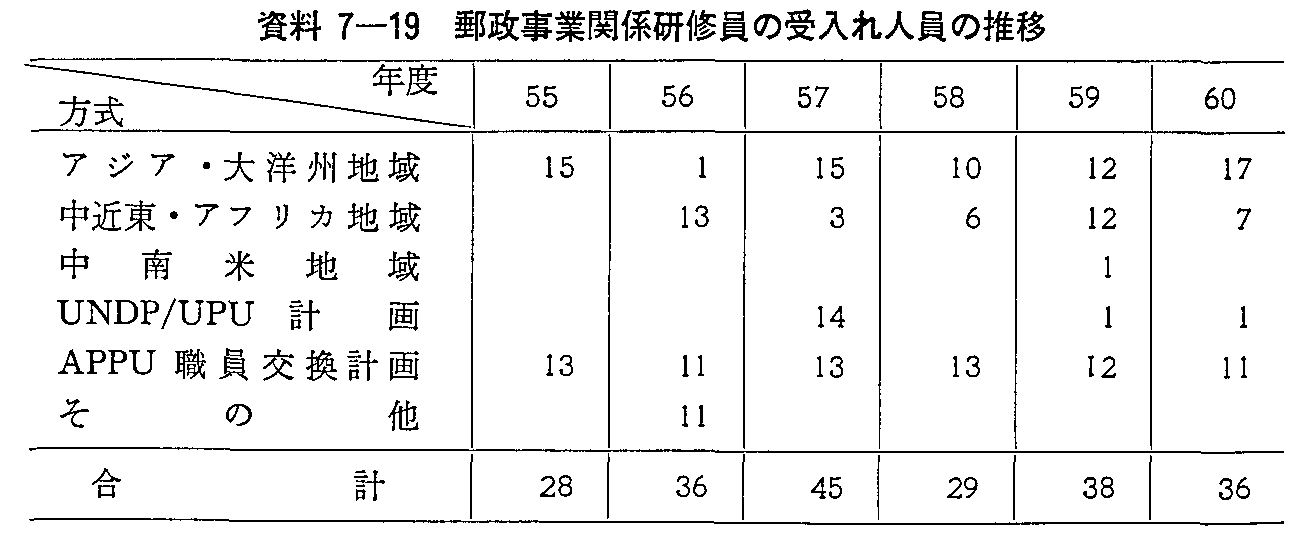
B 電気通信関係
電気通信分野における研修員の受入れは,当初,開発途上国の個々の要請に基づき,個別研修として実施されていたが,集団研修コースを創設して以来,コースの拡充・強化に努めている。
60年度に個別研修員として受け入れた56名の内訳は,交換5か国5名,伝送2か国2名,線路11か国19名,無線8か国8名(衛星5か国5名),電波監視2か国3名,その他10か国19名である。
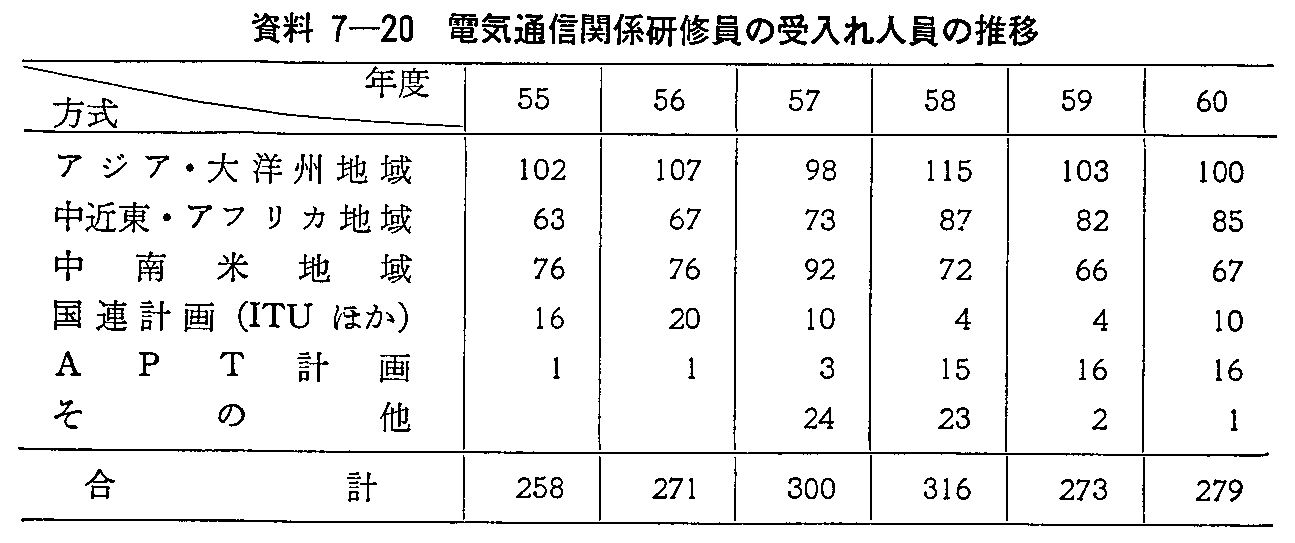
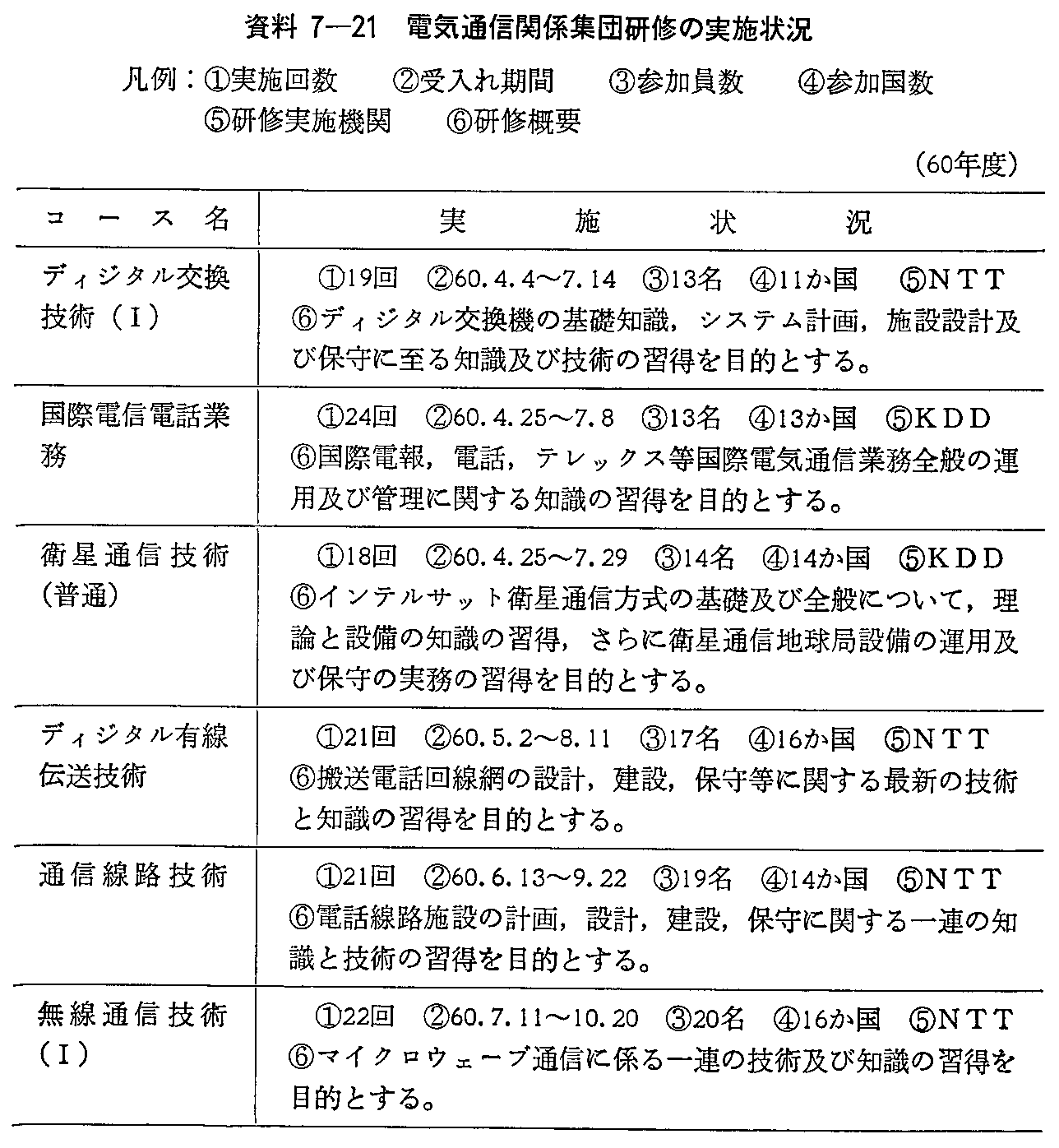
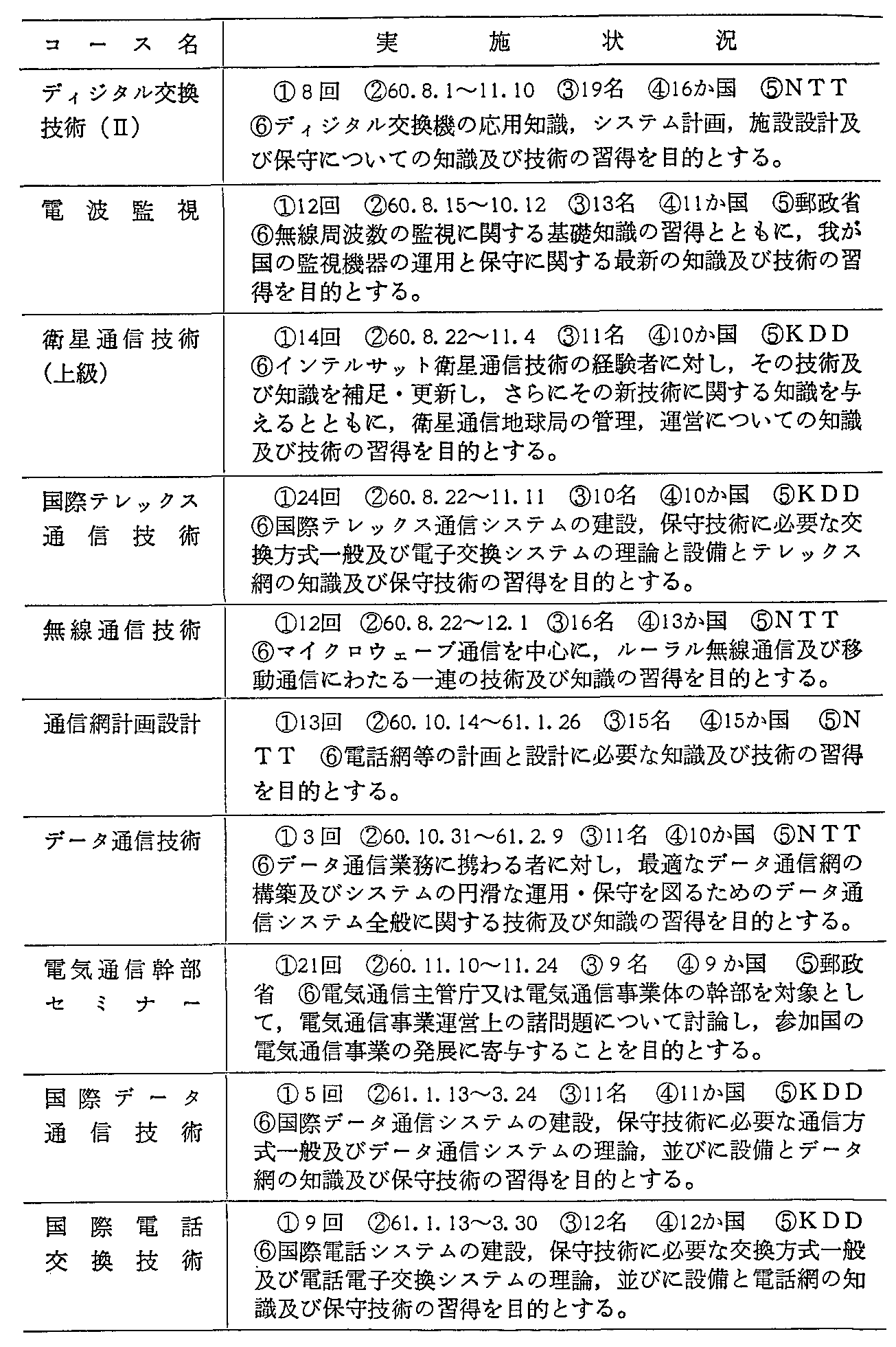
C 放送関係
放送分野における研修員の受入れは,当初,開発途上国の個々の要請に基づき,研修可能な分野について個別研修員として受け入れていたが,集団研修コースを創設して以来,コースの拡充・強化に努めている。
60年度に個別研修員として受け入れた27名の内訳は,番組制作2か国5名,制作技術7か国13名,送信技術1か国1名,その他3か国8名である。
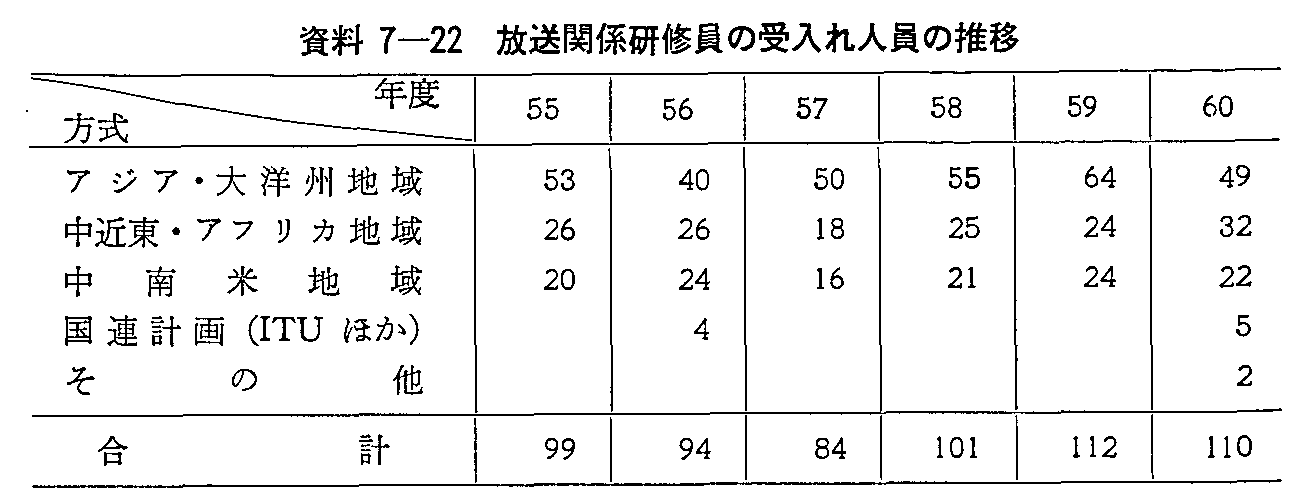
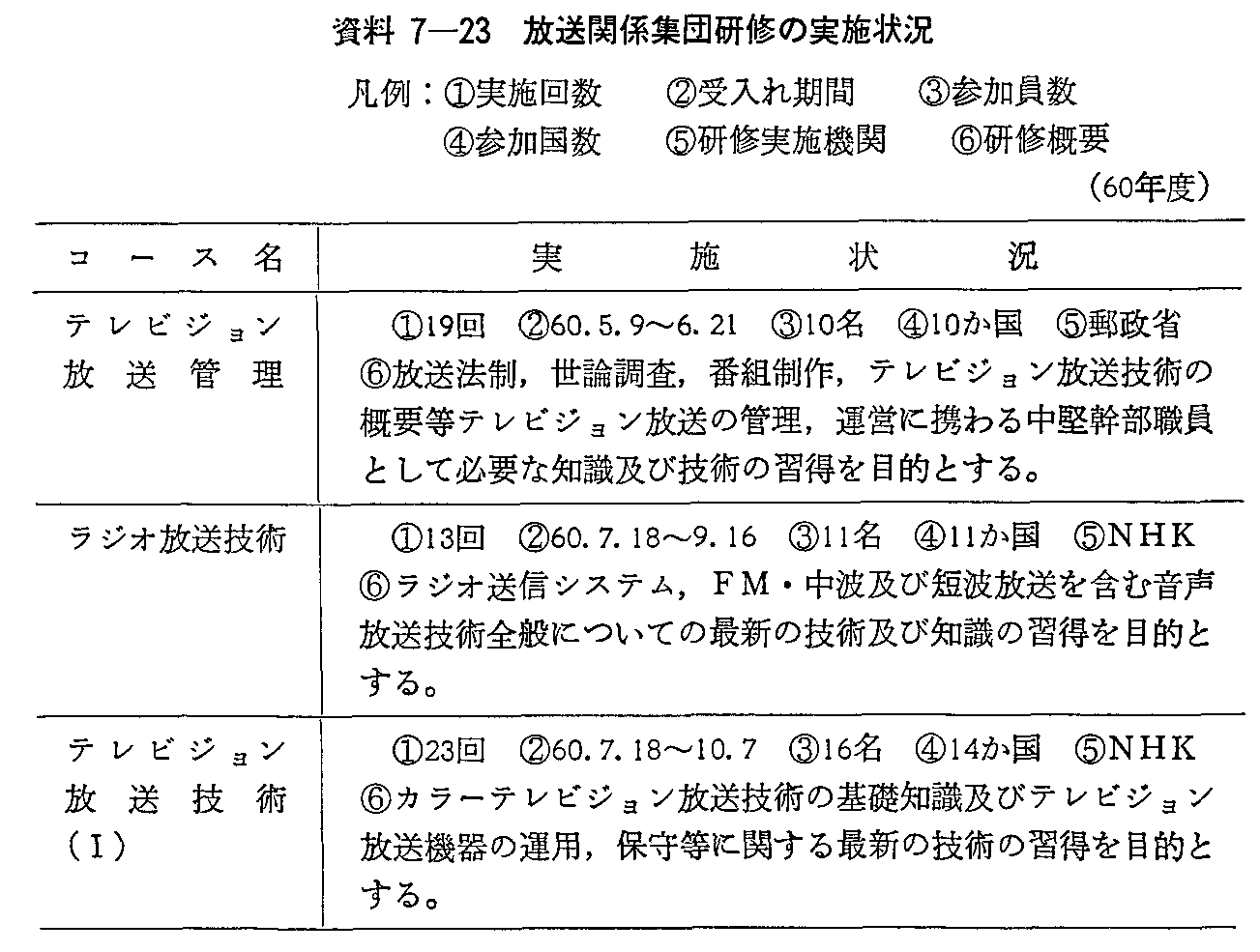
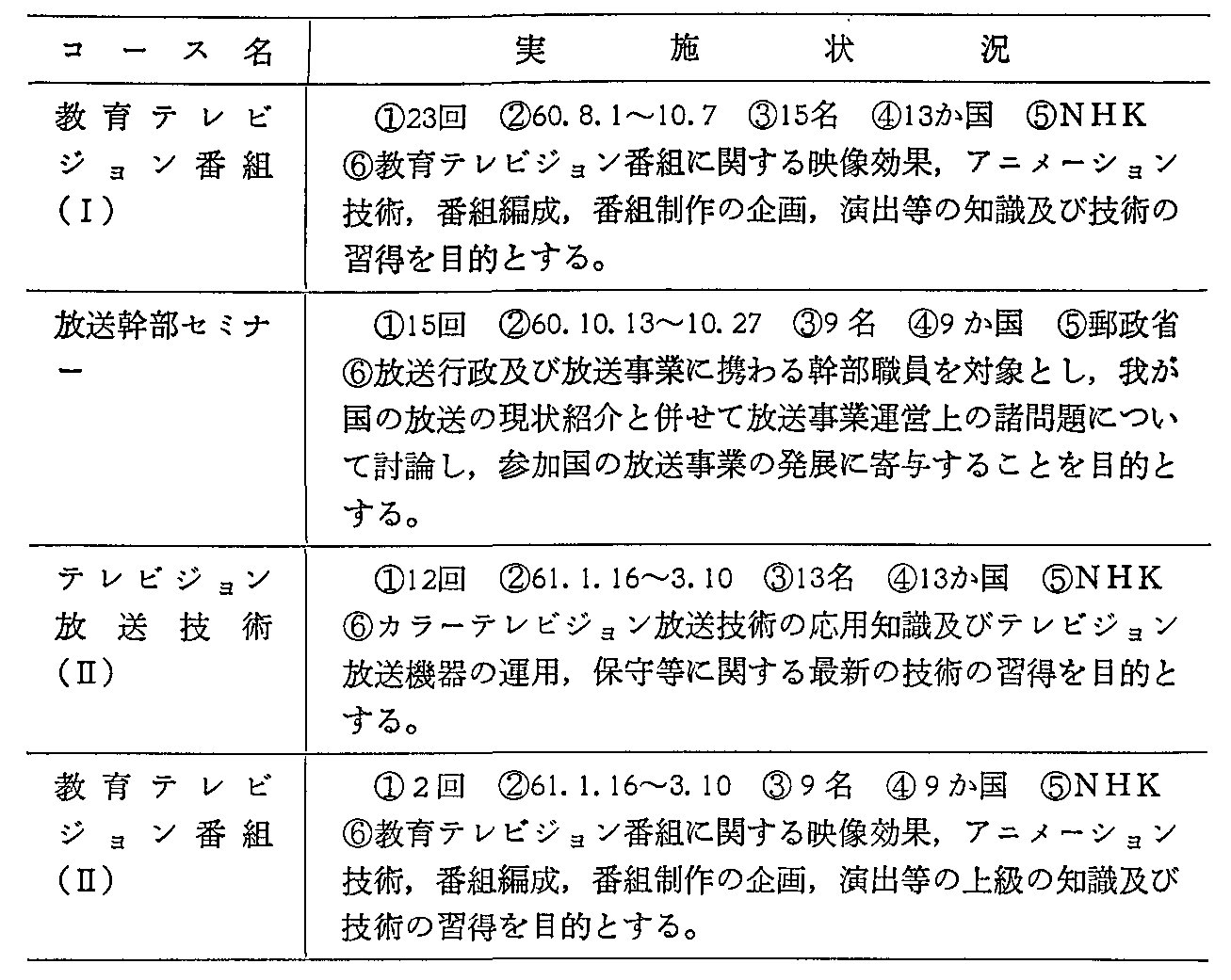
D 第三国研修
第三国研修は,我が国が特定の開発途上国で協力しているプロジェクトや電気通信訓練センター等に,生活環境の類似した近隣諸国から研修員を受け入れて,技術移転を効率的に実施する現地研修方式である。
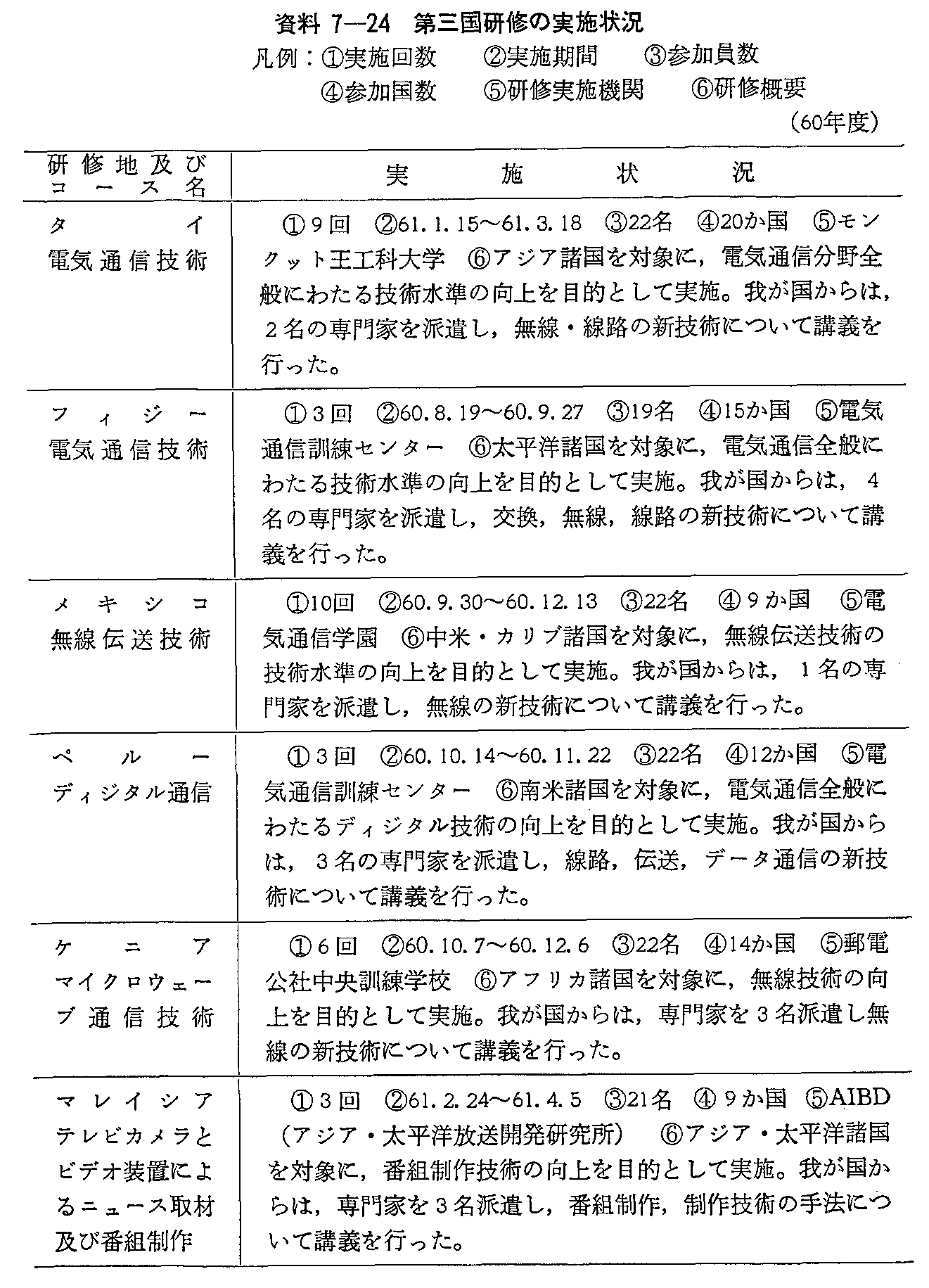
E 帰国研修員巡回指導
帰国研修員巡回指導は,帰国研修員に対するフォローアップ事業の一環として,彼らの所属機関等を訪問し,当該研修コースの効果測定,問題点及びニーズの把握,新技術の紹介等を行うことを目的として実施するものである。
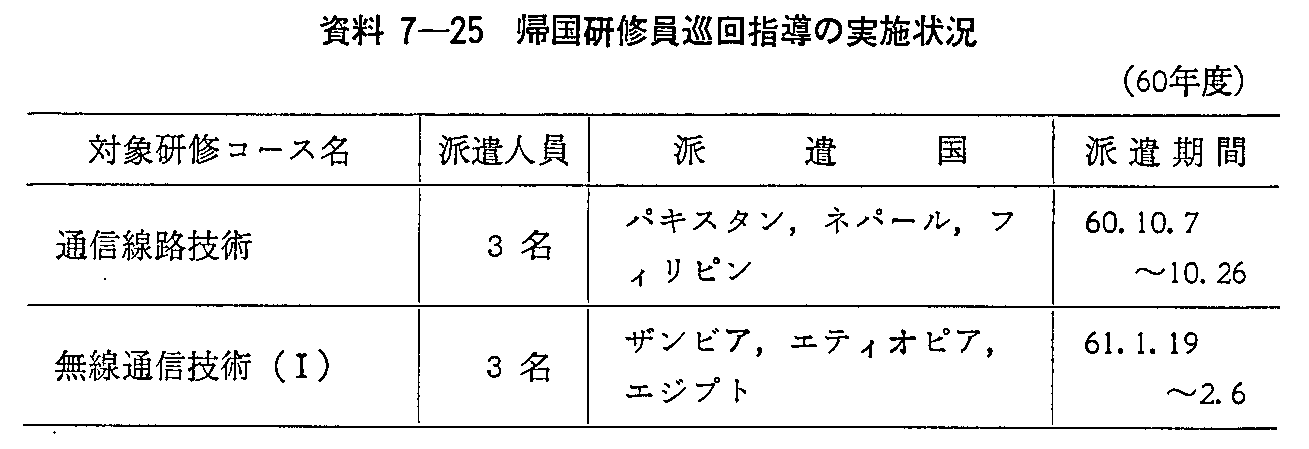
(イ)専門家の派遣
専門家の派遣は,開発途上国の郵便・通信・放送関係の主管庁,事業運営体,研究機関,教育訓練機関等へ専門家を派遣し,郵政事業・通信・放送開発計画の企画・助言,施設の建設,保守,運用面の指導,職員の訓練等を行うことにより開発途上国の人材育成に貢献することを目的として実施するものである。
A 郵政事業関係
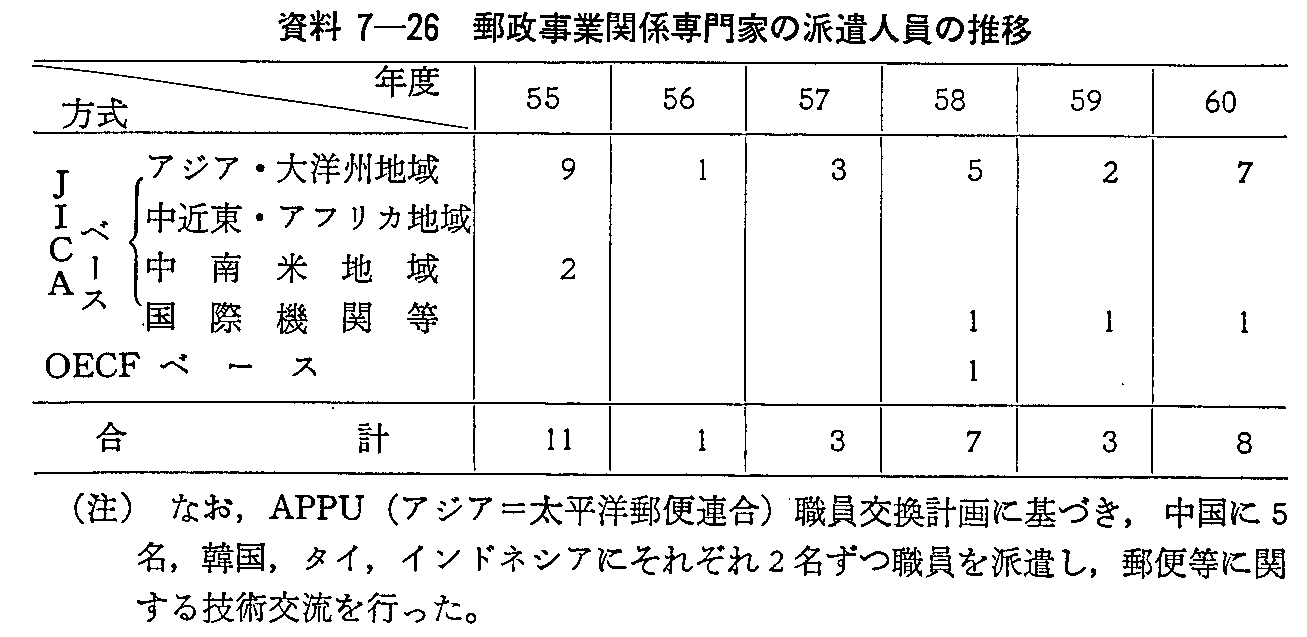
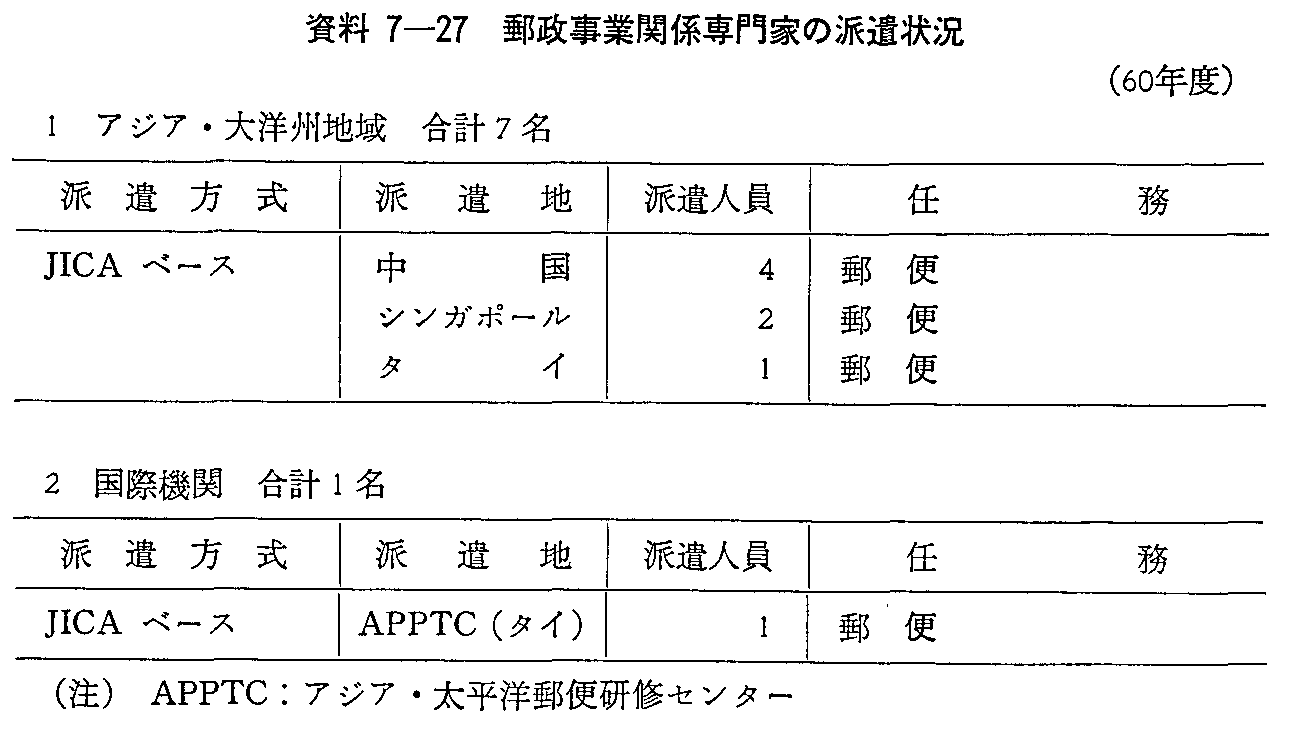
B 電気通信関係
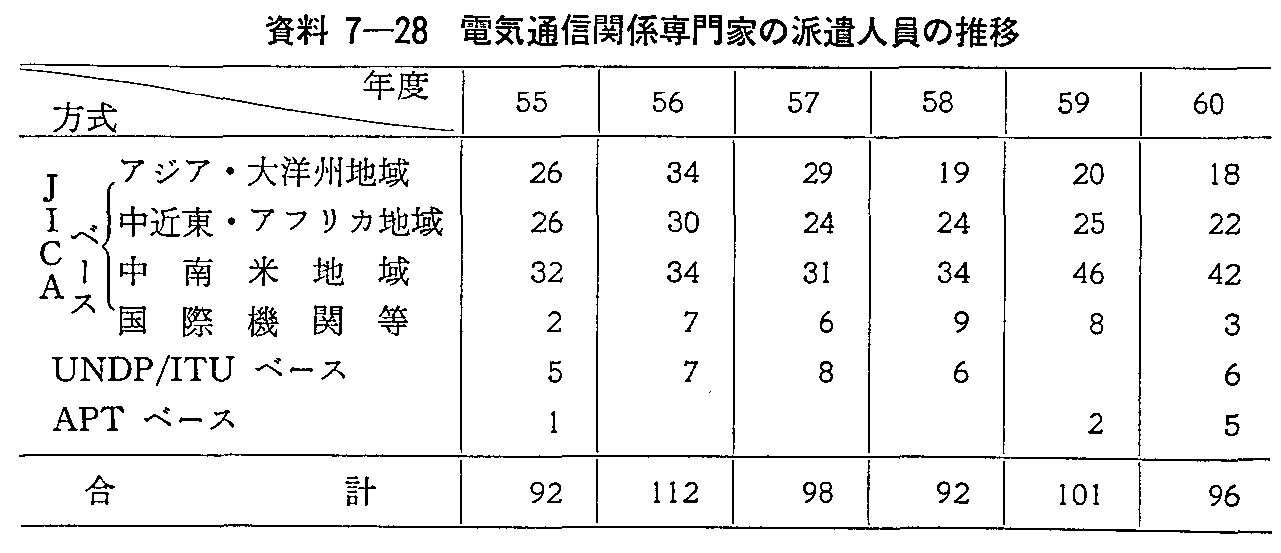
C 専門家派遣要請背景調査
専門家派遣要請背景調査は,専門家の派遣を実施するために必要な情報を入手し,併せて,日本の専門家派遣制度の説明を行うために実施している。
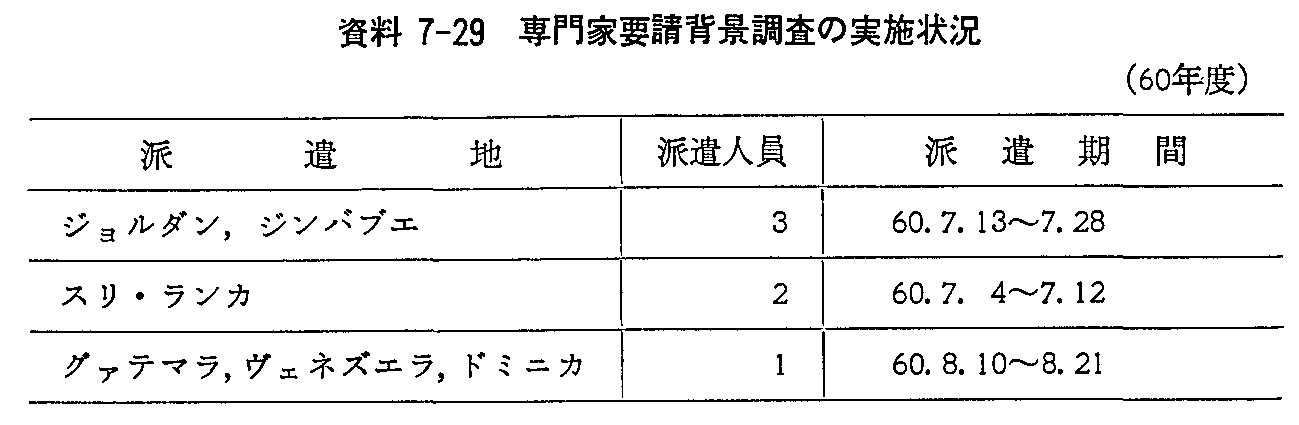
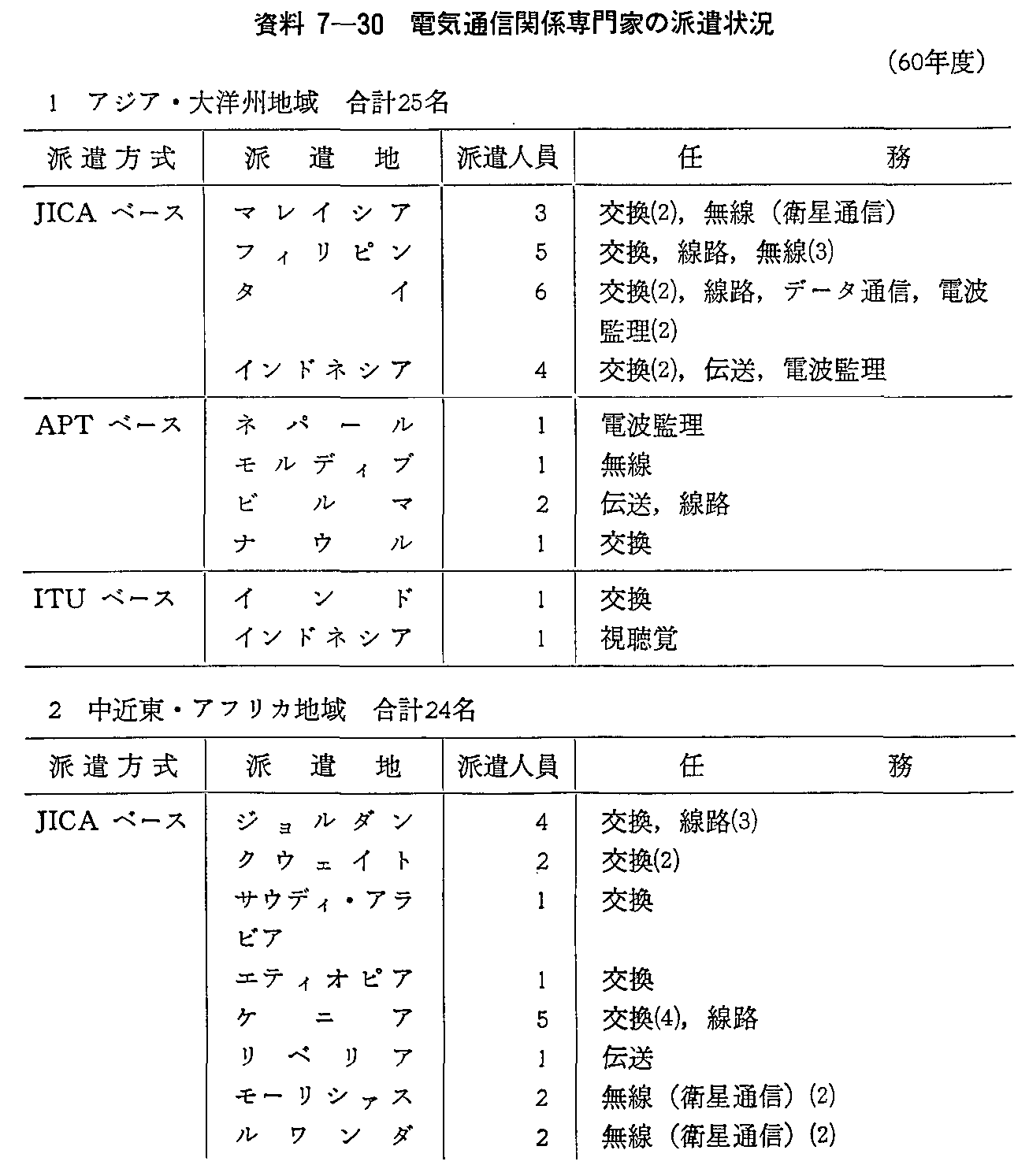
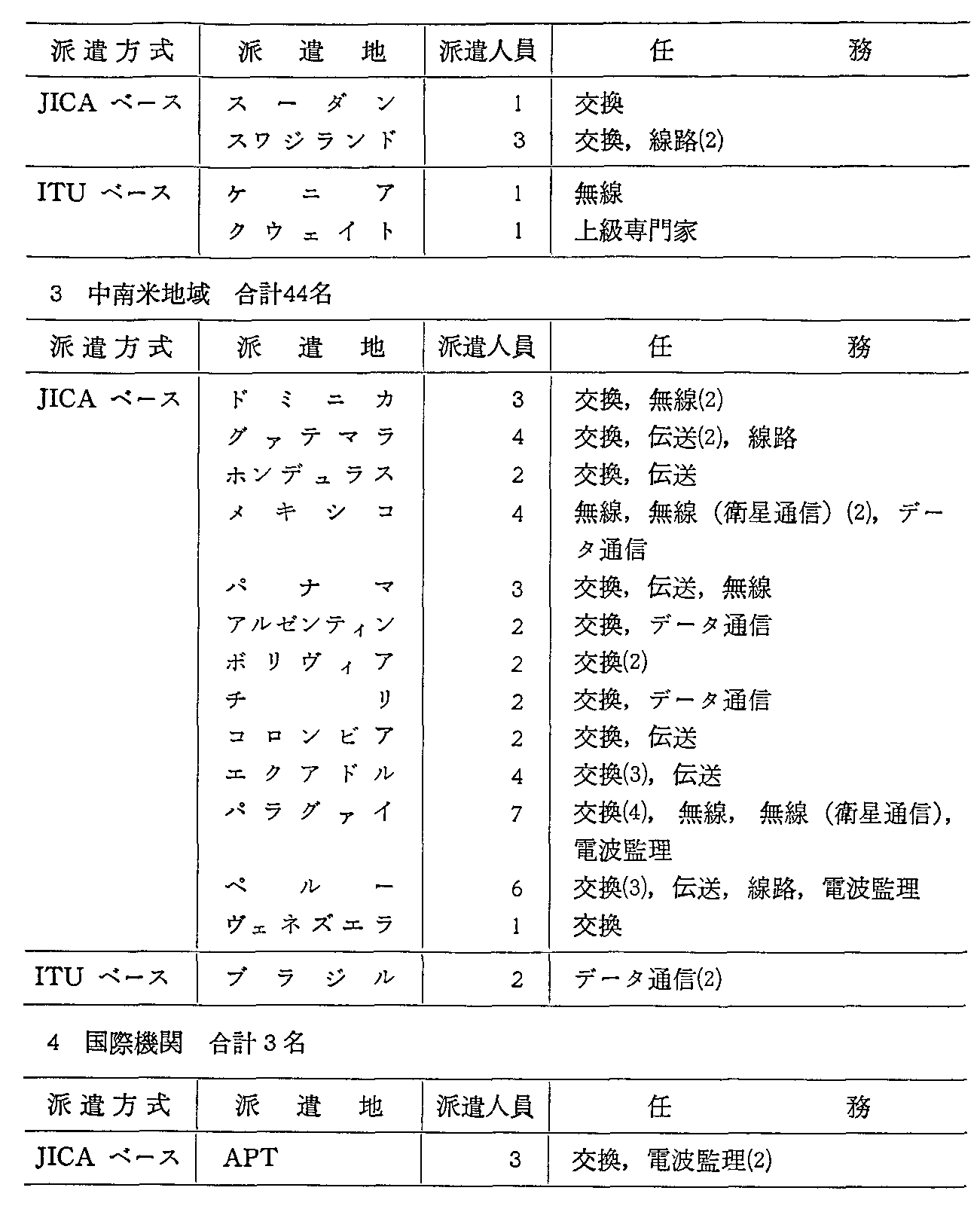
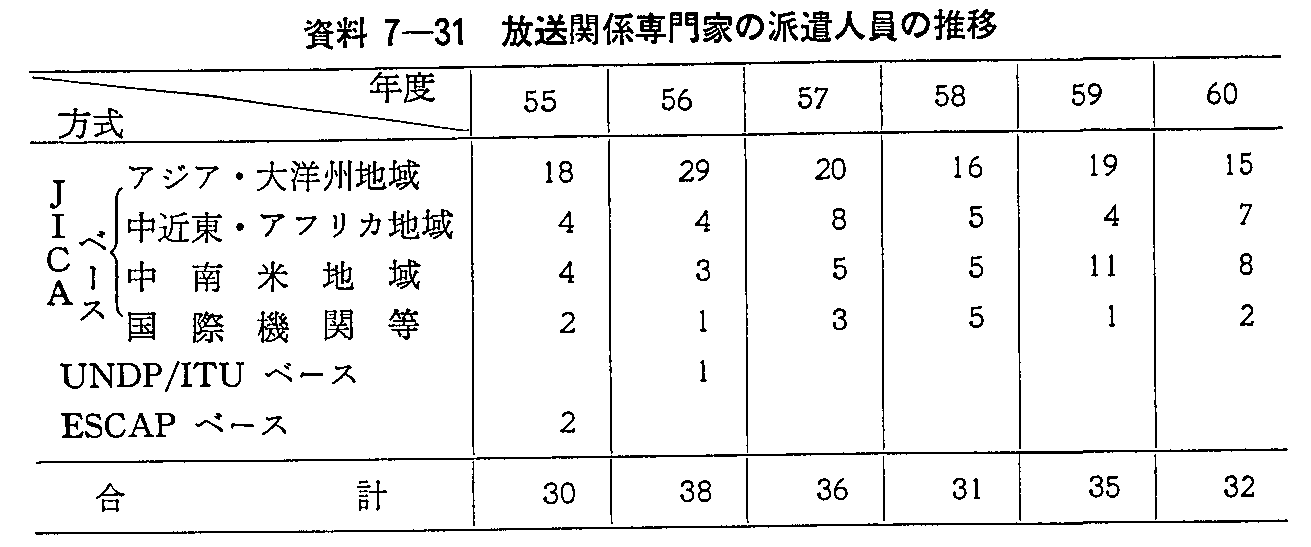
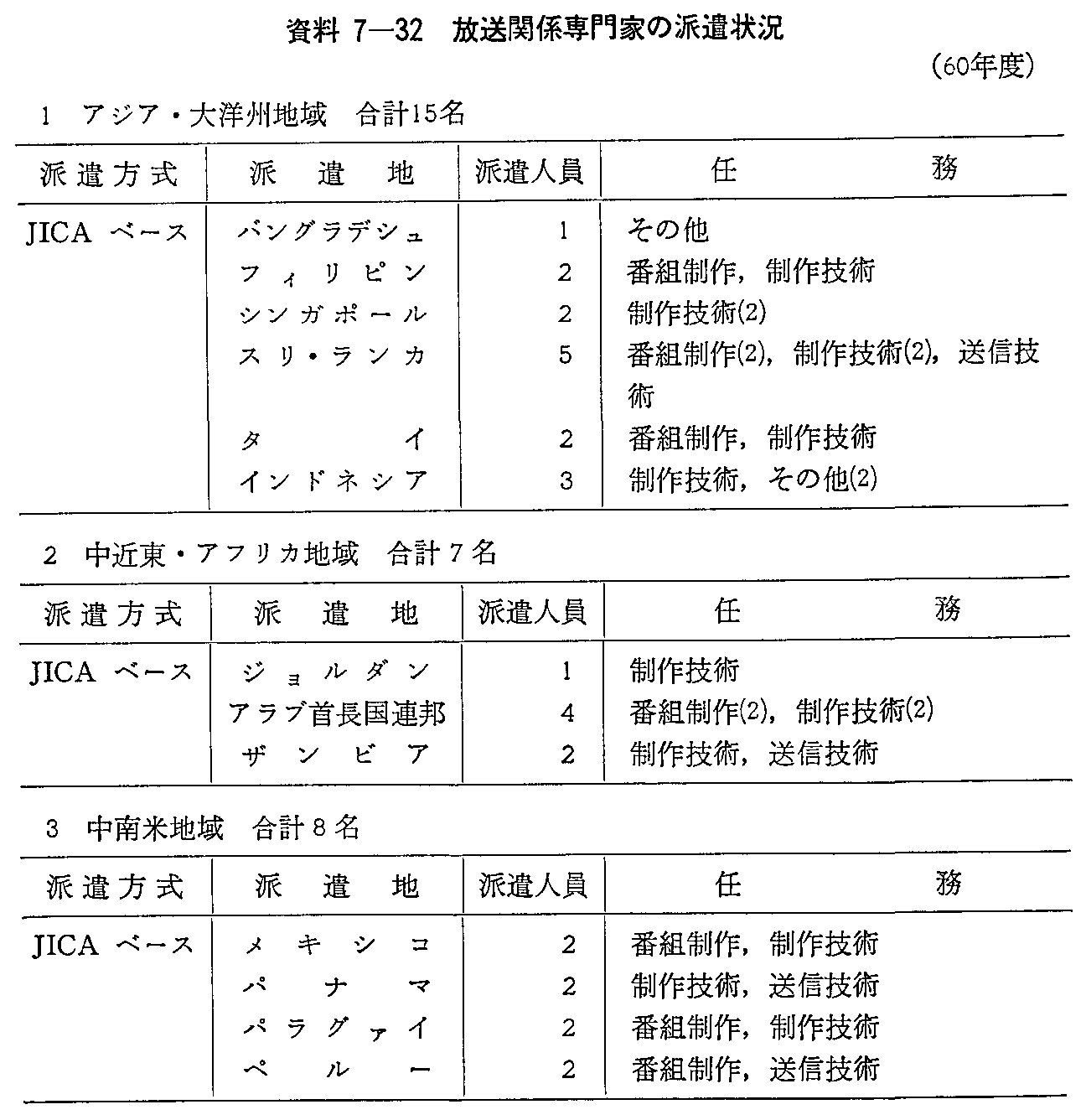
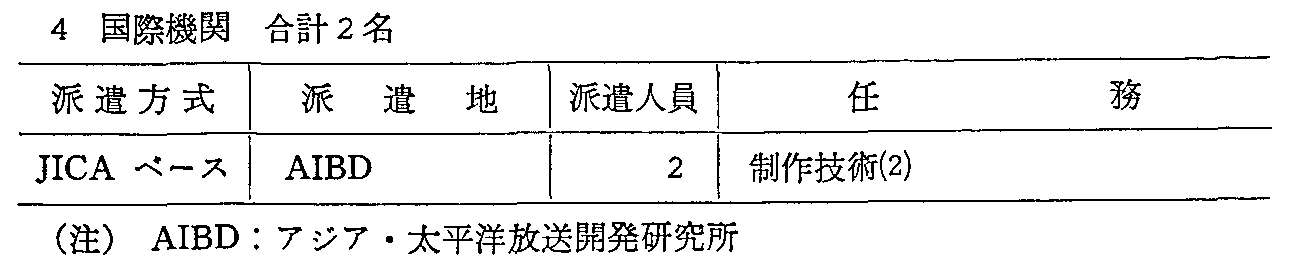
(ウ)プロジェクト方式技術協力
プロジェクト方式技術協力は,開発途上国における技術者等の養成,技術の研究開発等を目的とすRプロジェクトに対し,我が国政府が専門家の派遣,研修員の受入れ,機材の供与を有機的に関連付けて通常5か年にわたり計画的かつ総合的に運営実施する協力形態である。
60年度において通信・放送・コンピュータ分野のプロジェクトに対し派遣された専門家は35名,調査団は11件28名,我が国に受入れたカウンターパートは28名,また,我が国の機材供与総額は2.54億円であった。
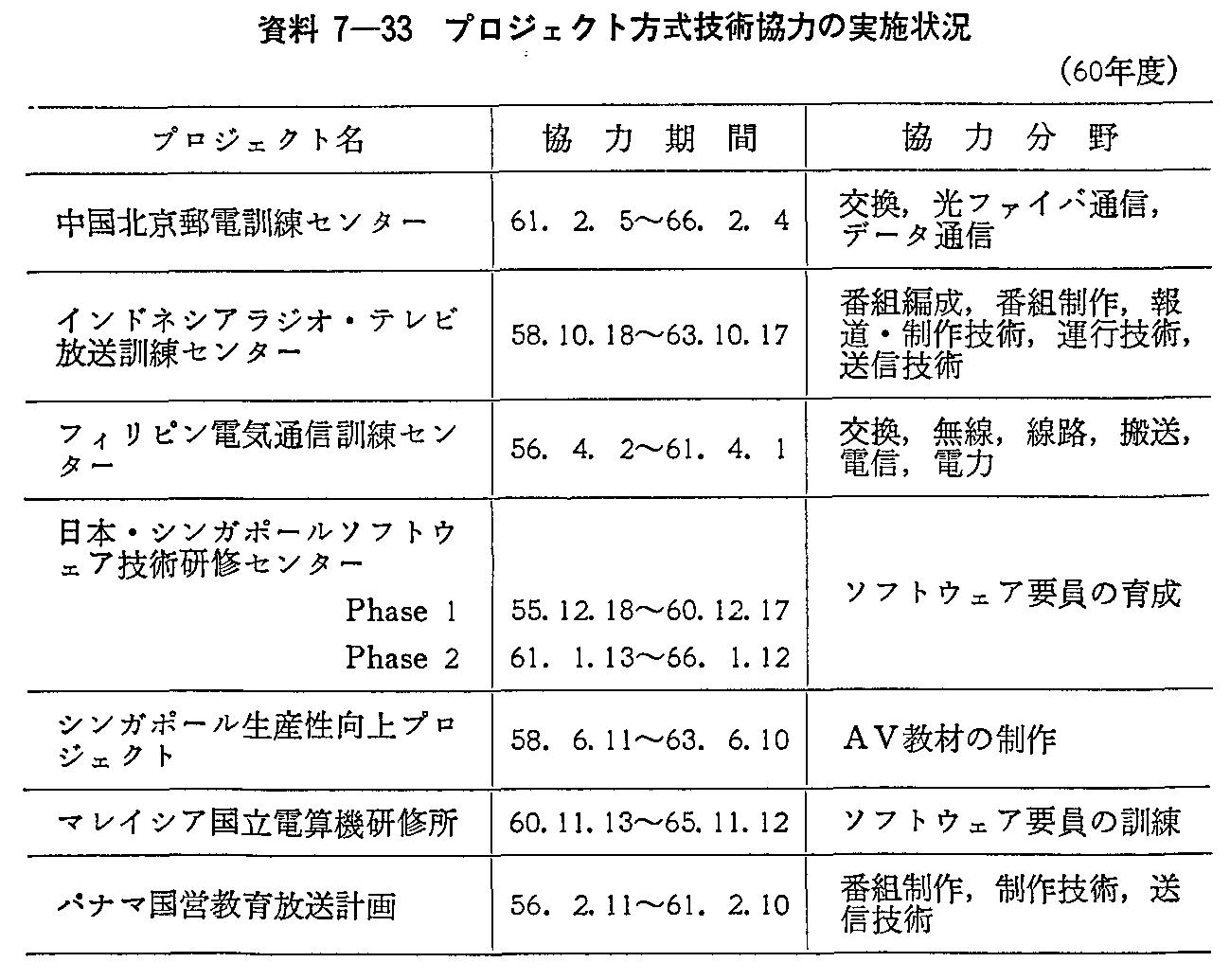
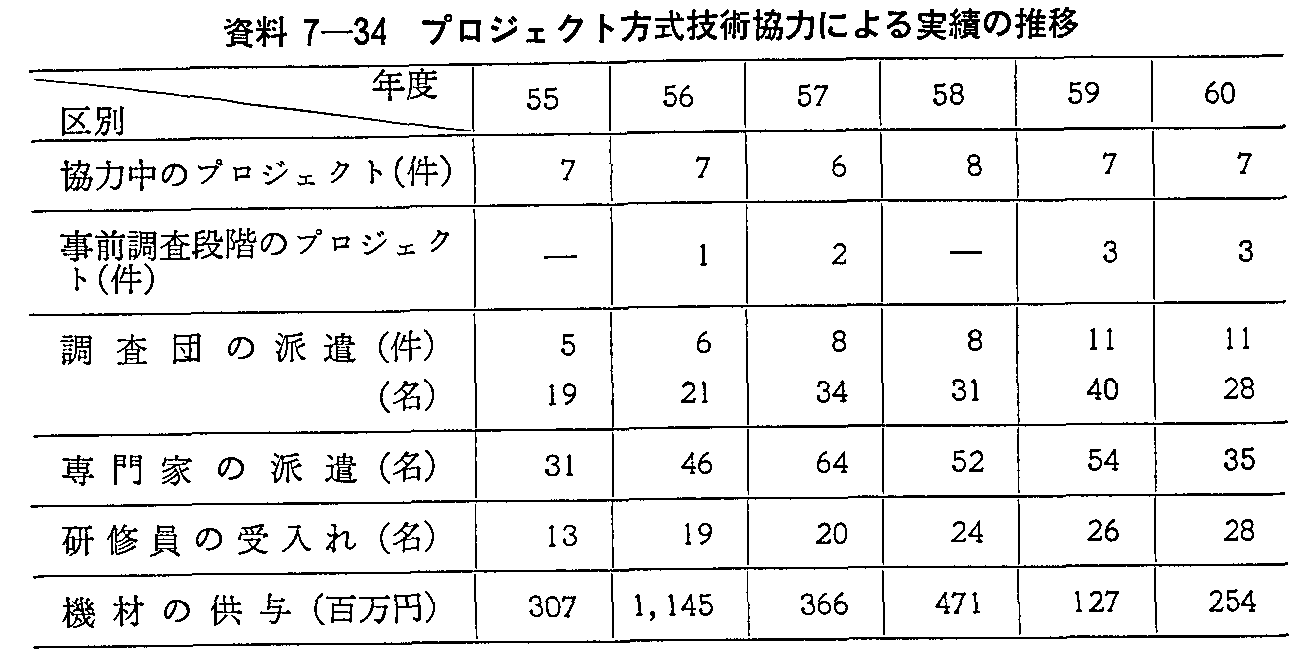
(エ)開発調査
開発調査は,開発途上国の公共的な開発計画に対し,調査団を派遣し,開発途上国の電気通信開発計画に関して,現地調査及び国内作業を行い,その開発計画の推進に寄与する報告書を作成するものである。
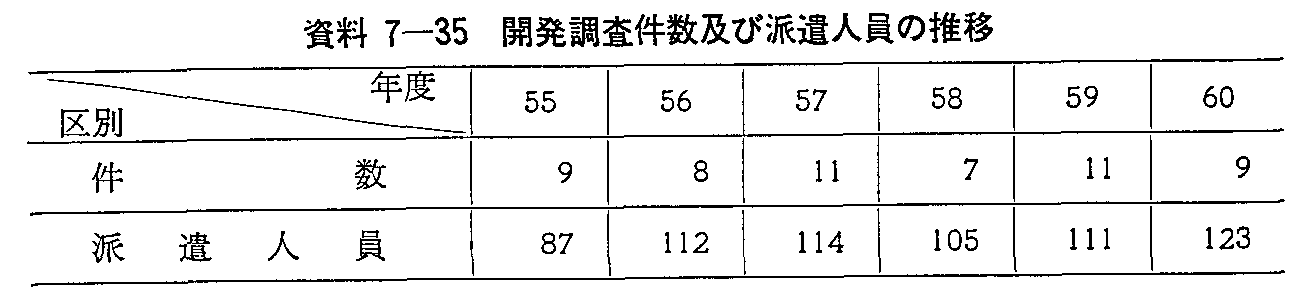
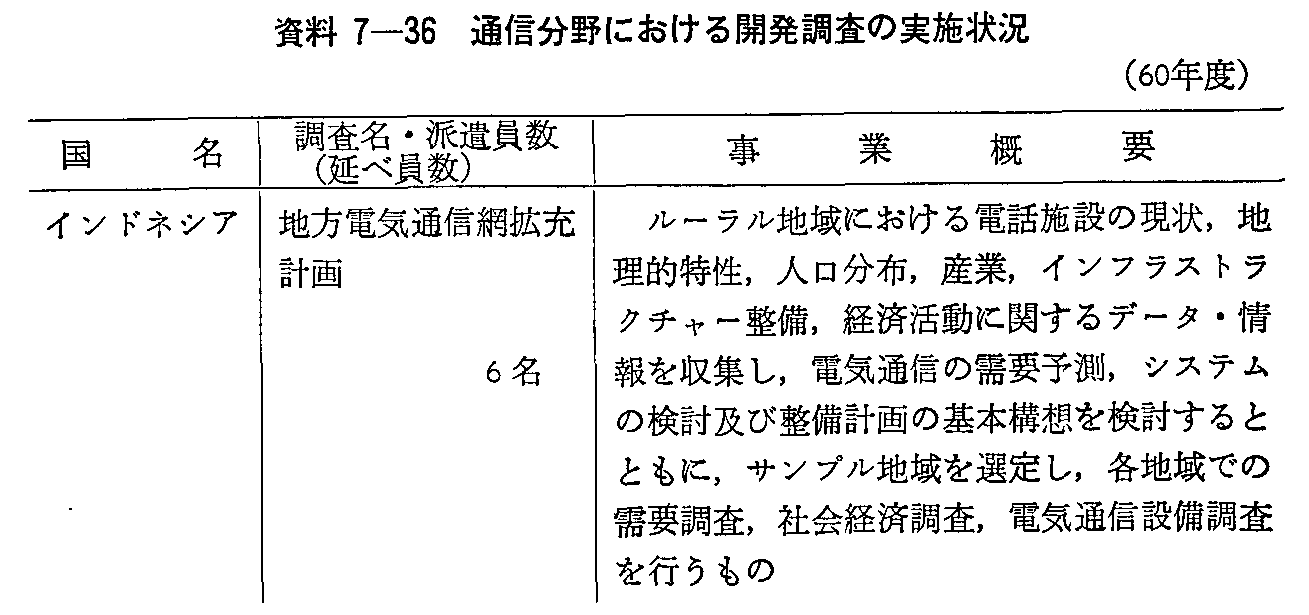
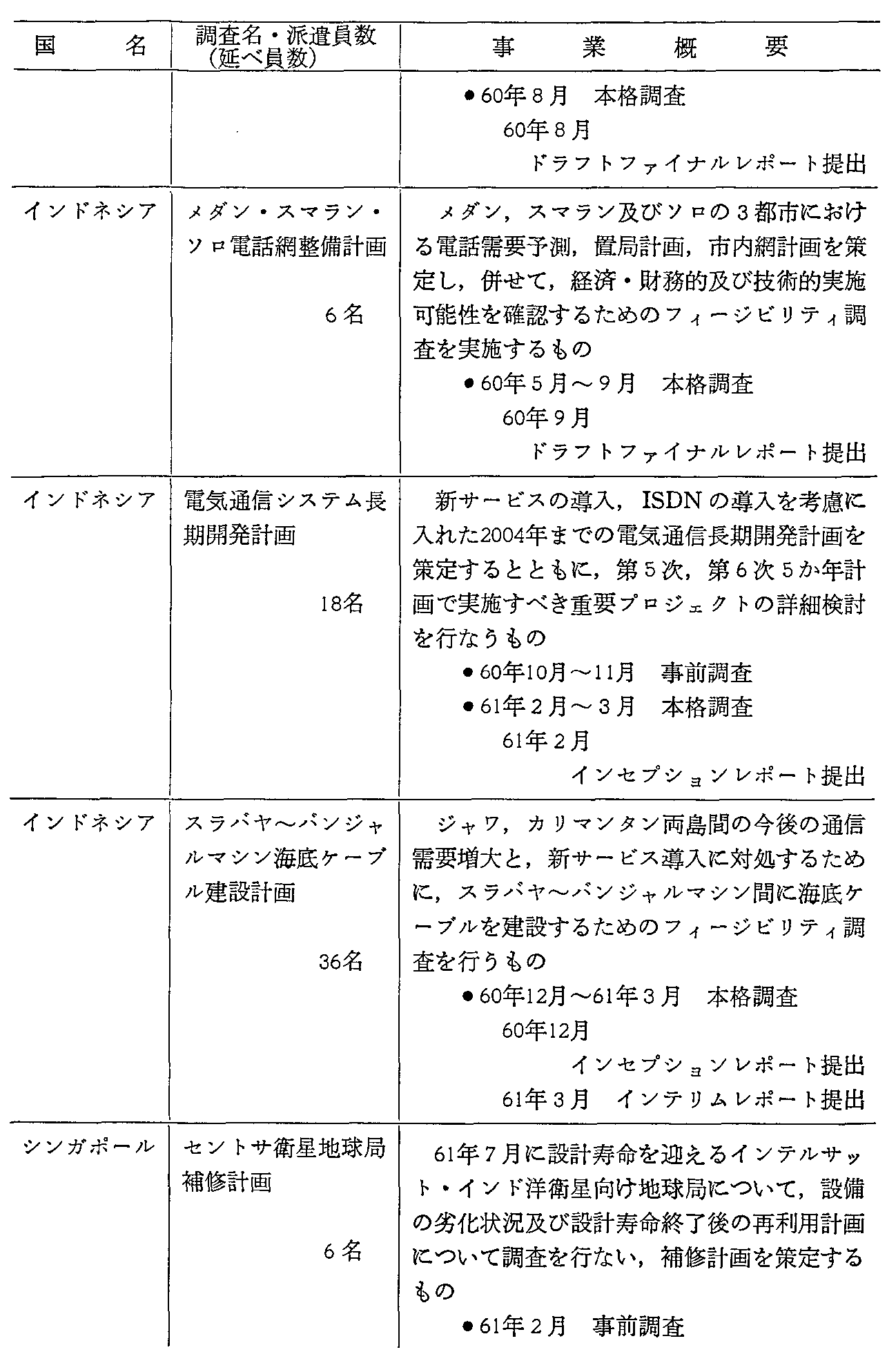
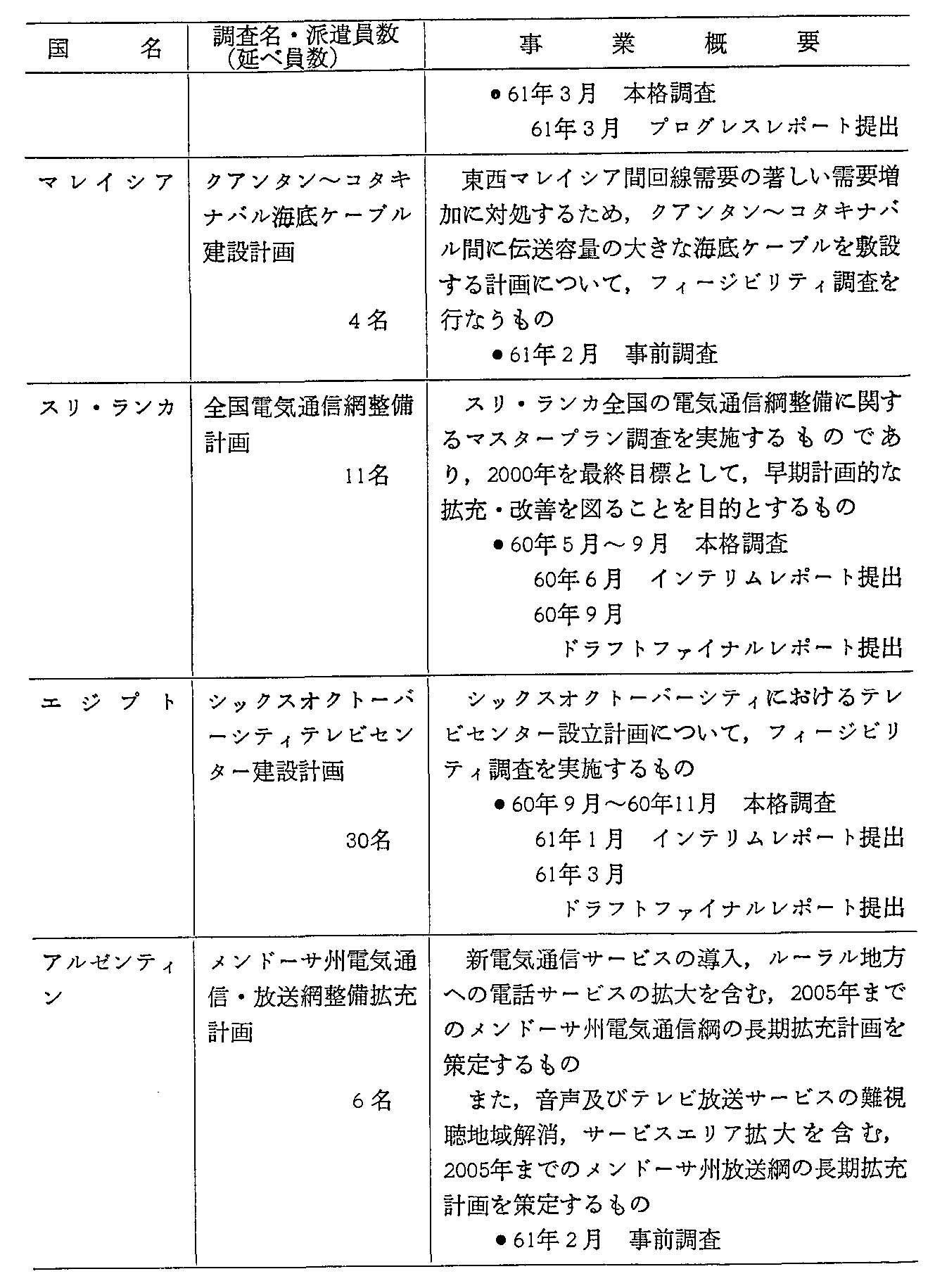
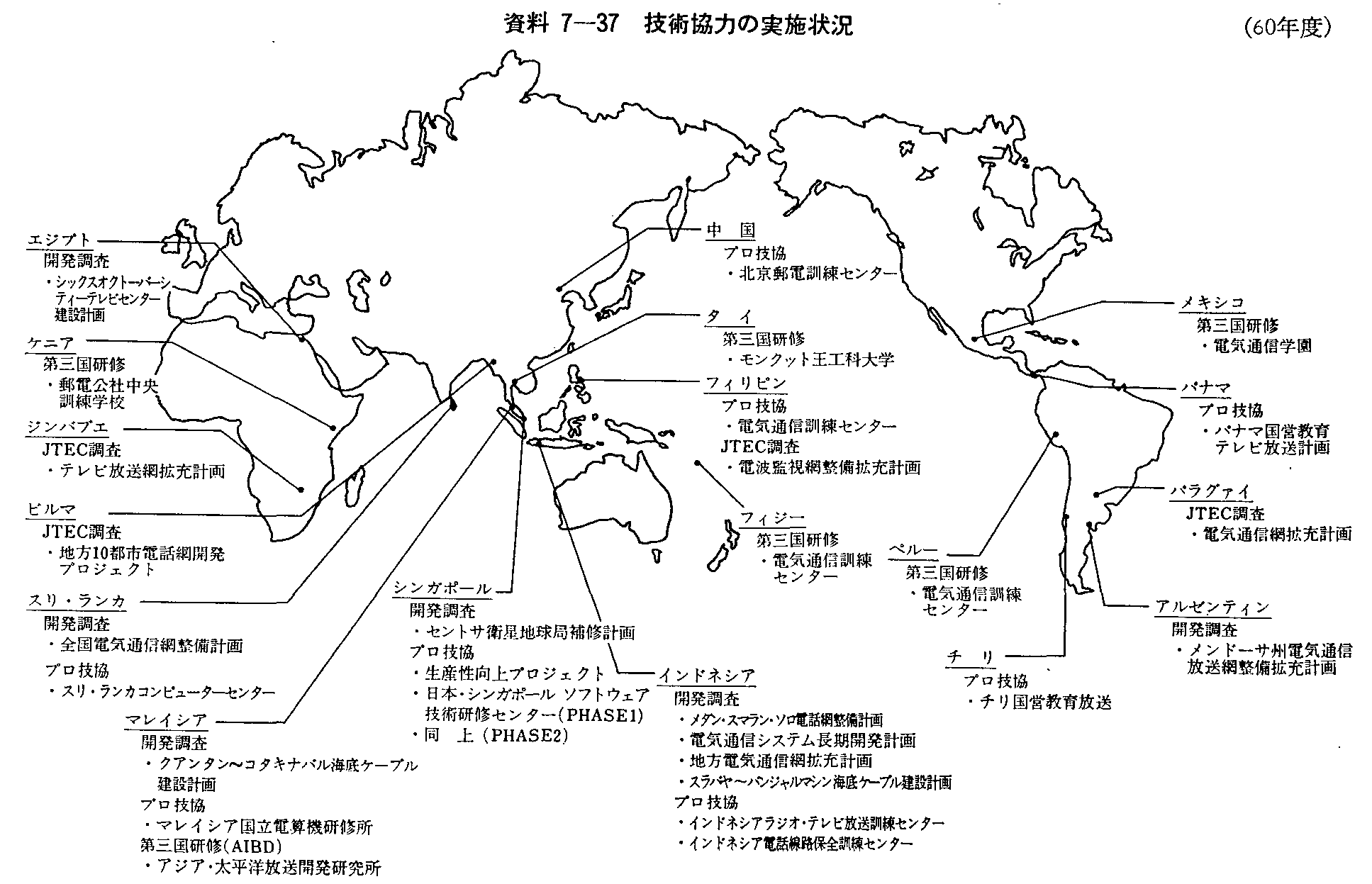
(オ)海外通信技術協力振興事業
通信・放送分野における我が国の国際協力体制を強化するため,[1]プロジェクトのフォーメーション及び円滑な実施のための事前調査,[2]技術協力基盤強化のため,海外派遣専門家の育成,[3]海外研修員受入事業を実施した。
イ.資金協力
(ア)円借款
60年度における通信分野における円借款は,11件502.55億円(全体の8.2%)に達し(交換公文ベース),電気通信網整備,衛星地球局の建設等に対する協力を中心に実施されている。
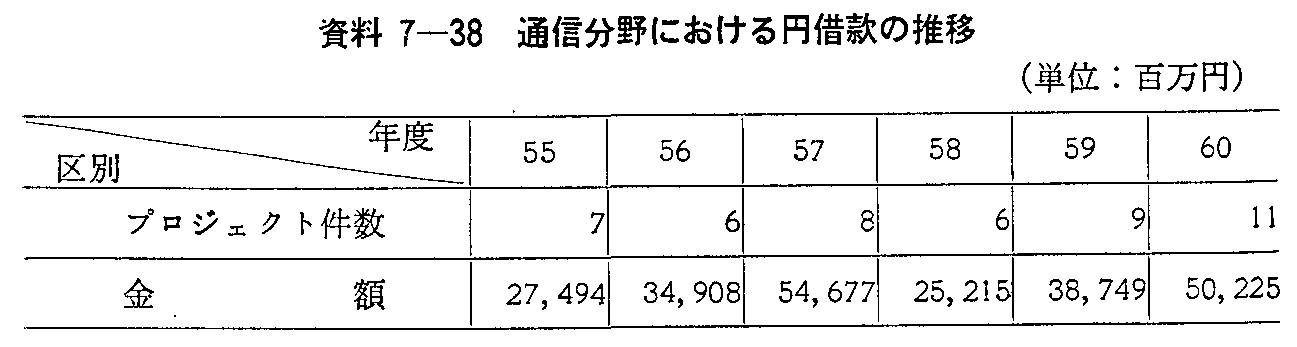
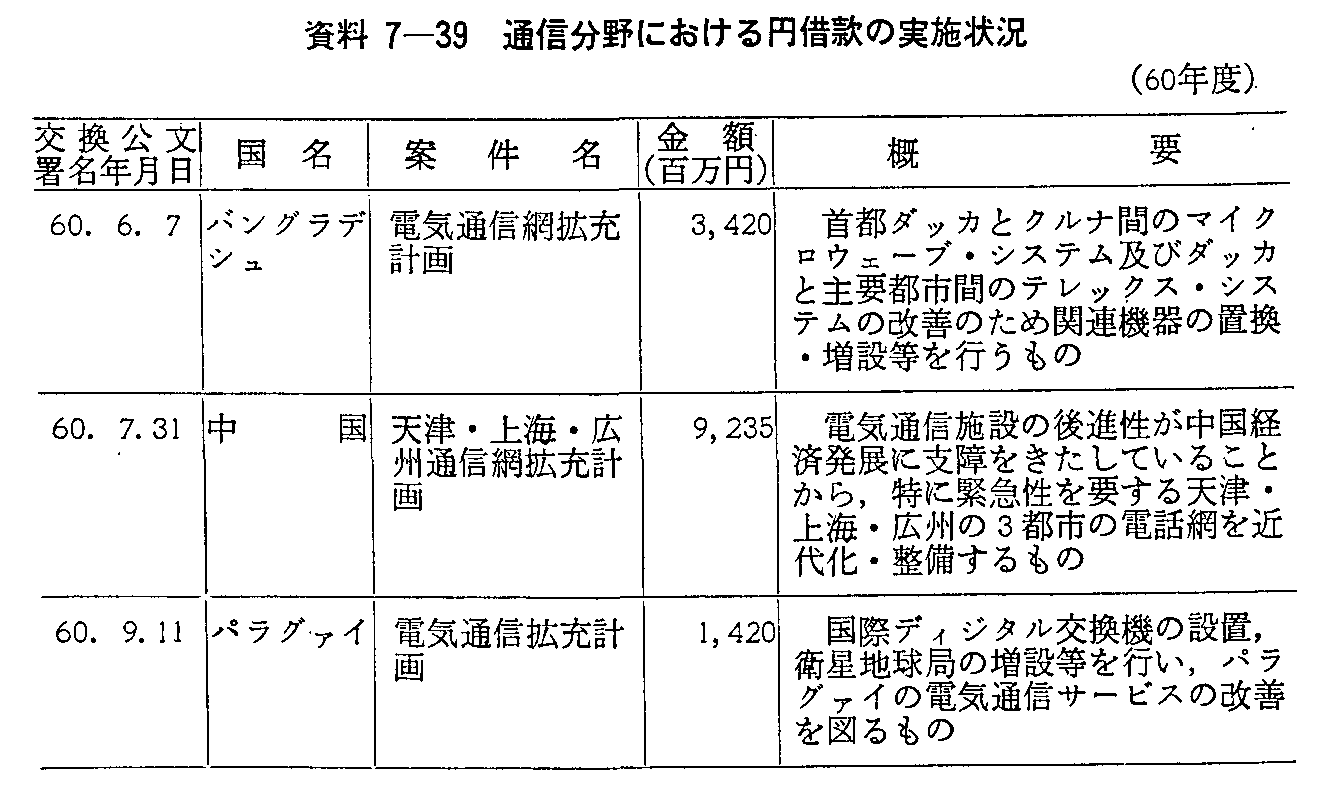
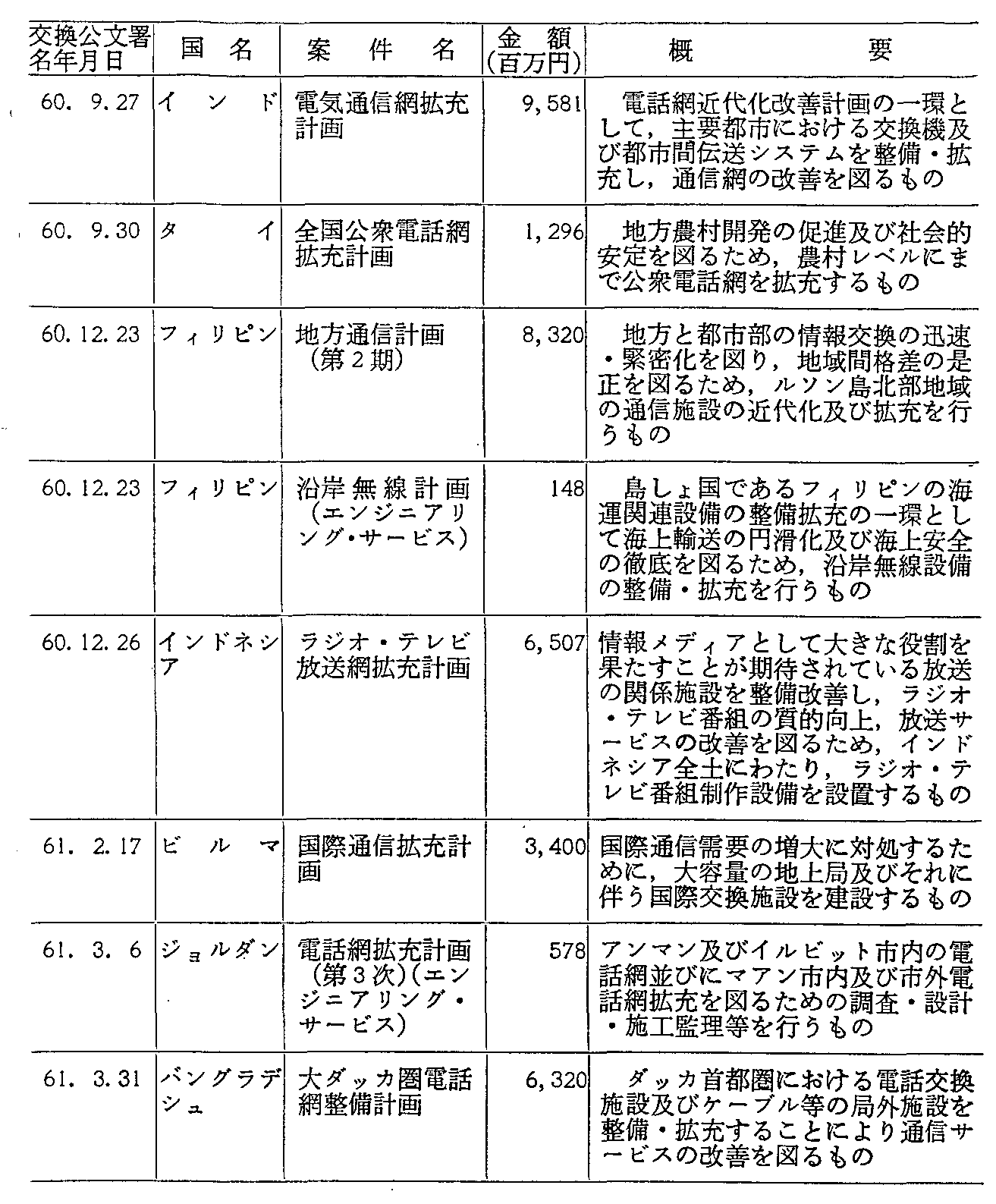
(イ)無償資金協力
60年度における通信・放送分野の無償資金協力では8件,54.83億円(対同一年度一般無償実績全体の5.7%)について交換公文締結が行われた。放送網拡充,LLDC(後発開発途上国)の電気通信網整備に対する協力等が実施されている。
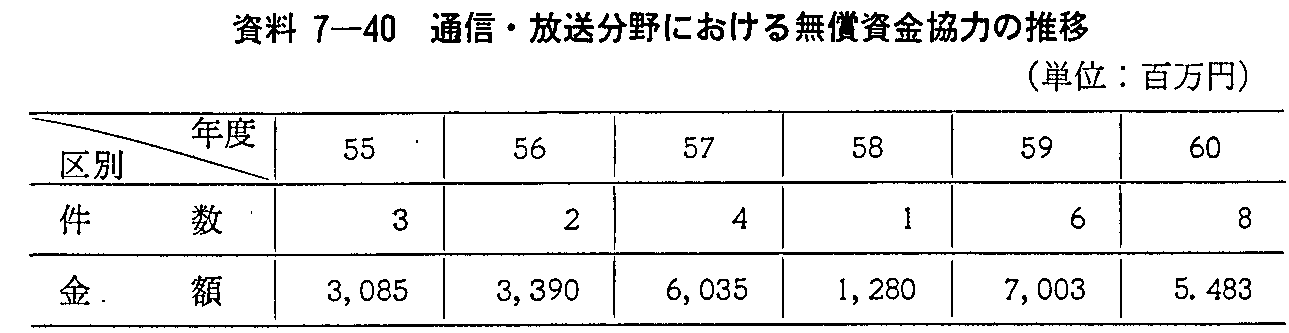
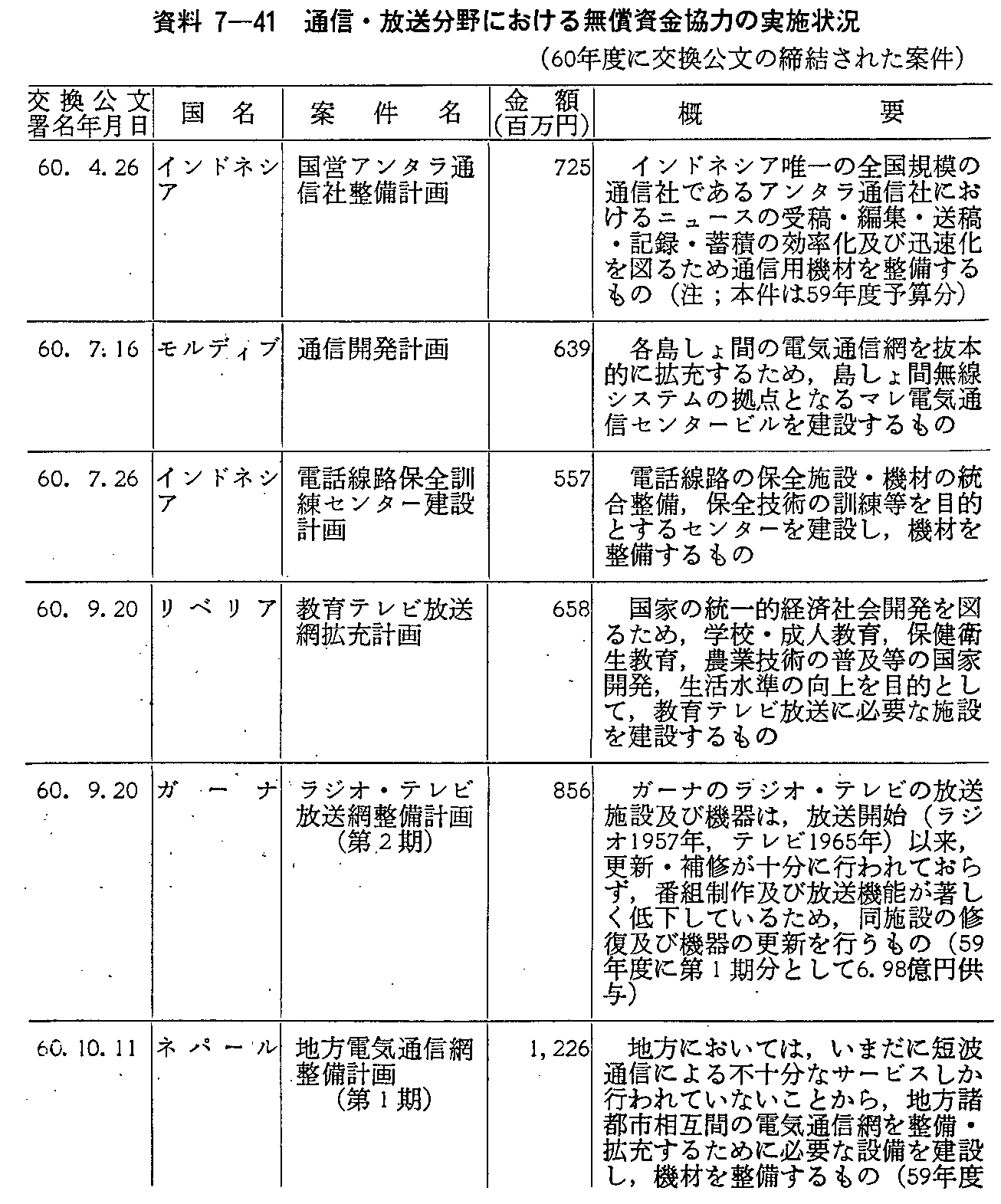
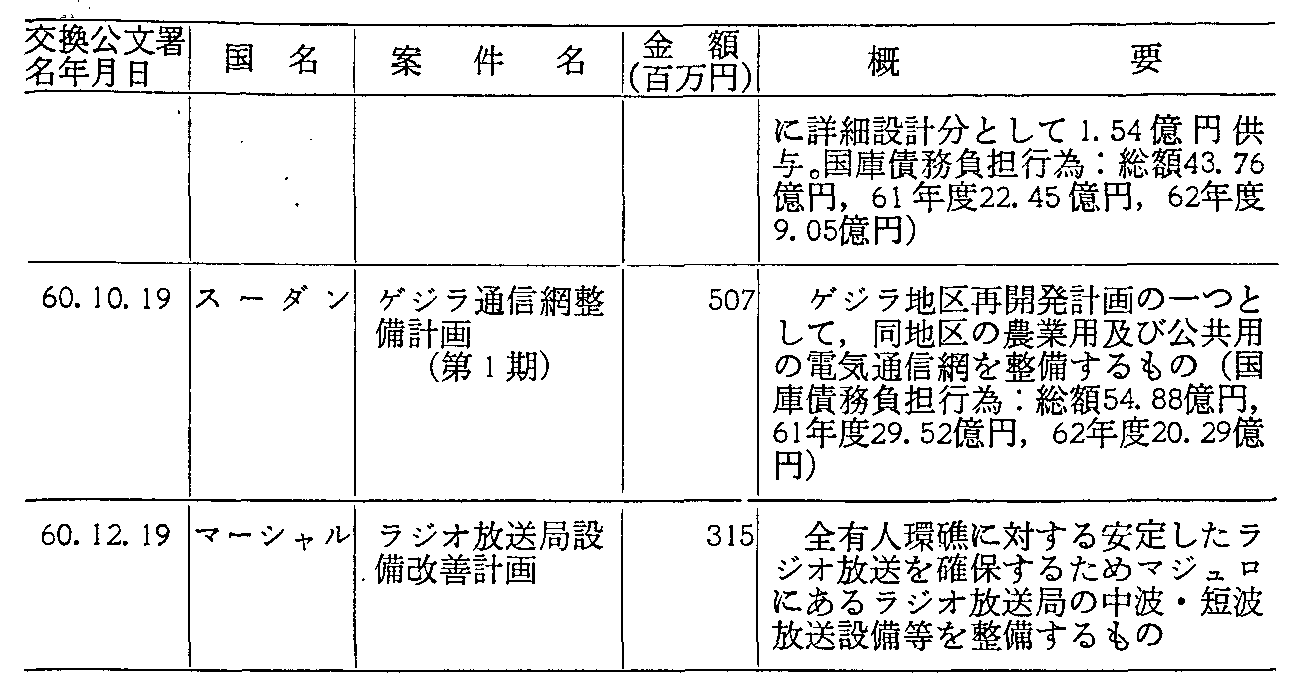
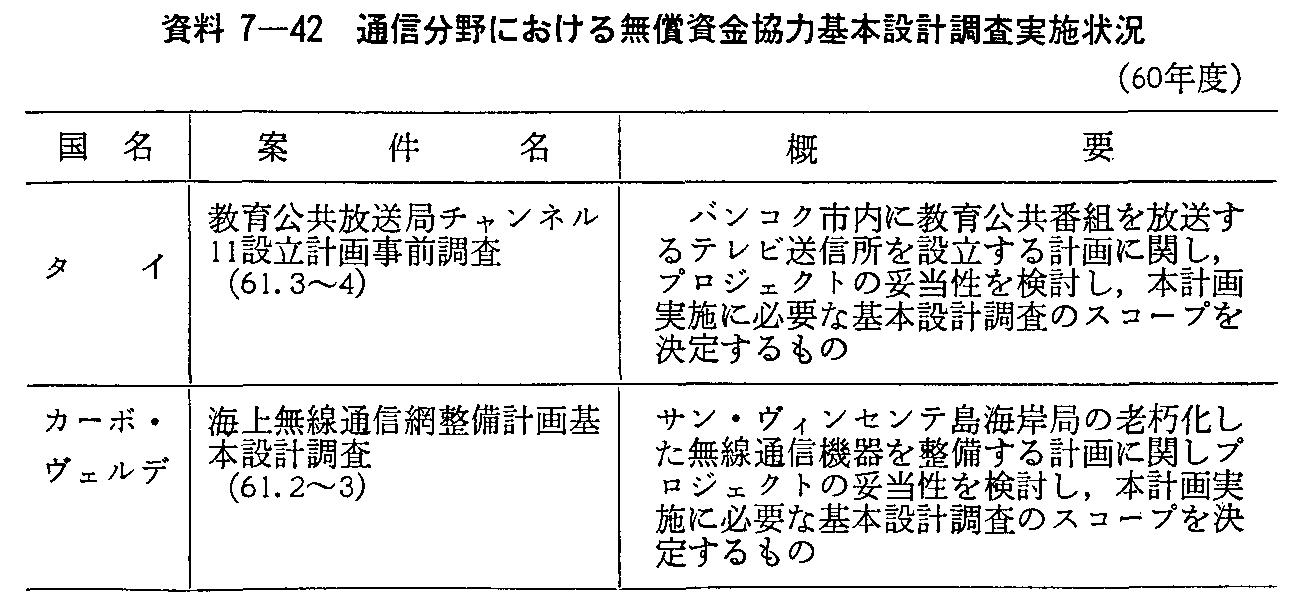
(2)二国間の科学技術協力協定等に基づく国際協力
科学技術分野の国際協力は,人類が直面する諸問題の解決,あるいは宇宙,海洋,原子力等国際協力を行った方が効果的,効率的に進められる研究開発の推進に必要であるばかりでなく,世界経済の再活性化と成長のためにも重要性を増してきている。
我が国は,先進工業国の一員として国際社会に貢献すべく,61年度6月末現在18か国と科学技術協力協定ないし取極の枠組みの下で二国間の科学技術協力を実施している。協力の主要内容は,科学者・技術者の交流,専門家会合等の開催,情報の交換,共同研究の実施,研究結果の交換等である。59年度以降,新たにインド(60年11月),韓国(60年12月)及びカナダ(61年5月)との間で協力協定が締結された。
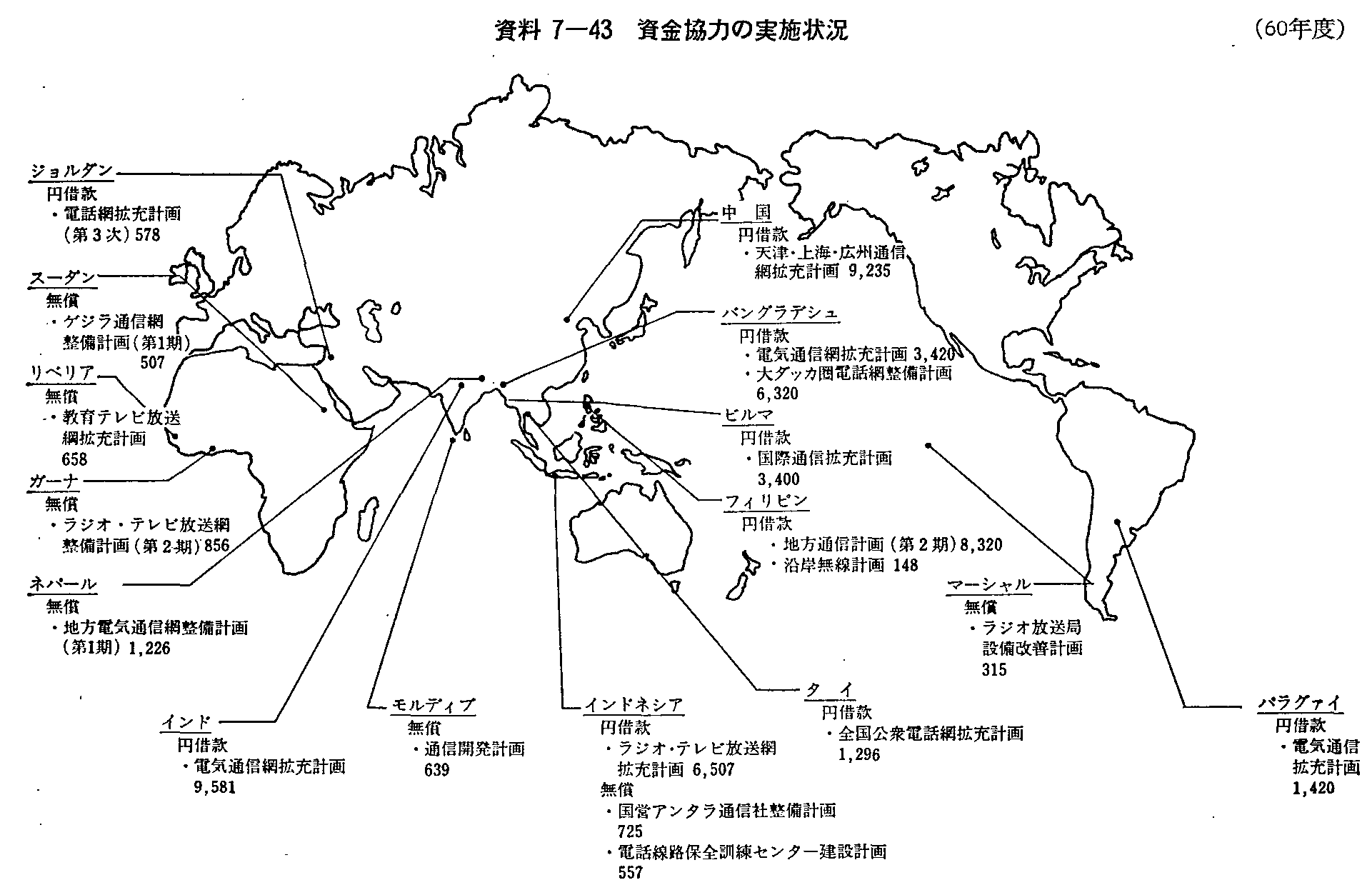
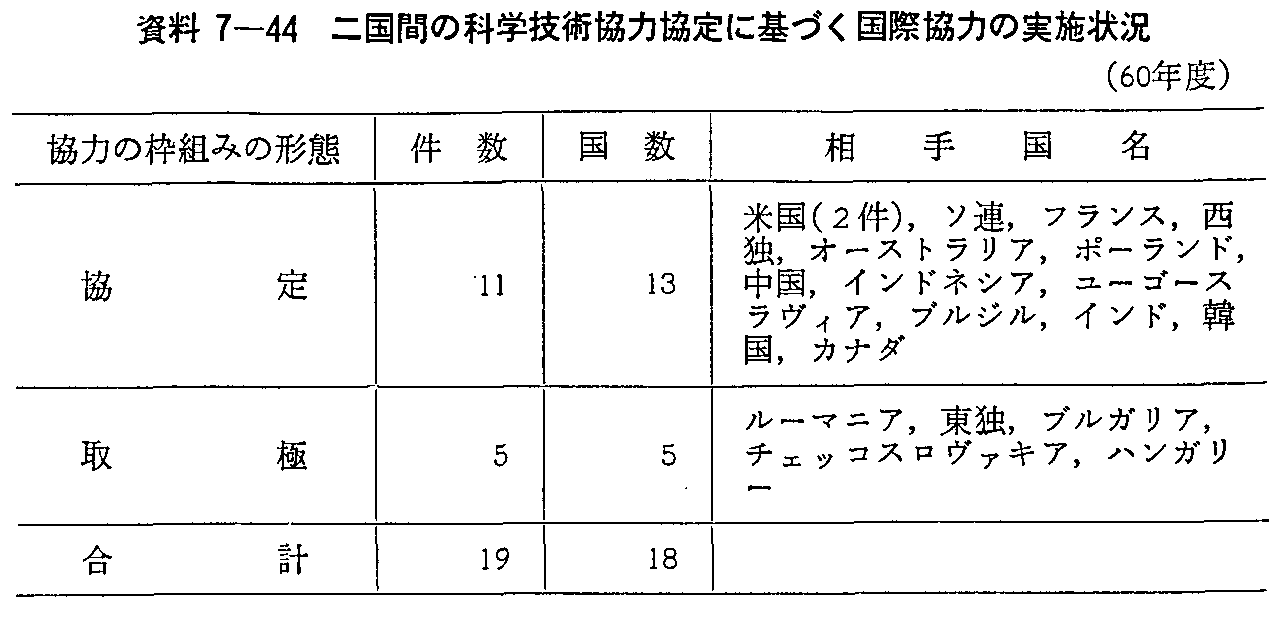
イ.活動状況
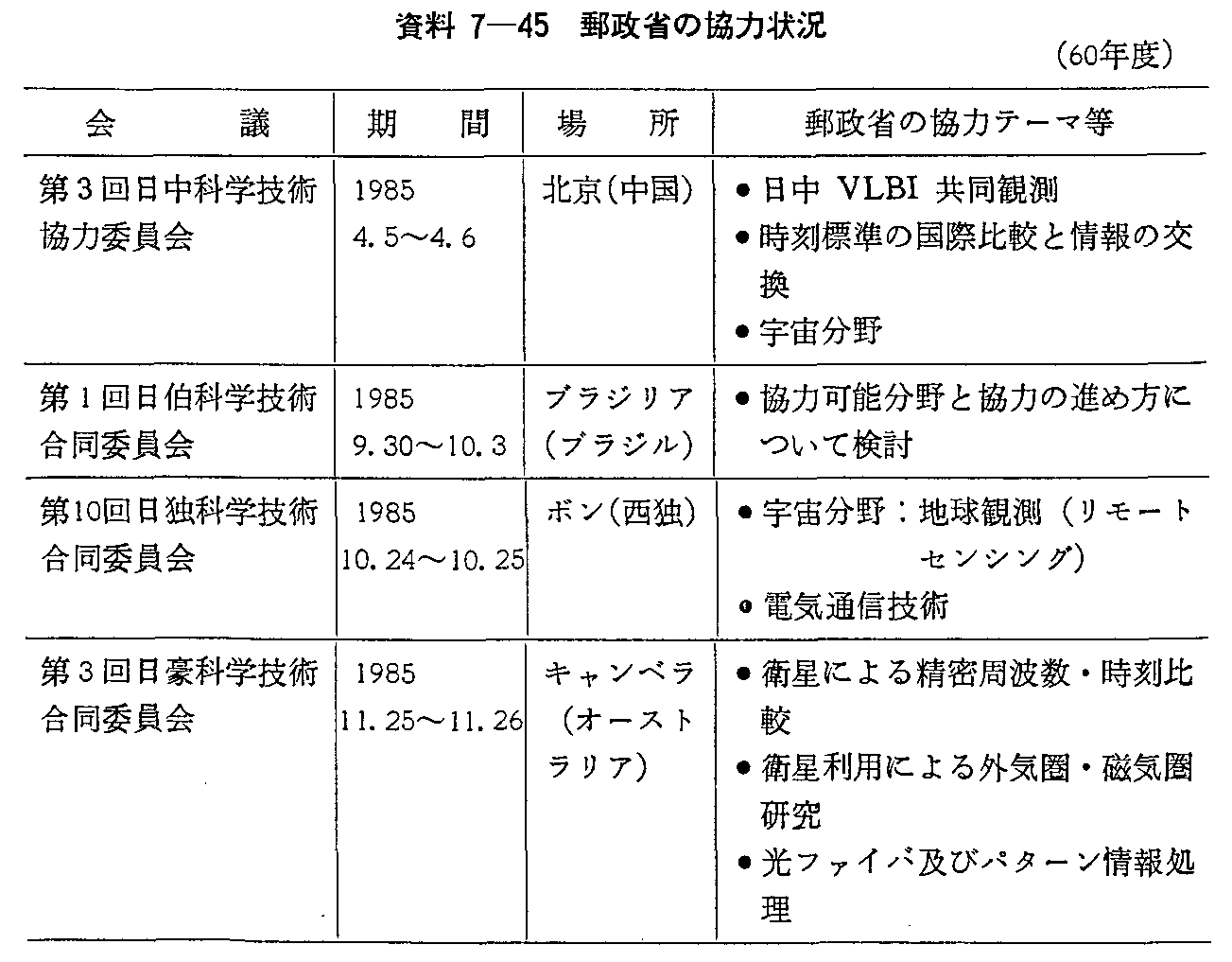
(3)要人往来
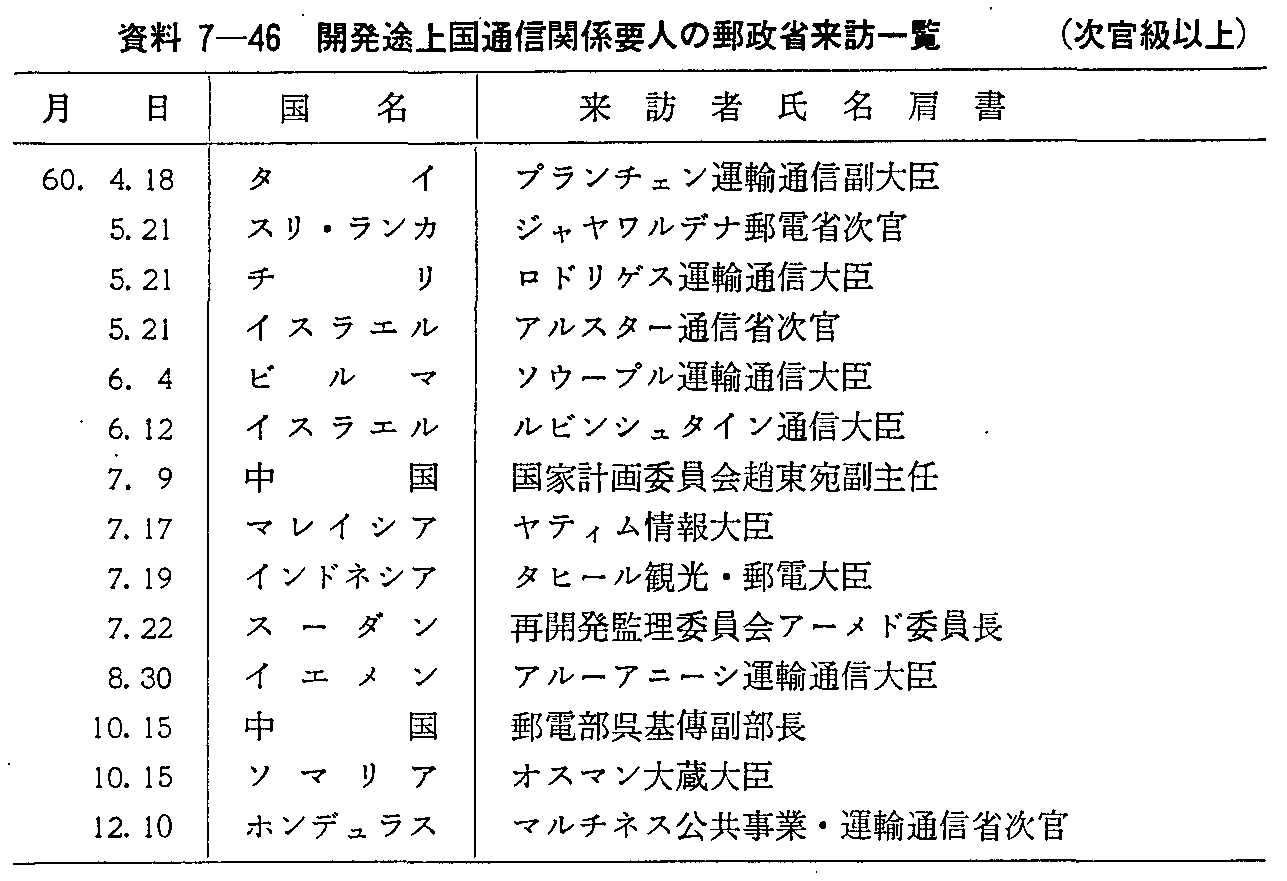
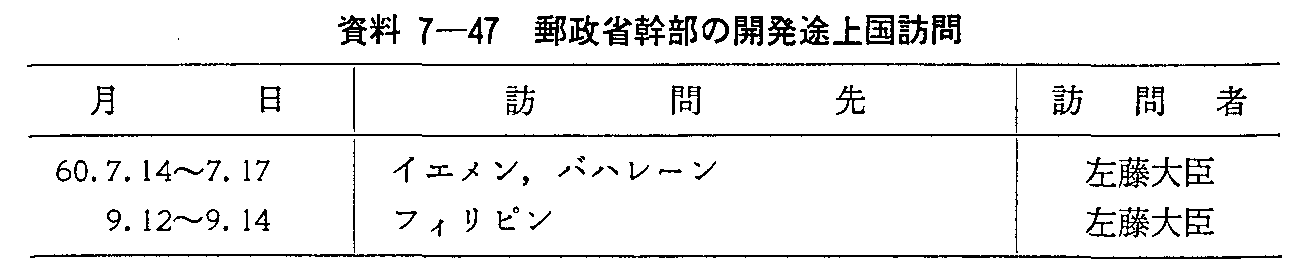
(4)主な民間ベース技術協力
NTT,KDD及びNHKは,海外の電気通信及び放送事業体との間で技術協力覚書等を締結し,これに基づき,いわゆる「覚書交流」を実施している。60年度においては,NTTがフィリピン及びクウェイトとの間で,NHKがシンガポール,フィリピン,タイ,インドネシア及びセネガルとの間で新たに覚書等を締結している。
また,昨年3月にアジア・太平洋地域の開発途上国に対する技術協力,調査研究を主たる目的として設立された(財)アジア電気通信技術協力機構(ATO)は,国際協力セミナーの開催,海外研修生の受入れ,及び韓国で開催された国際技術協力シンポジウムへの講師団の派遣等技術協力に積極的に取り組んでいる。
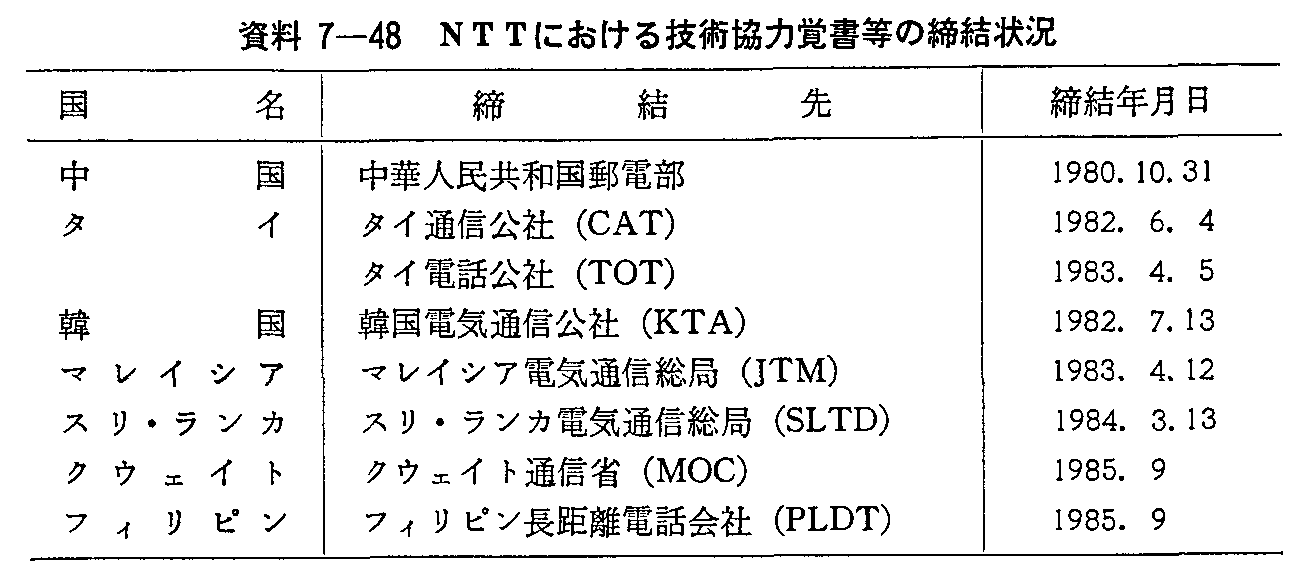
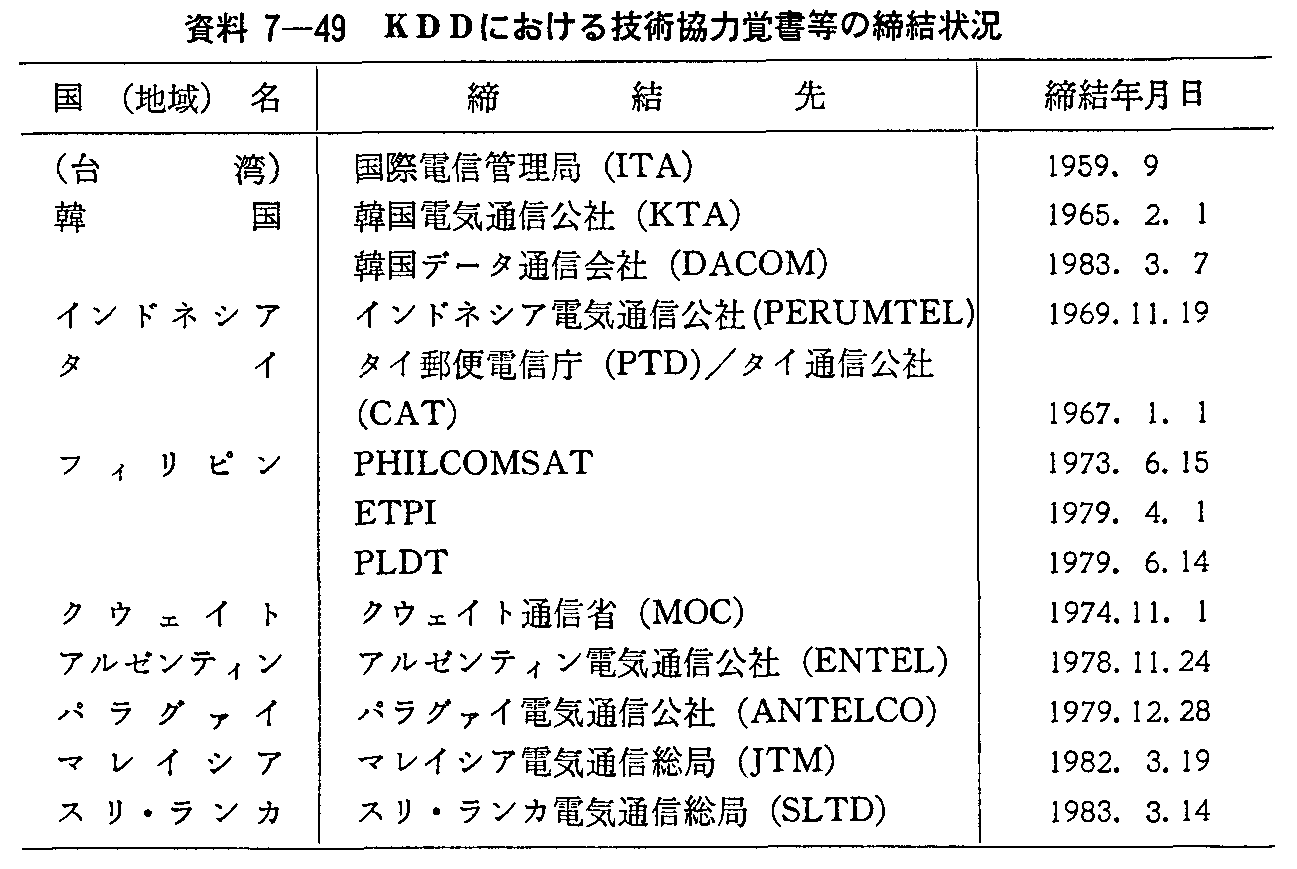
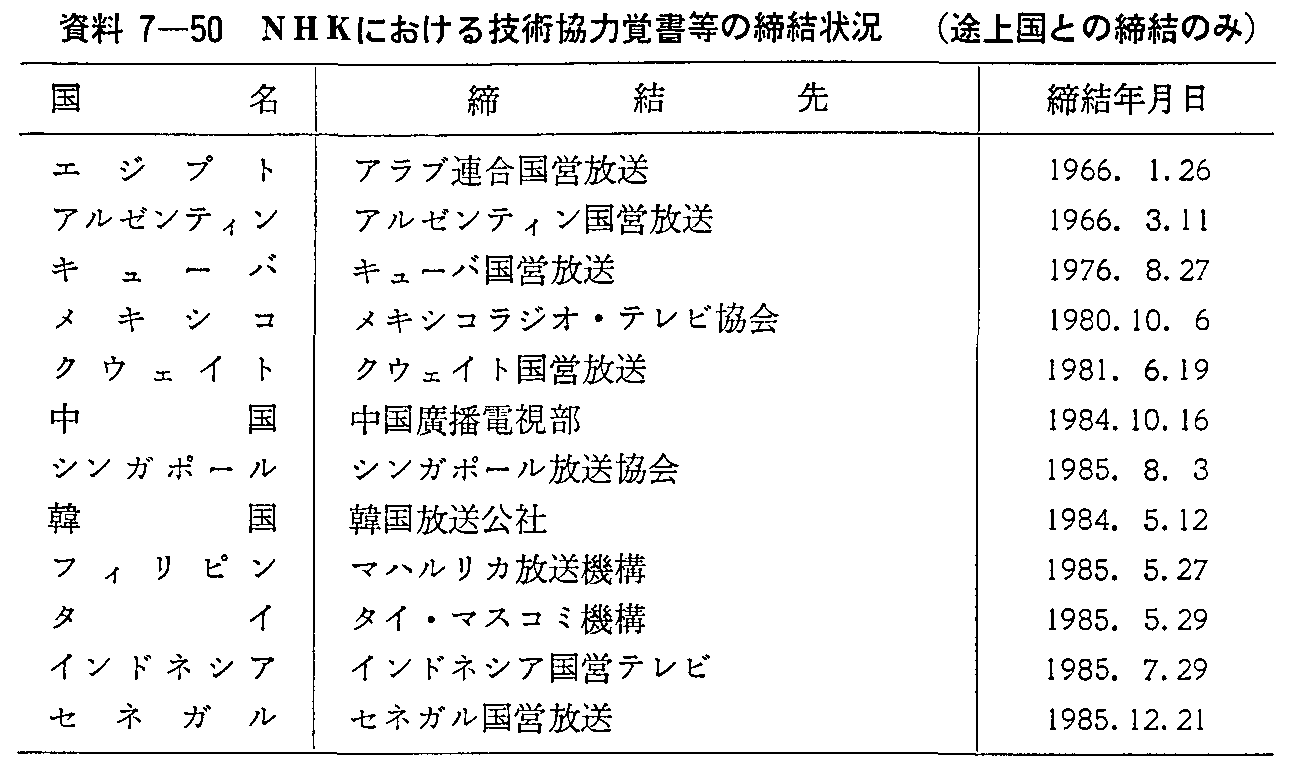
|