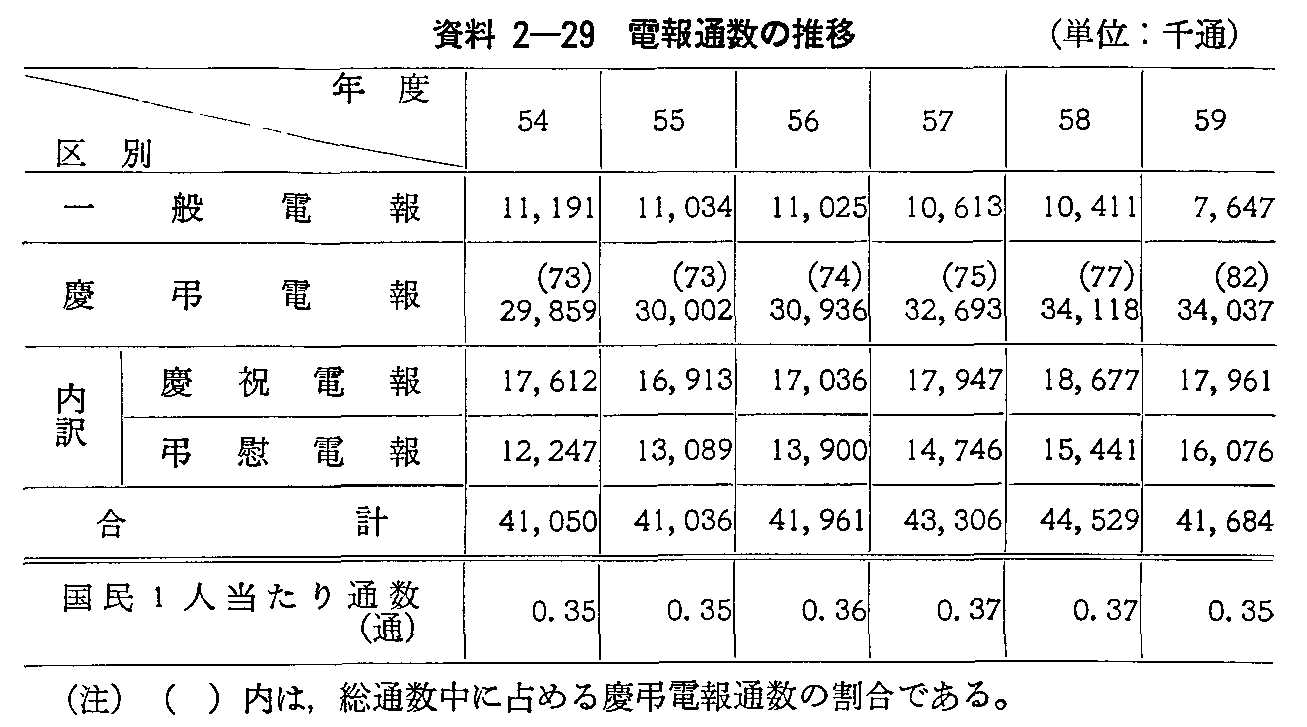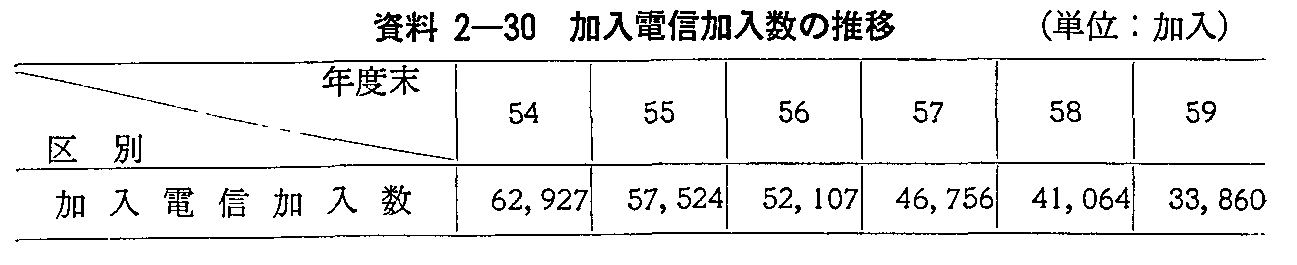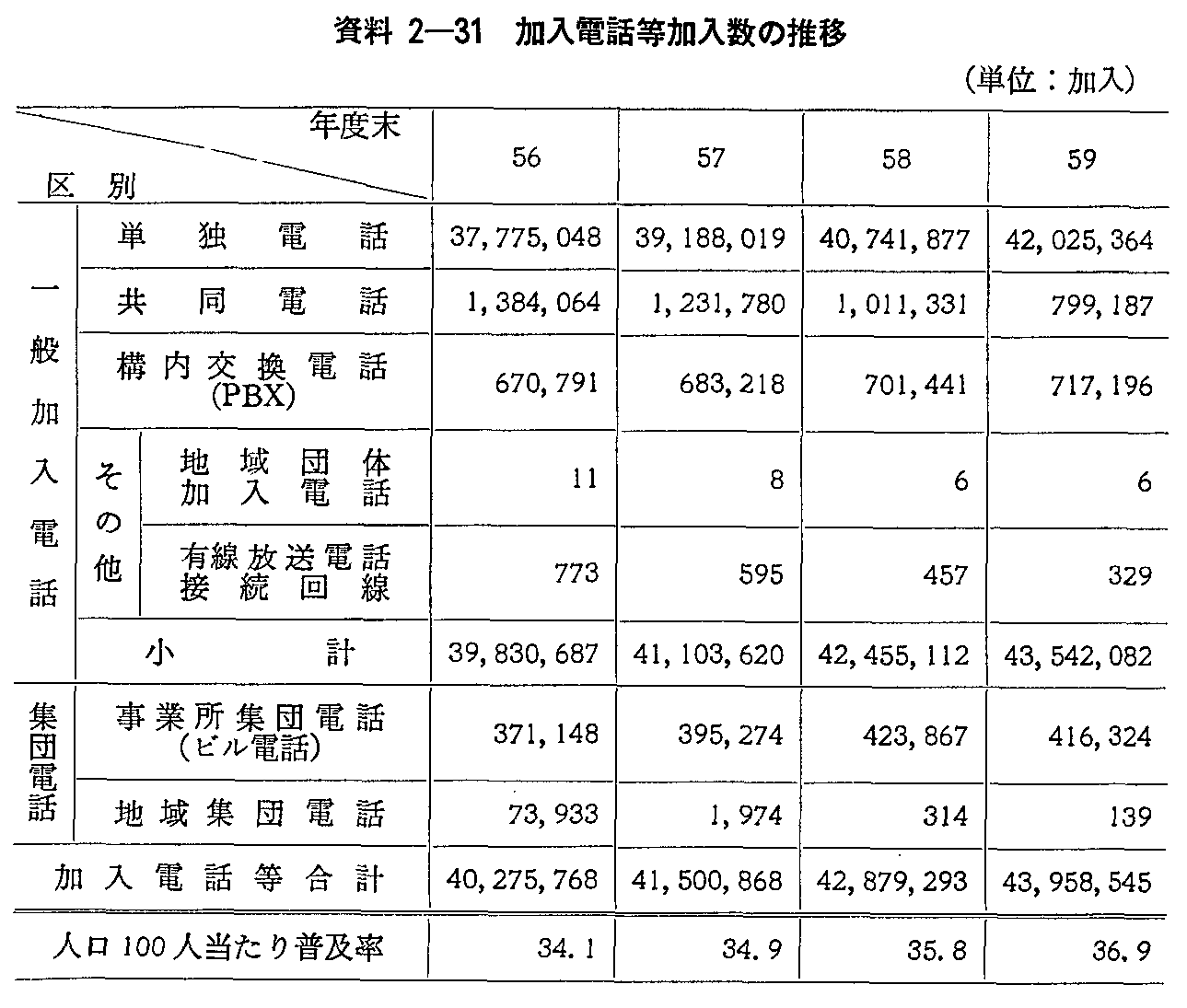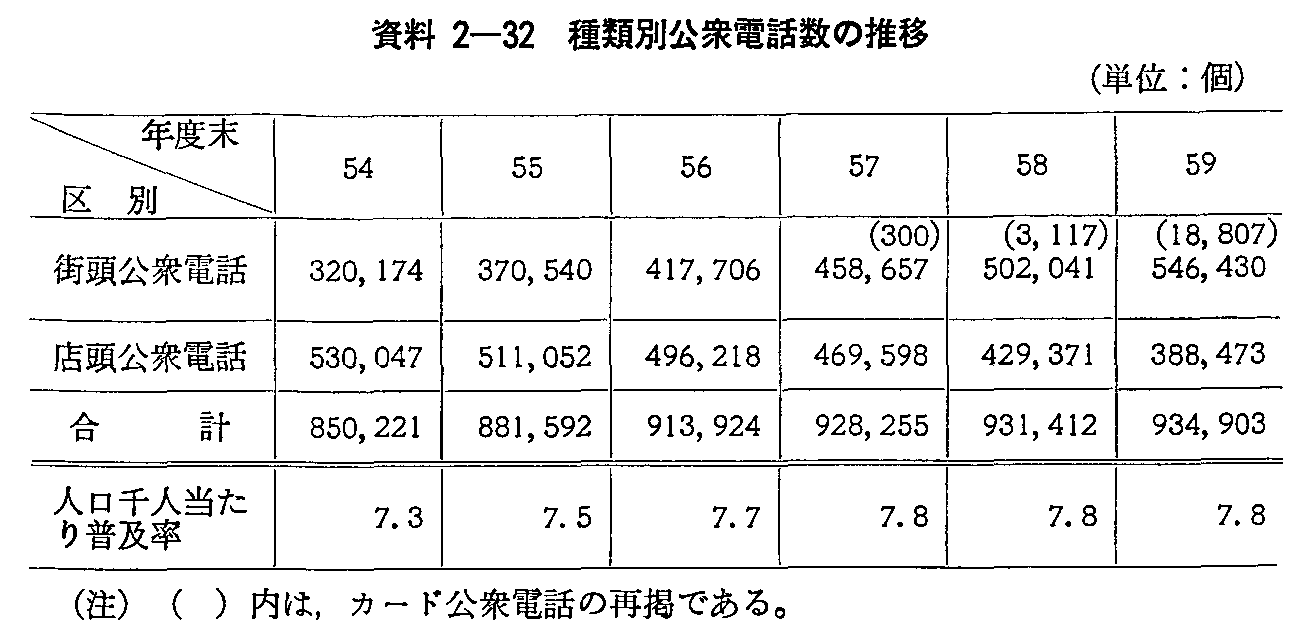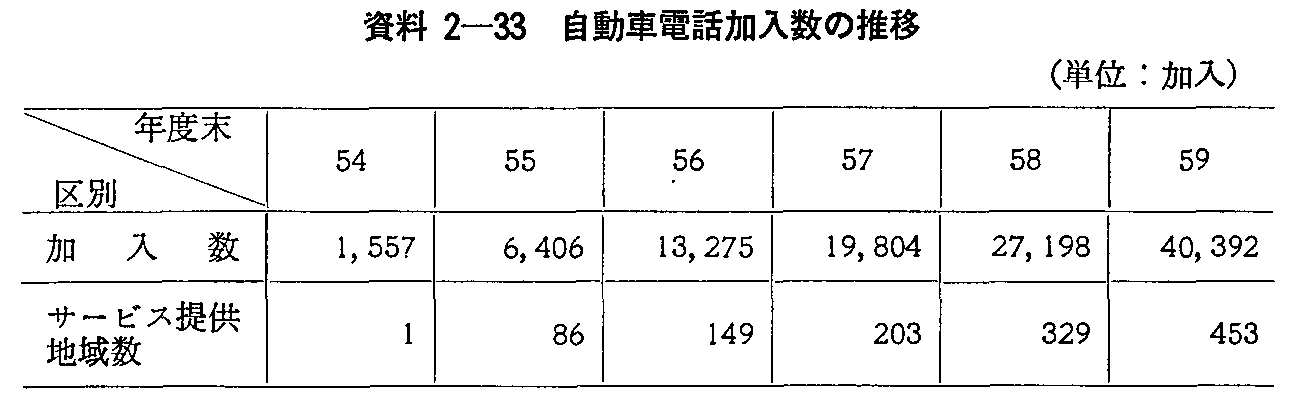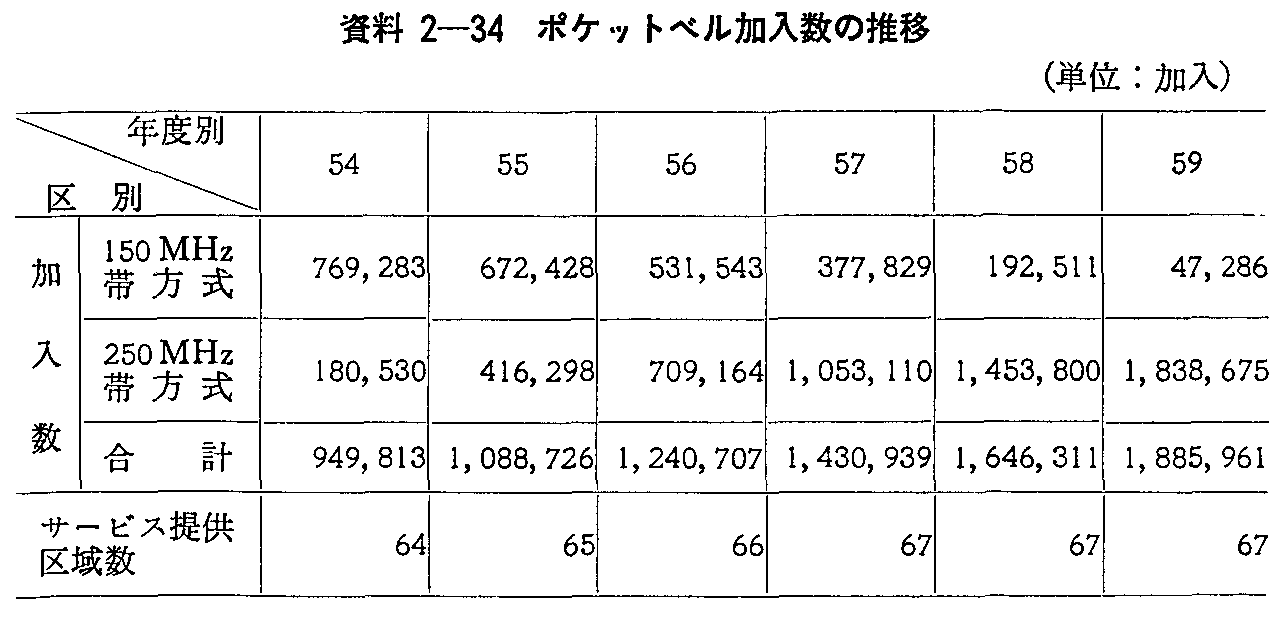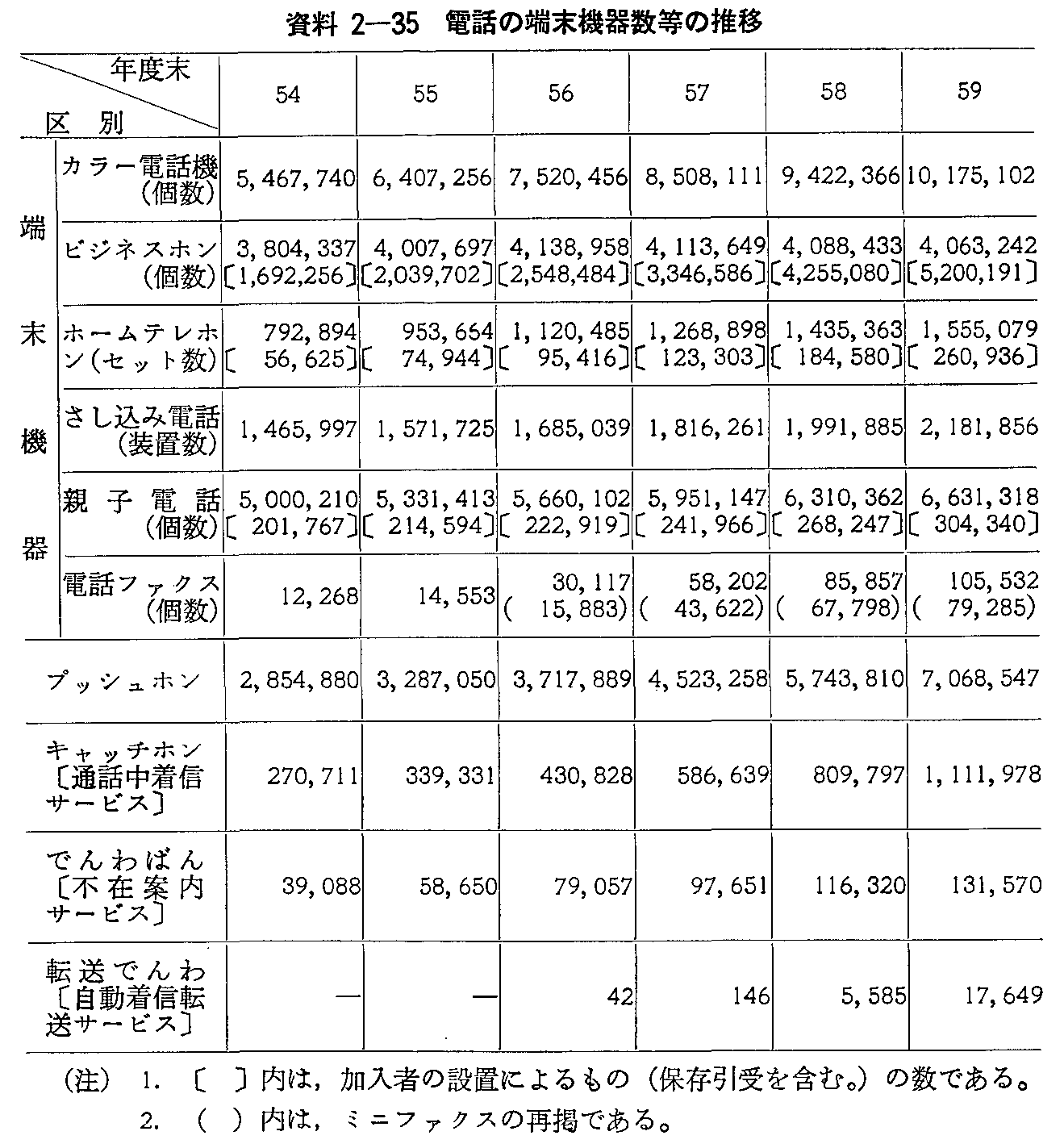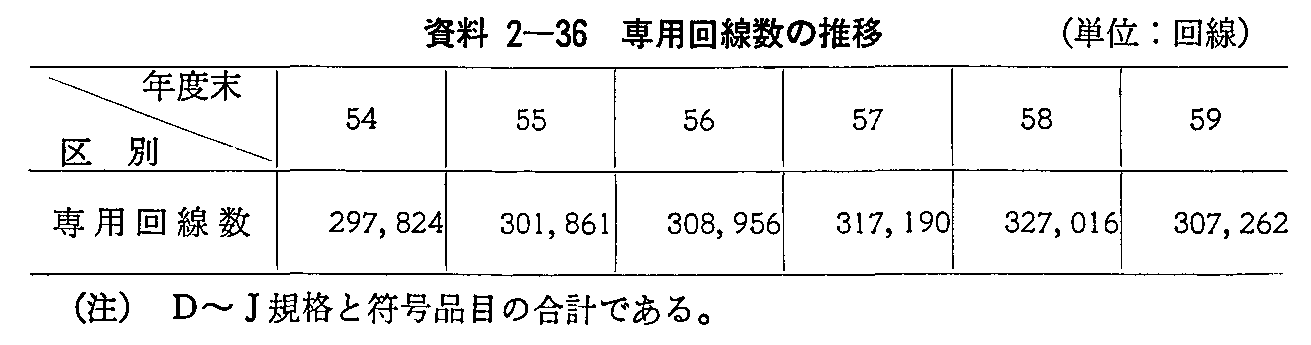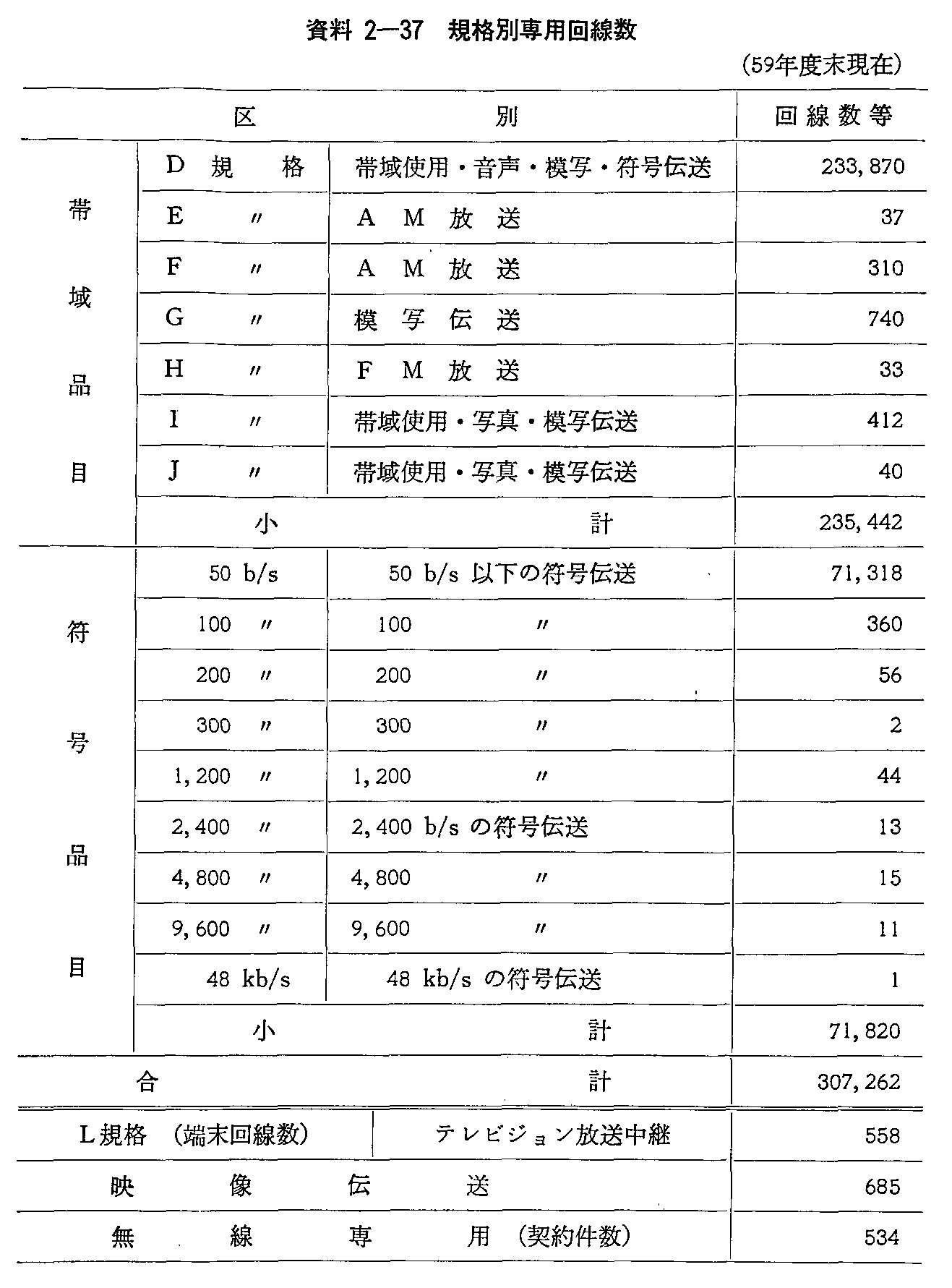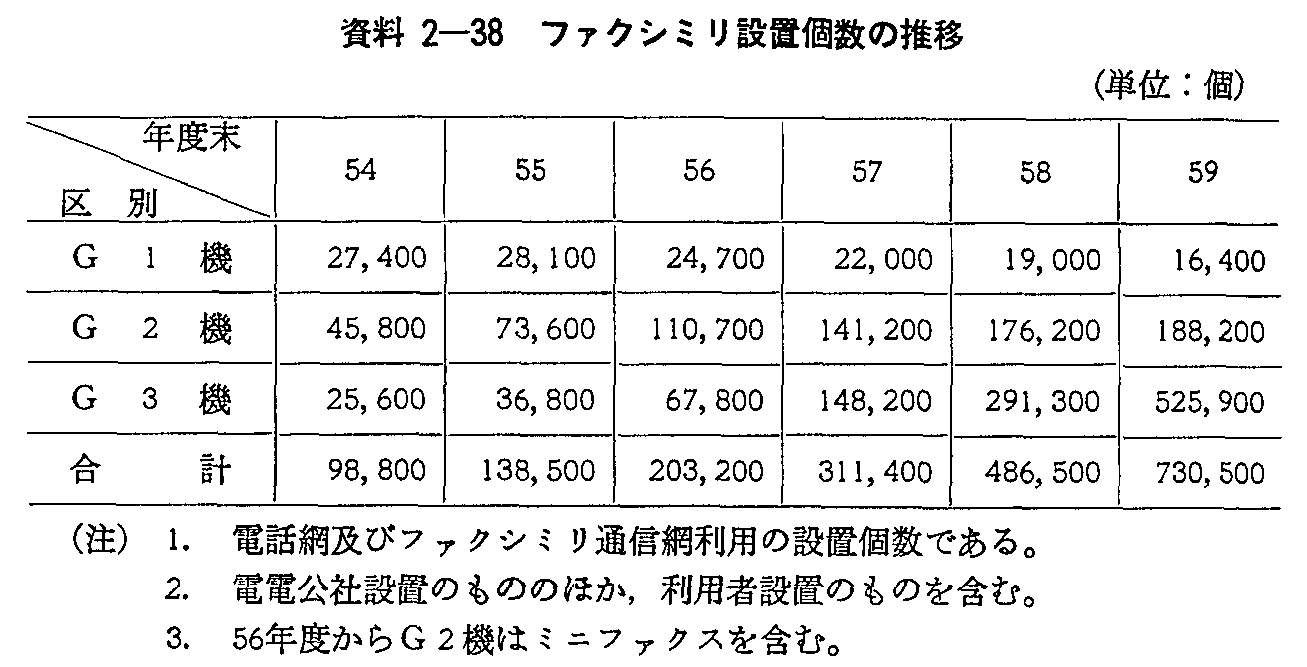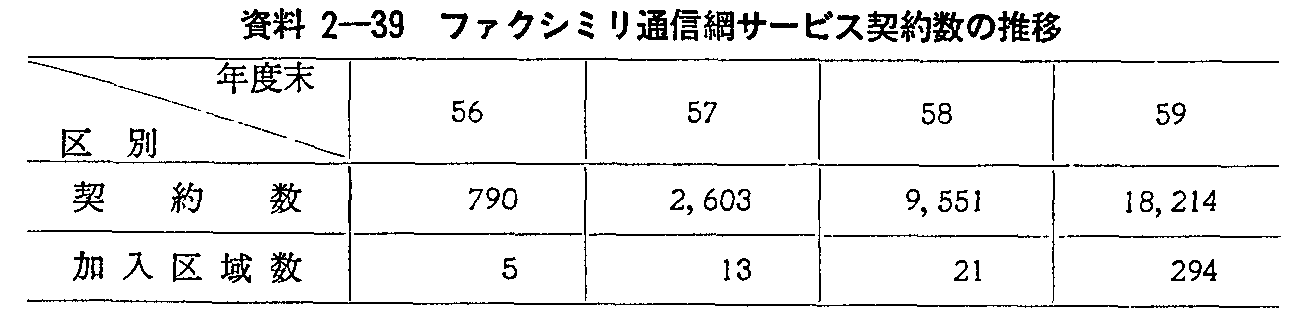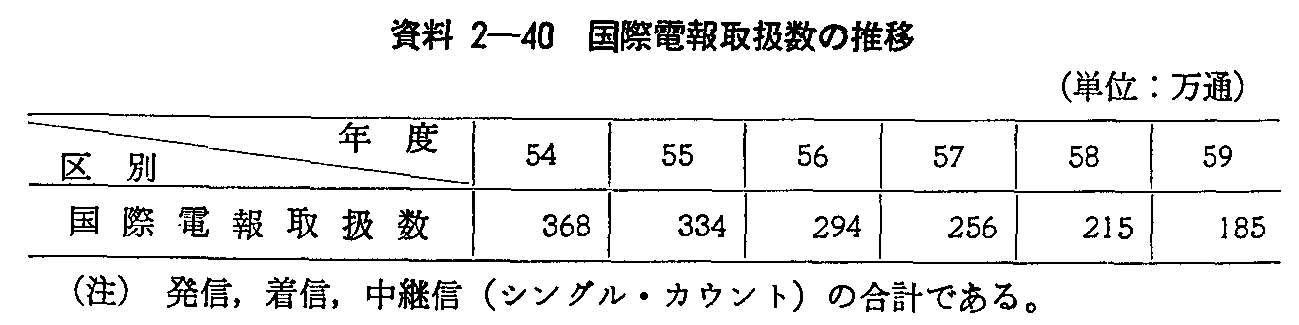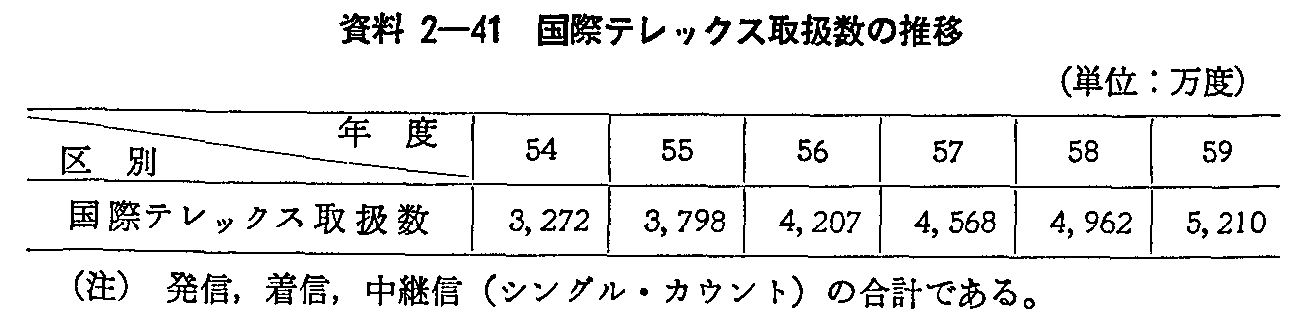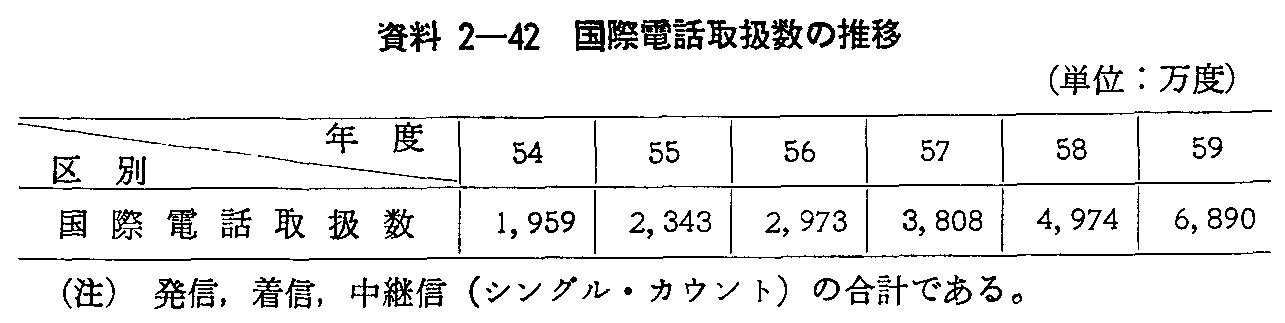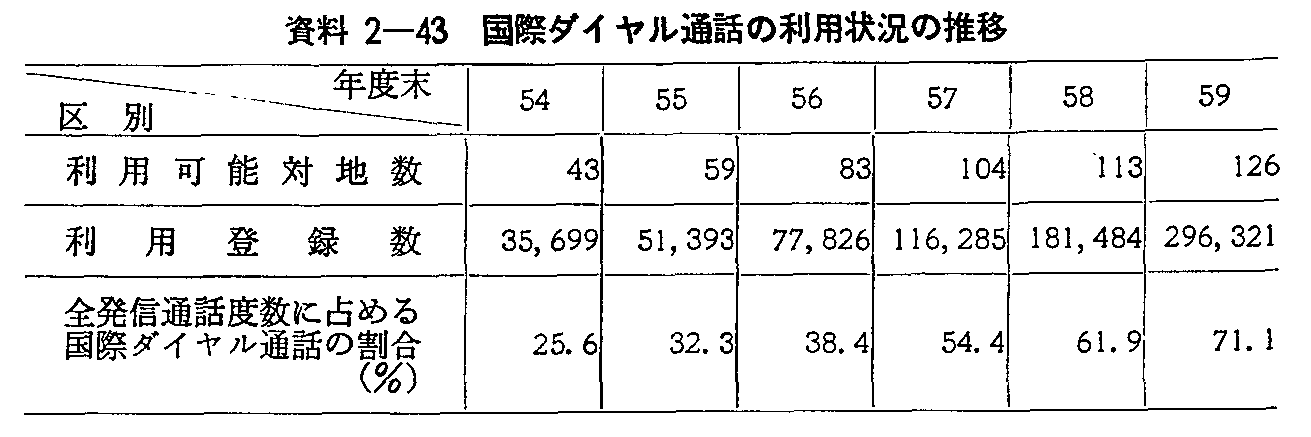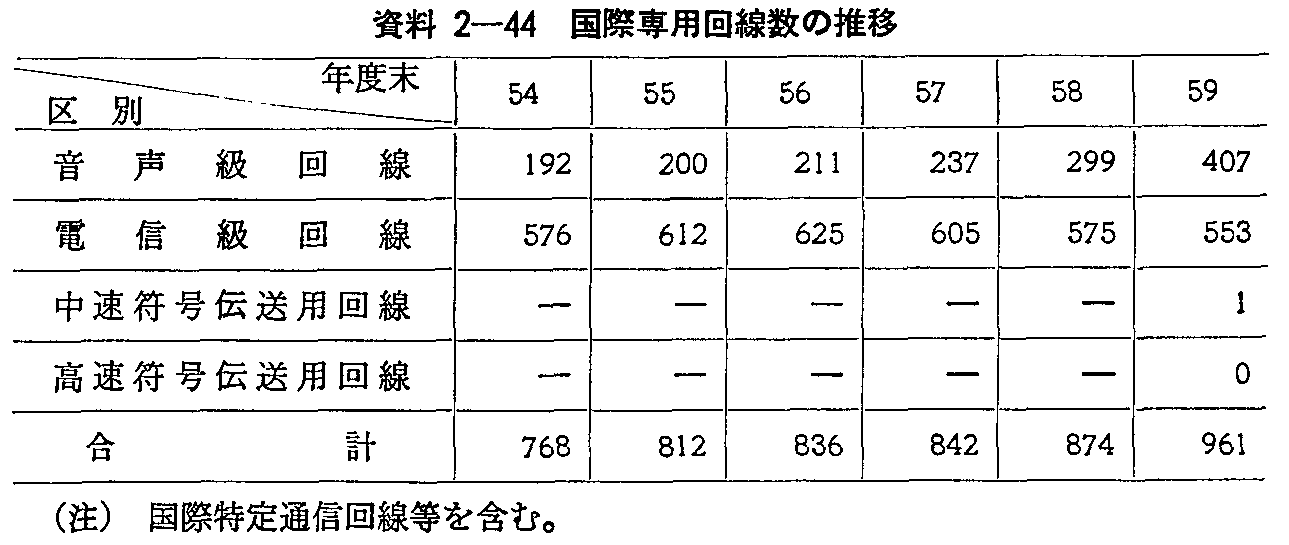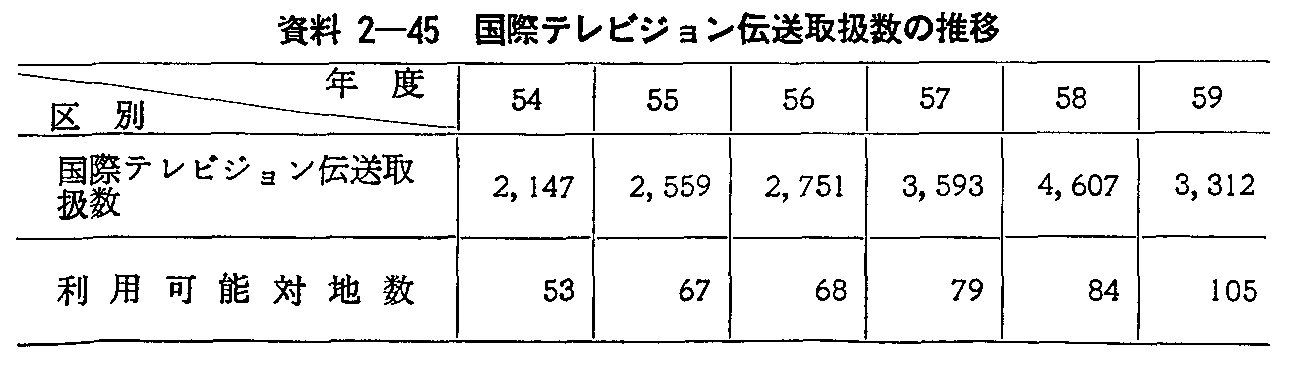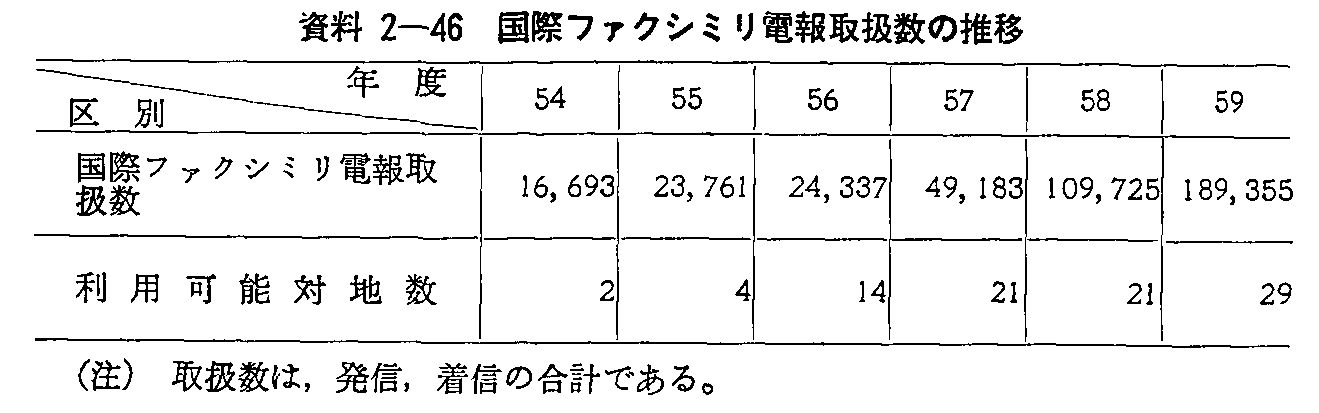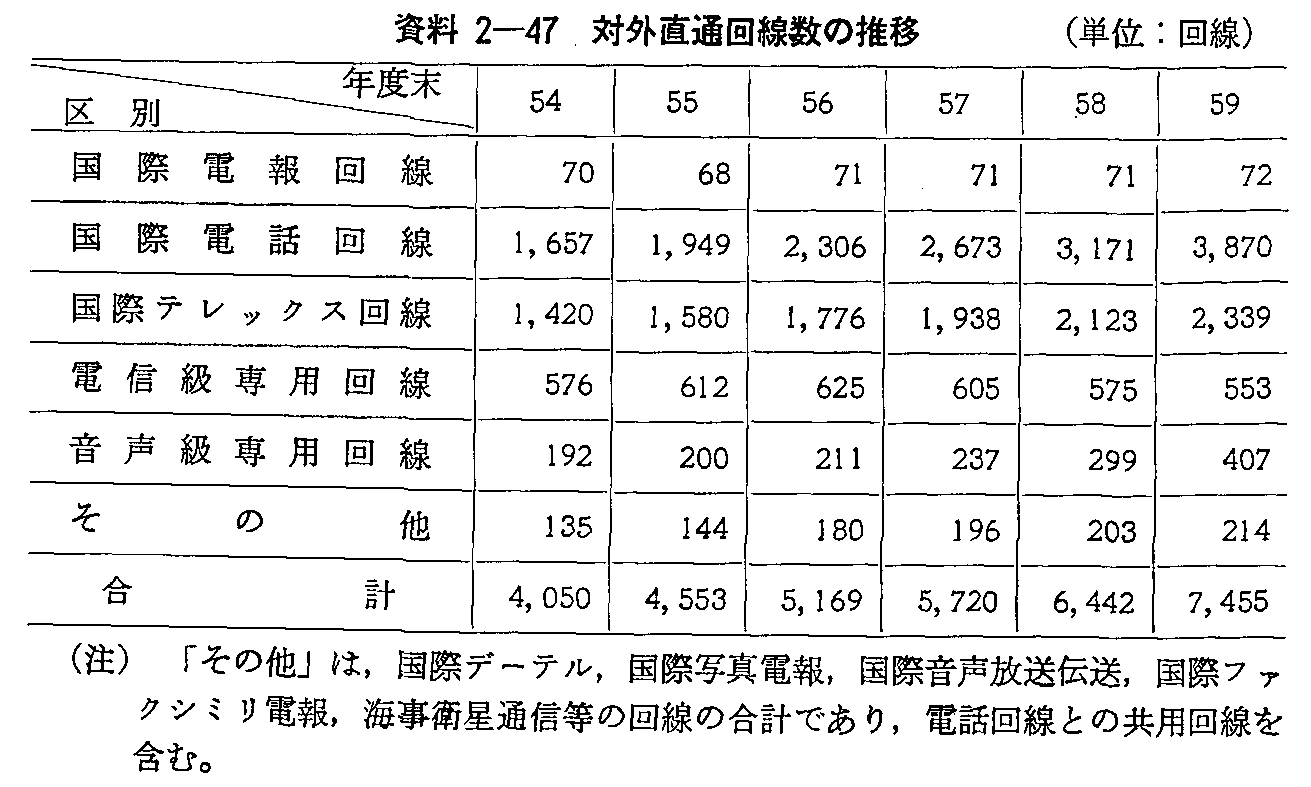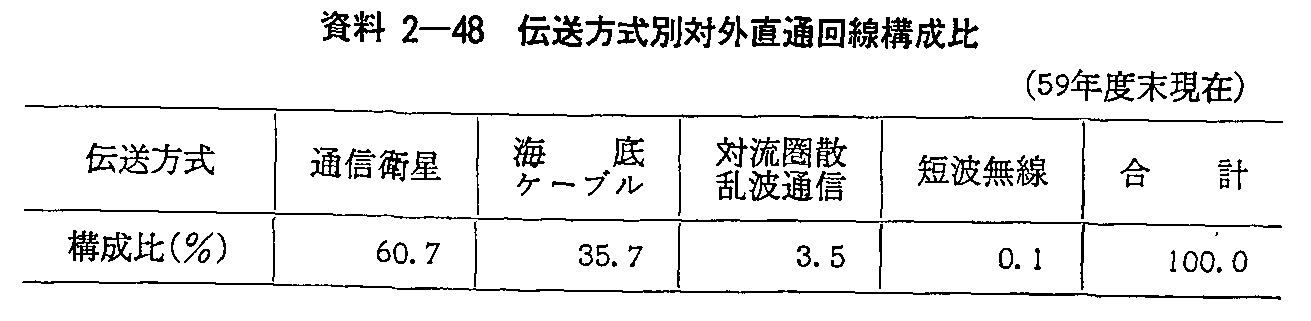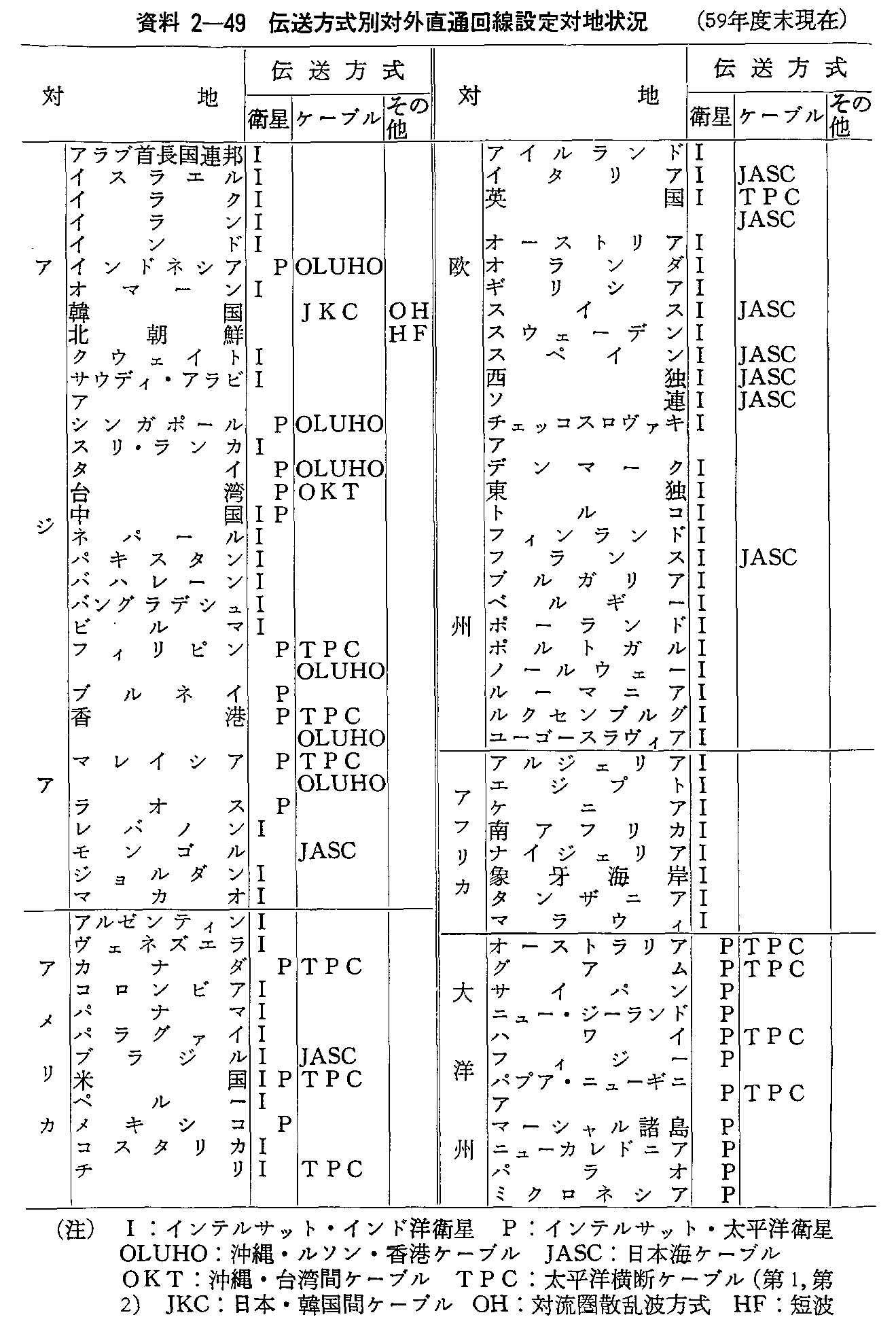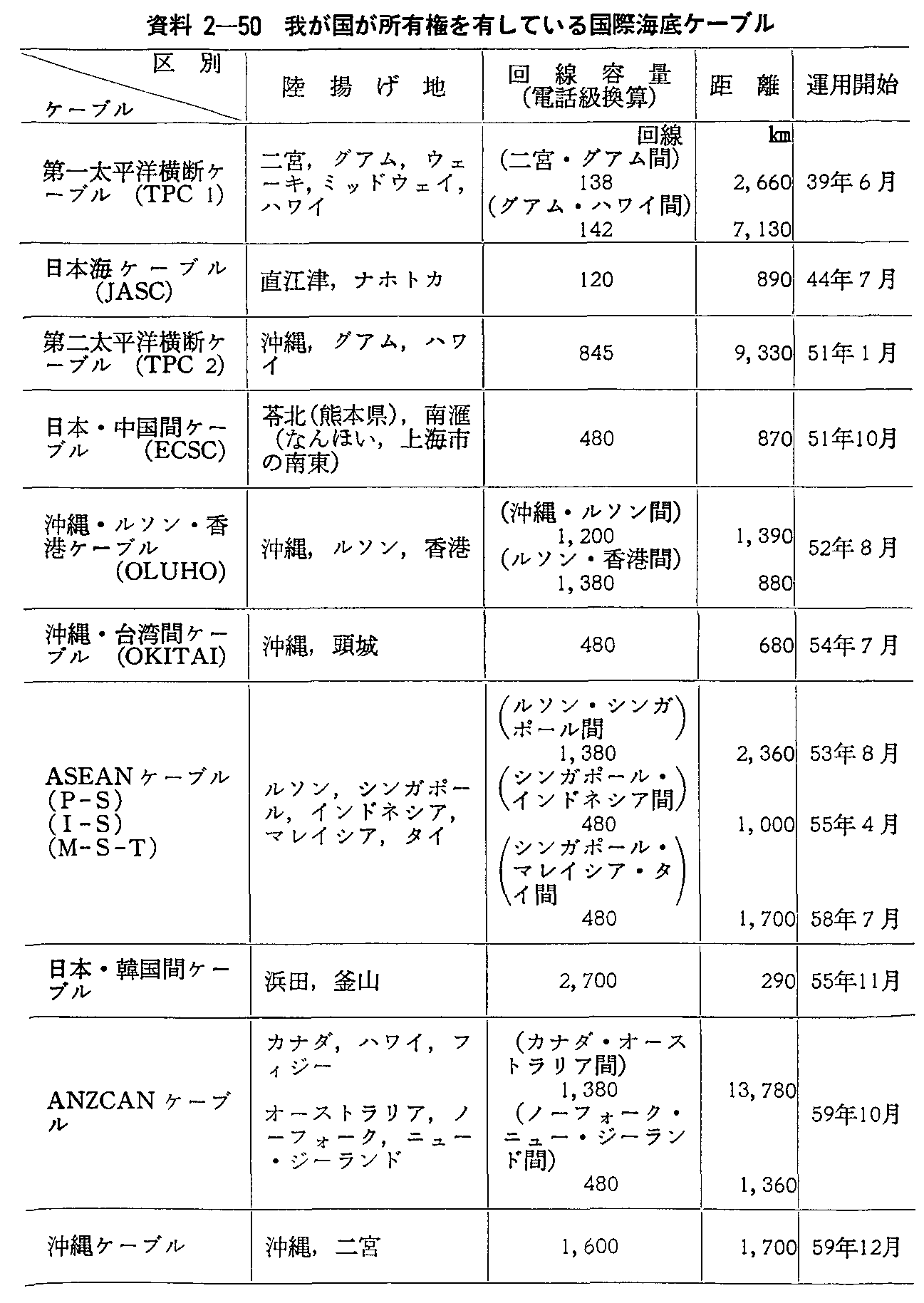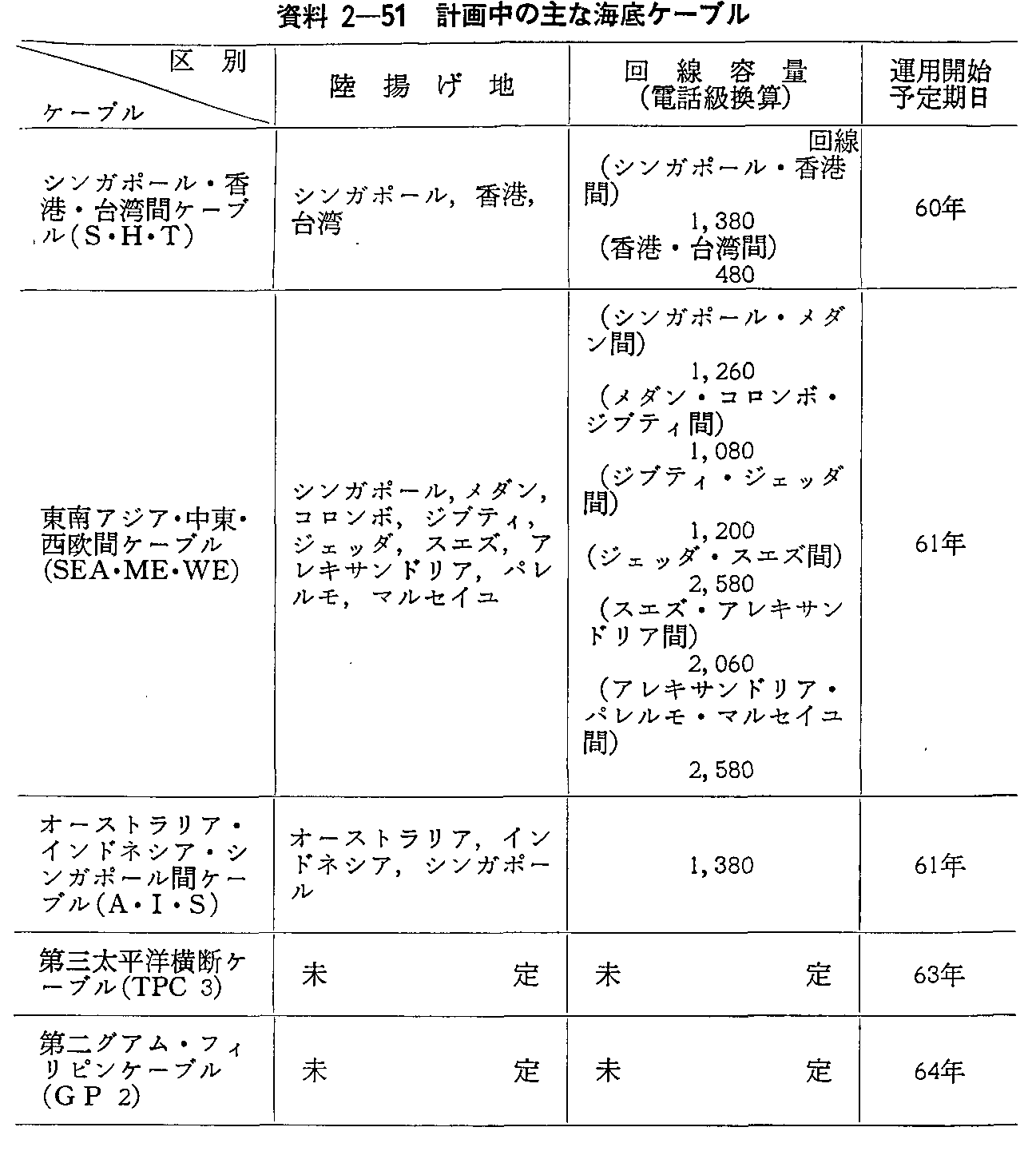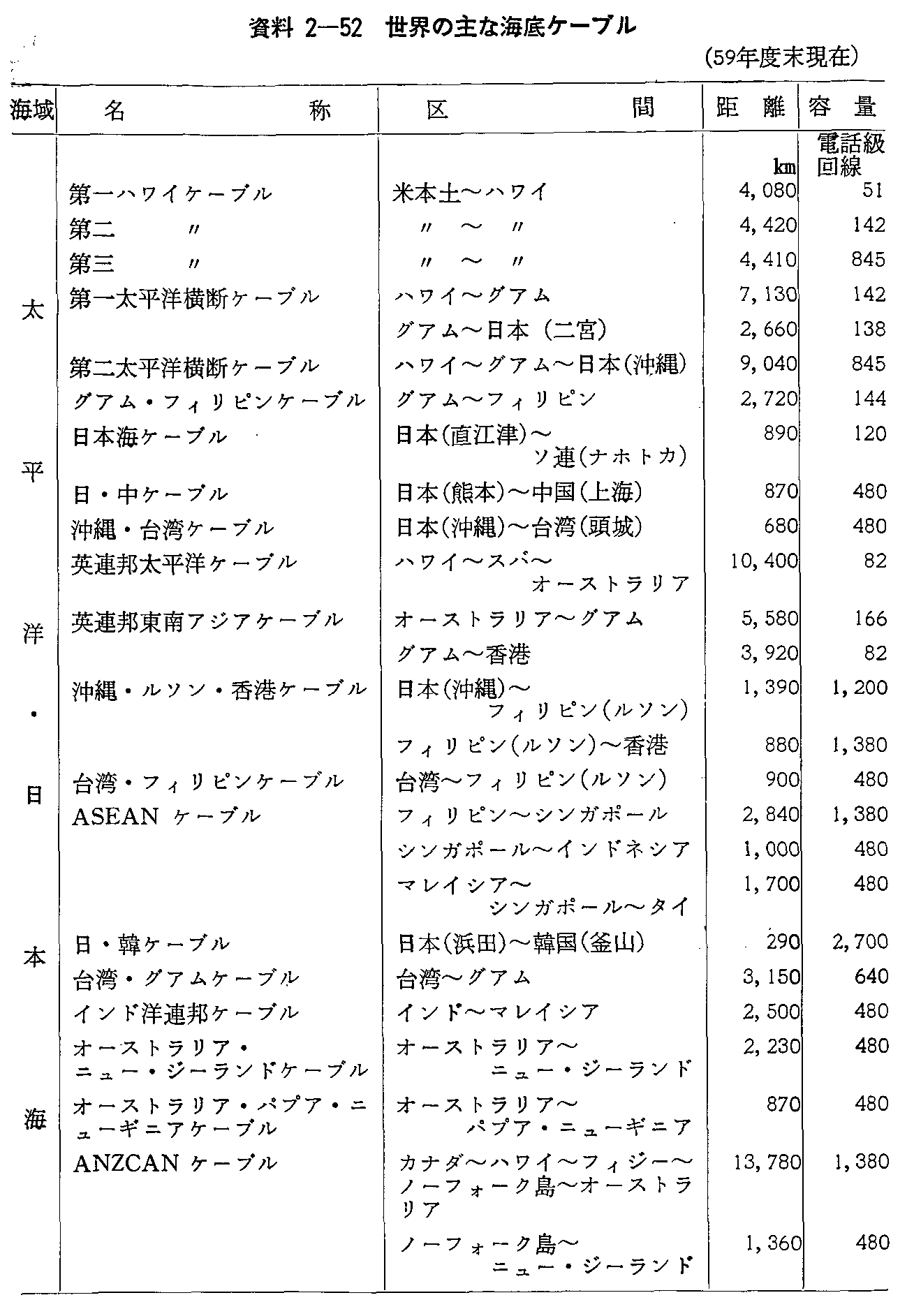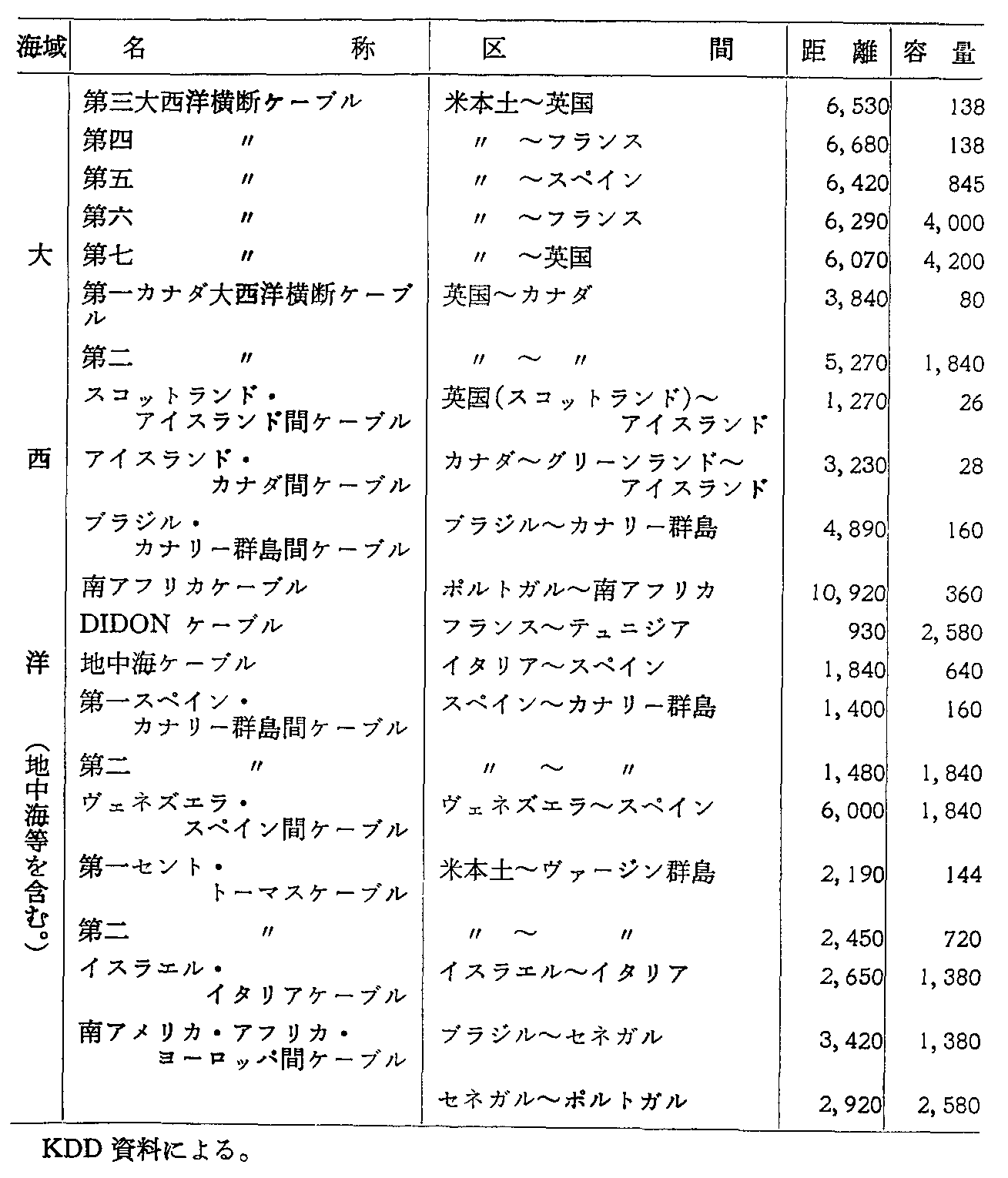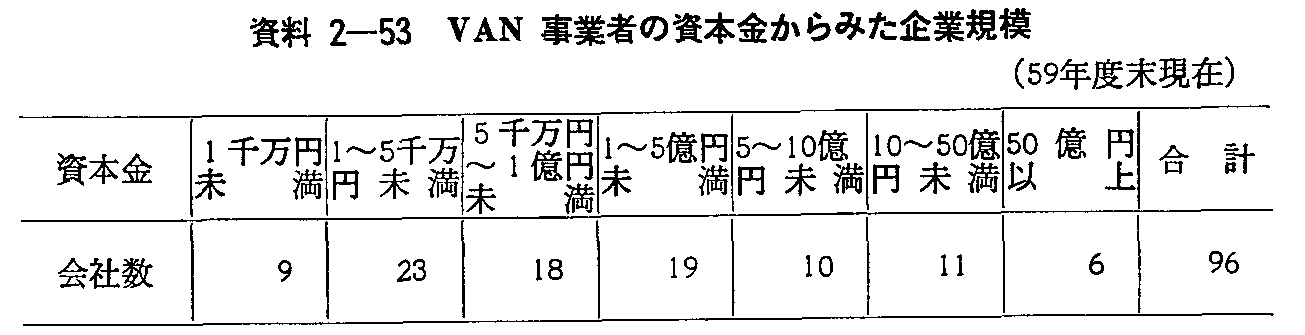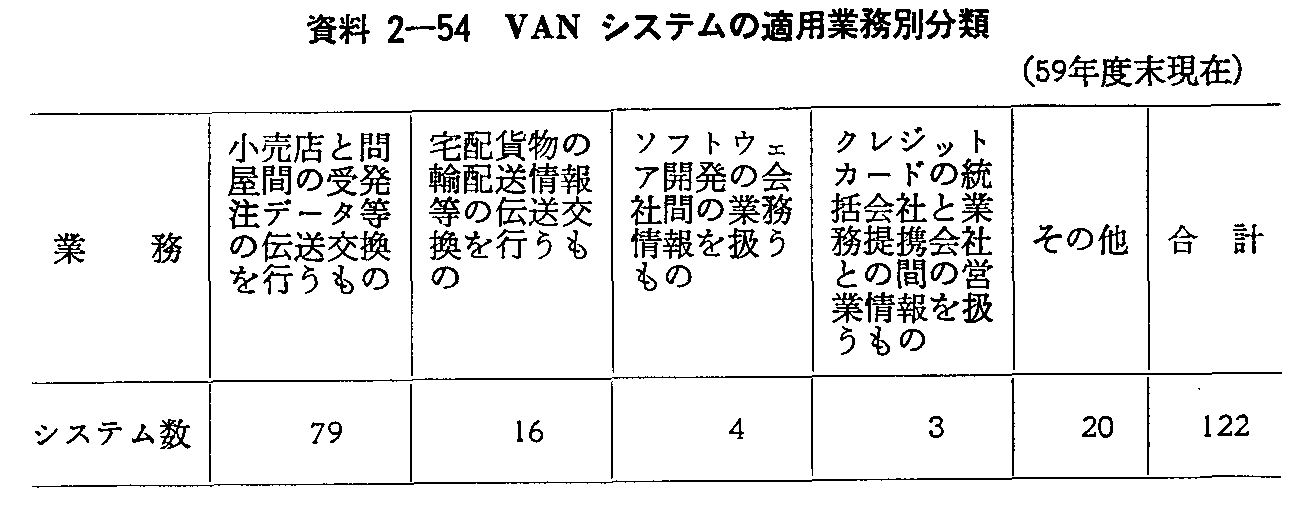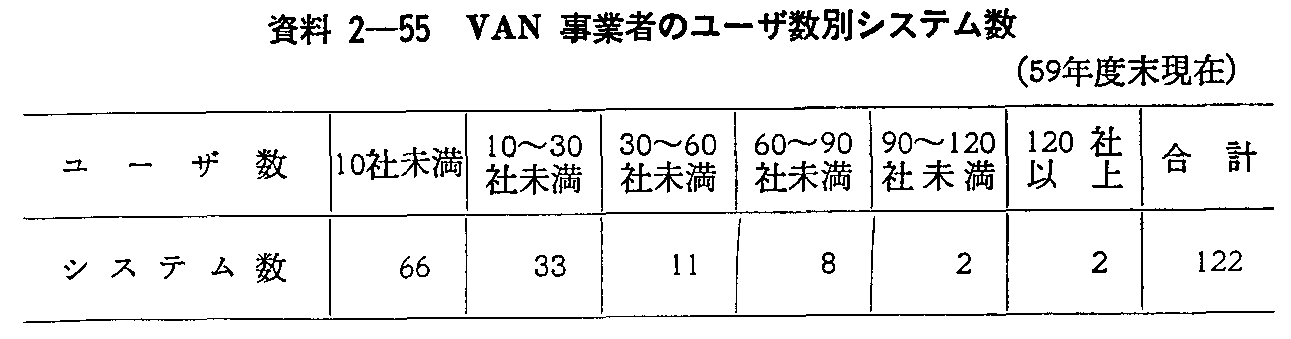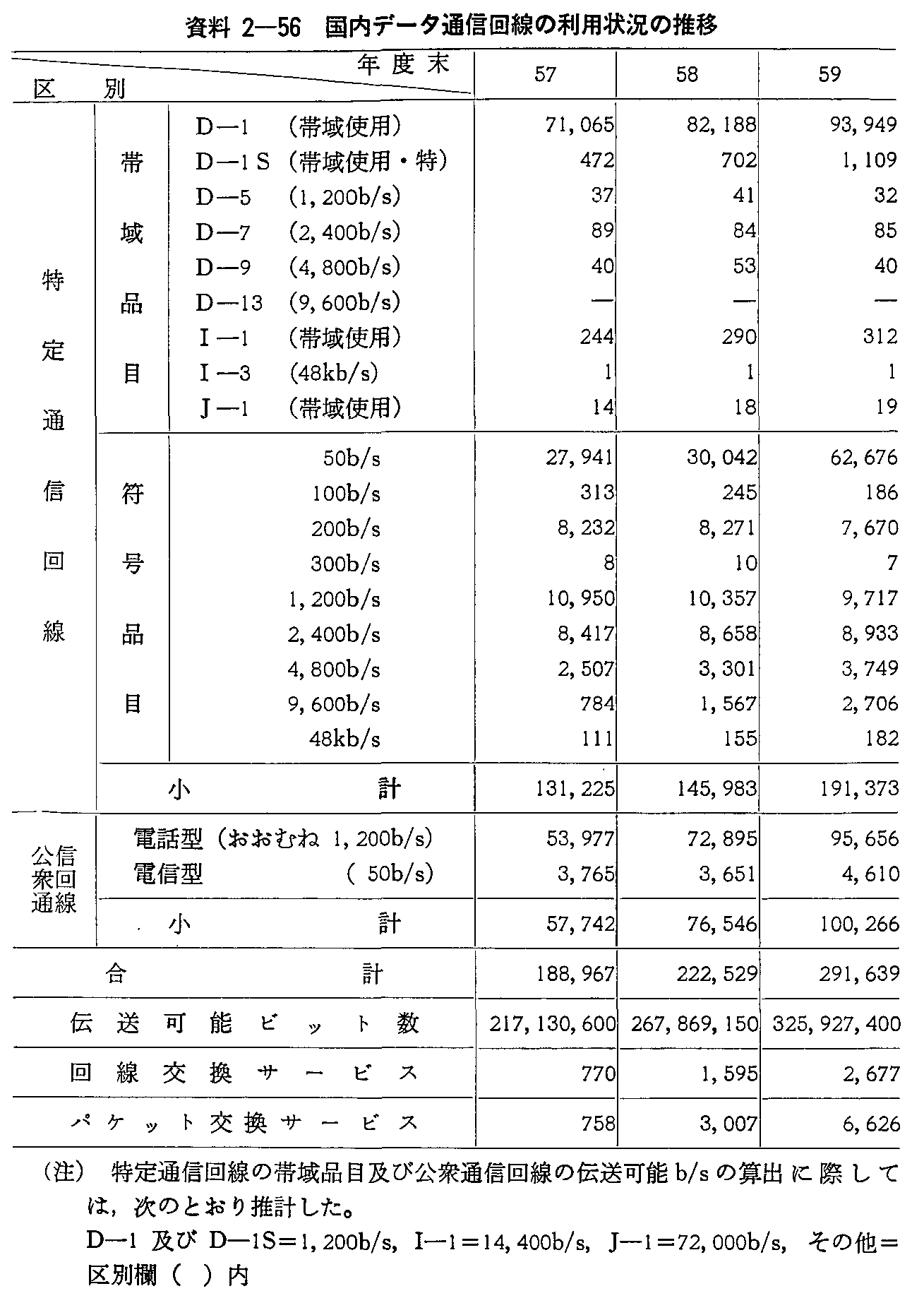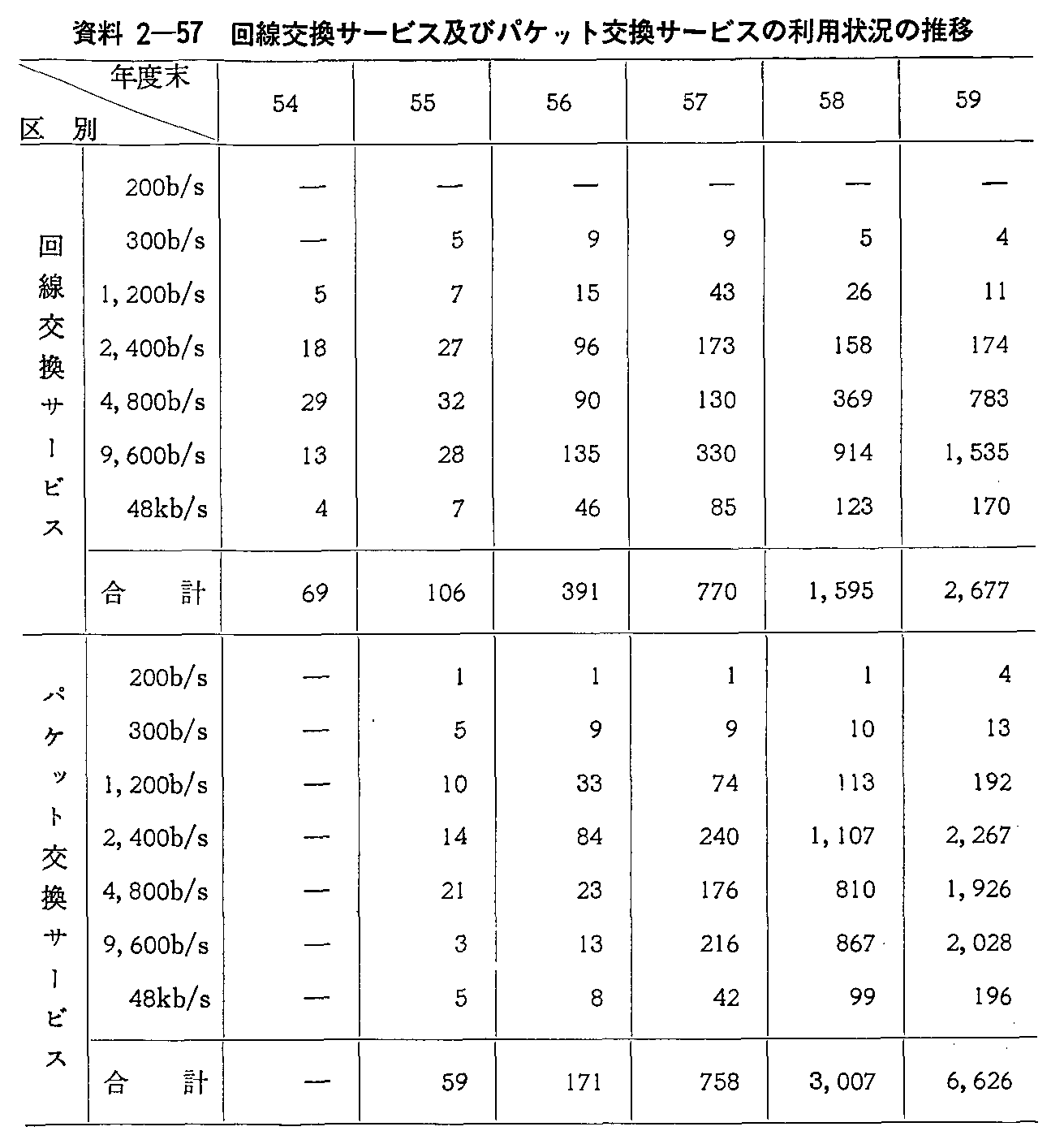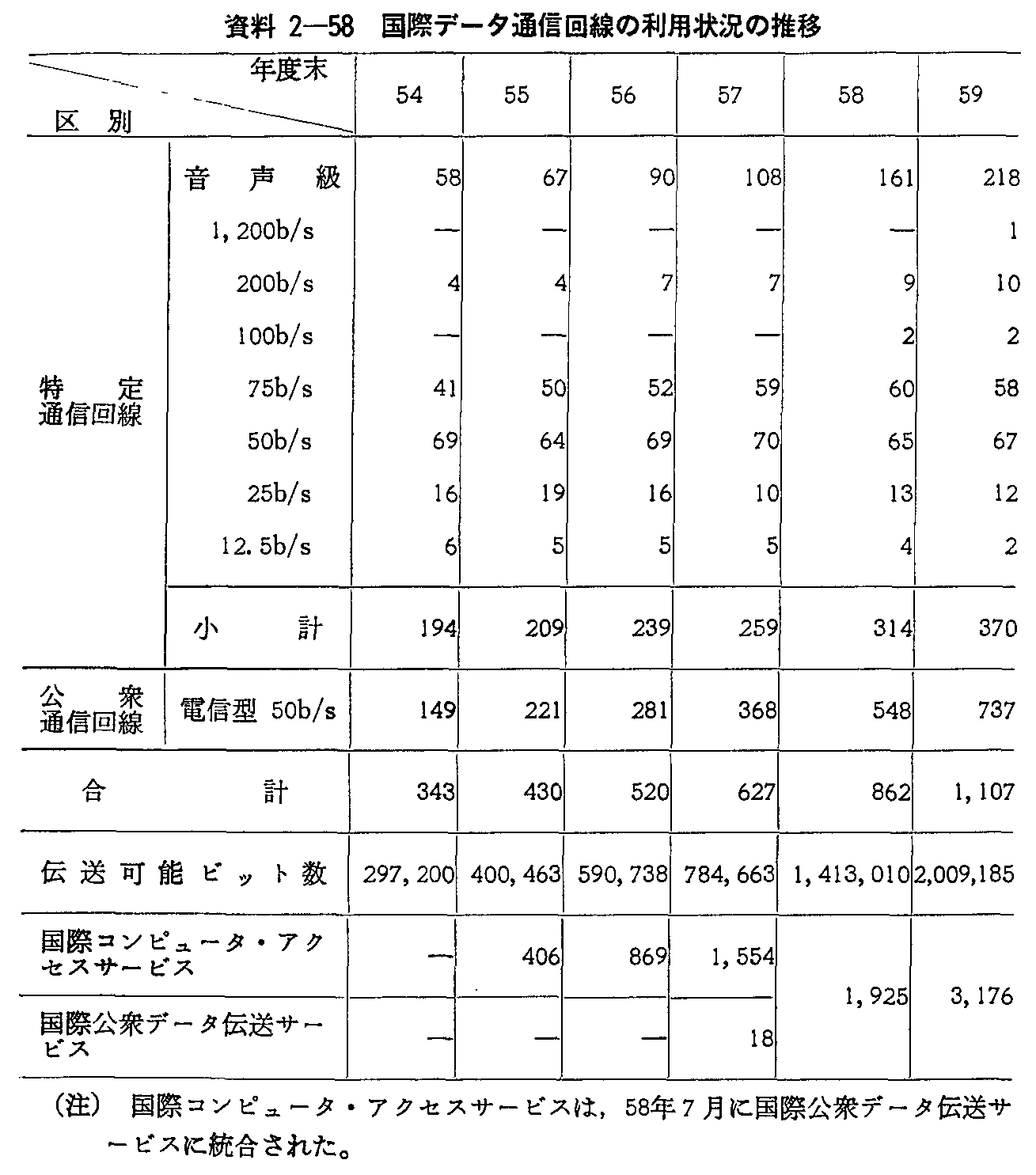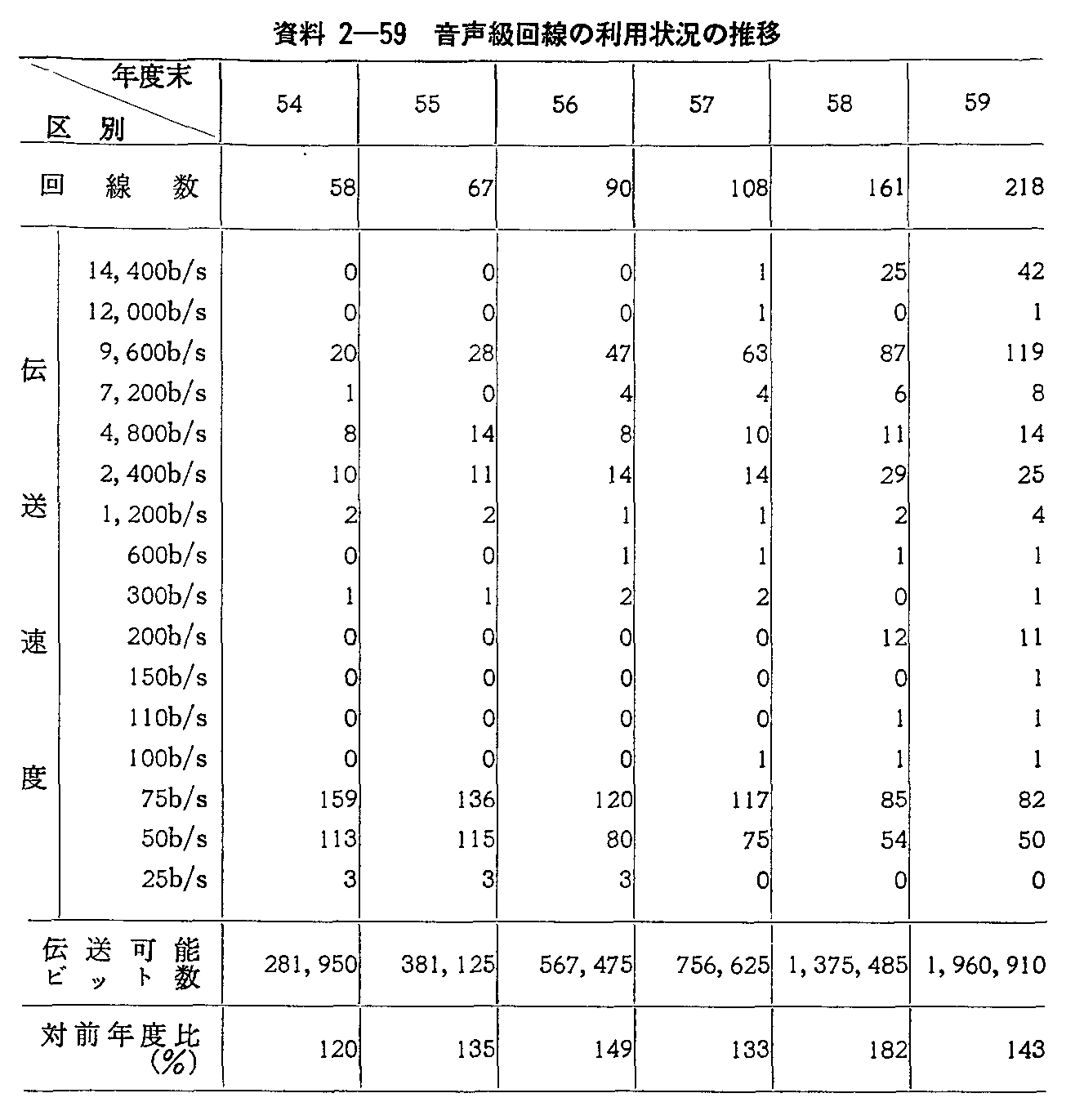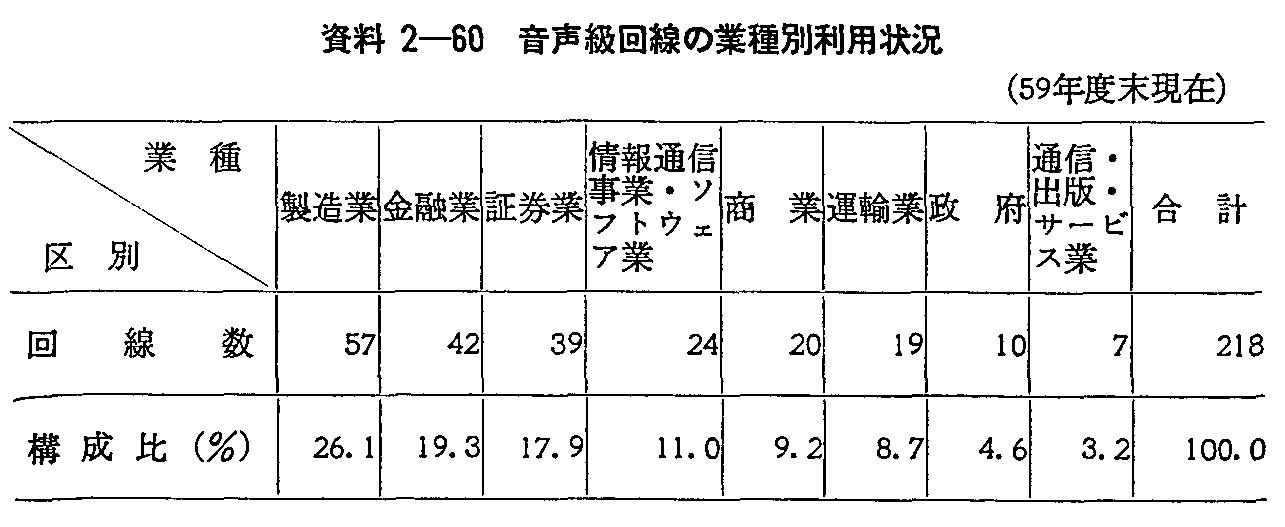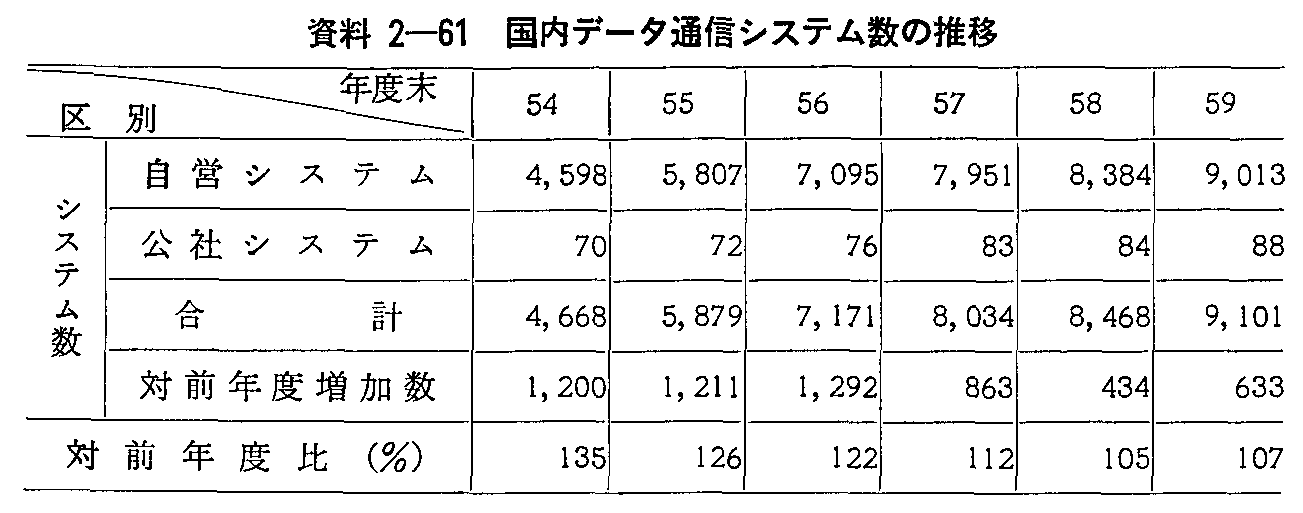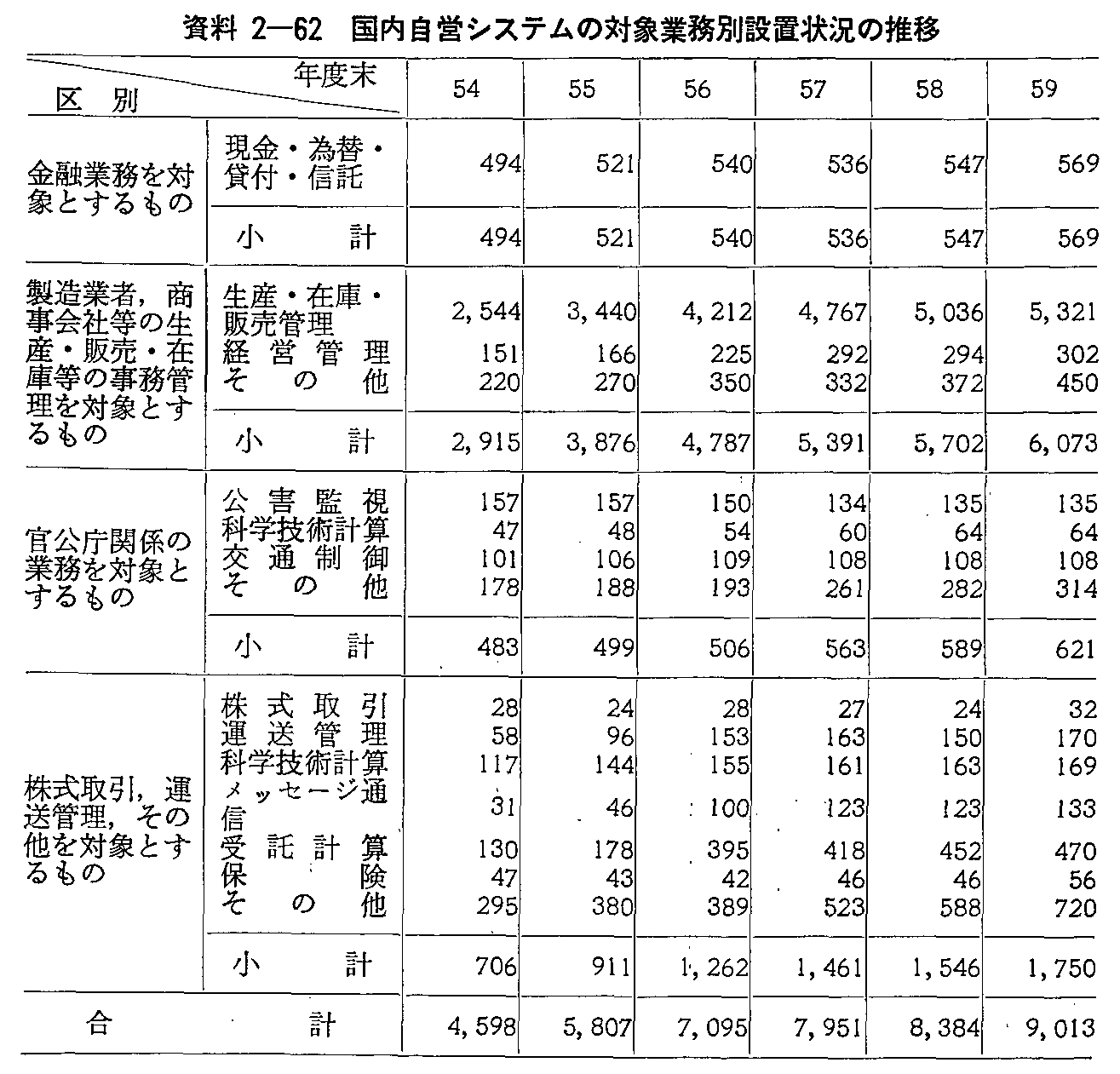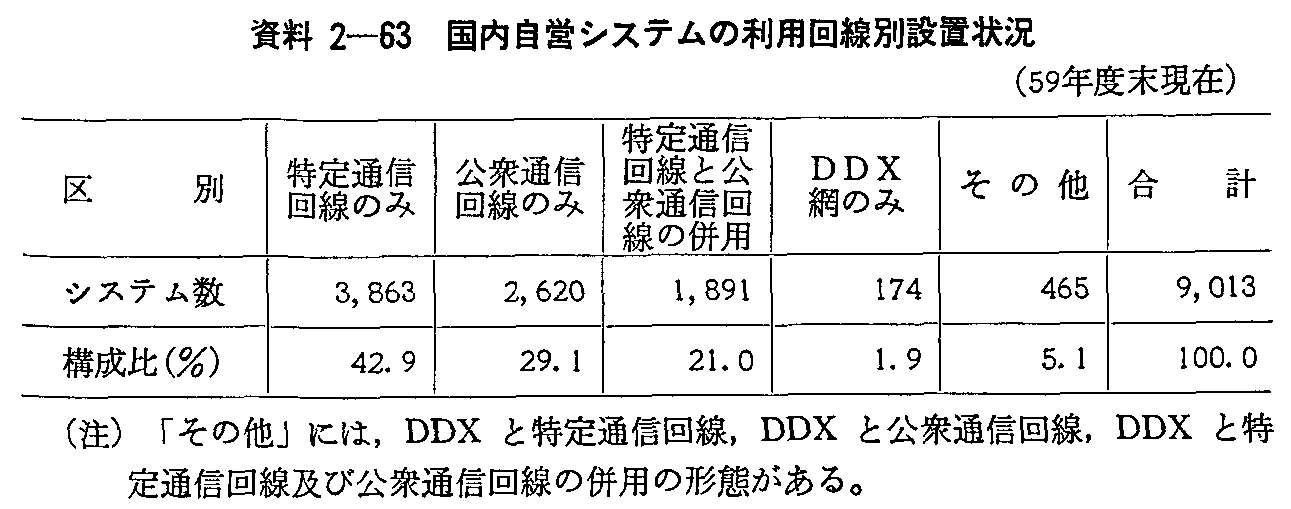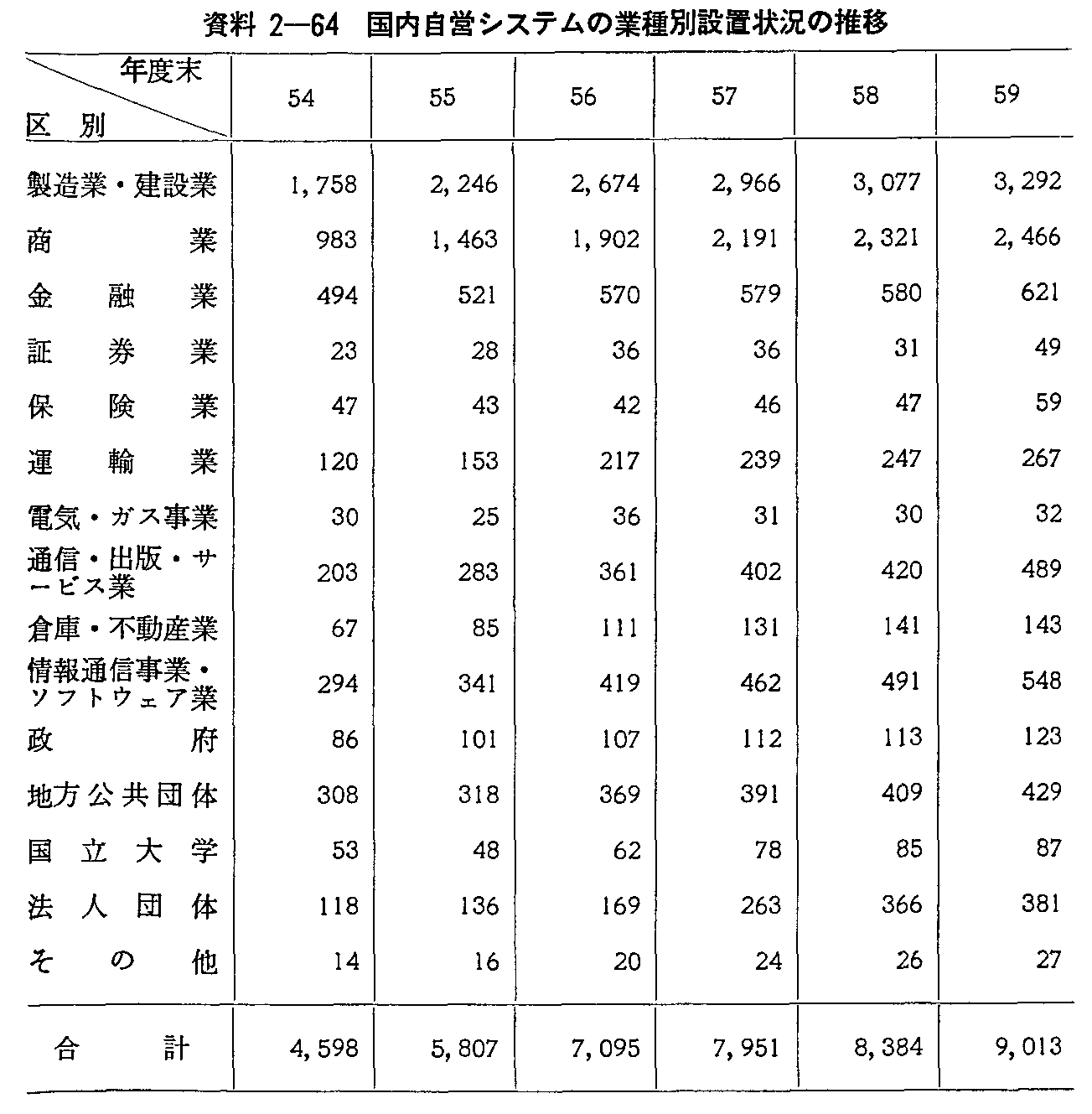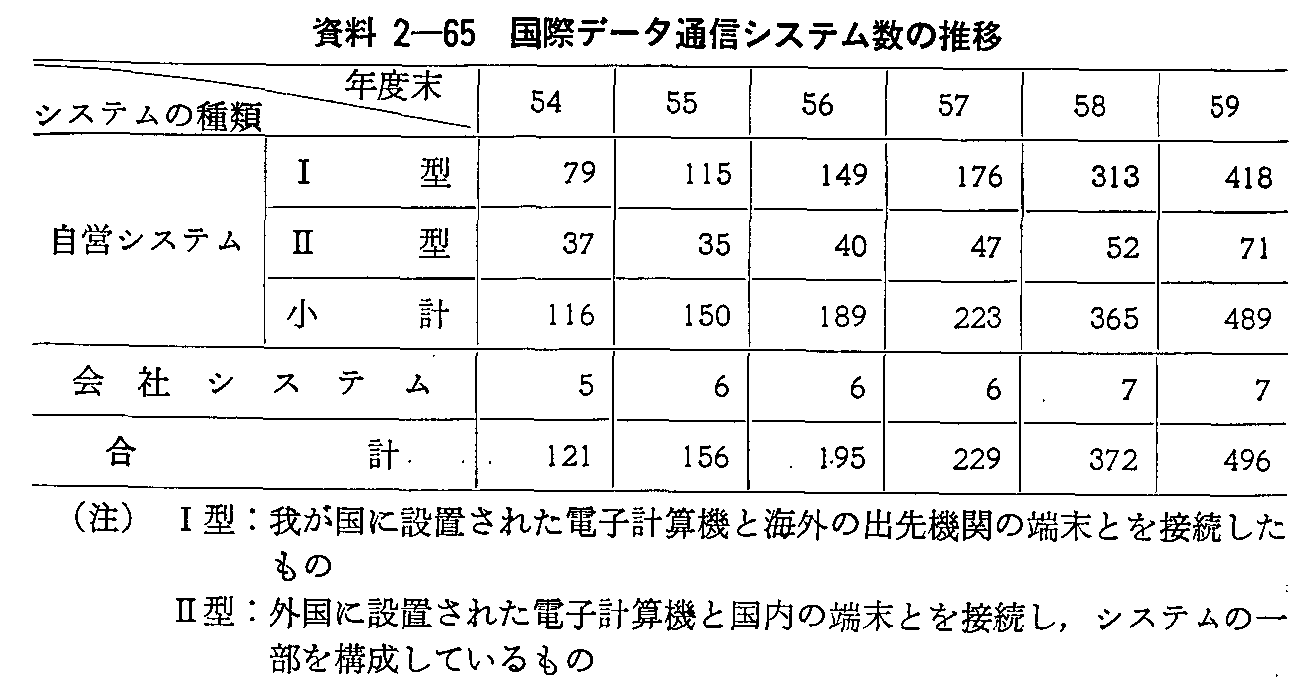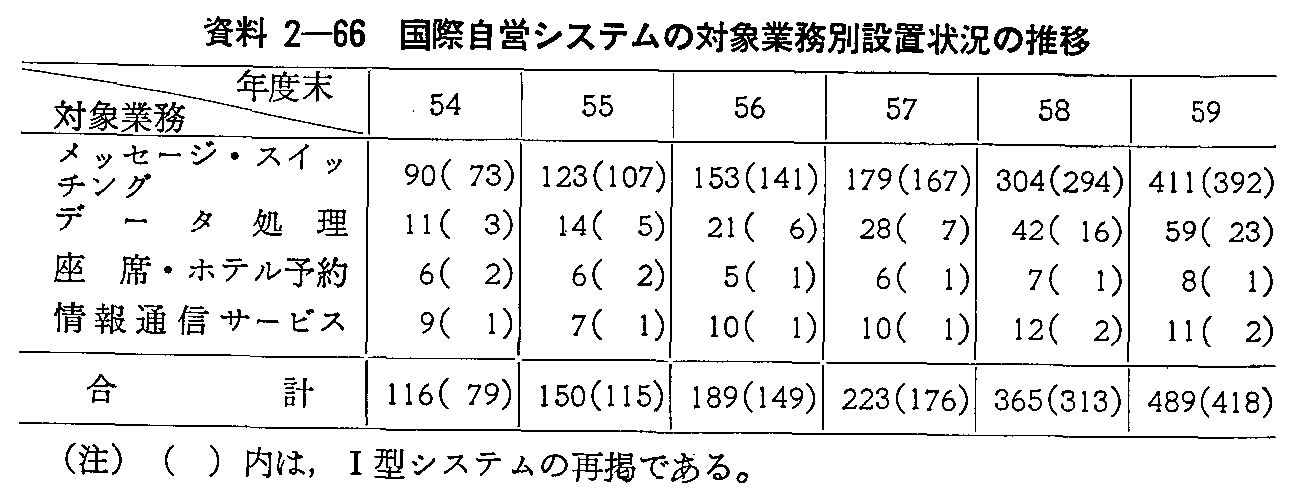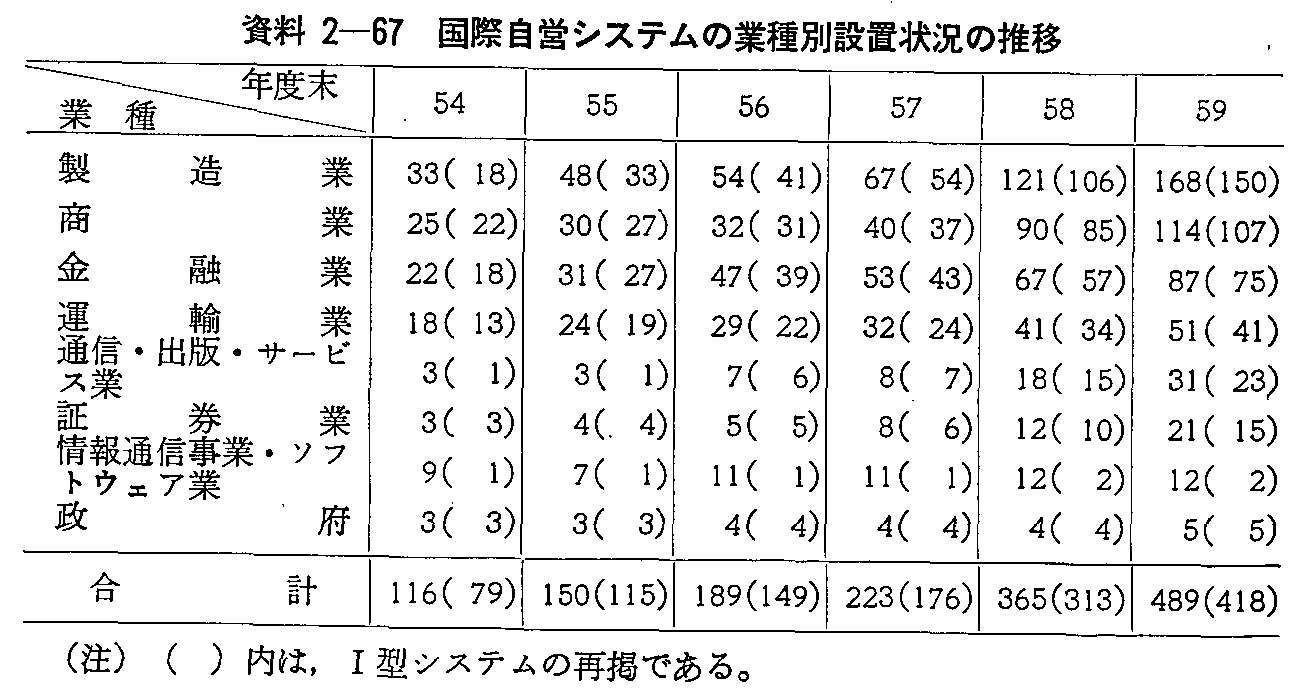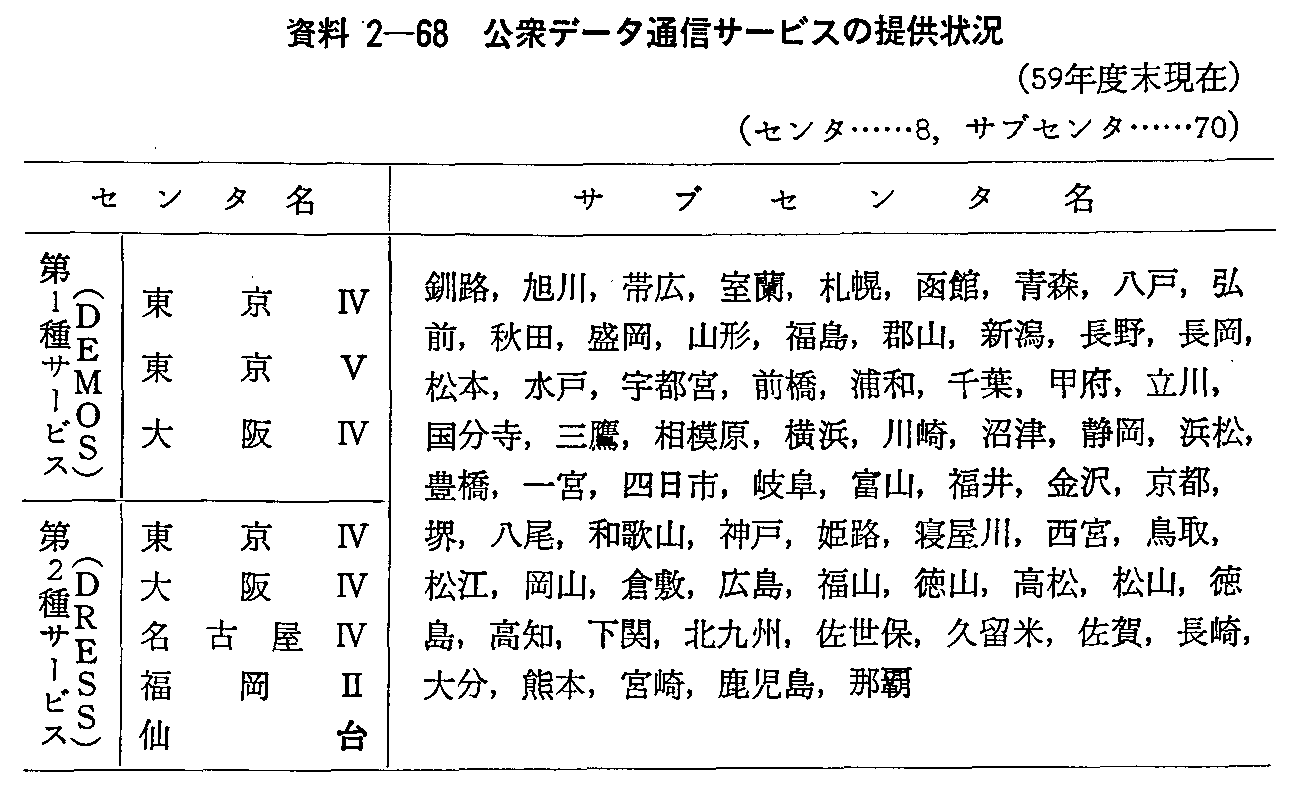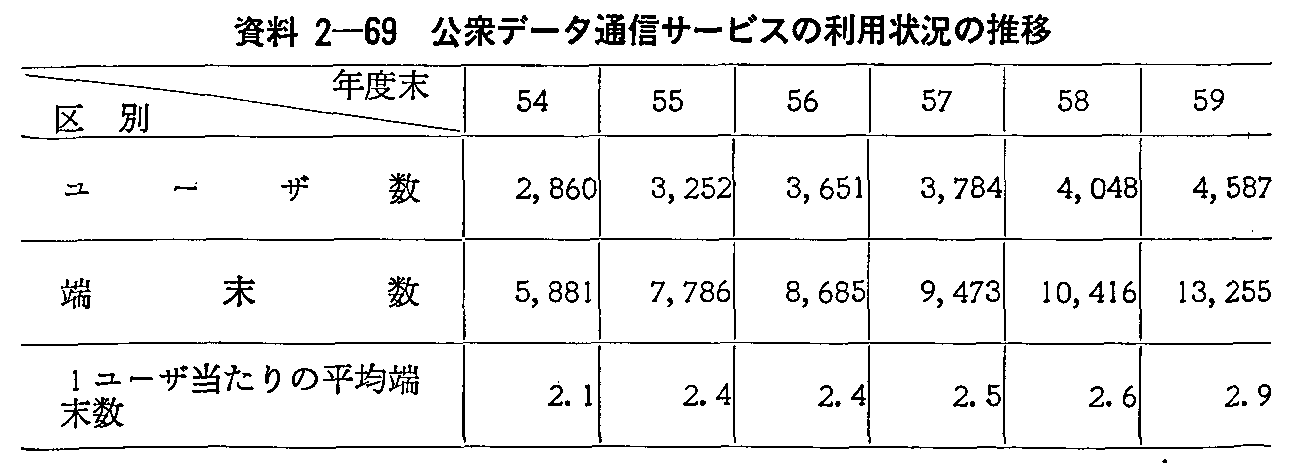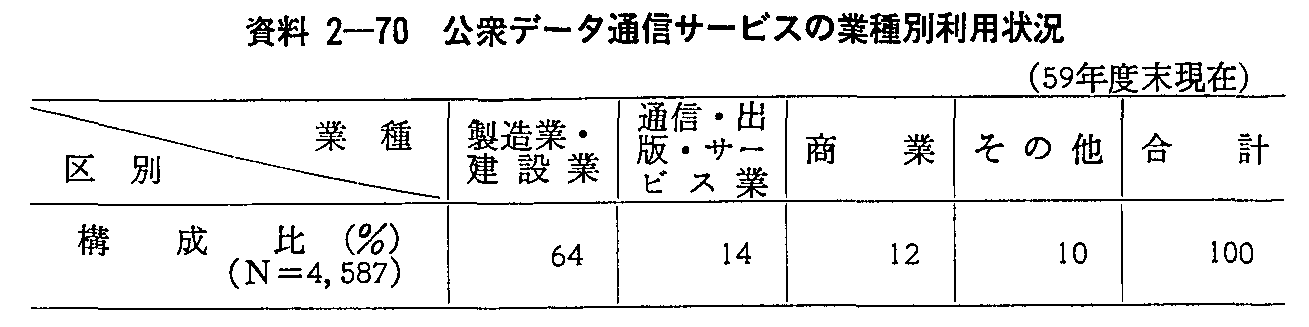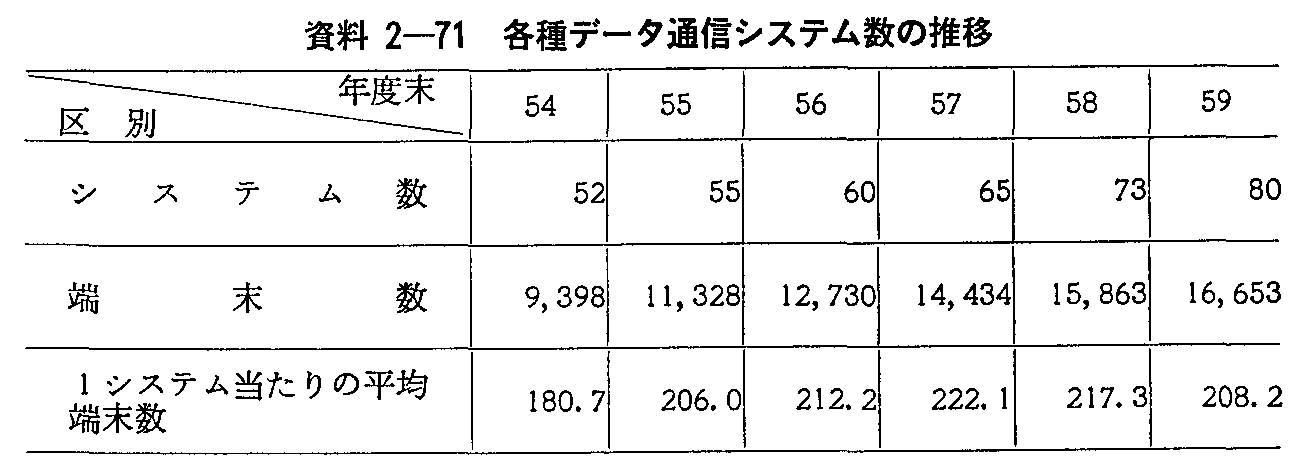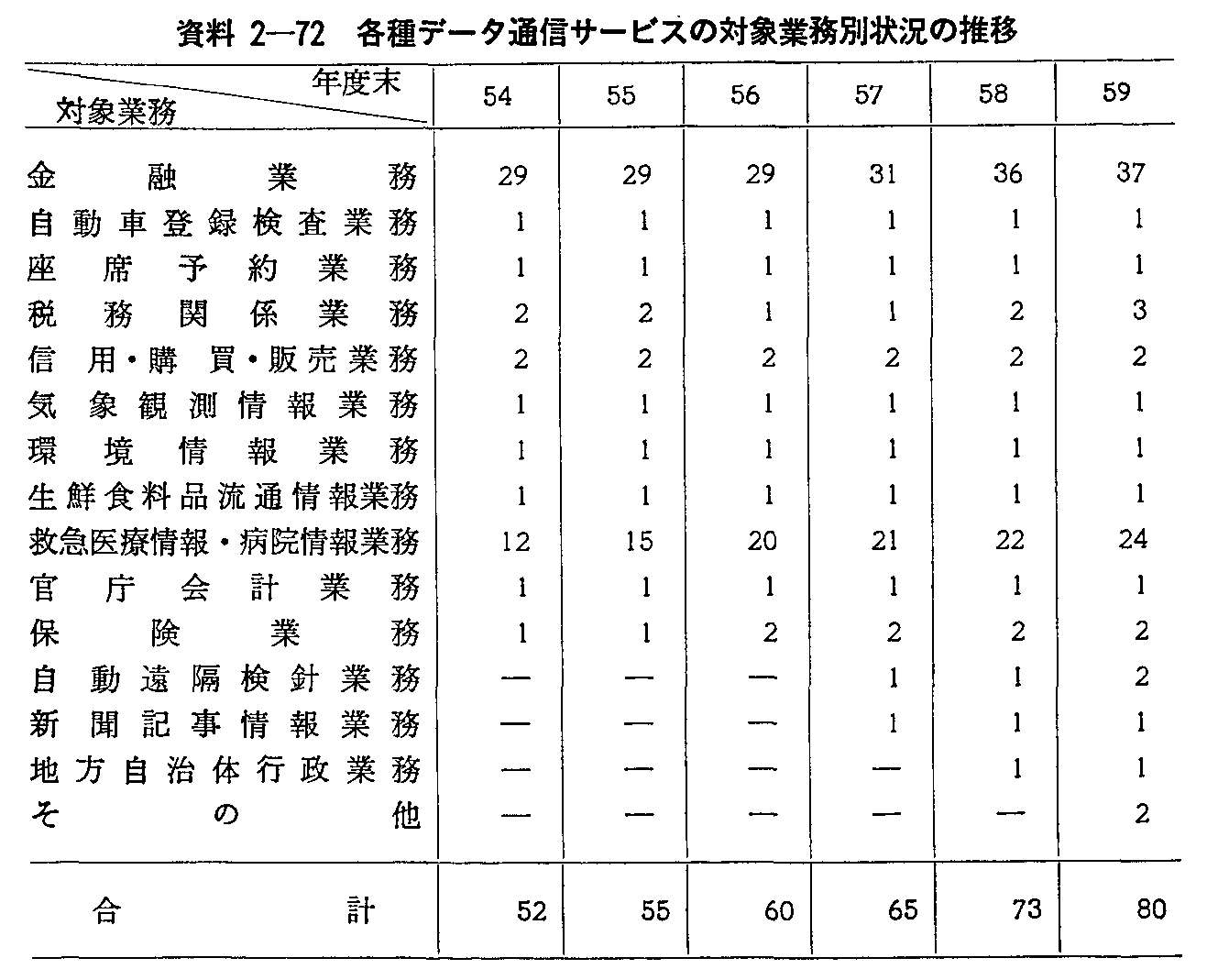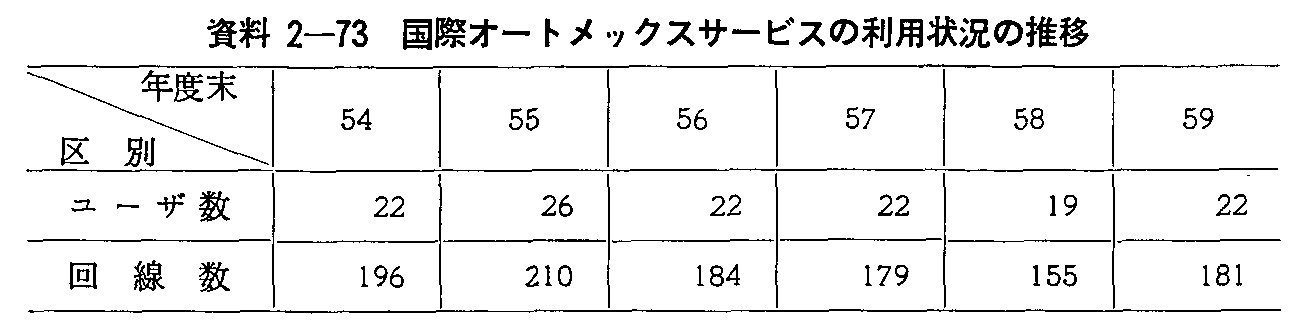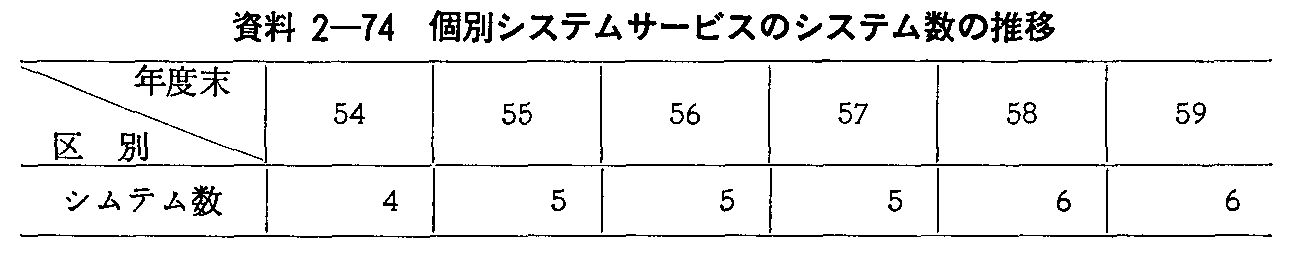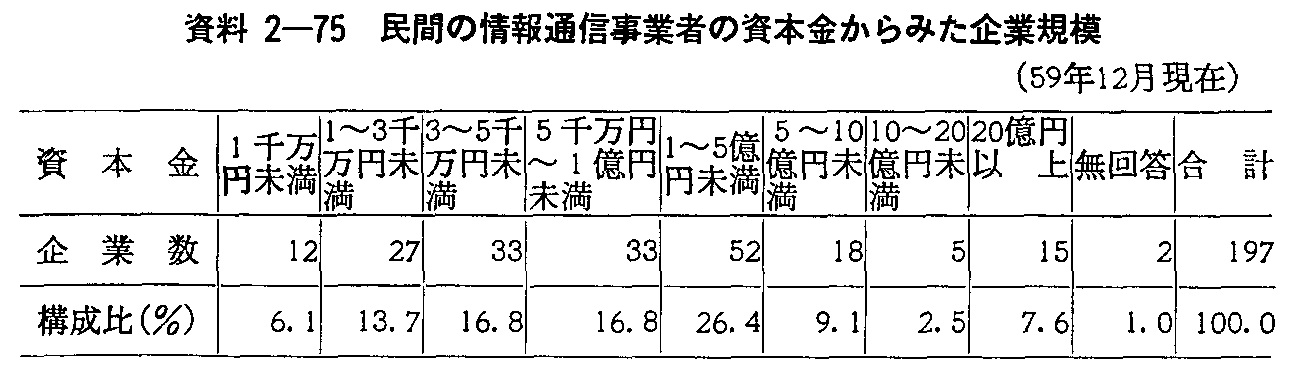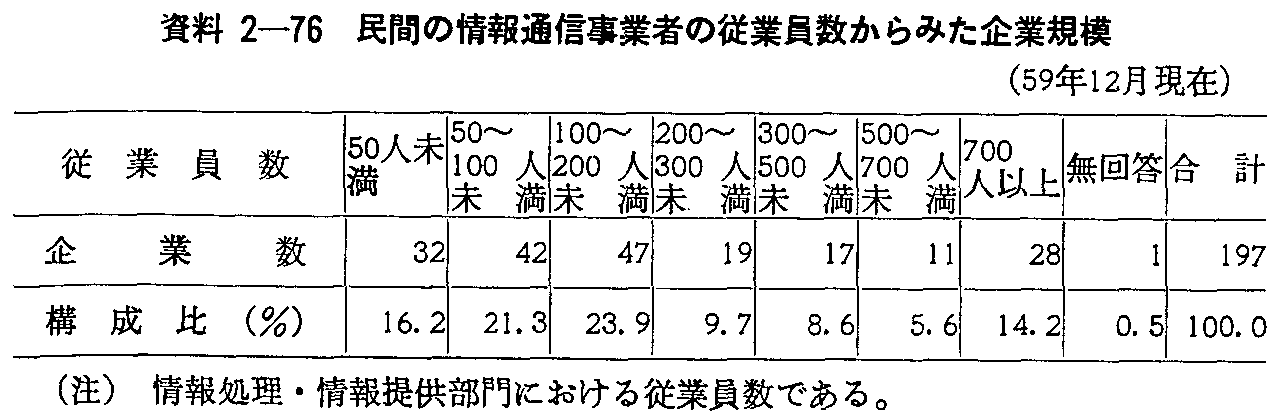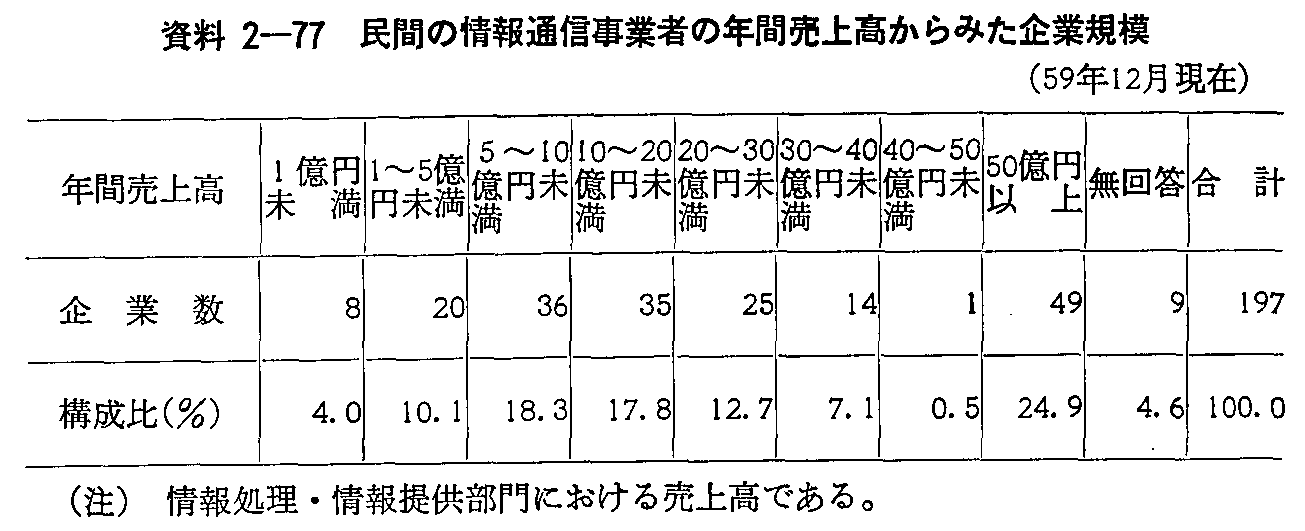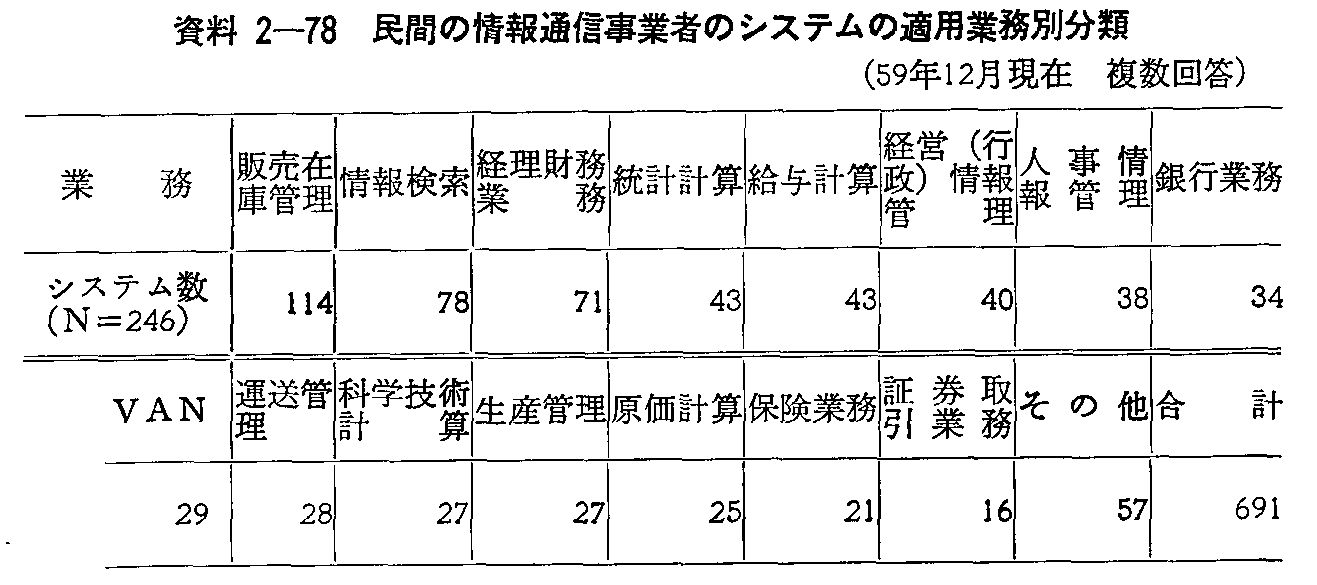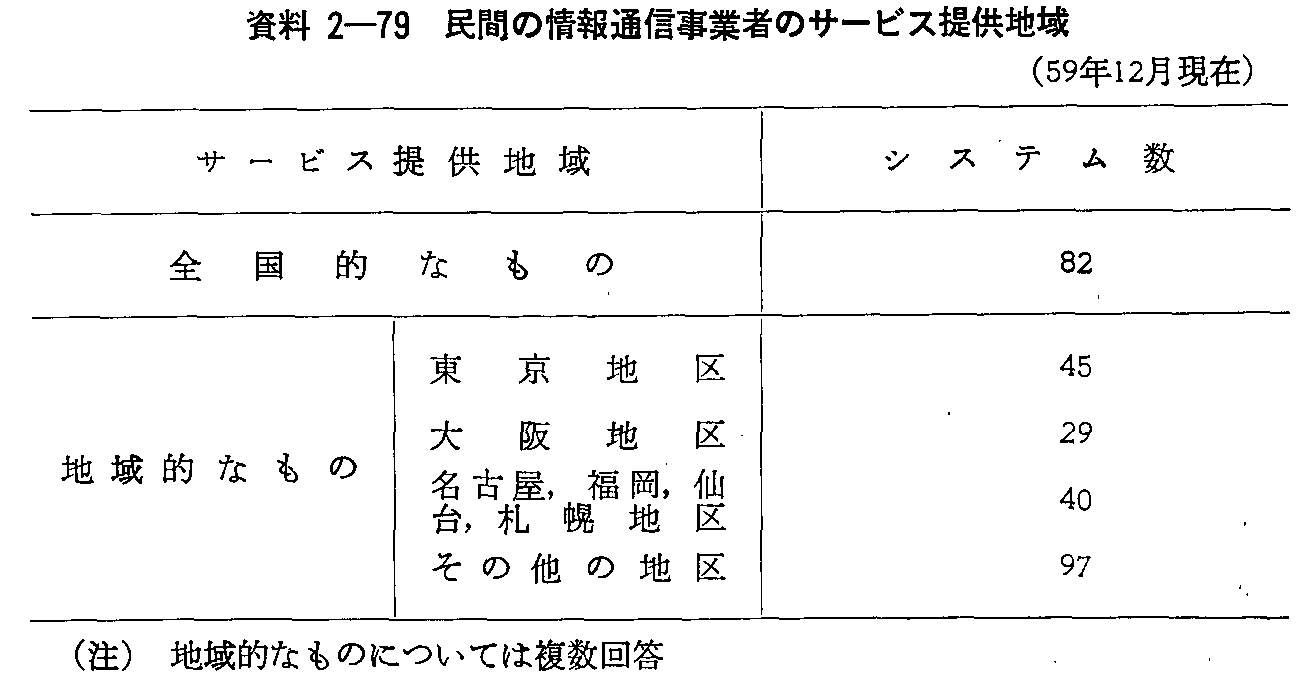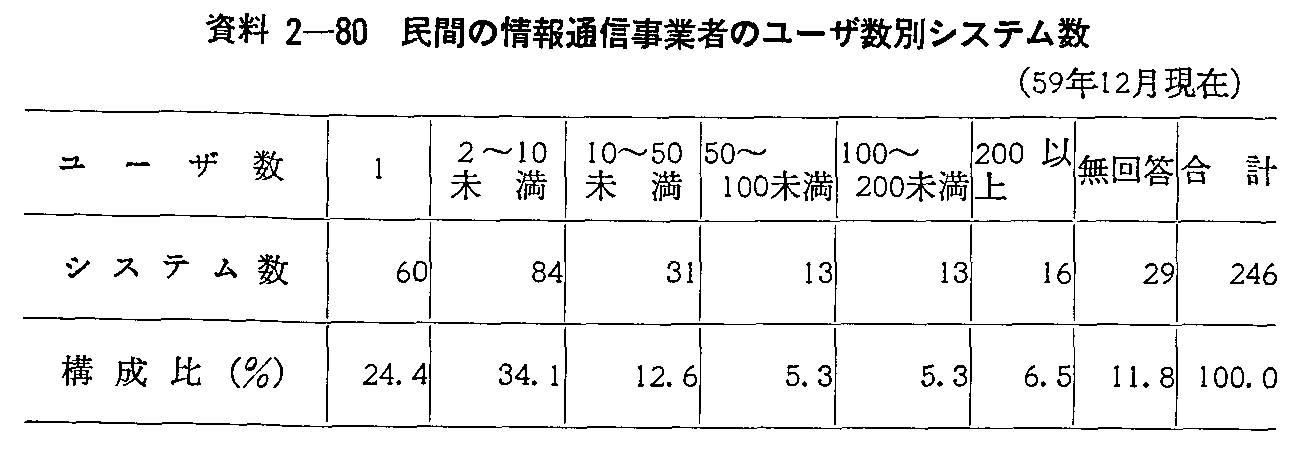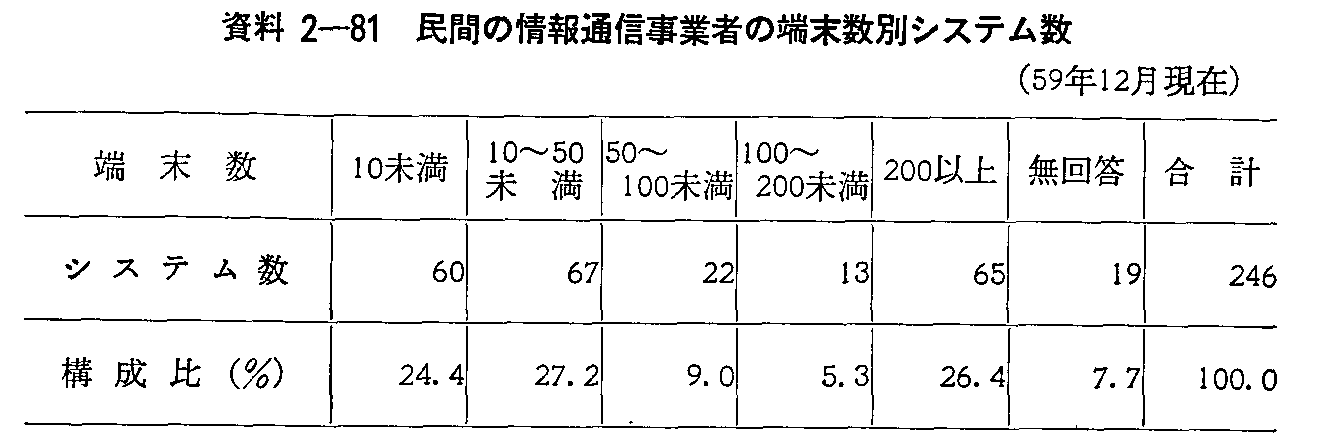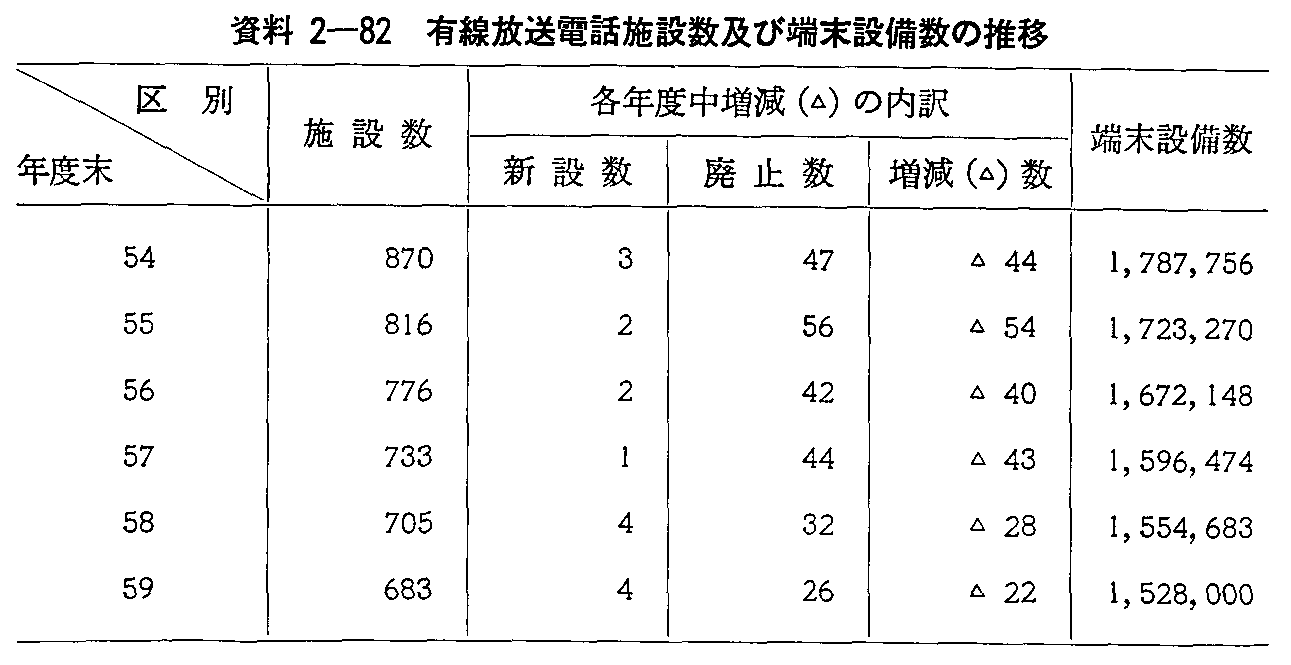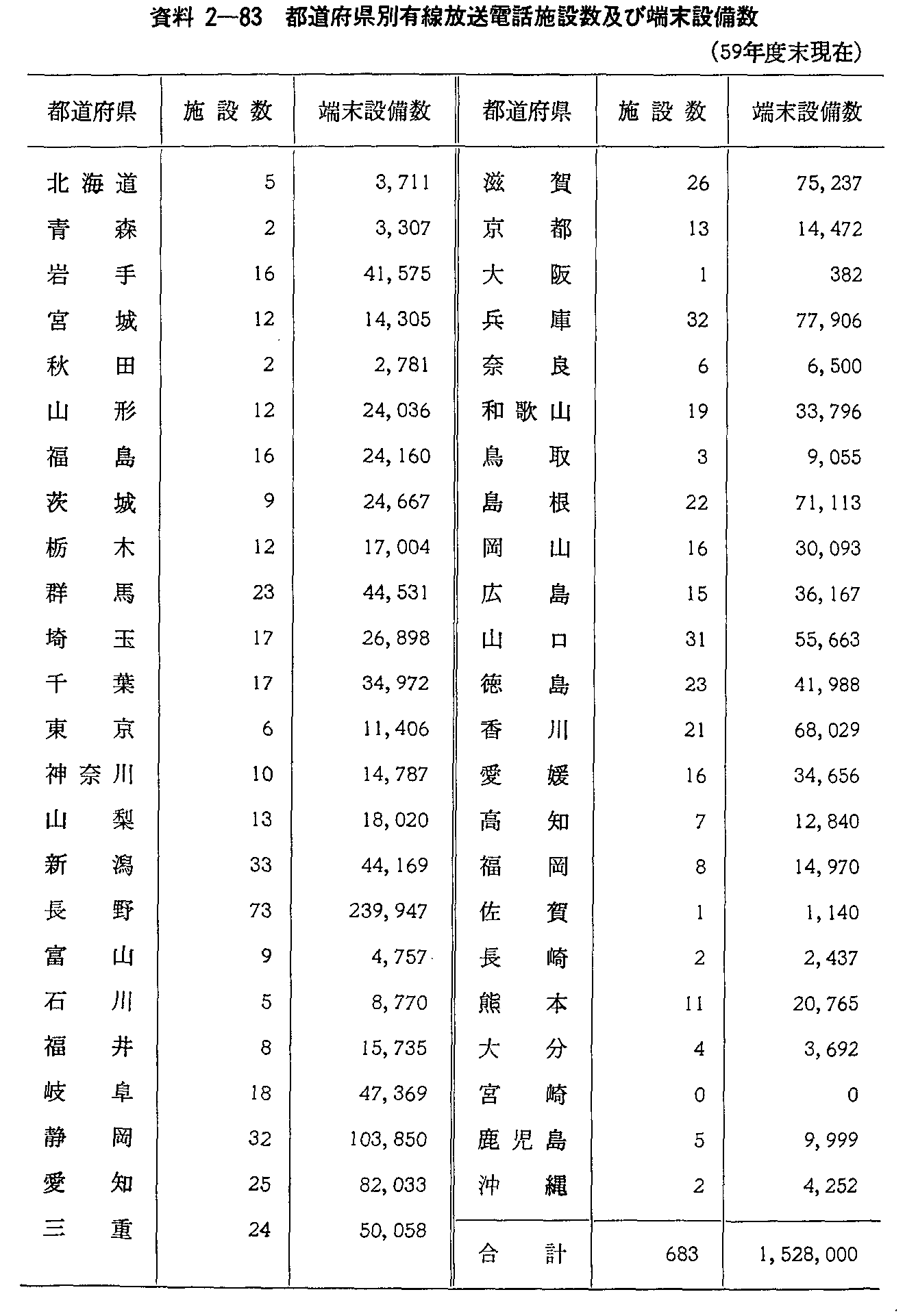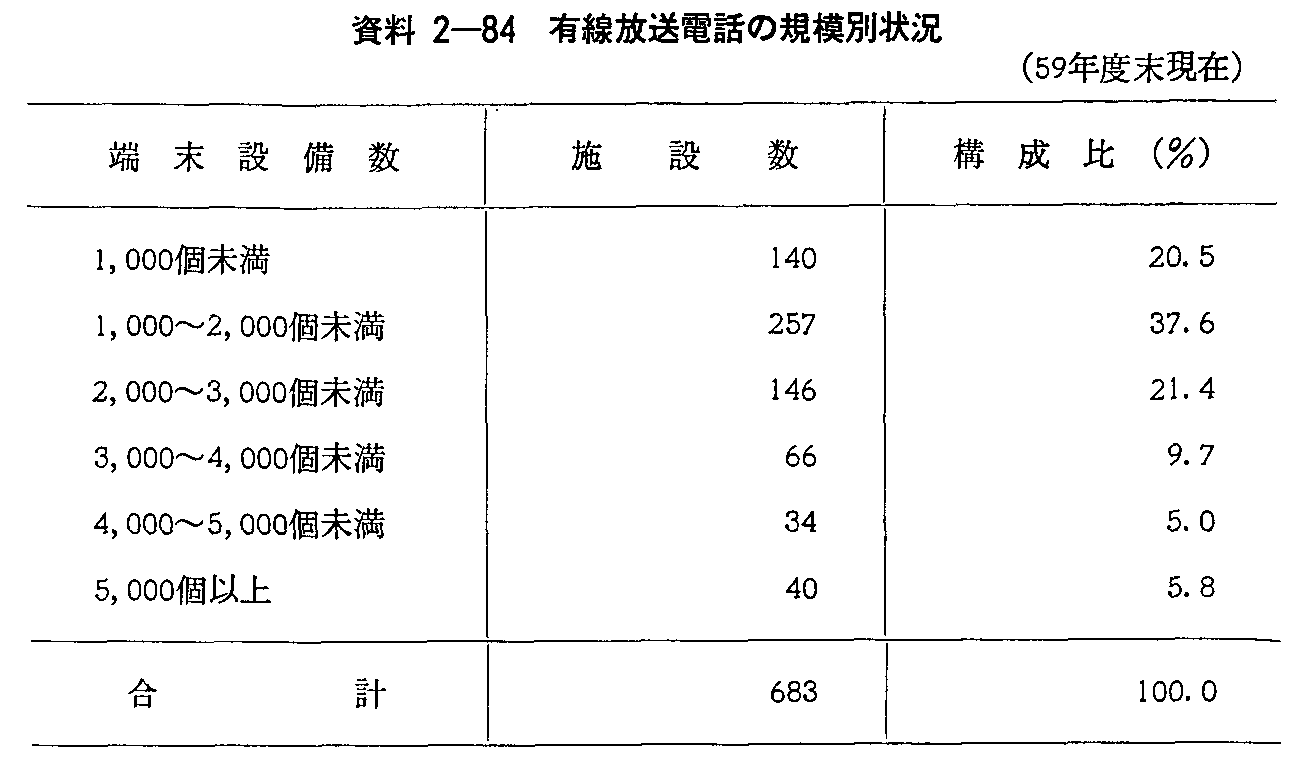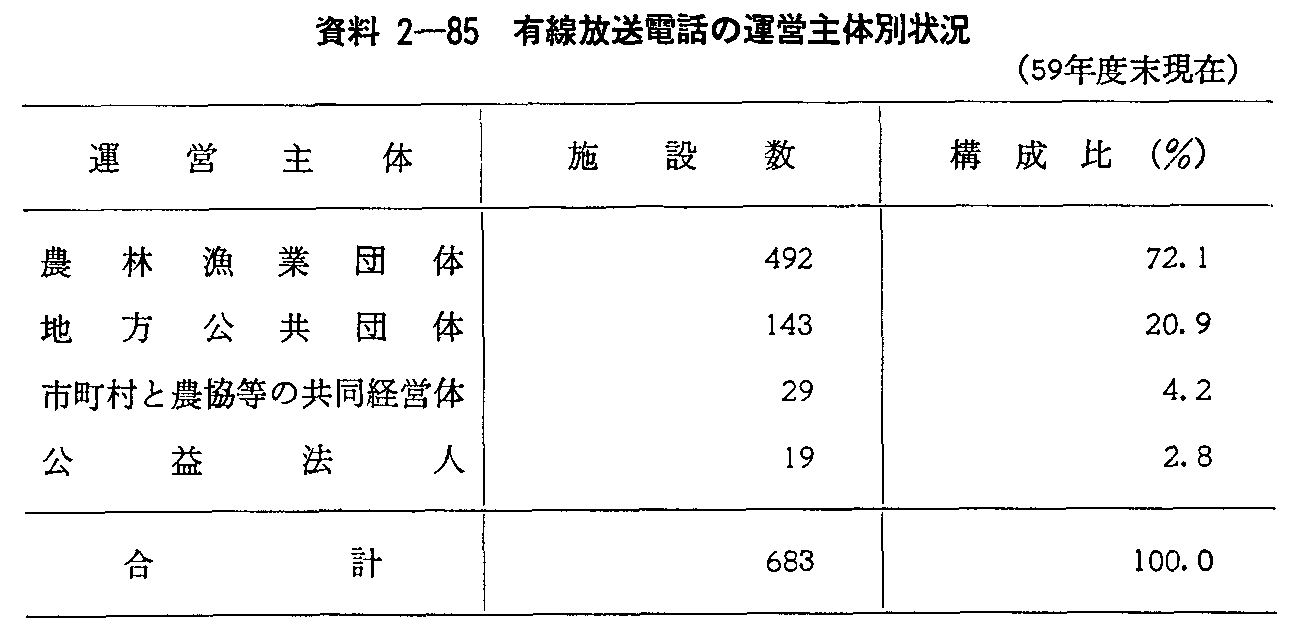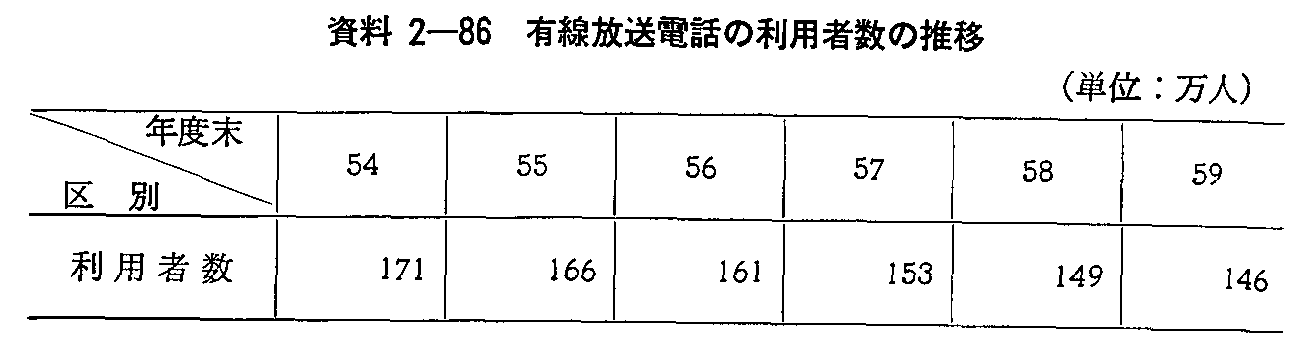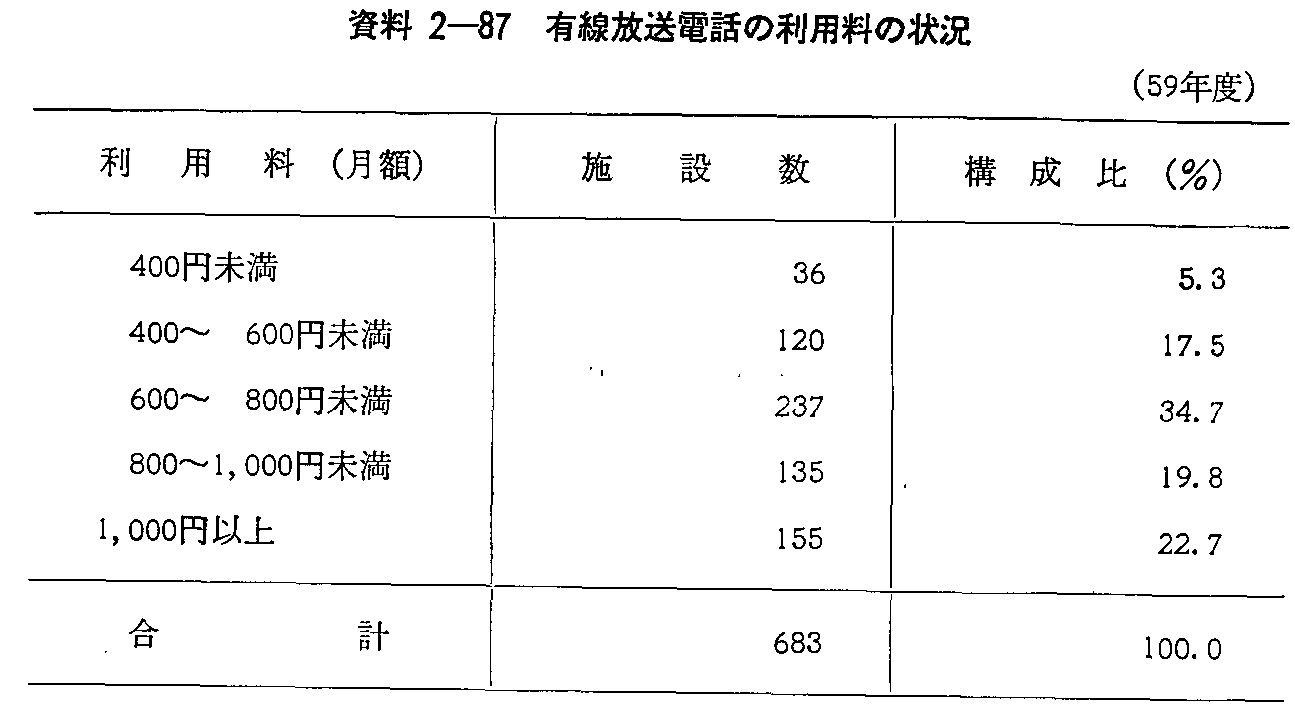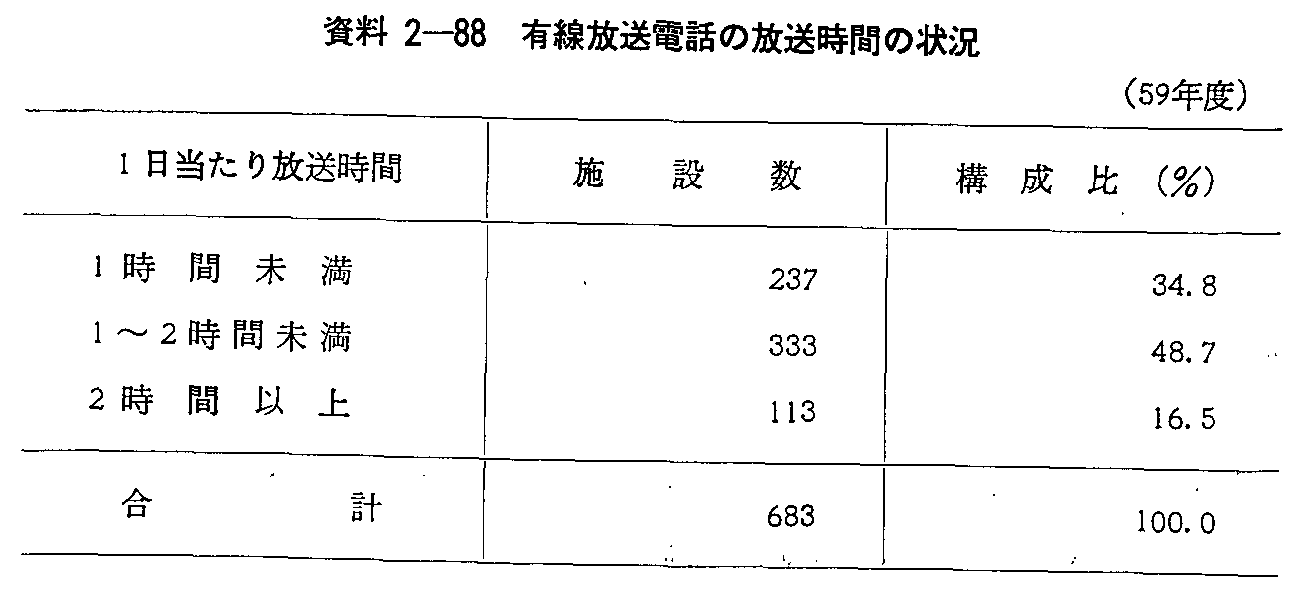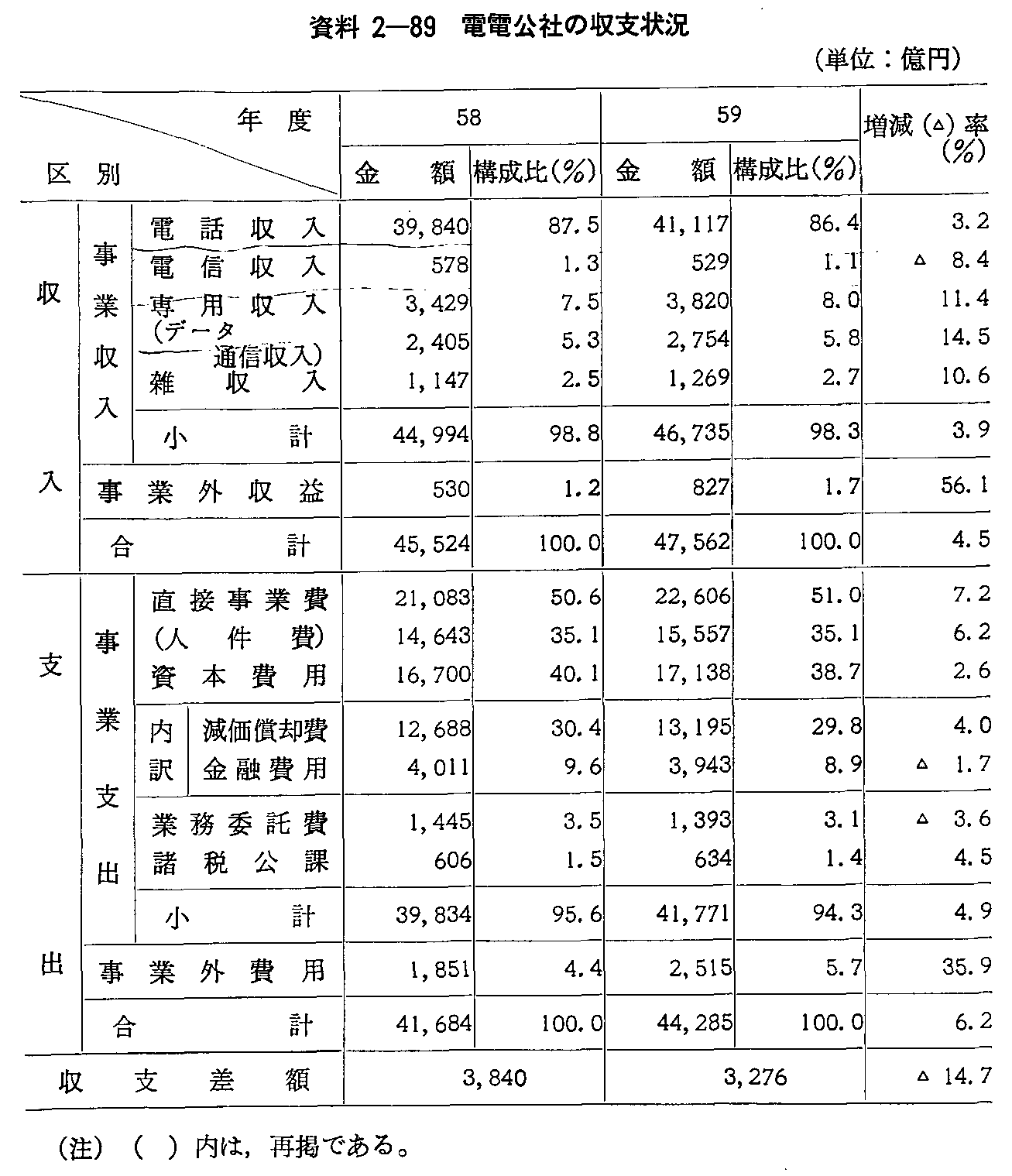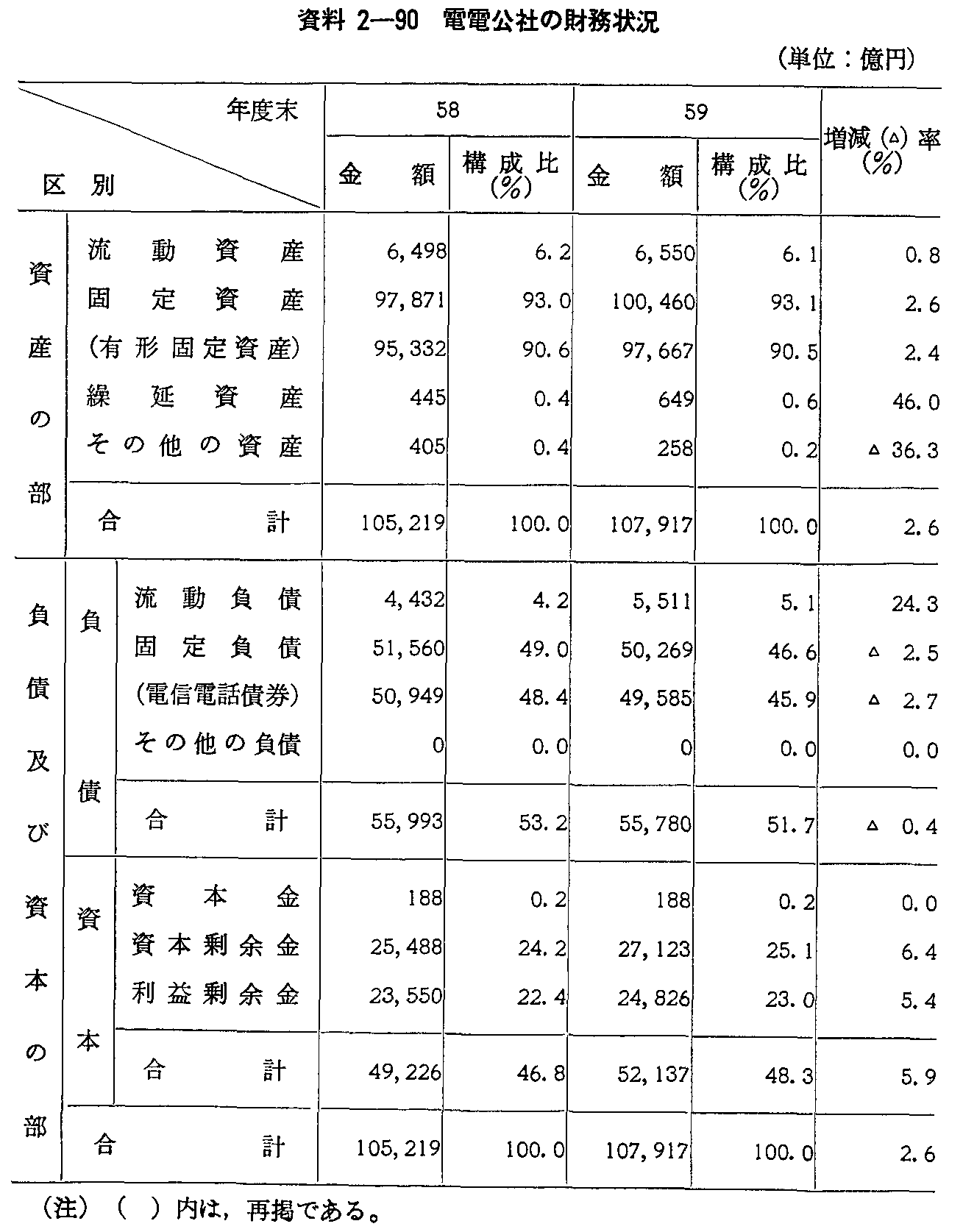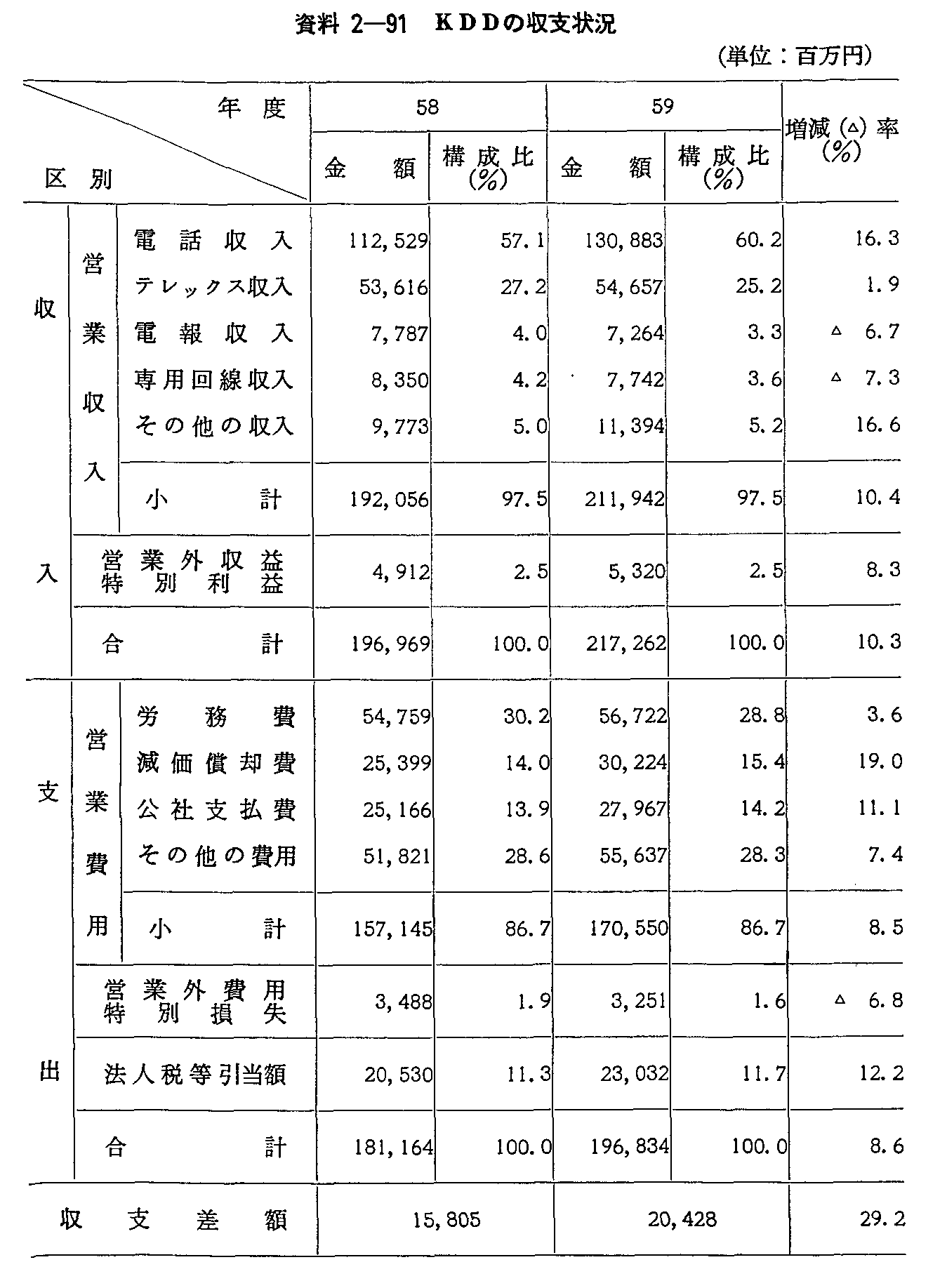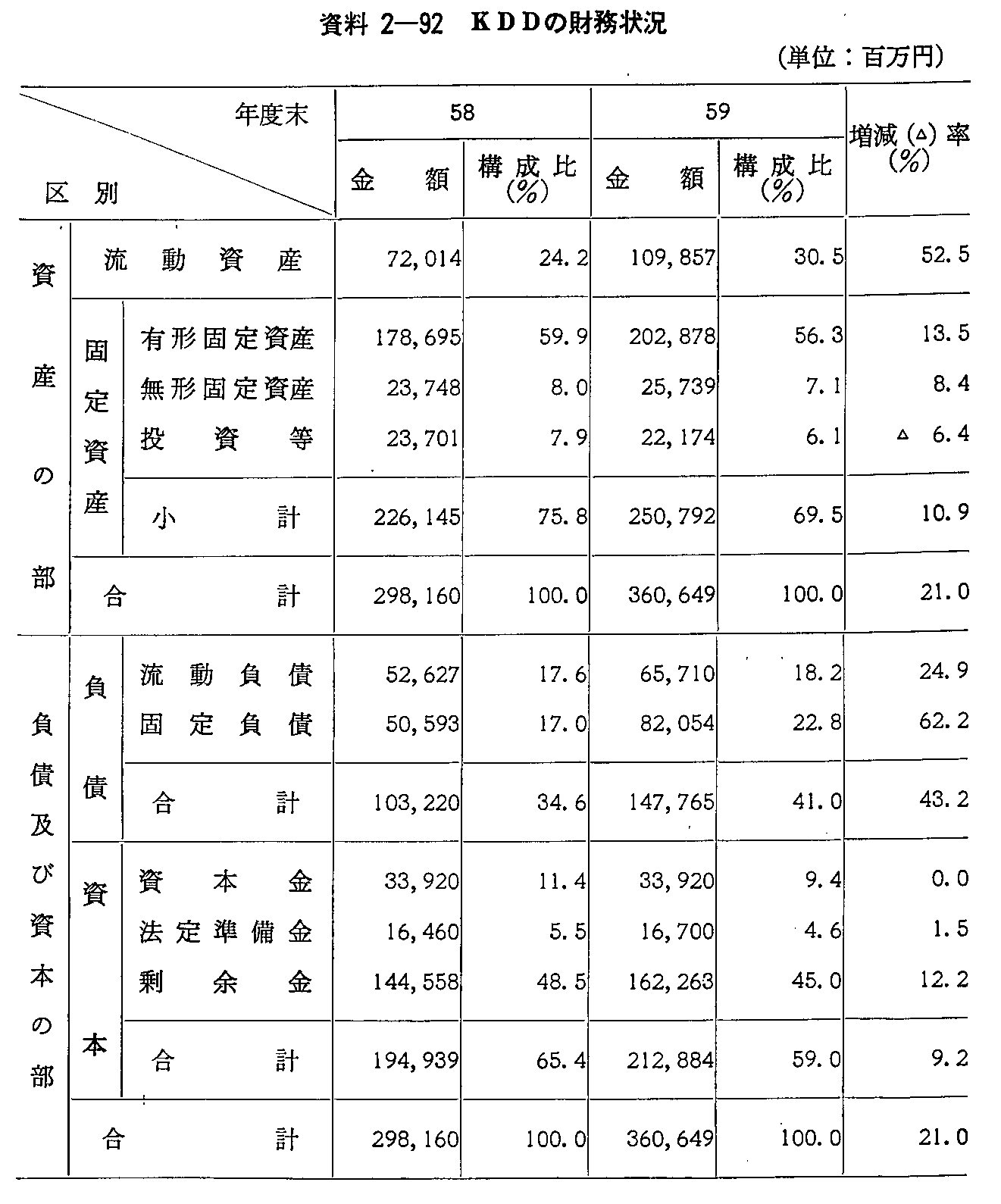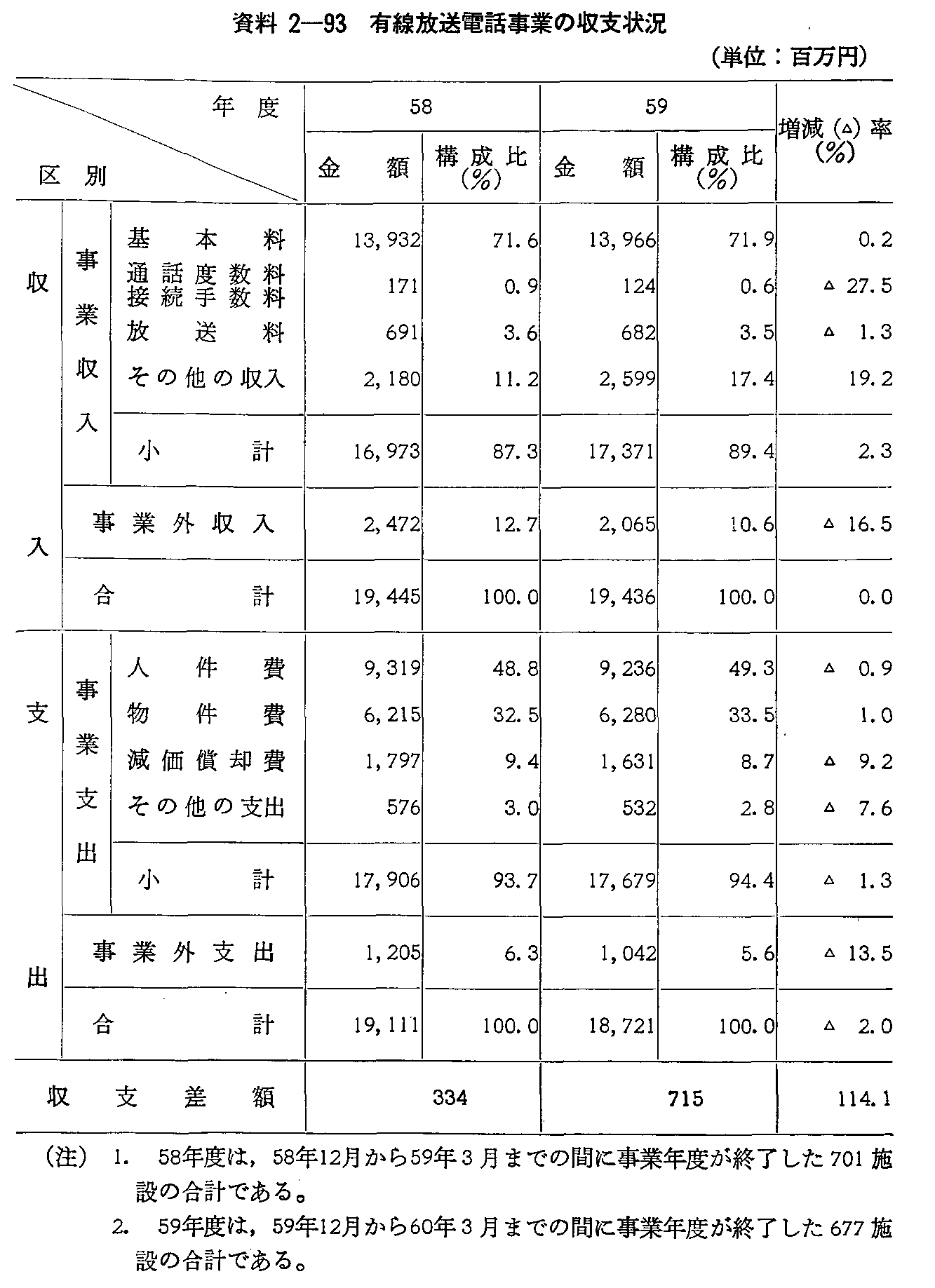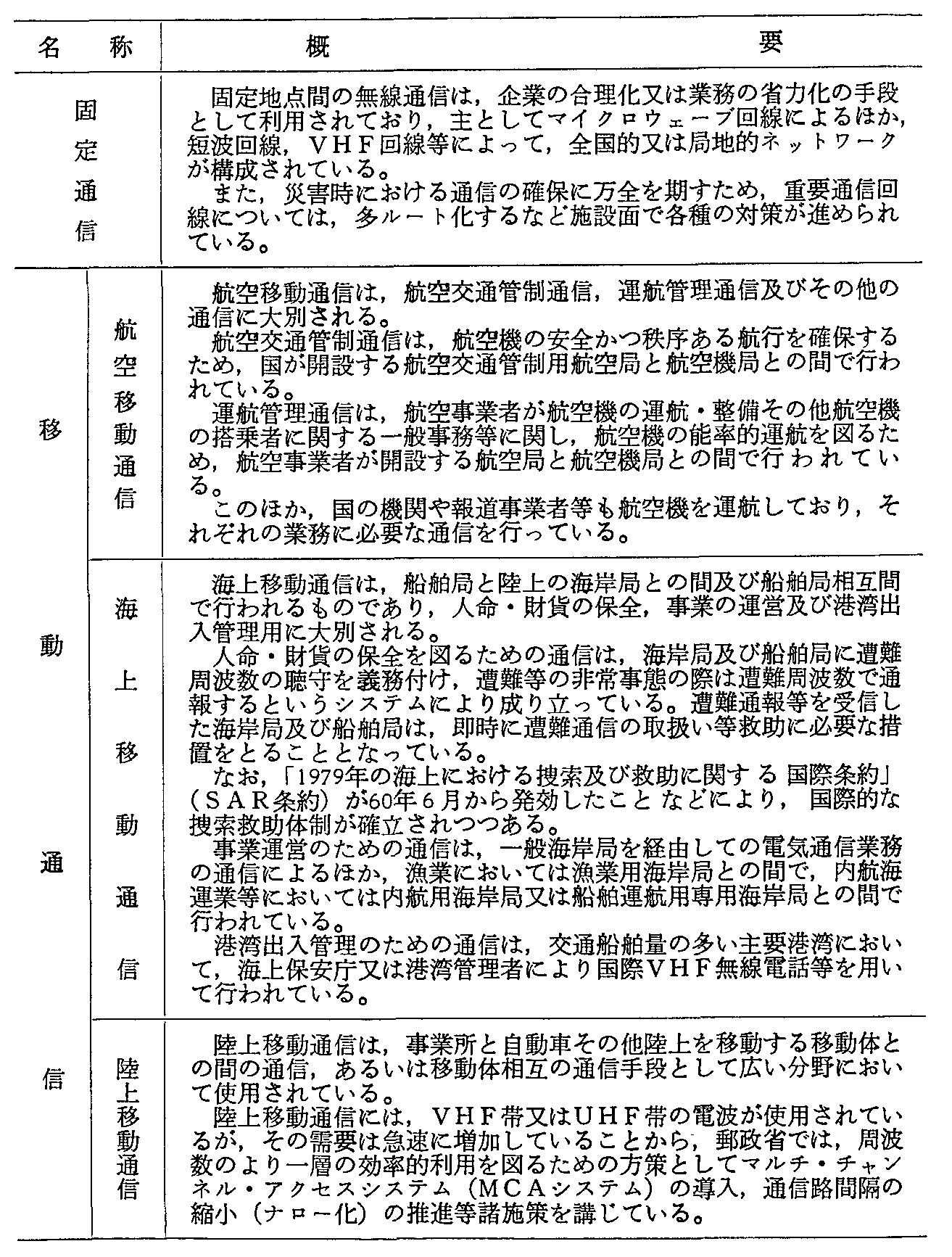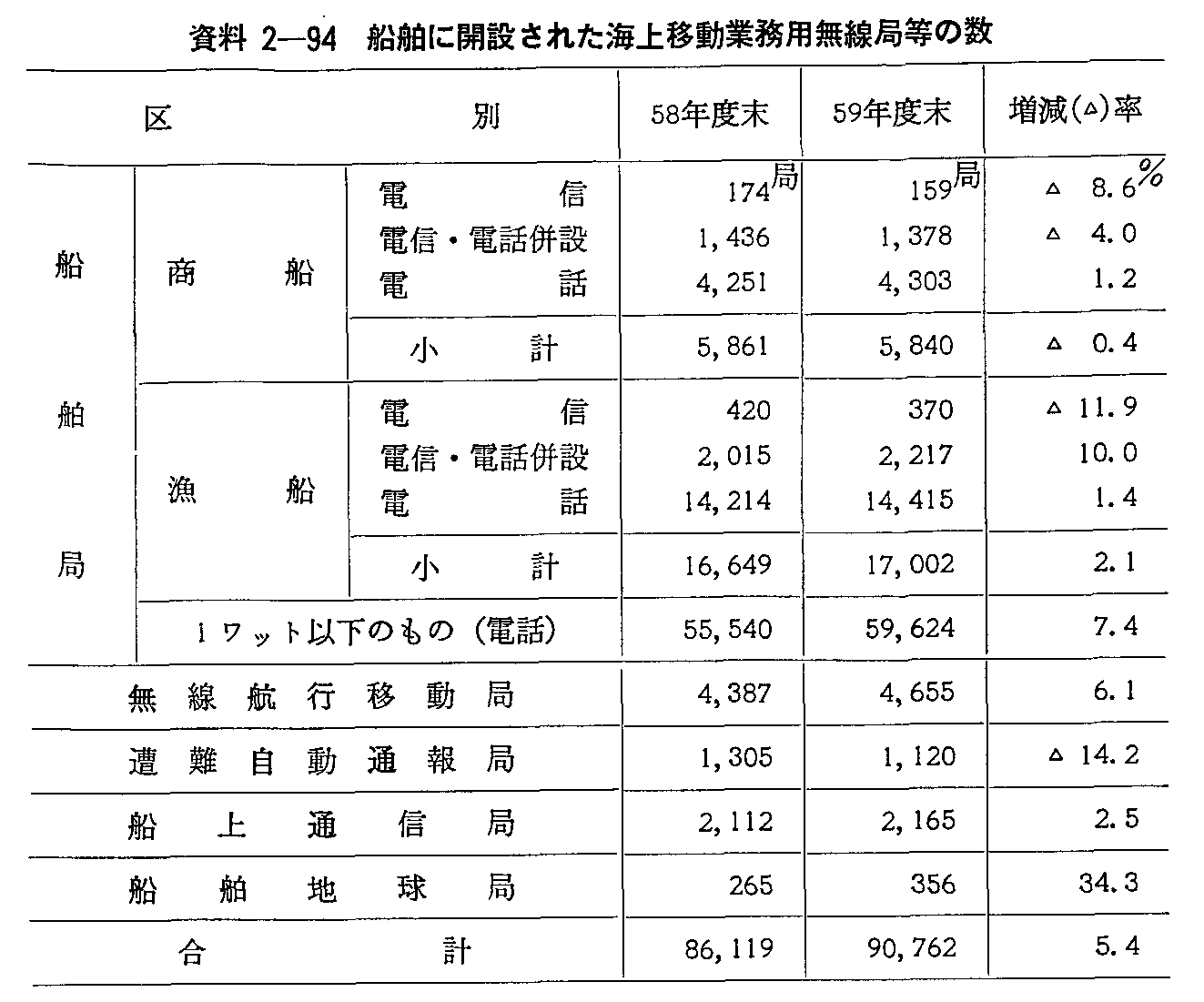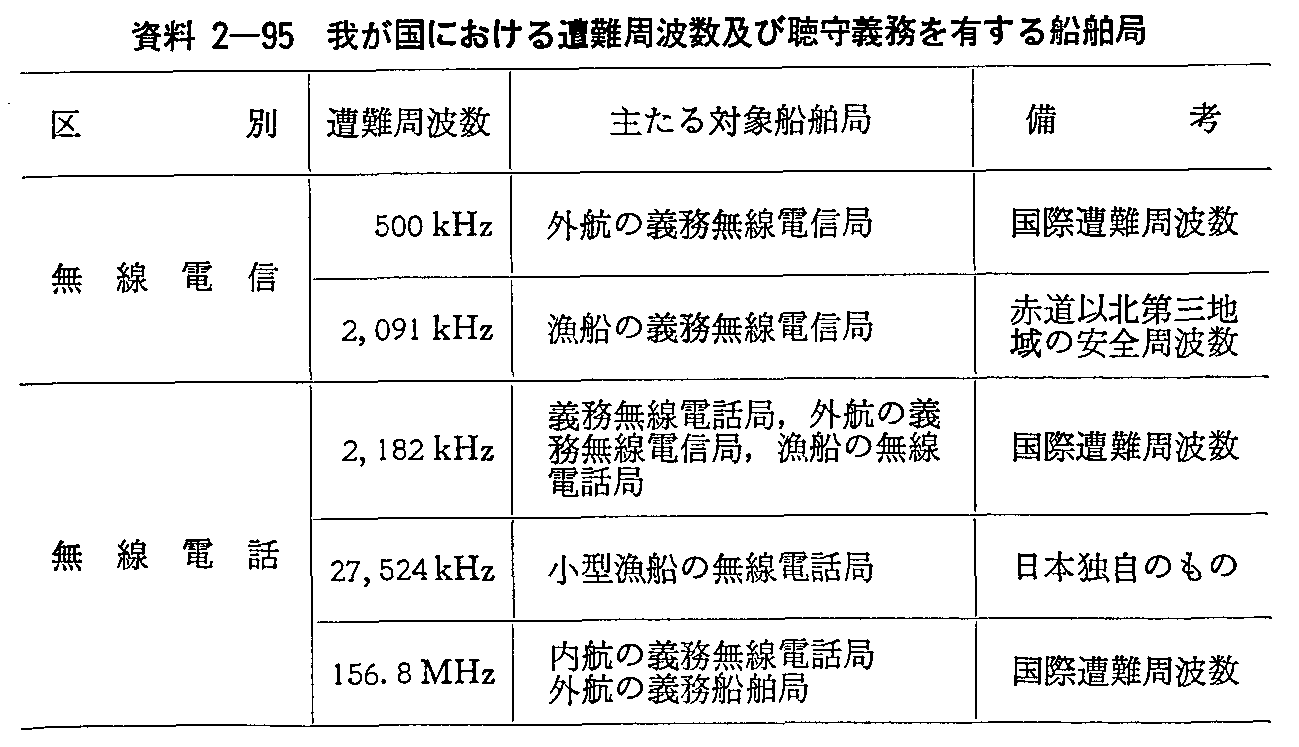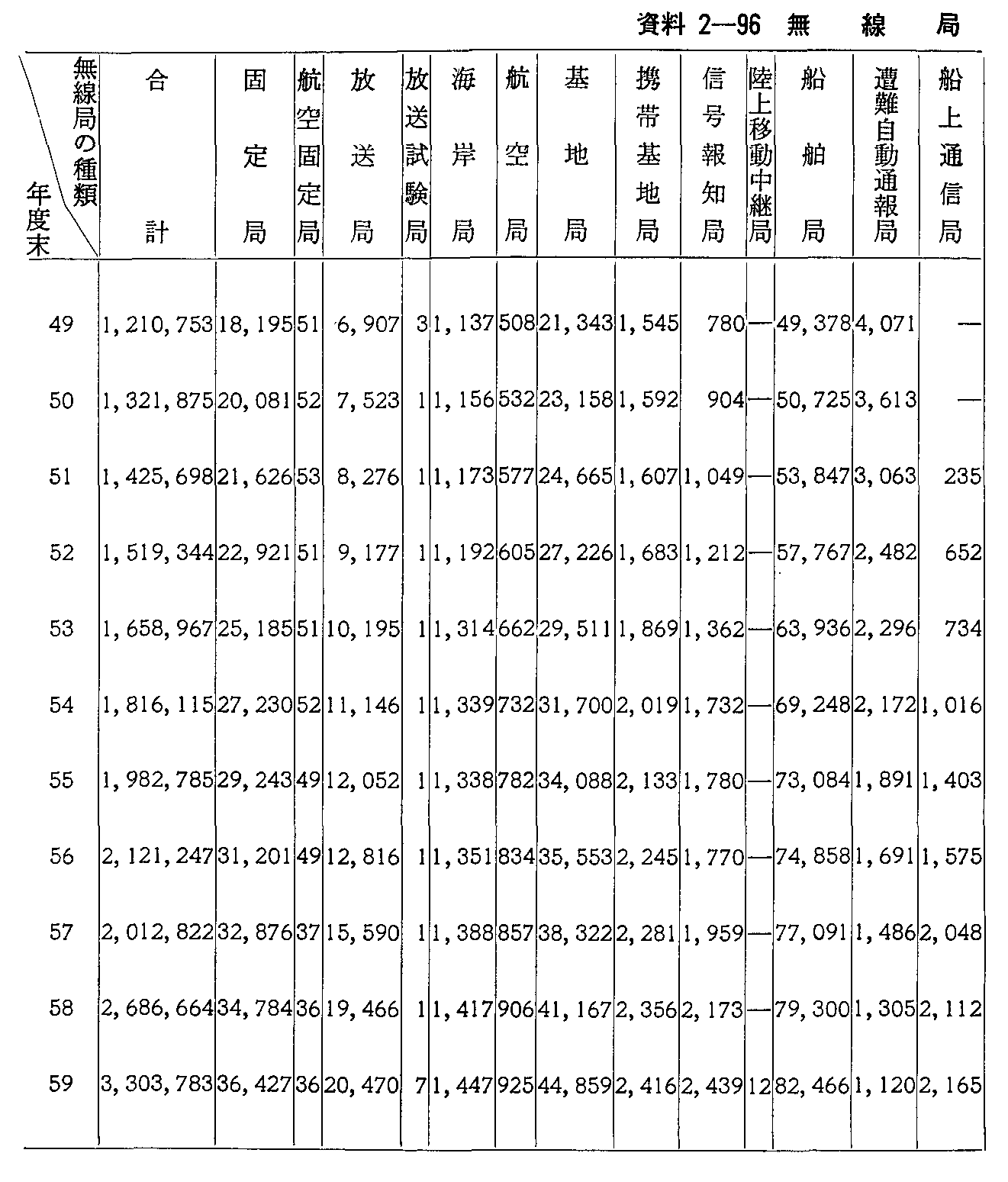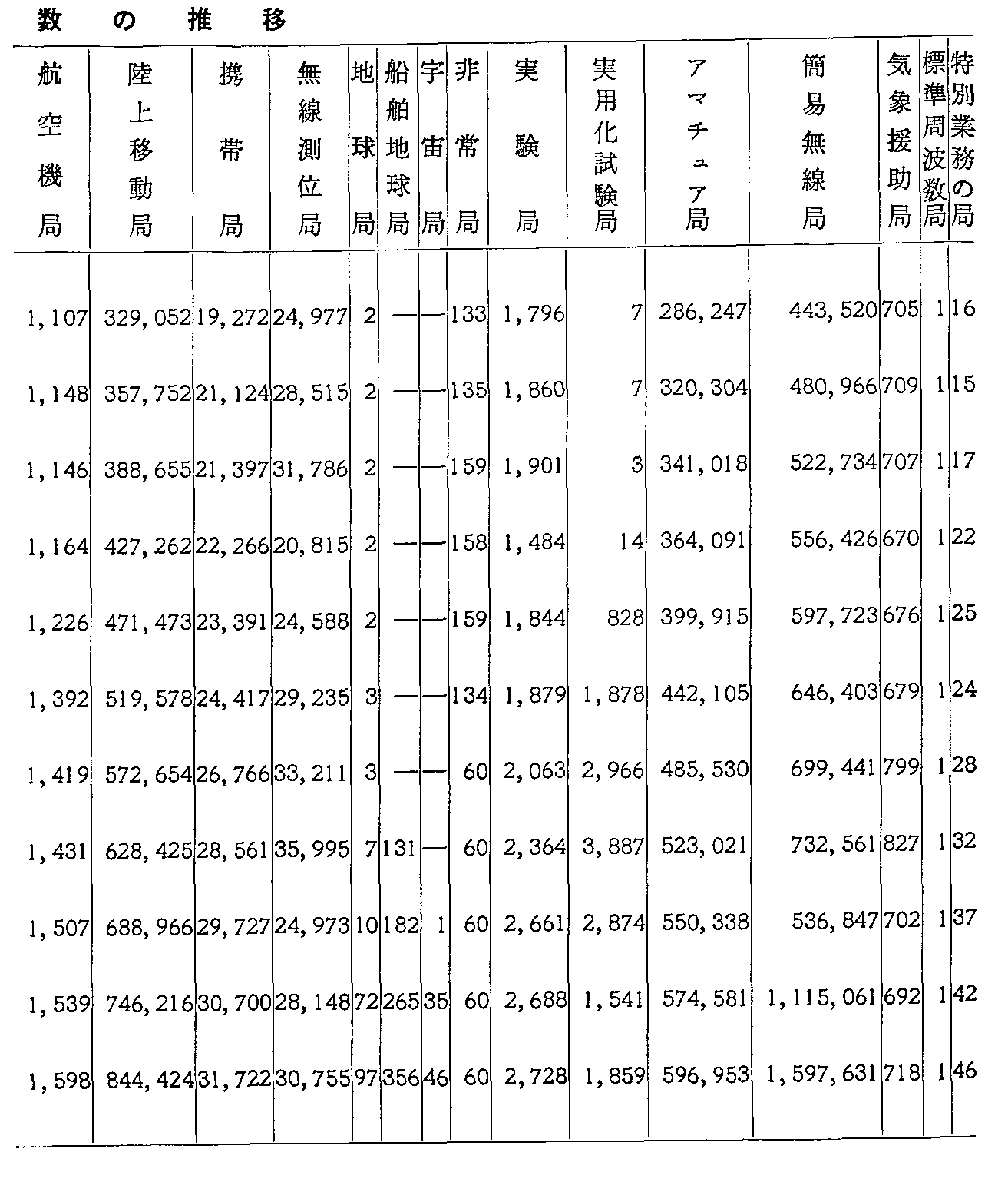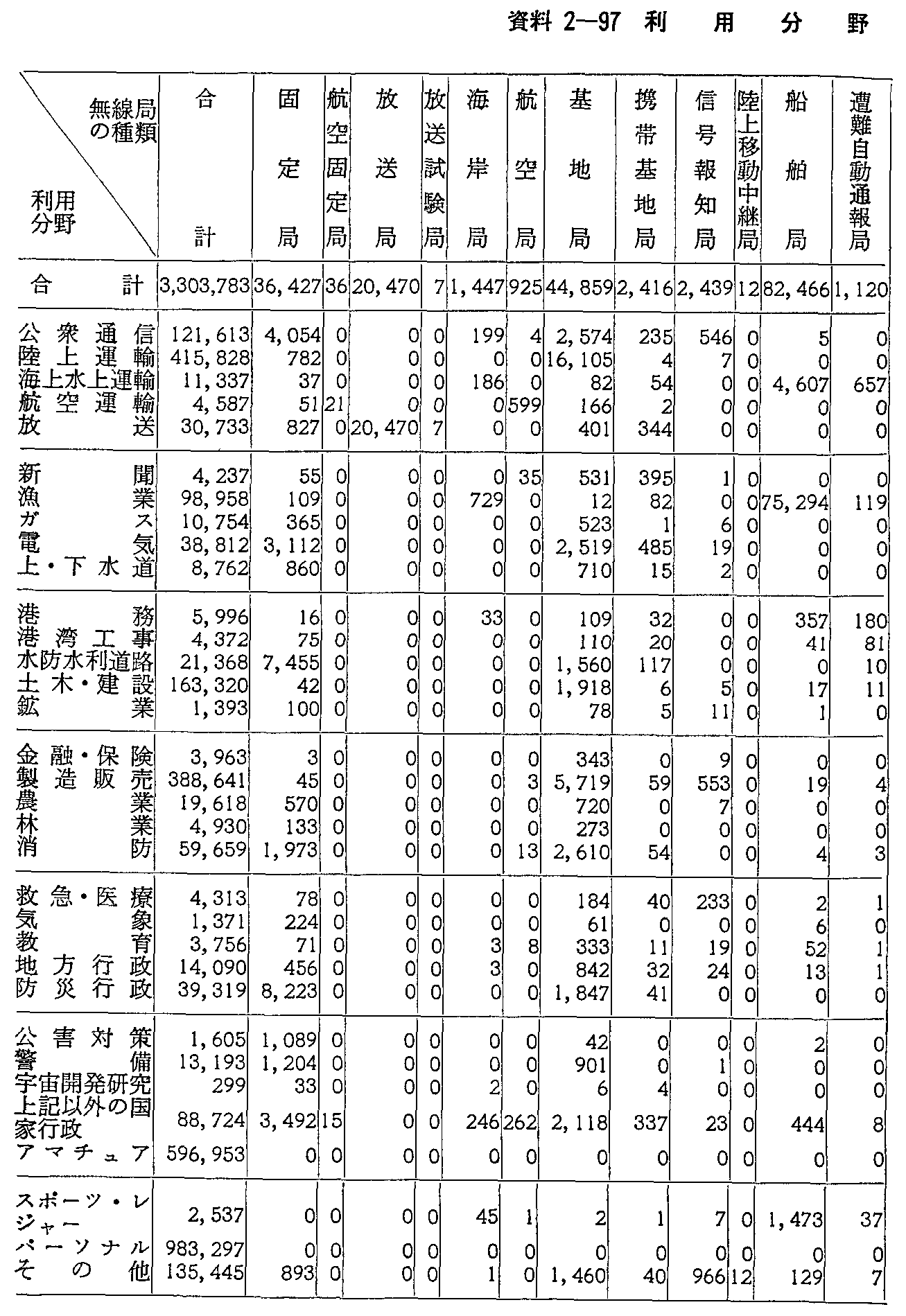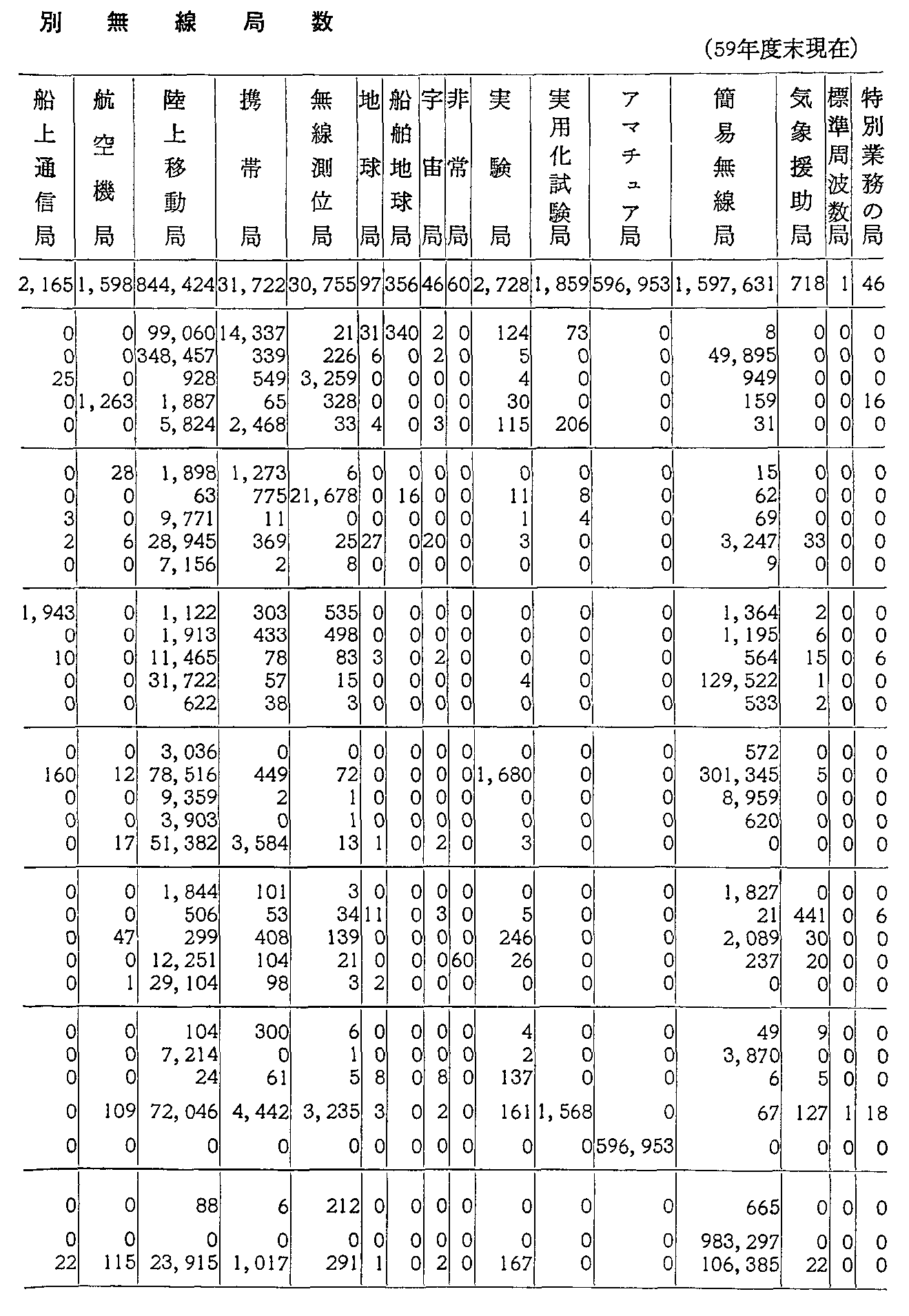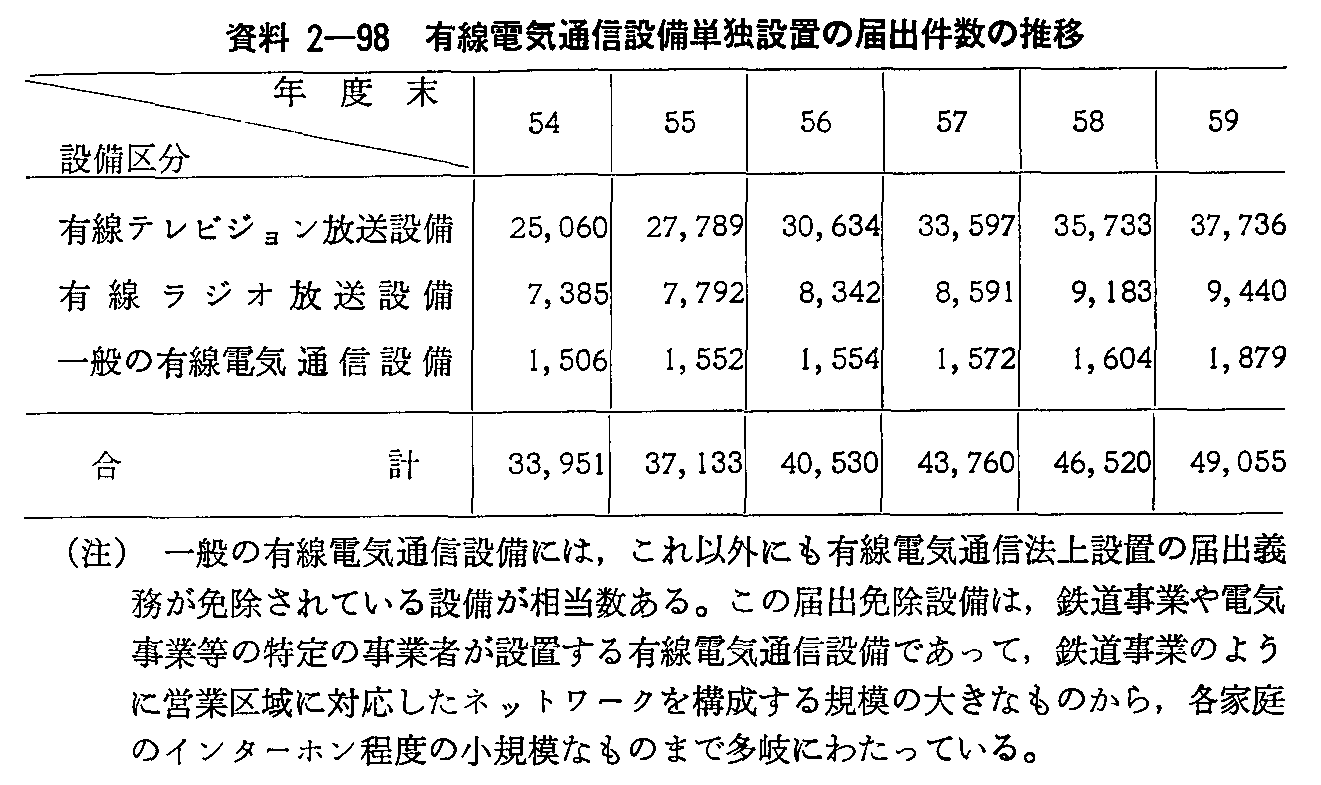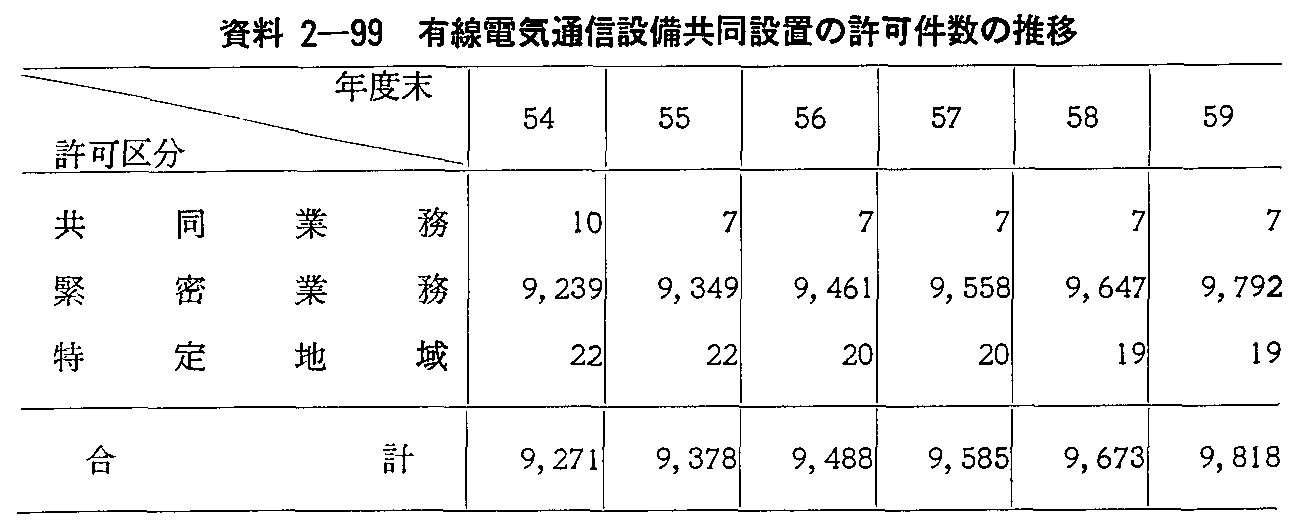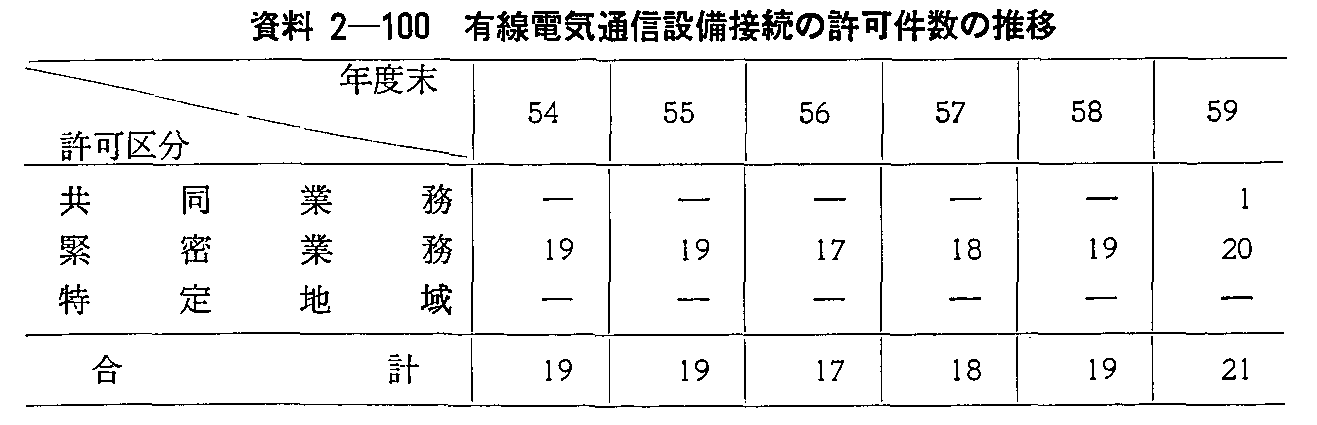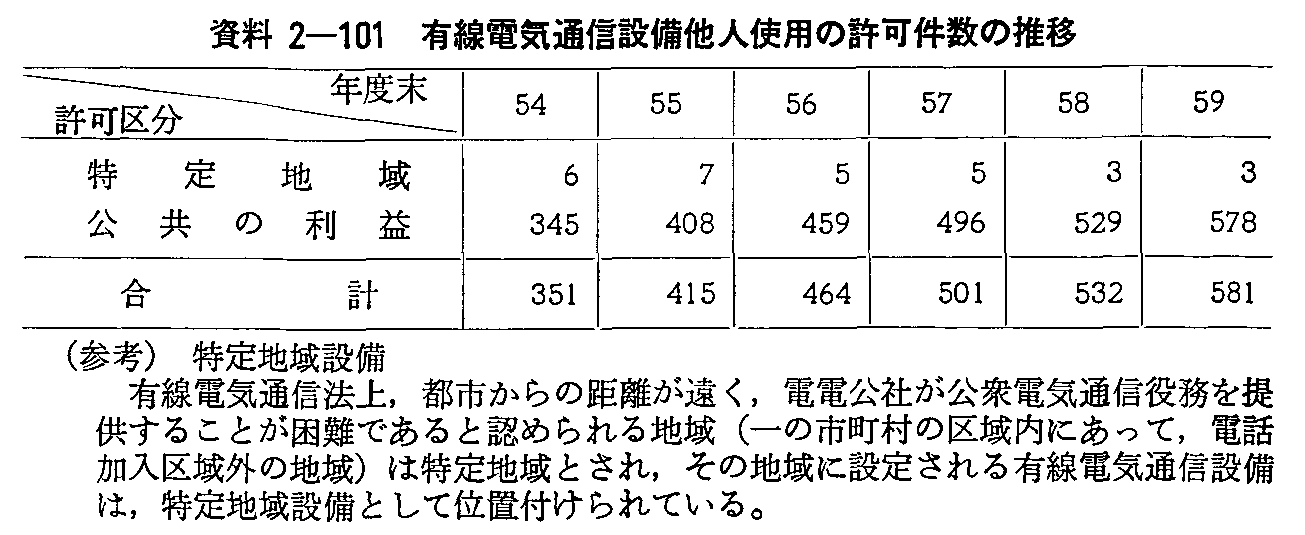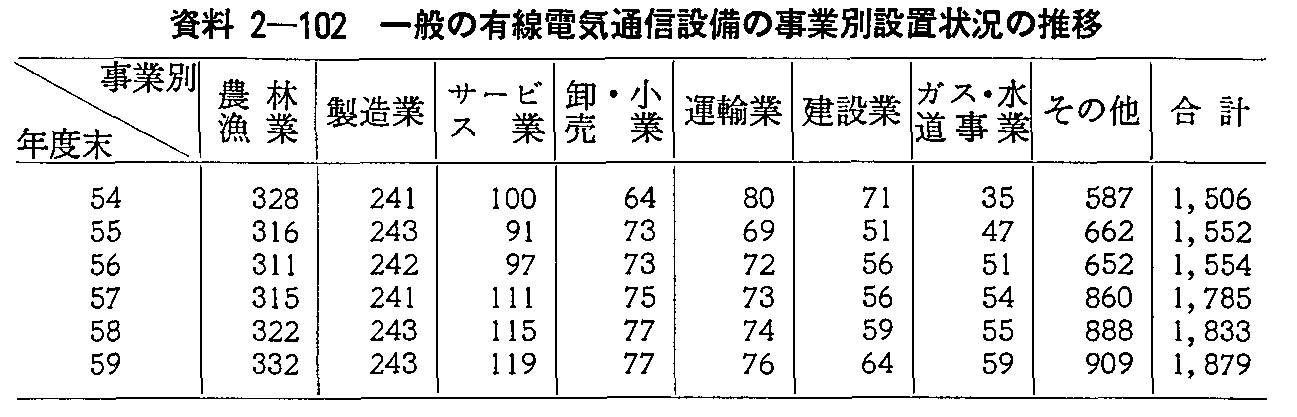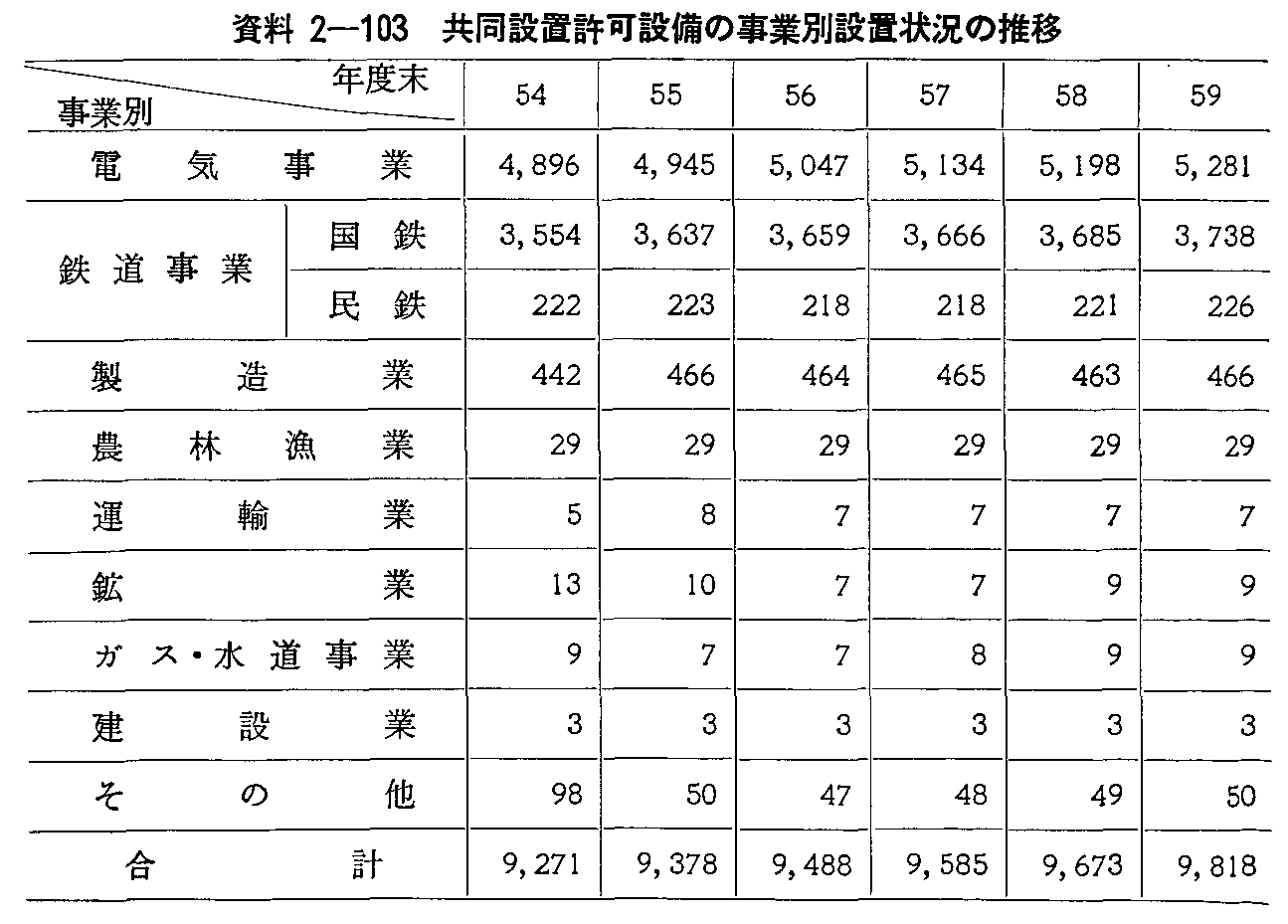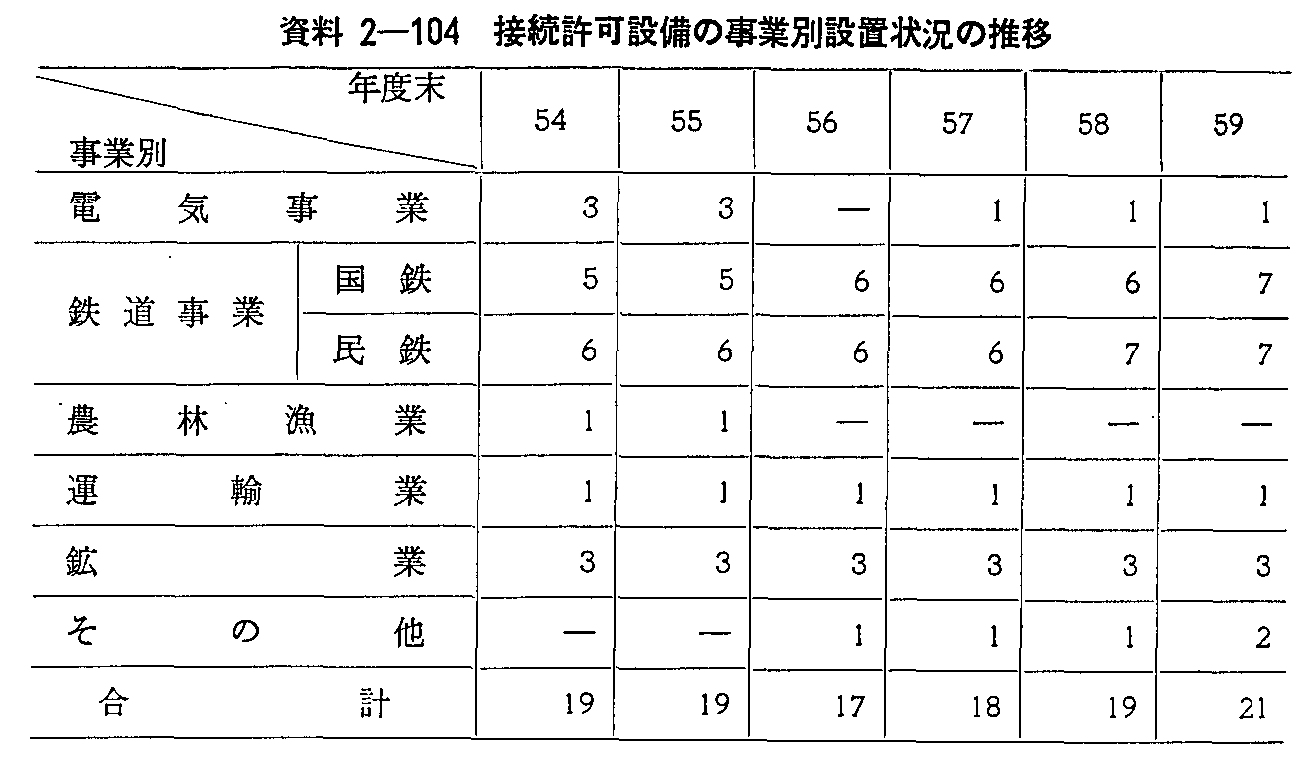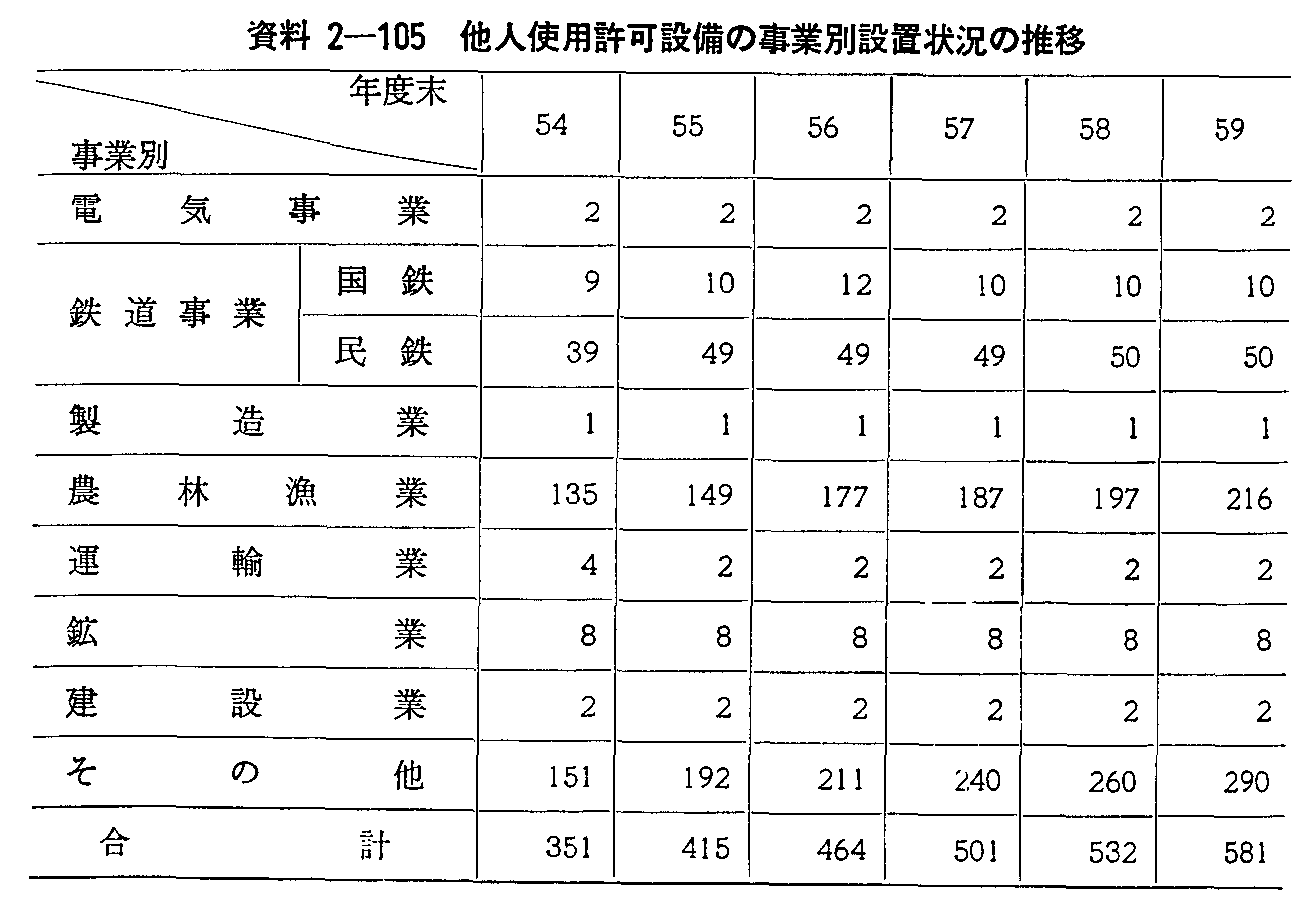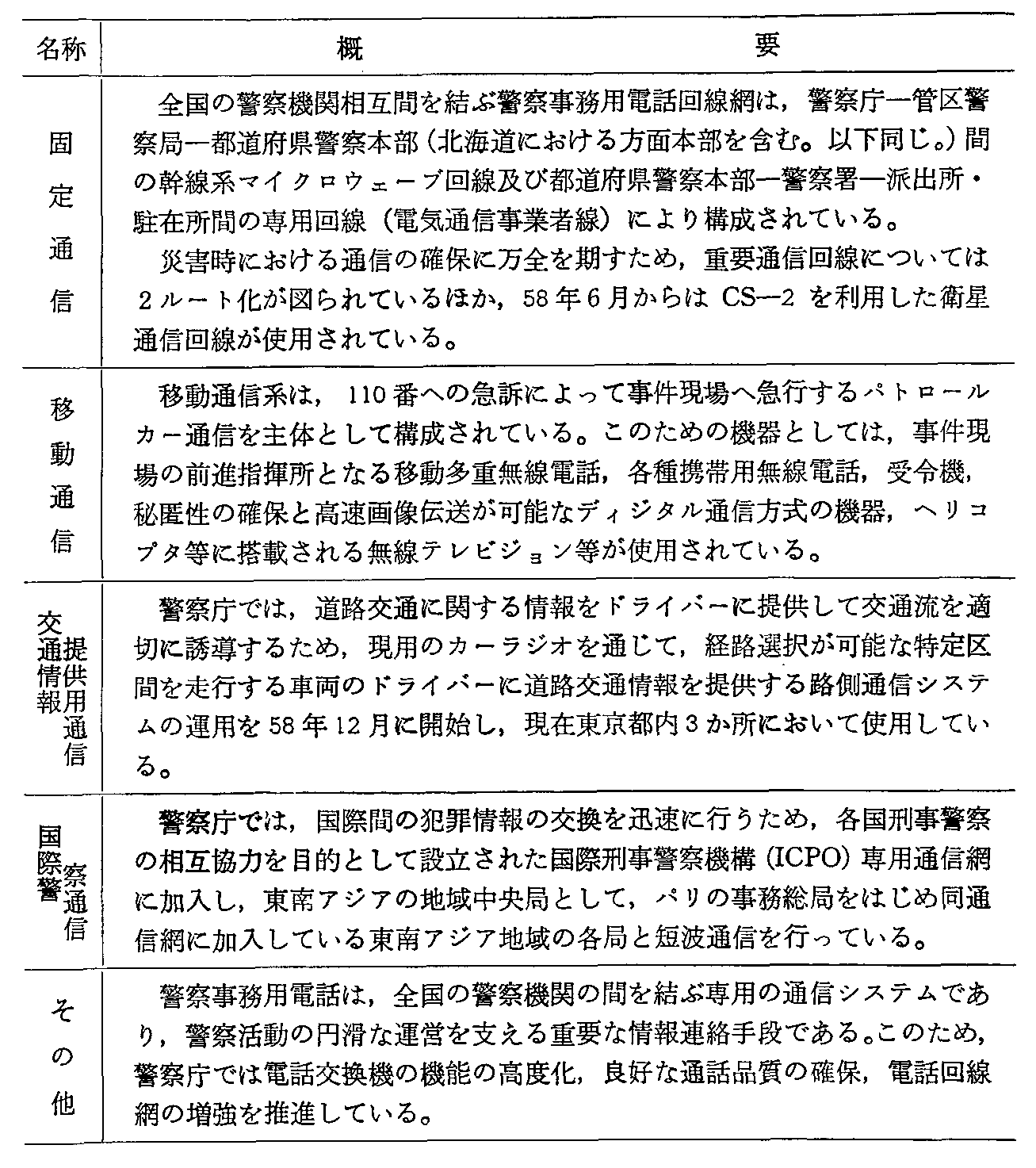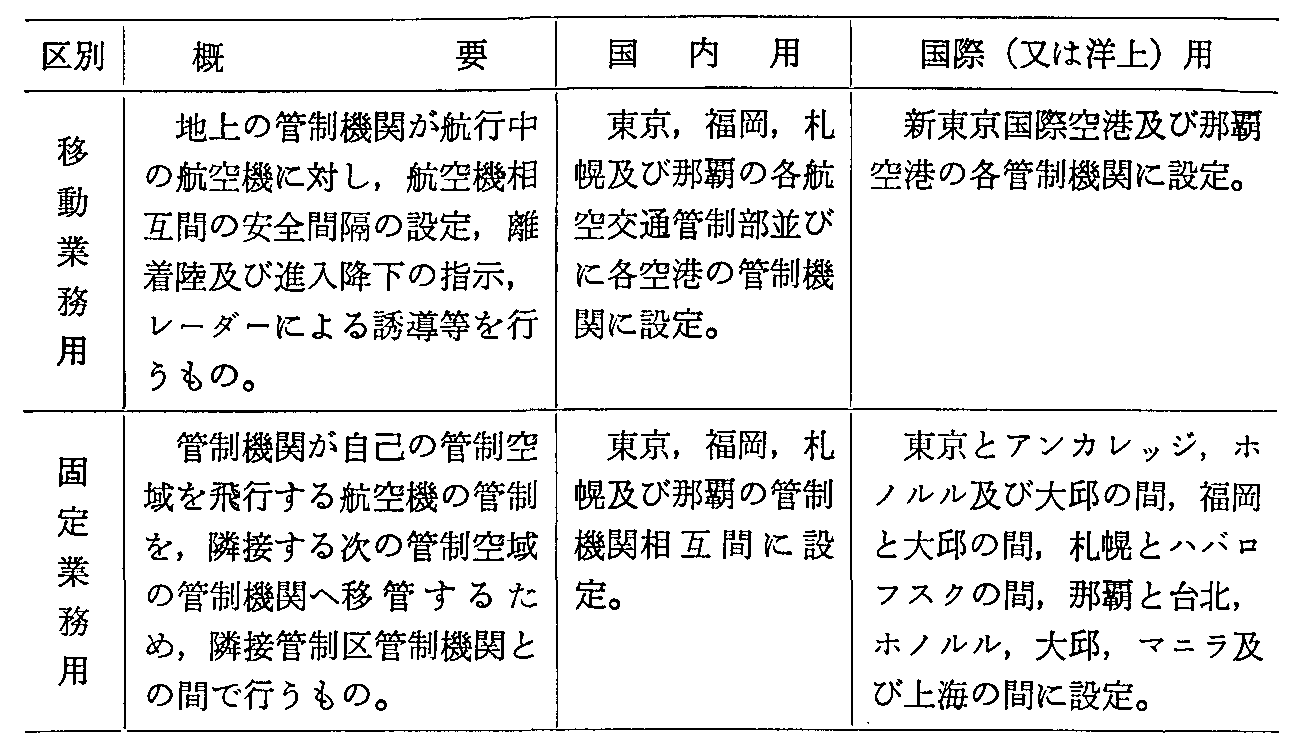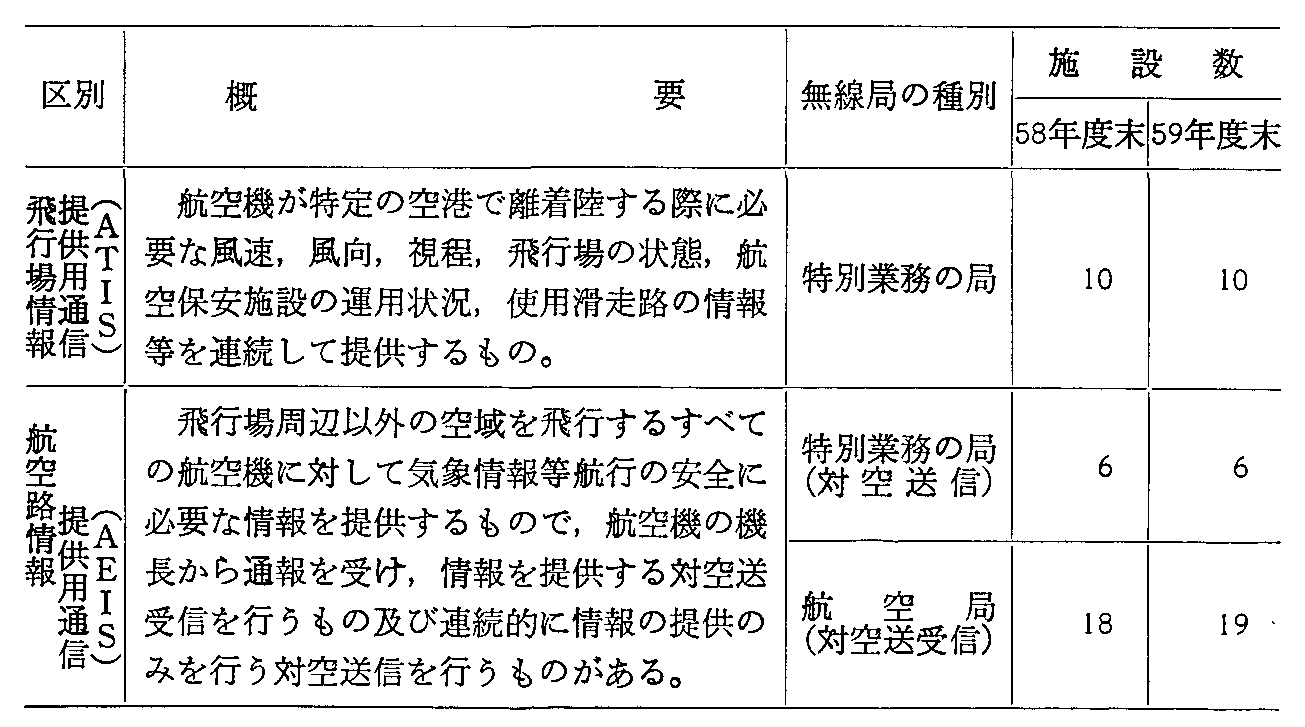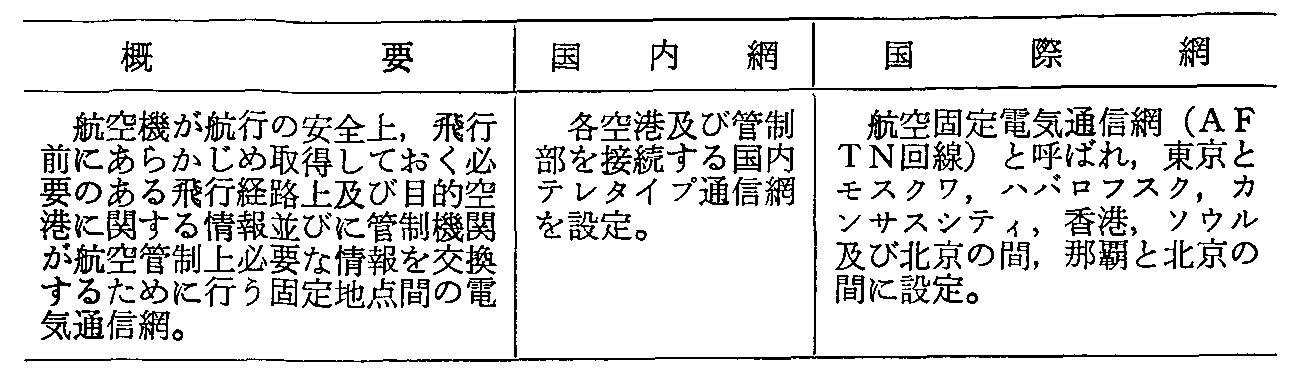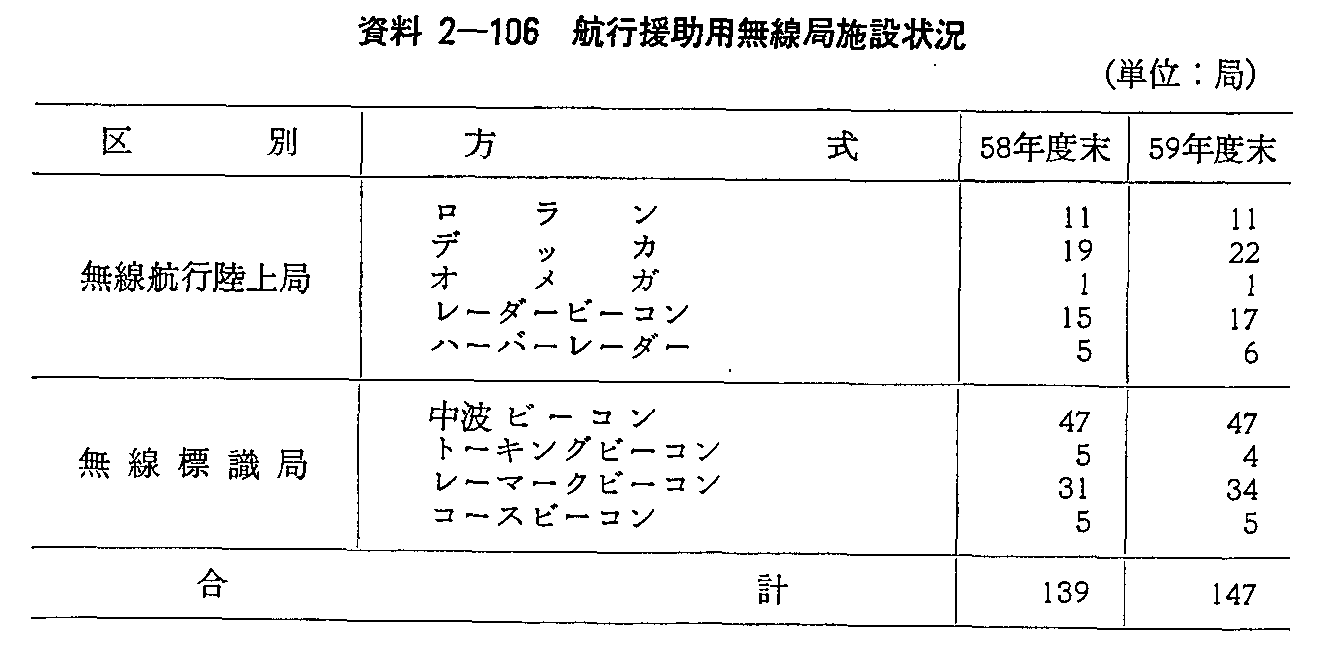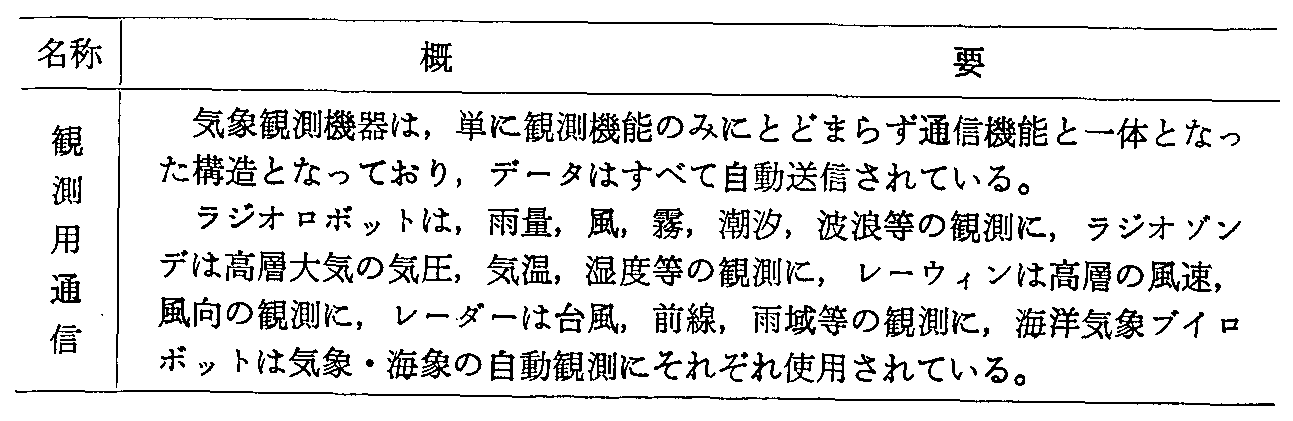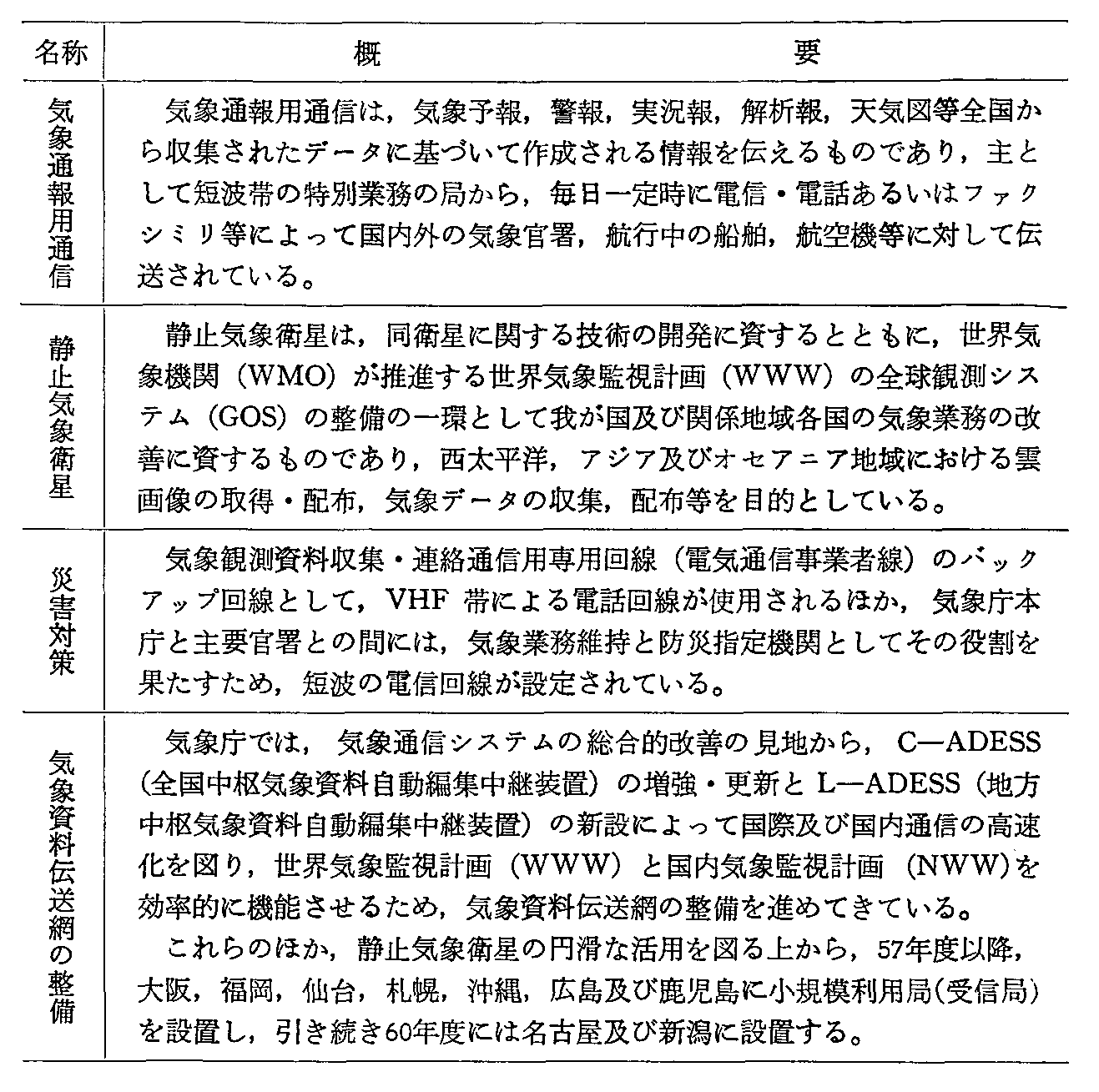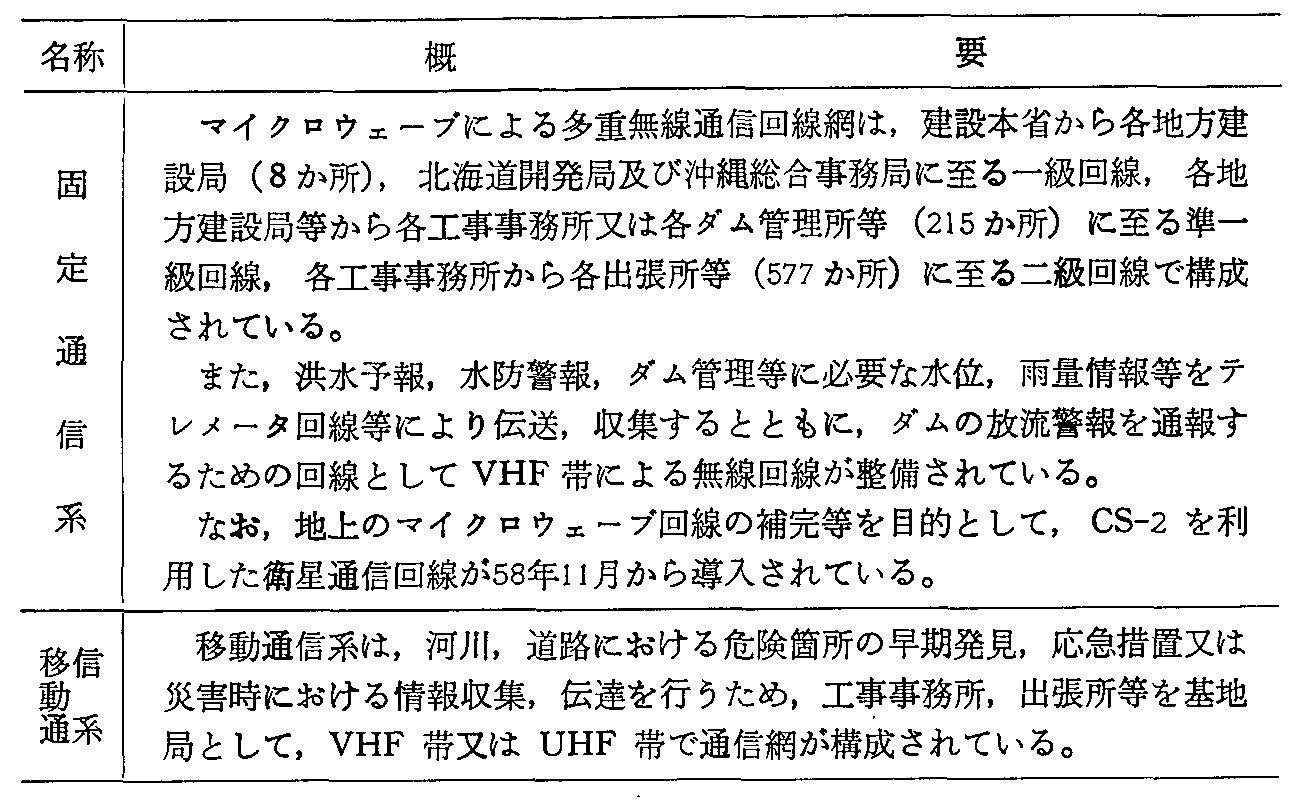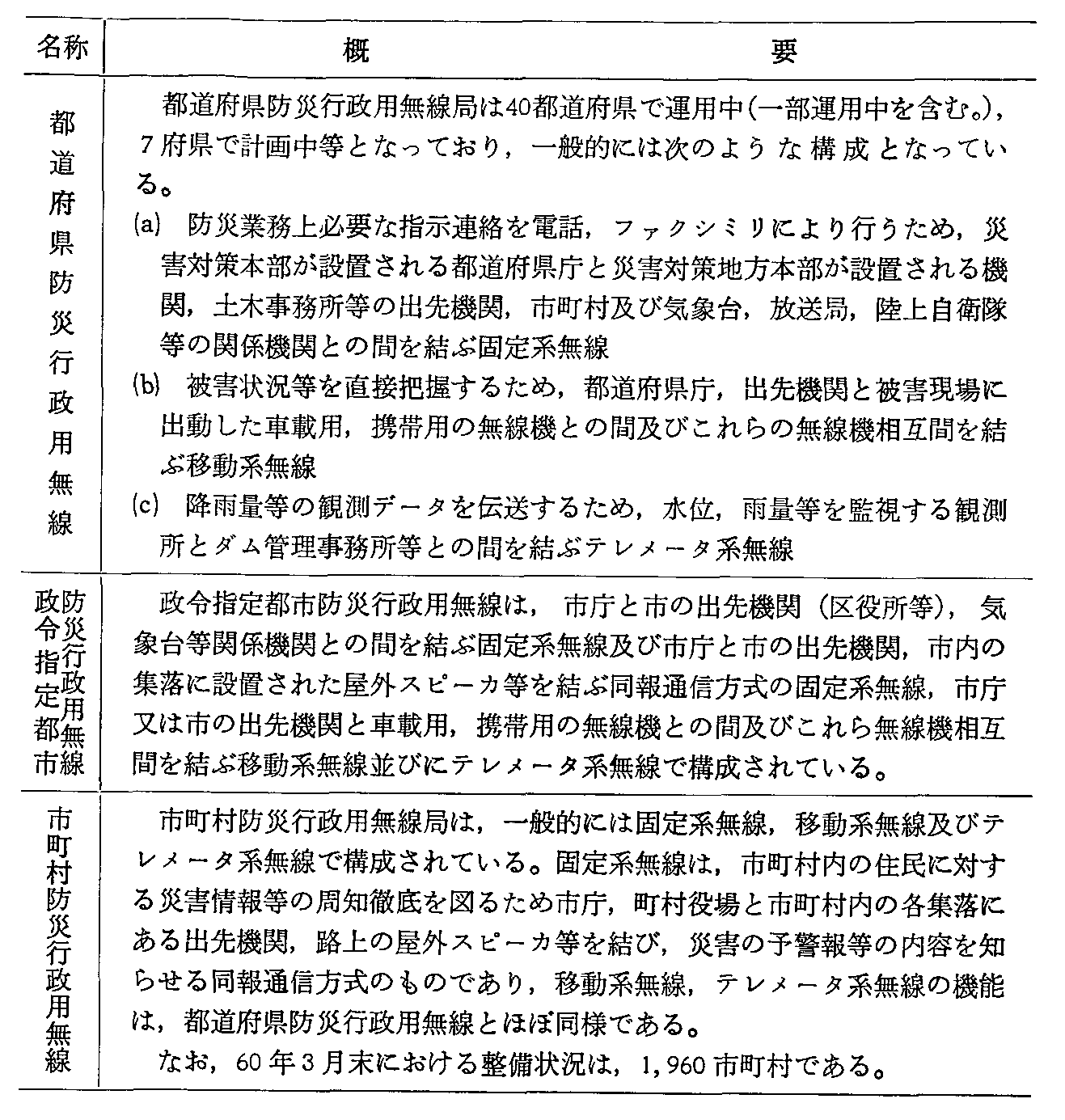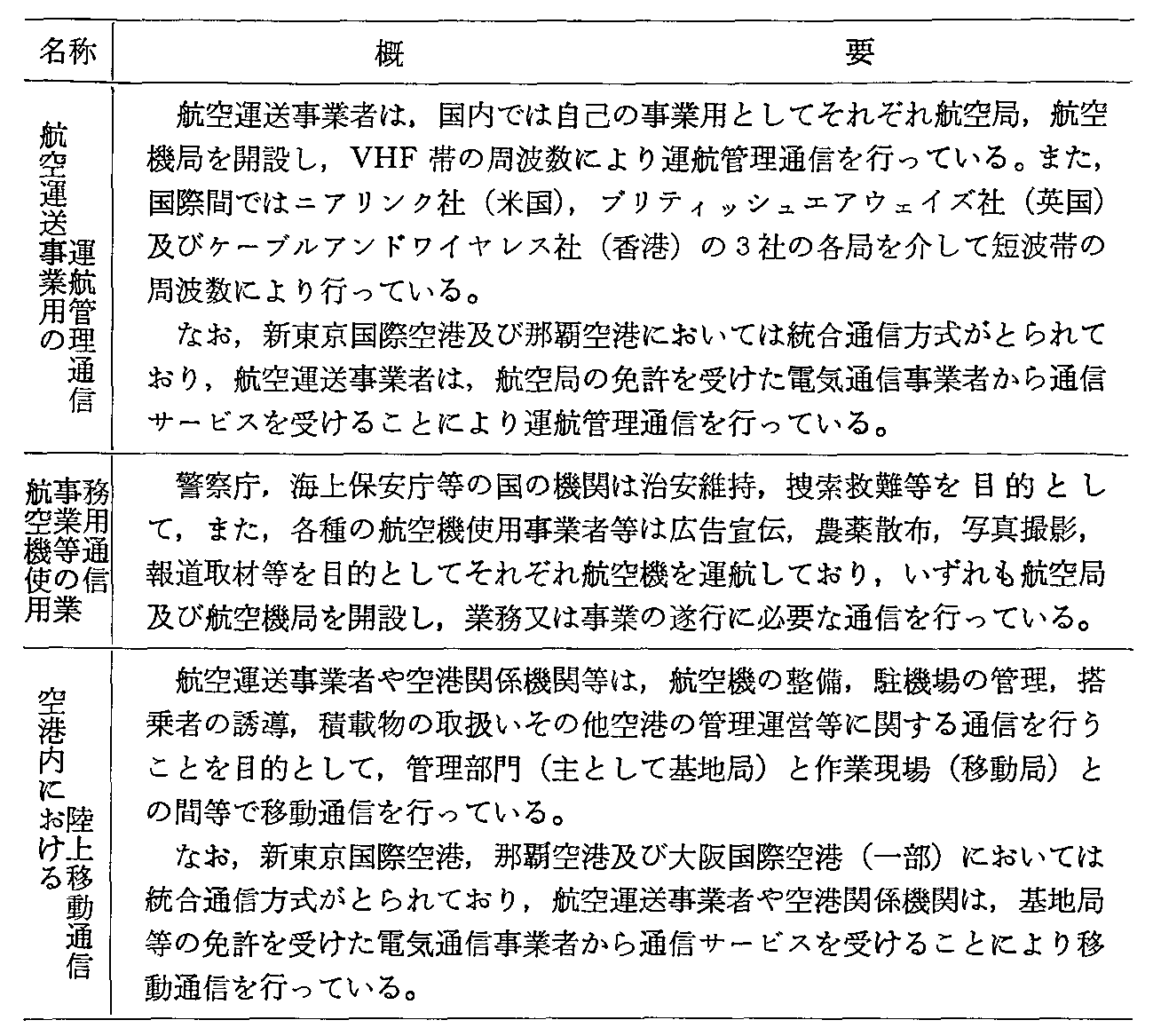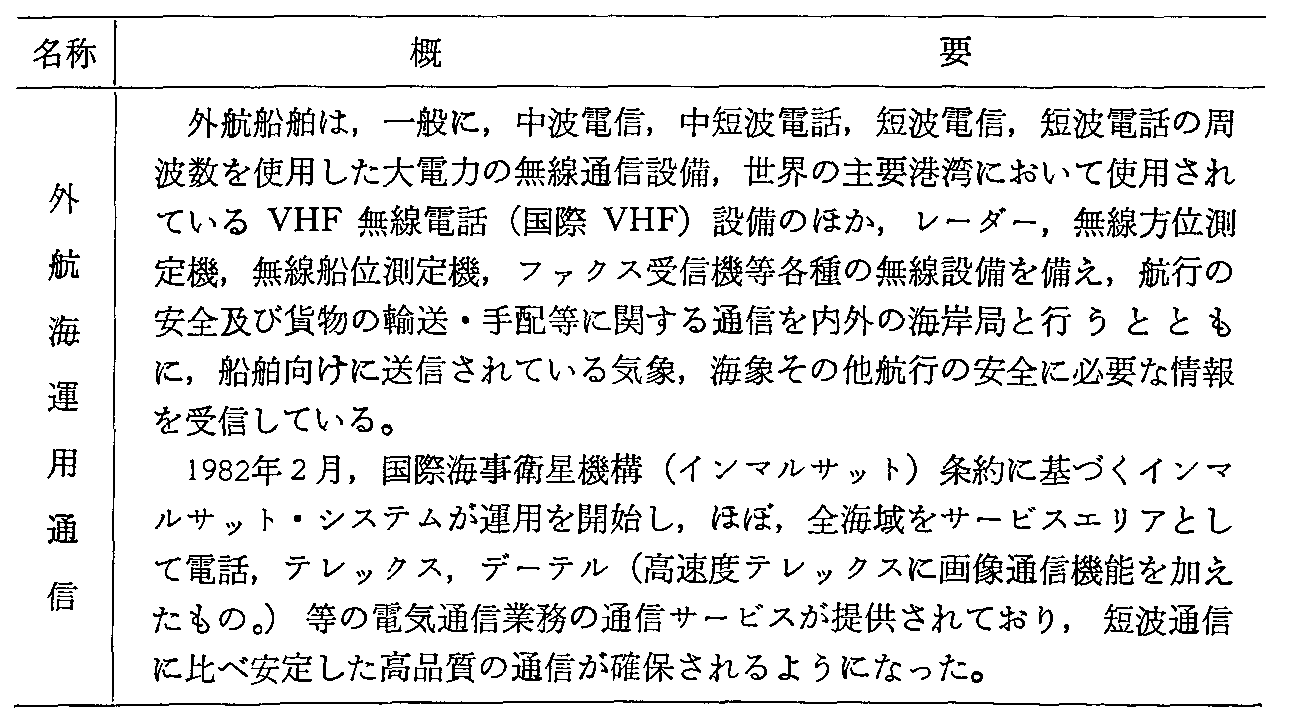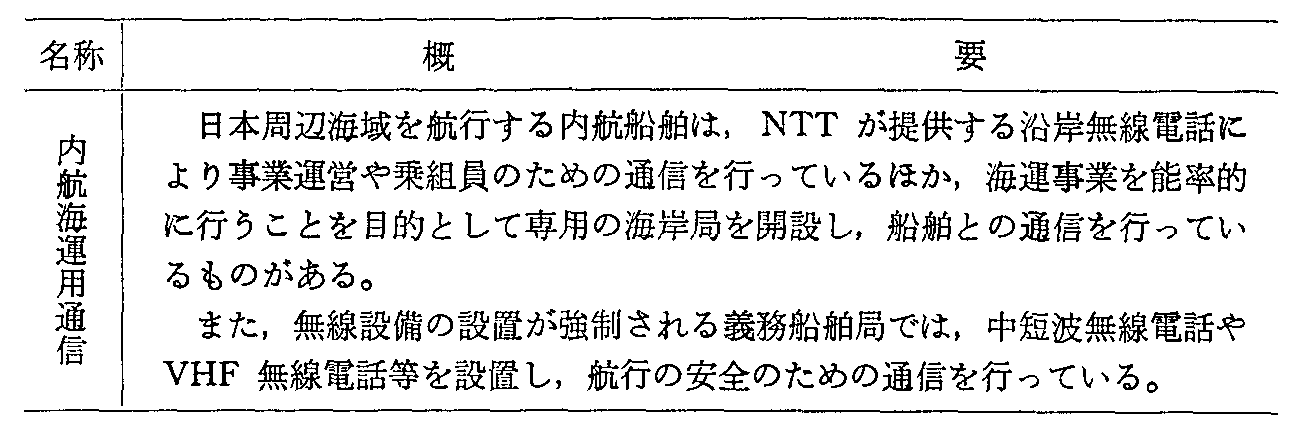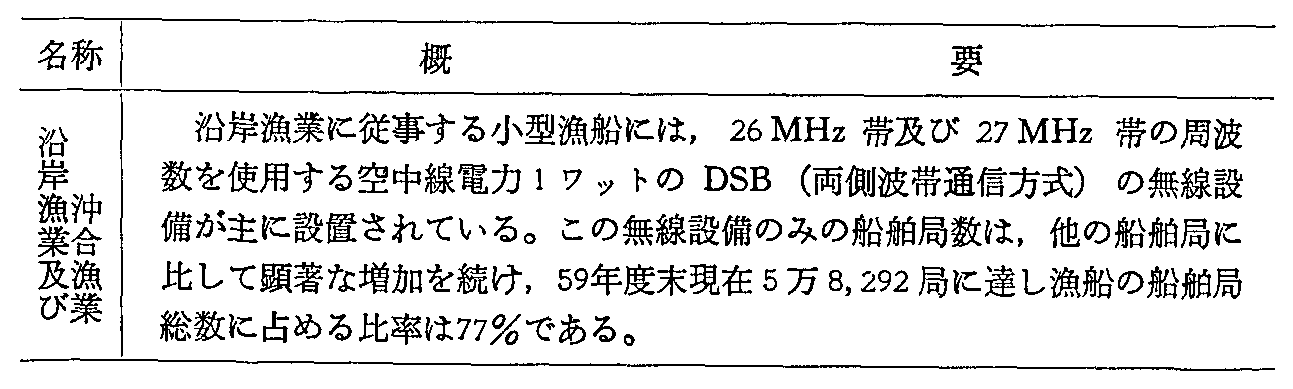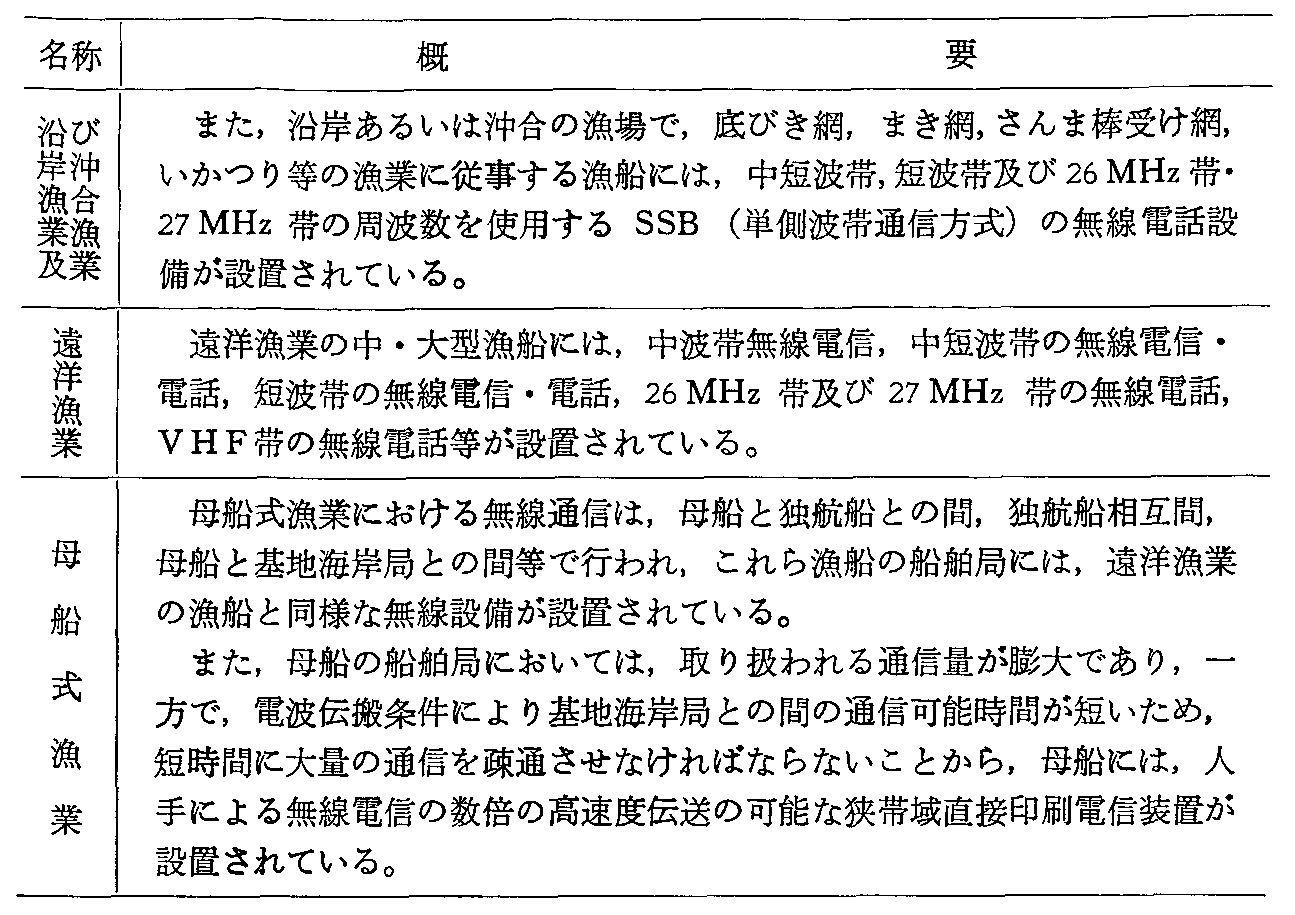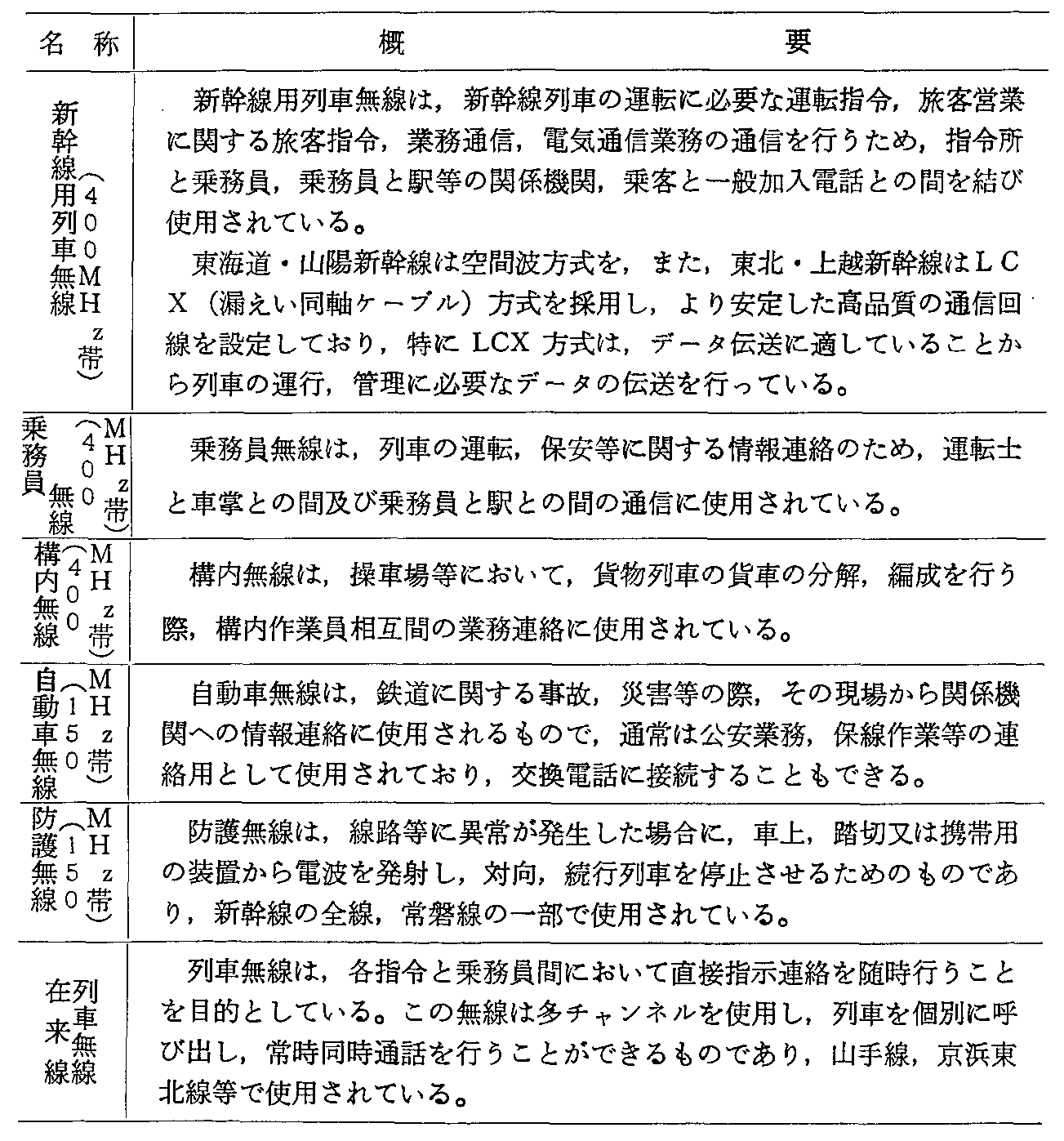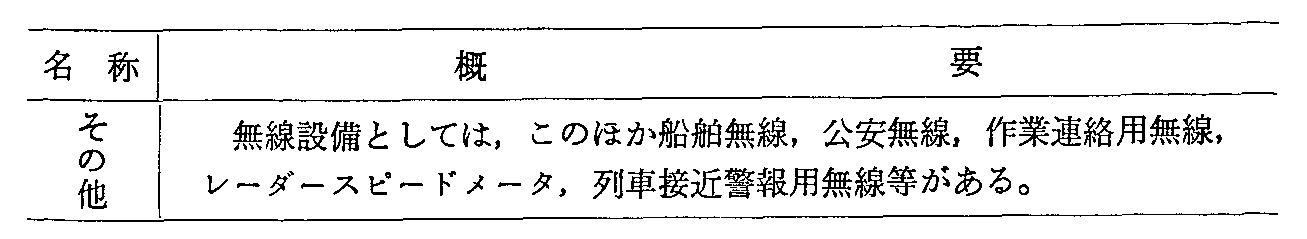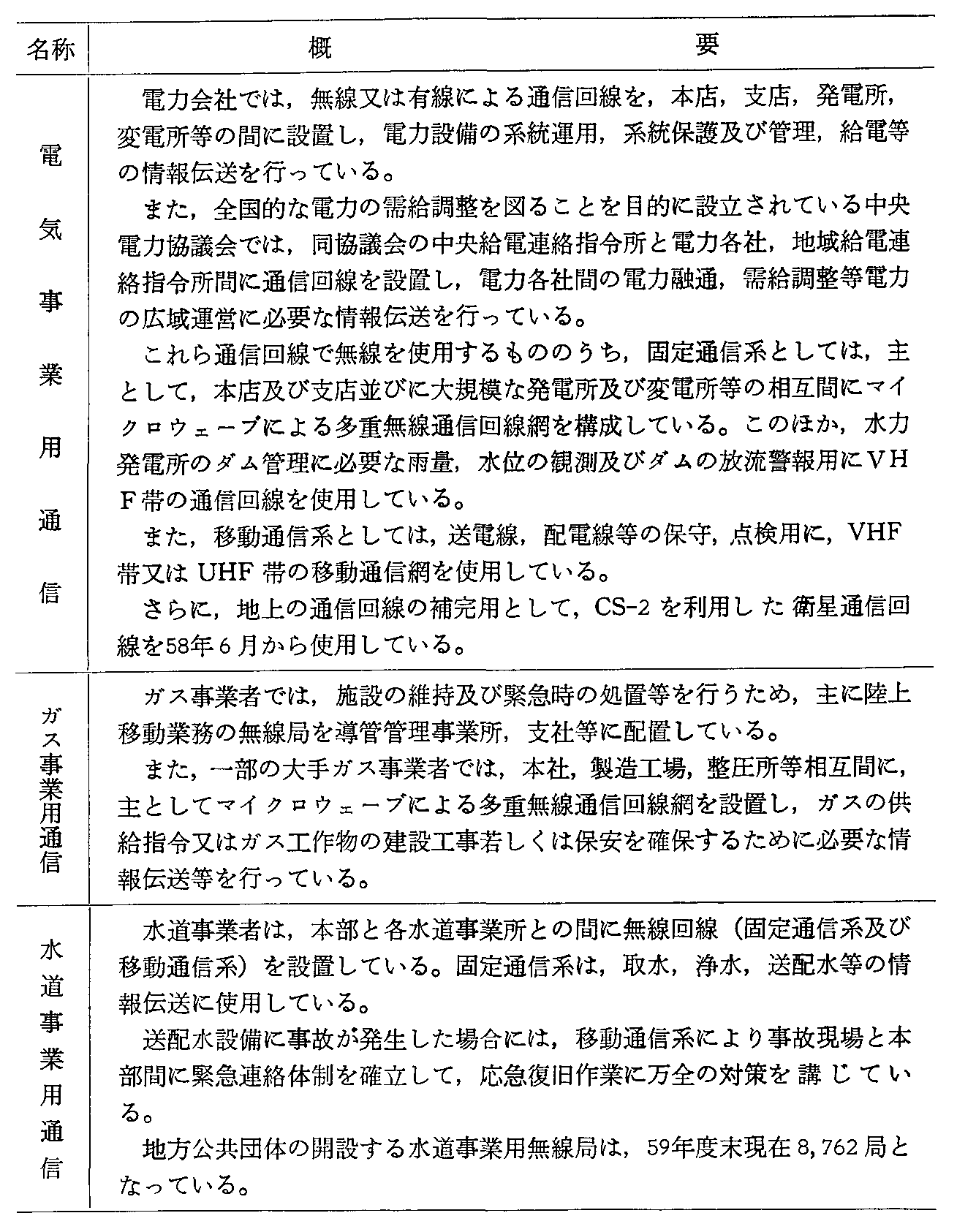3 電気通信
(1)電気通信事業
ア.第一種電気通信事業(データ通信を除く。)
(ア)国内電気通信
A 電報
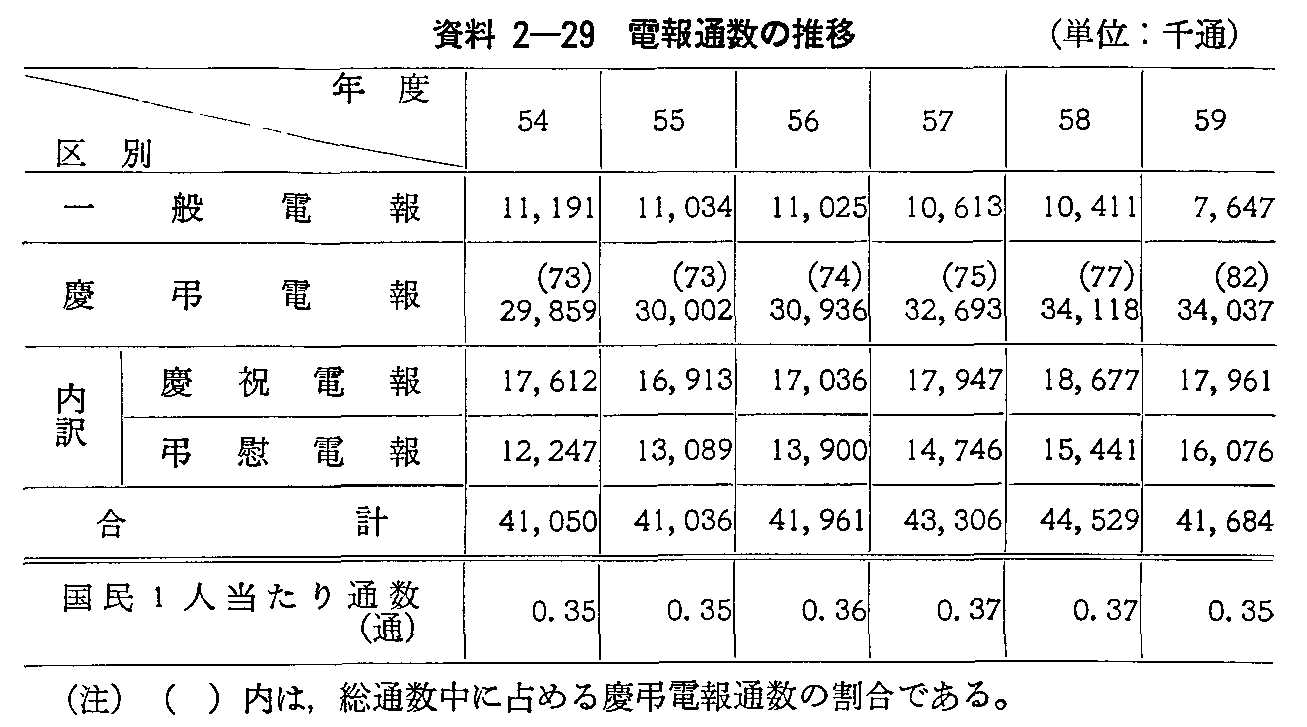
B 加入電信
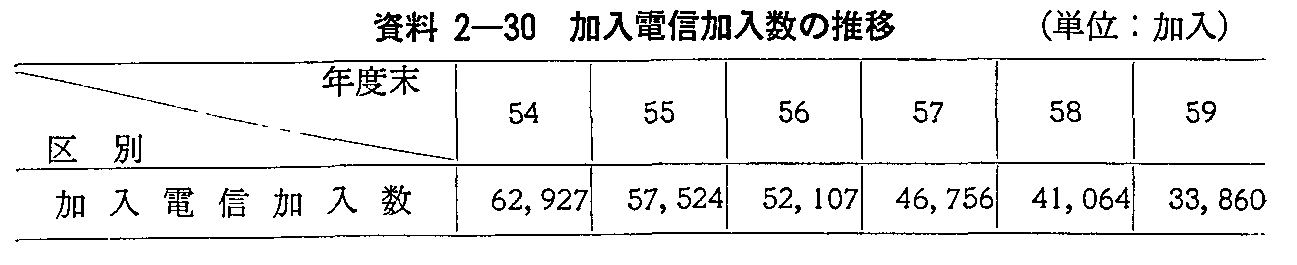
C 電話
電電公社が提供している電話サービスには,加入電話や公衆電話が代表的なものであるが,このほか移動体電話や着信用電話,内部通話用電話,支店代行電話及び緊急通報用電話等がある。
(A)加入電話
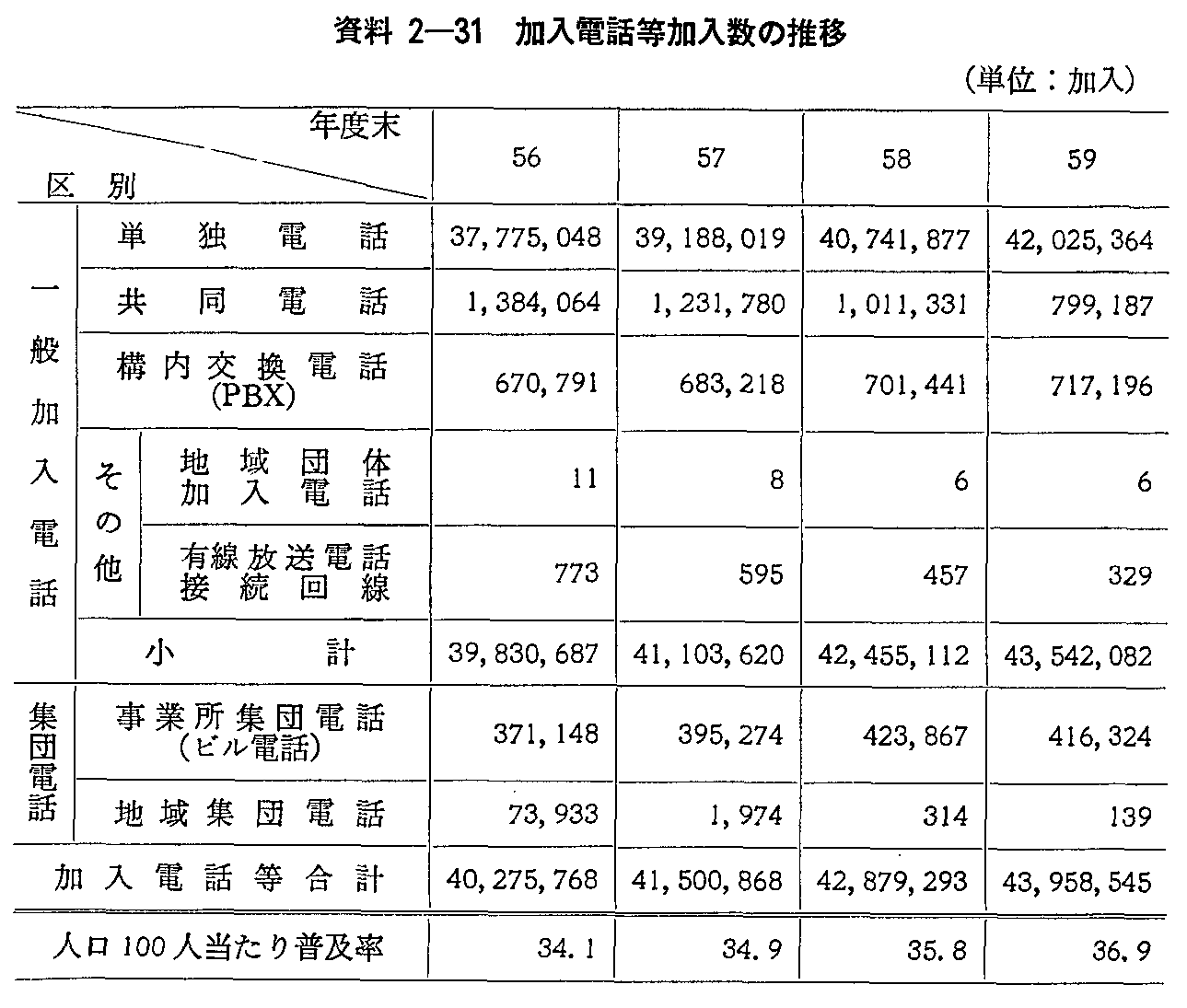
(B)公衆電話
公衆電話には,電電公社直営で電話ボックス等に設置されている街頭公衆電話と,商店等の通話の取扱いを委託している店頭公衆電話(赤電話)がある。
利用者の利便の向上を図るため,100円硬貨も使用して通話できる公衆電話や磁気カード(テレホンカード)を使用できる公衆電話の増設が進められている。
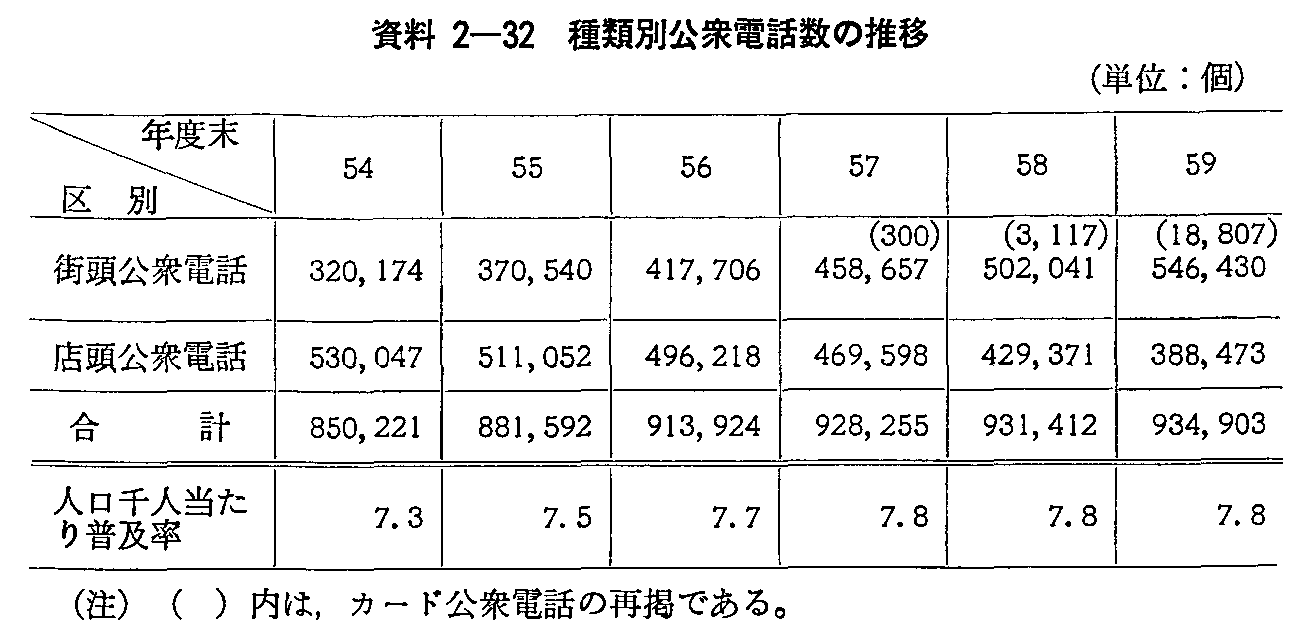
(C)移動通信
無線を利用した移動通信には,自動車電話,ポケットベル,船舶電話のほか,新幹線に設置されている列車公衆電話等がある。
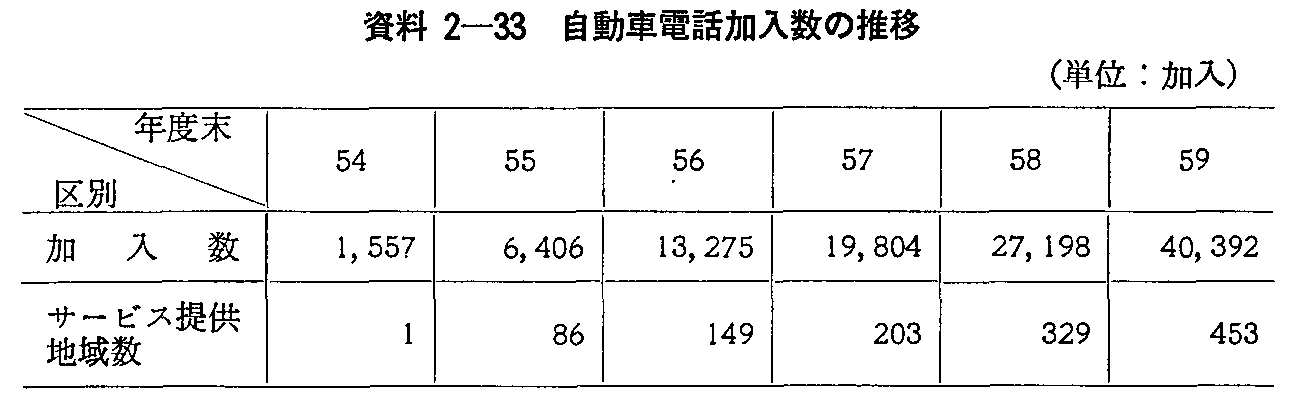
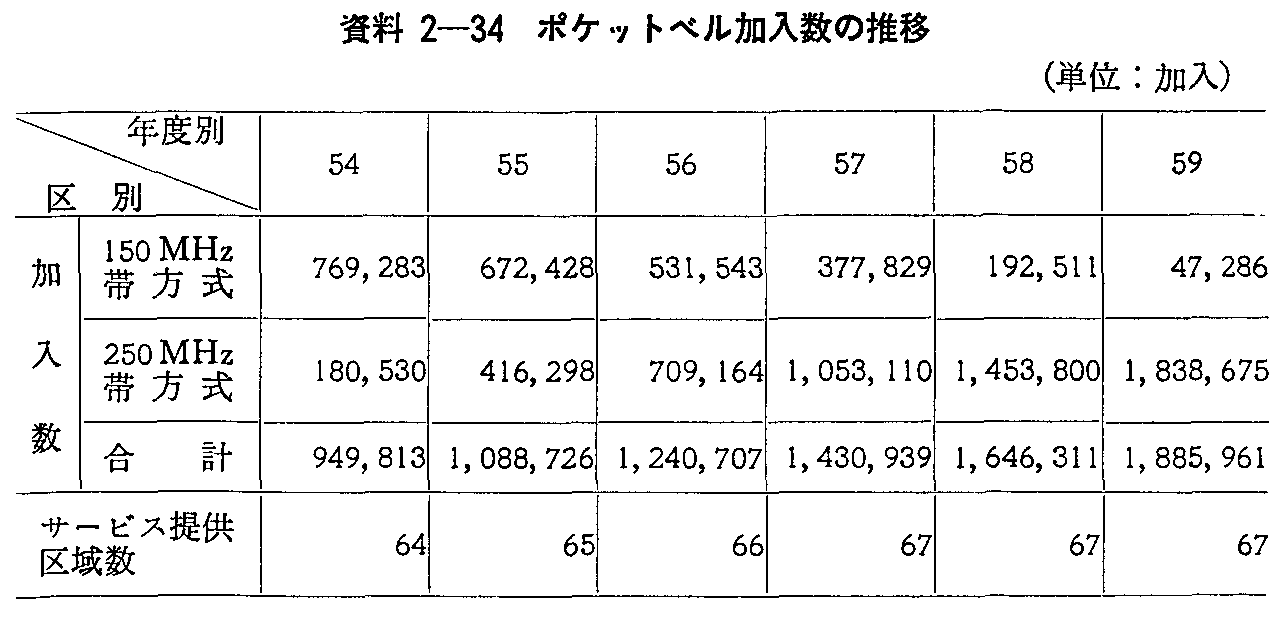
(D)各種付加機能サービス
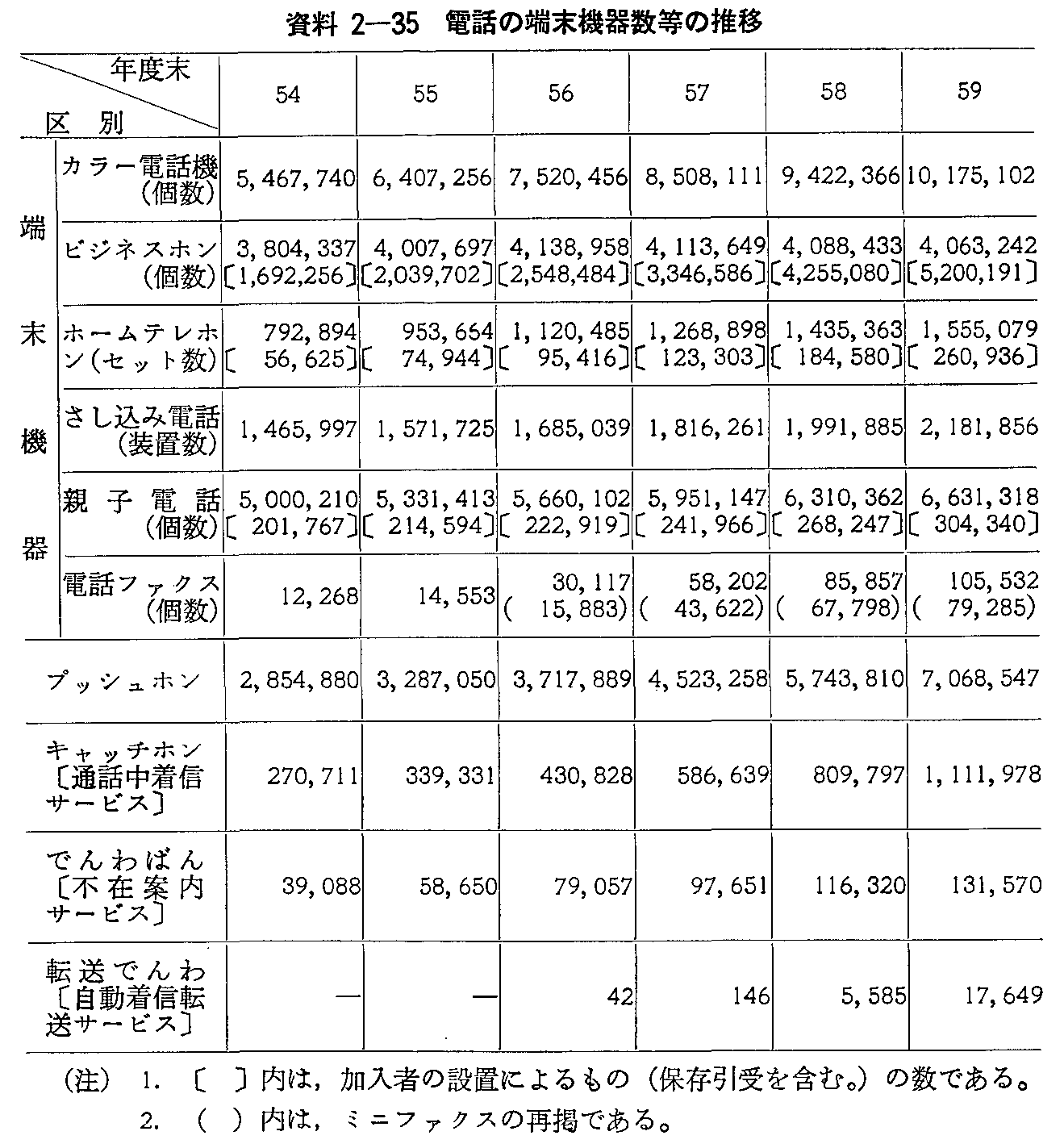
D 専用サービス
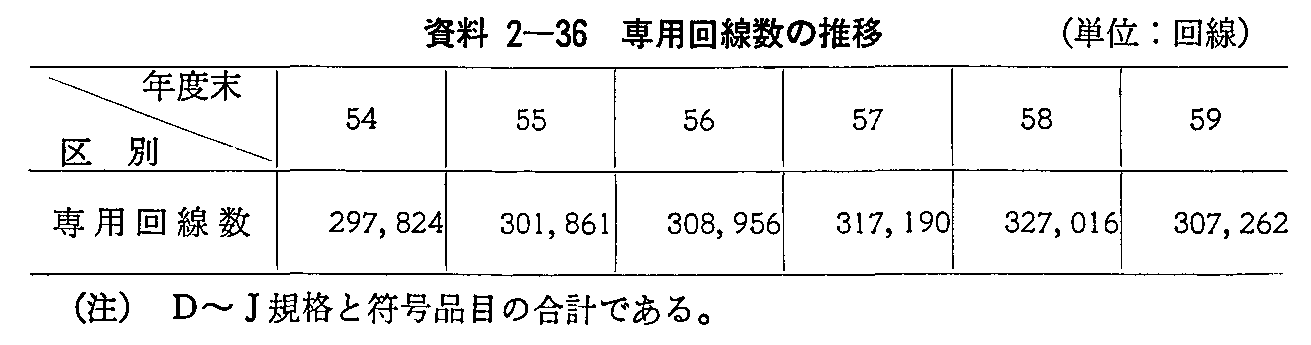
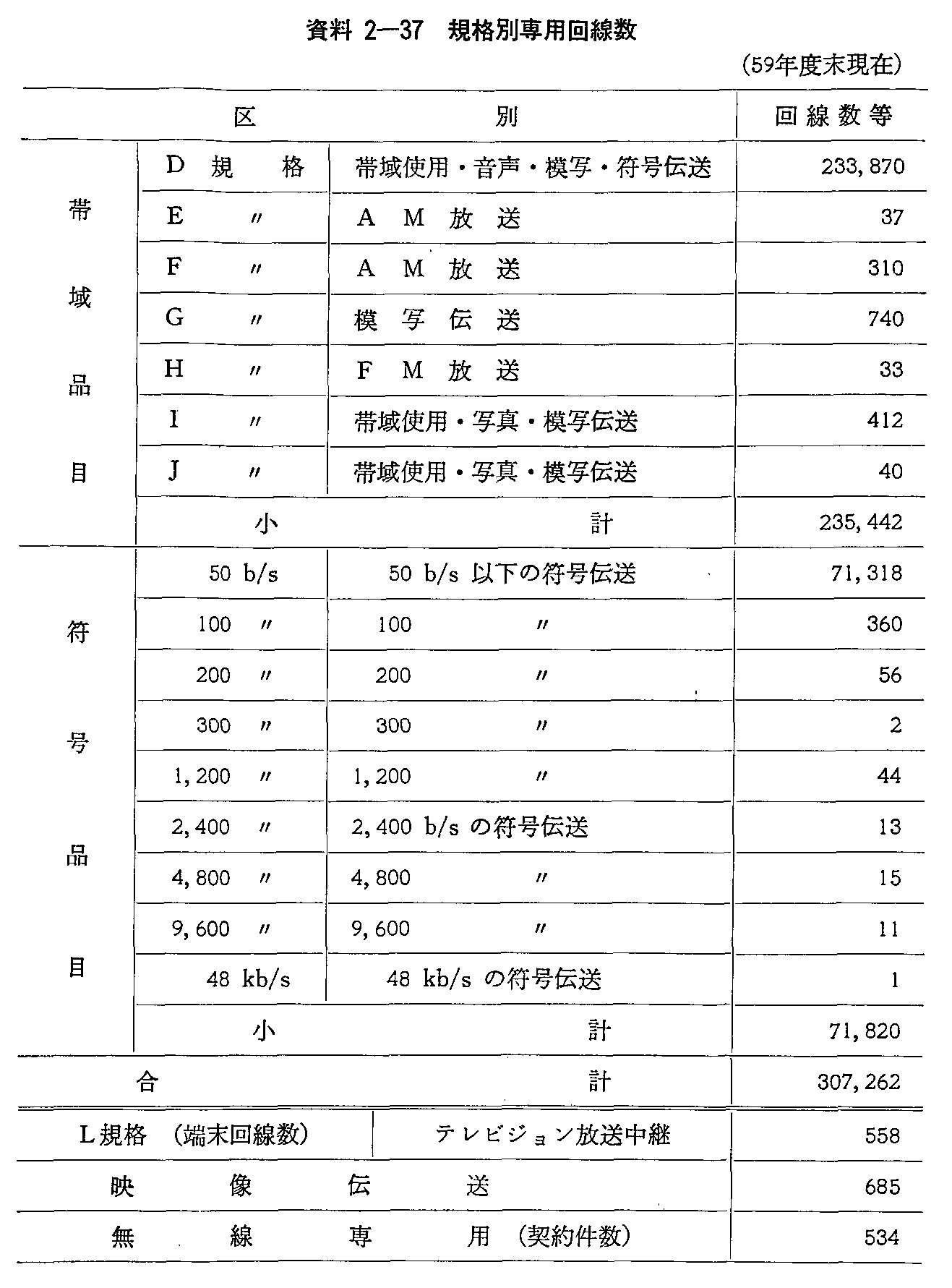
E ファクシミリ
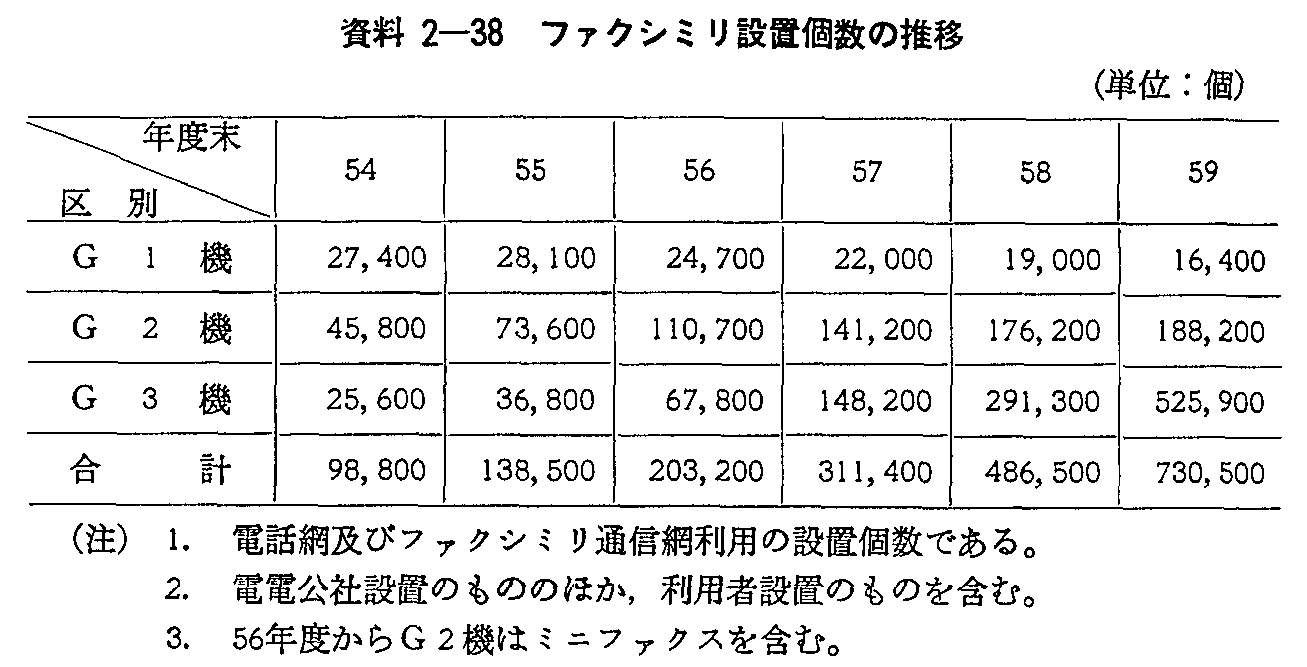
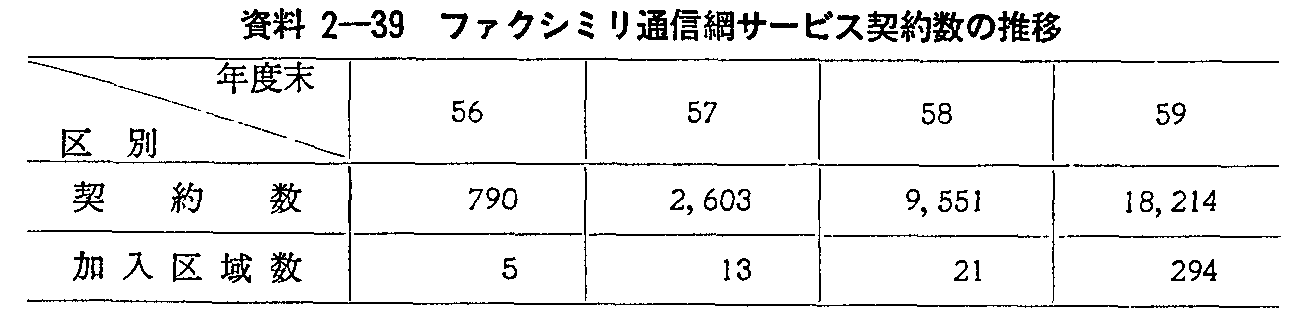
(イ)国際電気通信
A 国際電報
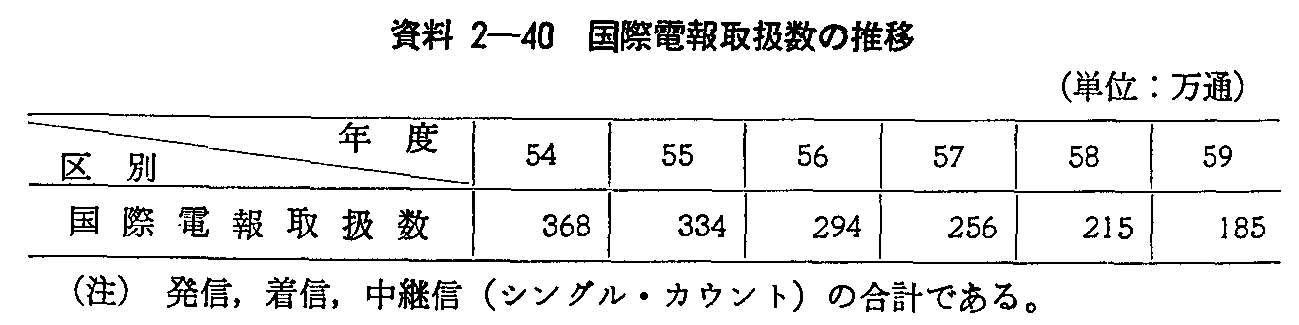
B 国際テレックス
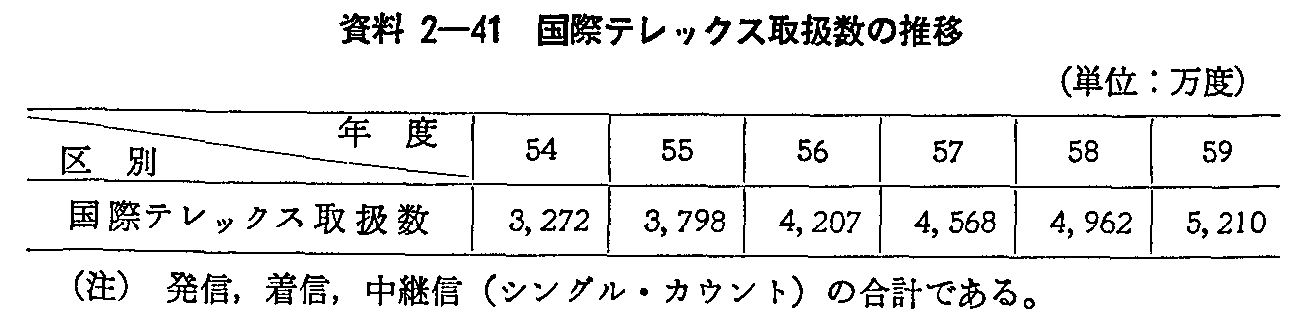
C 国際電話
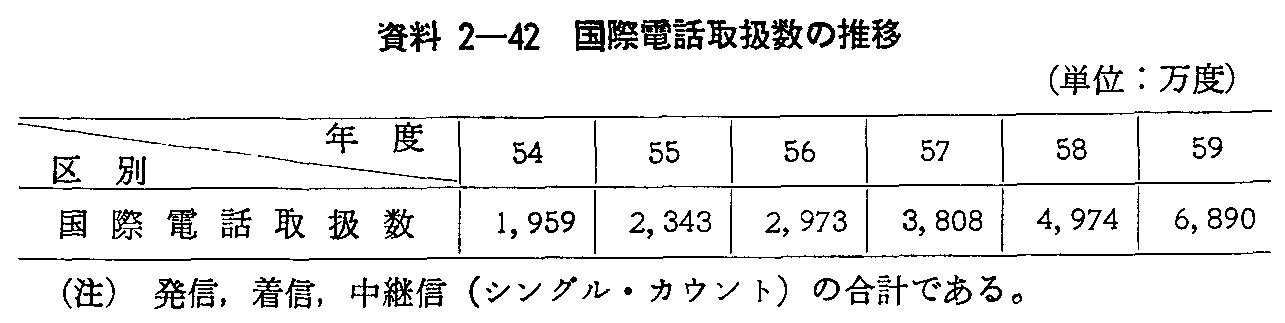
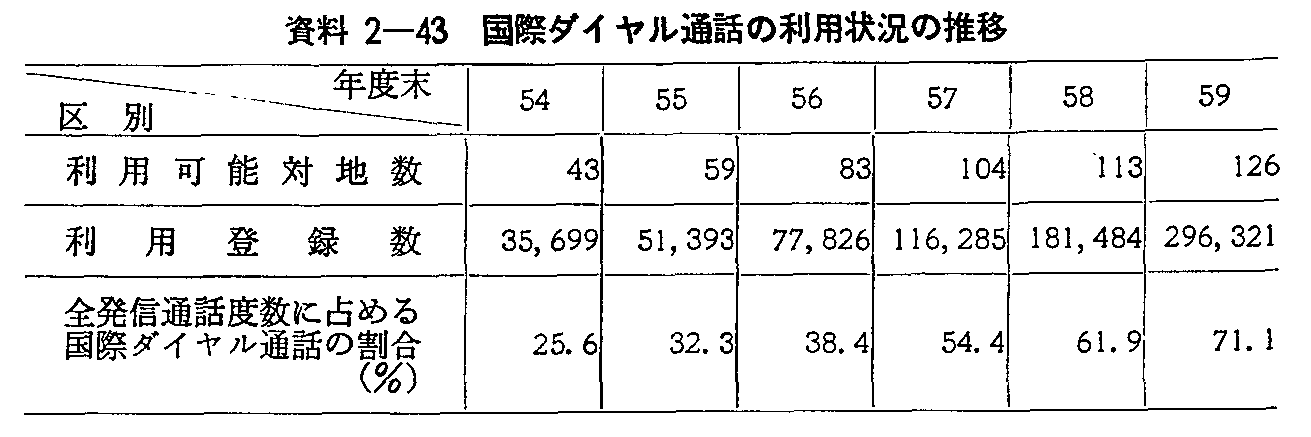
D 国際専用回線
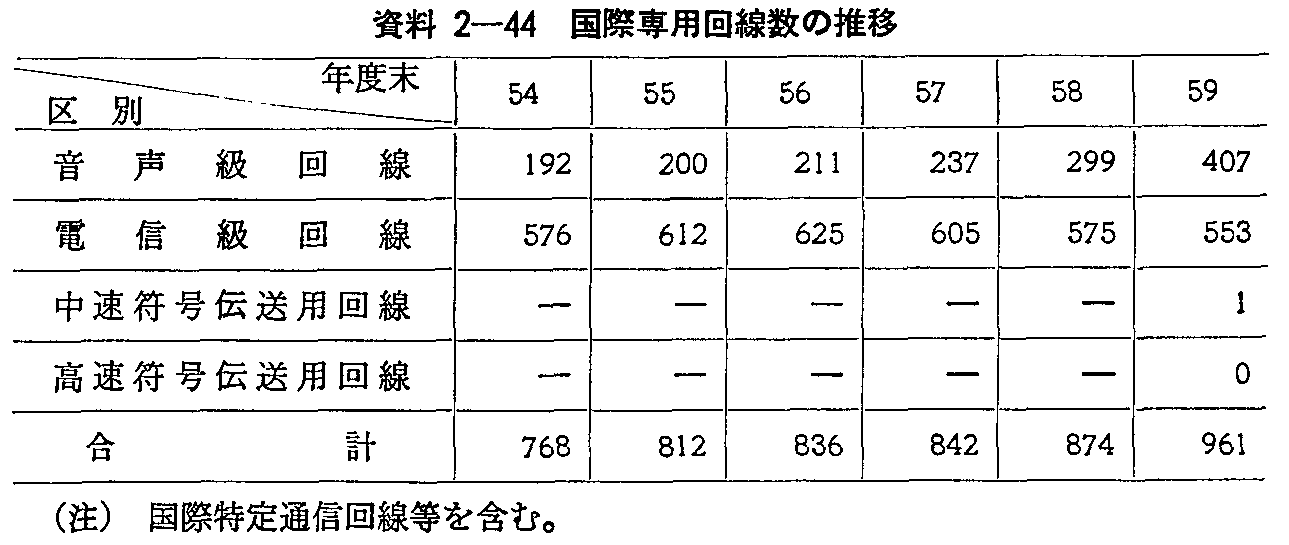
E 国際テレビジョン伝送
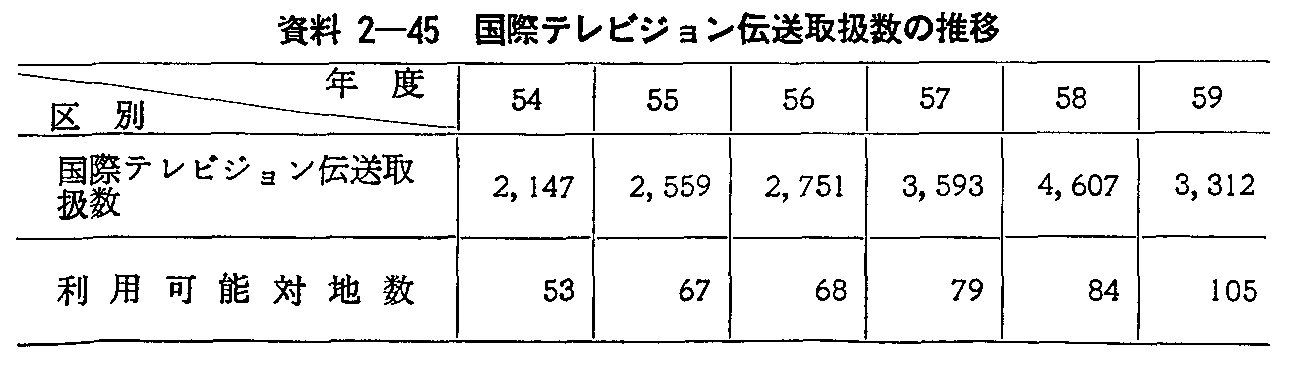
F 国際ファクシミリ電報
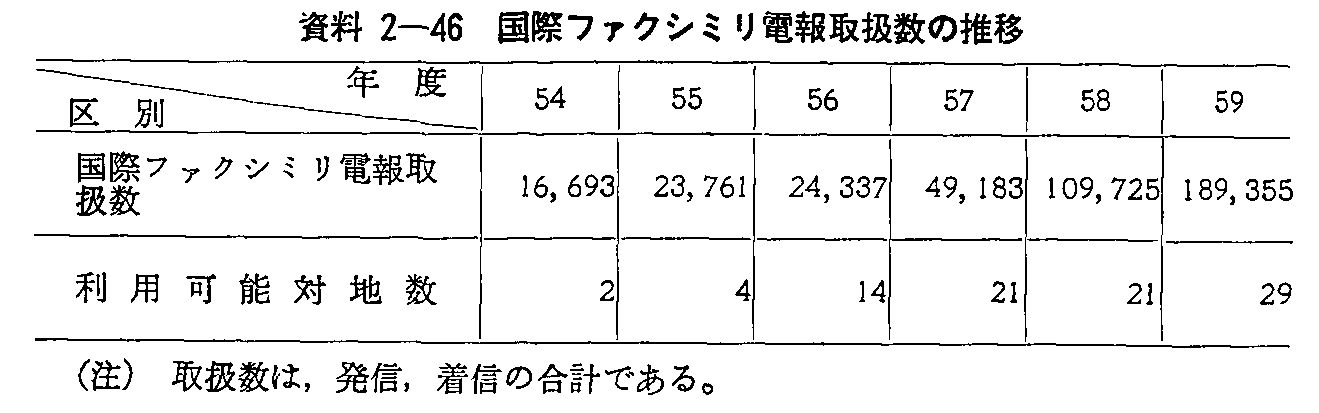
G 国際通信回線
(A)国際通信回線数
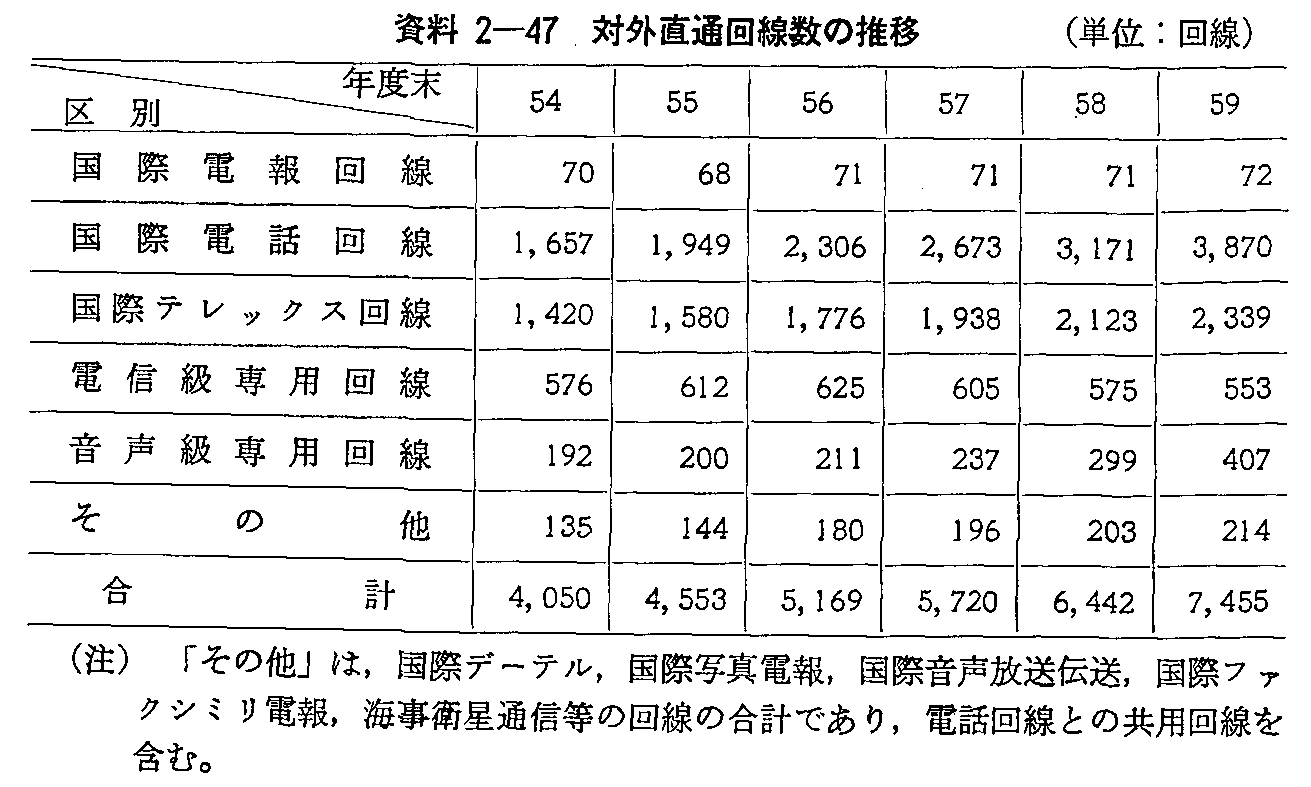
(B)伝送方式
我が国の国際通信回線は,通信衛星,海底ケーブル,対流圏散乱波通信及び短波無線の4つの伝送方式により構成されている。
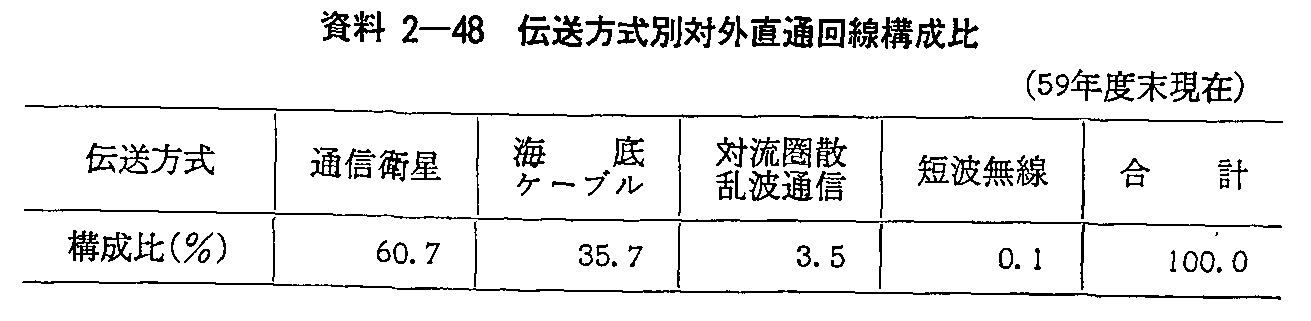
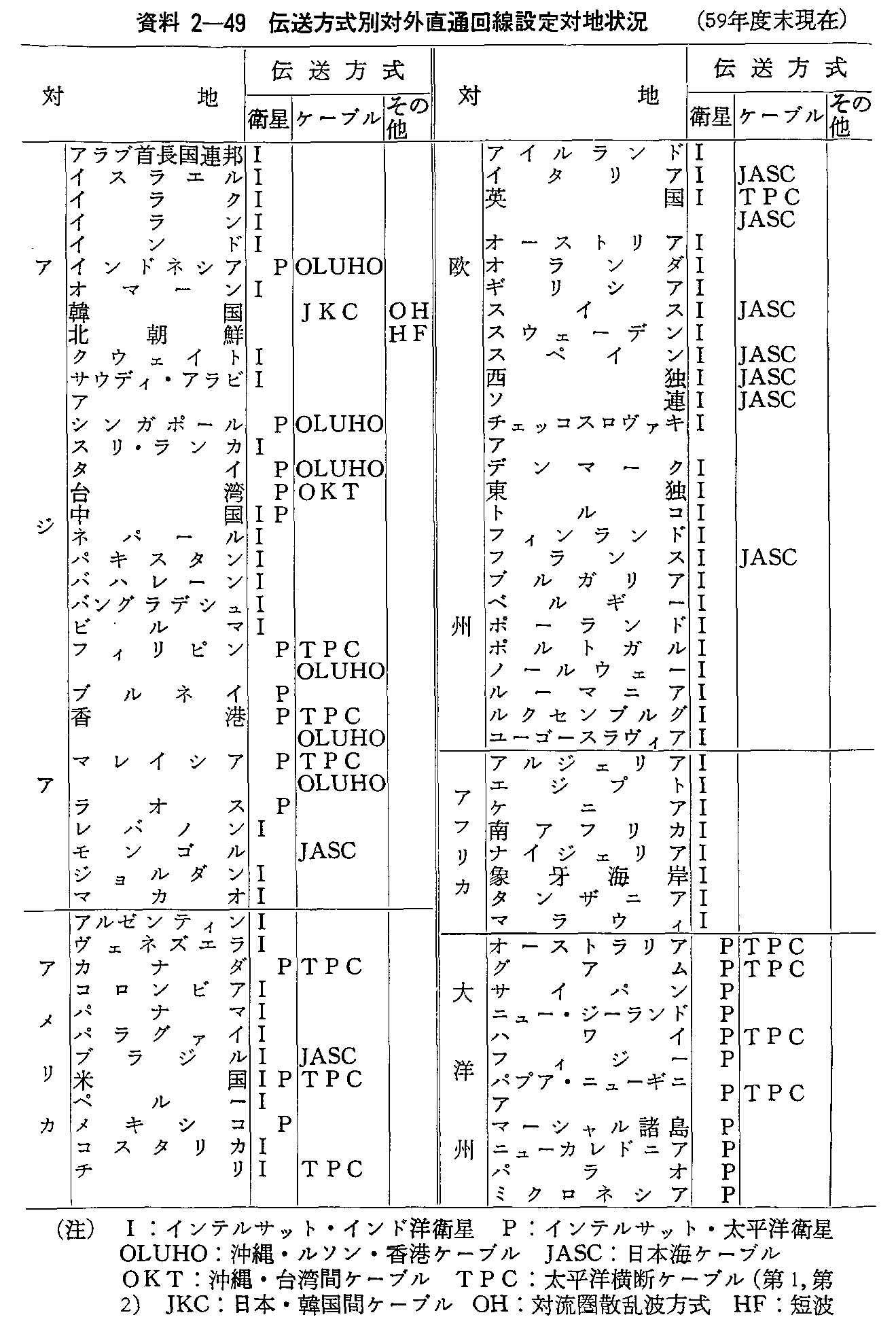
(C)通信衛星
インテルサットの世界通信システムは,59年度末においてIV号系衛星(電話級換算4,000回線及びテレビジョン2回線の容量をもつ。)IV-A号系衛星(電話級換算6,000回線及びテレビジョン2回線の容量をもつ。)及びV号系衛星(電話級換算1万2,000回線及びテレビジョン2回線の容量をもつ。)が,太平洋,大西洋及びインド洋上に計16機が設定運用(又は予備配置)されており,世界の通信のかなめとなっている。
我が国では,KDDが茨城衛星通信所(茨城県高萩市)と太平洋上の衛星を介して,米国,カナダ,オーストラリア及びアジア諸国との間に通信回線(59年度末現在1,471回線)を設定しており,また山口衛星通信所(山口県山口市)とインド洋上の衛星を介してアジア,ヨーロッパ,中東及びアフリカ諸国との間に通信回線(59年度末現在1,227回線)を設定している。
なお,インテルサット衛星を利用する各国の衛星通信所(地球局)数は,60年3月末で163か国(地域を含む。),702局(アンテナ数843)となった。
(D)海底ケーブル
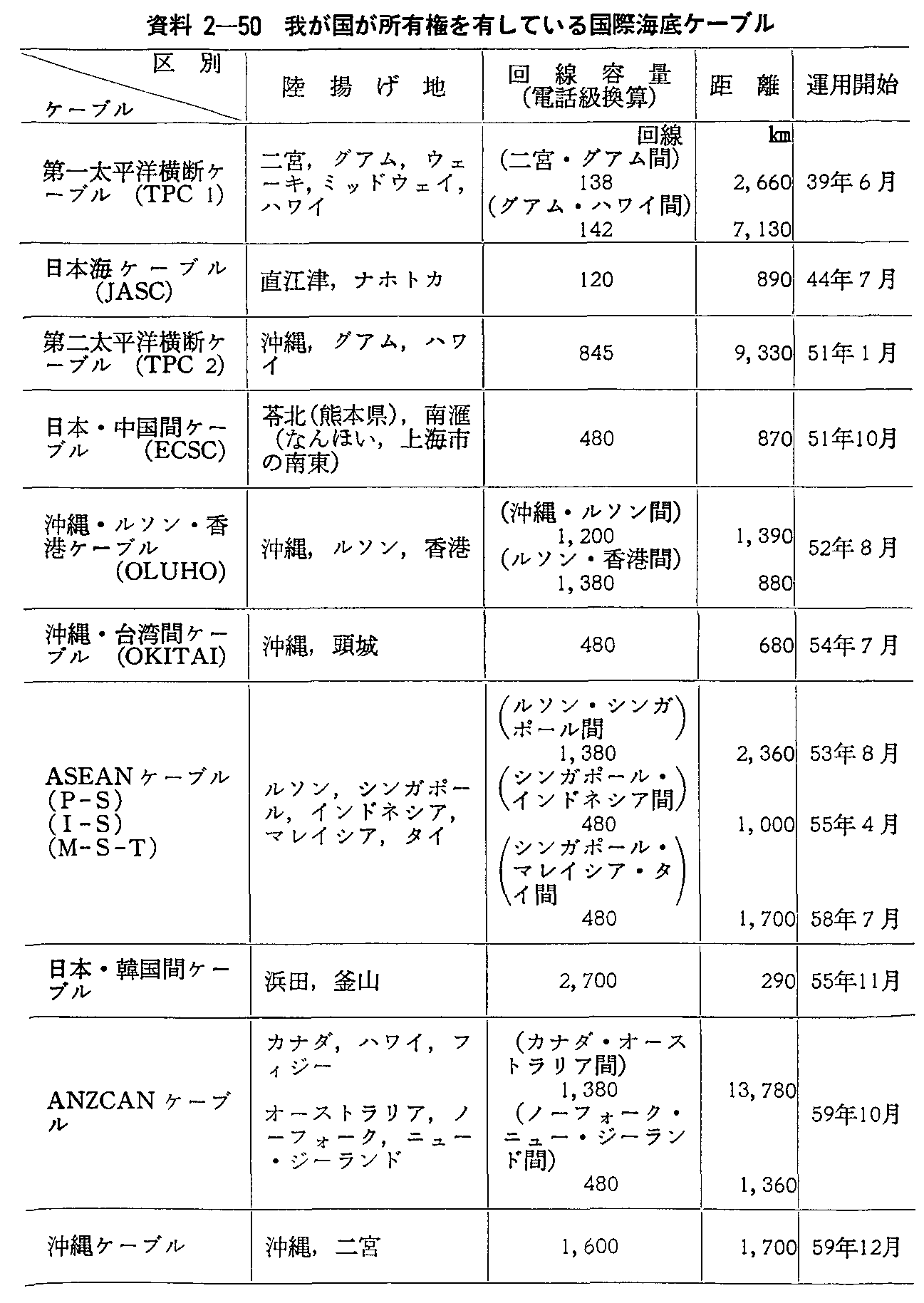
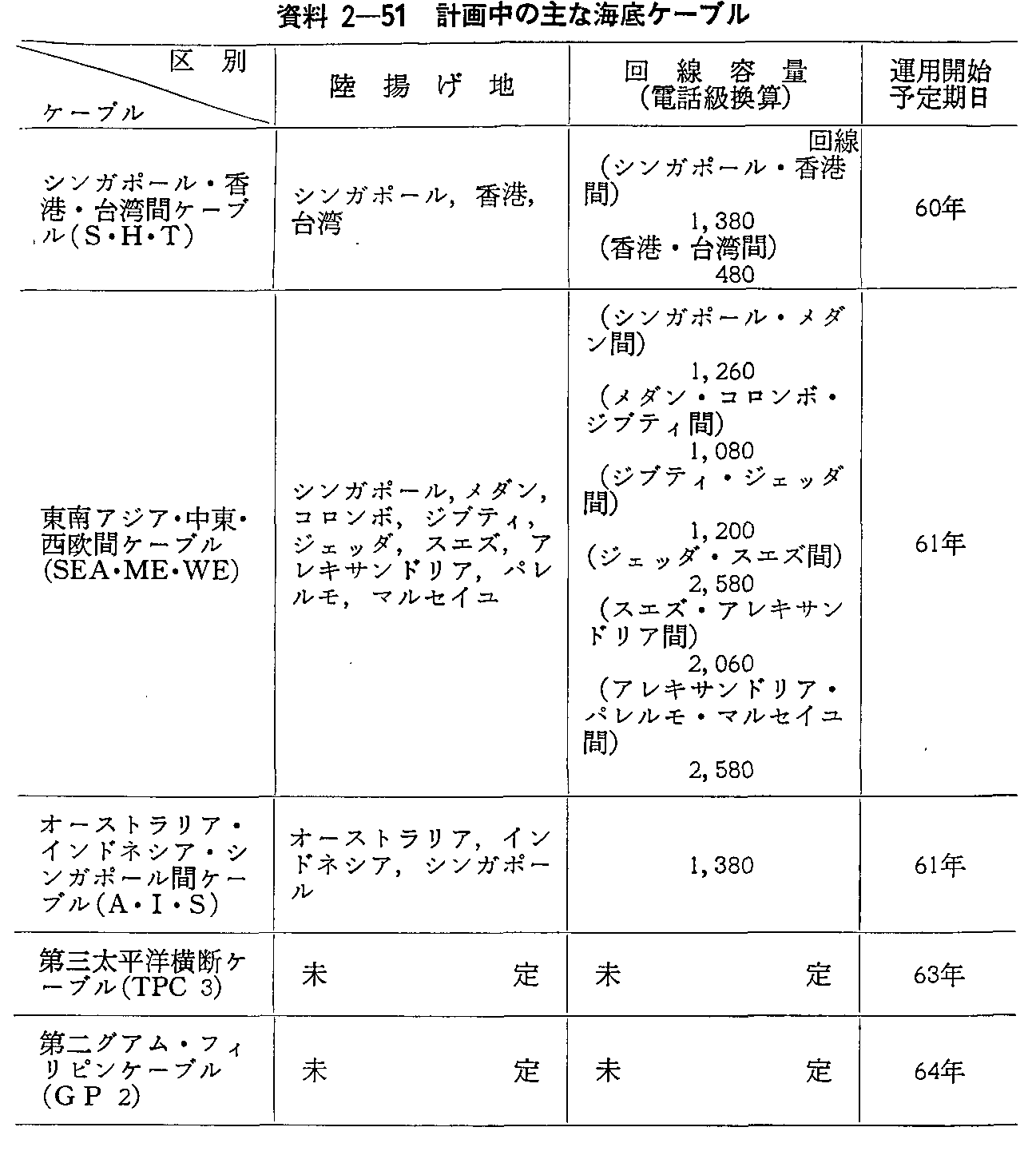
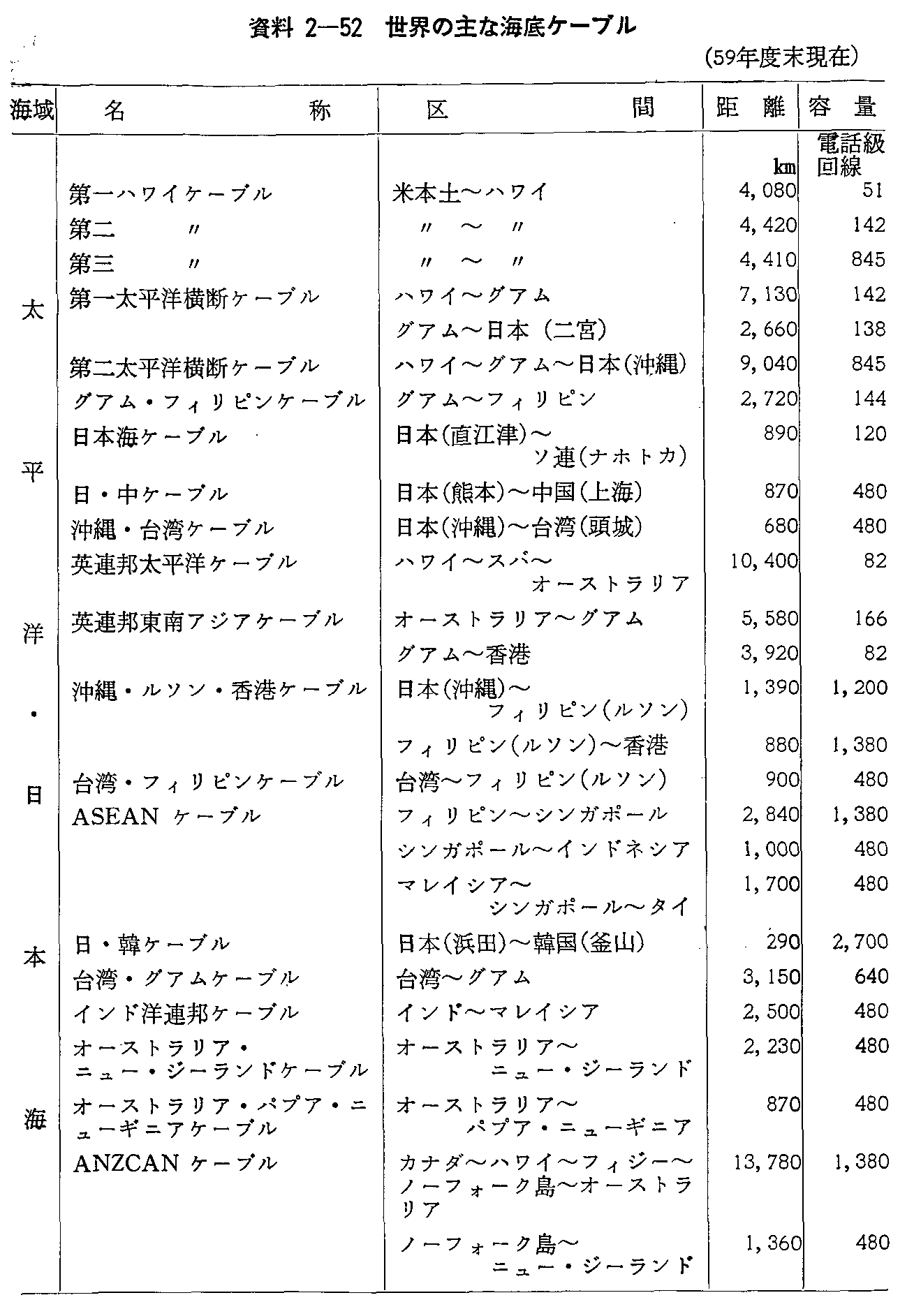
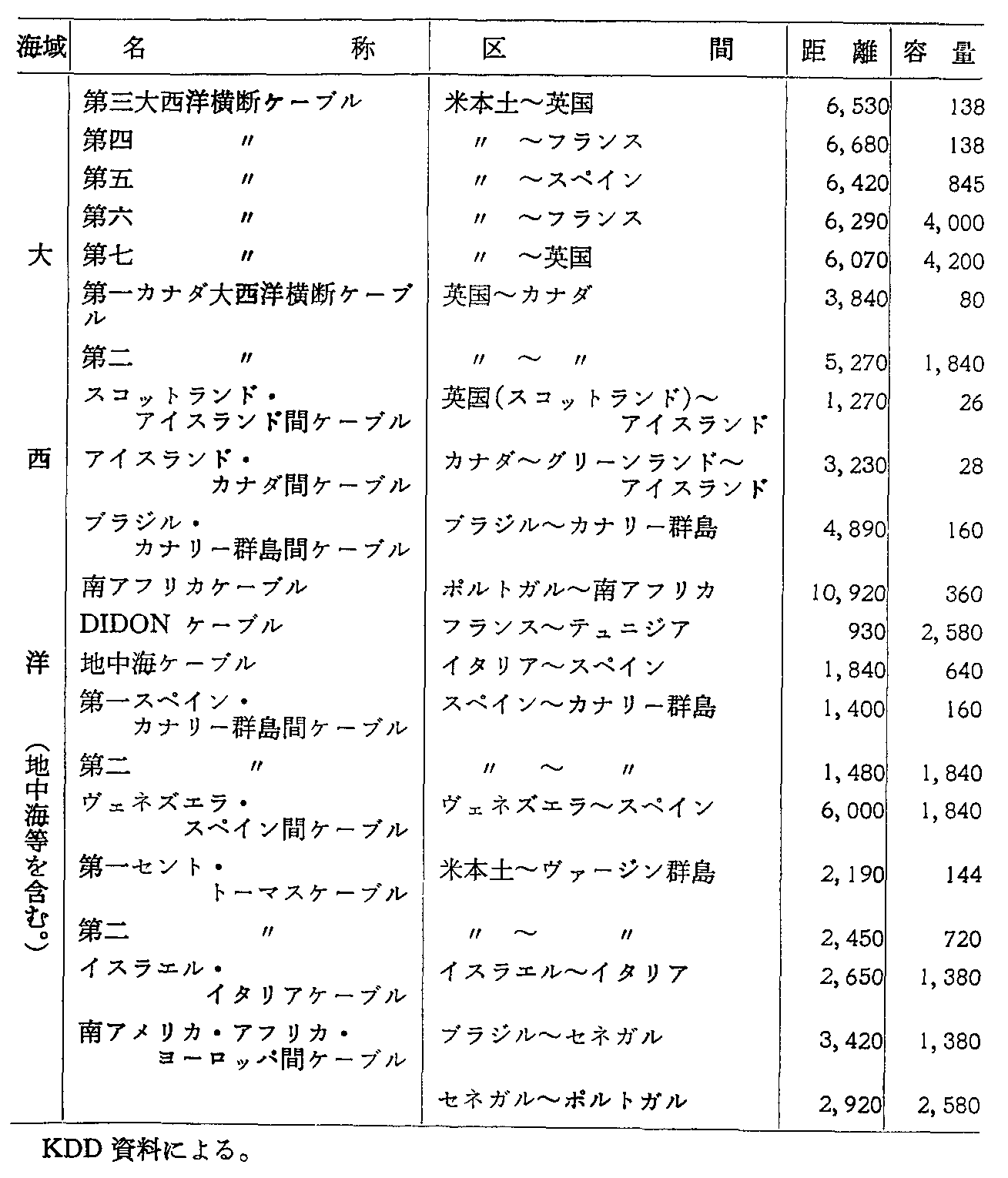
イ.第二種電気通信事業(データ通信を除く。)
57年10月,公衆電気通信法の一部改正により,いわゆるデータ通信回線利用の自由化が実施されたが,これに併せて臨時暫定措置として,主として中小企業者を対象とする民間企業による付加価値通信サービス(いわゆる中小企業VAN)が,郵政省令により制度化され郵政大臣への届出により可能となった。
この中小企業VANは,現在の第二種電気通信事業の嚆矢である。
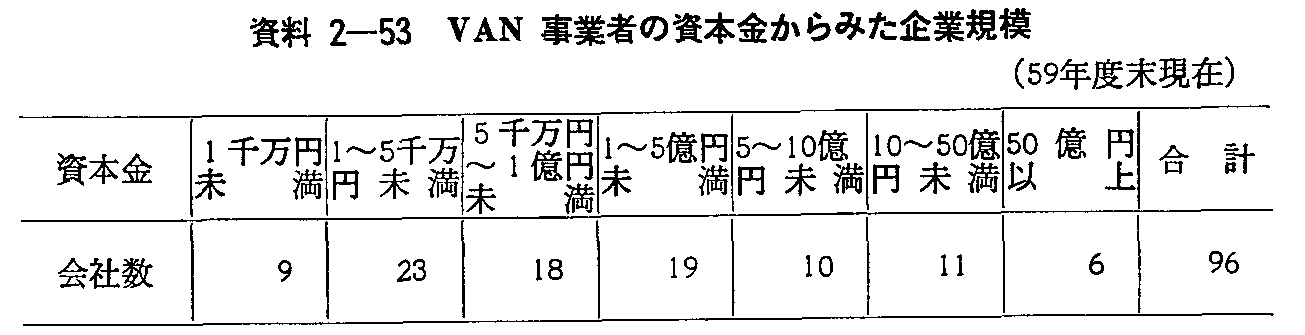
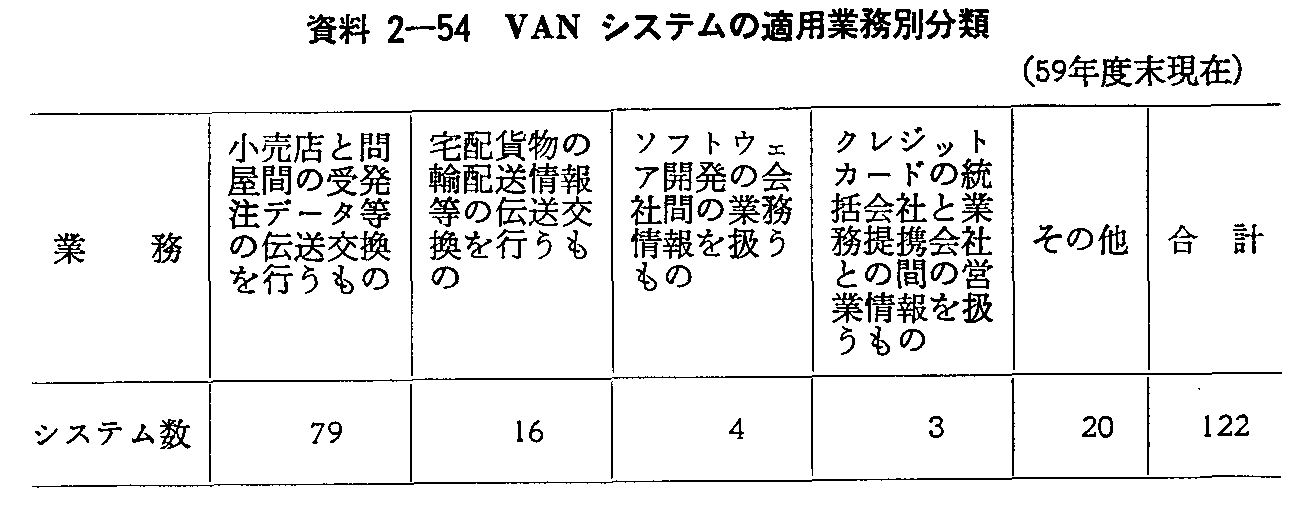
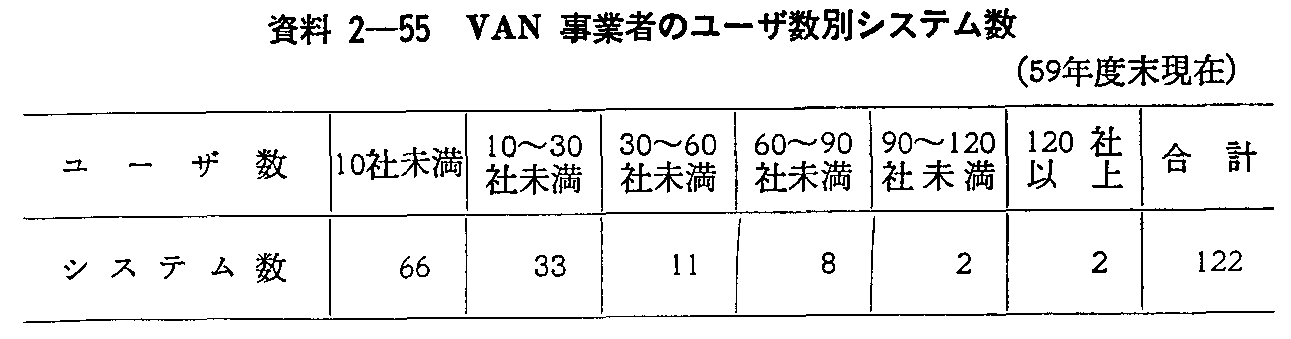
ウ.データ通信
(ア)データ通信回線
A 国内データ通信回線
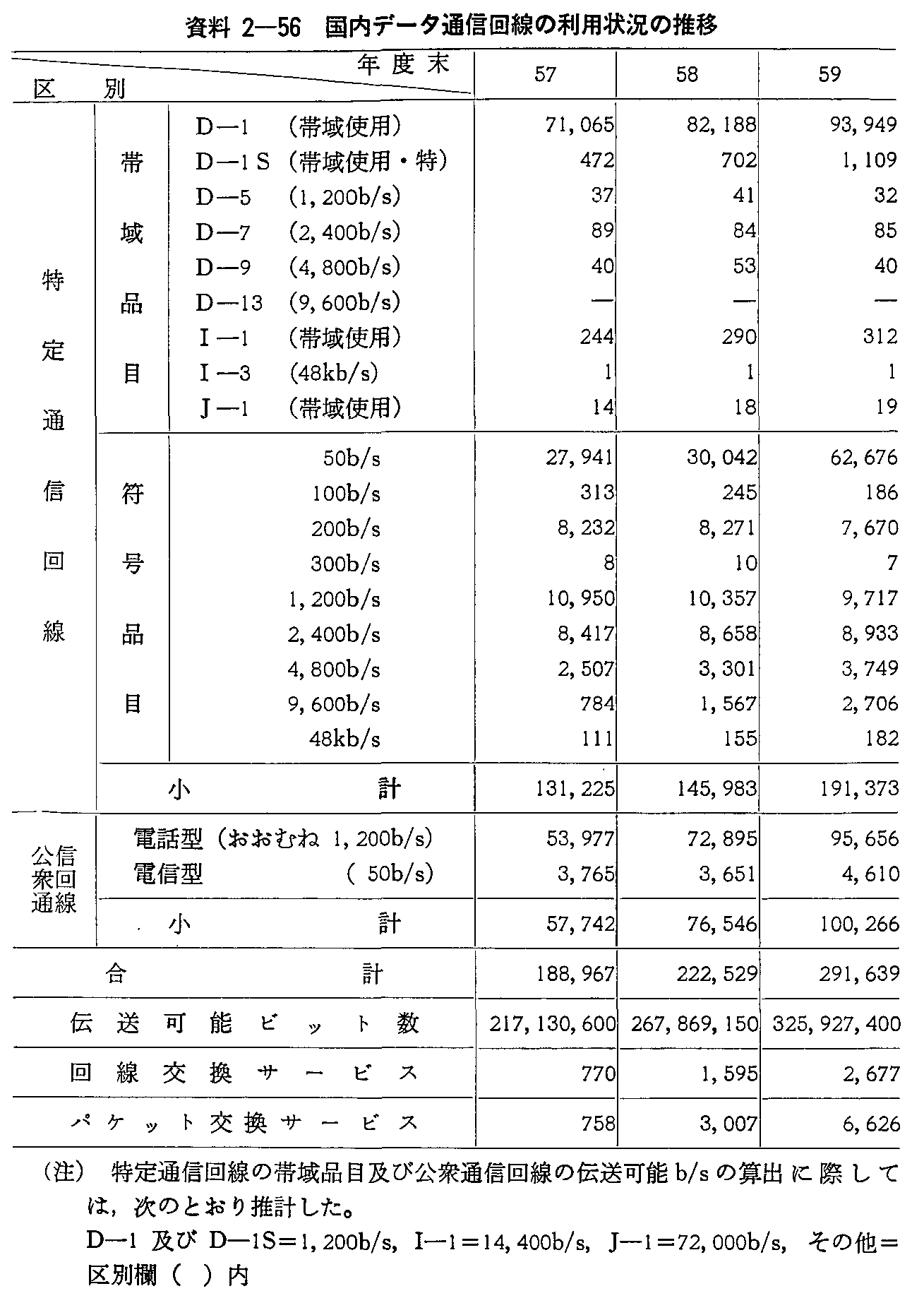
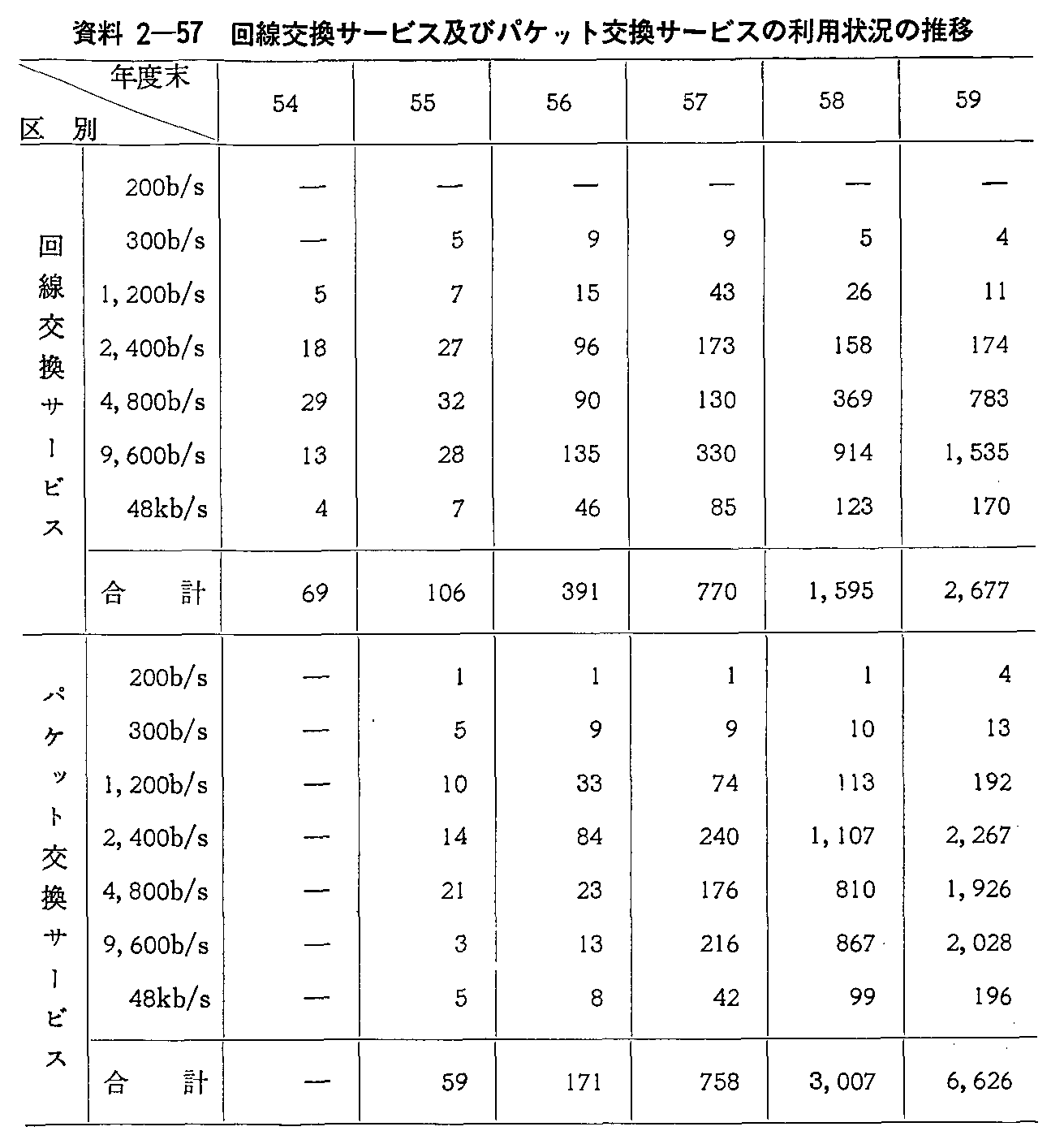
B 国際データ通信回線
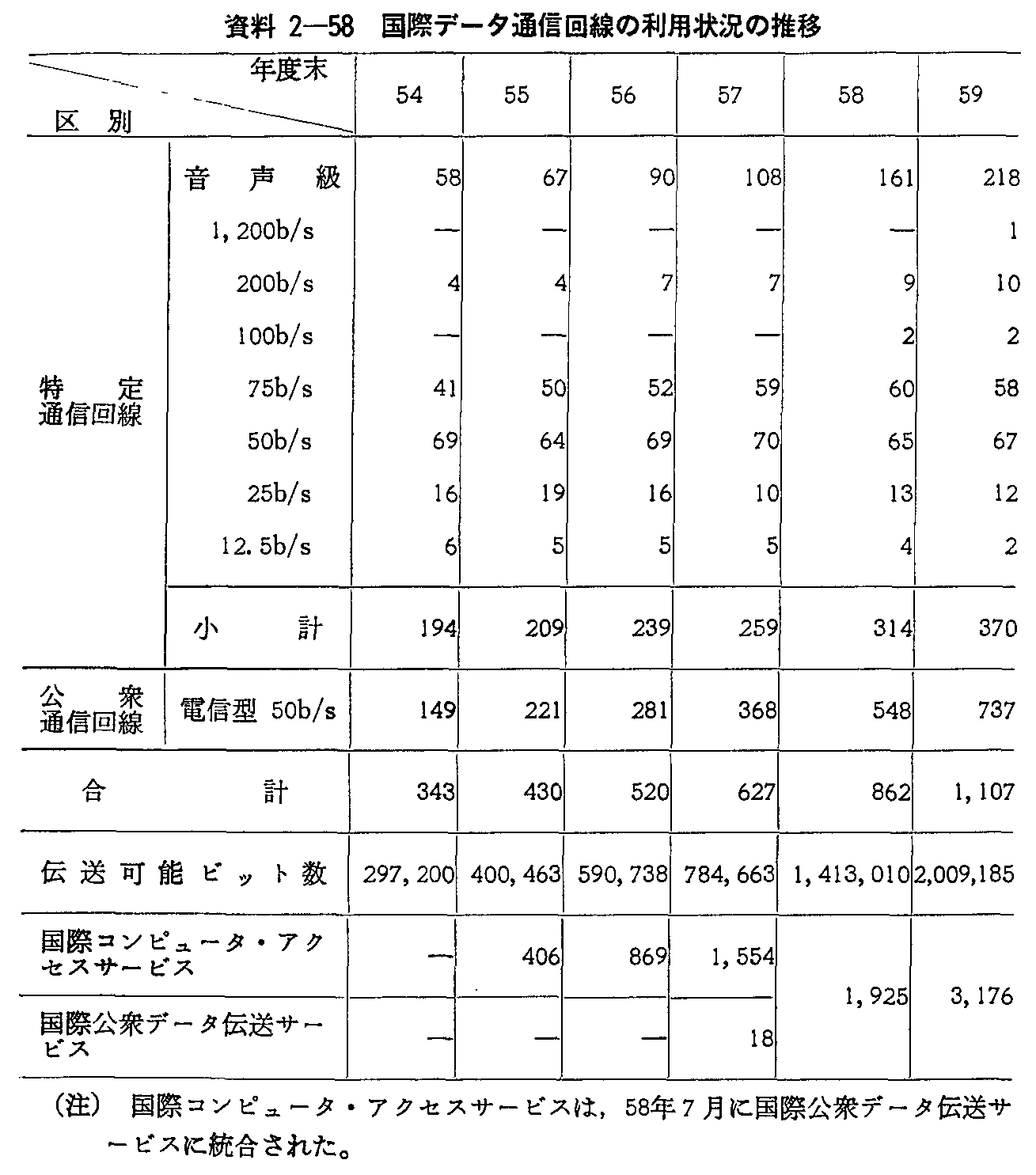
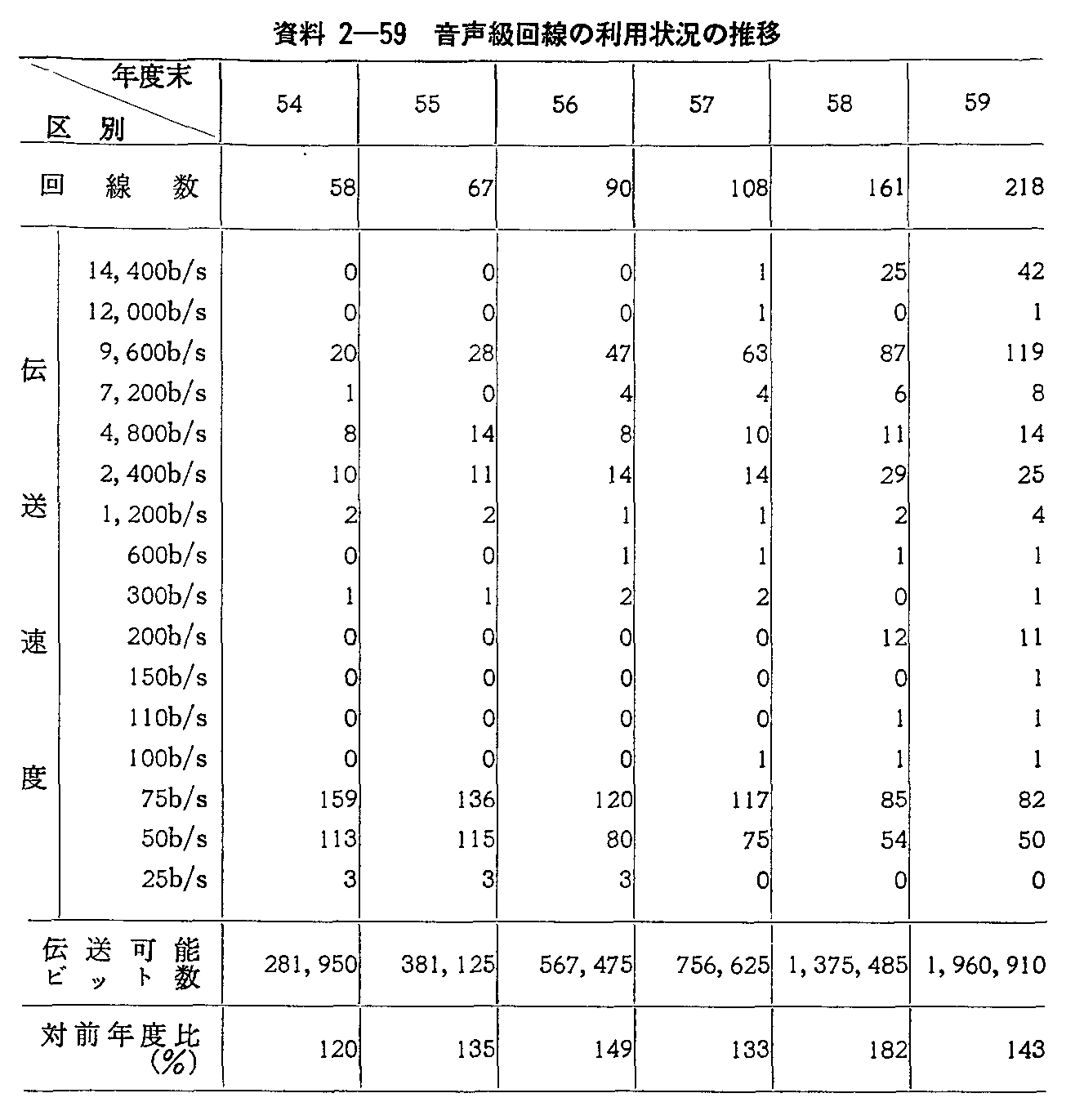
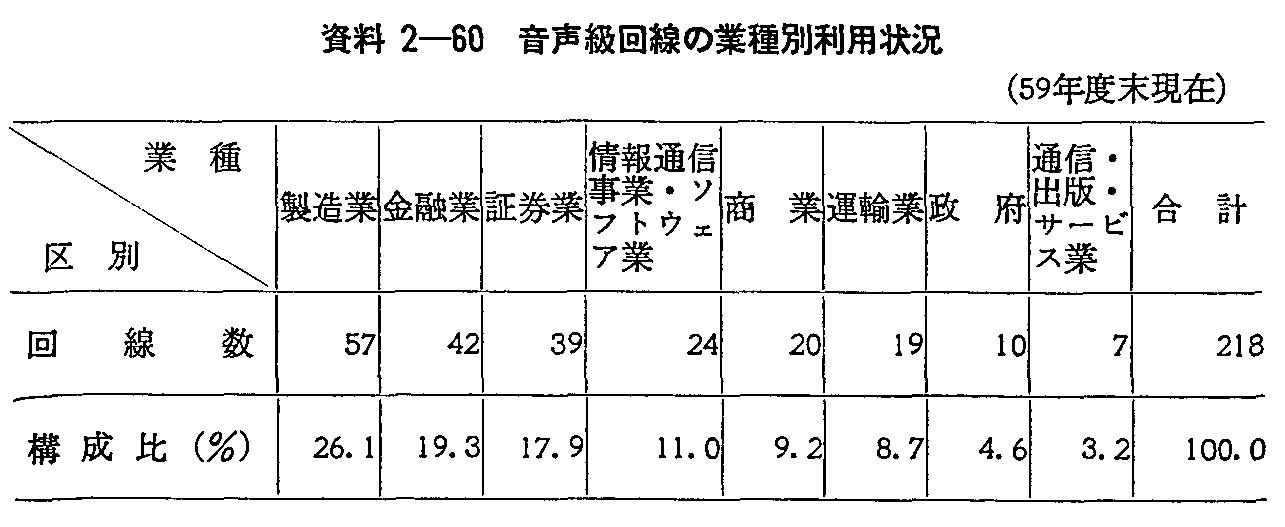
(イ)データ通信システム
A 国内データ通信システム
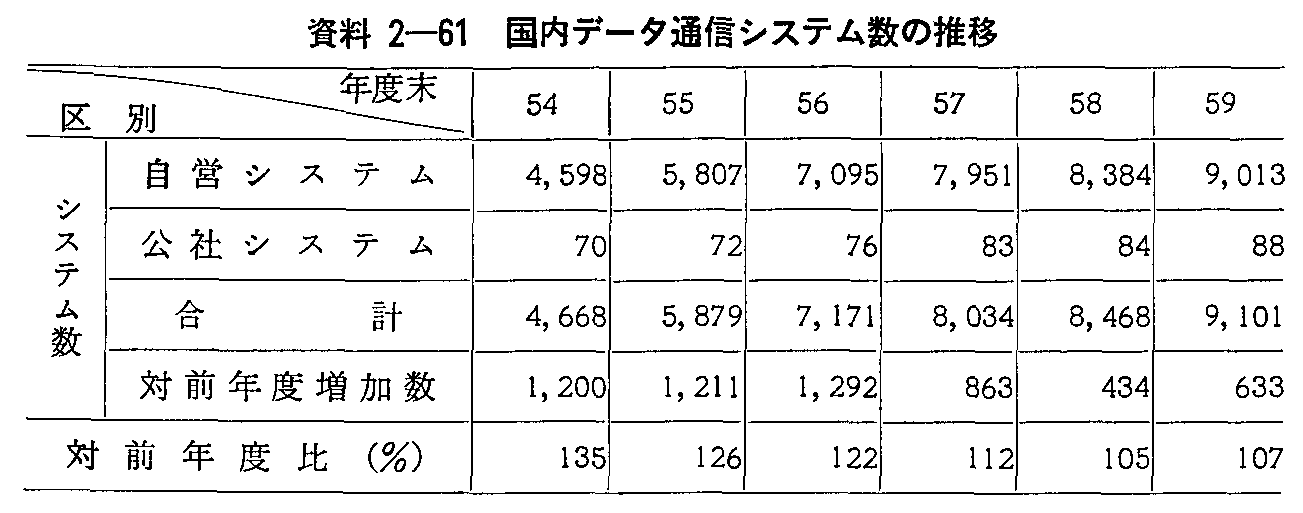
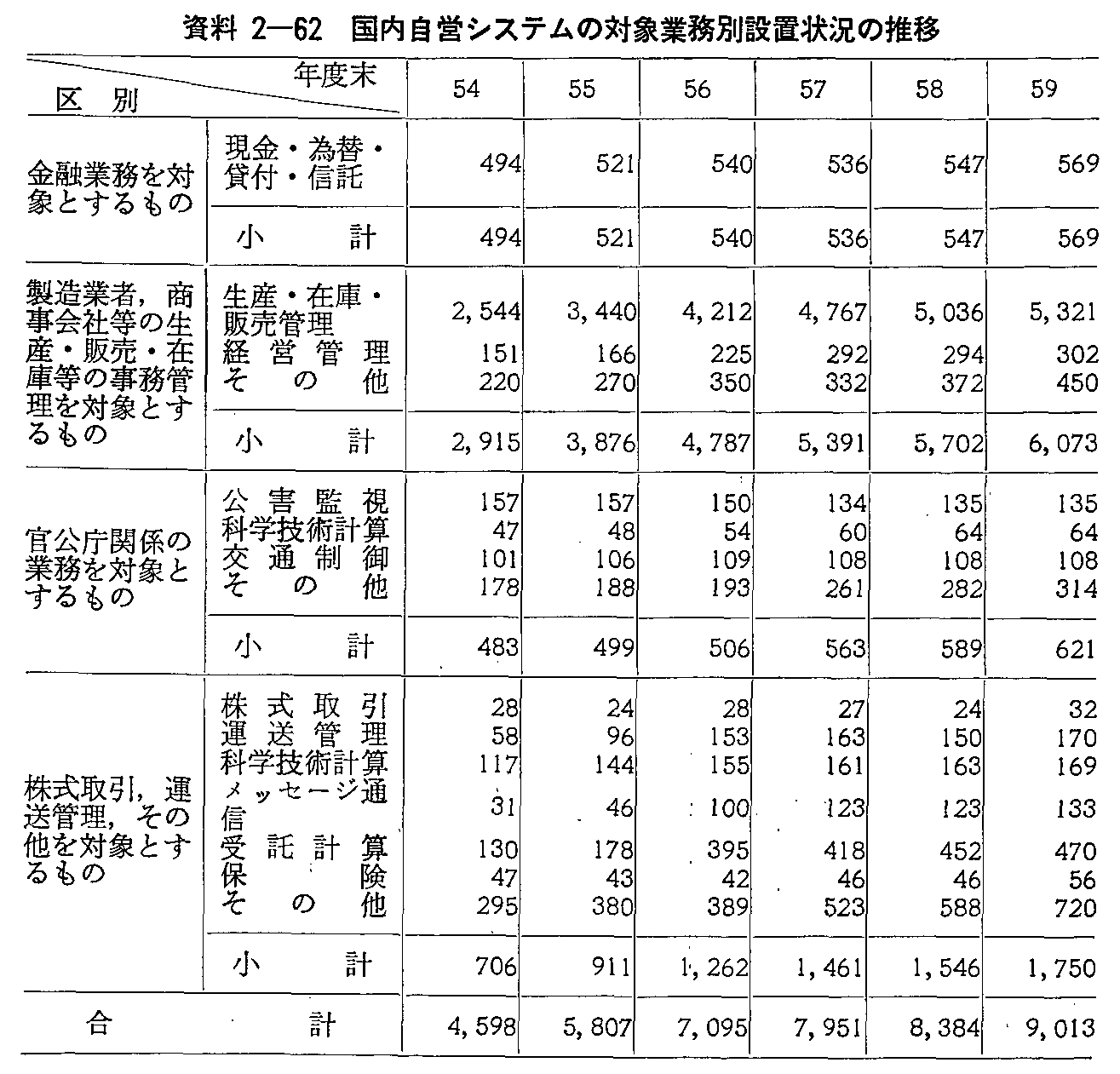
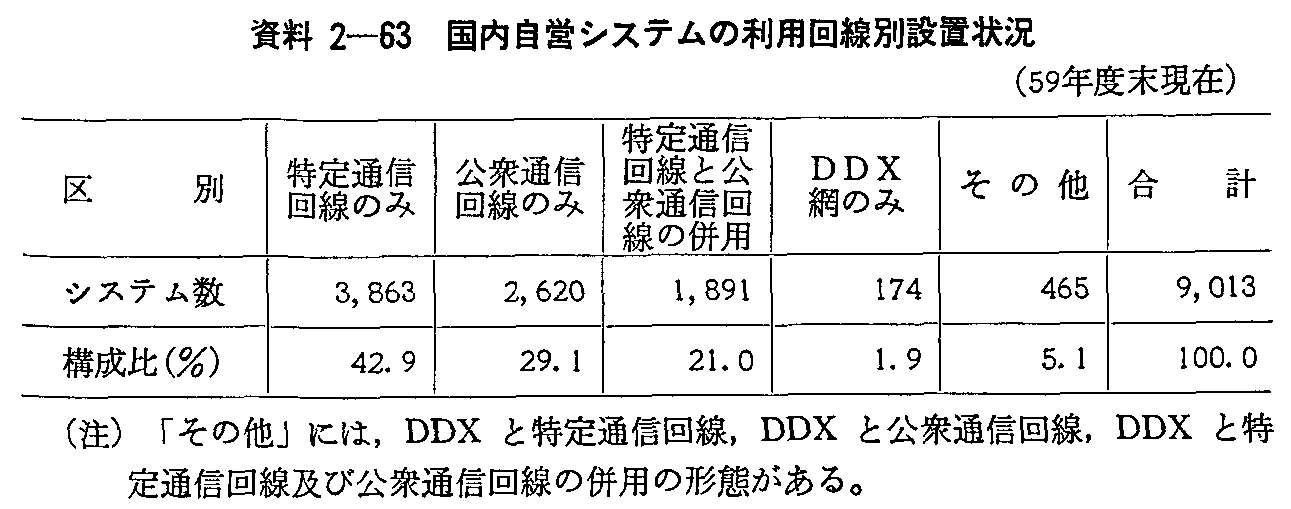
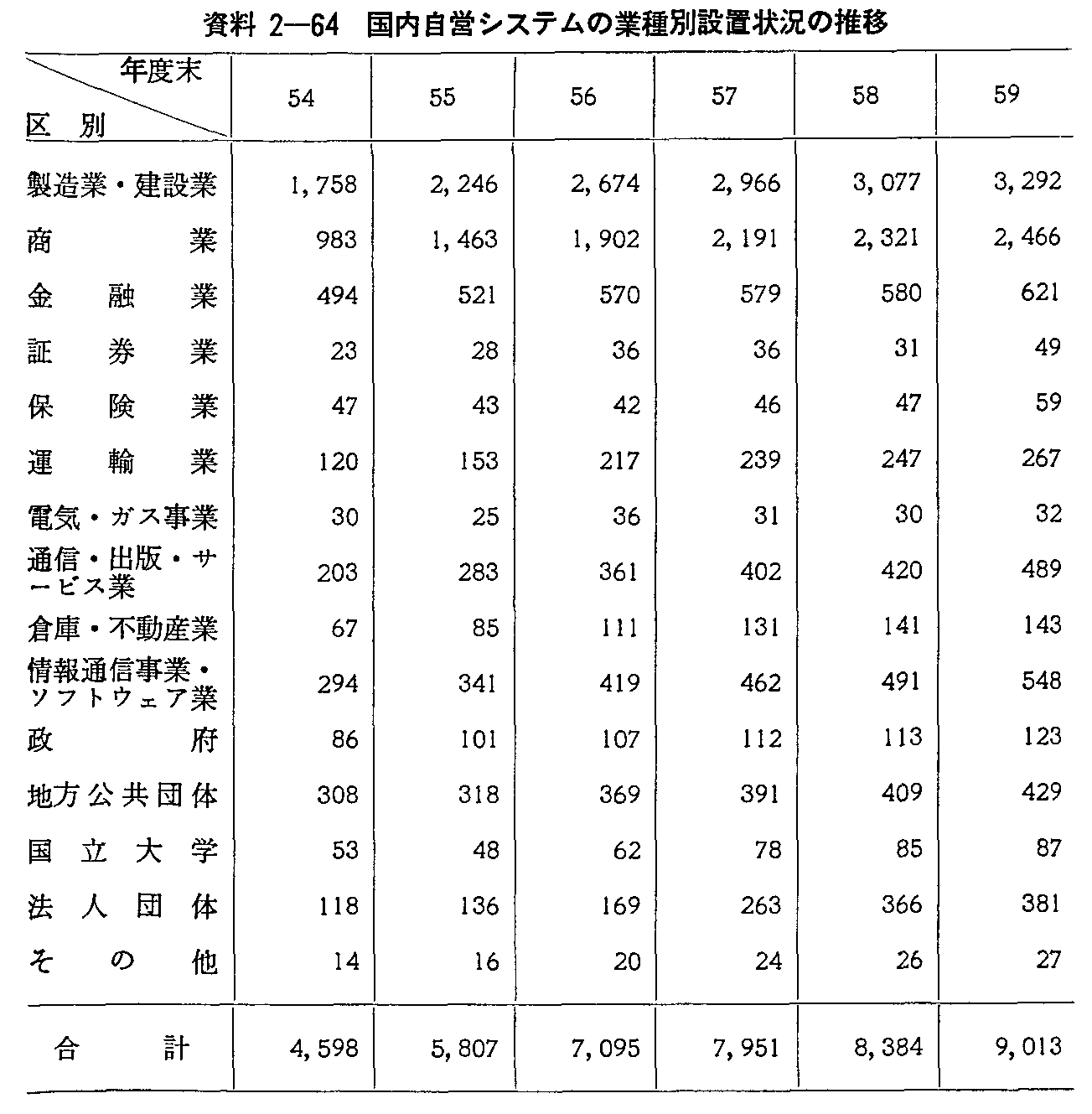
B 国際データ通信システム
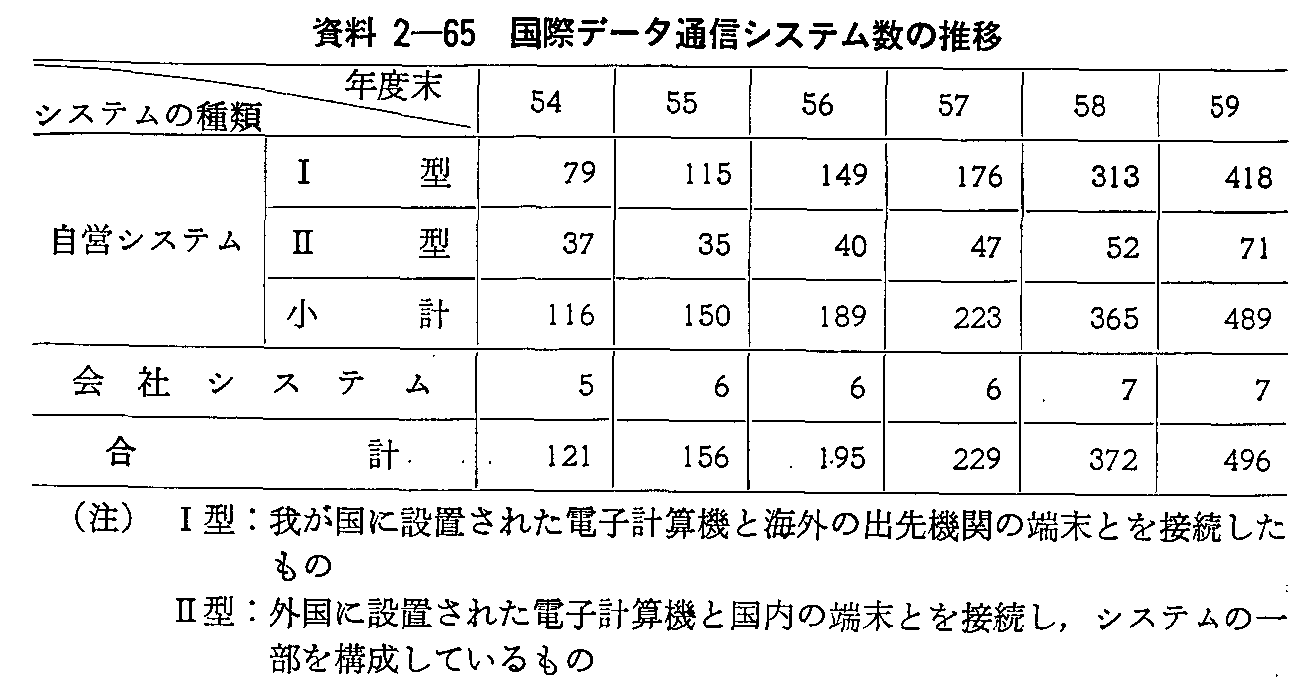
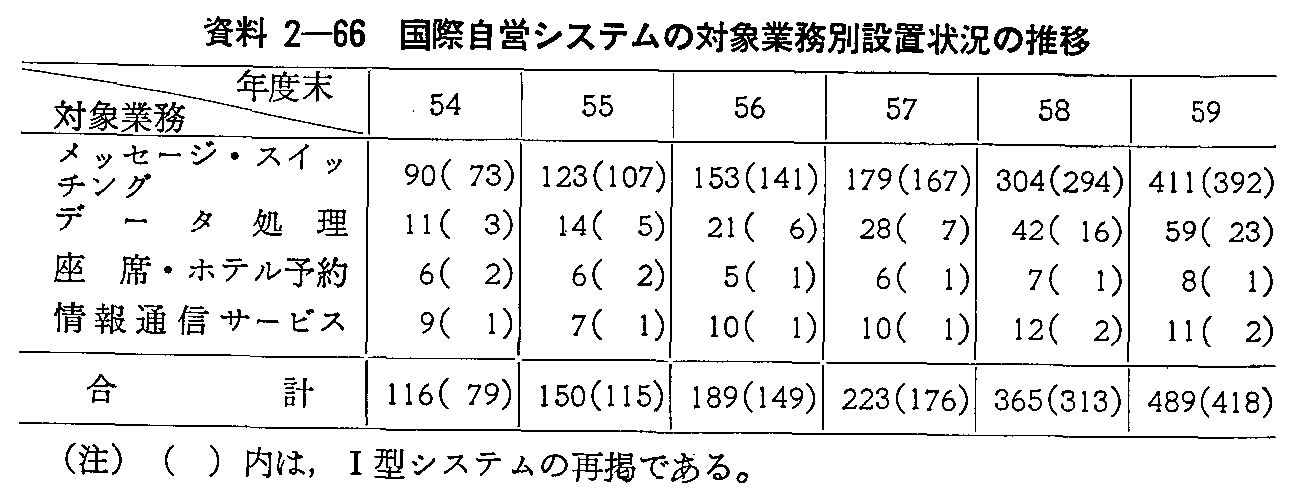
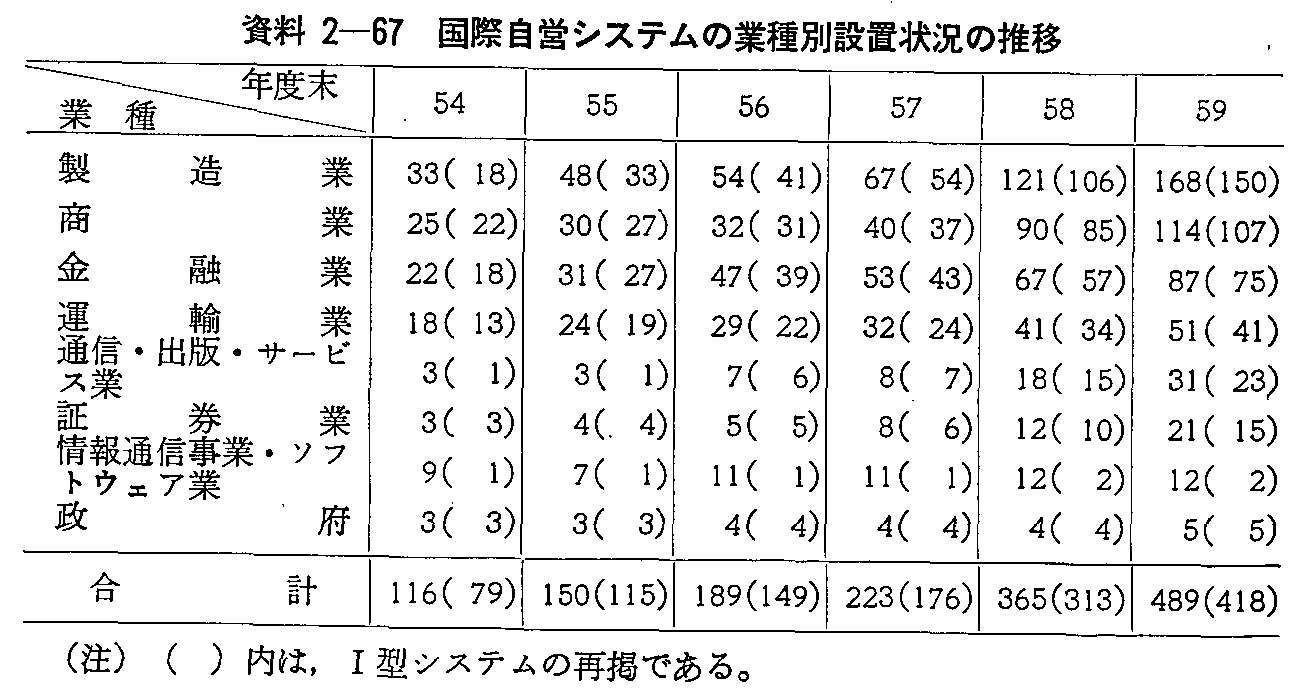
(ウ)情報通信事業
データ通信サービスを顧客の需要に応じて提供する情報通信事業は,電電公社,KDD及びそれ以外の民間企業により営まれている。
A 電電公社の情報通信事業
電電公社が提供しているデータ通信サービスには,電電公社が用意したシステムを共同利用するいわばレディメイド型の公衆データ通信サービスと,電電公社が顧客の求めにより対象業務に応じたサービスを提供するいわばオーダメイド型の各種データ通信サービスがある。
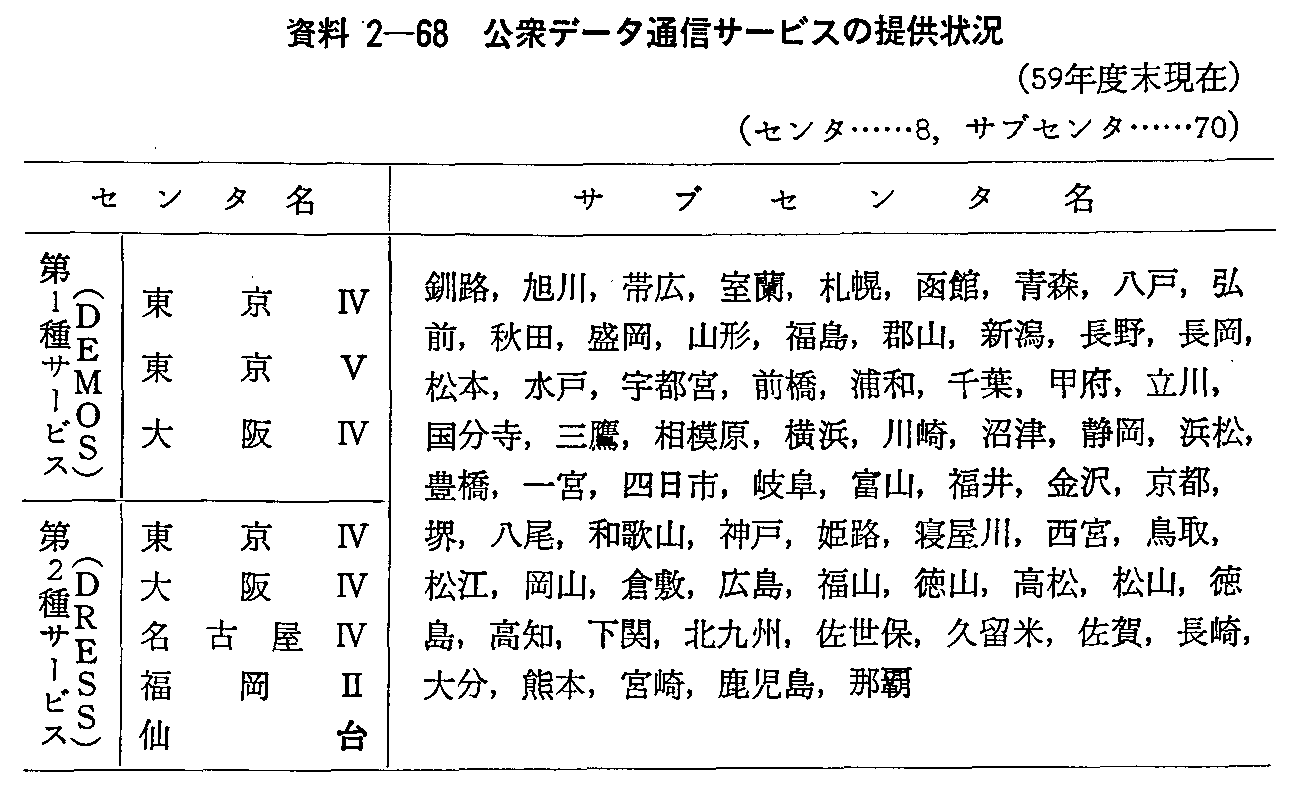
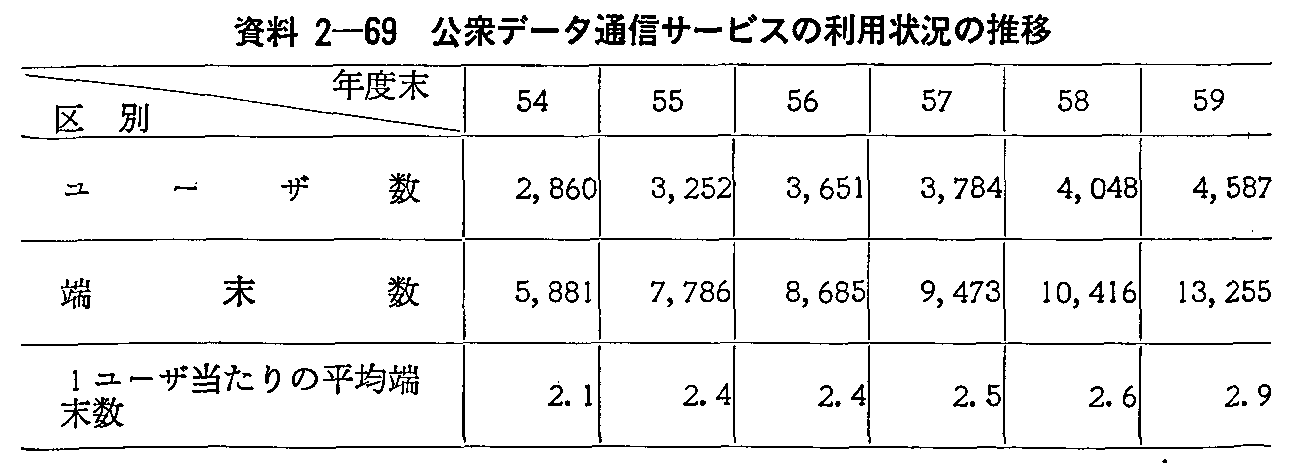
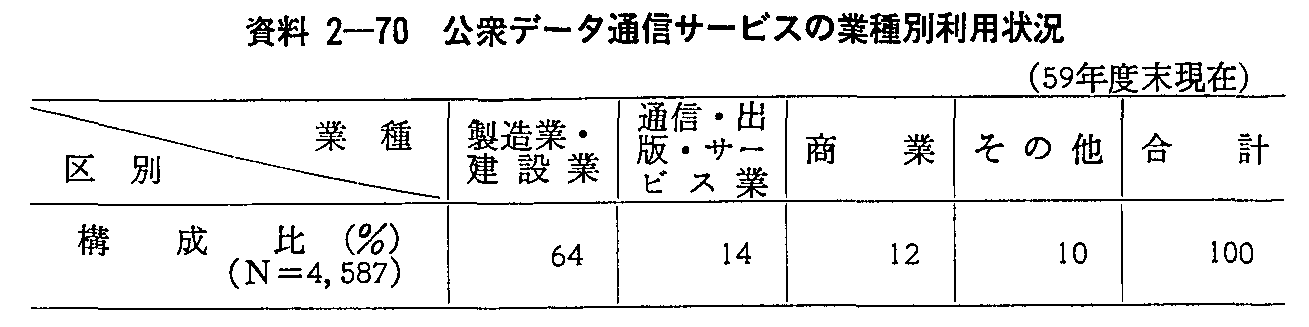
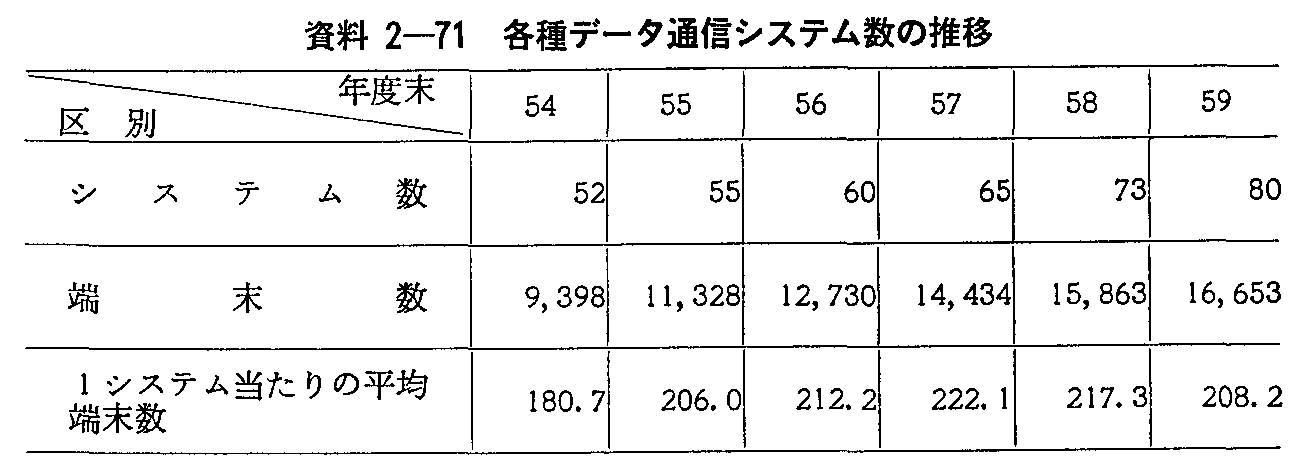
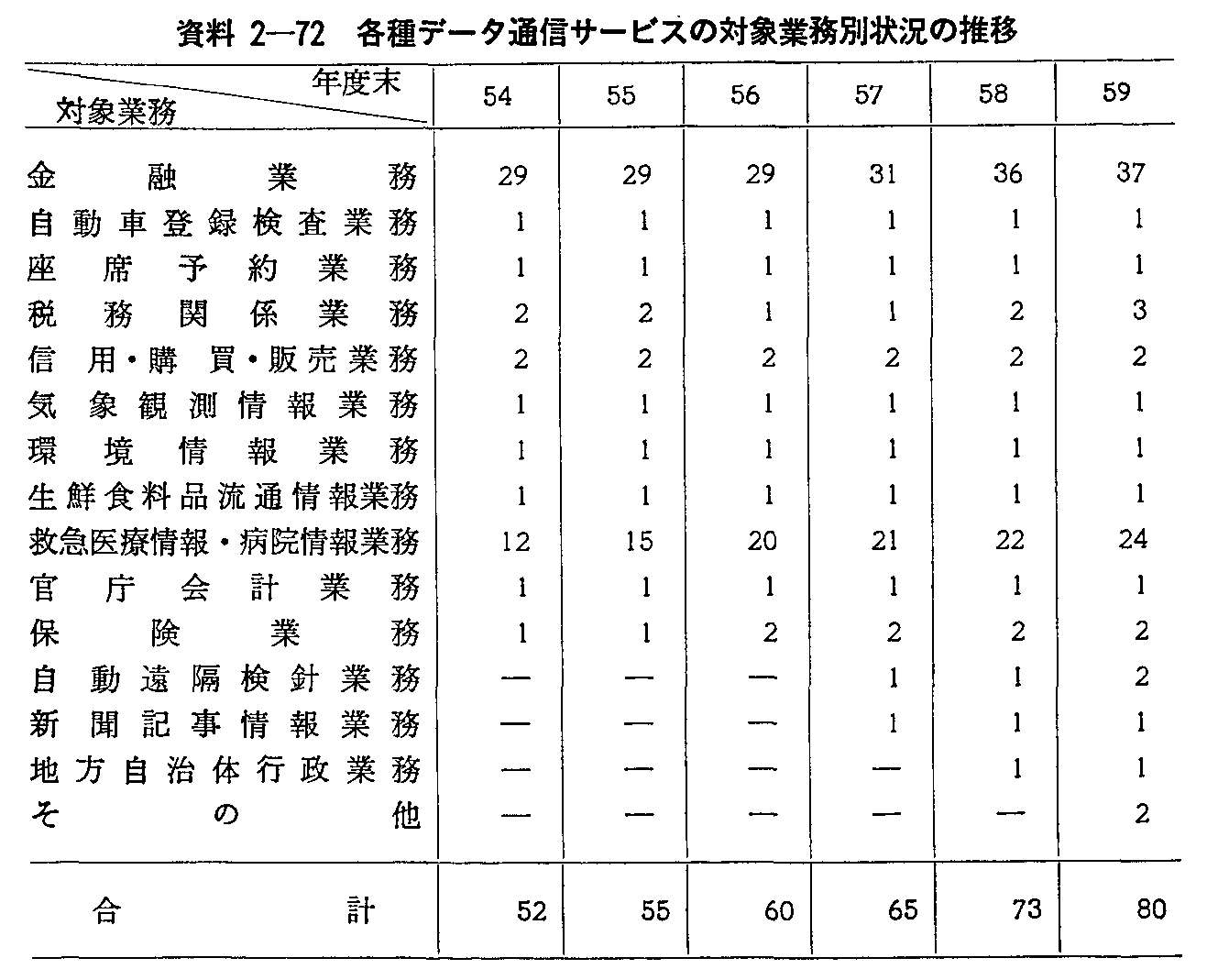
B KDDの情報通信事業
KDDが提供しているデータ通信設備サービスには,システムを顧客が共同利用するいわばレディメイド型の国際オートメックスサービスと,顧客の求めに応じてそれぞれシステムを設置してサービスを提供するいわばオーダメイド型の個別システムサービスがある。
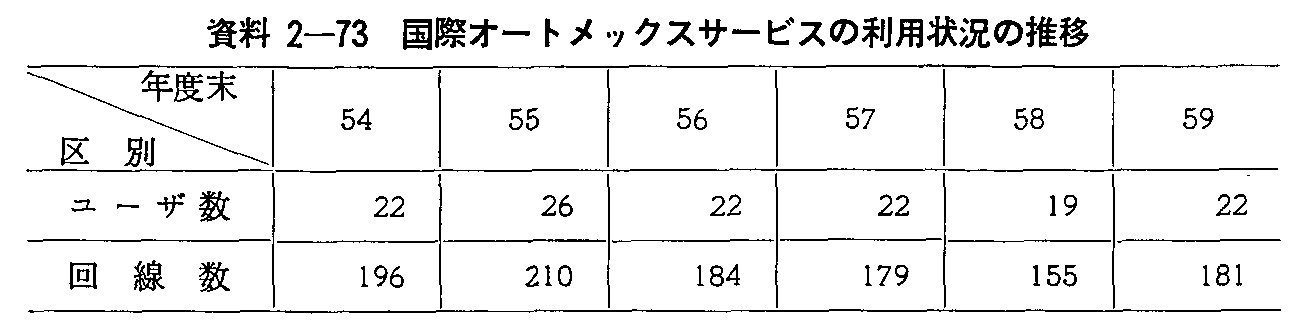
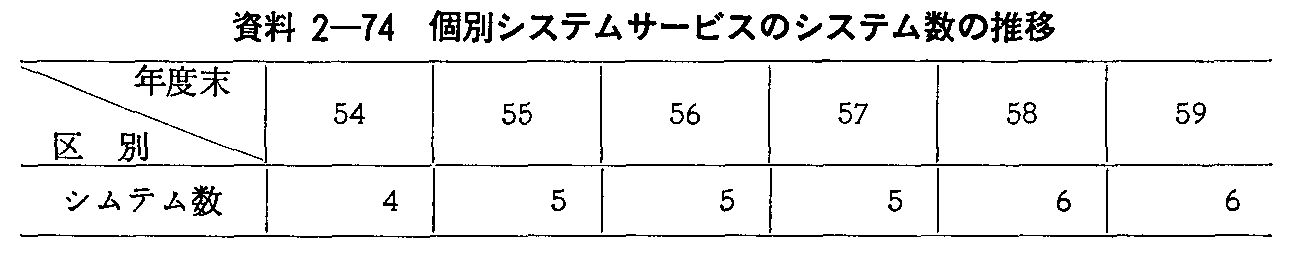
C その他の民間の情報通信事業
59年12月現在,電電公社及びKDD以外の民間企業における情報通信事業の状況について,郵政省が調査した結果は次のとおりである。
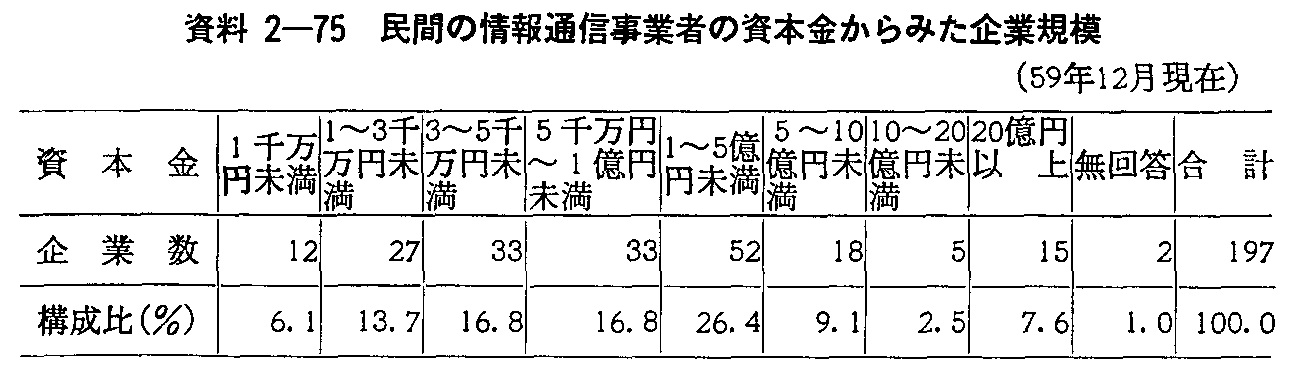
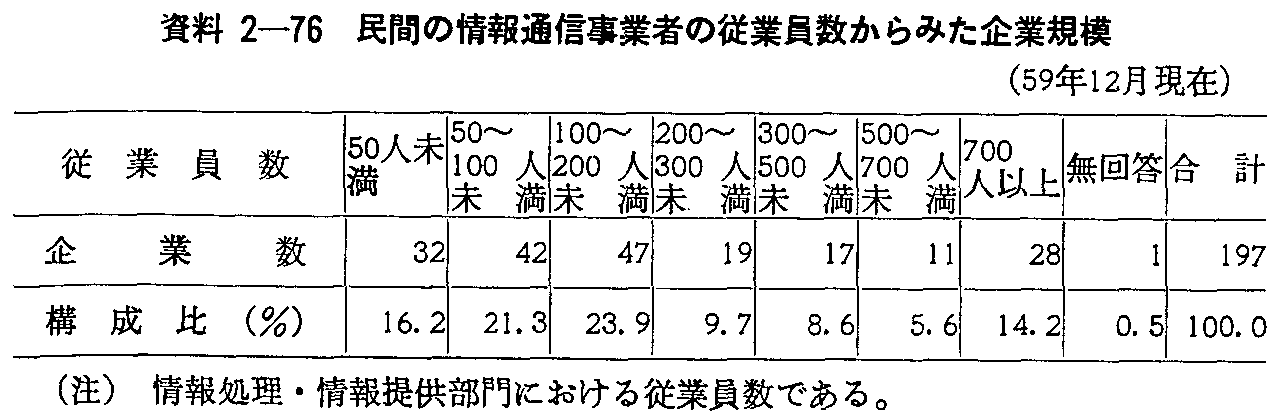
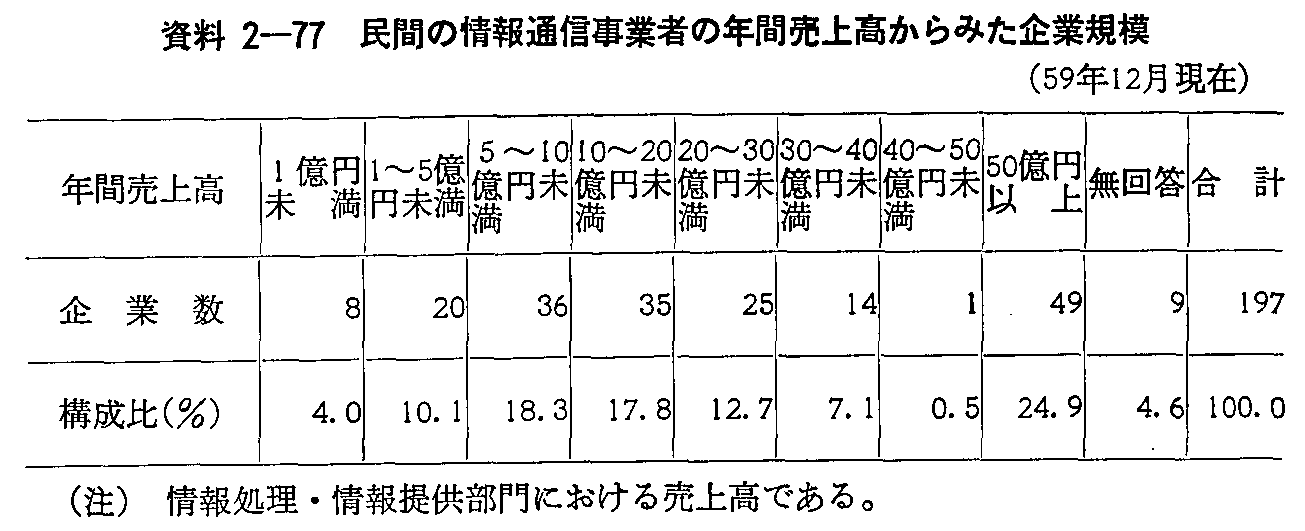
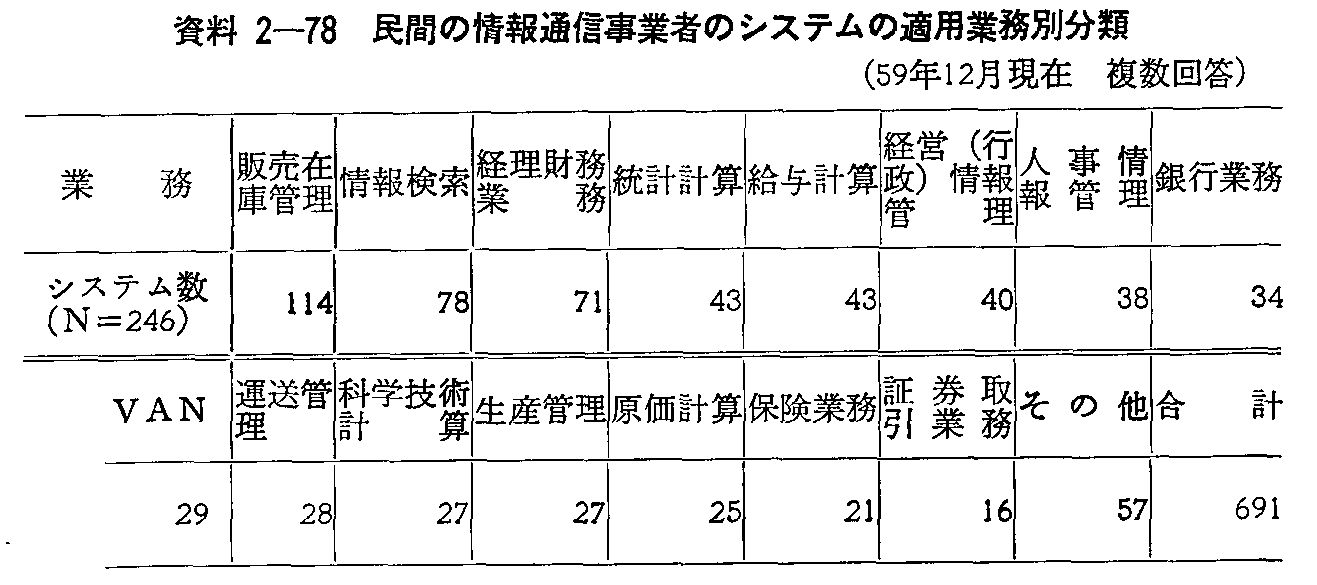
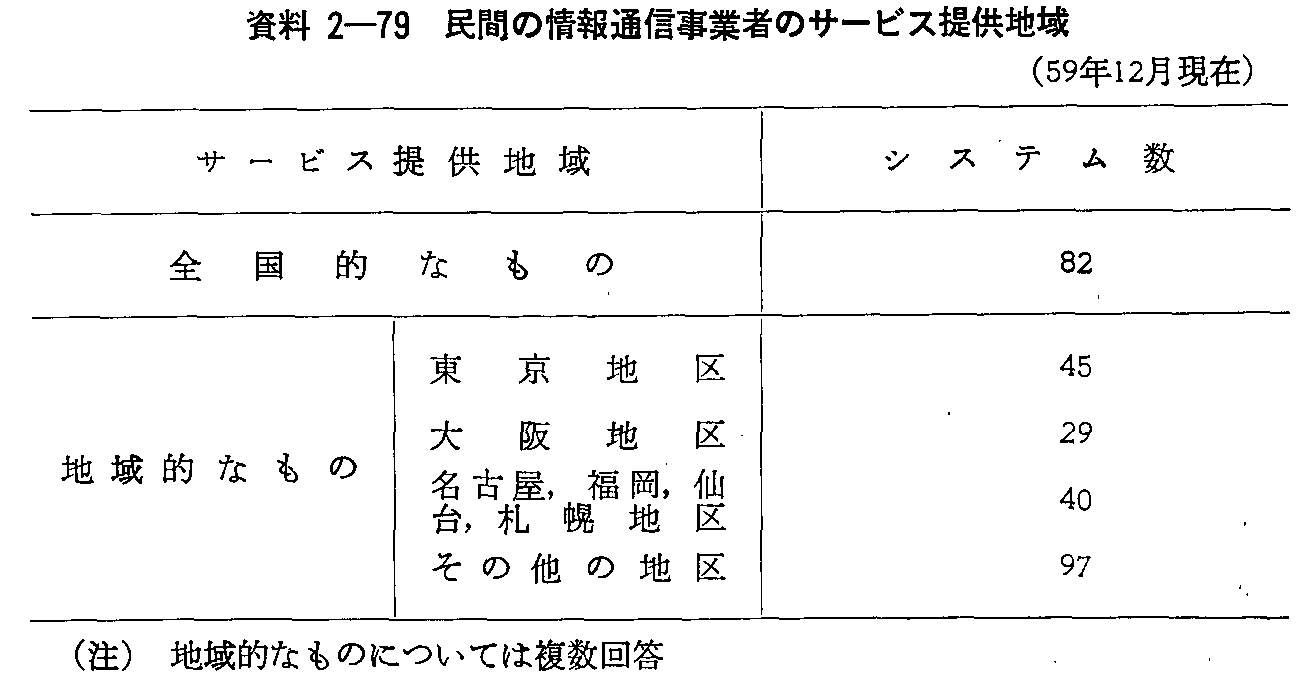
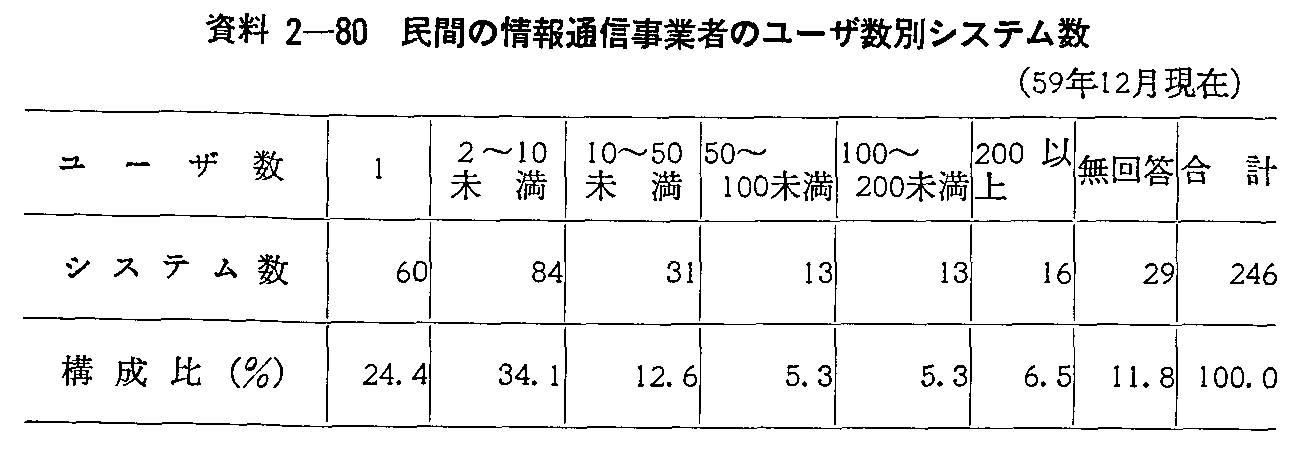
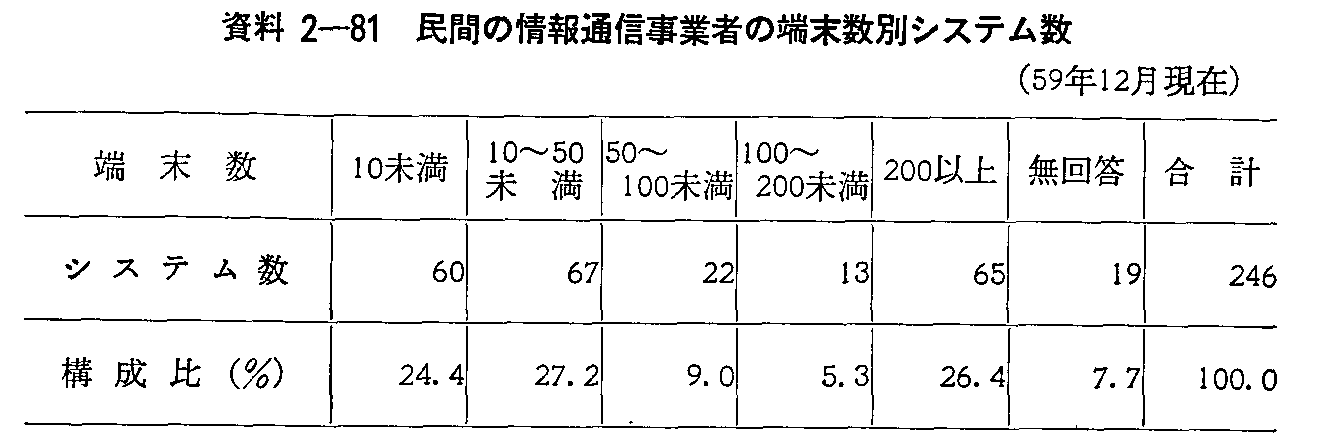
エ.有線放送電話事業
有線放送電話は,放送と通話の二つの機能を兼ね備えたメディアであり,農林漁業地域において簡易な広報連絡手段として利用されている。
(ア)有線放送電話設備の状況
A 施設数及び端末設備数
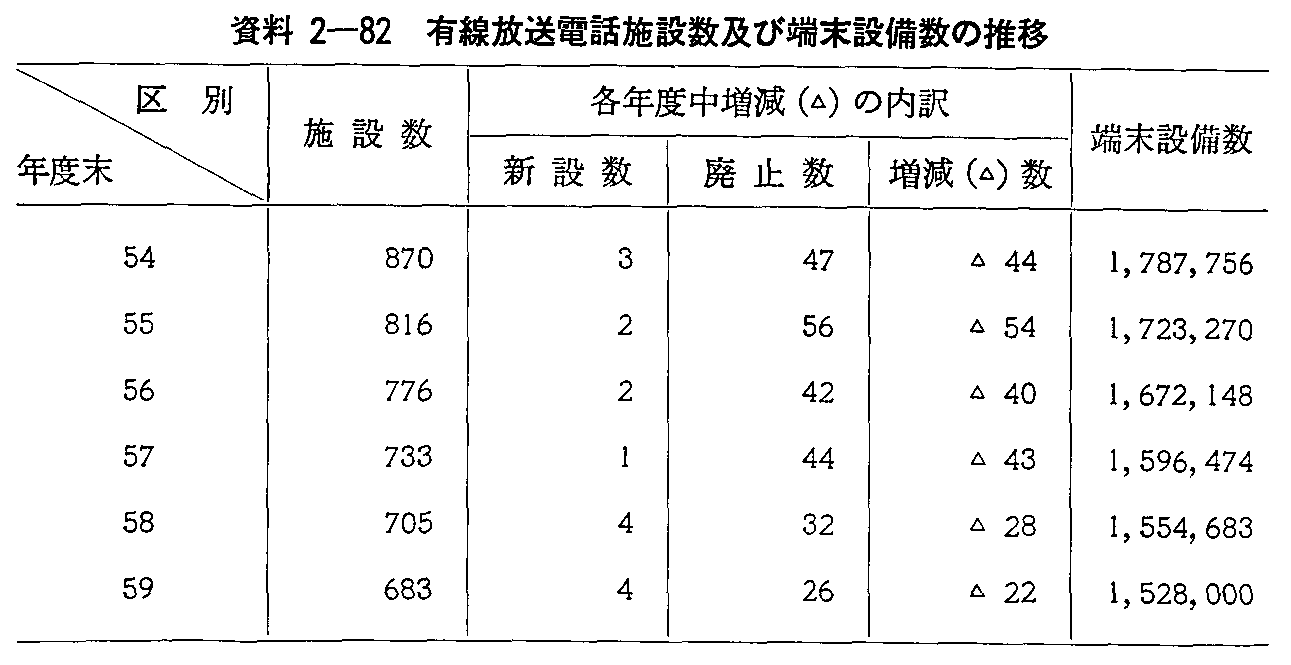
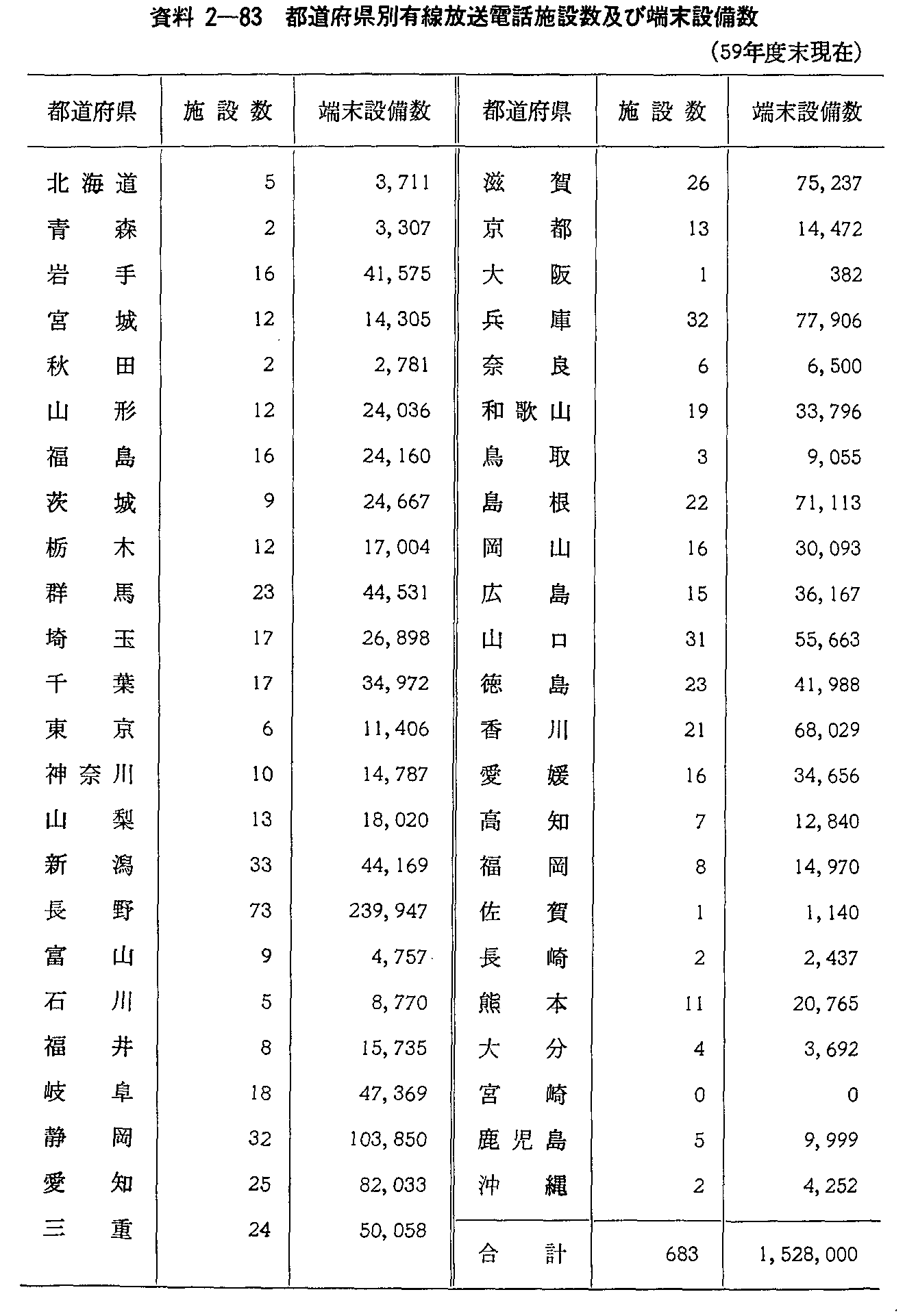
B 施設の規模
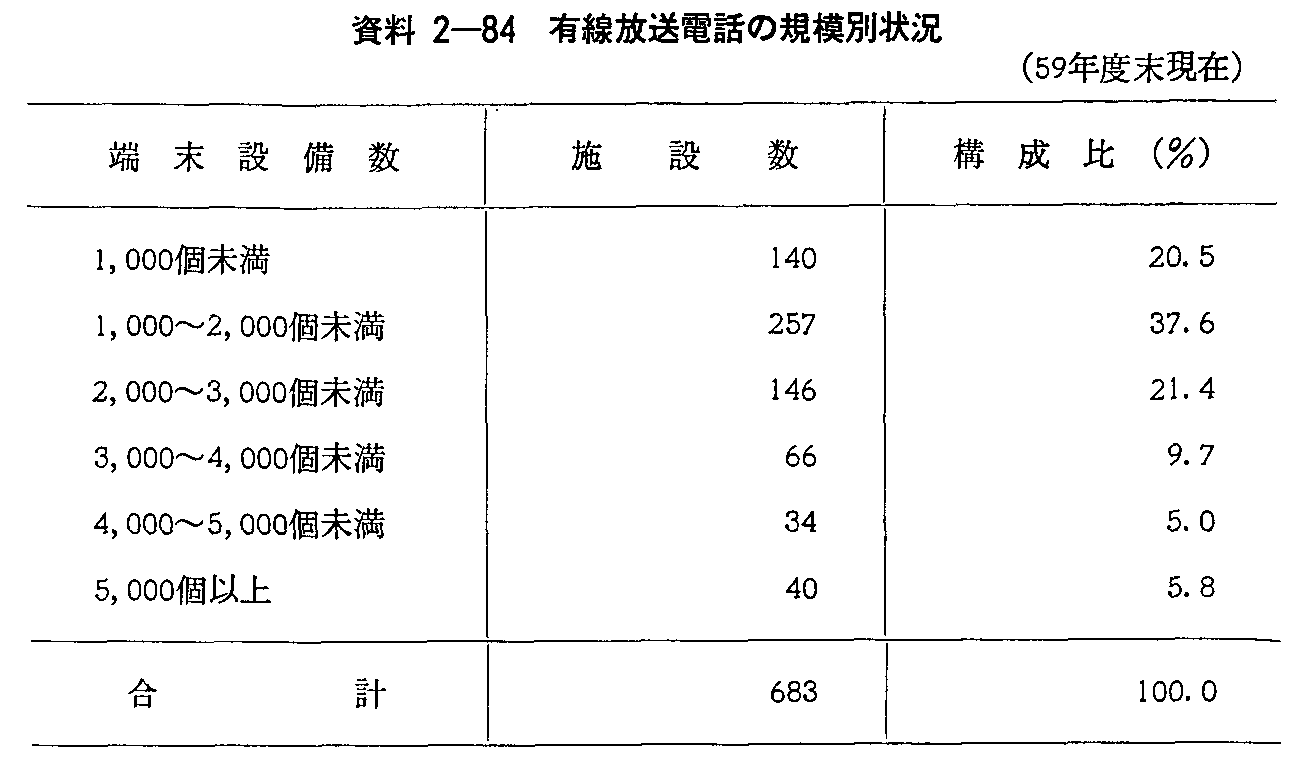
C 運営主体
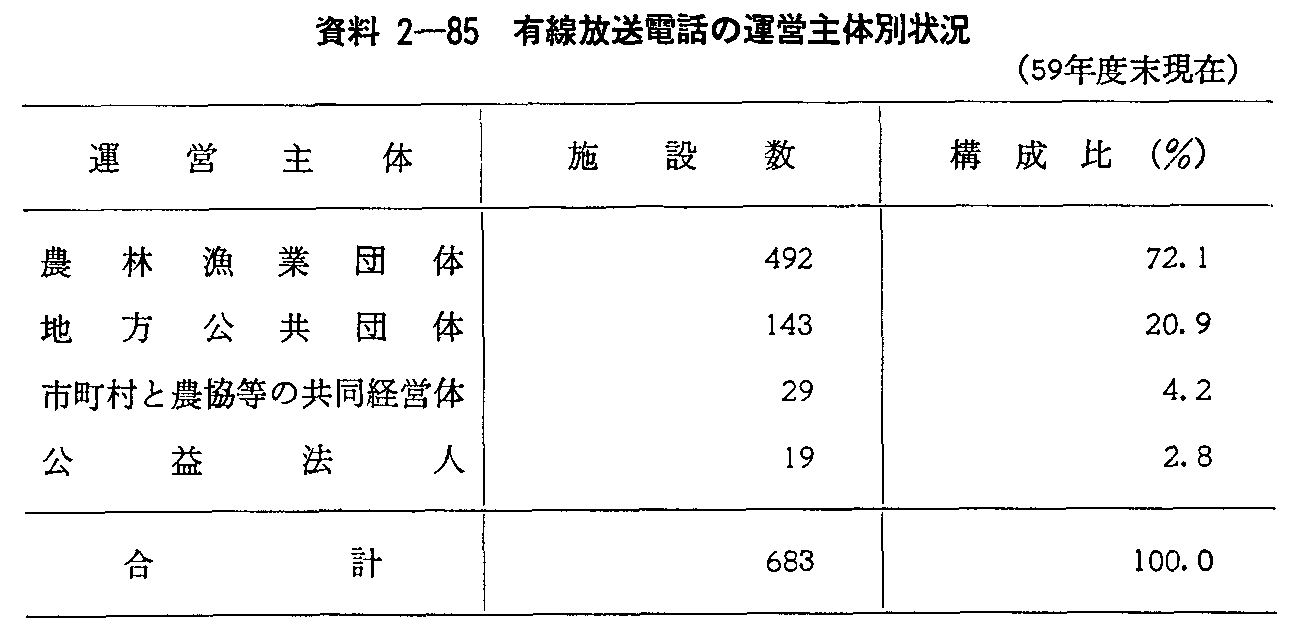
D 交換方式
自動交換方式をとっている施設は,59年度末において施設数で630,端末設備数で146万2千個である。
E 電電公社との接続施設
電電公社と接続通話契約を締結している施設は,59年度末において施設数で72,端末設備数で16万4千個である。
(イ)有線放送電話の利用状況
A 利用者数
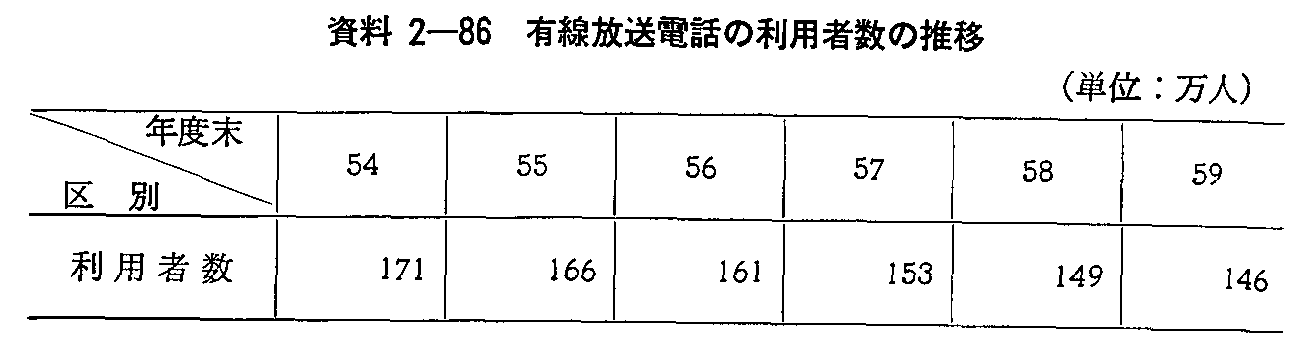
B 利用料
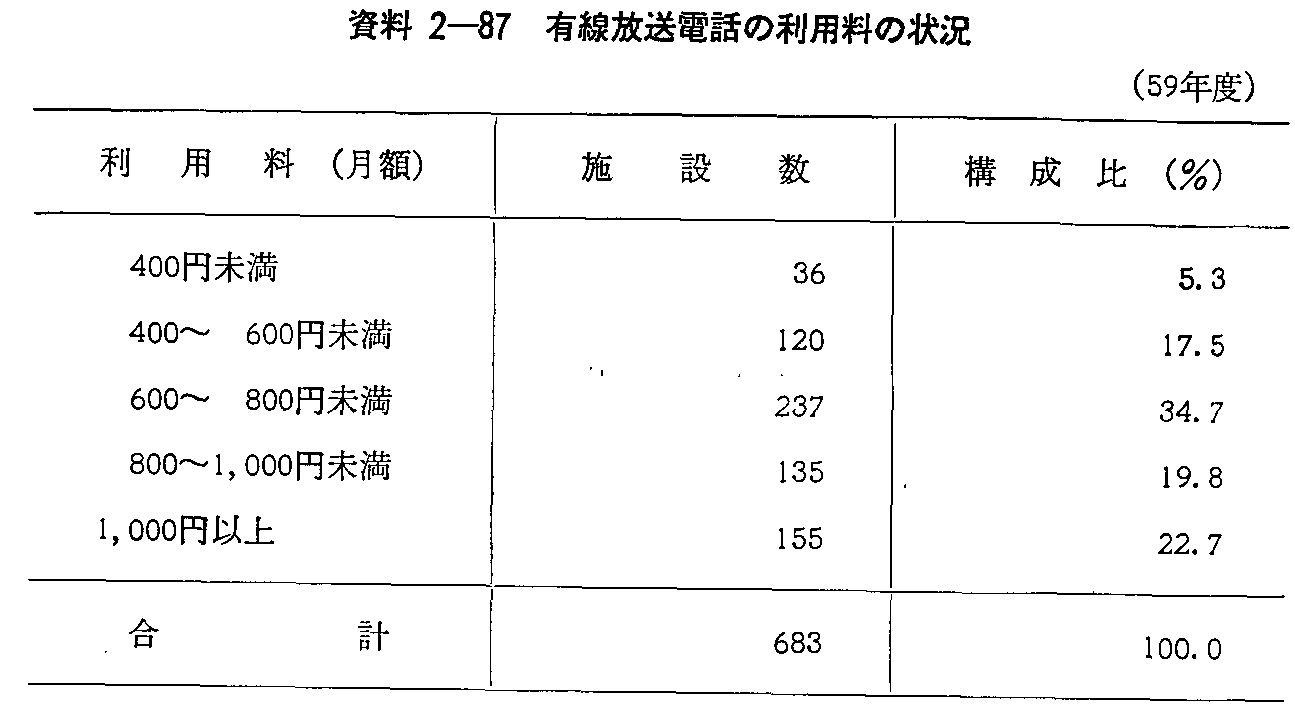
C 放送時間
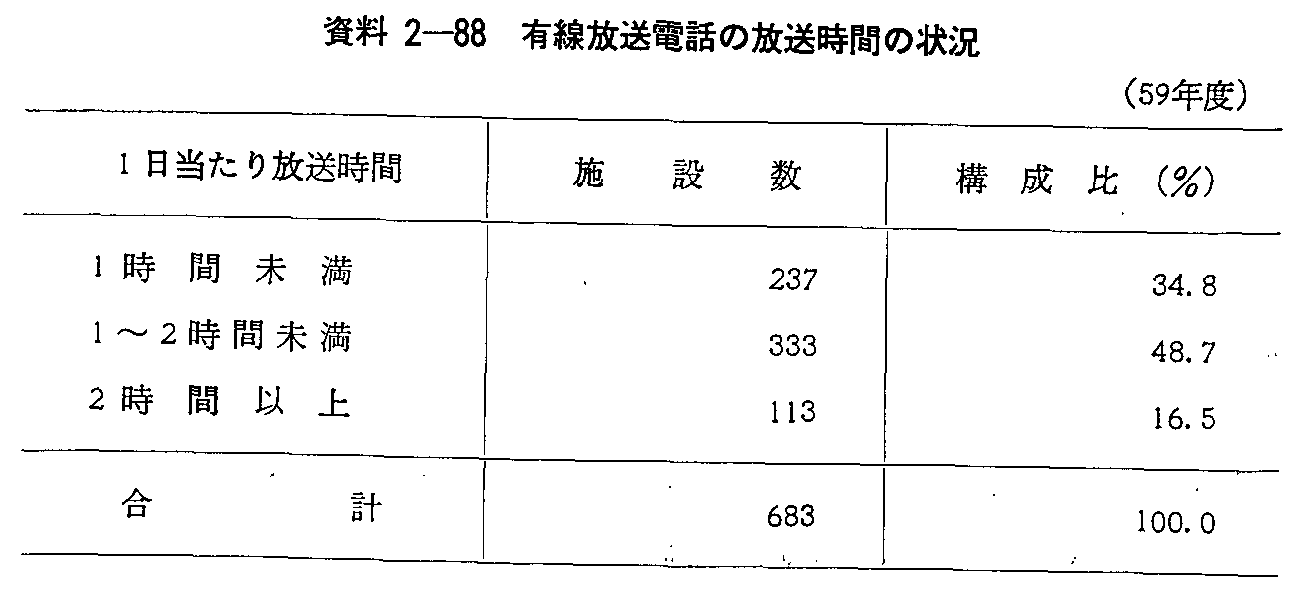
オ.事業経営状況
(ア)電電公社
A 収支状況
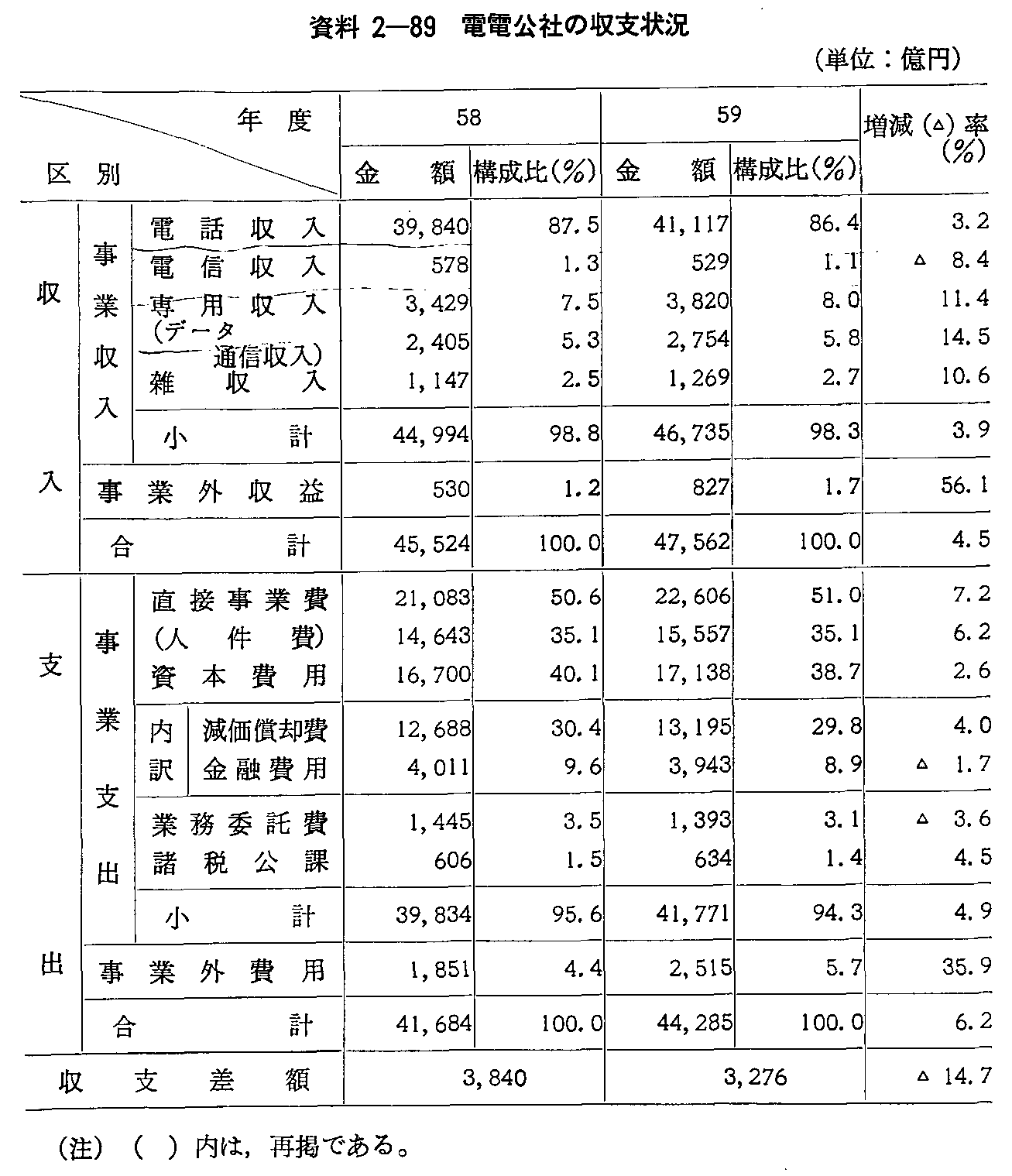
B 財務状況
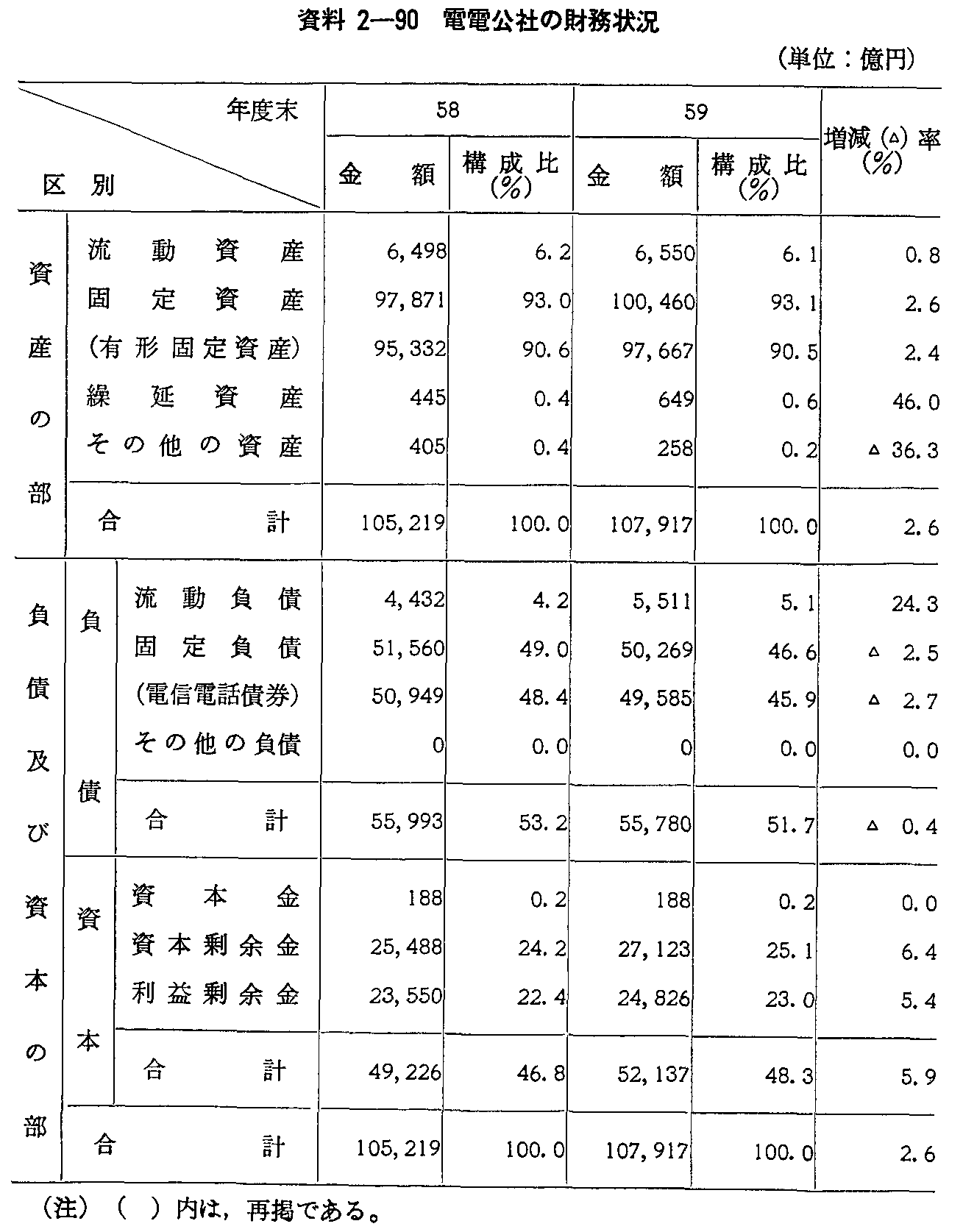
(イ)KDD
A 収支状況
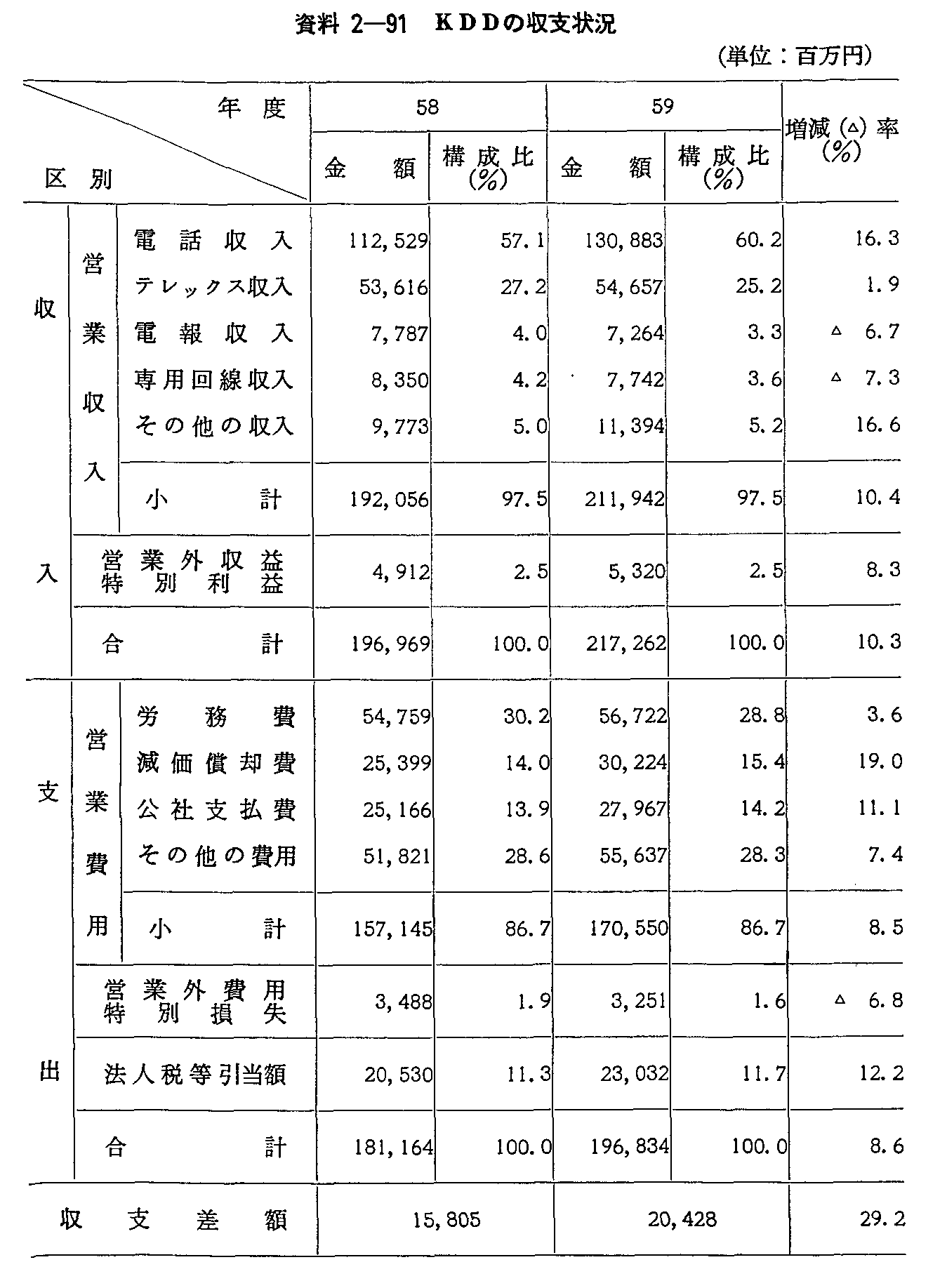
B 財務状況
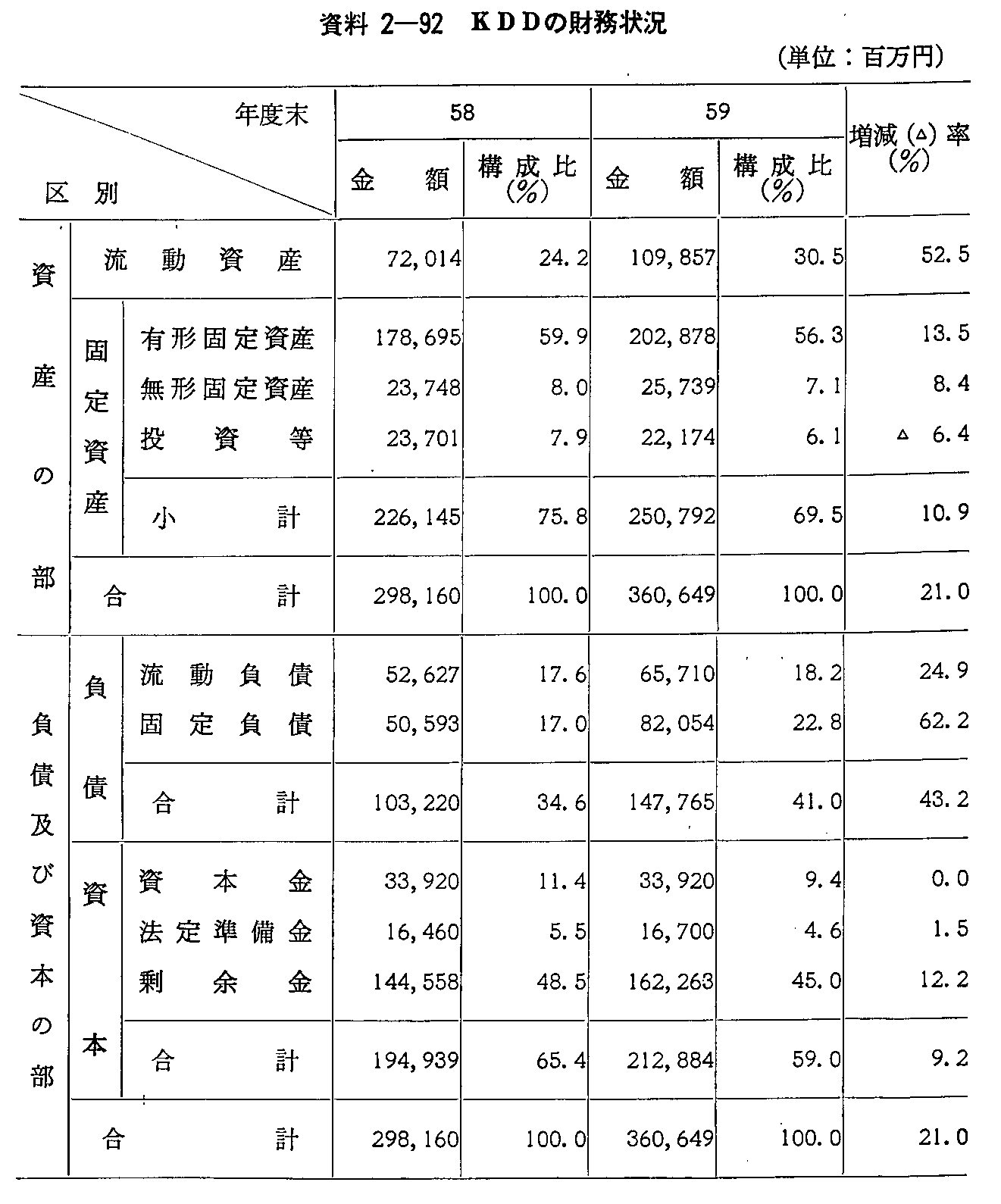
(ウ)有線放送電話事業
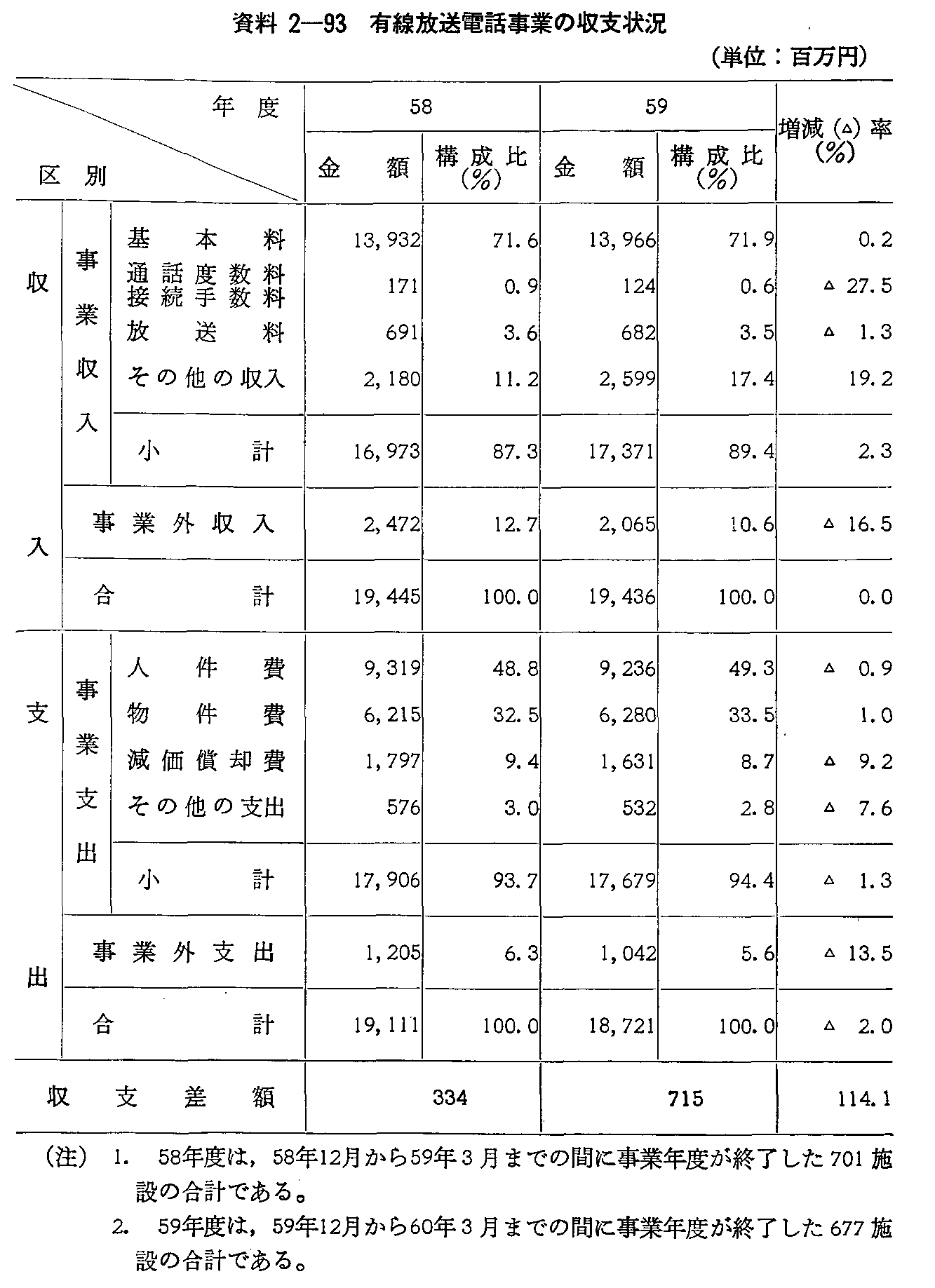
(2)自営電気通信
ア.無線通信の現況
(ア)無線通信の種類
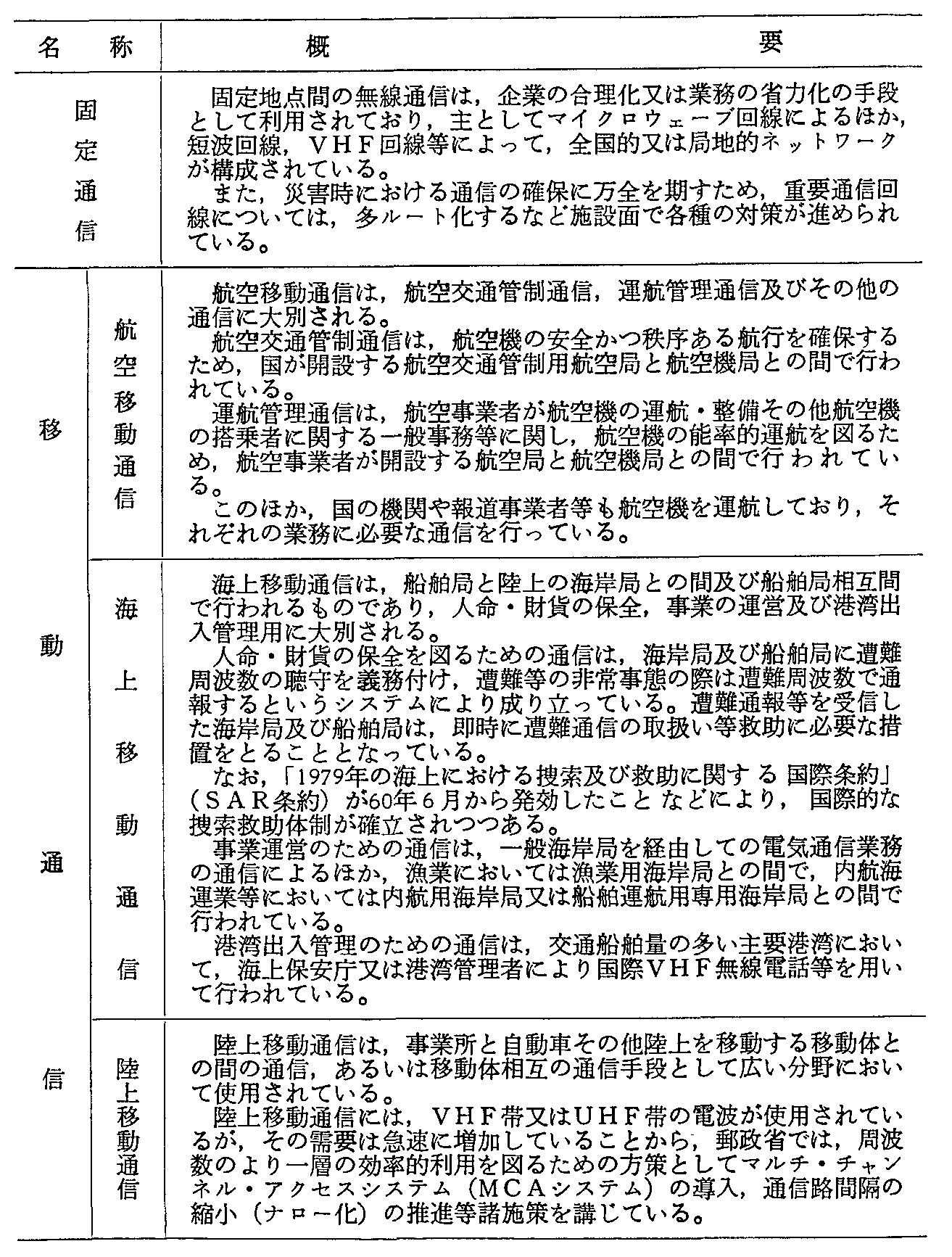
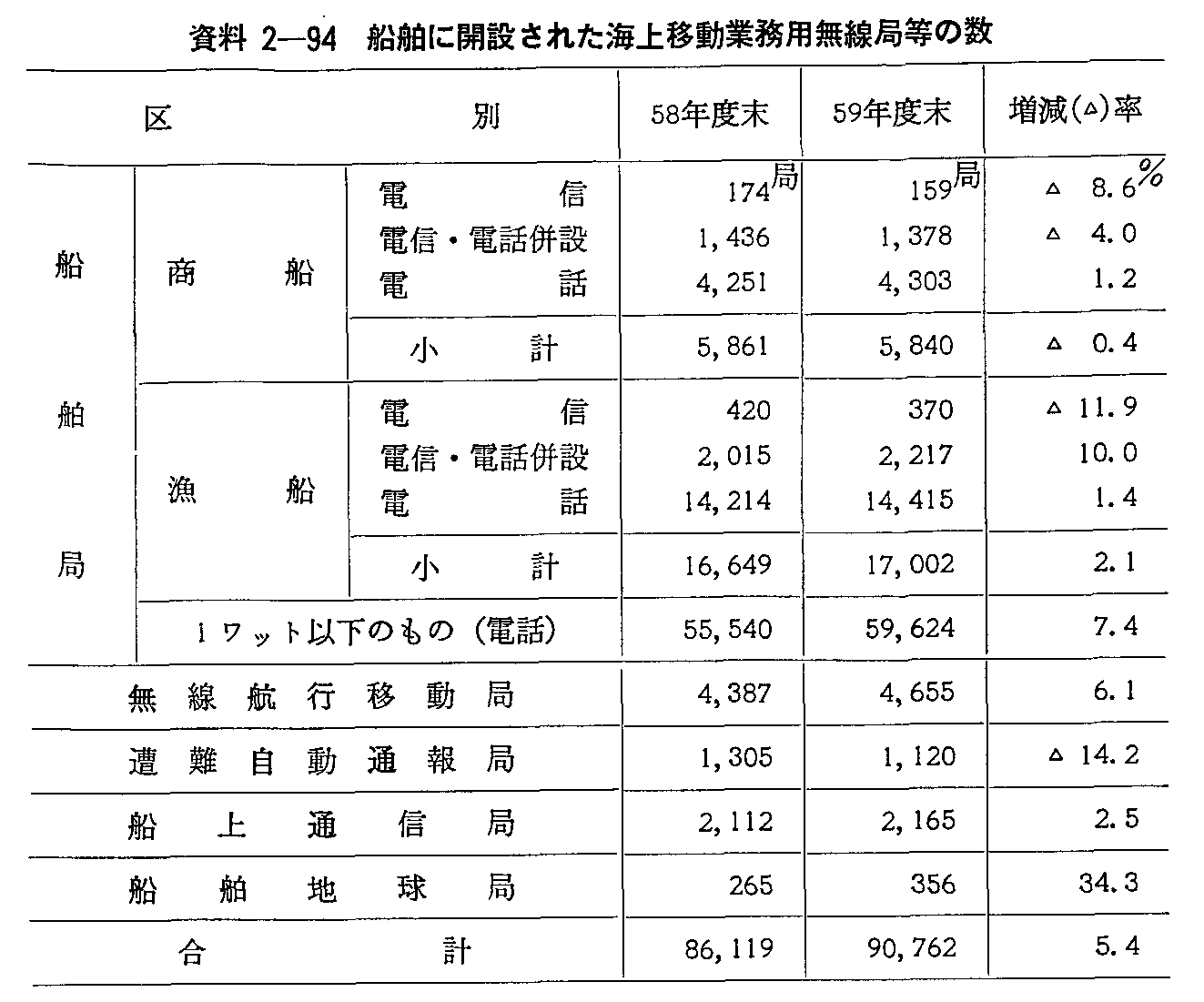
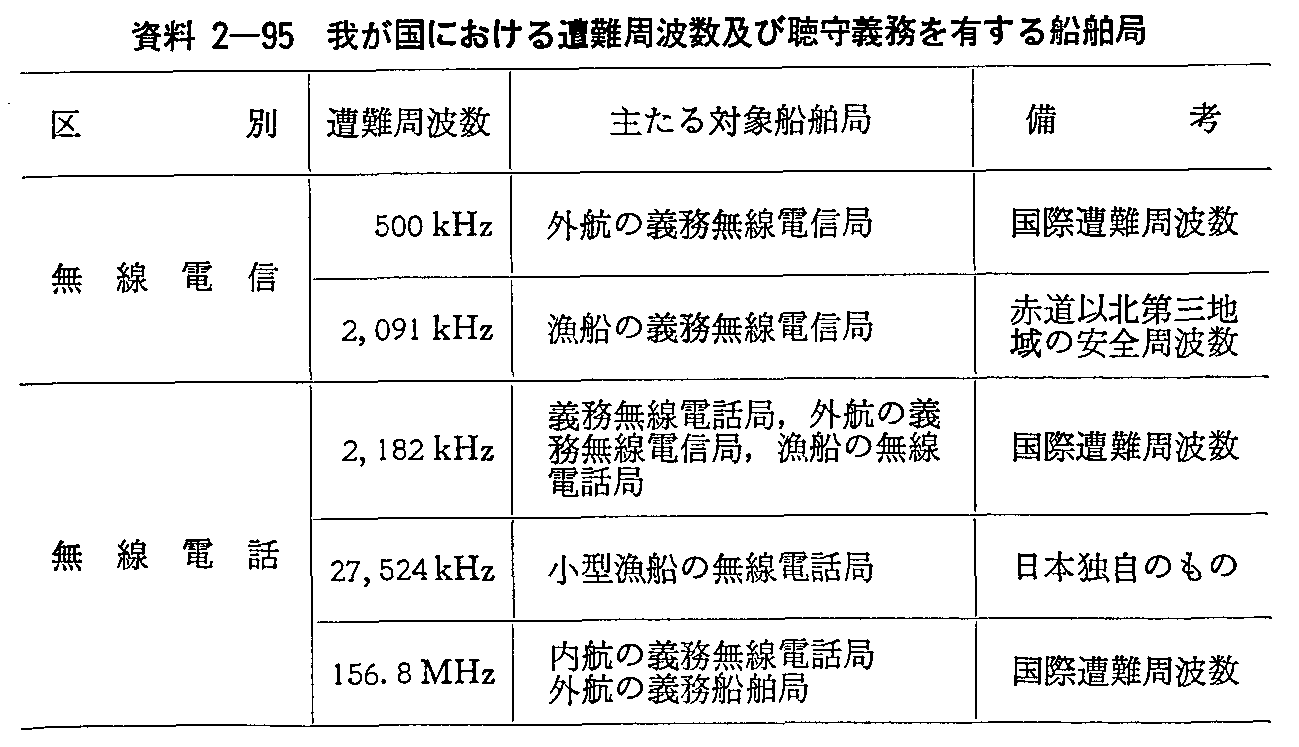
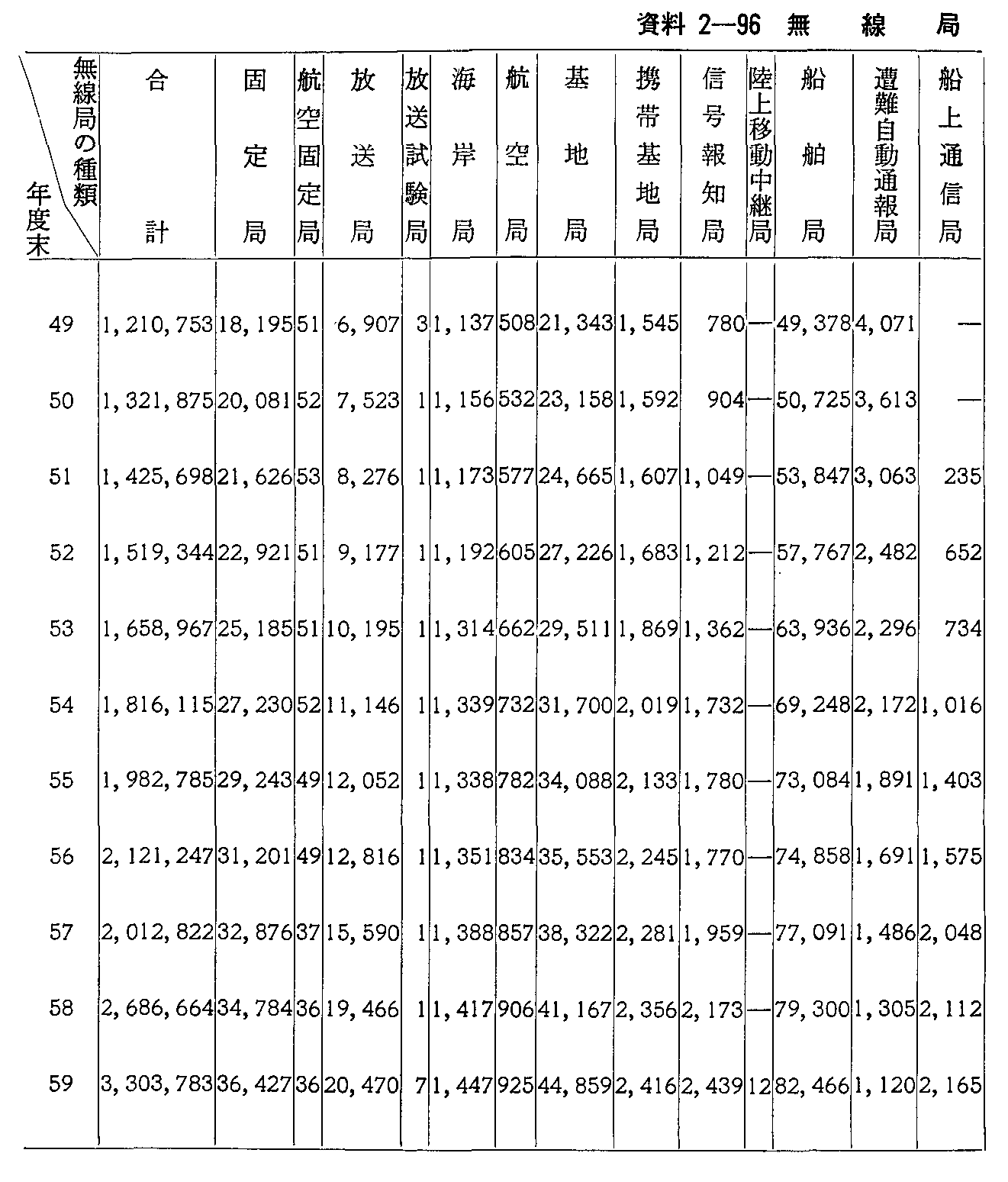
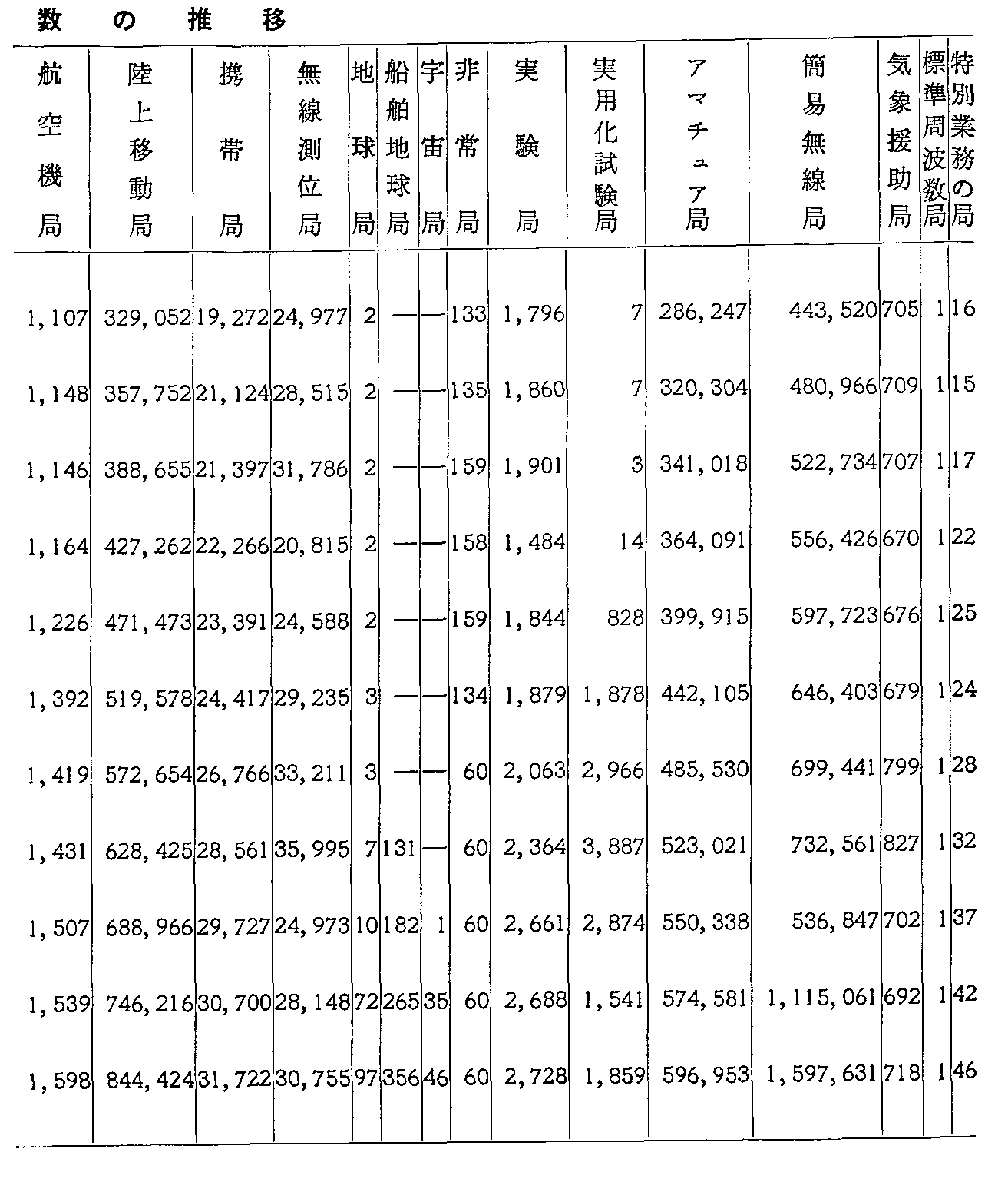
(イ)利用分野別無線局数
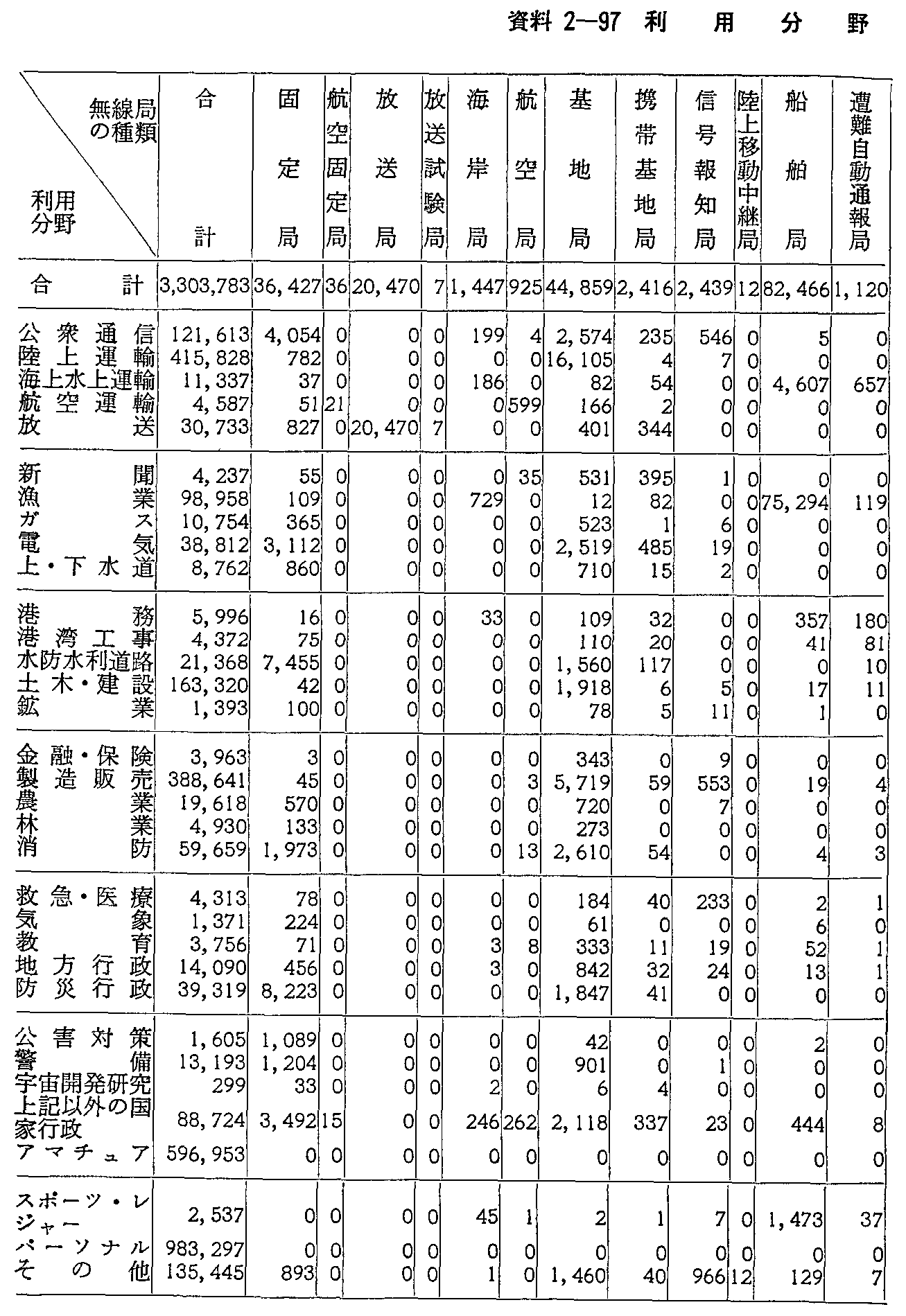
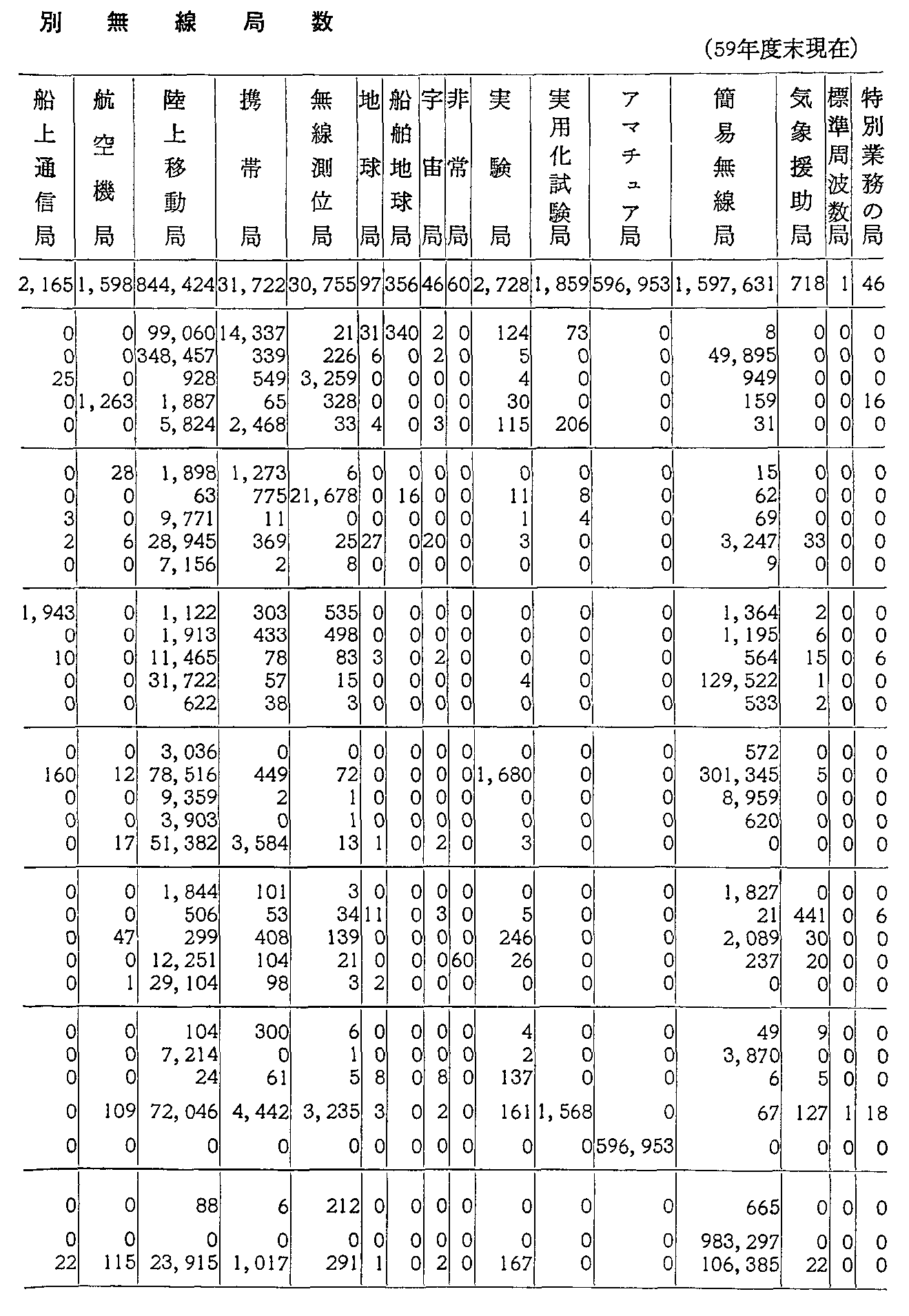
イ.有線電気通信の現況
(ア)設備の状況
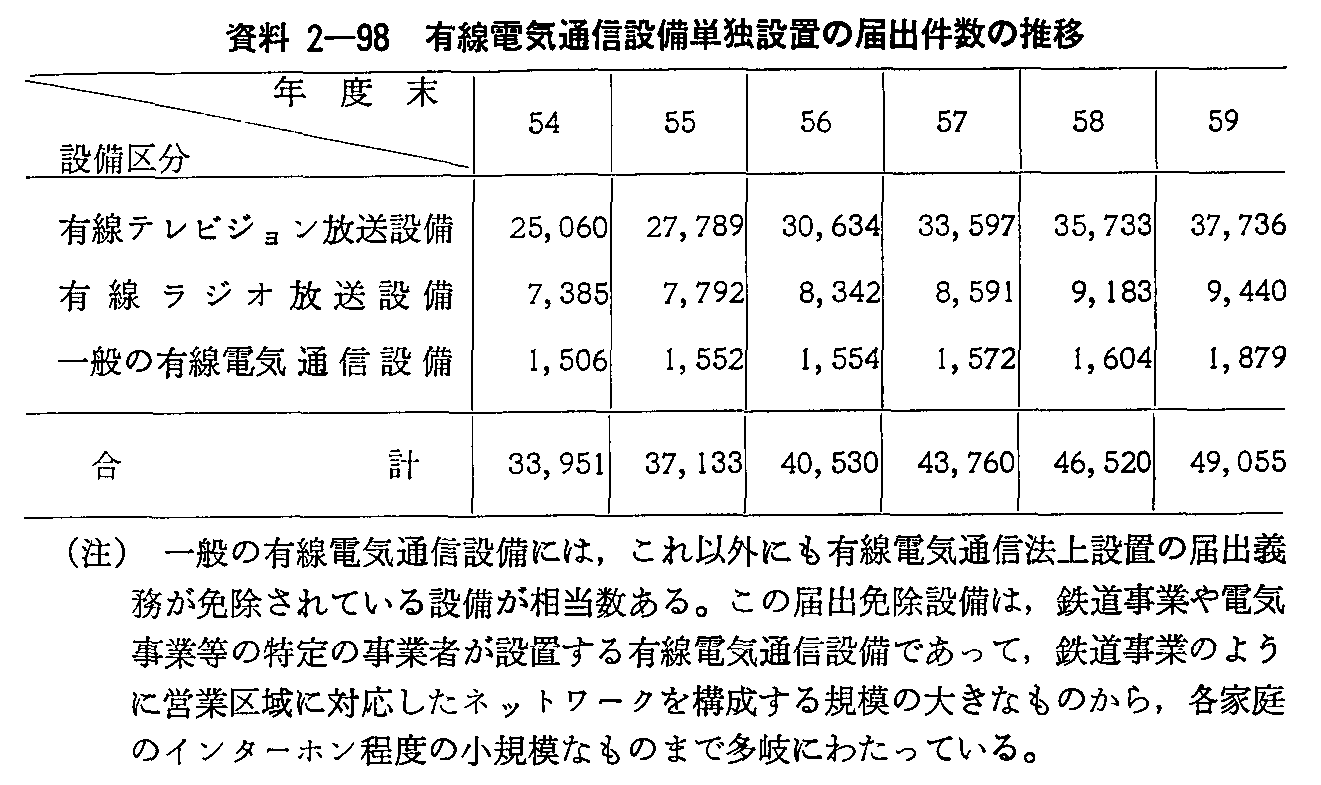
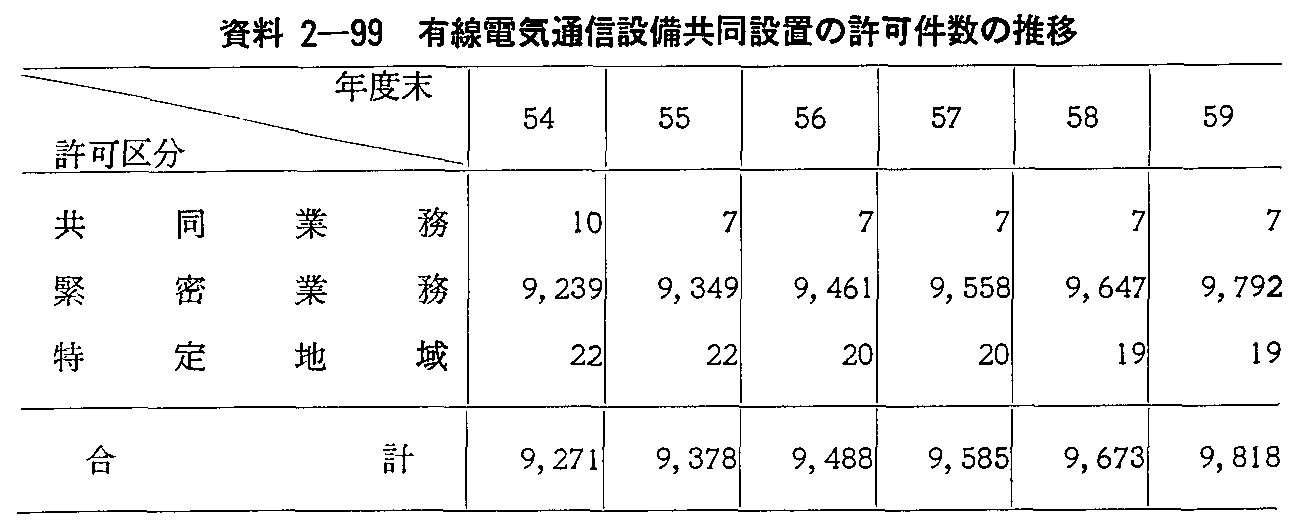
(イ)使用の状況
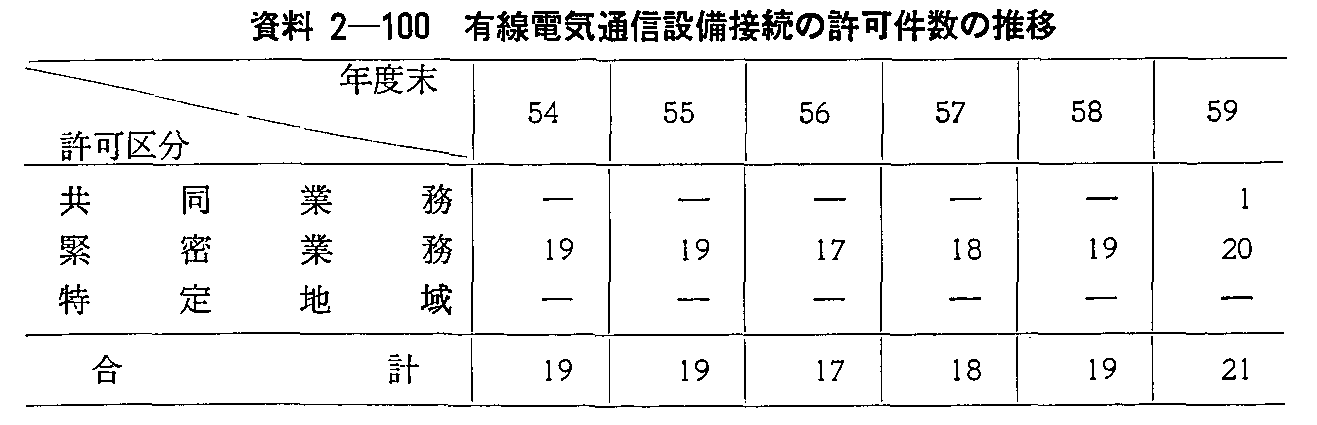
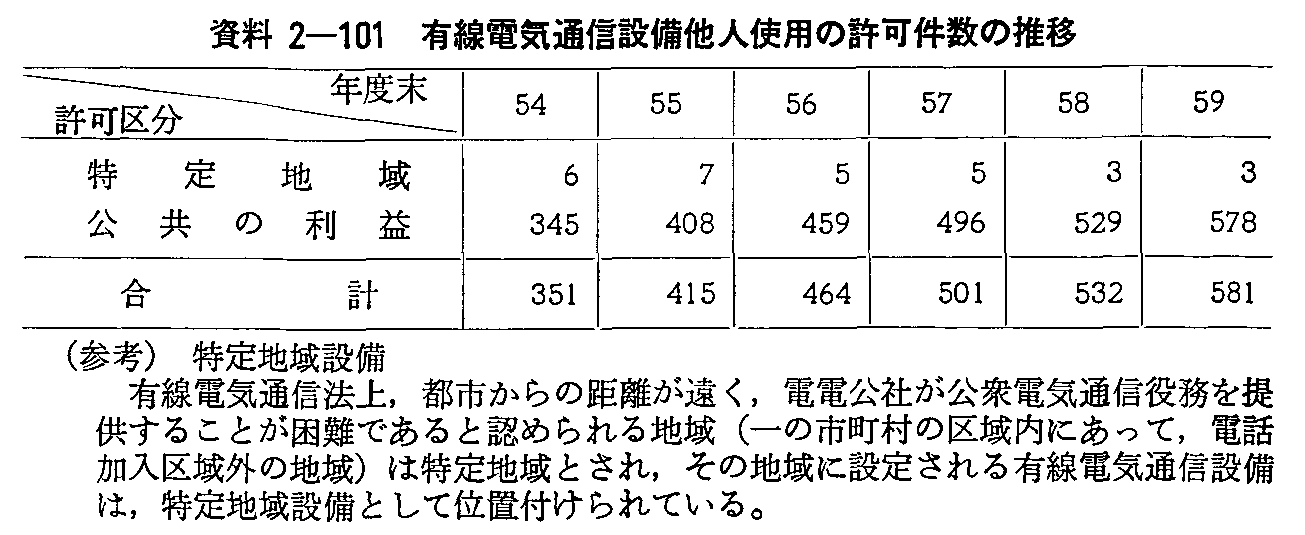
(ウ)事業別の利用状況
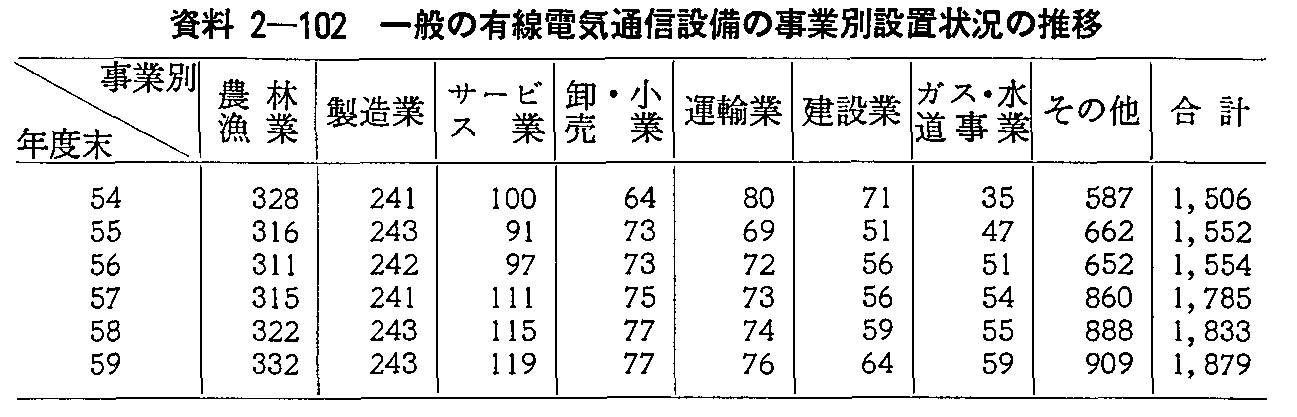
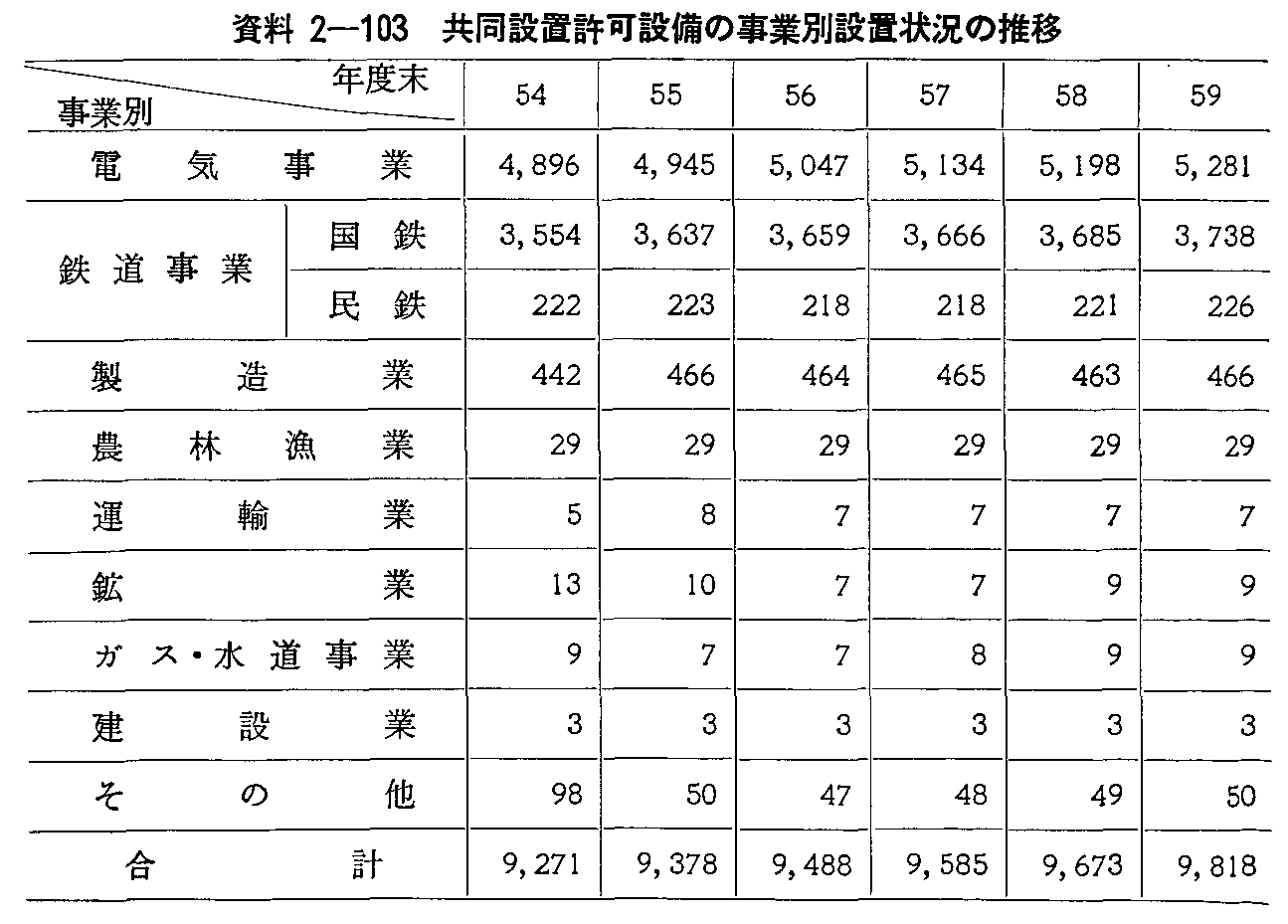
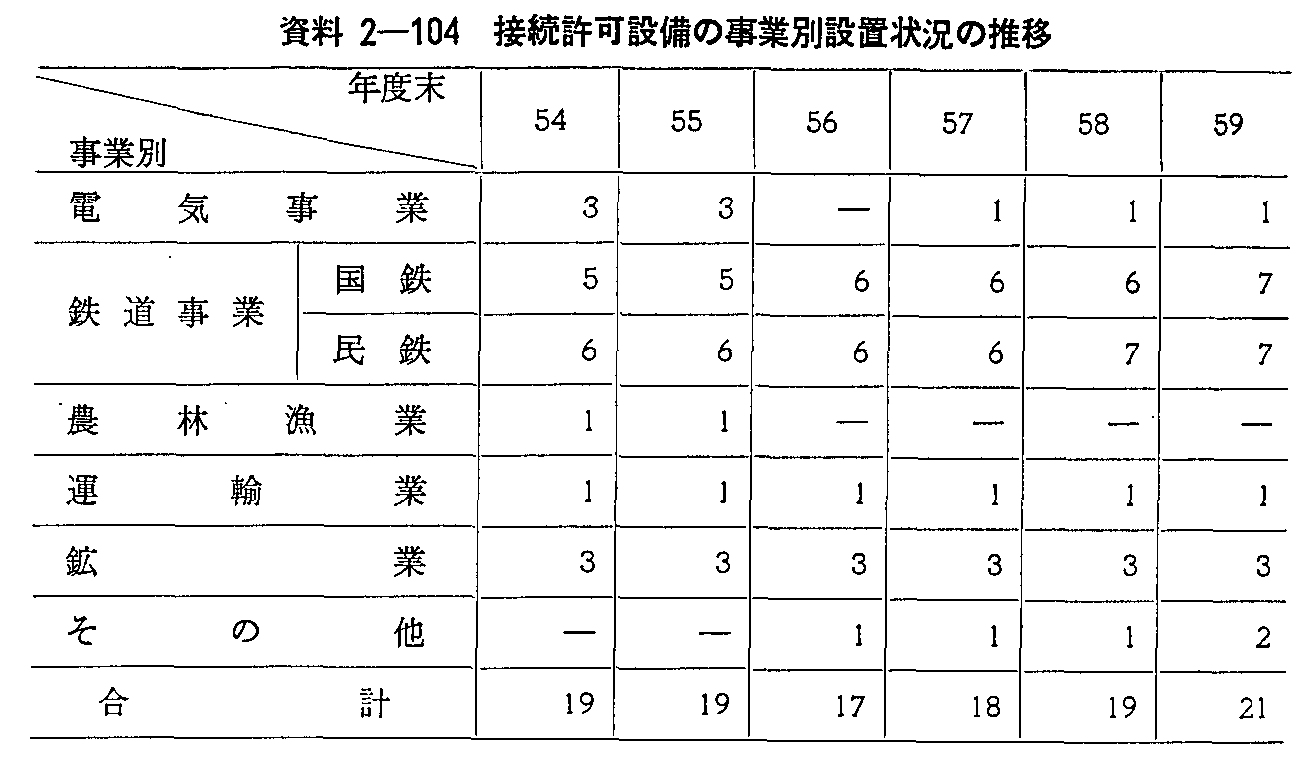
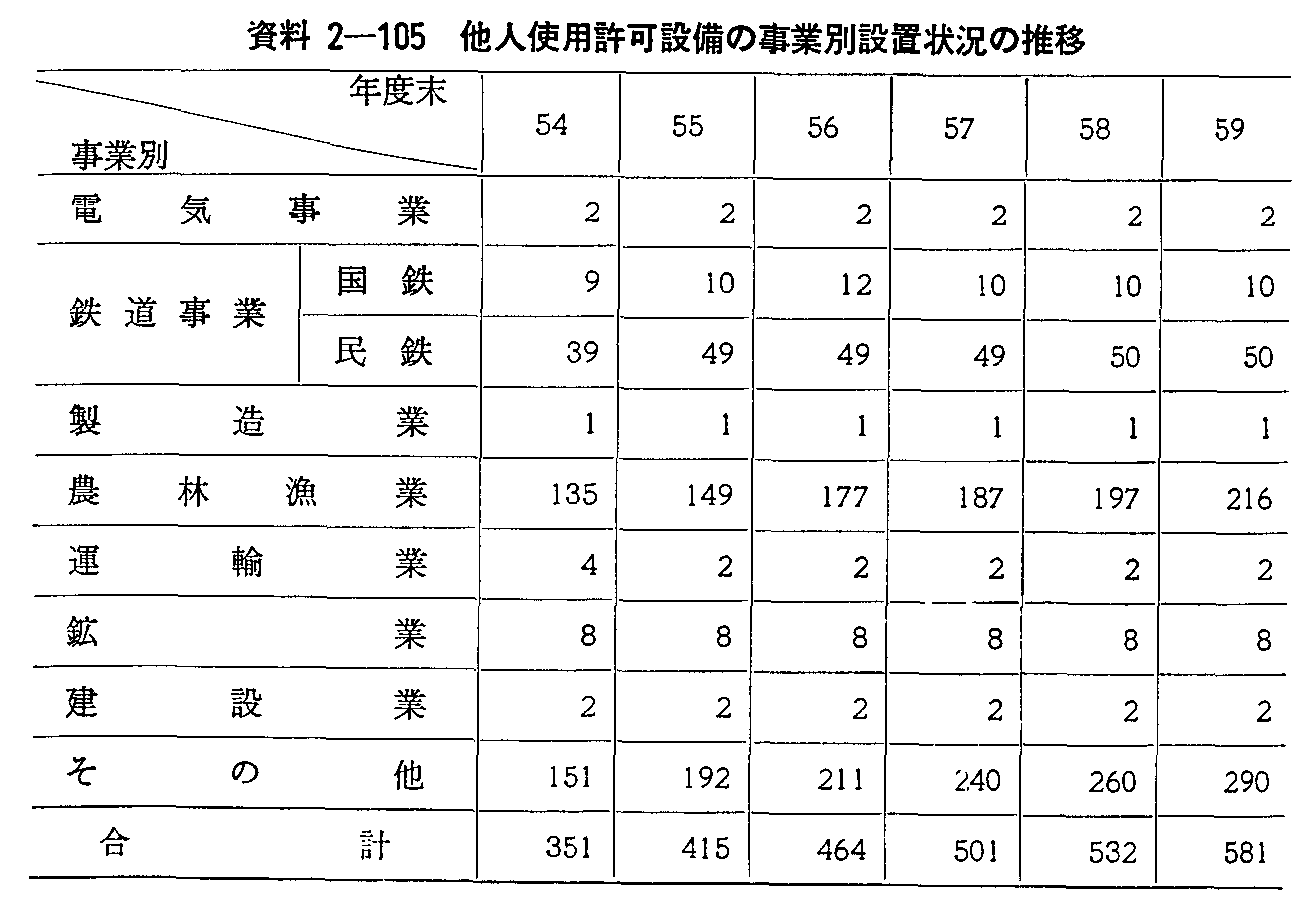
ウ.自営電気通信の分野別利用状況
(ア)警察用
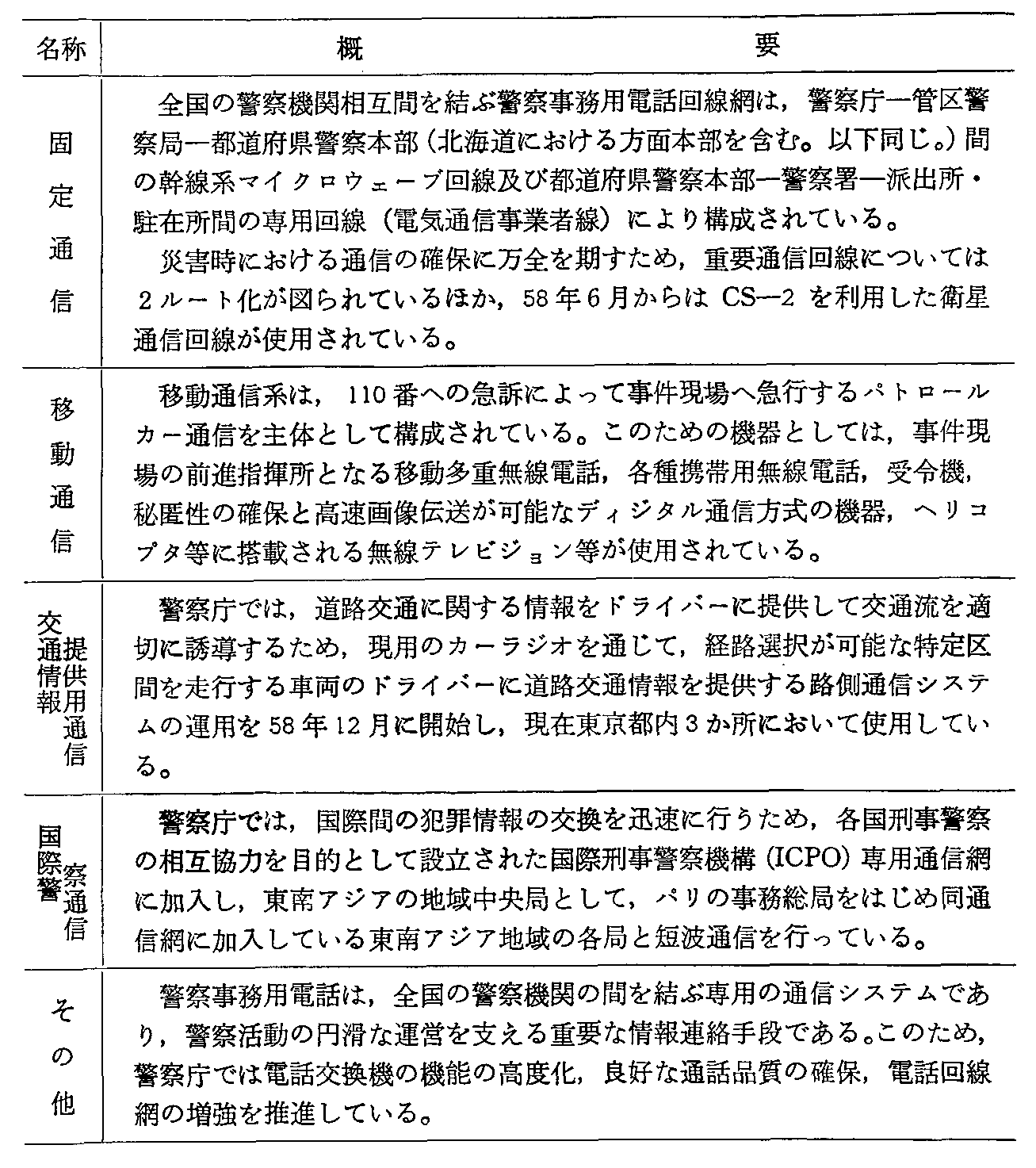
(イ)航空保安用
A 航空交通管制業務用通信
航空交通管制業務用通信は,航行中の航空機の衝突を防止し,航空交通の秩序正しい流れを保つために行われる通信であり,直接管制を行う移動業務用と管制機関相互間に設定された固定業務用の無線電話に大別される。
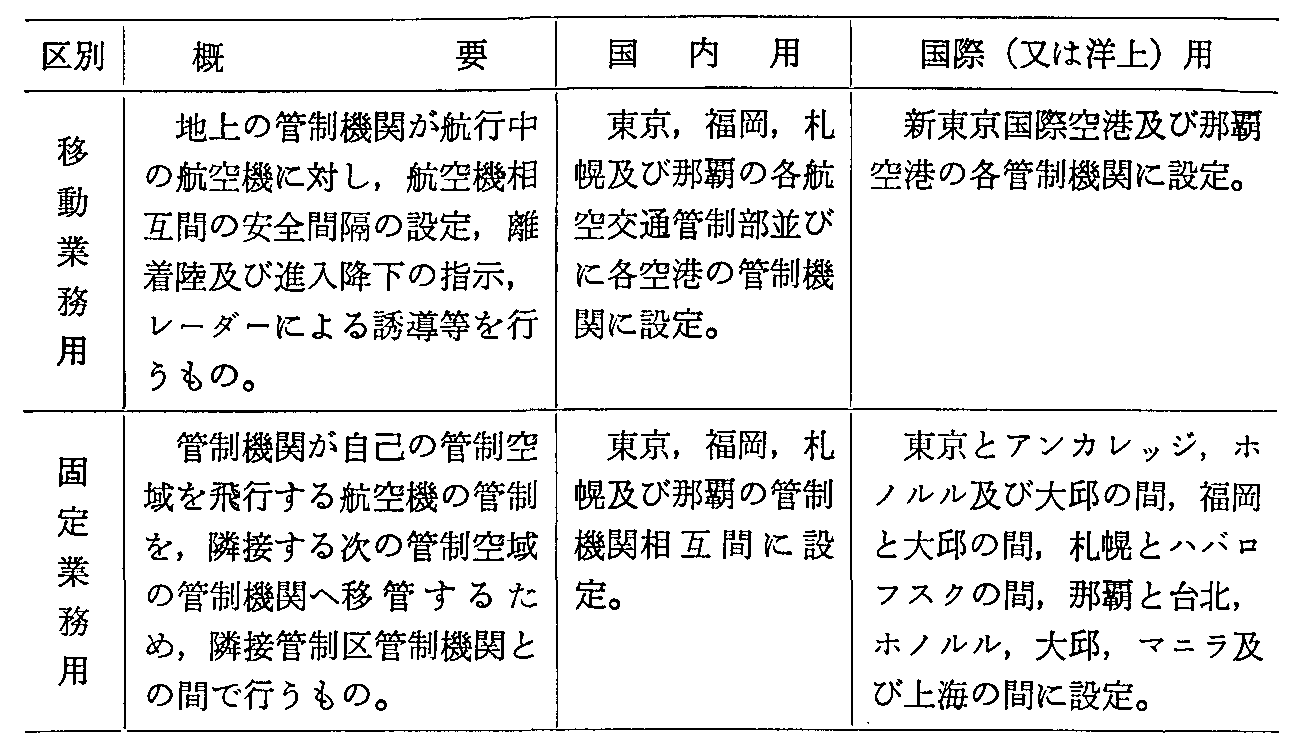
B 飛行情報業務用通信
飛行情報業務用通信は,航行の過程において必要な気象情報,航空保安施設の運用状況等を得るためのものであり,飛行場及び航空路情報提供用通信がある。また,これらの飛行情報は,他の必要な通報とともに固定電信網により各空港及び管制部に送られている。
(A)飛行場情報提供用通信及び航空路情報提供用通信
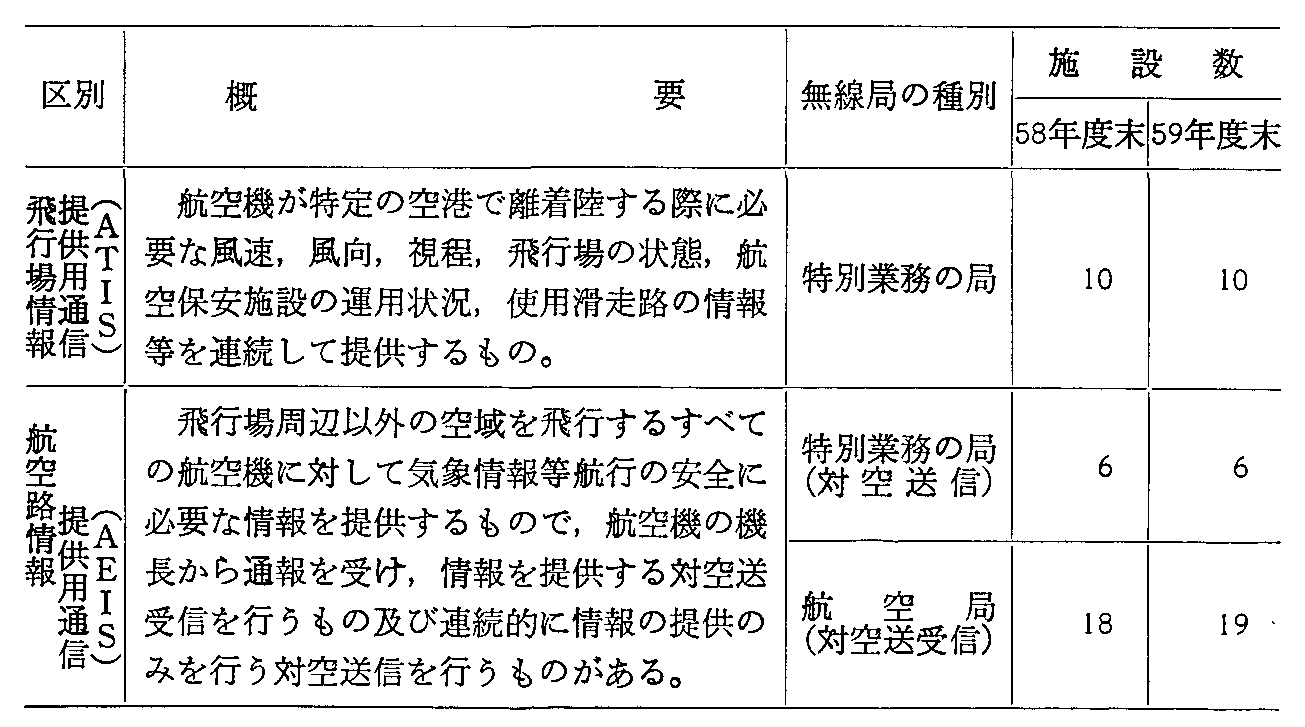
(B)航空固定電信網
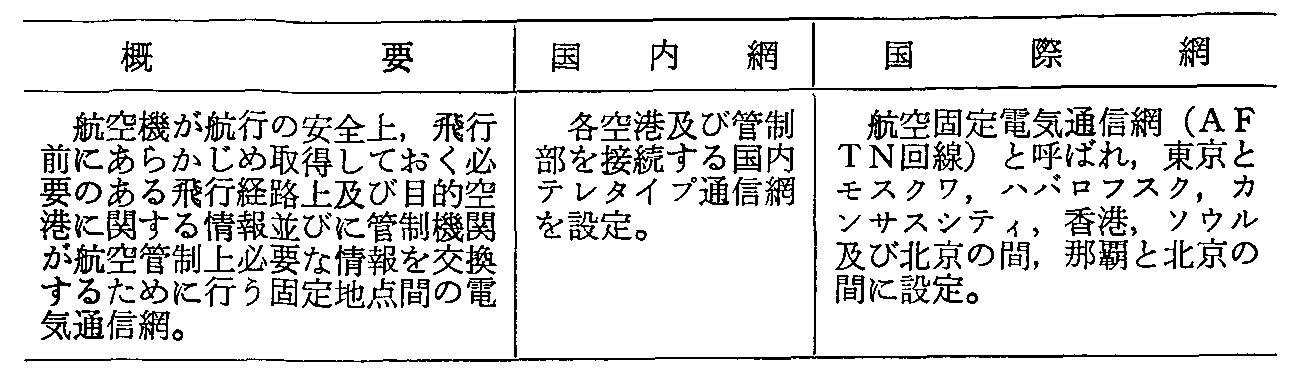
C 航空無線航行用通信
航空機は,パイロットの目視によるほか,地上の航空保安無線施設及び機上の無線航行装置を利用することにより自機の針路,位置,速度,高度等を確認し,安全航行を行っている。また,地上では,航空管制を行うためレーダーにより航空機の種類,位置,高度等を確認している。
(ウ)海上保安用
A 海難救助及び航行の安全等に関する通信
海上保安庁では,全国の海岸局及び行動中の巡視船艇の船舶局において,中波帯,中短波帯等の遭難周波数を常時聴守しており,遭難信号等が受信されたときは,直ちに海難救助に当たる体制をとっている。
また,SAR条約の発効に伴い船舶の動静を把握し,遭難時における捜索救助活動を容易にするための船位通報制度を,60年10月から発足させ,遠距離海域の船舶との通信を行うため短波海岸局を新設した。
さらに,海上交通安全法に基づく巨大船等の航行管制のための通信,港則法等に基づく入出港,検疫等に関する通信等を行うとともに,「世界航行警報業務システム」に基づく北太平洋西部及び東南アジア海域を対象区域とする航行警報の送信を行うほか,海上の気象,海象等の予報及び警報を全国の主要海岸局等から船舶へ送信するとともに,主要無線方位信号所(無線標識局,特別業務の局等)等から局地的な気象・海象の通報を行い,航行船舶の安全に役立てている。
同庁では以上のような海上保安通信体制の充実強化及び施設の近代化を図るため,海岸局等の統合再編成及び固定回線網の拡充を順次進めることとし,59年度から北海道東部地区の整備を行っている。
B 航行援助等に関する通信
海上保安庁では,電波を利用した各種の航行援助施設を設置し,船舶交通の安全に寄与している。特に,デッカについては,60年度から,北陸デッカチェーンの運用が開始されたことにより,南西諸島及び小笠原諸島を除く我が国周辺海域をカバーするに至った。
また,東京湾内においては,観音埼等に設置されたレーダーと本牧等の港内に設置されたITVを用いて船舶の動静を把握し,これら海域を航行する船舶に対して国際海上VHF無線電話及び中短波無線電話により海上交通に関する情報の提供を行うとともに,国際海上VHF無線電話により航行管制を行っている。瀬戸内海地区でも同様な業務を行うため,無線施設の整備を進めている。
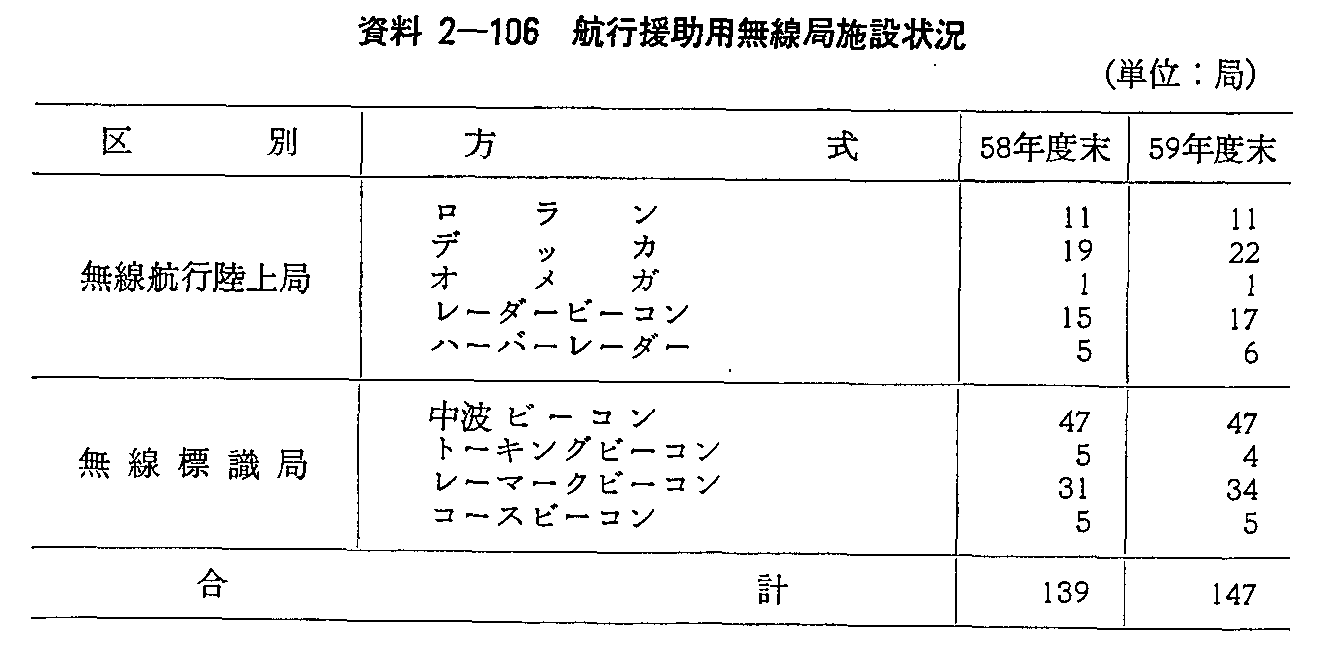
(エ)気象用
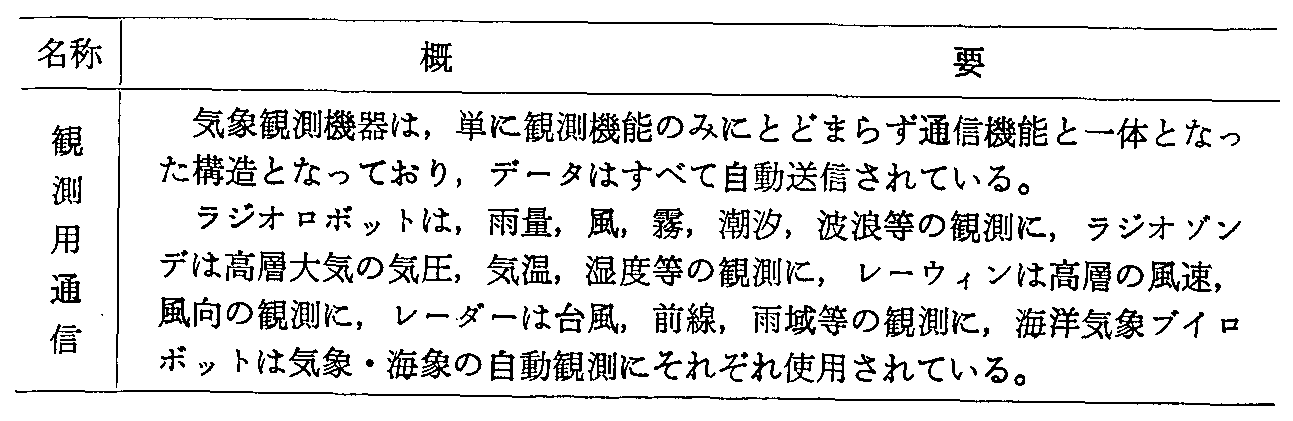
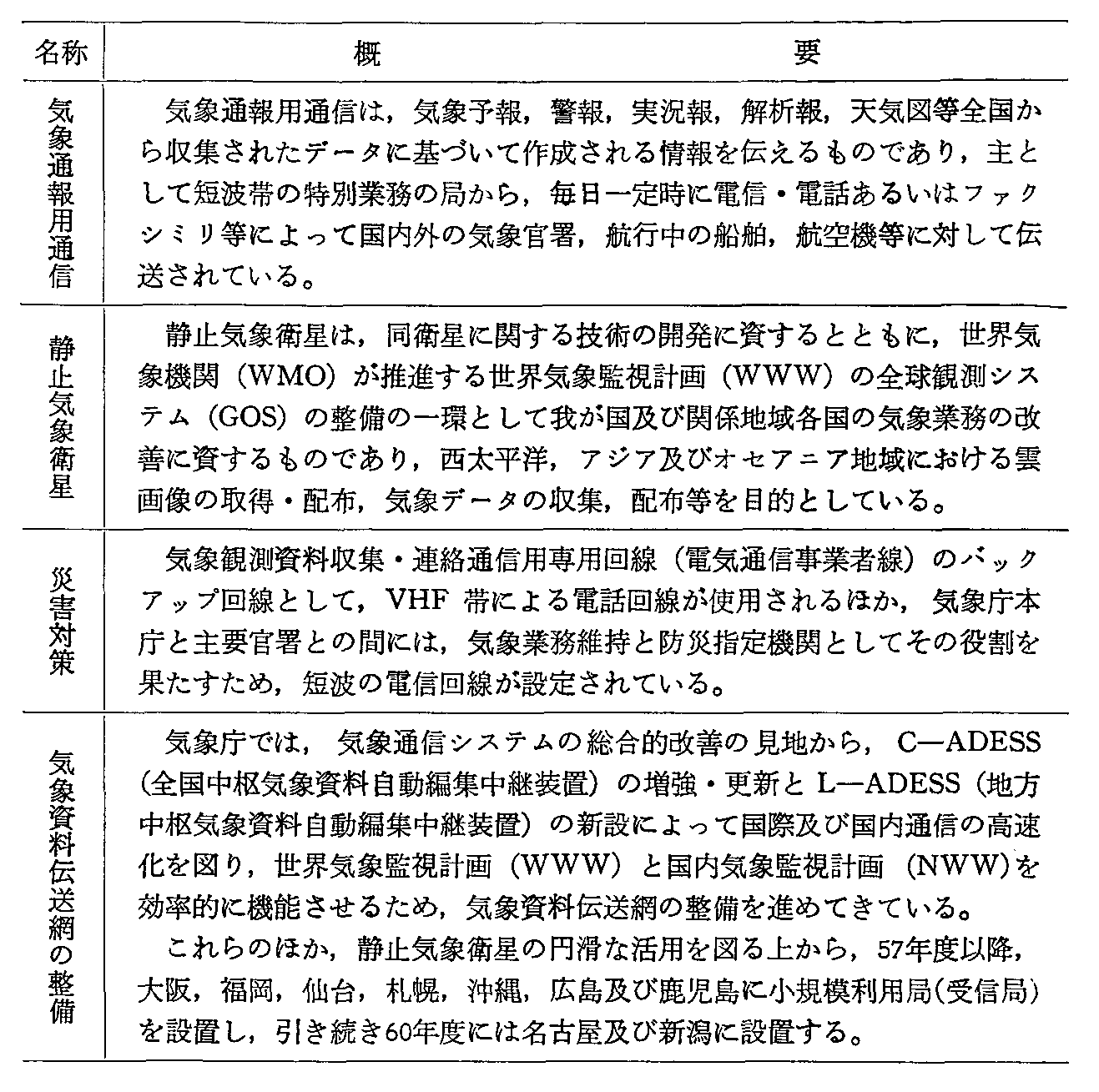
(オ)防災用
A 水防・道路用通信
建設省では,河川,ダム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため,水防・道路用無線局を開設し,災害の予防,応急対策,復旧,その他維持管理等に関するデータの収集,状況連絡,指示等の情報伝達用として活用している。
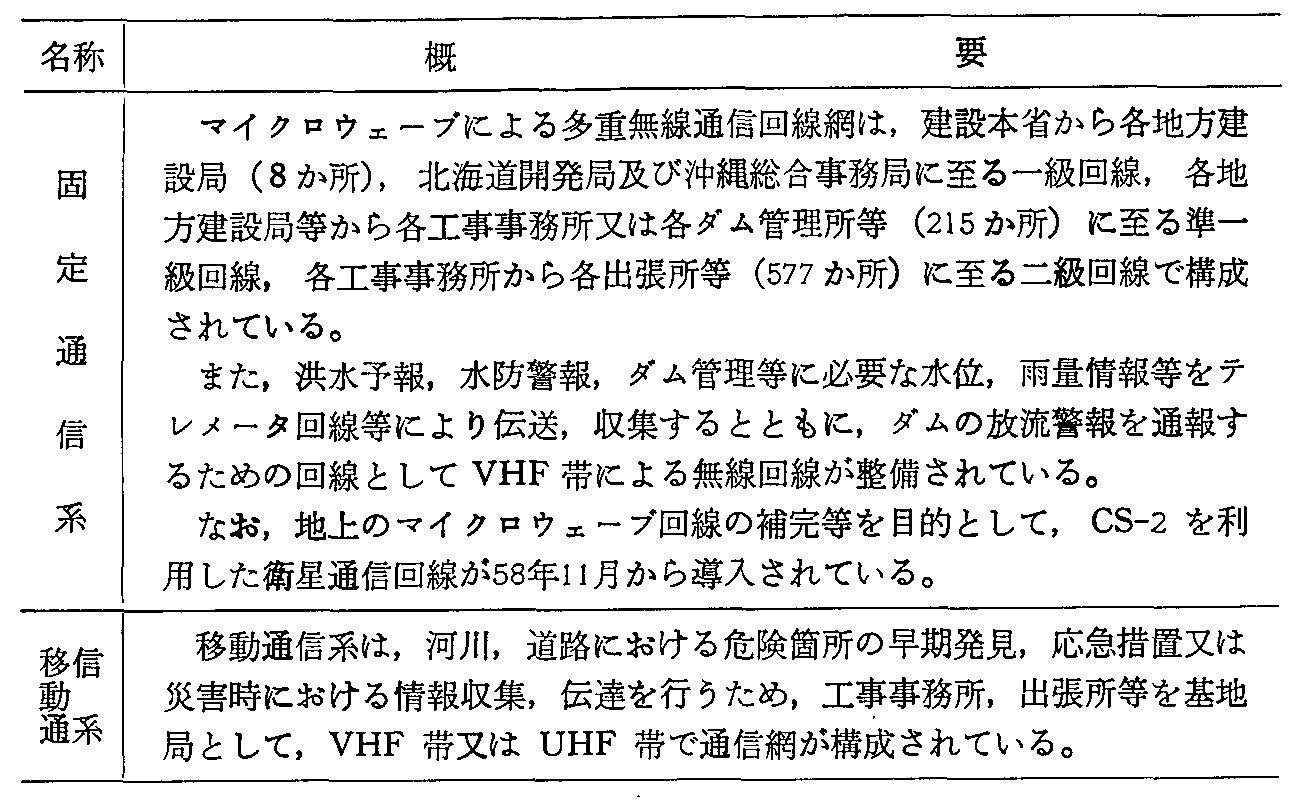
B 中央防災用通信
国土庁では,防災対策の一環として,平素における災害関係事務の調整,非常災害時における災害情報の収集,伝達のため,防災関係の指定行政機関(58年度末現在,国土庁,内閣官房(総理官邸)等28省庁)及び指定公共機関等(同日本国有鉄道,電電公社等20機関)相互を多重無線回線で結ぶ中央防災無線網の整備を53年度から進めてきたところであるが,59年度末をもって完成した。
なお,現在までの中央防災無線網におけるシステム構成は,国土庁に設置した自動交換機を介して,各関係機関に設置したファクシミリ及び電話機相互でダイヤル自動即時通話が可能となっており,また,自動交換機と端末装置を結ぶ回線は,同一庁舎内等の近距離回線を有線とするほかは,無線化されている。
C 防災行政用通信
防災行政用無線には都道府県が開設するもの,政令指定都市が開設するもの及び市町村が開設するものがある。いずれも防災関係業務に利用するのみならず,平常時には一般行政事務に利用することが認められている。
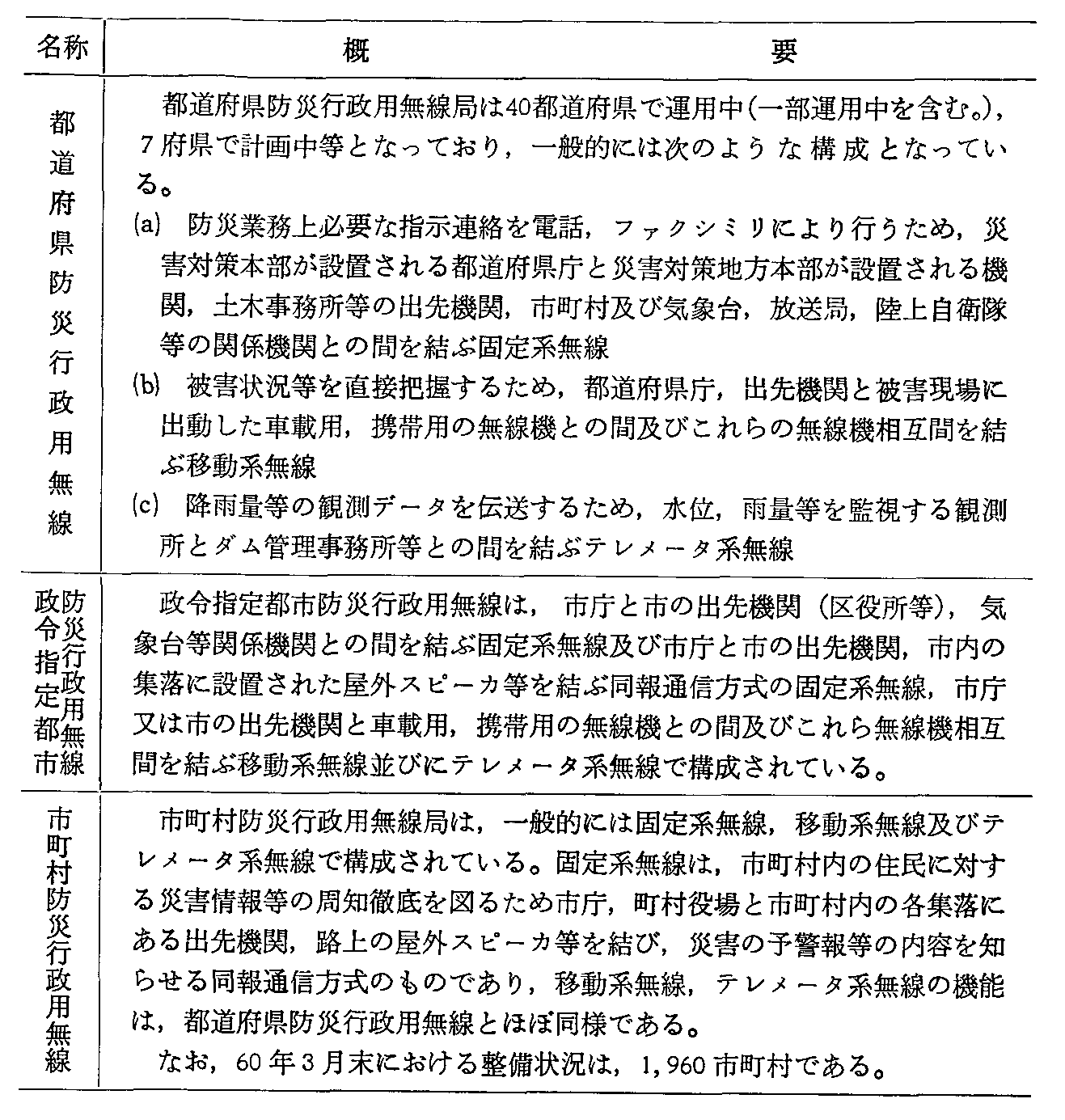
D 消防防災無線
消防防災無線は,国と地方公共団体との間で地震予知情報等の一斉伝達,災害報告,火災速報等の消防情報の収集及び伝達を行うためのものである。
消防庁は,水防・道路用無線として建設省が開設した全国マイクロウェーブ回線の一部を共用し,全国47都道府県との間に,それぞれ直通の消防防災用の通信回線(電話及び高速ファクシミリ)を設置している。
また,消防庁では,上記通信回線の多ルート化対策の一環として59年秋からCS-2を利用した衛星通信回線を導入している。
E 消防・救急用通信
地方公共団体は,消防の常備化を進め,広域化する消防・救急・救助活動を円滑に遂行するため,消防本部と消防署等の間に専用回線(電気通信事業者線)による消防事務用電話を設置するとともに,消防本部,消防署等に基地局,固定局を,消防車,救急車,ヘリコプタ等には陸上移動局又は携帯局を開設している。
このような消防機関による無線通信の利用が今後一層高まるものと予想されることから,郵政省では58年12月に当該無線局の免許方針を改正し,割当周波数の増波,利用範囲の拡大,消防団に対する専用波の割当て等の措置を行った。
F 防災相互通信用通信
防災相互通信用無線局は,石油コンビナート,市街地等で災害が発生した場合に災害現場で行政機関,公共機関,地方公共団体及び地域防災関係団体の防災関係機関が協力して防災対策に必要な情報を迅速に交換し円滑な防災活動を実施するためのもので,59年末現在全国で6,846局の無線局が運用されており,すべて移動系である。
(カ)航空運送事業用
A 固定通信系
定期航空運送事業者は,本社,支店,営業所及び旅行代理店の各部門の端末機と計算機センタの大型コンピュータとを特定通信回線で結ぶデータ通信システムを導入し,座席予約,運航情報,フライトプラン,気象情報等の各情報を伝送するほか,資材管理,営業統計の分析等に利用している。
また,海外の国際路線就航機の乗り入れ地については,国際電気通信回線又はSITA(国際航空通信協同体:Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques)の回線を利用して,テレタイプ糸を含め,データ通信網が構成されている。
B 移動通信系
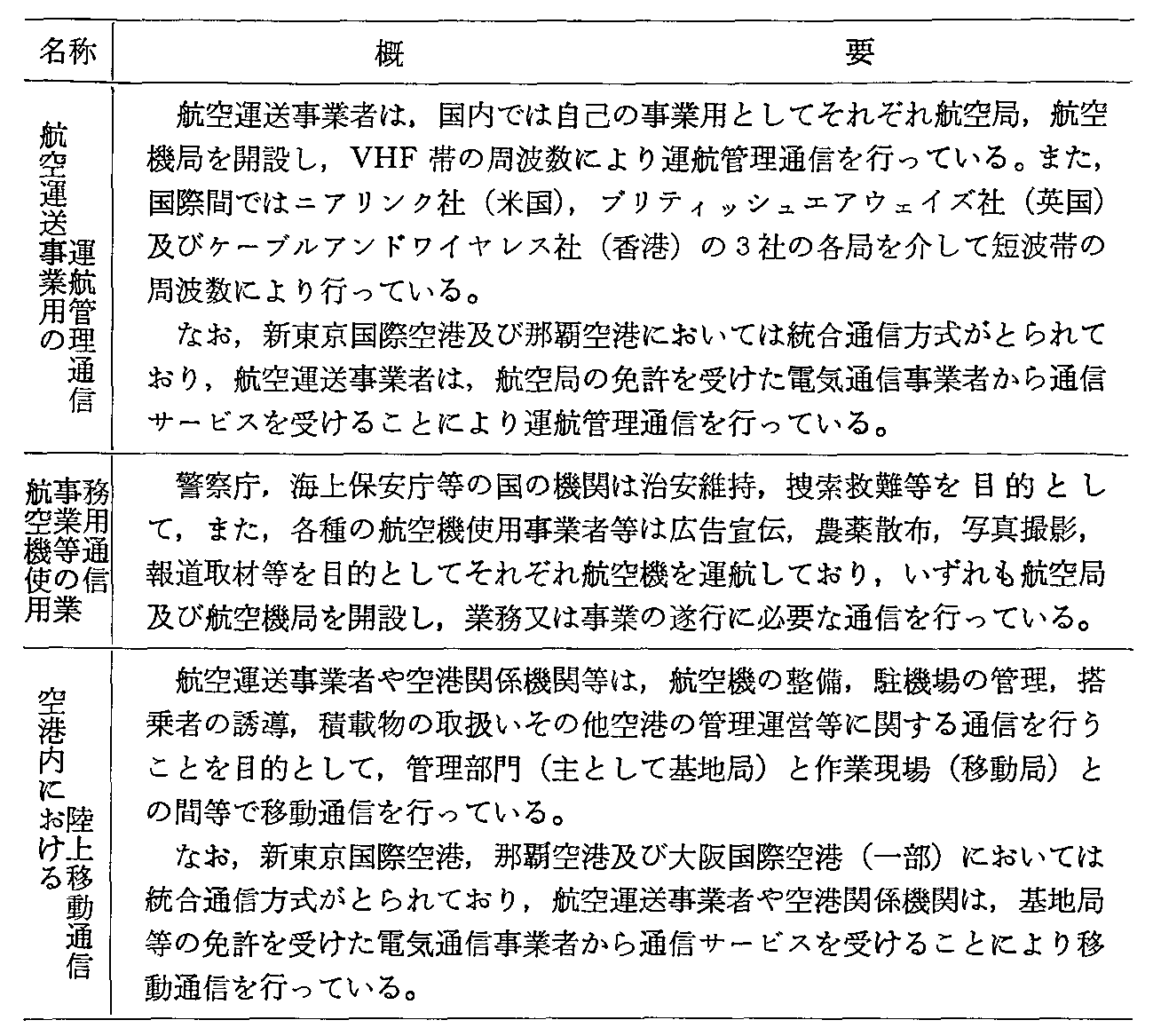
(キ)海上運送事業用
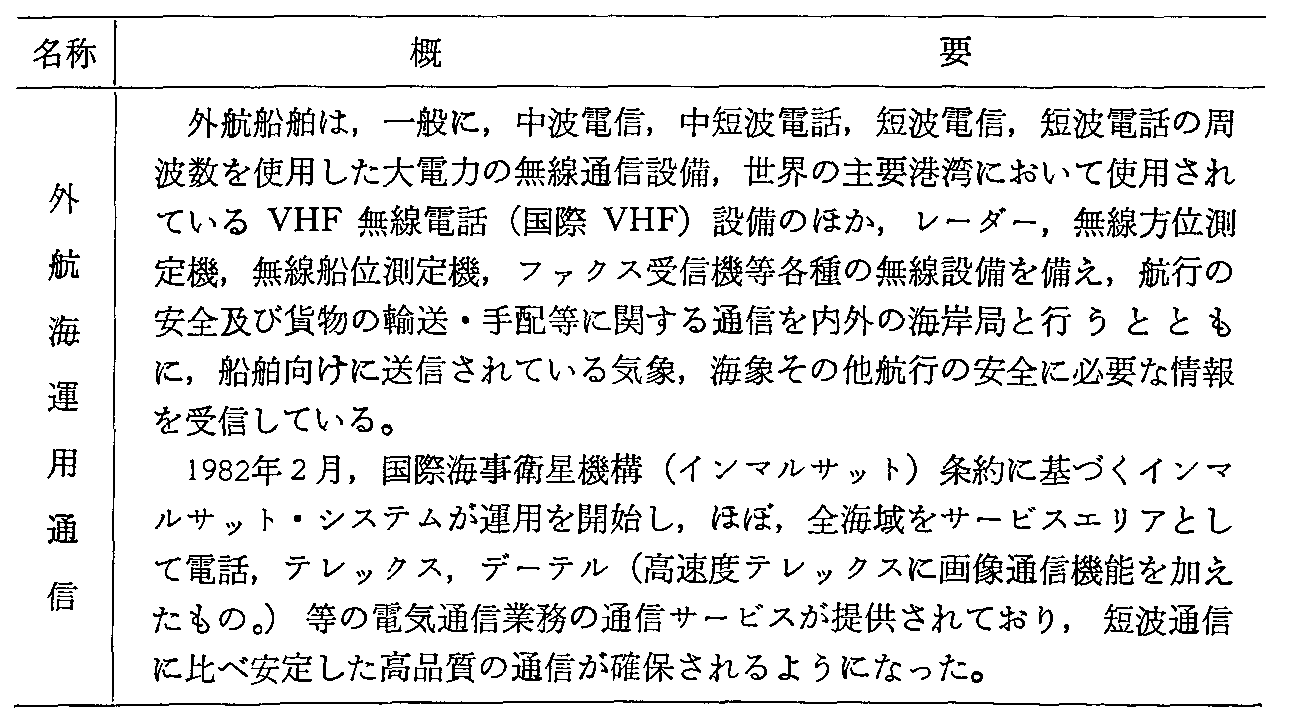
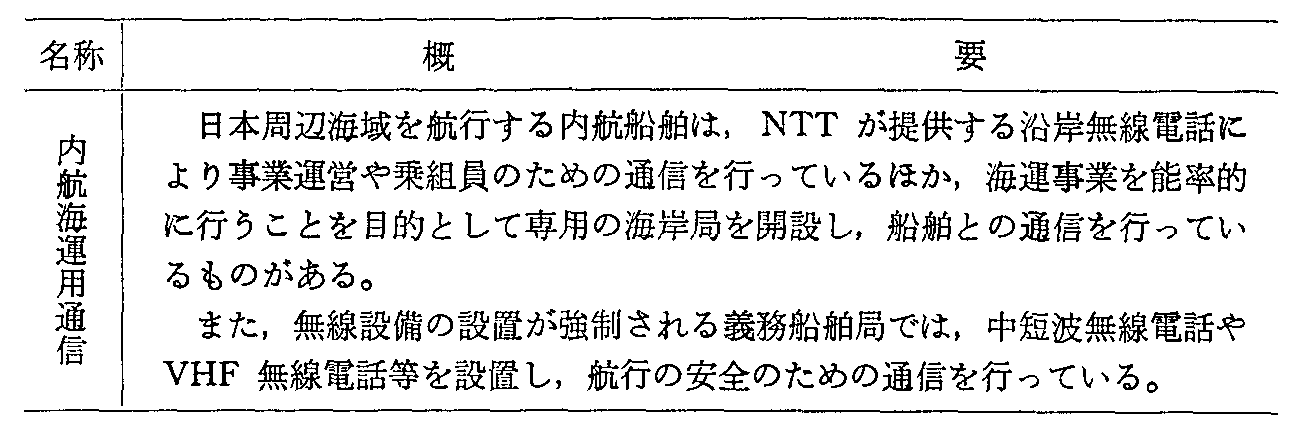
(ク)港湾通信業務用
港湾通信業務はVHF帯無線電話を用い,港湾内はその付近における船舶の交通整理,びょう地の指定,並びに検疫に関する通信のほか,船舶の移動に不可欠な水先業務,ひき船事業等を含む船舶の移動を安全かつ能率的に遂行するために行われるものであり,59年度末現在,海上保安庁の海岸局63局のほか,港湾管理者たる地方公共団体の開設する海岸局(ポートラジオ)19局がこの業務を行っている。
また,港湾内における水先業務及びひき船事業に使用する船上通信局に対しては,近年の需要増に対処すべく狭帯域化された設備の導入を図ることとされている。
(ケ)漁業用
漁業用通信は,僚船相互間の情報交換については,漁船に開設されている無線局(船舶局)を介して行われ,また船主等に対する報告及び船主等からの指示等については,陸上に開設されている無線局(漁業用海岸局)を介して行われる。
A 船舶局
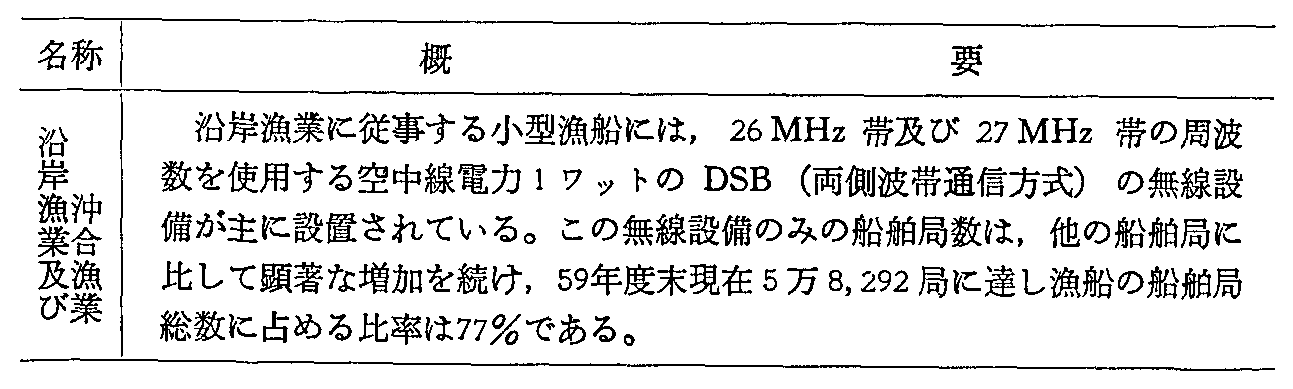
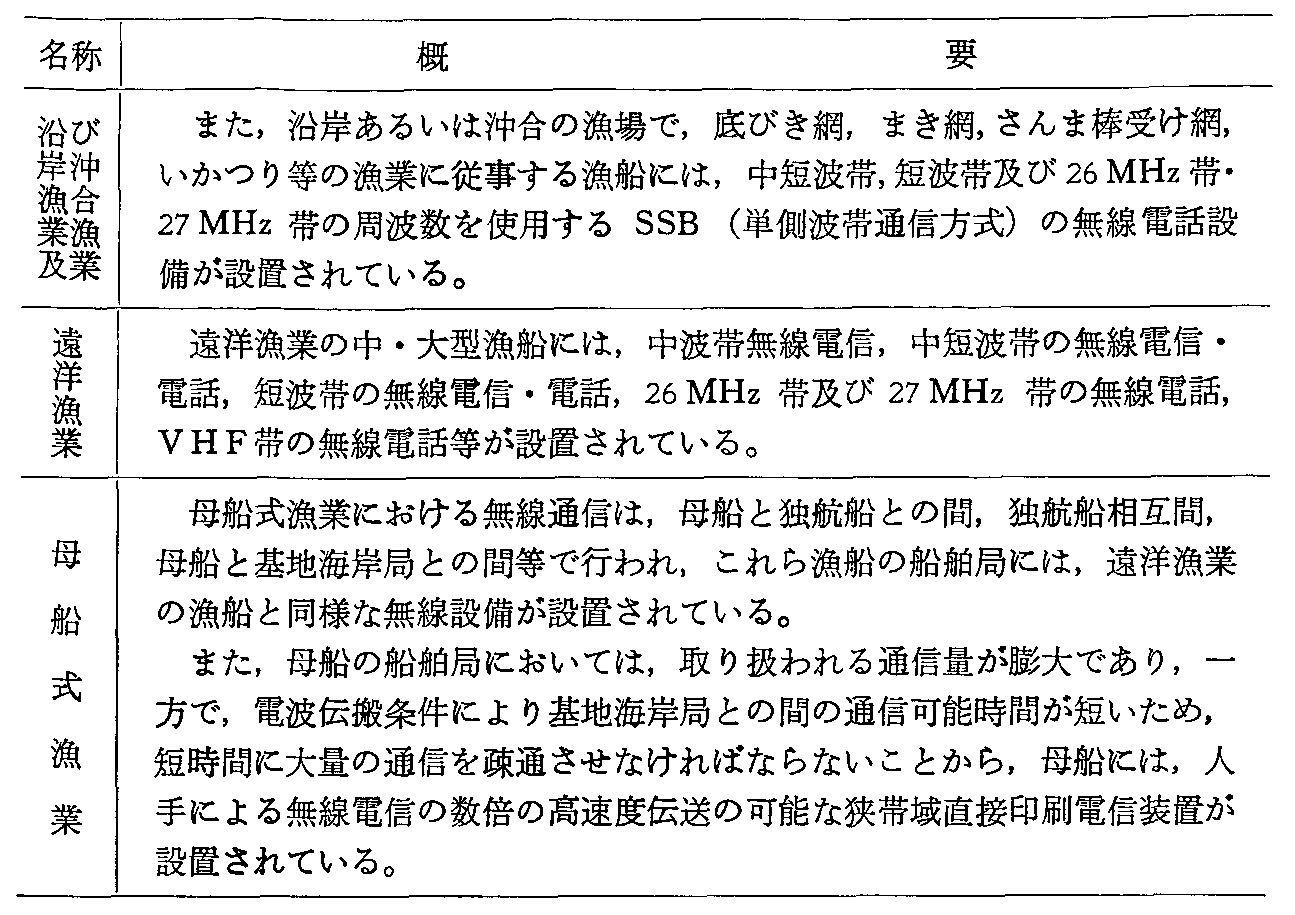
B 海岸局
漁業用海岸局は,漁船の船舶局を通信の相手方として無線電信又は無線電話により漁業通信を行う無線局であって,漁業共同組合等が免許人となって国内の漁業根拠地に開設されており,59年度末現在729局である。
近年は,総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局の増加に対応して,空中線電力1ワットのDSBの漁業用海岸局が増加しており,59年度末現在493局と,海岸局総数の68%を占めている。
漁業用海岸局の中には,国(水産庁)又は地方公共団体が開設する漁業指導用の海岸局を併せ開設し,我が国の沖合,遠洋の漁場で操業する漁船との間で中短波帯,短波帯の周波数を使用して無線電信又は無線電話による漁業通信等のほか,漁船向けのファクシミリによる漁・海況通報の放送を実施しているものがある。
C その他
(A)漁業における無線利用の特殊な設備
漁業における無線利用の特殊な設備として,遠隔制御魚群探知用無線設備(テレサウンダ),ラジオ・ブイ,レーダー・ブイが活用されている。テレサウンダは,40MHz帯の周波数を使用して網の中に入った魚群の情報を得る装置であり,定置網漁業及びまき網漁業に使用されている。ラジオ・ブイは2MHz帯又は27MHz帯の周波数により,また,レーダー・ブイはレーダー用周波数と40MHz帯の周波数を使用して漁具等の位置確認の情報を得る装置であり,はえなわ漁業,流し網漁業等に使用されている。
(B)中短波・短波帯漁業用海岸局の統合
近年,沿岸諸国の200海里水域内における外国漁船に対する規制の強化及び燃油価格の高騰による操業経費の増加等により,沖合及び遠洋漁業に従事する中・大型の漁船が減少し,漁業用海岸局の運営はますます困難になりつつある。
これらのことから,漁業関係者においては,運営の合理化と通信需要への対応を図るための施策の一環として,既設漁業用海岸局の統合,整備を推進している。
(C)沿岸漁業における無線通信の需要増とその対策
沿岸漁業に従事する総トン数10トン未満の小型漁船の船舶局は年々増加する傾向にあるが,これらの船舶局が利用している26MHz帯及び27MHz帯の周波数はひっ迫しており,増波は困難な状況にある。
このような状況に対処するため,新たに40MHz帯の周波数を使用する無線通信システムを58年6月制度化した。
この40MHz帯通信システムを設置している局は愛知県,山口県等の漁業協同組合所属の漁船470局となっており,今後も積極的にその普及促進を図ることとしている。
(コ)海上スポーツ・レジャー用
近年,海上でのスポーツ,レジャー人口の増加に伴い遊漁船やヨット等に船舶局を開設するものが増えており,これに対処すべく,59年度,新たに40MHz帯を導入した。
これらの船舶局は専用の海岸局との間又は船舶局相互間で安全等に関する通信を行っている。
(サ)新聞・通信用
新聞社及び通信社では,事件現場から本社,支社,支局等に対する記事,写真伝送等の取材活動に主にVHF帯又はUHF帯の陸上移動業務又は携帯移動業務の無線局を使用している。
また,通信社が経済ニュース等を,金融機関,商社等に通報する場合には,同報無線を利用している。
(シ)道路管理用
高速道路における維持管理,交通管理等のための通信系としては,現在,非常通信系,指令通信系,業務通信系,移動通信系,道路情報伝送系,映像伝送系,防災連絡用通信系等がある。
高速道路では,移動通信系を除き,名神高速道路及び中央自動車道の一部についてはマイクロウェーブ多重無線回線を主体としており,それ以外の高速道路については,NTTの通信回線を使用している。
日本道路公団は,災害対策基本法による指定公共機関として,大災害等における迅速かつ正確な情報収集とこれに基づく的確な情勢判断及び指揮命令伝達体制を確立するため,本社と地域防災対策強化地区を管理する各管理局及び各管理事務所間を無線回線で結ぶ防災対策用無線局を開設している。
また,日本道路公団,阪神高速道路公団,建設省及び首都高速道路公団では,道路交通情報をカーラジオを通じて車両のドライバーに提供する路側通信システムを,それぞれ58年12月,59年6月,59年12月及び60年1月から管轄高速道路の一部で運用している。
(ス)鉄道事業用
A 日本国有鉄道
日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の通信回線は,本社-鉄道管理局(26局)間等の固定通信系と対列車通信に代表される移動通信系等によって構成されている。
(A)固定通信系
固定通信系としては,本社と鉄道管理局との間及び鉄道管理局相互間を結ぶSHF多重無線回線(7GHz帯及び12GHz帯)と鉄道管理局と主要駅との間及び主要駅相互間を結ぶUHF多重無線回線(400MHz帯及び2GHz帯)とがあり,指令電話,CTC(列車集中制御装置)の制御,各種データ伝送等の回線として使用している。
また,災害時における危険分散を図るため,全国ネットワークのループ化(北海道を除く。)を図っている。
(B)移動通信系
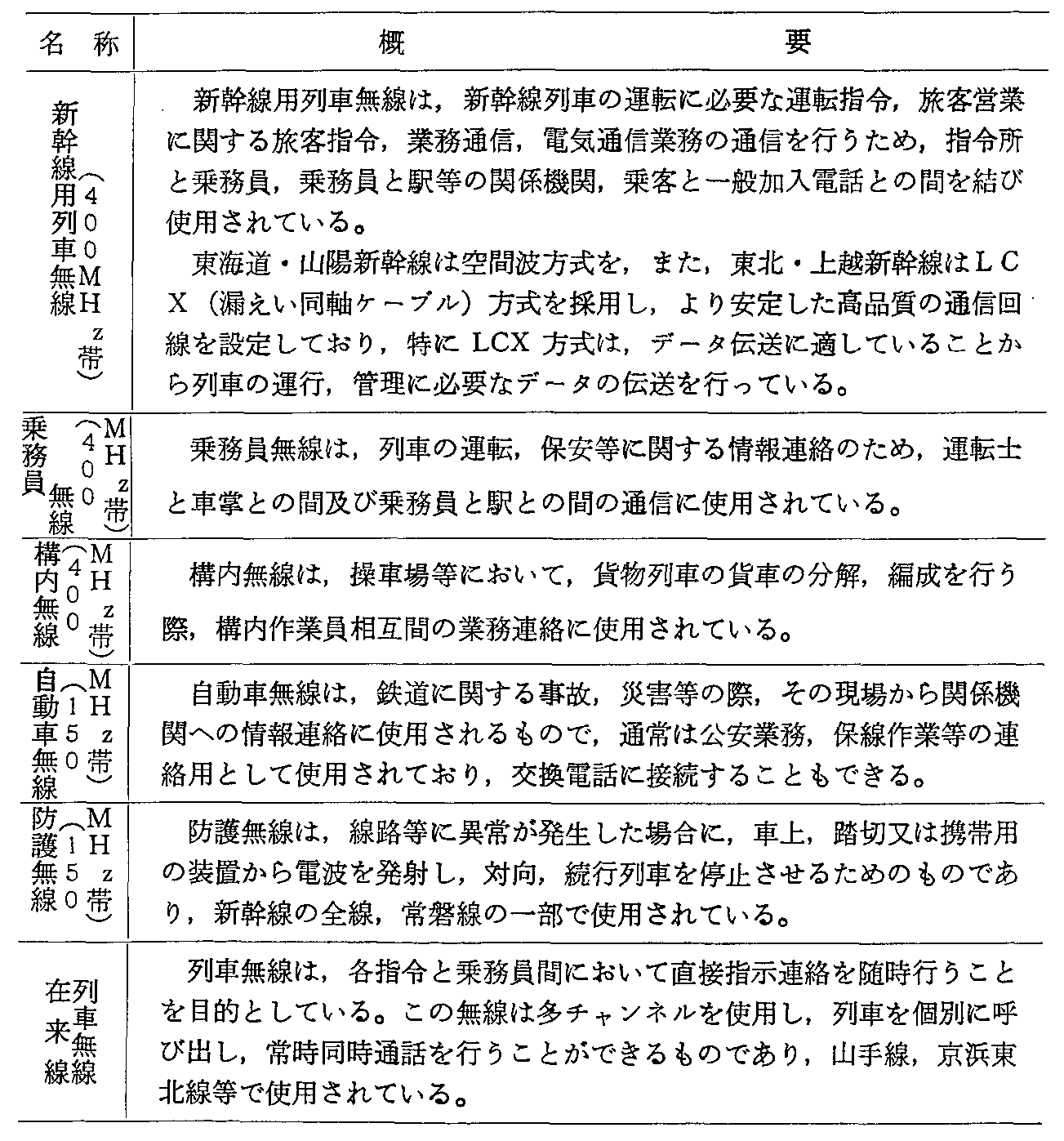
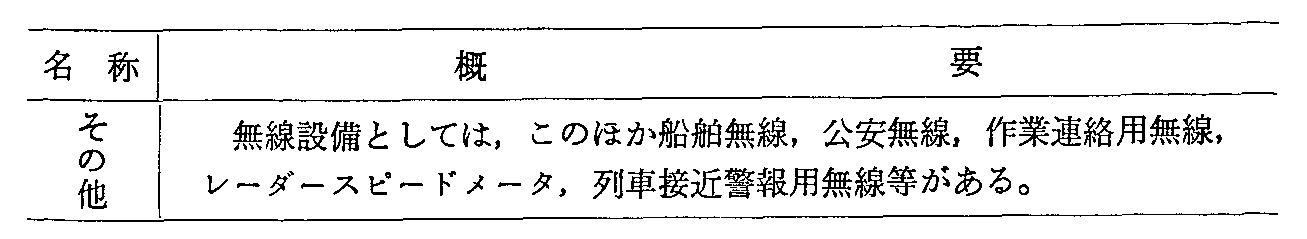
(C)衛星通信システム
国鉄では,CS-2を利用した衛星通信システムを58年6月23日から運用開始した。このシステムの利用目的は,[1]新幹線地震検知システム,[2]非常災害時における地上回線バックアップ回線,[3]災害・事故現場との回線設定を行うことであり,東京,静岡,仙台,新潟及び三浦半島に固定型地球局を設置している。
また,災害及び事故現場と管理局(事故対策室)間の回線設定に用いるため,59年3月,静岡に車載型地球局を配置した。
(D)その他
鉄道業務用電話は,本社,地方鉄道管理局,駅間等を結ぶ専用の全国的ネットワークであり,鉄道業務の円滑な運営に資するほか,座席予約,列車運行,コンテナ情報等の各種情報システムの基礎となっている。
B 民営鉄道
民営鉄道では,無線通信を列車の運転指令用,事故発生時における運輸指令所と駅及び列車乗務員間,近接列車相互間の緊急連絡用,踏切事故発生時における二重衝突等の事故防止のための警報用,操車場内での車両の入換編成作業用等に使用している。
このほか,線路上あるいは踏切道上の障害物を発見した場合,近接列車に警報信号を送信するための防護警報用の無線局を踏切付近に設置している。
また,踏切道上の障害物を電波を利用して検知する障害物検知用の無線局を交通量の多い踏切道上に設置している。
(セ)電気・ガス・水道事業用
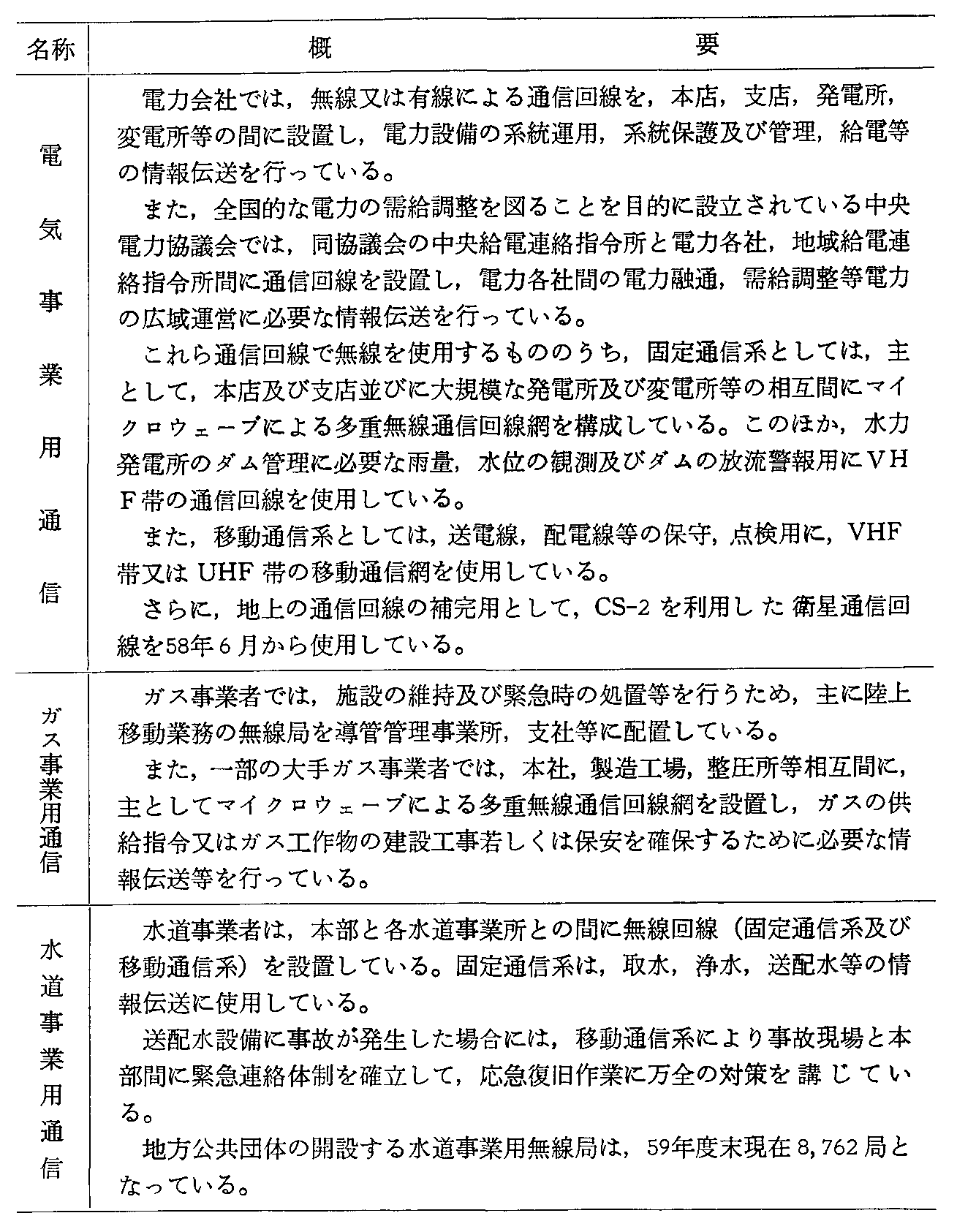
(ソ)自動車運送事業用
自動車運送事業用の通信は,営業所等に設置した基地局と車両に設置した陸上移動局との間で通信系を構成し,配車指令,荷物の集配指令等を行っている。
また,車両の一層の効率的運行を図るため,走行中の車両の現在位置や活動状況(動態)を基地局(運行管理センタ)において常時把握できる「車両位置等自動表示システム(AVMシステム)」が全国の主要都市に普及している。
貨物運送事業では,主として,貨物の集配指示,配車指令等を行っている。近年,小口貨物の宅配部門の需要増加に伴い,トラック業者のこの部門への進出は目覚ましく,無線設備を装備したトラックは増加の一途をたどっている。特に貨物運送事業者が集中する大都市においては,通信需要の増大に対処するためMCAシステムを57年から導入している。59年度には,既にサービスが行われている東京等4地区に加えて,札幌,横浜,埼玉,静岡,神戸,福岡及び北九州の各地区でもこのシステムのサービスが開始された。
(タ)アマチュア業務用
アマチュア業務用の無線局は,「金銭上の利益のためでなく,専ら個人的な無線技術の興味によって,自己訓練,通信及び技術的研究の業務」を行うものであり,世界的に共通の周波数帯を使用して,通信技術の研究あるいは国際親善に役割を果たしている。最近のアマチュア局は自動車に設置して運用するモービル・ハムが急増していることから,VHF帯,UHF帯の周波数を利用するものが急速に増加している。また,高度の技術を要する人工衛星を利用する通信(VHF帯,UHF帯),大電力(500W)により月面反射を利用する通信,ラジオ・テレタイプ(RTTY),スロー・スキャニング・テレビジョン(SSTV)等も行われている。
さらに,アマチュア業務用レピータ局(自動中継局)として,日本アマチュア無線連盟(JARL)が430MHz帯及び1,200MHz帯を使用するレピータ局を各地に設置しており,ハンディ型の小出力の無線設備を使用するアマチュア局の交信範囲の拡大を図っている。
(チ)簡易無線業務用
簡易無線業務は,一般簡易無線局,パーソナル無線及び50GHz帯の電波を使用する簡易無線局に区別される。
一般簡易無線局は,主に業務用に使用されており,全国的に普及している。また,パーソナル無線は,スポーツ,レジャー,個人的用務への利用等広範囲に使用されている。
50GHz帯を使用する簡易無線局は,音声だけでなく,データや画像の短距離間伝送を手軽に行うことができる簡易無線局であり,道路や河川等を隔てた地点間におけるデータ伝送や工事現場における画像伝送等に使用されている。
(ツ)その他
上記各項のほか,自営の無線通信は次のとおり広く各分野にわたっている。これらの無線通信は一部が固定通信であるほか,ほとんどが陸上移動業務,携帯移動業務又は無線標定業務等の移動通信である。
(1)国の業務用
[1] 検察,矯正管理,出入国管理用 [2] 税関用
[3] 南極観測用 [4] 検疫,麻薬取締用 [5] 港湾工事用
[6] 干拓事業用 [7] 林野事業用 [8] 漁業指導用
[9] 地質調査用 [10] 電波監理,電波監視用
(2)国の業務以外の事業用
[1] 水防用 [2] 港湾建設事業用 [3] コンテナ荷役用
[4] 造船事業用 [5] 石油採掘事業用 [6] 測量用
[7] 金融事業用 [8] 警備業務用 [9] 医療用
[10] 無線呼出業務用 [11] 農業用 [12] 学校教育用
[13] その他
|