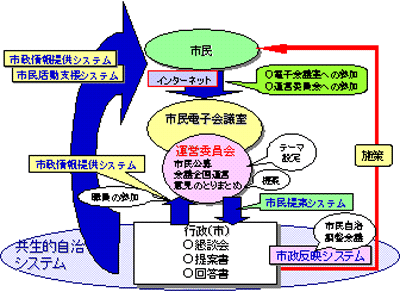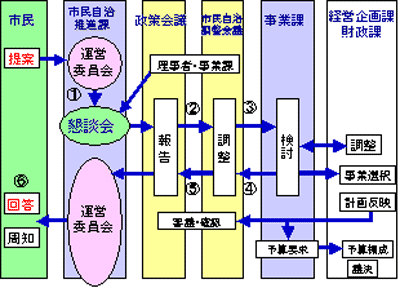|
■ どのようにして施策に反映させるのですか?
キーワード
関連項目
・ ICTはあくまでも意見収集のひとつの手段であり、住民参画ツールとして活用するには、行政施策などに反映させるための制度、仕組みが必要となります。
・ 藤沢市では、市民電子会議室の中に「市民エリア(市民が運用ルールに則って活用)」と「市役所エリア(市が会議室を主催するエリア)」を設けていますが、このうち市役所エリアの会議室を、市が進める「市民提案システム」制度の一つとして位置づけています。
・ 市役所エリアの会議室は、市政に関することを運営委員会(市民から公募)がテーマとして設定してスタートします。運営委員会が選任する進行役が会議の進行、取りまとめを担当し、成果は運営委員会を通じて「市政への提案」として提出されます。会議室には市職員も参加し、市民の意見交換に必要な情報を市役所が積極的に提供します。市役所エリアの会議室では、全ての参加者は実名で発言することとしており、ニックネームによる発言は認めていません。
● 藤沢市市民電子会議室における市政への反映の仕組み
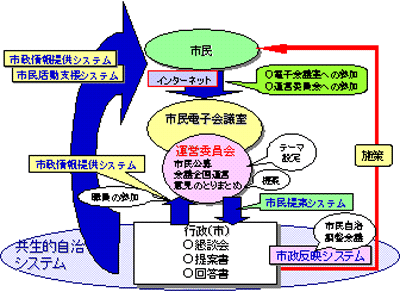
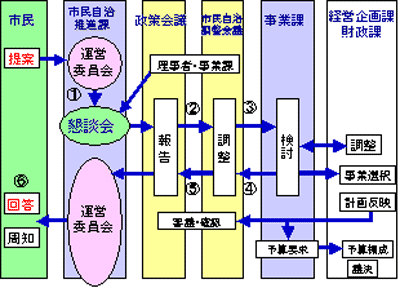
図中の番号は、次頁に対応。
資料:藤沢市
藤沢市における施策への反映の例
・ 1997年11月、「環境問題に関すること ごみ収集制度の改善」として「資源ごみ、不燃ごみの収集日の定曜日制への移行」について、運営委員会から提案書が提出されました。以下は、その際の庁内手続きを示したものです。(前頁の図中の番号に対応しています。)
(1)他の提案項目と一緒に、市民自治推進課主催の市長・助役・環境部長出席の懇談会上で運営委員長が提案書を手渡しし、ここまでの議論の経過を含めて懇談した。
(2)その後、理事者は政策会議で提案を受けたことを報告し、市民自治推進課主催の市民自治調整会議(各部の調整課長、財政課長、職員課長、企画課長が出席)で諮り、各部間の調整を行う。
(3)環境部の調整課(環境政策課)が持ち帰り、担当課(環境事業センター)に回答検討を指示。
(4)その結果を回答書として市民自治推進課へ提出。市民自治推進課は、再度、市民自治調整会議に諮る。
(5)特に問題がなければ、市民自治部長が政策会議に報告し、運営委員会へ回答を渡す。
(6)当時の回答結果(実施予定だが課題はある)
【現在】
・ 資源ごみ:市内を12のブロックに分け、月2回業者に委託して収集。
・ 不燃ごみ:市内を12のブロックに分け、月2回業者に委託して収集。収集日の周知は、3月、6月、9月、12月の10日発行の広報に次回3ヶ月分を掲載。
【今後】
・ 収集日を定曜日化することにより、分別収集の一層の徹底が図れると考えているが、定曜日化するためには、可燃、不燃、資源ごみの収集日の調整、収集ブロックの見直し、祝祭日の取り扱い等の課題がある。
・ また、「容器包装リサイクル法」による、平成12年度からの収集品目の増加に伴う、収集体制の見直しも検討課題。定曜日収集については、すべての収集体制の見直しの中で定曜日化に向け検討中。
現在の状況(解決)
・ 現在、市内を2ブロックに分け、可燃ごみは収集。資源物、不燃ごみ、廃プラ等は定曜日収集となっている。
|