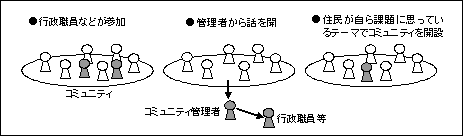|
■ 地域SNSや電子アンケートを使って住民ニーズを把握するにはどうしたらいいですか?
キーワード
・行政職員などもコミュニティに参加する
・コミュニティ管理者から意見を聞く
・住民が自らコミュニティを立ち上げる |
関連項目
【地域SNS】
・ 地域SNSを用いて住民の様々なニーズを把握することが可能です。アンケート調査が特定のテーマや予め作成した設問に対する回答であるのに対し、地域SNSでは、日々の生活の中での意見の把握や、双方向でのやりとりが可能です。
・ 例えば、「子育て」「バリアフリー」などのコミュニティに、行政職員などが参加することにより、住民の関心や苦労していること、要望などを、より具体的に把握することができます。場合によっては改善策の検討や実施まで、そのコミュニティで実現できるかもしれません。
・ コミュニティ管理者から、最近コミュニティで話題になっていることや、意見として出ている課題、要望などについて、話を聞く方法もあります。把握しておきたい住民ニーズに合致するコミュニティの管理者からは、定期的に話を聞いてもいいでしょう。
・ 公認コミュニティ(藤沢市の市民電子会議室では「市役所エリア」に相当)は、開設する際に運営主体の承認が必要ですが、一般コミュニティは、参加者が自由に開設可能です。自分の趣味や関心ごとなど、利用規約に反しない範囲で、どんなコミュニティでも開設できます。一般コミュニティの開設傾向などから、住民の関心のありかがわかります。また、住民自らがニーズや課題と感じているテーマについてコミュニティを開設し、そこで様々な意見を交わすことで、住民ニーズを顕在化することができます。行政施策に関係がありそうなテーマのコミュニティについては、公開のものは定期的に内容を閲覧し、ニーズを把握するのに役立てることができます。
・ なお、行政(職員)側の役割として、議論をただウォッチするだけではなく、行政情報のタイムリーな提供等インタラクティブな体制が必要になります。情報源となる行政ホームページのコンテンツ充実はもとより、行政職員の積極的な参加と発言が効果的な住民ニーズの把握には必要不可欠なものであり、行政職員にもコミュニティの一員としての意識(同じ議論のテーブルについているという感覚)を持つよう求められます。
・ またその他、住民が公開の日記に記載している日々の出来事や雑感の中などにも、隠されたニーズが潜んでいる場合もあります。このように、地域SNSは、住民の様々な思いを顕在化、可視化するツールとして、有効活用が可能です。
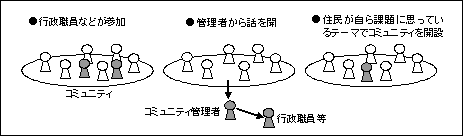
【電子アンケート】
・ 電子アンケートは、紙のアンケートに比べて、
1)何度もできる
2)手軽にできる
3)すぐに回収、集計できる
4)繰り返しできる
5)大量にできる
6)地域SNSのコミュニティと組み合わせて使うことができる
などの特徴があります。
・ 従来は、2年に一度、1,000人を対象に紙で行っていたアンケートを、半年に一度、10,000人を対象に行うことも可能になります。その分、最新かつより多くの意見を収集し、様々な施策の検討などに活用することができます。
・ なお、電子アンケートを行う場合、「母集団」の違いに留意する必要があります。紙のアンケートは、基本的には住民の中から均等に意見を収集できますが、電子アンケートの回答は、パソコンや携帯電話を活用する人に限られます。分析の際には、この点に十分留意するとともに、数回に一度は紙のアンケートを同時に行って補完することも有効です。
|