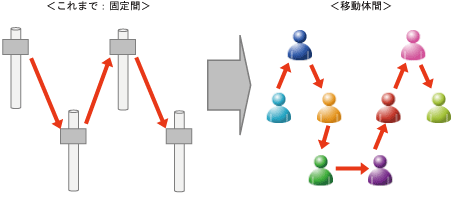報道資料
平成26年3月19日
東海総合通信局
マルチホップ移動無線通信システム調査検討会が報告書を取りまとめ
総務省東海総合通信局(局長 木村 順吾(きむら じゅんご))では、マルチホップセンサーネットワーク技術が複数の移動する無線通信装置間でも応用可能か否かについて調査検討してきたところ、可能であるとの結論に達しました。
1 調査検討の目的
マルチホップセンサーネットワーク技術
(注)とは、複数の無線通信装置がそれぞれ隣接する他の無線通信装置同士を連鎖経由して、バケツリレーのようにデータを伝送していく通信技術であり、現状では固定の無線通信装置間での使用に留まっています。
注記
- それぞれの無線通信装置が連携することで広い範囲での通信が可能となるとともに、無線通信装置の送信出力を小さくすることができ、省電力にも優れています。また、無線通信装置が自ら通信経路を選択してつないでいくため、障害が発生した場合にも自動的に別経路に切り替わる特質を持っています。
しかし、このマルチホップセンサーネットワーク技術が、移動する無線通信装置間でも使用できるようになれば、新たな応用用途の開拓が期待されます。そこで、総務省東海総合通信局では、昨年9月から、920MHz帯マルチホップセンサーネットワーク技術を応用した移動無線通信システムに関する調査検討会
(座長:小栗 宏次(おぐり こうじ) 愛知県立大学情報科学部教授)にその技術的な調査検討を委嘱してきたところです。
図:マルチホップセンサーネットワーク技術のイメージ
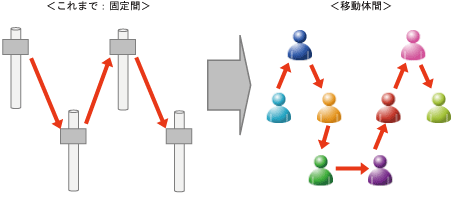
2 調査検討の結果
この調査検討会では、実際にマルチホップセンサーネットワーク技術を応用した移動型の無線通信装置を試作した上で、マラソン大会においてランナーに装置を装着して走行してもらったところ、マルチホップ通信が可能であることを確認しました(報告書の概要は、以下のとおり)。
これまでのマルチホップセンサーネットワーク技術に関する規格が固定の無線通信装置間での使用を前提としたものとなっていたため、総務省では、今後、移動する無線通信装置間での使用を想定したものに見直していくことを検討していきます。他方、民間企業等において、実用化に向けて、更に多数の無線通信装置間での使用や信頼性の向上が図られ、マルチホップセンサーネットワーク技術を応用した新たな機器やサービスが登場することを期待しています。
関係報道資料
報告書の概要
- 1 試作機の技術的条件と通信方式
-
- ア ニーズ調査と要求される性能
- 実験(ウォーキングとマラソン)での利用ニーズから、当面の目標とする所要性能として、移動速度18km/h、収容端末数100台、基地局1台のカバー範囲1km、データ伝送速度736bps/台と決定した。
- イ 通信方式の検討
- ツリー型のネットワーク構成、TDMA(時分割多重方式)を選択。基地局から1秒毎にビーコンを各移動局が中継することによりルートを決定し、各移動局からはその逆方向にデータを送信・中継する方式とした。
- 2 試作機の製作と基礎技術試験
-
- ア 試作機の製作
- 基地局2局と移動局10局を製作。基地局1局につき移動局50台を収容し、最大5ホップの中継が可能。移動局は、10秒分のデータ保持と再送が可能。
- イ 基礎技術試験
- 所要性能の動作を確認した。最大通信距離は、見通しで最大400m得られた。
- 3 実験(マラソン大会)での結果
-
- ア マルチホップ通信の確認
- マルチホップ動作によるデータ伝送がほぼ予定どおりに機能し(移動局が一定の距離を維持できた場合、データ欠損率は10%程度)、データ欠損時の再送機能によるリカバリーも機能することを確認した。
- イ 問題点
- 無線が人体により遮蔽される等のため、無線通信装置を装着する人が密集するような場合には伝送効率が低下した。
- マルチホップネットワークの経路構成によっては特定の移動局に通信中継が集中することがあり、その場合には通信時間制限の規格値を超えた。
- 4 今後の課題等
-
- 特定の移動局への通信集中を回避するため、送信時間を長くして、利便性を向上させることが望ましい。
- マルチホップネットワークを安定させるためには、基地局の高さや移動局のアンテナの位置、マルチホップの影響も定量的な評価が必要。
- 実用化の検証のためには、50台から100台規模での実証実験も必要。
報告書の公表
報告書は、3月下旬を目途に当局ホームページにて公表する予定です。
ページトップへ戻る