
| 平成21年3月24日 |
|
平成17年(2005年)産業連関表(確報)の公表 |
|
| ■産業連関表とは、我が国の1年間の経済活動を統計表としてとりまとめたもの ■平成17年を対象にした今回の産業連関表は、10府省庁の共同事業として4年の歳月をかけて完成させたもの ■平成17年(2005年)産業連関表の速報は20年8月26日に公表済み ■今回の確報は、速報(108部門)をさらに詳細(行520部門×列407部門)に推計し、内訳表となる付帯表を揃えて確定データとして公表するもの |
1 公表する統計表
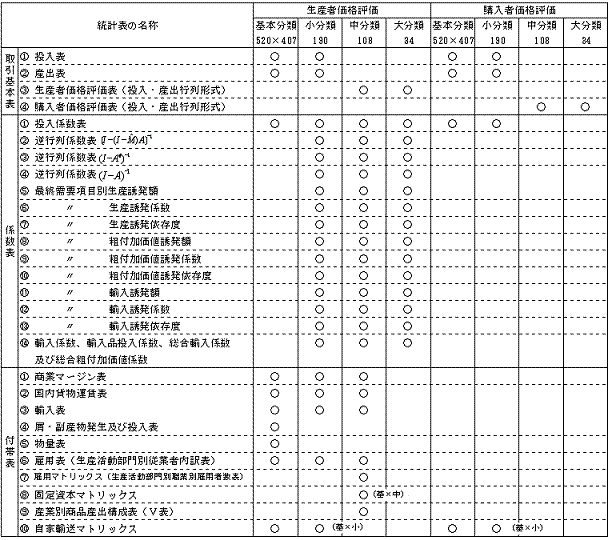
2 産業連関表の入手方法
統計表は、総務省のホームページから入手できます。3 平成17年(2005年)産業連関表(確報)からみた財・サービスの流れ
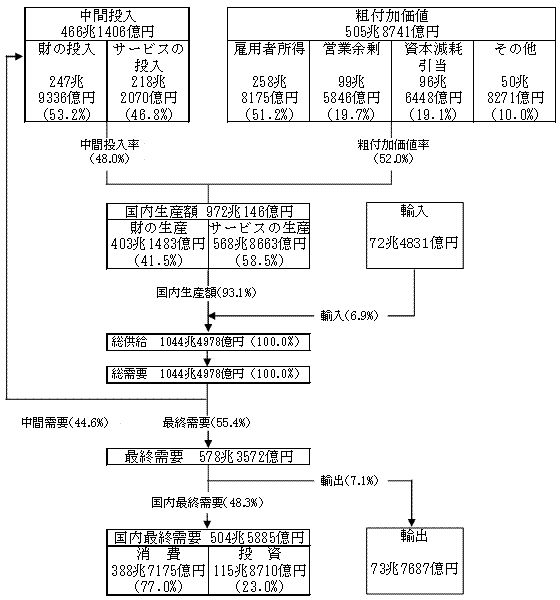
4 平成17年(2005年)産業連関表からみた日本経済
| 平成17年(2005年)の国内生産額(972兆円)は平成12年(2000年)に比べ1.4%微増、また、輸出は28.3%、輸入は33.8%と大幅に増加 |
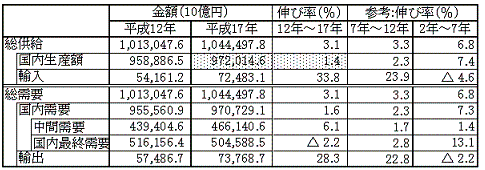 平成17年の総供給(総需要)は、平成12年に比べて3.1%増加しました。
平成17年の総供給(総需要)は、平成12年に比べて3.1%増加しました。| 中間投入率が低下傾向から上昇に転換 |
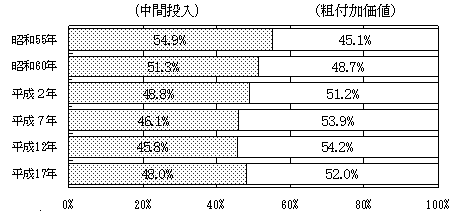 国内生産額は、生産活動に必要な原材料やサービスの購入費用となる「中間投入」と雇用者所得や営業余剰といった生産活動によって新たに付け加えられた「粗付加価値」に分けられます。
国内生産額は、生産活動に必要な原材料やサービスの購入費用となる「中間投入」と雇用者所得や営業余剰といった生産活動によって新たに付け加えられた「粗付加価値」に分けられます。| 生産波及の大きさが上昇 |
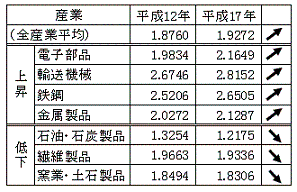 1単位当たりの最終需要に対する生産波及の大きさは、全産業平均で1.9272倍で平成12年(1.8760倍)に比べ上昇しました
1単位当たりの最終需要に対する生産波及の大きさは、全産業平均で1.9272倍で平成12年(1.8760倍)に比べ上昇しました5 産業連関表の構造
産業連関表は、さまざまな産業が1年間に生産した財・サービスをどのように他産業や家計、輸出等に配分されたのかを行列(マトリックス)の形で一覧表にしたものです。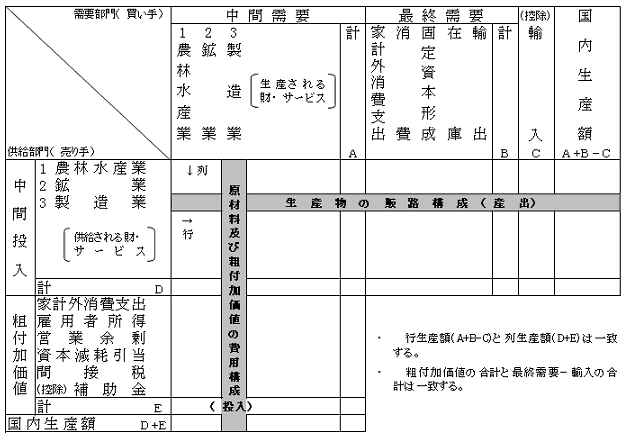
6 産業連関表の作成と利用
平成17年(2005年)産業連関表の作成は、10府省庁が共同で行なっており、経済に関する各種統計を基に平成17年の一年間の財・サービスの流 れを行列(マトリックス)の形で一覧表にとりまとめています。公表は5年ごとに行なっており、今回で11回目となります。
|