7 国際機関及び国際協力
7-1 国際機関
(1)万国郵便連合(UPU)
ア 概要
UPUは,国際連合の専門機関の一つで,郵便業務の効果的運営によって諸国民間の通信連絡を推進し,文化,社会及び経済の分野における国際協力に寄与することを目的とする政府間国際機関であり,1874年に設立された。我が国は,1877年にこれに加盟した。
イ 組織
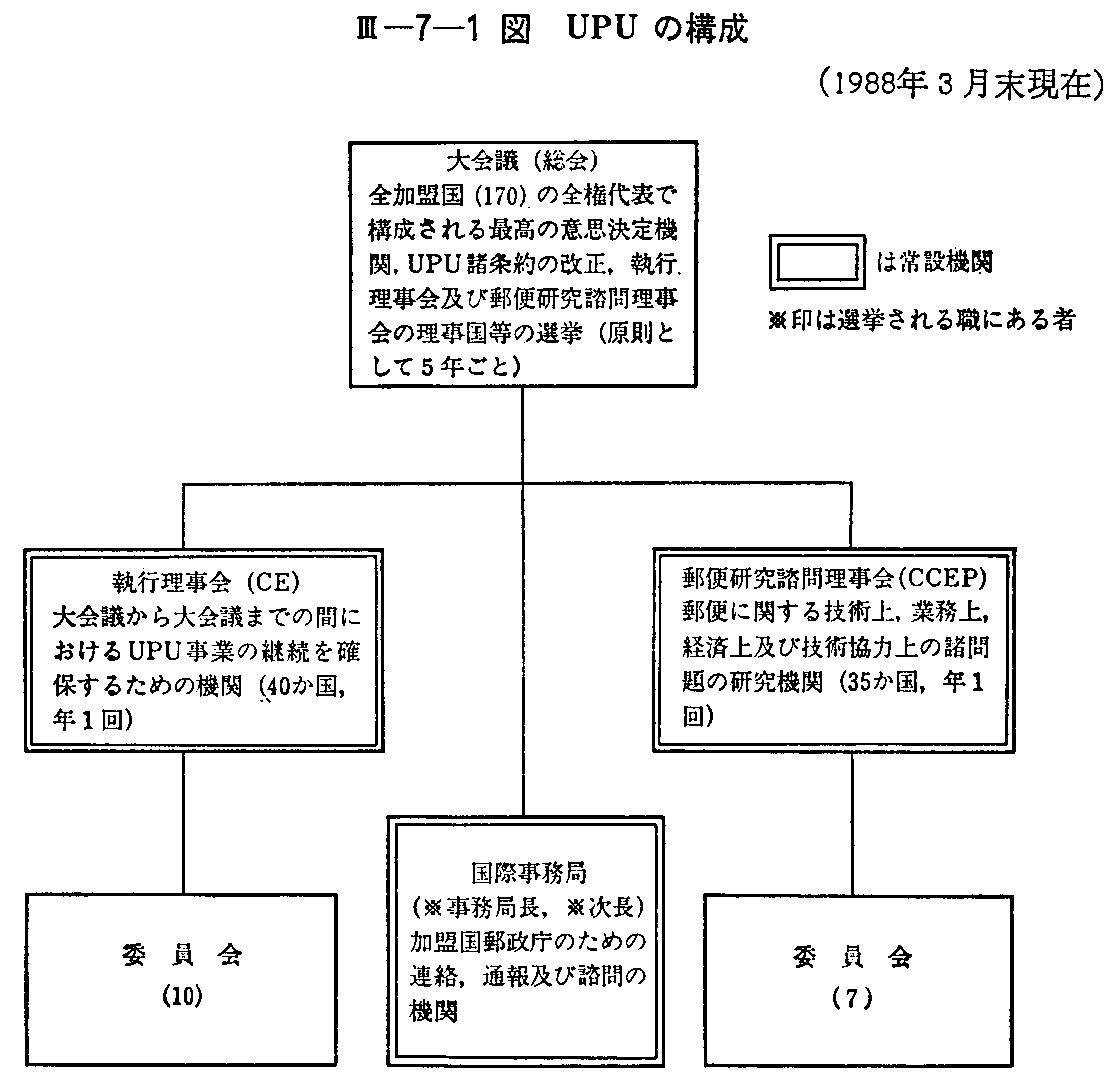
ウ 活動状況
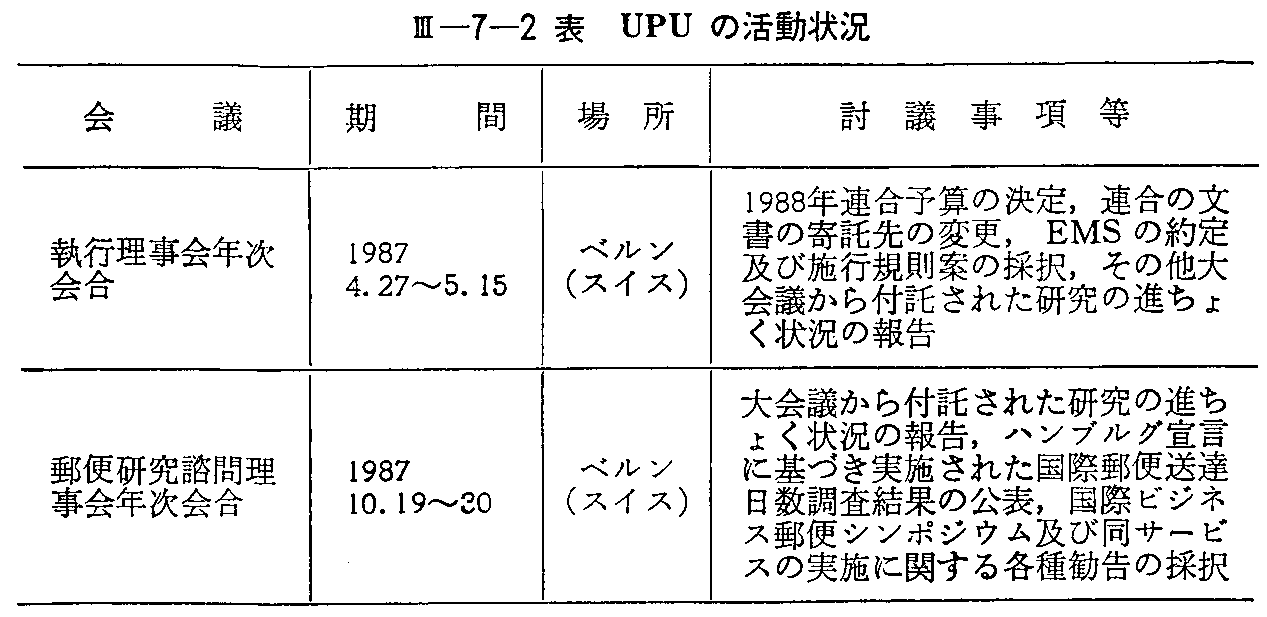
エ アジア=太平洋郵便連合(APPU)
APPUは,UPU憲章に基づき設立されている九つの限定郵便連合(地域的な郵便連合)の一つで,アジア・太平洋地域内における郵便業務の改善及び協力関係の緊密化をその目的としている。
現在,域内のUPU加盟国中21か国が加盟しており,我が国は,1968年にこれに加盟した。
(2)国際電気通信連合(ITU)
ア 概要
ITUは,国際連合の専門機関の一つで,電気通信の分野において広く国際的責任を有する政府間国際機関である。1865年に万国電信連合として発足し,我が国は,1879年にこれに加盟した。本部は,スイスのジュネーヴにある。
イ 組織
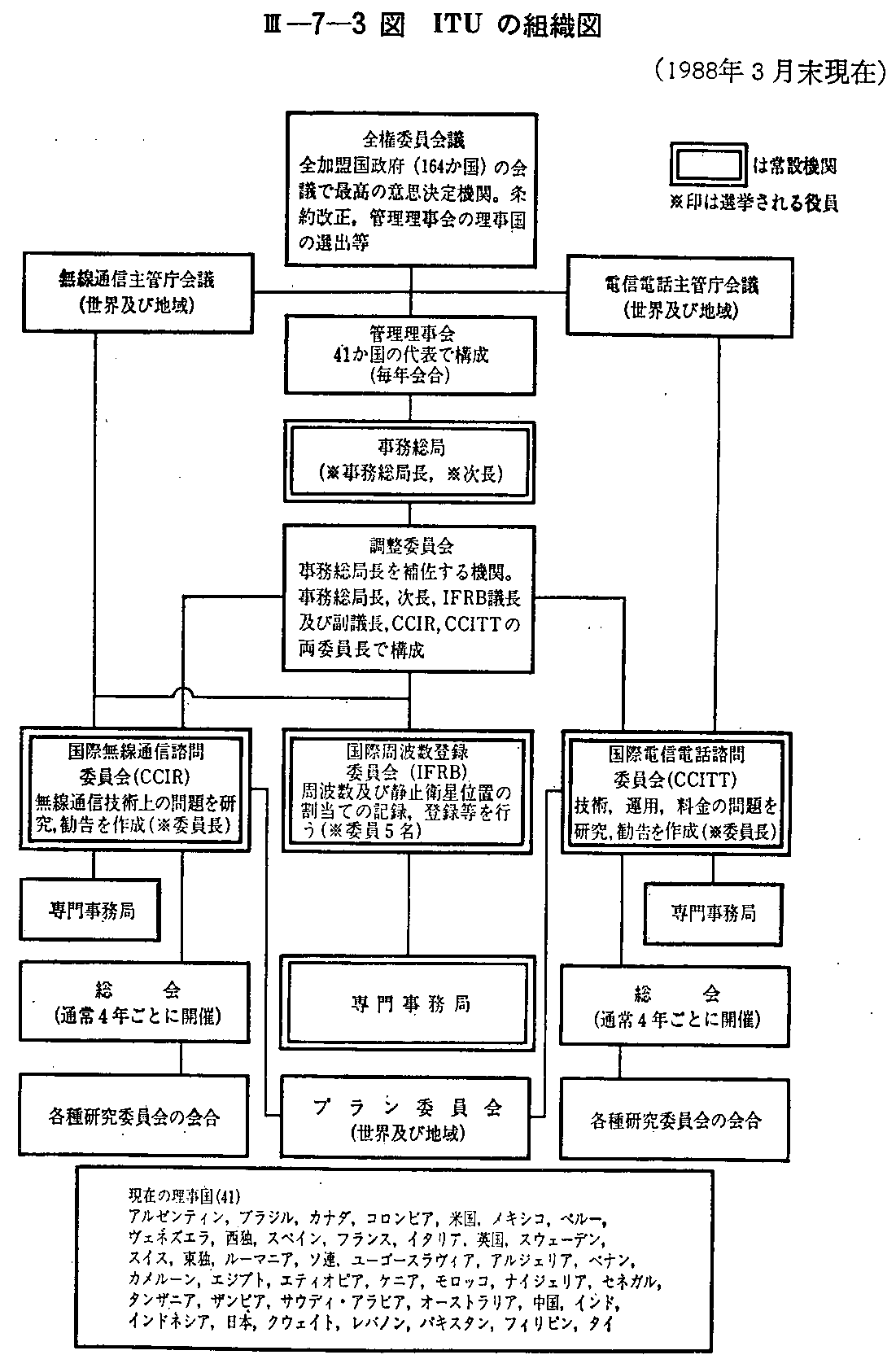
ウ 活動状況
62年度においては,第42会期管理理事会が1987年6月15日から同26日までの間,スイスのジュネーヴ(ITU本部)で開催され,1988年予算案,会議・会合計画,技術協力等について審議が行われた。また,電気通信と宇宙空間の平和利用に関する報告,電気通信開発センターのアドバイザリー・ボード委員の改選等が行われた。
エ 電気通信開発センター
1982年のITUナイロビ全権委員会議決議第20に基づき設けられた「電気通信の世界的発展のための独立国際委員会」(通称:メイトランド委員会)の報告を受けて1985年7月の管理理事会で設置されたものである。メイトランド委員会は,開発途上国からのITUの援助拡大要求に対し,電気通信分野の南北格差解消の方策を探るため設けられたもので,開発センターは,その具体的なものとして提唱されたものである。電気通信開発センターの運営は,各国の官・民からの任意拠出金によって賄われるが,我が国は,1987年分として,20万USドルを拠出し,現在のところ各国の中で最も多い拠出金となっている。
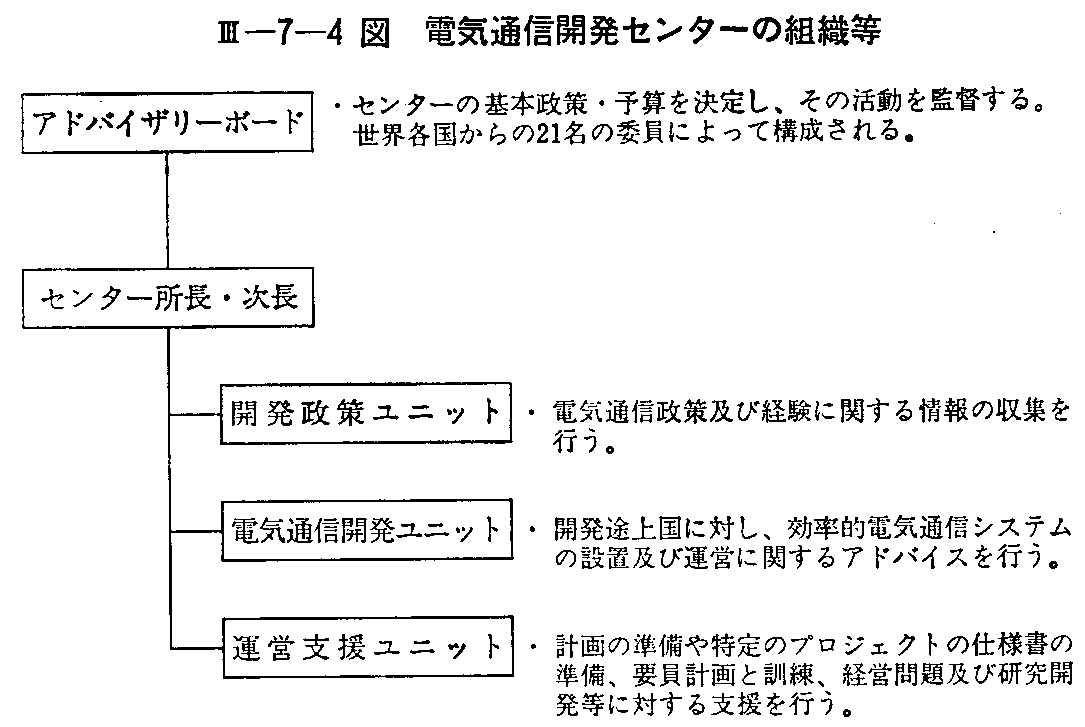
オ 世界無線通信主管庁会議(WARC)
「移動業務に関する世界無線通信主管庁会議」(WARC-MOB)(1987年9月〜10月,ジュネーヴ)は,移動業務,特に遭難及び安全に関する無線通信規則の規定並びに技術の進歩及び新しい方式の導入により移動業務に関する規定を改正するために開催され,[1]移動業務,移動衛星業務,無線航行及び無線測位衛星業務の規定の見直し,[2]GMDSSの実施のための規定の無線通信規則への包含,[3]航空機による公衆通信のための措置等について審議された。
会議では,移動衛星業務サービスのために周波数の分配の見直しがなされ,現在の航空移動衛星(R)業務及び海上移動衛星業務用の1.5GHz及び1.6GHz帯の一部は,陸上移動業務に使用できることとしたほか,GMDSSのための遭難安全周波数,運用手続を新たに定めた。また,GMDSSに対応した無線従事者の資格証明書を新たに設けた。
カ 世界電信電話主管庁会議(WATTC)
世界電信電話主管庁会議準備委員会(PC/WATTC)は,最終会合を1987年4月27日から5月1日までの間ジュネーヴで開催し,1988年のWATTCにおける審議に向けて,国際電気通信規則の草案を作成した。WATTCにおいては,現在及び将来の電気通信技術の進歩,新サービスの導入等を考慮し,現在の電信・電話規則の抜本的な見直しを行うこととなっているが,PC/WATTCにおいては新規則の適用範囲及び被適用主体等をめぐって各国の間で議論が交わされた。
キ 国際無線通信諮問委員会(CCIR)
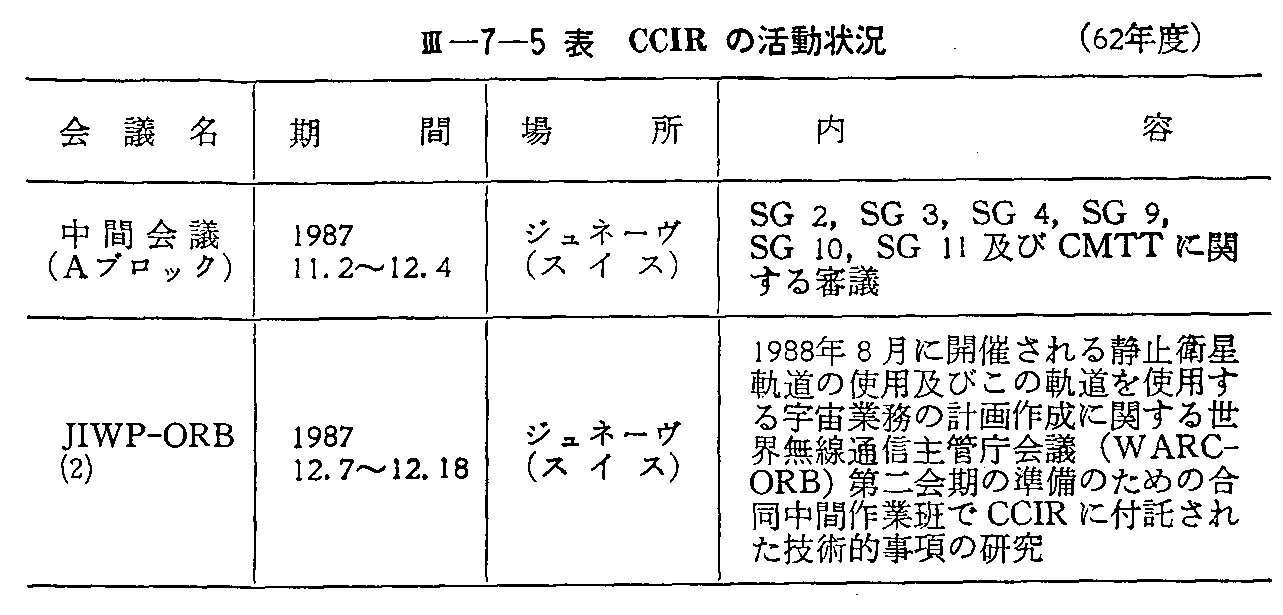
ク 国際電信電話諮問委員会(CCITT)
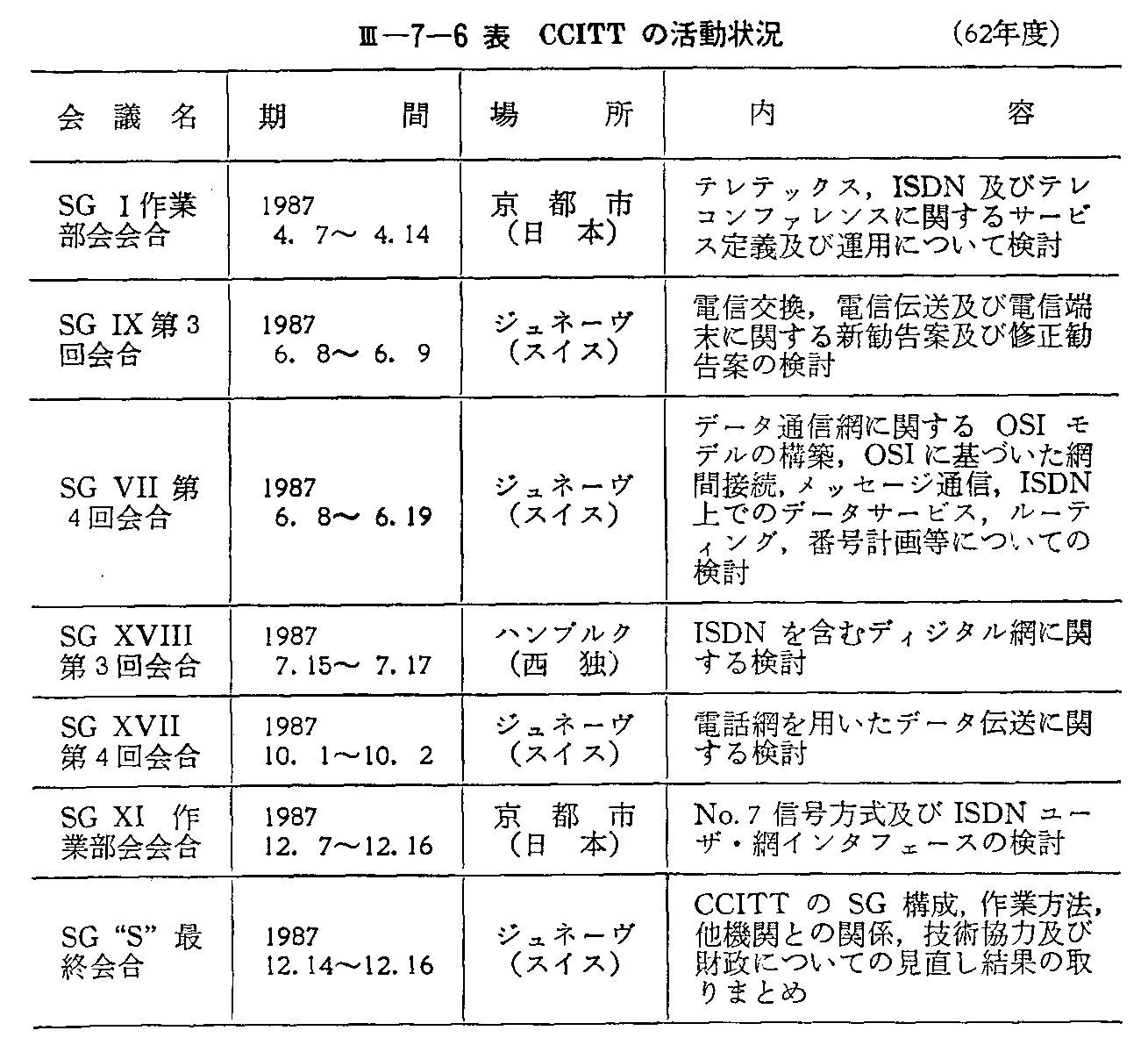
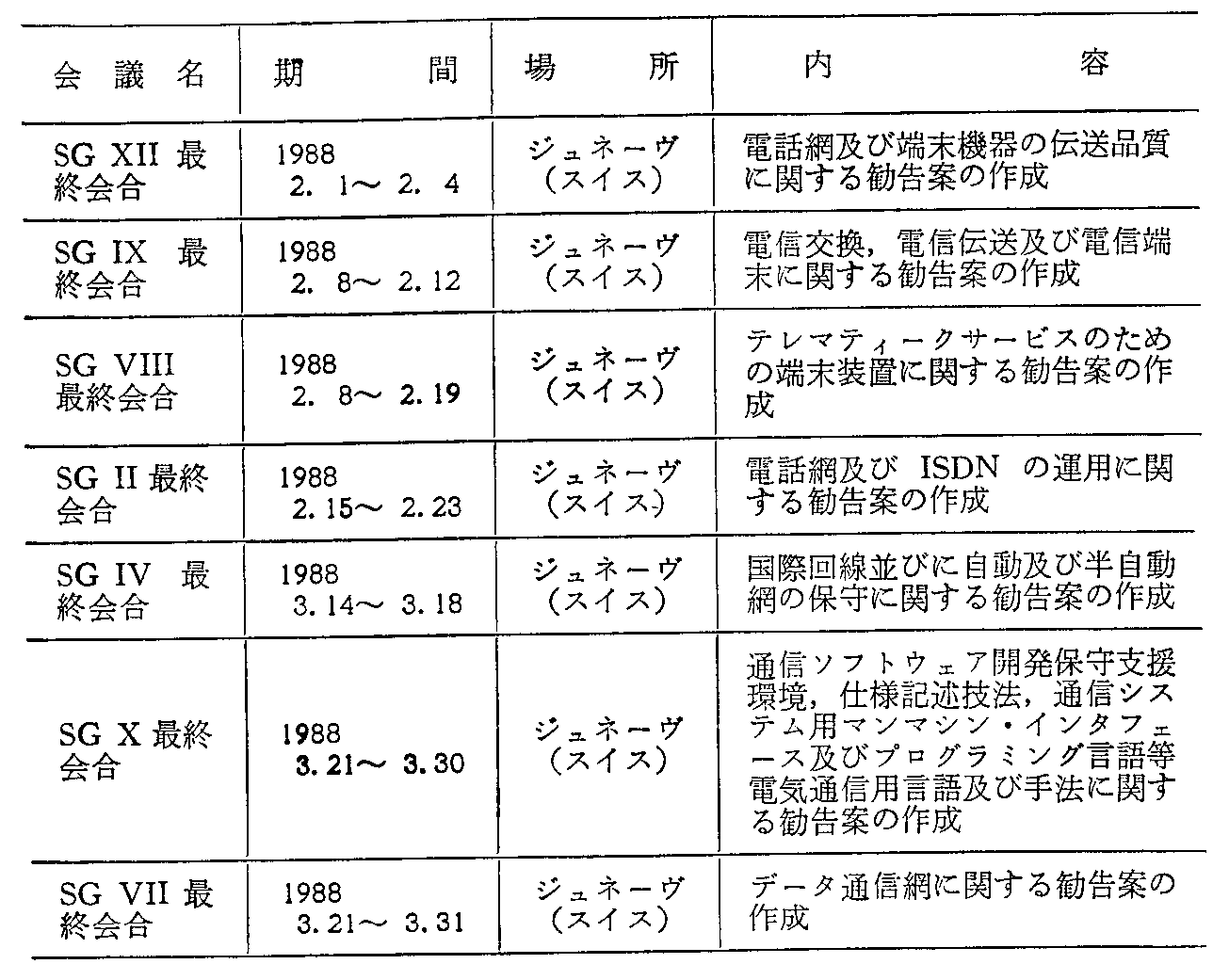
ケ 国際周波数登録委員会(IFRB)
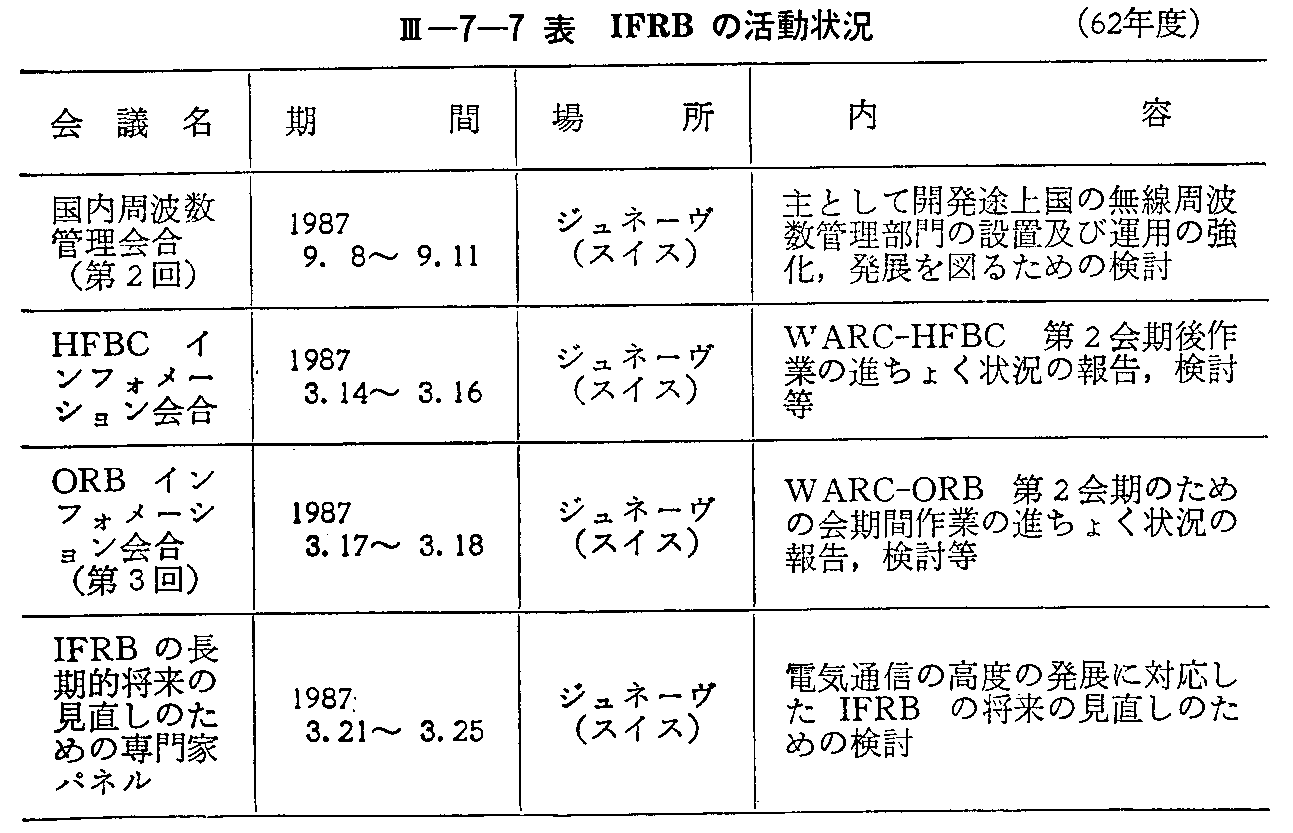
(3)国際電気通信衛星機構(INTELSAT)
ア 概要
インテルサットは,国際公衆電気通信業務に必要な宇宙部分(衛星及びその管制等に必要な関連地上設備)を加盟国,非加盟国を問わず世界のすべての地域の政府,又は政府が指定した電気通信事業体に提供することを主たる目的とする国際機関であり,1987年12月末現在の加盟国数は114か国である。
1964年8月に暫定的制度として発足した後,1973年2月,「国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する協定」及び「国際電気通信衛星機構(インテルサット)に関する運用協定」が発効して恒久的制度となっている。
両協定のうち,前者は,インテルサットに加盟する国の政府が署名する政府間協定で,機構の組織等の基本的事項を規定するものであり,後者は,インテルサットに出資してその運営に参画する国の政府,又は政府が指定した電気通信事業体が署名する協定で,機構の財政・運用に関する事項を規定するものである。我が国は,この電気通信事業体としてKDDを指定している。
インテルサットに対する我が国の出資率は,1987年12月末現在,最も多い米国(25.633356%)から数えて4番目の4.409273%となっている。
イ 組織
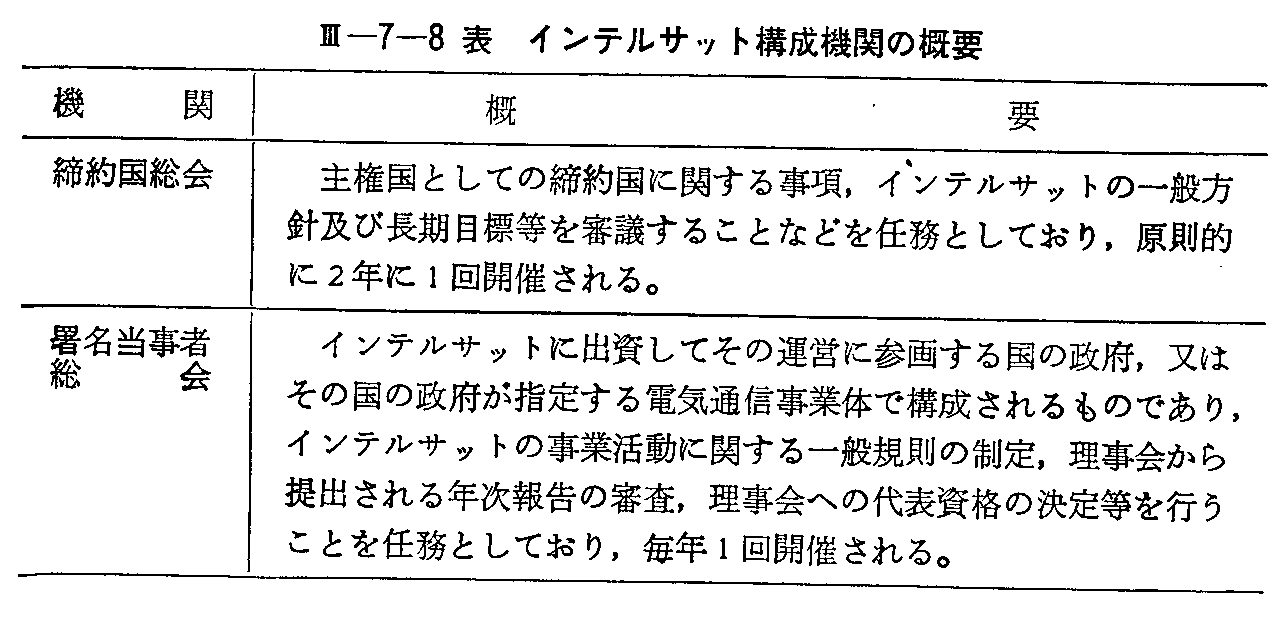
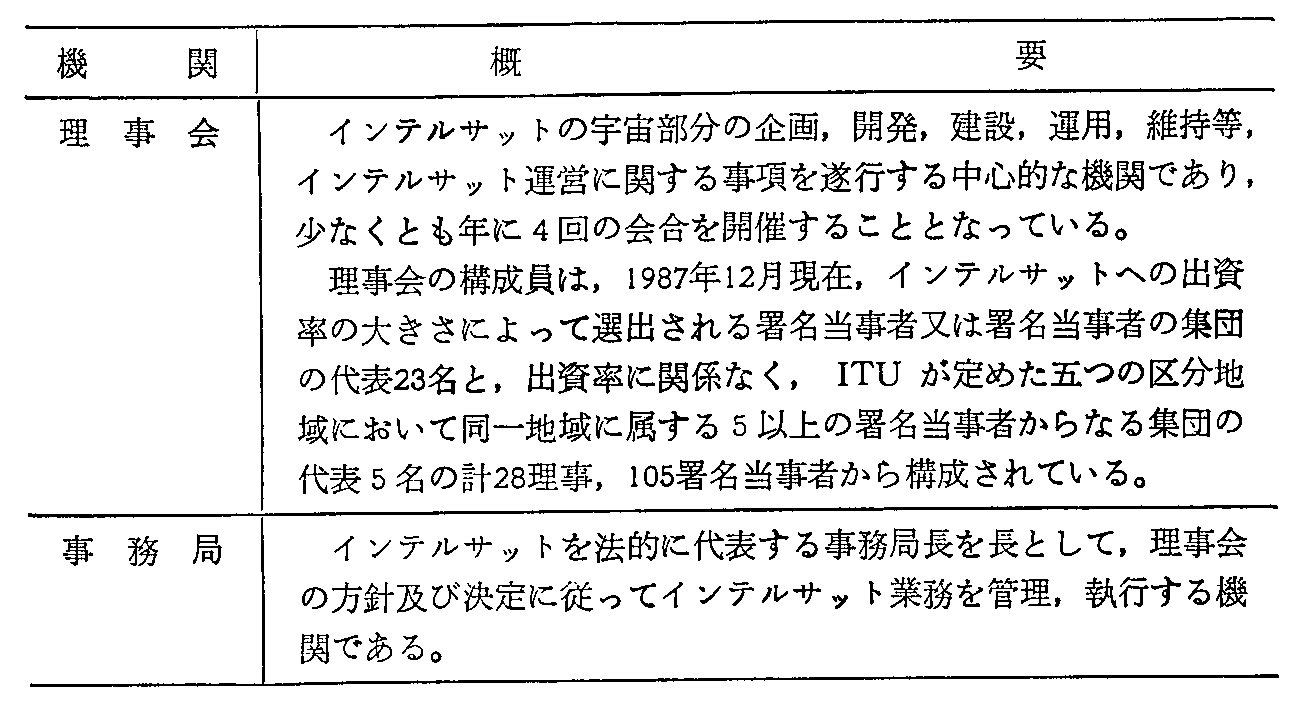
ウ システム構成
インテルサット・システムは,インテルサットが所有する宇宙部門と各国の政府又は政府が指定した電気通信事業体が所有する地球局とで構成される。
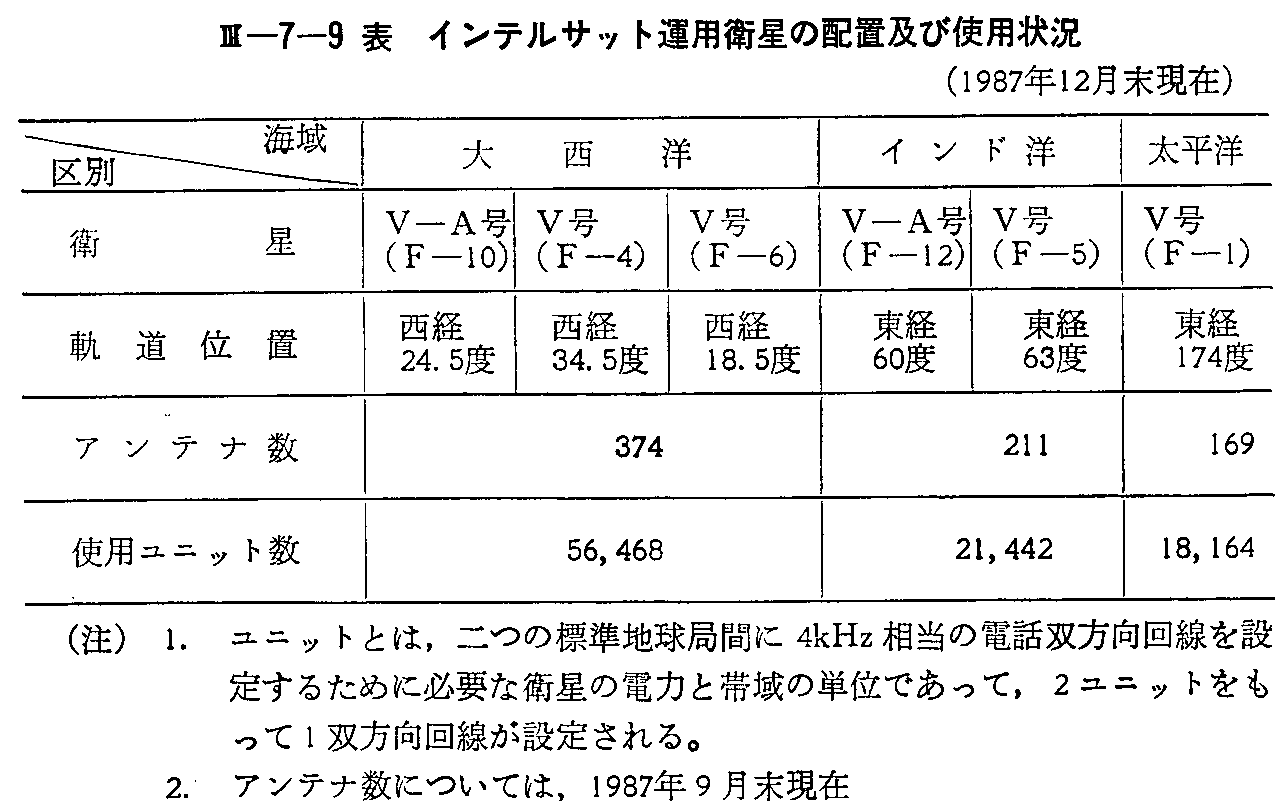
エ 活動状況
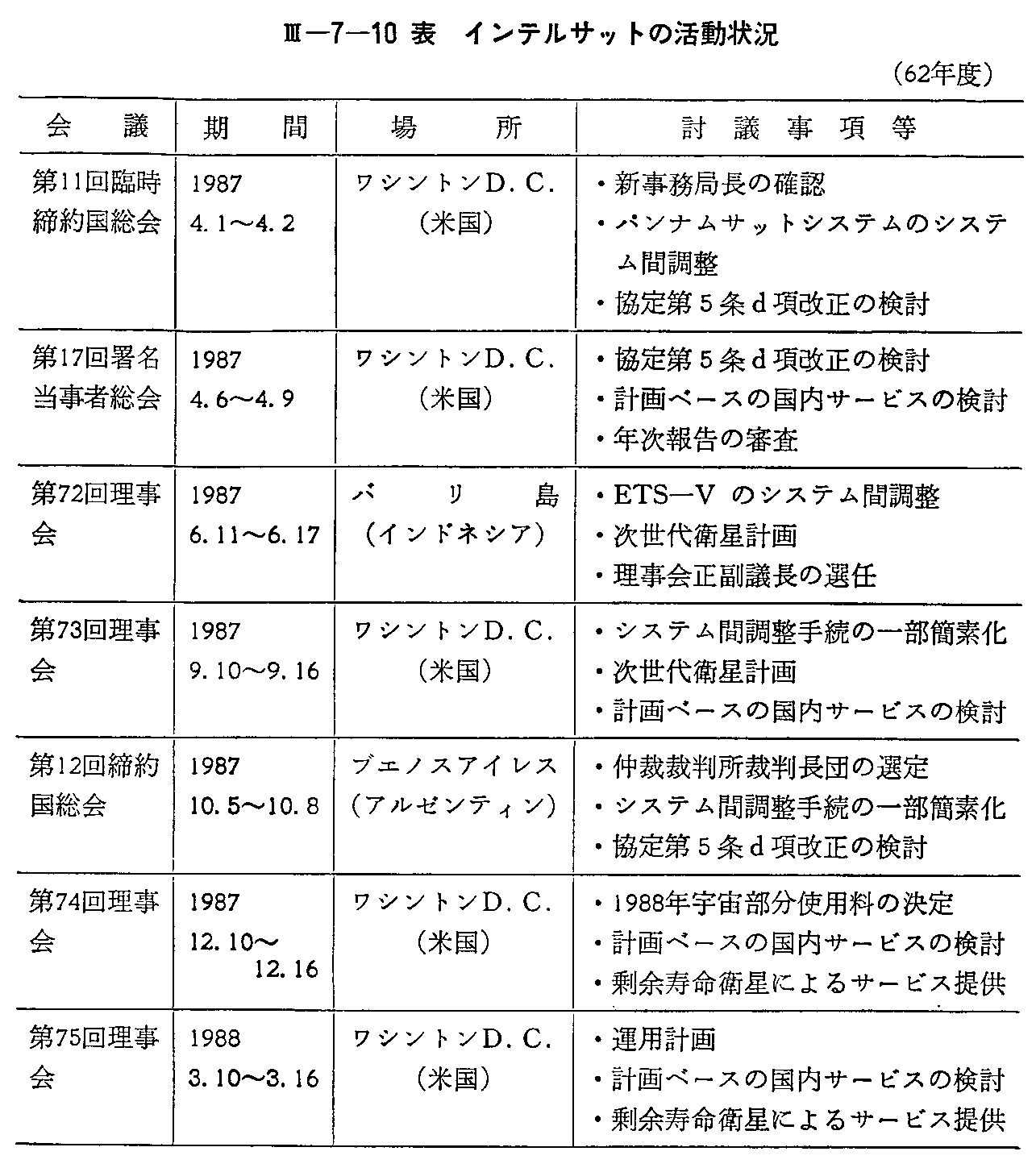
(4)国際海事衛星機構(INMARSAT)
ア 概要
インマルサットは,海事通信を改善するために必要な宇宙部分(衛星及びその管制等に必要な関連地上設備)をすべての国籍の船舶による使用のために開放し,これにより海上における遭難及び人命の安全に係る通信,船舶の効率及び管理,海事公衆通信並びに無線測位能力の改善に貢献することを目的とした国際機関であり,1988年2月末現在の加盟国は54か国である。
1979年7月の「国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約」及び「国際海事衛星機構(インマルサット)に関する運用協定」の発効に伴い発足した。
同条約は,インマルサットに加盟する国の政府が締結する政府間条約で,機構の組織等の基本的事項を規定しており,また,同運用協定は,インマルサットに出資してその運営に参画する国の政府,又はその国の政府が指定した権限ある事業体が署名する協定であり,機構の財務・運用に関する事項を規定している。我が国は,この権限ある事業体としてKDDを指定している。
インマルサットに対する我が国の出資率は,1988年2月末現在,最も多い米国(27.48619%)から数えて4番目の9.47941%となっている。
イ.組織
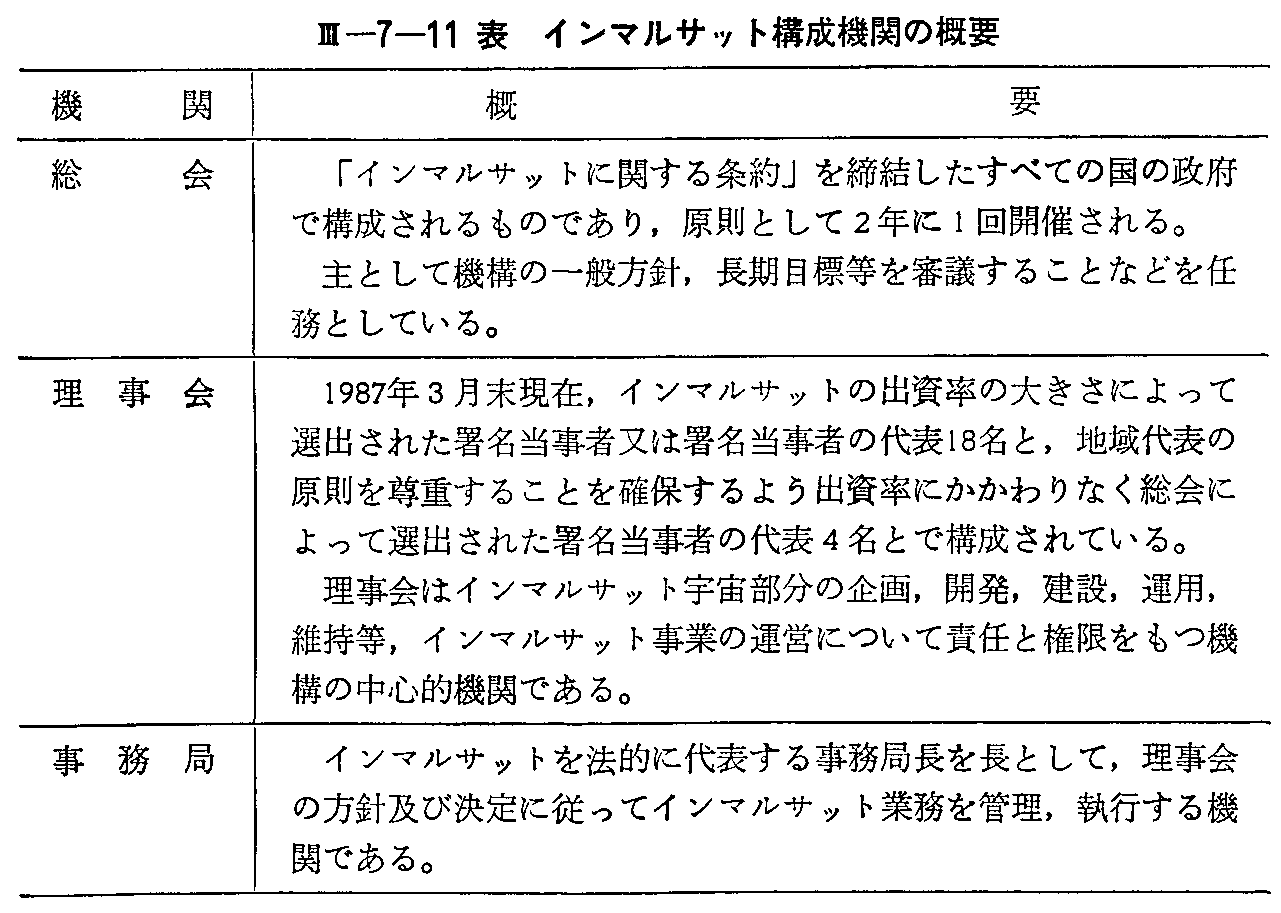
ウ.システム構成
インマルサット・システムは,大西洋海域を欧州宇宙機関(ESA)からリースしたマレックス衛星,インド洋及び太平洋海域をインテルサットからリースしたインテルサット<5>号衛星に搭載の海事通信サブシステム(MCS)で各々カバーしている。
なお,インマルサット・システムを利用して海事通信を行っている船舶等は,1987年12月末現在で,93か国の6,484隻である。
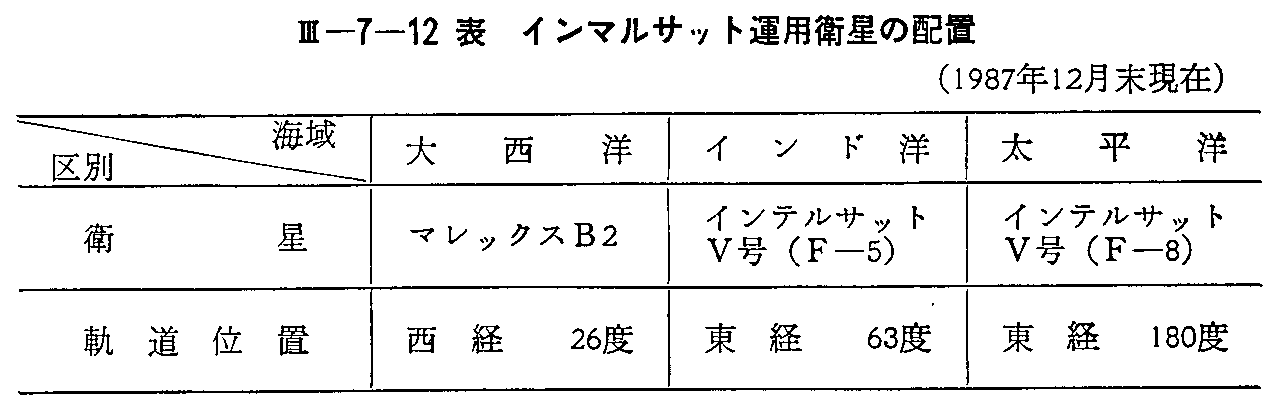
エ.活動状況
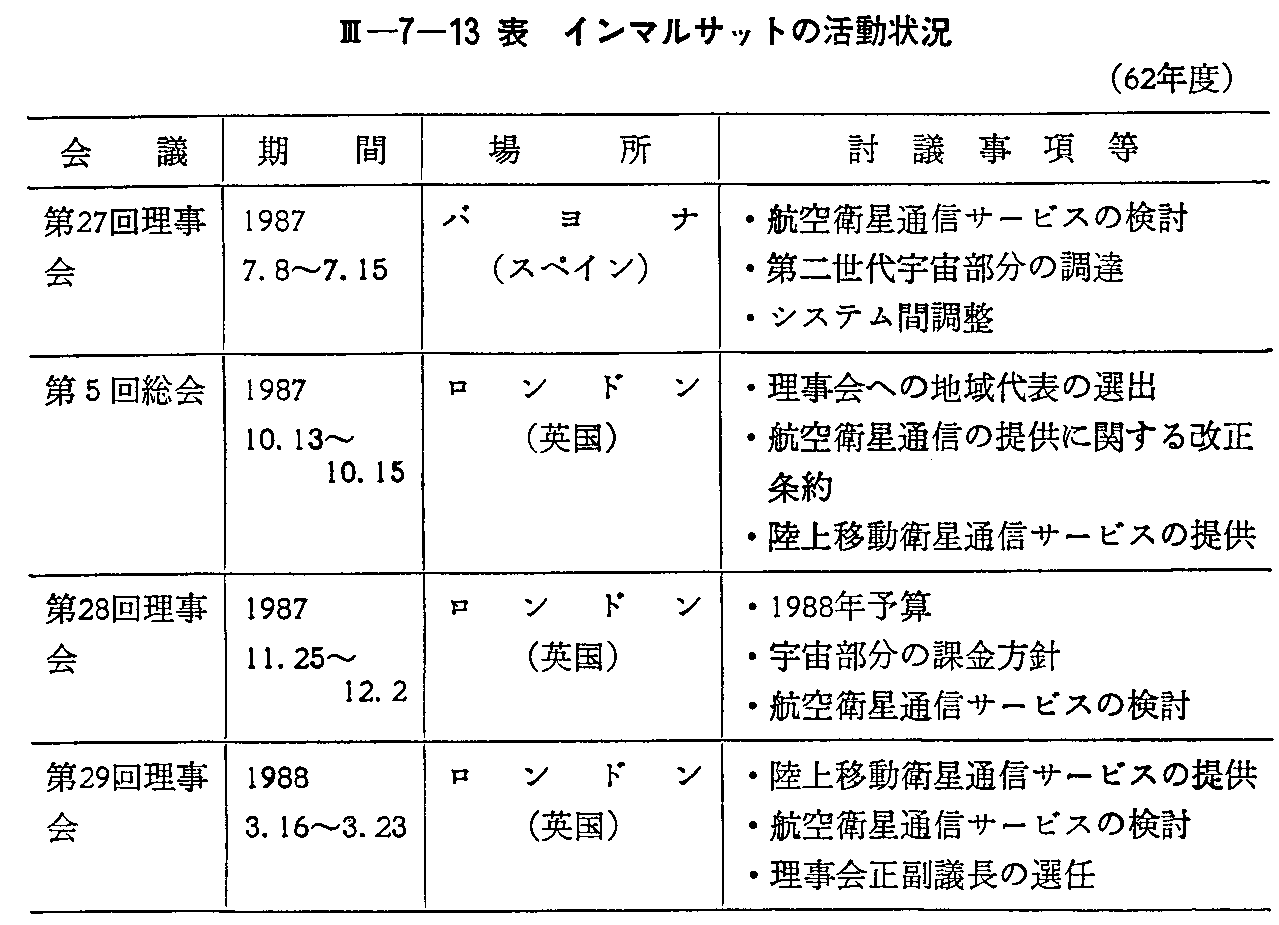
(5)アジア・太平洋電気通信共同体(APT)
ア.概要
APTは,アジア・太平洋地域における電気通信の開発促進及び地域電気通信網の整備を主たる目的としており,1976年3月の第32回ESCAP総会において設立憲章が採択された。我が国は1977年11月25日に同憲章の受託書を寄託した。同憲章は,APT本部所在国であるタイを含む7か国の批准書又は受託書が寄託されて1979年2月に発効した。
APTは国際電気通信条約(1982年ナイロビ)の規定に合致する地域的電気通信機関であり,1988年3月末現在,加盟国21か国,準加盟国(地域)2か国及び賛助加盟員13事業体から構成されている。
イ.組織
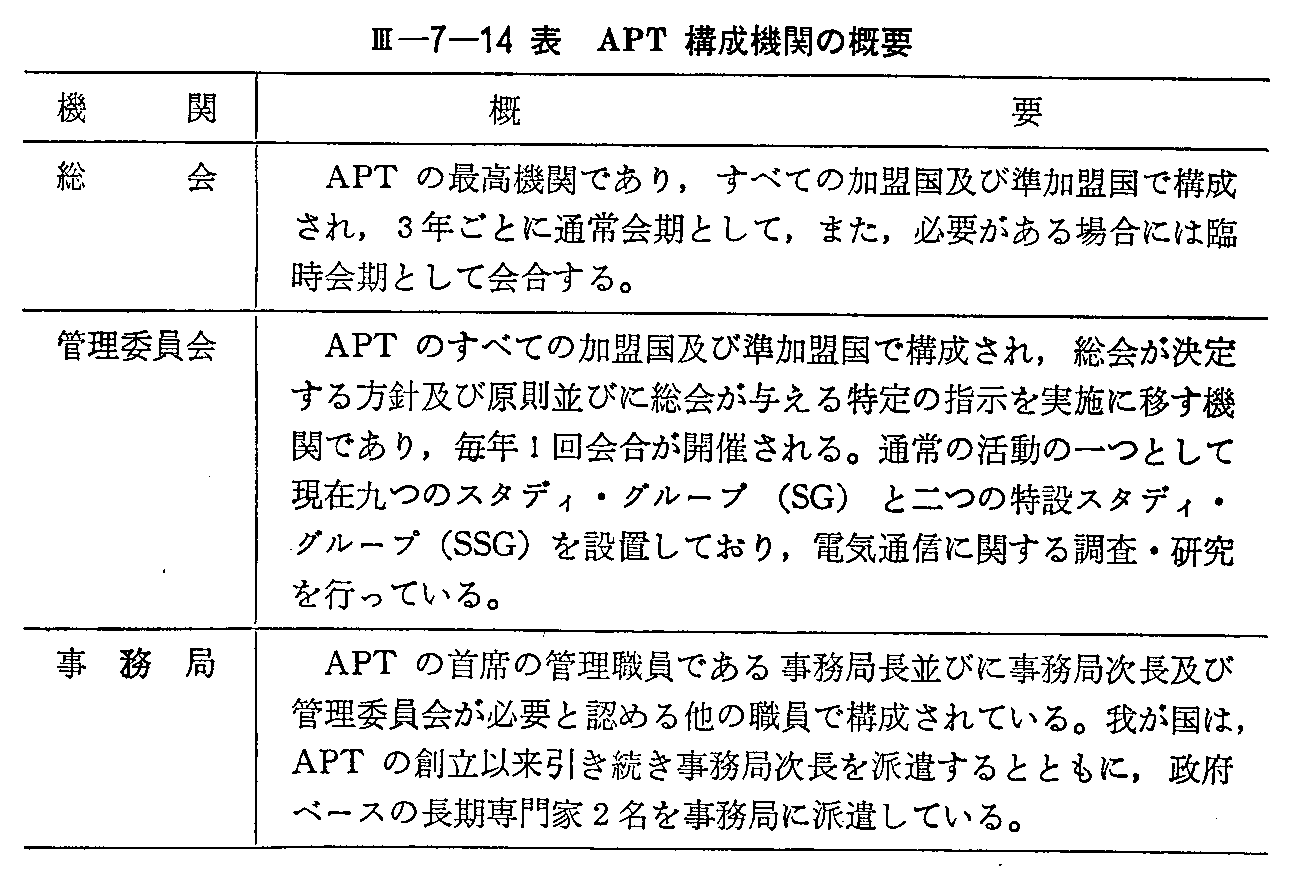
ウ.活動状況
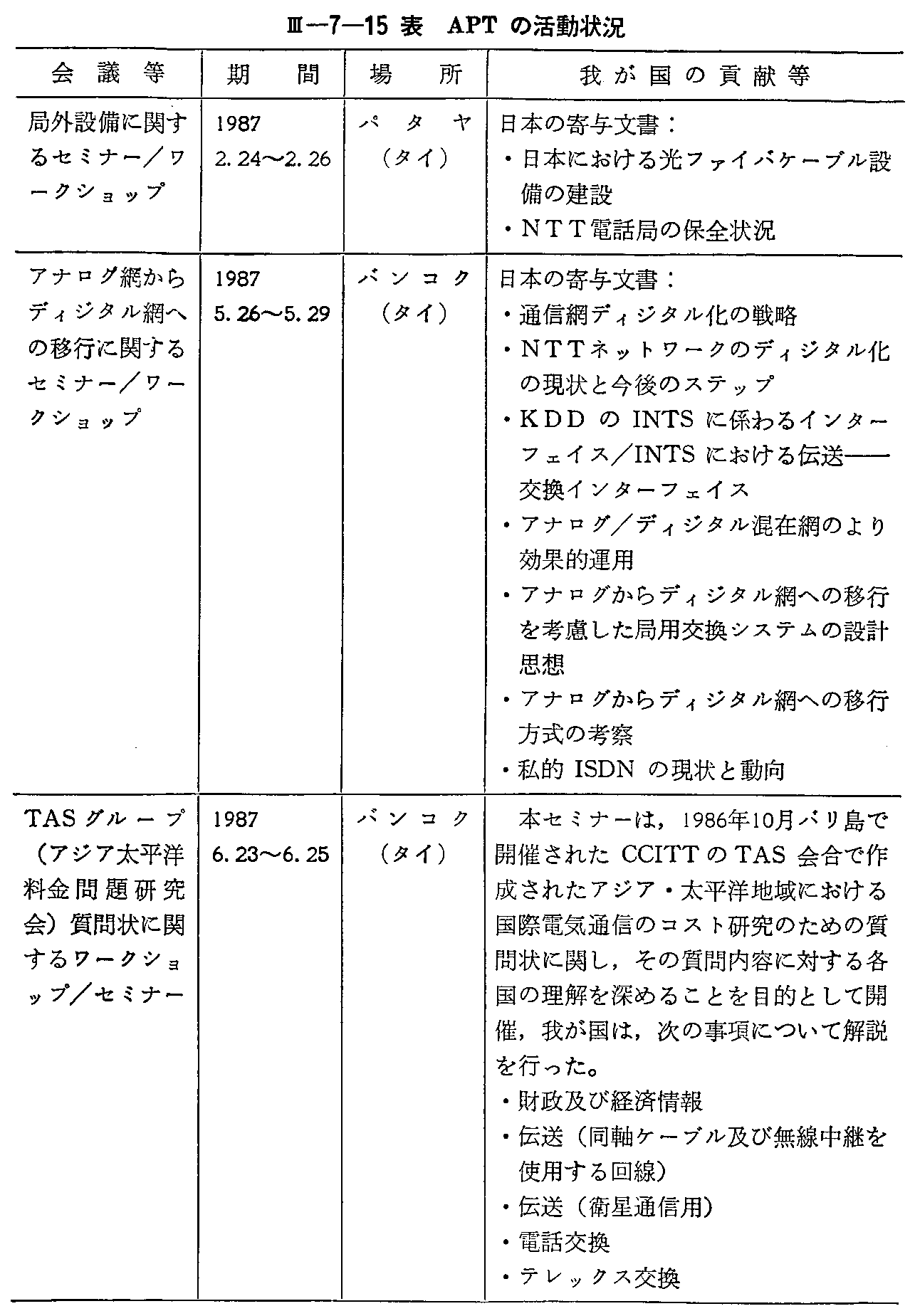
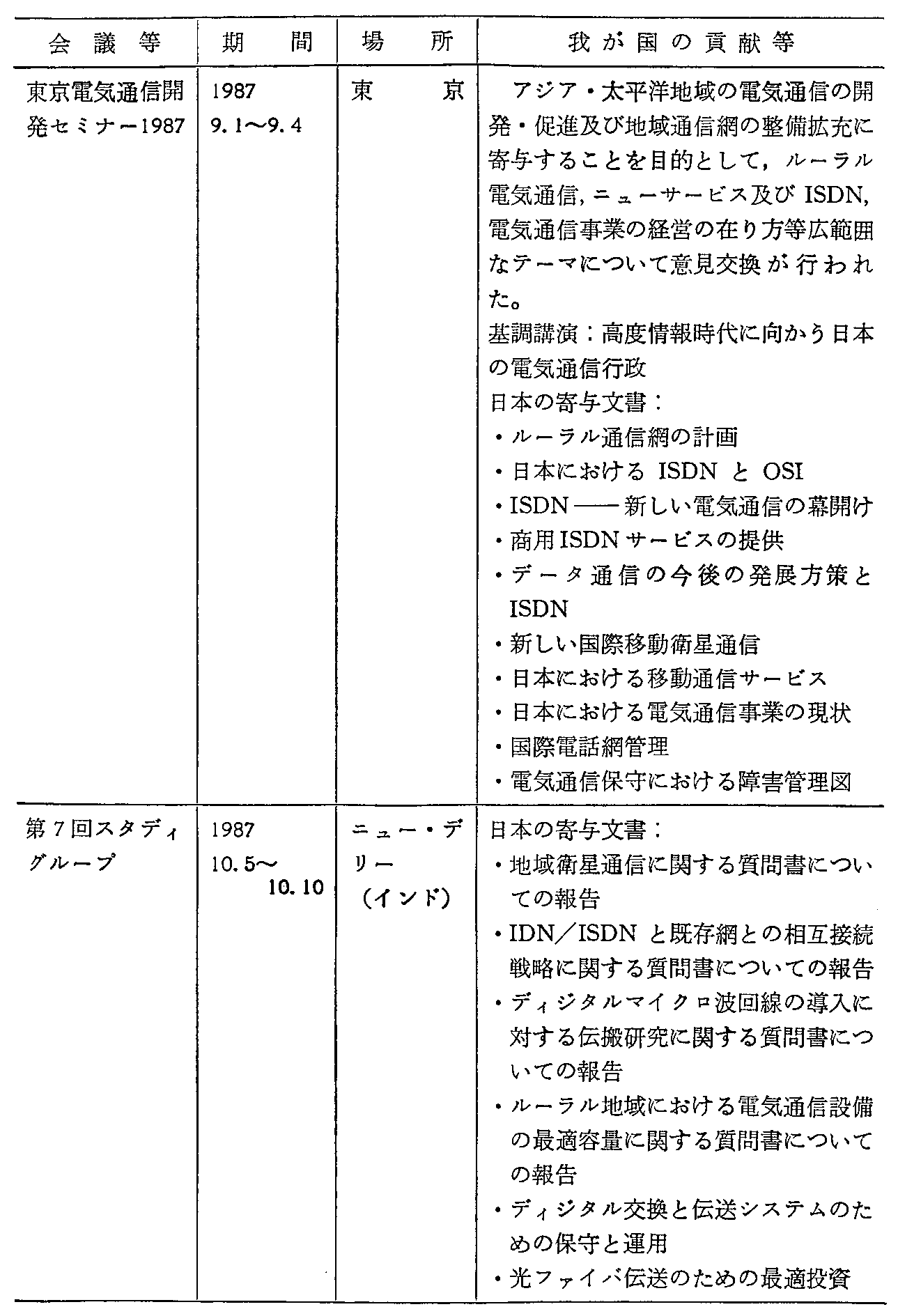
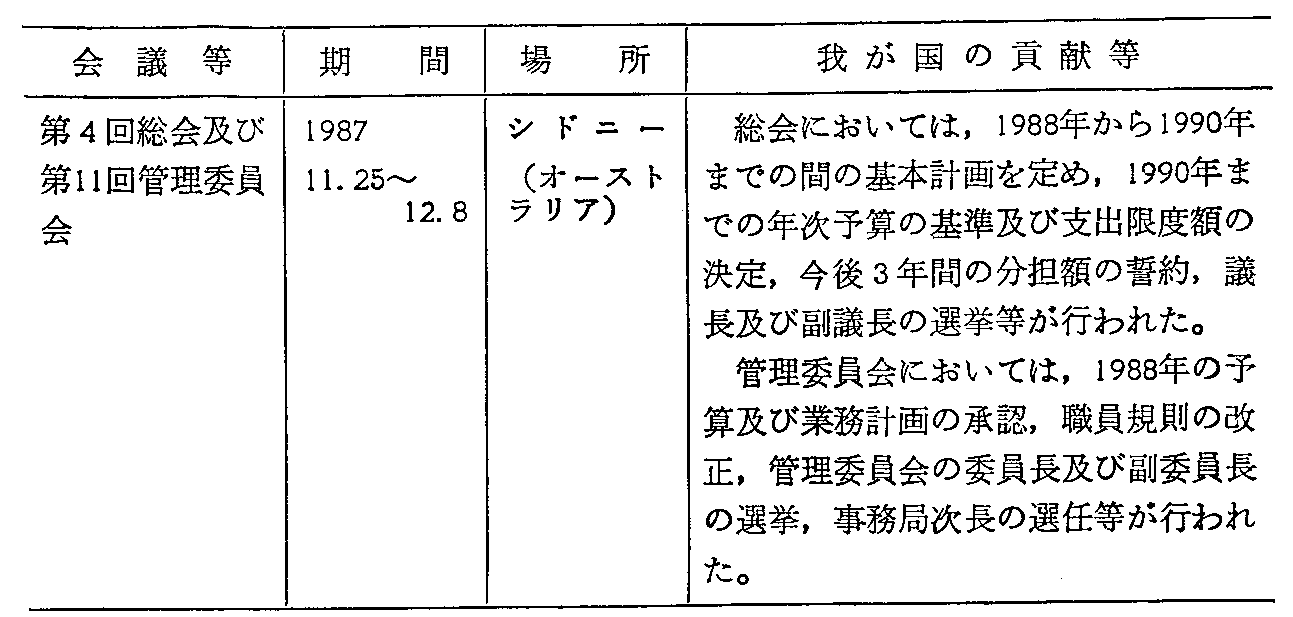
(6)国際連合アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)
ア.概要
ESCAPは,国連経済社会理事会の監督下にある地域経済委員会の一つで,1947年3月に設立された国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の名称が変更され(1974年9月),現在に至っているものである。
ESCAPの本部はタイのバンコクにあり,アジア・太平洋地域の経済・社会開発の促進のための協力をはじめ,これに関する調査・研究・情報収集等を行っている。1988年3月末現在加盟国は,域内国42か国(うち準加盟9か国),域外国5か国の計47か国である。
なお,我が国は1952年に準加盟国,1954年に加盟国となった。
イ.組織
ESCAPには,総会の下部機構として,九つの常設委員会があり,その一つである海運・運輸通信委員会の運輸・通信・観光ウイングは,隔年ごとに開催され,そこでは域内の電気通信及び郵便の開発に関する技術及び経済関係の諸問題の討議勧告及び勧告を行い,その実施状況について検討が行われている。
ウ.活動状況
1987年4月に開催された第43総会において,我が国は,国を支えるあらゆる分野での人材を広く養成し,もって人材層を厚くしていくことを目指す長期的な「ESCAP総合人造り計画」の策定を提唱したが,この計画策定の第一歩として1987年12月7日から12月10日まで,東京においてエスカップ人造り専門家会合を開催した。この会合においては,人造りの主要分野として,雇用と人材開発,科学・技術,及び生活改善の三つの分野を中心に討議が行われた。
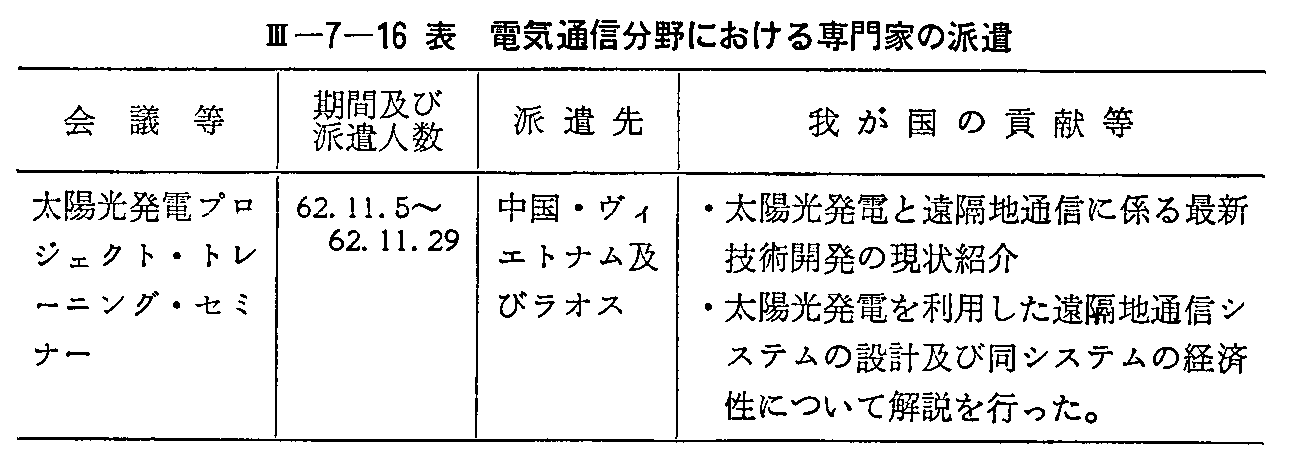
(7)国際海事機関(IMO)
IMOは,海運に影響のあるすべての種類の技術的事項について国際協力を促進することを目的として設立された国際連合の専門機関の一つであり,政府間海事協議機関(IMCO)の名称が変更され(1982年5月),現在に至っているものである。
我が国は1958年3月に加盟しており,1987年12月末現在の加盟国数は準加盟国を含め132か国である。
イ.組織
IMOは,総会,理事会,各種委員会及び機関が必要と認める補助機関並びに事務局で構成されている。無線通信に関する事項は,主として,海上安全委員会及び無線通信小委員会で審議されており,現在,1991年の導入に向けて,「全世界的な海上遭難安全制度(FGMDSS)」の審議に重点を置いている。
ウ.活動状況
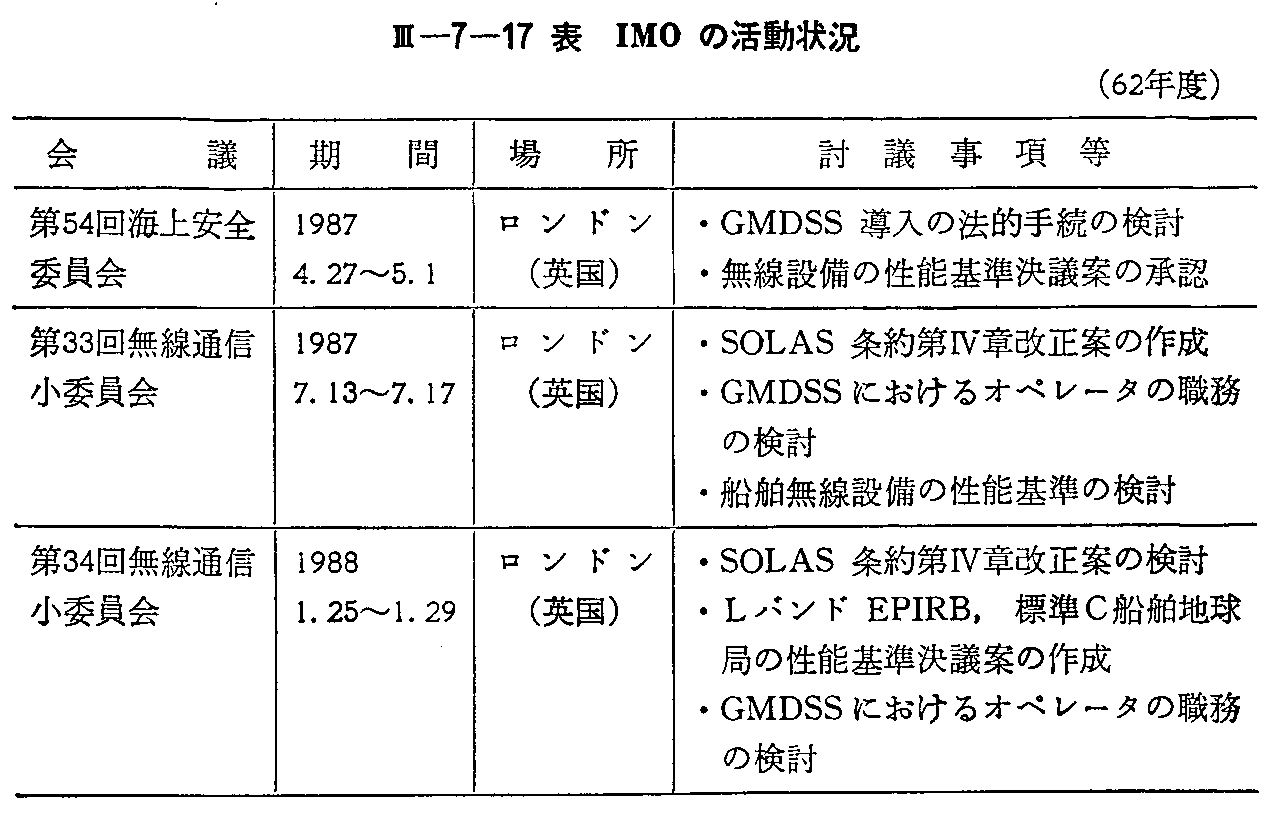
(8)国際民間航空機関(ICAO)
ア.概要
ICAOは,国際民間航空の安全かつ秩序ある発展及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営を目的に設立された国際連合の専門機関の一つである。
我が国は1953年10月に加盟国となっており,1987年12月末現在の加盟国数は157か国である。
ICAOの主要な任務には,航空通信の要件,無線設備の技術基準,航空通信に分配された周波数の使用等について,国際的な統一基準を設定することが含まれており,これらの具体的な内容は,国際標準・勧告方式として国際民間航空条約の附属書に規定されている。
イ.組織
ICAOの組織は,総会,理事会,事務局等のほか,それぞれの分野における専門的な活動を行う各種委員会や,地域航空会議等の補助機関により構成されており,無線通信に関する事項は,主として,航空委員会及びその下部機関である通信部会等で審議され,その結果を理事会に勧告,助言することになっている。
ウ.活動状況
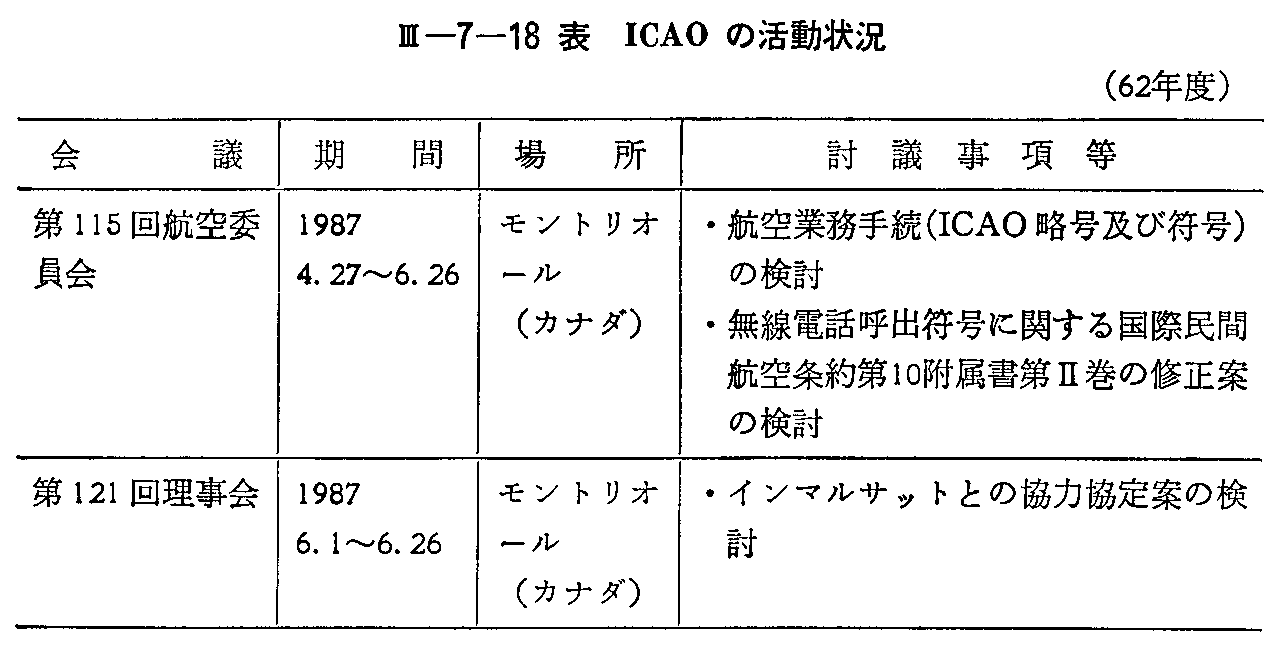
(9)経済協力開発機構(OECD)
ア.概要
OECDは,1961年に発足した西側先進工業国間の経済に関する国際協力機関であり,我が国(1964年加盟)を含む24か国が加盟している。その目的として,経済成長,開発援助,貿易の拡大の三つを掲げており,これを達成するため,加盟国相互の情報及び経験の交換,政策の調整,共同研究等を行っている。
イ.組織
OECDの組織は,正式意思決定機関であり全加盟国によって構成される上部機構である理事会のほか,経済政策委員会,開発援助委員会,貿易委員会等約30の各種委員会及び事務局等から構成されている。また,民間の諮問機関として,経済産業諮問委員会(BIAC),労働組合諮問委員会(TUAC)が設けられている。専門委員会の一つである情報・コンピュータ・通信政策(ICCP)委員会では,情報通信の経済的側面を中心とした検討を行っており,62年度には3回の定期会合の他に,「VAN」,「電気通信の構造変化の経済社会的効果」,「電気通信サービスの自由化の影響」等各種のアド・ホック専門家会合が開催された。
1987年12月には,1982年に本委員会が設立されて以来初の「ハイレベル会合」が開催され,情報通信分野に関するこれまでの活動を振り返るとともに,今後のICCP委員会の方向付けがなされた。また,ギリシャのアテネで地域開発のための情報通信技術に関するセミナー」が開催されている。
その他の委員会においても,電気通信に関する諸問題が注目されるようになっている。貿易委員会では,サービス貿易の自由化に関する検討が行われており,情報通信分野についてもICCP委員会のレポートをベースに検討が進められている。また,国際投資・多国籍企業委員会においては,電気通信事業をはじめとするサービス分野における,外資企業への内国民待遇の適用に関する検討に力を入れている。さらに,資本移動・貿易外取引委員会では,「資本移動自由化コード」と「経常貿易外取引自由化コード」の2つのコードにより加盟国に課されている自由化義務の履行状況をウォッチしている。自由化義務には,[1]条件が整備されるまで自由化を猶予する「留保」,[2]コード第3条「公の秩序・安全保障」に基づく規制,による2つの例外がある。本委員会では,これら例外措置の濫用を防ぎ,合理的かつ円滑な資本移動,貿易外取引の自由化を推進するために,各国の自由化の推進状況を検討している。
ウ 活動状況
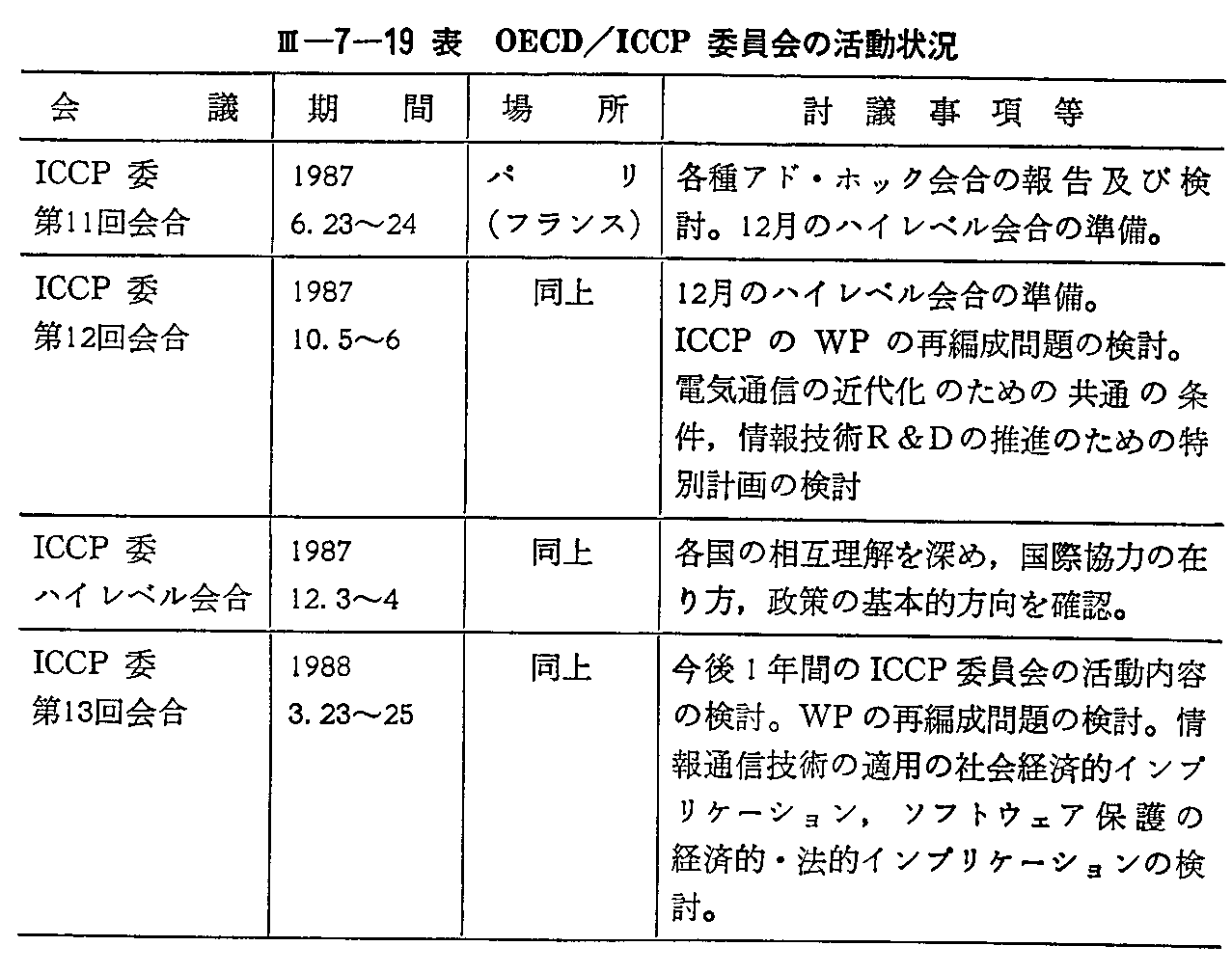
(10)GATT(関税及び貿易に関する一般協定)
ア 概要
GATTは,発足以来,東京ラウンドまで7回にわたる関税交渉を通じて加盟国の関税水準の引下げ及びダンピング・補助金等の非関税障壁の撤廃を進めてきたが,1986年9月に開始が宣言されたウルグアイラウンドでは,従来の物の貿易に関する交渉のほか,新たにサービスの貿易自由化のための交渉を行うことが決められた。サービス貿易に関する交渉の期間は4年とされ,個別分野の有りうべき規律の策定を含め,サービス貿易に関する原則及び規律についての多角的枠組みを確立することを目指している。
電気通信サービスは,金融,運輸と並んで交渉の主要な分野になるものと見られており,交渉の進み方次第では,国際的にこの分野の自由化が進むことが予想される。
1987年1月に交渉計画が決定された後,第1回会合が2月に開催されたのを始め,1987年中には合わせて6回の会合が開催され,サービス貿易の定義及び統計,サービス貿易に適用される原則,枠組みの適用範囲等について各国の意見が交換された。
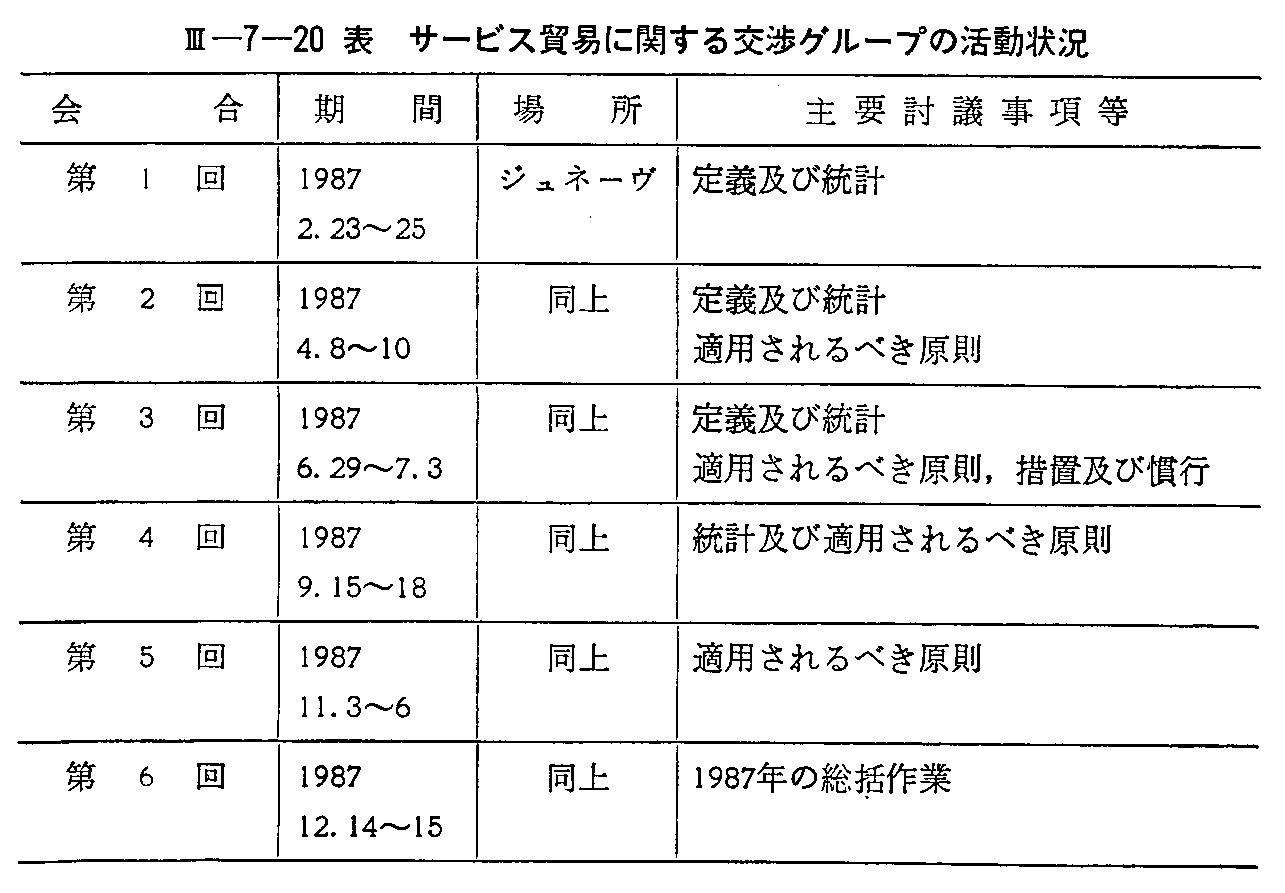
|