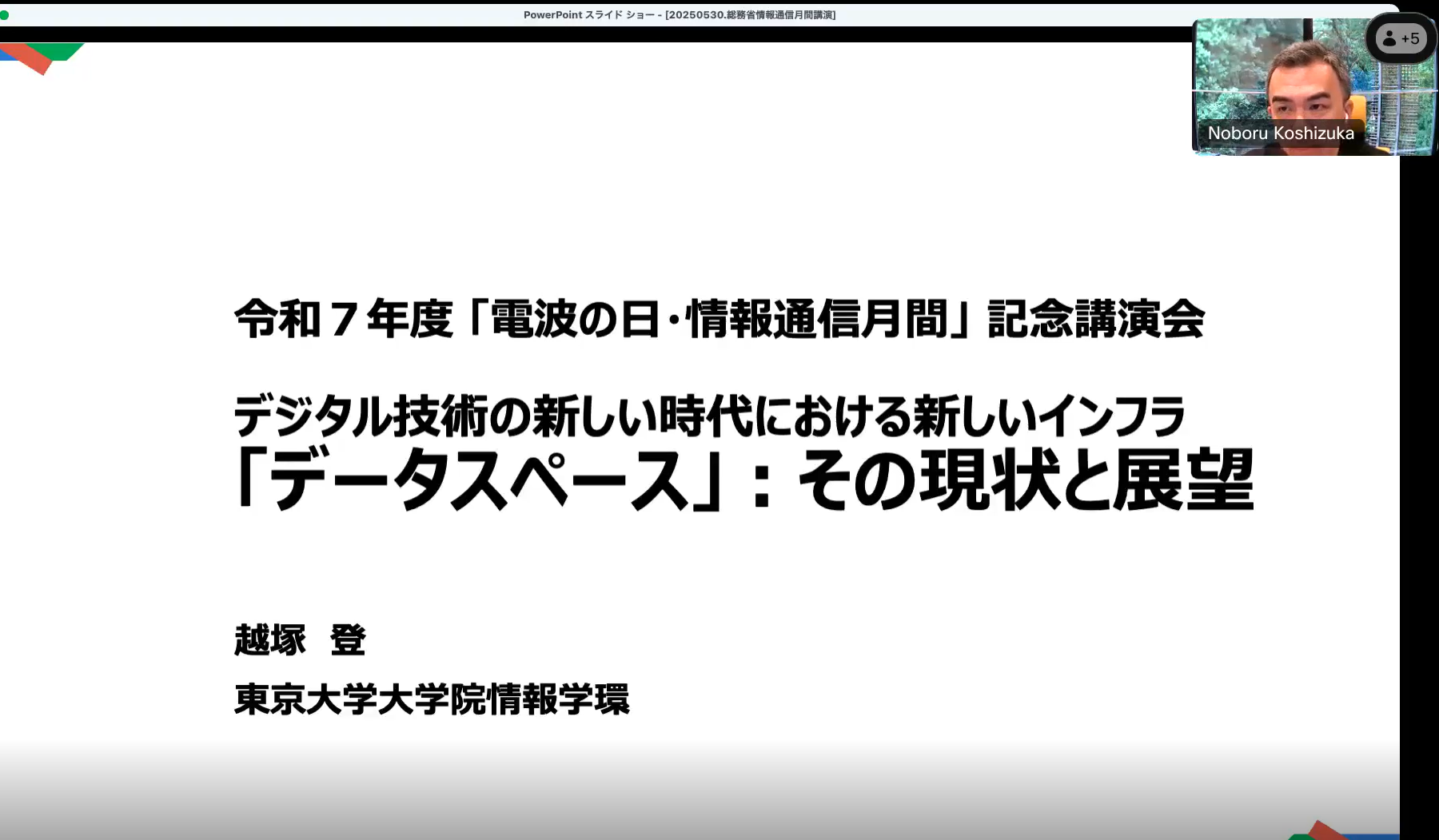本記念講演会は、関東情報通信協力会会員及び一般参加者215名の方々に御聴講いただきました。
主催者挨拶の後、講師の越塚氏より、新しい時代の新しいインフラとして注目される「データスペース」について、次のようなご講演をいただきました。
【デジタル技術の新しい時代における新しいインフラ「データスペース」:その現状と展望】
講師:東京大学大学院 情報学環 教授 越塚 登 氏
現在、日本は人口減少や高齢化、特に社会保障費を中心とする財政支出の増加といった構造的な課題に直面しています。これまでの成長モデルから脱却し、成熟社会にふさわしい新しい社会の形を作っていく必要があると感じています。日本全体の生産性を底上げしていく上でデジタル技術は非常に重要な役割を果たすと考える一方、残念ながら日本のデジタル分野は、インフラやプラットフォーム部分での主導権を握れていない現状が浮き彫りになっています。
一方、デジタル技術は約20年ごとにパラダイムシフトを迎える流れにありますが、現在も大きな転換期を迎え、新しくAIとデータの時代に突入していると言えます。これにより、これまでのGAFAのような企業とは異なる新しいプレイヤーが台頭している状況で、日本にとってもデジタル分野における挽回の機会が巡ってきていると考えられます。
この新しい時代においては、これまでのインターネット等のレイヤーに加えてグローバルにデータを流通させる信頼性のあるインフラのレイヤーが必要であり、それが「データスペース」であると考えています。このレイヤーの考え方にはいくつか異なるものがありますが、そのうちヨーロッパと日本ではこれをインターネットと同様にビジネスの基盤となる協調領域と捉えており、これが理想的な在り方と捉えています。これをどのような形で成立させていくかが世界的な競争の争点となっています。
データスペースの定義については、国際的に完全に合意されておらず、若干の揺れがありますが、単なるシステムではなく、データの共有・流通を支える技術的な仕組みと、それを運用するためのルール・ガバナンス・組織体制を含めた社会的・技術的なプラットフォームを指しているものです。
データスペースの基本的な考え方は、すべてのデータを一括で共有するのではなく、「必要なデータを、必要な人に、必要なタイミングで」共有できることにあります。そのため、特にデータソースがデータ制御権を持てること、トラストを担保し、信頼できる相手にだけ、必要な分だけ出せる仕組みを作ることが重要であり、これに加えて分散型・連邦型によるアーキテクチャ、API連携等を通じて仮想的に統合されたデータ環境を構築することが必要となります。
こうしたデータスペースに関する取組は「GAIA-X」(※1) をはじめヨーロッパを中心に進んでいますが、日本でも農業、製造業、医療、公共交通等様々な分野でデータ基盤の構築が進んでいます。日本は理念よりもまず実装を優先する傾向があり、トップダウン型のヨーロッパとは異なるアプローチを取っているものの、仕組みそのものの数としてはヨーロッパに引けを取らないと感じています。
例えばモビリティ分野では「Japan Mobility Data Space」が、大阪・関西万博では「データ連携基盤(DLP)」が構築され、その運用が始まっています。また、政府・自治体を中心とするオープンデータ化も進展し、すでに全国で1,449ものオープンデータサイトが存在することは、日本におけるデータスペースの潜在的な力を示していると考えます。
国際連携の観点では、一般社団法人データ社会推進協議会(DSA)(※2) と欧州のFIWARE Foundation(※3)・国際データスペース協会(IDSA)(※4)・GAIA-X等の主要組織と連携を進めるとともに、国際イベントの開催を通じて日本のプレゼンスを高めています。東京大学でもデータスペースのテストベッドを構築し、国際的な研究開発と技術標準化への貢献を進めており、このような取組の中で日本は国際協調のハブとしての役割を果たすことが期待されていると考えています。
今後は、AIとデータスペースの連携・融合が重要になると考えています。AIは汎用的な知識を有しているものの、リアルタイムデータ、企業秘密及び個人情報等の、これまで持ち得なかった領域の情報が不足しています。それらの情報がデータスペースを通じてAIと連携されることで、新しい知性を創造できると考えます。データスペ―スはAIの重要なバックエンドインフラとなり、両者の連携が未来のサイバーインフラの構築につながると考えます。
最後になりますが、今後のデータスペースの取組の推進に向け、政府・自治体においてはデータ分野の司令塔機能の強化と初期投資の拡充に加え、制度を含むトラスト基盤の整備をお願いしたいと思います。ヨーロッパでは数千億円規模の公的投資が行われているところ、日本とは大きな差があり、今後は戦略的な投資が必要だと強く感じています。
また、民間やアカデミアにおいては、技術環境の整備及び技術標準化の推進、若手を巻き込んだコミュニティの拡大、ビジネスモデルの構築、アジアを中心とした国際連携の強化を期待しています。
データスペースは、これからの時代の新しい社会インフラとして、日本の未来を支える大事な要素であると考えています。産官学が連携して取り組むことで、より良い未来を築いていけると信じています。
(※1)GAIA-X:ヨーロッパのデータ基盤構築プロジェクトであり、自律分散型の企業間データ連携の仕組み・フレームワークを構築することが目的である。
(※2)FIWARE Foundation:自治体、企業などの業種を超えたデータ利活用やサービス連携を促すために開発されたソフトウェア群の「FIWARE」を運営する非営利団体。
(※3)国際データスペース協会(IDSA):国際的にデータスペースを推進する組織であり、ビジネス、研究機関、政府機関などと協力して、データスペースのコンセプトと関連技術の開発と実装を進めている。
(※4)一般社団法人データ社会推進協議会(DSA):産官学の連携により分野を超えた公正、 自由なデータ流通と利活用による豊かなデータ社会を実現し、国内はもとより世界と連携し貢献を図ることを目的とした一般社団法人。
講演終了後には、聴講者から「データスペースの概念は非常に先進的で、大所高所の話と感じました。現時点で地域や各自治体としてはこういった話をどのように意識すれば良いでしょうか。」などの質問があり、越塚氏から「データスペースの枠組みを最初から意識する必要はなく、まずは自治体内で『どんなデータを使って地域のエリアで役立てていくか』を考えることが重要です。例えば高知県では、特に温室農業において環境データを収集・活用し、地元の農家とノウハウを共有しながら、県全体での生産性向上に役立てています。こうした現場での実践の中で、データ共有の必要性が高まり、結果的にデータスペースのような仕組みが求められるようになるものと考えています。」との御回答をいただきました。
また、「データスペースについてこれまで講演等を拝聴する機会がほぼなかったので、たいへん勉強になるとともに、充実した時間となりました。」「新しいデータの在り方について考えを深めることができました。」といった多くの感想が寄せられました。
関東総合通信局では、引き続き、関東情報通信協力会との共催により、ICTに関連した様々なテーマによる講演会やセミナーなどの企画を行って参ります。