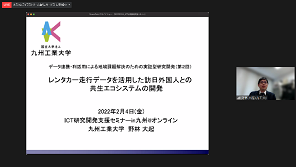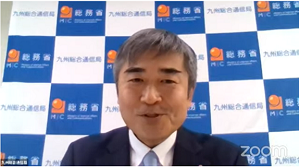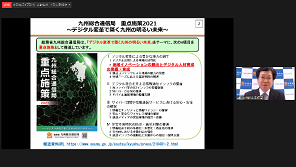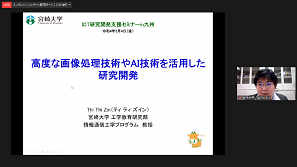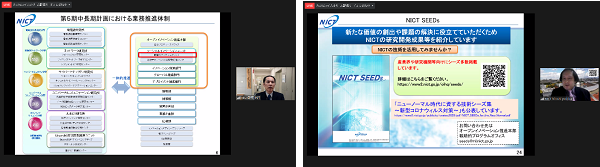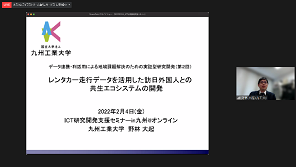九州総合通信局は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)及び一般社団法人九州テレコム振興センター(KIAI)と共催で、令和4年2月4日(金)に「ICT研究開発支援セミナーin九州」を、Zoom及びYouTubeによるオンラインで開催し、当日は219名の参加がありました。
【講演内容】
(1)九州総合通信局の施策紹介
「地域イノベーションの創出とデジタル人材の発掘・育成」
講師:九州総合通信局 情報通信部長 篠原 信
(2)地域のICT研究開発課題の発表
「高度な画像処理技術やAI技術を活用した研究開発」
講師:宮崎大学 工学教育研究部 情報通信工学プログラム
教授 Thi Thi Zin(ティ ティ ズイン)氏
(3)NICTの取組紹介
ア 「NICTの地域連携事例の紹介」
講師:NICT オープンイノベーション推進本部
ソーシャルイノベーションユニット 戦略的プログラムオフィス
統括 野尻 英行
イノベーションプロデューサー 吉田 一志
イ 「『きれいな空気を測定』@北九州市での実証実験」
講師:NICT Beyond5G研究開発推進ユニット テラヘルツ研究センター
テラヘルツ連携研究室 主任研究員 佐藤 知紘
(4)NICTの委託研究「データ連携・利活用による地域課題解決のための実証型研究開発」の研究成果報告
「レンタカー走行データを活用した訪日外国人との共生エコシステムの研究開発」
講師:九州工業大学 工学部 電気電子工学研究系 准教授 野林 大起 氏
冒頭、主催者挨拶として布施田九州総合通信局長から、当セミナーは、九州地域のICT研究開発の支援による地域イノベーションの創出を目指し、当局とNICTが連携して地域のICT研究開発を支援させていただくために、今年度初めて企画したものであり、本日のセミナーに参加し、NICTとの共同研究や実証実験等にご興味を持たれた方は、ぜひ当局やNICTに問い合わせや相談をしてください、と呼び掛けました。
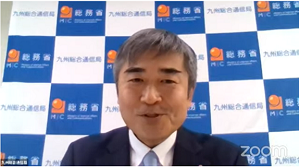
<九州総合通信局 布施田局長の主催者挨拶>
はじめに、当局の篠原情報通信部長より、当局の重点施策2021から「地域イノベーションの創出とデジタル人材の発掘・育成」について紹介しました。
その中でまず、「NICTプログラムを活用したBeyond5G研究開発の推進」、「独創的な技術課題への挑戦の支援」、「ICT起業家やビジネスモデル等の支援」、「ワイヤレス技術の人材育成」などの当局施策の取組状況と今年度の実績について報告しました。
さらに、当局とNICTの連携の必要性について、それぞれが単独で取り組むのではなく両者がしっかりと連携し、NICTの様々な能力や資源を最大限に活用し支援することが、九州管内のICT研究開発に効果的である旨を説明しました。
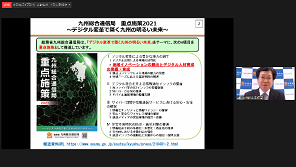
<九州総合通信局 篠原情報通信部長の講演>
次に、宮崎大学のThi Thi Zin教授より、地域のICT研究開発を紹介する講演がありました。
まず、総務省の戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE)「地域ICT振興型研究開発」の採択課題であった「ICTを活用した牛のモニタリングシステムの開発」の成果報告があり、非接触・非侵襲センサー情報の解析アルゴリズムを独自の手法で応用し、生産者の負担を大幅に軽減しながら家畜の状態を24時間監視できるシステムを目指した研究成果についてご講演いただきました。
さらに、見守りが必要な患者に対して、深度カメラから得られた距離画像(深度画像)を用いて、高度画像処理技術とAIによる身体・精神機能低下患者の行動見守りシステムの開発に取り組んだ「自立生活を支援するための高齢者24時間見守りシステムの開発」等についてもご講演いただきました。
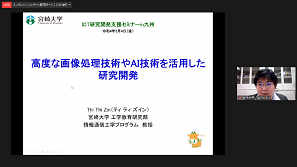
<宮崎大学 Thi Thi Zin教授の講演>
続いて、NICTの取組を紹介する講演がありました。
まず、戦略的プログラムオフィスの野尻統括より、NICTの組織概要や業務推進体制について紹介した後、吉田イノベーションプロデューサーより、九州工業大学において実施されたアイデアソン・ハッカソンの開催事例や、NICTの委託研究事例等について紹介しました。
また、テラヘルツ連携研究室の佐藤主任研究員より、キレイな空気指数(Clean aIr Index, CII)を用いた研究を紹介しました。CIIは、大気汚染物質量データを指数化し、一般市民にも理解できる形で大気汚染の程度を数値化します。さらに、北九州市を中心に進めている画像データからPM2.5を含むエアロゾル濃度を推定する実証実験について紹介しました。このアルゴリズム(SNAP-CII)とCIIにより、研究者と一般市民がフィードバックしながら研究開発を推進するスキームを作ります。
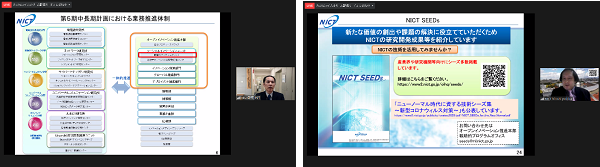
<NICT 佐藤主任研究員の講演>
最後に、九州工業大学の野林准教授より、NICTの委託研究「データ連携・利活用による地域課題解決のための実証型研究開発」に採択されていた「レンタカー走行データを活用した訪日外国人との共生エコシステムの研究開発」の研究成果について、ご講演がありました。
講演では、「LPWA通信を利用した安価な車載GPSロガーの開発」、「レンタカーに搭載したGPSロガーと通信型カーナビのデータ活用スキームの開発」、「収集したレンタカー走行データ統合プラットフォームの開発」について解説され、九州北部地域におけるレンタカー走行データ収集・活用の実証実験の模様が報告されました。さらに、今後の展開・普及として、LPWA通信を用いた走行車両向けデータ収集に関する知見が集積したことから、社会展開や普及を意識したLPWA通信インフラの研究開発を推進することや、コロナ前の訪日外国人のレンタカー観光行動を詳細に記録した貴重なデータとなったことから、アフターコロナの反転攻勢を目指す各地域における施策立案基礎データとして自治体等における活用を促進する計画等が紹介されました。