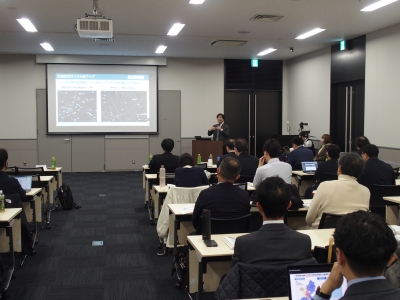九州総合通信局は、令和7年2月12日(水)、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)及び一般社団法人九州テレコム振興センター(KIAI)との共催により、会場及びYouTubeによるオンライン配信のハイブリッドにて、「ICT研究開発支援セミナー2025」を開催し、全国から100名を超える皆様にご参加いただきました。
本セミナーでは、ICTによる地域課題解決の取組やNICT委託研究の採択課題の取組及びNICTにおける研究開発の紹介を行いました。
はじめに共催者を代表し、中西悦子九州総合通信局長が挨拶を行いました。
本セミナーは、地域のICT研究開発の支援のため2021年度から開催しており、Beyond 5G基金の委託研究による熊本都市圏での渋滞をテーマとした都市交通のための基盤技術開発など、九州総合通信局とNICTが連携して地域のICT研究開発を支援していること等を紹介することで、今後の地域での研究活動推進に寄与させていただきたいと呼びかけました。
<中西局長>

【講演内容】
(1)ICTによる地域課題解決の取組紹介(40分)
「行動変容と交通インフラの動的制御によるスマートな都市交通基盤技術の研究開発」
ご講演資料
講師:東京大学 大学院情報理工学系研究科 附属ソーシャルICT研究センター 准教授 伊藤 昌毅 氏
はじめに、NICTの委託研究である本研究では、ICT技術による自動運転の進化とモビリティアズアサービス(MaaS)につながる移動手段のシェアの発展など、モビリティの大変革が起き、車両や交通インフラなどが高度化するなか、ICTによって地方都市でも誰でも自由に自家用車なしで移動できる環境を作ることと、その技術で日本が世界をリードしていくことを目指しているとご説明いただきました。
本研究では、道路情報等をより正確かつ効率的に把握する技術の開発や、システムのバリアフリー化、交通シミュレーションなどを活用した道路交通の制御技術の最適化とそれらを支える通信とデータの技術の高度化などについて、様々な交通問題を抱える熊本をモデルに、「車を1割削減して渋滞を半分に、公共交通利用は2倍に」という目標を掲げ実践的な研究を進めており、Beyond5Gによって交通量データの精密な取得と分析が可能となり、信号サイクルの調整やバスの増便及び交通予算の見直しなどで目標の実現が可能であることが説明され、最後に、情報通信の時代にふさわしい交通をつくっていきたいとご講演いただきました。
<東京大学 伊藤氏>

(2)大学における研究開発事例の紹介(30分)
「データ駆動型観光回遊に関する研究開発」
ご講演資料 
講師:早稲田大学理工学術院 情報生産システム研究科 講師 家入 祐也 氏
はじめに、本研究は情報通信技術による観光DX振興に取り組むもので、データを使いながら社会科学と情報学及び経営工学を融合させた総合知によって、従来の観光ルートが抱えるオーバーツーリズムや渋滞などの問題を解消しつつ、観光客の心に寄り添い満足度も向上させる新たな観光設計を産官学の連携を得て実践していく研究であるとご紹介いただきました。
続いて、観光行動を設計する手法として、情報通信技術を使って観光客に皮膚電気活動(EDA)データ計測用リストバンドを装着してもらい、得られたデータの時系列変化から観光客の主観的情報(ドキドキ感)を計測・評価することをご説明いただきました。
北九州市内観光地での実践では、冒頭での感興度の急速な高まりや、途中の各観光スポットで感興度のピークが出現することなどが確認でき、この手法で最適観光ルートを設計し、アプリで観光ルートを誘導することによりオーバーツーリズムの解消や新たな潜在的観光資源の発掘が可能となることなどをご紹介いただきました。
<早稲田大学 家入氏>

(3)NICTの委託研究紹介(30分)
「ICTを用いたインフラサウンド高密度観測の実証実験」
ご講演資料
講師:九州大学 大学院理学研究院 地球惑星科学部門 准教授 中島 健介 氏
はじめに、インフラサウンドとは人間の耳には聞こえない、3ミリヘルツから20ヘルツの超低周波音であり、これを捉えることで津波、火山噴火、雷、土砂崩れ、雪崩、竜巻、隕石などの自然の声を聴くことができ、数千km先の核実験等の人工的爆発を探知することもできるとご説明いただきました。
本研究はNICTの委託研究として、全国の研究機関や大学が協力する観測コンソーシアムにより観測が行われており、高知工科大学などの大学や研究機関等が参加し全国で実証実験を実施しており、九州大学では、福岡市のサポートを受け、同市の45地点にセンサーを置いて高頻度・高密度の観測を行うことで、ゲリラ豪雨など局地的・突発的で予測困難な災害現象の発生や予兆を即時把握する可能性を探る実証実験を行っていることをご紹介いただきました。
今後、重低音センサーによるIoT観測網を広げ、誰もがアプリなどで「地球の声を聴く」近未来社会を創造することで、住民がいち早く災害現象の予兆を入手し、避難や地域防災に繋げるという展望をお示しいただきました。
<九州大学 中島氏>

(4)NICTの研究開発の紹介(30分)
「音声マルチスポット再生技術に関する研究開発」
ご講演資料
講師:NICTユニバーサルコミュニケーション研究所 研究マネージャー 岡本 拓磨 氏
はじめに、音声認識や音声合成及び機械翻訳の技術について、実際の合成音声の再生やNICTが提供する音声翻訳アプリVoiceTraの紹介を交えご説明いただきました。
続いて、発話が終わるのを待たずに翻訳結果を出力できる多言語同時通訳技術や、収録した音空間そのものを別の場所で忠実に再現する音場再生技術の説明があり、さらに、ある領域にのみ特定の音が聞こえ、ほかの場所では聞こえないという局所再生技術と、それを重ね合わせて異なる領域それぞれに別の音を届けることができる「マルチスポット再生技術」をご紹介いただきました。
この技術と多言語同時通訳技術を組み合わせると、例えば異なる言語を話す4人が四角いテーブルの4辺に座って向き合い、通訳者等を介さずより自然に会話するといったことが実現できることから、国際会議をはじめ駅や空港、展覧会など、くらしの様々な場面での応用が期待されると解説され、今回はデモ機を展示しているのでぜひ体験してもらいたいとご紹介いただきました。
<情報通信研究機構(NICT) 岡本氏>

講演後は、展示デモコーナーで音声マルチスポット再生スピーカーの実演を体験していただきました。体験された方々は、スピーカーの周囲を輪になって歩きながら、聞く位置によって英語、中国語、韓国語など異なる言語を聞き分けられる技術を驚いた様子で体験していました。また会場では、各講演者による研究開発関連の機器やポスターを見学しながら講演者への質問や意見交換も行われていました。
<展示の様子(中央が音声マルチスポット再生スピーカー)>

<セミナーの様子>
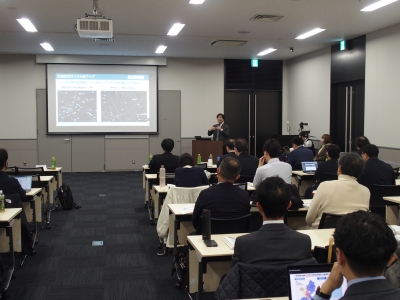
九州総合通信局では、引き続き、NICTやKIAIほか関係機関と連携して、地域におけるICTの利活用やDXを推進する取組を支援してまいります。
共催の九州テレコム振興センター(KIAI)によるICT研究開発支援セミナー2025の開催報告は、以下URLに後日掲載予定です。
URL:
https://www.kiai.gr.jp/index.html
お問合せ先:情報通信連携推進課 096-326-7314