2 通信をめぐる国際活動
(1)国際標準化活動
通信方式の国際標準化は,利用者の利便性を大きく向上させるばかりでなく,通信機器,サービスの自由な流通を促進し,通信の高度化にも大きく貢献するものである。
我が国は,その優れた技術力を生かし,ITU(国際電気通信連合)をはじめとする国際標準化活動に一層の貢献を行うとともに,その活動を積極的にリードし,我が国に対する期待にこたえていく必要がある。
ITUにおける標準化活動は,CCIR(国際無線通信諮問委員会)及びCCITT(国際電信電話諮問委員会)で進められている。CCIRでは前研究期(1978年〜1982年)において,スタジオ用ディジタルテレビの符号化,衛星を用いた時刻信号及び標準周波数の分配等の標準化について勧告を行った。CCITTでは前研究期(1981年〜1984年)において,ファクシミリG4機,ビデオテックス,メッセージ通信システム,OSI(開放型システム間相互接続),ISDN,ディジタル伝送方式等の標準化について一部勧告を行った。
なお,OSI等に関しては,ISOとCCITTとが連携して国際標準化活動を推進している。
(2)国際的政策協議
世界各国の社会経済の国際化が進展する中で,電気通信の分野においても相互依存関係が深まりつつあり,近年の電気通信の急速な発展,将来の成長性に適切に対応し得る電気通信政策について,各国間で調整し国際的整合性を図る必要性が生じてきている。
ア.OECD
OECDでは,従来,情報・コンピュータ・通信分野の政策問題に関する意見交換,評価・分析を行う場としてCSTP(科学技術政策委員会)の下に作業部会を設けていたが,近年この分野の重要性が増してきたため,1982年4月,作業部会を昇格させて常設委員会として情報・コンピュータ・通信政策委員会(ICCP)を設置した。
ICCPの活動内容は,TDFの経済的・法的諸問題,コンピュータ社会のぜい弱性,電気通信サービスの市場構造変化等の広範な分野にわたっている。
これまでの大きな活動成果としては,1980年に勧告「プライバシー保護と個人データの越境流通に関するガイドライン」を,1985年3月にはデータの自由流通の原則を確認し,今後のTDF問題の検討の方向性を示す「TDF宣言」を取りまとめており,これらは閣僚理事会で採択の後,公表された。
イ.二国間電気通信定期協議
電気通信分野におけるニ国間の政策協議の場としては,現在,我が国と英国,米国,カナダ及び西独のそれぞれの国との間に定期協議が設けられており,また,フランスとの間でも設置について合意した。
これまでに行われた定期協議においては,主として共通の課題及び関心事項について意見・情報交換が行われた。
57年6月,58年7月に開催された日英定期協議では,電気通信事業体の民営化及びOECD等の国際機関について,また,59年6月の日米電気通信専門家会議では,電気通信分野における規制緩和政策,ニューメディアの振興政策等について意見及び情報の交換が行われた。さらに,60年5月には,日加電気通信定期協議,日独電気通信協議がそれぞれ開催され,両国の電気通信政策について意見交換が行われた。
電気通信分野における二国間の政策協議は,それぞれの国の電気通信政策の策定に資するばかりでなく,両国の相互理解と友好関係の促進に大きく寄与するものであり,今後もこのような協議の充実を図っていくことが必要である。
ウ.先進国テレコム閣僚会議我が国の呼びかけにより,60年5月22日,「先進国テレコム閣僚会議」が開催された。この会議は,日本,米国,英国,西独,フランス及びカナダの先進6か国の通信担当閣僚級による国際会議として世界で初めて実現されたものであり,筑波国際科学技術博覧会会場とロンドン,ワシントンの会場をインテルサット衛星回線で結び,テレビ会議形式で行われた。
会議では、国際間の相互理解を深める電気通信の役割の重要性について意見交換が行われ,電気通信メディアの有効な活用による国際社会への貢献等について関係各国の相互理解を深めることができた。
(3)国際協力
ここでいう国際協力は,開発途上国に対する技術協力と資金協力からなる経済協力をいう。
現在,先進国と開発途上国との間には電気通信サービスの普及に大きな格差が生じている。また,多くの開発途上国では,電気通信サービスは都市部においてのみ享受可能であり,開発途上国の人口の約8割が住む広大なルーラル地域は,電気通信の恩恵にほとんど浴していない現状にある。
通信インフラストラクチャーは,国の社会経済発展に不可欠のものであるが,開発途上国においては,この整備・拡充が不十分である。
我が国は,通信の分野において世界の最高水準の技術力を有しており,開発途上国に対しこの分野で協力を行うことが求められている。このため,郵政省は,通信分野における国際協力を積極的に推進しているところである。
ア.国際協力の概要
国際協力には,政府ベースのものと民間ベースのものとがあるが,政府ベースの協力である政府開発援助(ODA)は,資金協力及び技術協力からなる二国間協力と国際機関への出資・拠出に大きく分けられる。
イ.二国間の資金協力
資金協力は,無償資金協力(返済義務を課さない資金供与)と有償資金協力(円借款:資金を長期・低利で融資するもの)との二つに分けられる。
一般無償の中で通信の占める割合は,59年度についてみると,70億3百万円で全体の7.5%となっている。一方,円借款の中で通信の占める割合は,59年度においては,387億49百万円で全体の6.9%となっている。
ウ.二国間の技術協力
技術協力は、開発途上国に対して,技術を普及させ又はその国の技術水準を向上させるために実施する協力をいい,政府ベースの技術協力は,主として国際協力事業団(JICA)を通じて実施される。JICAべースの技術協力の形態としては次のものがある。
[1] 専門家の派遣及び研修員の受入れ
通信分野における専門家の派遣についてほ,59年度は新規に95名(プロジェクト方式技術協力による派遣を除く。)を派遣した。
また,通信分野における研修員の受入れについては,59年度の実績 で376名である。
[2] 第三国研修
第三国研修とは,特定国の電気通信訓練センター等に近隣開発途上国から研修員を受け入れて実施する研修に対し,我が国が専門家の派遣,研修員の滞在費負担等の方法により協力するものである。
59年度に通信分野で実施した第三国研修は次のとおりである。
タイ (モンクット王工科大学:電気通信技術)
フィジー(電気通信訓練センター:電気通信技術)
メキシコ(電気通信学園:無線伝送技術)
ペルー(電気通信訓練センター:ディジタル通信技術)
ケニア(郵電公社中央訓練学校:マイクロウェーブ通信技術)
AIBD(アジア・太平洋放送開発研究所:テレビカメラとビデオ装置によるニュース取材及び番組制作)
[3] 開発調査
開発調査とは,開発途上国の公共的な開発計画に対し,専門家及び
コンサルタントからなる調査団を派遣し,現地におけるデータ収集及び国内における分析作業を通じて開発計画の推進に寄与する計画を策定し,報告書を作成するもので,59年度,通信分野において実施した開発調査は17件で派遣人数は160名である。
[4] プロジェクト方式技術協力
プロジェクト方式技術協力とは,特定分野について,研修員の受入れ,専門家の派遣,機材供与の三形態の協力を有機的に関連付けて技術協力を行うものである。
59年度の実績については次のとおりである。
シンガポール(日本・シンガポールソフトウェア技術研修センター:ソフト要員の養成,国家生産性庁:視聴覚番組の作成)
フィリピン(電気通信訓練センター:保守・運用要員の養成)
パナマ(国営教育テレビ:番組制作,スタジオ技術及び送信技術)
インドネシア(ラジオ・テレビジョン放送訓練センター:放送要員の訓練,放送機器の運用・保守管理)
パキスタン(中央電気通信研究所:電気通信方式及び機器の開発)
ペルー(電気通信訓練センター:電気通信・放送要員の養成)
エ.国際機関に対する協力我が国は,国際連合の専門機関であるITU及び地域的電気通信機関であるAPT(アジア・太平洋電気通信共同体)が行う技術協力活動に対して協力を行っている。
ITUでは,1982年の全権委員会議において,ITUの今後の技術協力の在り方を見直すとともに,広く電気通信分野の南北問題を解決することを目的として「電気通信の世界的発展のための独立国際委員会」を設立した。同委員会では5回の会合を経た後,1985年1月,最終報告書をITU事務総局長に提出した。
この報告書は,開発途上国援助プログラムの中での電気通信部門のプライオリティ向上,人材開発,職業訓練の強化,技術移転の促進等を勧告しているほか,緊急にとるべき措置として,ITUの技術協力活動を補完する電気通信開発センターの設立を勧告している。
この電気通信開発センターの設立に関する勧告は,1985年7月のITU第40会期管理理事会において承認された。
一方,APTの設立に当たって,我が国は,その中心的役割を果たし,また分担金の4割を負担しているなど,APTの活動に対して指導的な役割を果たしている。
60年4月には,我が国はAPTとの共催により「つくばEXPO’85電気通信セミナー」を開催し,高度情報社会に向けての我が国の動向を域内各国に紹介した。
オ.民間ベースの技術協力
NTT,KDD及びNHKは,海外の電気通信事業体との間で技術協力覚書等を締結し,これに基づき,いわゆる「覚書交流」を実施している。
例えば,NTTは,中国,タイ,韓国,マレイシア,シンガポール,スリ・ランカ等の事業体との間で覚書を締結しており,毎年70名前後の職員を受け入れている。
また,JTEC(財団法人海外通信・放送コンサルティング協力)は,国際協力事業の一環として,海外通信計画調査,海外派遣専門家の養成及び研修員の受入れを行っている。
60年3月には,アジア・太平洋地域の開発途上国に対する技術協力,調査研究等を主たる目的とする財団法人アジア電気通信技術協力機構(ATO)が設立された。ATOはアジア・太平洋地域に対する民間ベースの協力の強化に大きく貢献するものと期待されている。
カ.開発途上国向けルーラル電気通信システム調査研究会
開発途上国にとって,人口,面積等において大きな比重を占めるルーラル地域の開発はその国の社会・経済発展に不可欠であり,またこれら地域の開発に果たす電気通信の役割も極めて重要となっている。しかしながら,開発途上国のルーラル地域における電気通信の開発は,極めて立ち遅れているのが現状である。したがって,今後開発途上国からの協力要請は,このルーラル電気通信システムに対するものが中心になってくるものと予想される。
郵政省では,開発途上国のニーズに的確に対応し,国際協力の一層の推進を図るため,59年3月に電気通信関係者,学識経験者等からなる「開発途上国向けルーラル電気通信システムに関する研究会」を設置し,ルーラル地域に電気通信システムを導入する際の社会経済的及び技術的問題等について検討を進めている。
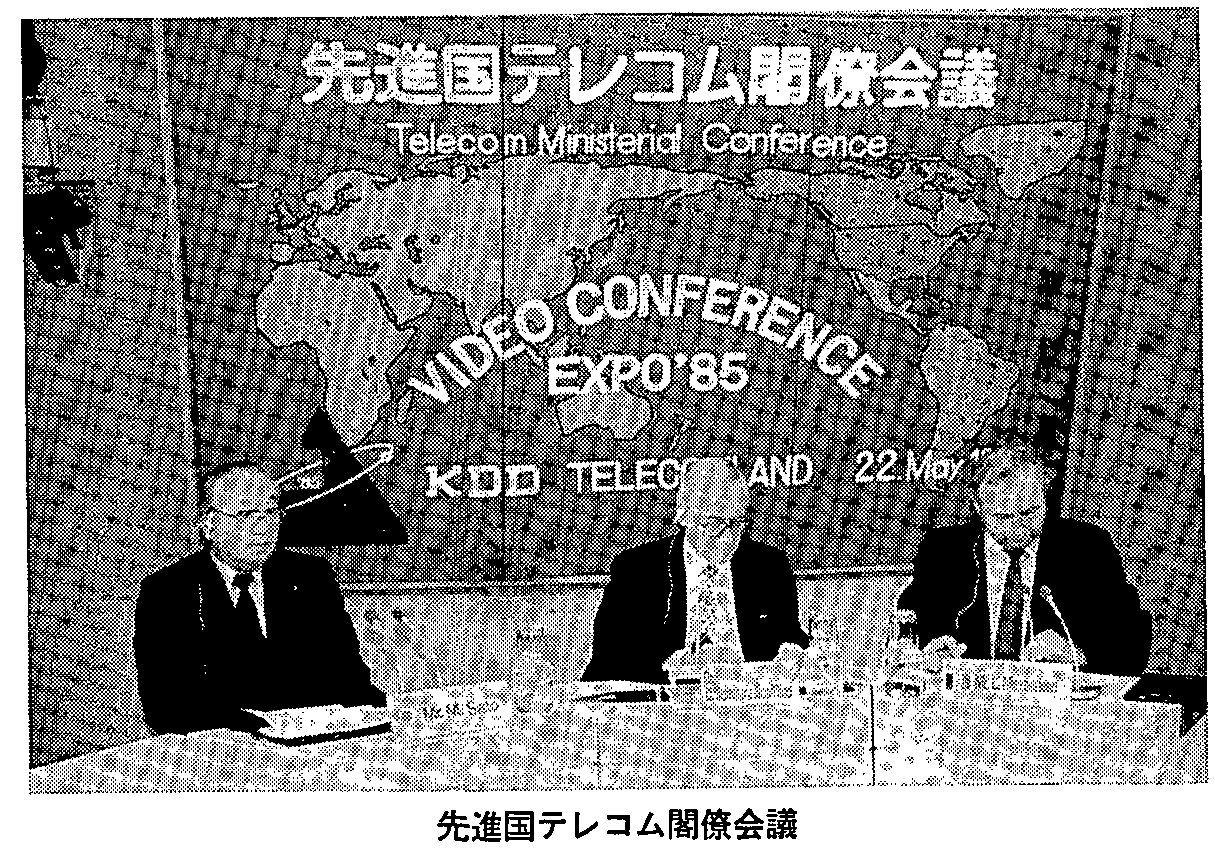
|