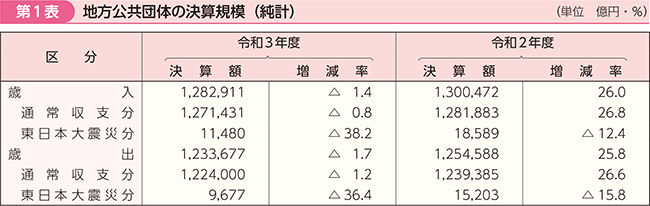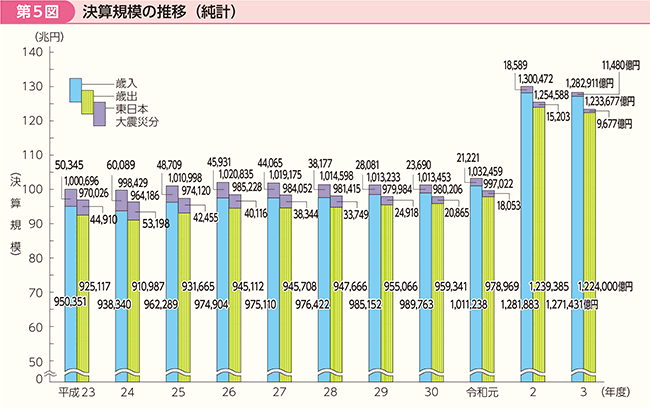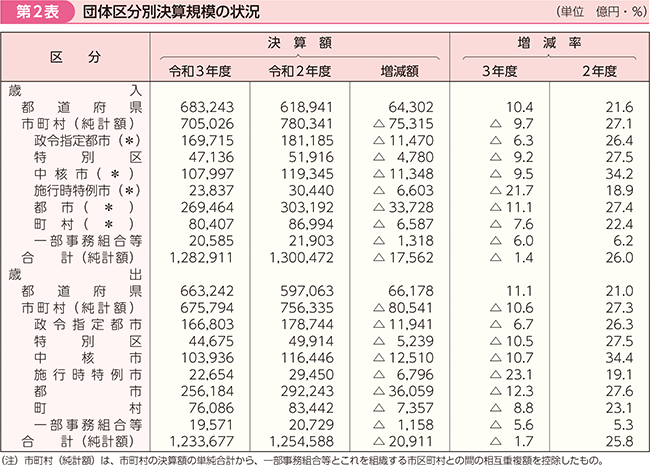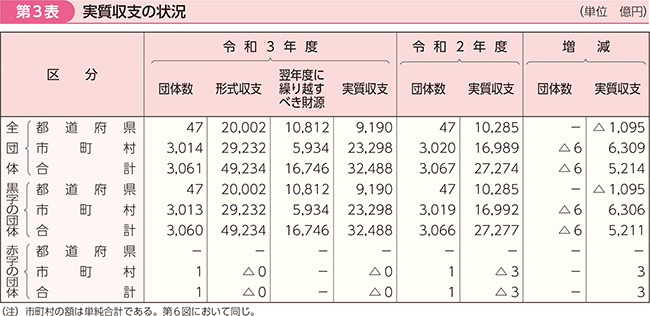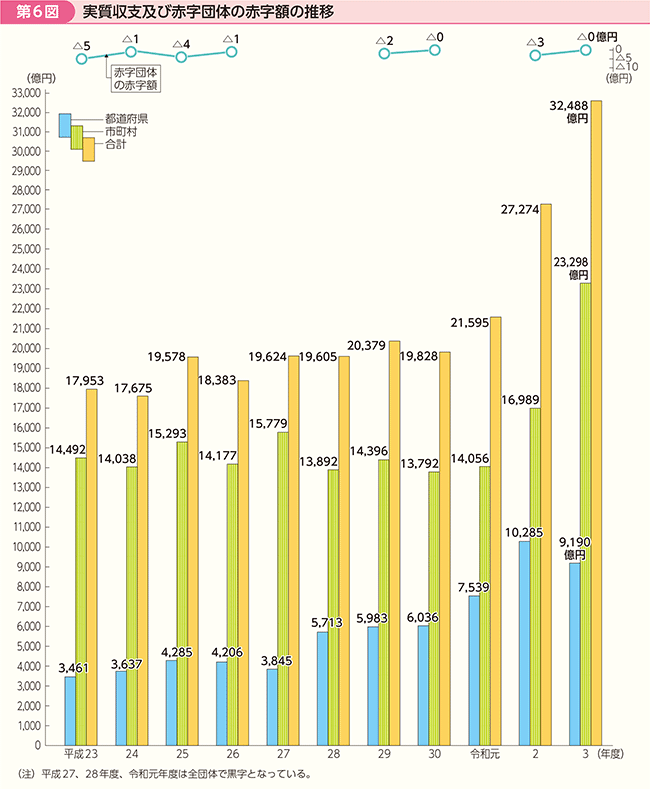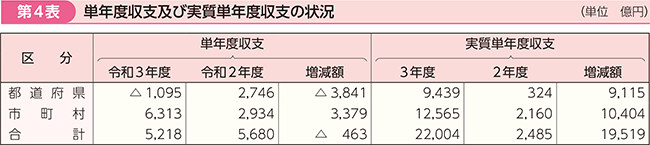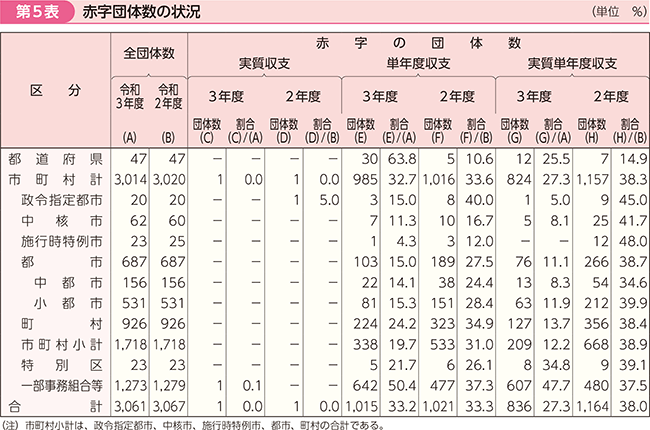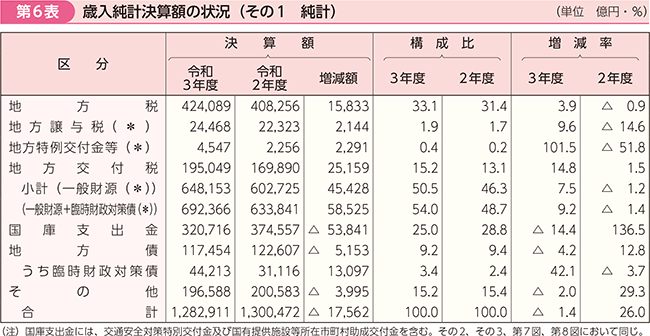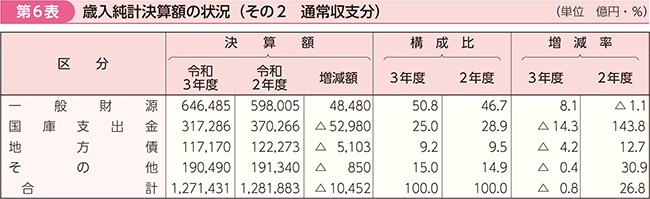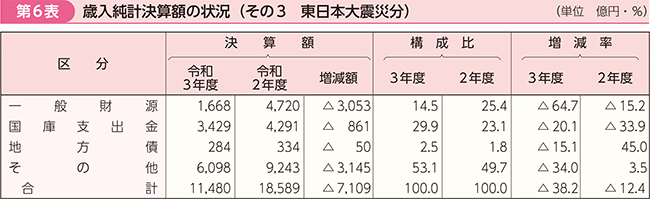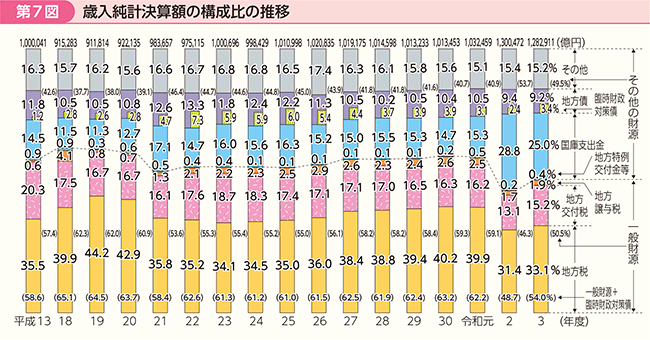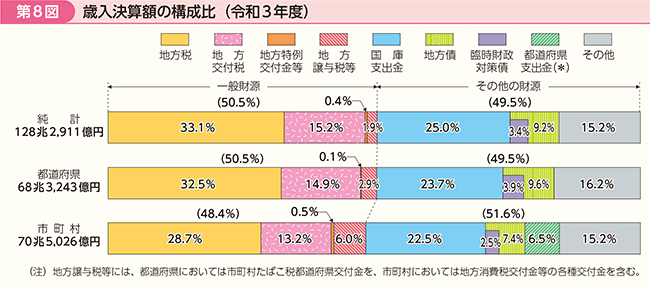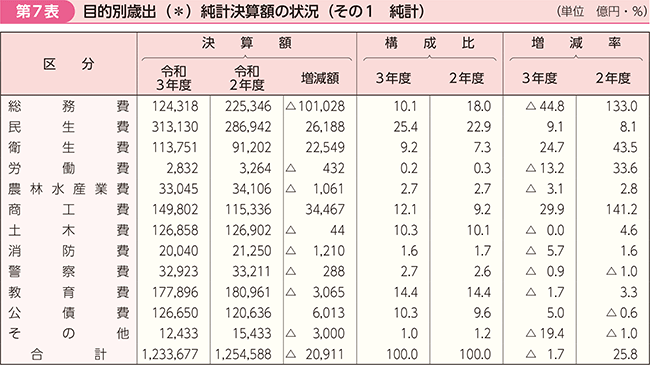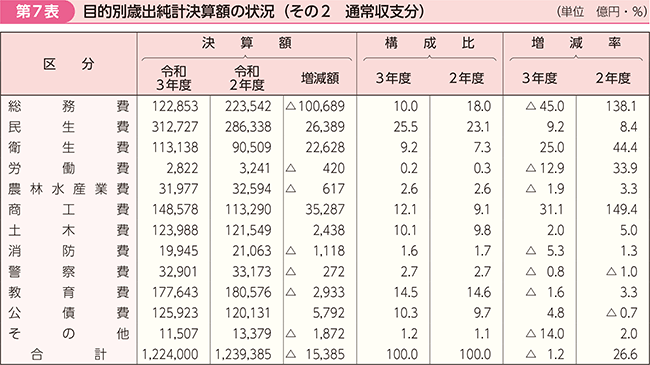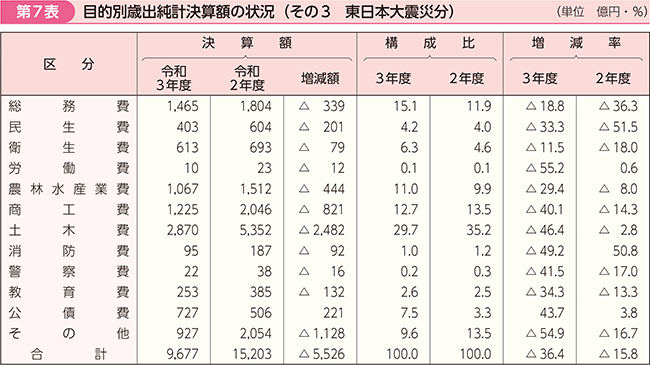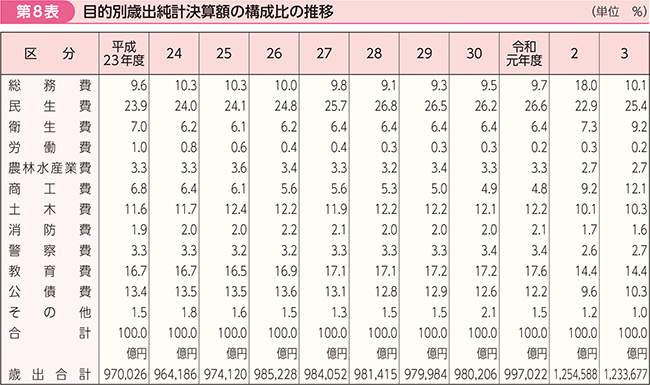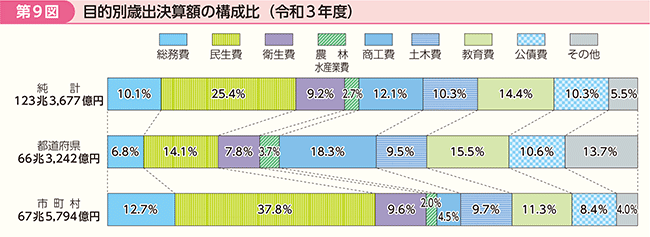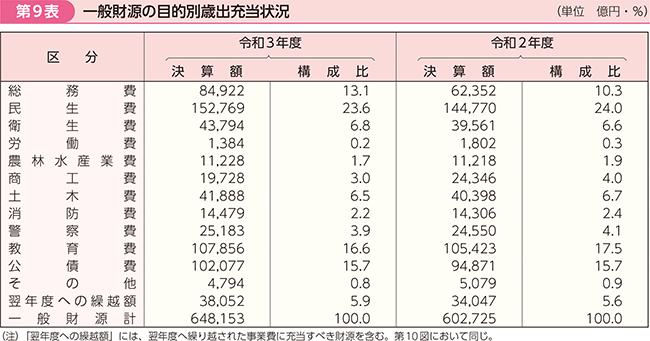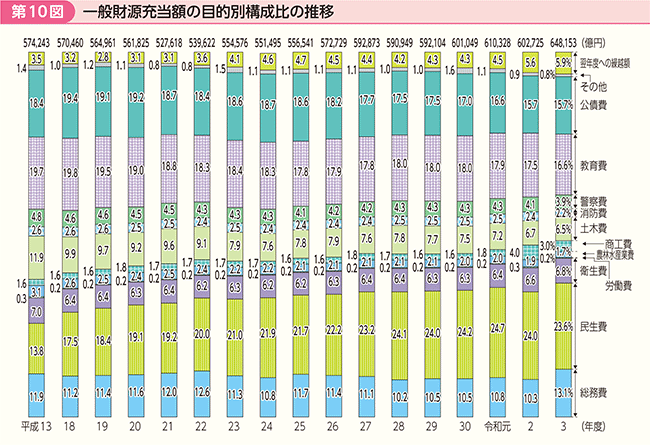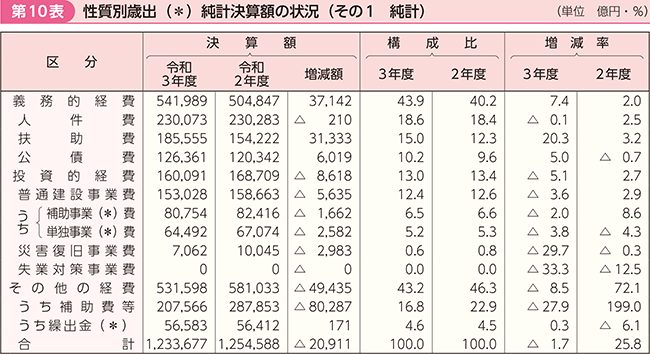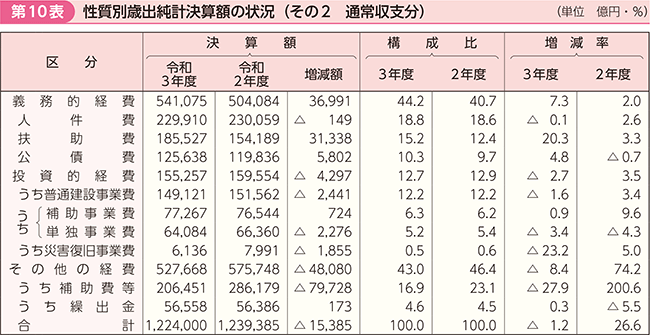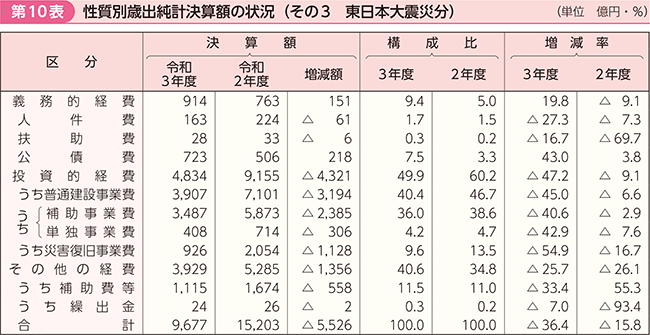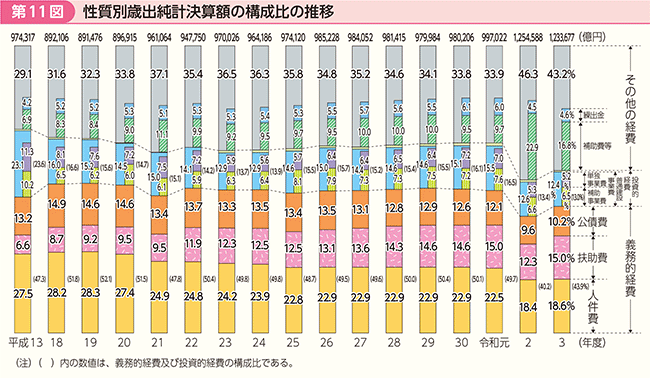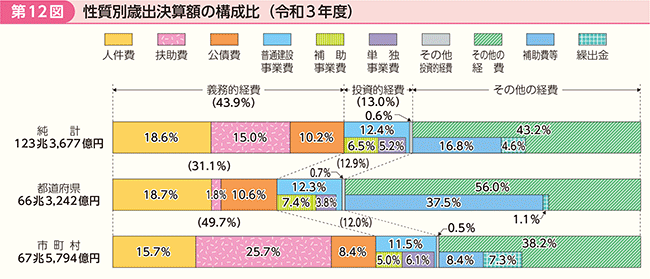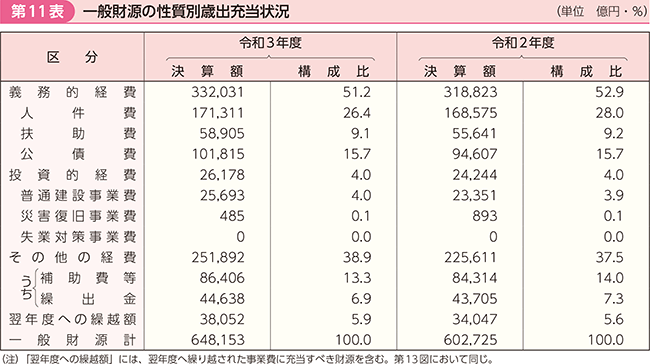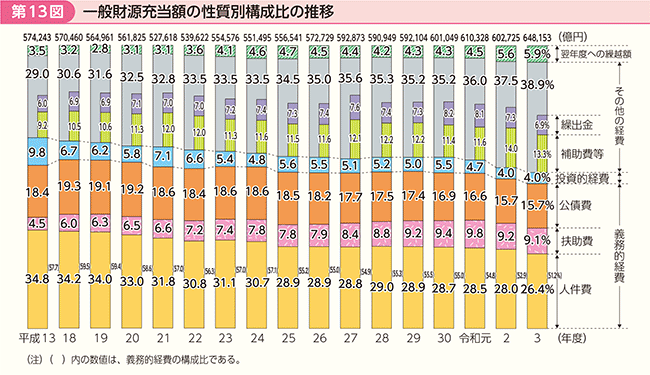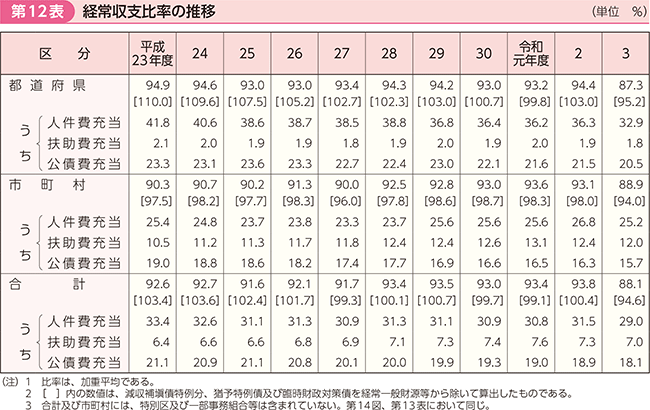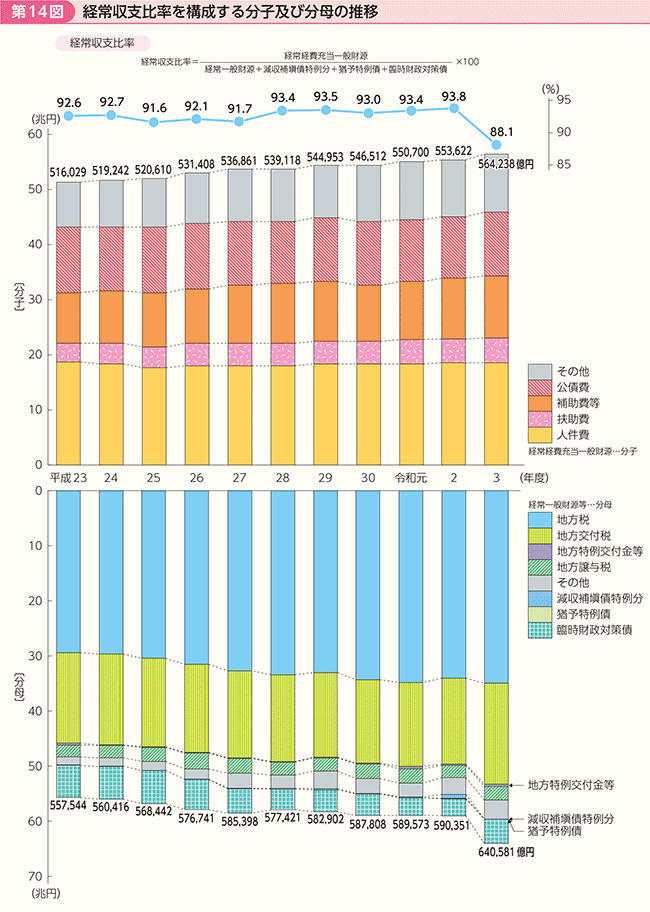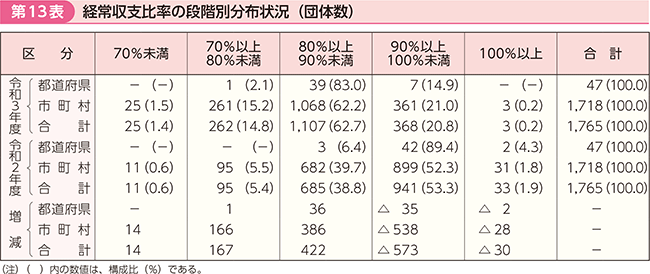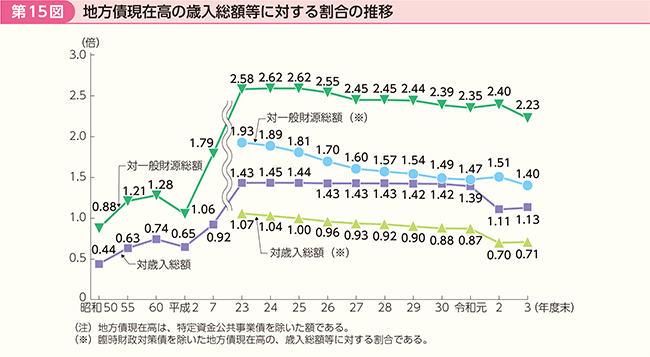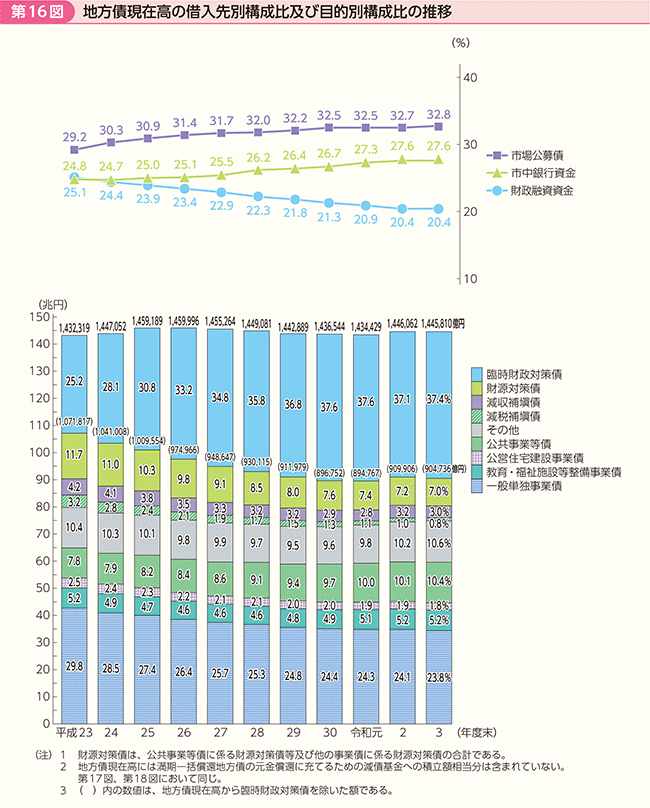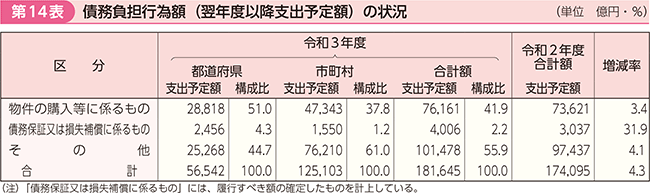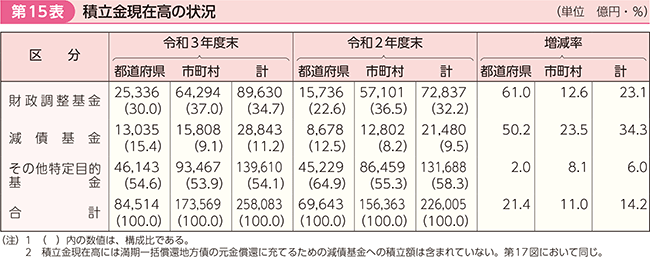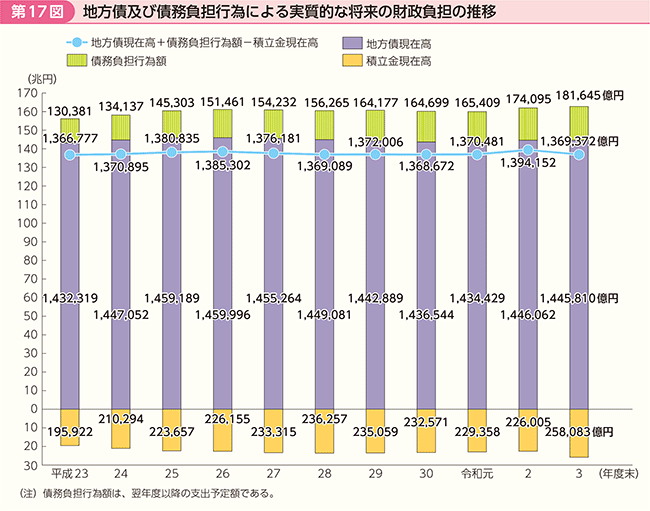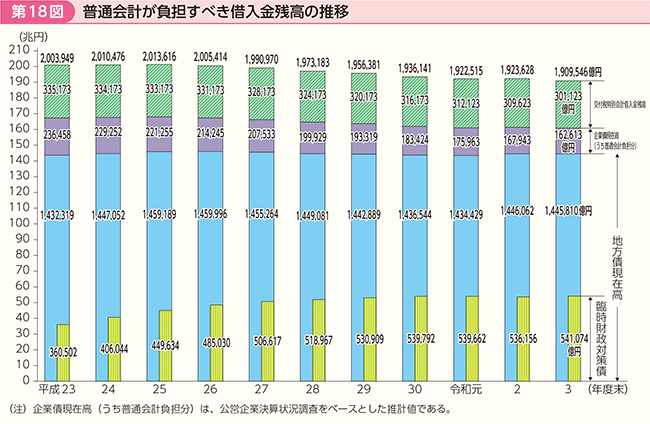2 地方財政の概況
地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分して経理されているが、特別会計の中には、一般行政活動に係るものと企業活動に係るものがある。
このため、地方財政では、これらの会計を一定の基準によって、一般行政部門と水道、交通、病院等の企業活動部門に分け、前者を「普通会計」、後者を「公営事業会計」として区分している。
なお、普通会計決算については、平成23年度から、通常収支分(全体の決算額から東日本大震災分を除いたもの)と東日本大震災分(東日本大震災に係る復旧・復興事業及び全国防災事業に係るもの)とを区分して整理している。
(1)決算規模
令和3年度の地方公共団体(47都道府県、1,718市町村、23特別区(*)、1,160一部事務組合(*)及び113広域連合(*)(以下一部事務組合及び広域連合を「一部事務組合等」という。))の普通会計の純計決算額(*)は、第1表のとおり、歳入128兆2,911億円(前年度130兆472億円)、歳出123兆3,677億円(同125兆4,588億円)となっており、前年度と比べると、特別定額給付金事業の終了等により、歳入、歳出ともに減少している。
歳入については、地方交付税(*)、地方税が増加したものの、国庫支出金(*)、繰入金の減少等により、前年度と比べると1.4%減となっている。歳出については、扶助費(*)、積立金が増加したものの、補助費等(*)、貸付金の減少等により、前年度と比べると1.7%減となっている。
また、決算規模の推移は第5図のとおりであり、近年増加傾向にあるが、令和3年度は、前年度と比べると減少している。
決算規模の状況を団体区分別にみると、第2表のとおりである。令和3年度は、都道府県の歳入及び歳出は前年度と比べると増加、市町村(特別区及び一部事務組合等を含む。特記がある場合を除き、以下第1部及び第2部において同じ。)の歳入及び歳出は前年度と比べると減少している。
(2)決算収支
ア 実質収支
実質収支(*)(形式収支(*)から明許繰越等のために翌年度に繰り越すべき財源を控除した額)の状況は、第3表のとおりである。
令和3年度の実質収支は3兆2,488億円の黒字であり、昭和31年度以降黒字となっている。
団体区分別にみると、都道府県においては9,190億円の黒字であり、平成12年度以降黒字となっている。また、市町村においては2兆3,298億円の黒字であり、昭和31年度以降黒字となっている。
実質収支が赤字である団体は、一部事務組合で1団体となっている。
なお、近年の実質収支及び赤字団体の赤字額の推移は、第6図のとおりである。
イ 単年度収支及び実質単年度収支
単年度収支(*)(実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額)及び実質単年度収支(*)(単年度収支に財政調整基金(*)への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額)の状況は、第4表のとおりであり、令和3年度の単年度収支は5,218億円の黒字、実質単年度収支は2兆2,004億円の黒字となっている。
なお、実質収支、単年度収支及び実質単年度収支の赤字団体数の状況は、第5表のとおりである。
(3)歳入
歳入純計決算額は128兆2,911億円で、前年度と比べると1.4%減となっている。このうち、通常収支分は127兆1,431億円で、前年度と比べると0.8%減となっており、東日本大震災分は1兆1,480億円で、前年度と比べると38.2%減となっている。
歳入純計決算額の主な内訳をみると、第6表のとおりである。
地方税は、法人関係二税(法人住民税及び法人事業税)の増加等により、前年度と比べると3.9%増となっている。
地方譲与税は、特別法人事業譲与税の増加等により、前年度と比べると9.6%増となっている。
地方特例交付金等は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の創設等により、前年度と比べると101.5%増となっている。
地方交付税は、国税収入の補正等に伴う増加等により、前年度と比べると14.8%増となっている。
その結果、一般財源は、前年度と比べると7.5%増となっている。なお、一般財源に臨時財政対策債を加えた額は9.2%増となっている。
国庫支出金は、特別定額給付金給付事業費補助金の減少等により、前年度と比べると14.4%減となっている。
地方債は、臨時財政対策債が増加したものの、減収補填債(*)の減少等により、前年度と比べると4.2%減となっている。
その他は、基金からの繰入金の減少等により、前年度と比べると2.0%減となっている。
歳入純計決算額の構成比の推移は、第7図のとおりである。
地方税の構成比は、税源移譲等によって平成19年度までは上昇し、その後、景気の悪化や地方法人特別税の創設等に伴って低下していた。平成24年度以降は再び上昇の傾向となり、令和2年度は低下したが、令和3年度においては、法人関係二税の増加等により、前年度と比べると上昇している。
地方交付税の構成比は、平成13年度以降、財源不足額に関して交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)における借入金による方式に代えて、臨時財政対策債を発行し、基準財政需要額(*)の一部を振り替えることとしたことや、三位一体の改革に伴う地方交付税の改革等により、平成21年度までは低下した。その後、地方財政対策における地方交付税総額の増加等により上昇したが、平成24年度以降は、地方税収の増加等により低下の傾向にあった。令和3年度においては、国税収入の補正等に伴う地方交付税の増加等により前年度と比べると上昇している。
国庫支出金の構成比は、平成16年度以降、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化、普通建設事業費支出金の減少等によって低下していたが、平成20年度以降、国の経済対策の実施、東日本大震災への対応の影響等により上昇の傾向にあった。近年は15%前後で推移していたが、令和2年度及び令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金の増加等により、大きく上昇している。
地方債の構成比は、臨時財政対策債の増加等により、平成22年度まで上昇の傾向にあったが、近年は臨時財政対策債の減少等により低下の傾向にある。
一般財源の構成比は、平成18年度まで上昇した後、平成21年度には大きく低下した。平成26年度以降は再び上昇の傾向となり、令和2年度は低下したが、令和3年度においては、地方交付税、地方税の増加等により、前年度と比べると上昇している。なお、一般財源に臨時財政対策債を加えた額の構成比も、前年度と比べると上昇している。
歳入決算額の構成比を団体区分別にみると、第8図のとおりである。
(4)歳出
歳出の分類方法としては、行政目的に着目した「目的別分類」と経費の経済的な性質に着目した「性質別分類」が用いられるが、これらの分類による歳出の概要は、次のとおりである。
ア 目的別歳出
(ア)目的別歳出
地方公共団体の経費は、その行政目的によって、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、公債費(*)等に大別することができる。歳出純計決算額は123兆3,677億円で、前年度と比べると1.7%減となっている。このうち、通常収支分は122兆4,000億円で、前年度と比べると1.2%減となっており、東日本大震災分は9,677億円で、前年度と比べると36.4%減となっている。
歳出純計決算額の主な目的別の内訳をみると、第7表のとおりである。
総務費は、特別定額給付金事業の終了等により、前年度と比べると44.8%減となっている。
商工費は、営業時間短縮要請等に応じた事業者に対する協力金の給付等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の増加等により、前年度と比べると29.9%増となっている。
民生費は、子育て世帯等臨時特別支援事業等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の増加等により、前年度と比べると9.1%増となっている。
衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業、病床確保支援事業等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の増加等により、前年度と比べると24.7%増となっている。
公債費は、臨時財政対策債元利償還金の増加等により、前年度と比べると5.0%増となっている。
目的別歳出純計決算額の構成比の推移は、第8表のとおりである。民生費の構成比は、社会保障関係費の増加を背景に平成19年度以降、全区分の中で最も大きな割合を占めている。
目的別歳出決算額の構成比を団体区分別にみると、第9図のとおりである。
都道府県においては、営業時間短縮要請等に応じた事業者に対する協力金の給付等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の増加等により、商工費が最も大きな割合を占め、以下、教育費、民生費、公債費の順となっている。
また、市町村においては、児童福祉、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村に限る。)等の社会福祉事務の比重が高いこと等により、民生費が最も大きな割合を占め、以下、総務費、教育費の順となっている。
(イ)一般財源の充当状況
一般財源の目的別歳出に対する充当状況は、第9表のとおりである。
目的別歳出純計決算額(第7表その1参照)と比べると、公債費、総務費、教育費等は一般財源充当額の構成比が大きく、商工費、土木費、衛生費等は一般財源充当額の構成比が小さくなっている。
一般財源充当額の目的別構成比の推移は、第10図のとおりである。近年、民生費充当分が上昇の傾向にあり、土木費充当分及び公債費充当分は低下の傾向にある。
イ 性質別歳出
(ア)性質別歳出
地方公共団体の経費は、その経済的な性質によって、義務的経費(*)、投資的経費(*)及びその他の経費に大別することができる。
歳出純計決算額の主な性質別の内訳をみると、第10表のとおりである。
義務的経費は、子育て世帯等臨時特別支援事業等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業費の増加等による扶助費の増加等により、前年度と比べると7.4%増となっている。
投資的経費は、単独事業費の減少等による普通建設事業費の減少等により、前年度と比べると5.1%減となっている。
また、その他の経費は、特別定額給付金事業の終了等による補助費等の減少、制度融資の減少等による貸付金の減少等により、前年度と比べると8.5%減となっている。
次に、性質別歳出純計決算額の構成比の推移は、第11図のとおりである。
義務的経費の構成比は、平成19年度には52.1%まで上昇し、近年は50%前後で推移していたが、令和2年度及び令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策による補助費等の増加等によりその他の経費の構成比が上昇したことにより、低下している。内訳をみると、人件費は平成20年度以降、公債費は平成18年度以降低下の傾向にあったが、令和3年度においては上昇している。扶助費は社会保障関係費の増加等により上昇の傾向にあり、令和2年度は低下したが、令和3年度においては上昇している。
投資的経費の構成比は、平成23年度までは低下の傾向にあったが、平成24年度に上昇に転じ、近年は15〜16%台で推移していたが、令和2年度及び令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策による補助費等の増加等によりその他の経費の構成比が上昇したことにより、低下している。
その他の経費の構成比は、補助費等の増加等により、平成23年度までは上昇の傾向にあった。平成24年度以降は低下の傾向にあったが、令和2年度及び令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症対策による補助費等の増加等により、大きく上昇している。
性質別歳出決算額の構成比を団体区分別にみると、第12図のとおりである。
人件費の構成比は、都道府県において、政令指定都市を除く市町村立義務教育諸学校教職員の人件費を負担していること等から、都道府県が市町村を上回っている。また、扶助費の構成比は、市町村において、児童手当の支給、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村に限る。)等の社会福祉関係事務が行われていること等から、市町村が都道府県を上回っている。
普通建設事業費のうち、補助事業費の構成比は、都道府県が市町村を上回る一方、単独事業費の構成比は、市町村が都道府県を上回っている。
(イ)一般財源の充当状況
一般財源の性質別歳出に対する充当状況は、第11表のとおりである。
性質別歳出純計決算額(第10表その1参照)と比べると、義務的経費は一般財源充当額の構成比が大きくなっており、投資的経費は一般財源充当額の構成比が小さくなっている。
一般財源充当額の性質別構成比の推移は、第13図のとおりである。
義務的経費充当分は、近年、扶助費充当分が上昇の傾向にあるものの、人件費充当分及び公債費充当分が低下の傾向にあり、平成19年度以降、全体として低下の傾向にある。
投資的経費充当分は、近年、低下の傾向にある。
その他の経費充当分は、近年、補助費等充当分の上昇等により、全体として上昇の傾向にある。
(5)財政構造の弾力性
ア 経常収支比率
地方公共団体が社会経済や行政需要の変化に適切に対応していくためには、財政構造の弾力性が確保されなければならない。財政構造の弾力性の度合いを判断する指標の一つが、経常収支比率(*)である。
経常収支比率は、経常経費充当一般財源(人件費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出される経費に充当された一般財源)の、経常一般財源(一般財源総額のうち地方税、普通交付税等のように毎年度経常的に収入される一般財源)、減収補填債特例分(*)、猶予特例債及び臨時財政対策債の合計額(以下「経常一般財源等」という。)に対する割合である。
令和3年度の経常収支比率(加重平均による。市町村分は特別区及び一部事務組合等を除く。)は、分子である経常経費充当一般財源が、公債費や補助費等の増加等により1.9%増となったものの、分母である経常一般財源等が、臨時財政対策債償還基金費の創設*2を含む普通交付税の再算定による増加や地方税の増加等により8.5%増となり、分母が分子の増加率を上回ったことから、前年度と比べると5.7ポイント低下の88.1%となっている。なお、令和3年度に措置された普通交付税における臨時財政対策債償還基金費は、令和4年度以降の公債費負担対策に係るものであることを考慮し、当該措置額を経常一般財源等から控除した場合の経常収支比率は、90.2%となり、前年度より3.6ポイント低下したものとなる。
経常収支比率の推移は第12表のとおりであり、また分子及び分母の推移は第14図のとおりである。分子である経常経費充当一般財源については、補助費等の増加等により、増加の傾向にある。分母である経常一般財源等については、平成24年度以降地方税の増加等により、増加の傾向にある。
経常収支比率の段階別分布状況(団体数)をみると、第13表のとおりである。
イ 実質公債費比率
地方債の元利償還金等の公債費は、義務的経費の中でも特に弾力性に乏しい経費であることから、財政構造の弾力性をみる場合、その動向には常に留意する必要がある。その公債費に係る負担の度合いを判断するための指標に、実質公債費比率(*)がある。
実質公債費比率は、当該地方公共団体の標準財政規模(*)(普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費等を除く。)に対する、一般会計等(*)が負担する元利償還金及び公営企業債の償還に対する繰出金などの元利償還金に準ずるもの(充当された特定財源及び普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費等を除く。)の割合である。
令和3年度の実質公債費比率(一部事務組合等を除く加重平均)は、元利償還金の減少や標準財政規模の増加等により、前年度と比べると0.2ポイント低下の7.6%となっており、初めて算定された平成17年度以降低下傾向にある。
(6)将来の財政負担
地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収支状況のみならず、地方債、債務負担行為(*)等のように将来の財政負担となるものや、財政調整基金等の積立金のように年度間の財源調整を図り将来における弾力的な財政運営に資するために財源を留保するものの状況についても、併せて把握する必要がある。これらの状況は、次のとおりである。
ア 地方債現在高
令和3年度末における地方債現在高は144兆5,810億円で、地方道路等整備事業債の現在高の減少等により、前年度末と比べると252億円減(0.0%減)となっている。また、臨時財政対策債を除いた地方債現在高は90兆4,736億円で、前年度末と比べると5,170億円減(0.6%減)となっている。
なお、地方財政状況調査においては、満期一括償還地方債の元金償還に充てるための減債基金(*)への積立額は歳出の公債費に計上するとともに、地方債現在高に当該積立額相当分を含まない扱いとしているが、これを含む場合の地方債現在高は157兆3,277億円となっている。
地方債現在高の歳入総額に対する割合及び一般財源総額に対する割合の推移は、それぞれ第15図のとおりである。
地方債現在高は、地方税収等の落込みへの対応や減税に伴う減収の補填のため、また、経済対策に伴う公共投資の追加等により、地方債が急増したことに伴い、歳入総額に対する割合及び一般財源総額に対する割合は平成4年度末以降急増し、さらに、13年度からの臨時財政対策債の発行等により、高い水準で推移している。
近年の地方債現在高の借入先別構成比及び目的別構成比の推移は、第16図のとおりである。近年の市場における地方債資金の調達の推進及び公的資金の縮減等に伴い、市場公募債や市中銀行資金が上昇の傾向にある一方で、財政融資資金が低下の傾向にある。また、臨時財政対策債が上昇の傾向にある一方で、一般単独事業債が低下の傾向にある。
地方債現在高を団体区分別にみると、都道府県においては87兆7,781億円、市町村においては56兆8,029億円で、前年度末と比べると、それぞれ1,013億円増(0.1%増)、1,265億円減(0.2%減)となっている。また、臨時財政対策債を除いた地方債現在高を団体区分別にみると、都道府県においては54兆3,662億円、市町村においては36兆1,074億円で、前年度末と比べると、それぞれ3,523億円減(0.6%減)、1,647億円減(0.5%減)となっている。
イ 債務負担行為額
地方公共団体は、翌年度以降の支出を約束するために、債務負担行為を行うことができる。
この債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額の状況は、第14表のとおりである。
ウ 積立金現在高
地方公共団体の積立金現在高の状況は、第15表のとおりであり、令和3年度末における積立金現在高は25兆8,083億円で、普通交付税の基準財政需要額において臨時財政対策債償還基金費が算入されたことに伴う将来の臨時財政対策債の償還に備えた積立ての実施、税収変動、災害、公共施設の老朽化に備えた積立ての増加等により、前年度末と比べると14.2%増となっている。
その内訳をみると、年度間の財源調整を行うために積み立てられている財政調整基金は、前年度末と比べると23.1%増、地方債の将来の償還費に充てるために積み立てられている減債基金(満期一括償還地方債に係るものを除く。)は34.3%増、将来の特定の財政需要に備えて積み立てられているその他特定目的基金(*)は、6.0%増となっている。
エ 地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担
地方債現在高に債務負担行為に基づく翌年度以降の支出予定額を加え、積立金現在高を差し引いた地方公共団体の地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担の推移は、第17図のとおりである。令和3年度末においては、地方債現在高は0.0%減、債務負担行為額は4.3%増、積立金現在高は14.2%増となったことにより、地方債及び債務負担行為による実質的な将来の財政負担は136兆9,372億円で、前年度末と比べると1.8%減となっている。
団体区分別にみると、都道府県においては84兆9,809億円、市町村においては51兆9,562億円で、前年度末と比べると、それぞれ1.4%減、2.4%減となっている。
オ 普通会計が負担すべき借入金残高
普通会計が将来にわたって負担すべき借入金という観点からは、地方債現在高のほか、交付税特別会計借入金や、公営企業(*)において償還する企業債のうち、経費負担区分の原則等に基づき、普通会計がその償還財源を負担するものについても併せて考慮する必要がある。
この観点から、地方債現在高に交付税特別会計借入金残高と企業債現在高のうち普通会計が負担することとなるものを加えた普通会計が負担すべき借入金残高の推移をみると、第18図のとおりであり、近年は減少傾向にあるものの、依然として190兆円を超える高い水準にある。
なお、令和3年度末における普通会計が負担すべき借入金残高は190兆9,546億円で、交付税特別会計借入金残高の減少等により、前年度末と比べると1兆4,082億円減(0.7%減)となっている。
*2 国の令和3年度補正予算(第1号)において、国税収入の補正等に伴い令和3年度分の地方交付税の額が増額となったことを受け、令和3年度の臨時財政対策債を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するため、基準財政需要額の費目に「臨時財政対策債償還基金費」を創設し、同年度の普通交付税を1兆5,000億円増額交付することとした。