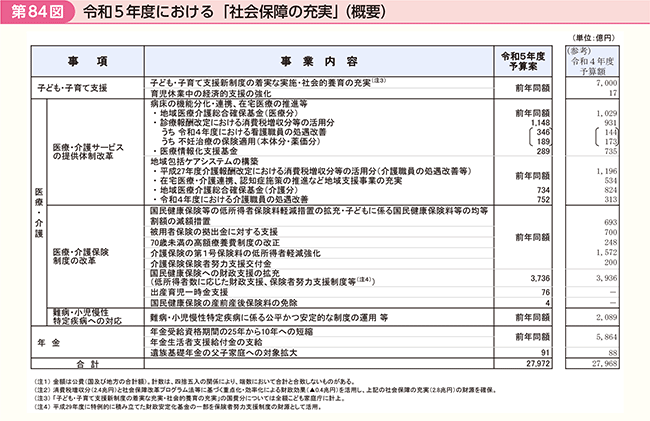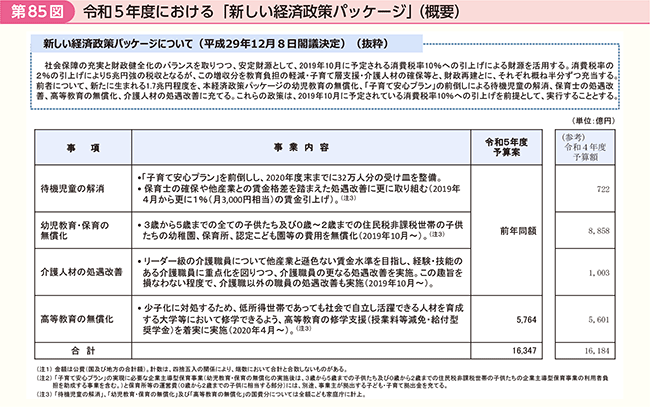6 社会保障制度改革
少子高齢化など人口構成の変化が一層進んでいく中、年金、医療、介護などの社会保障を持続可能なものとするためには、社会保障制度を見直し、給付・負担両面で、人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平が確保された制度へと改革していくことが必要である。
また、子育て、医療、介護など社会保障分野のサービス・給付の多くが地方公共団体を通じて国民に提供されていることから、国と地方が一体となって安定的に実施していくことが重要であり、社会保障制度改革は国・地方が協力して推進していく必要がある。
(1)社会保障の充実と人づくり革命
社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実・安定化に向け、安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである。
消費税率の引上げ分は、「社会保障の充実」、「人づくり革命」等として、全額社会保障の財源に使われることとされている。
「社会保障の充実」では、消費税率5%から10%への引上げによる増収分の一部及び重点化・効率化による財政効果を活用して、子ども・子育て支援、医療・介護、年金の各分野について実施することとされた。
令和5年度における「社会保障の充実」の施策に係る所要額については、第84図のとおりである。
また、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)における「人づくり革命」では、待機児童の解消・保育士の処遇改善、幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善等の施策を推進するための安定財源として、消費税率8%から10%への引上げによる増収分の一部を活用することとされた。
令和5年度におけるこれらの施策に係る所要額については、第85図のとおりである。
(2)全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行うため、内閣総理大臣を本部長として関係閣僚による全世代型社会保障構築本部(令和4年1月設置。以下「構築本部」という。)が、全世代型社会保障改革担当大臣の下に有識者による全世代型社会保障構築会議(令和3年11月設置。以下「構築会議」という。)が設置され、令和4年12月に「全世代型社会保障構築会議 報告書 〜全世代で支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する〜」(以下「報告書」という。)が取りまとめられた。
報告書においては、
- 「こども・子育て支援の充実」については、少子化の危機的な状況から脱却するための更なる対策が求められており、特に現行制度で手薄な0〜2歳児への支援が重要との認識の下、妊娠・出産・子育てを通じた切れ目ない包括的支援を早期に構築すべきであること。あわせて、恒久的な施策には恒久的な財源が必要であり、支援策の更なる具体化とあわせて検討すべきであること。また、令和5年度の「骨太の方針」において、将来的にこども予算の倍増を目指していく上での当面の道筋を示していくことが必要であること。
- 「働き方に中立的な社会保障制度等の構築」については、働き方が多様化する中、どのような働き方をしても、誰もが安心して希望どおりに働くことができる社会保障制度等の構築が求められていること。また、少子化対策の観点からも、非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが円滑に労働移動できる環境整備が重要であること。
- 「医療・介護制度の改革」については、後期高齢者の割合が急激に高まることを踏まえ、負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みを早急に構築する必要があること。あわせて、医療の機能分化と連携の更なる推進、医療・介護人材の確保・育成、働き方改革や医療・介護サービス提供体制の改革を進めていく必要があること。
- 「「地域共生社会」の実現」については、今後、更なる増加が見込まれる独居高齢者や孤独・孤立、生活困窮の問題に直面する方々を社会全体でどのように支えていくかが大きな課題であること。中でも、住まいについては生活の基盤であるため、その確保を社会保障の重要な課題として位置付け、必要な施策を本格的に展開することが必要であること。
などが記載されており、項目ごとに「今後の改革の工程」が示されている。報告書については、構築本部に報告されるとともに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築に向けた取組について報告書に基づき着実に進めていくものとすることが、構築本部として決定された。
(3)こども・子育て支援の強化
構築会議の報告書においては、最も緊急を要する取組は、「未来への投資」として、子育て・若者世代への支援を急速かつ強力に整備することとされている。同報告書において、足元の課題として掲げられた項目等については、以下のとおりである。
ア 出産・子育て応援交付金
「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において、「支援が手薄な0歳から2歳の低年齢期に焦点を当てて、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、地方自治体の創意工夫により、妊娠・出産時の関連用品の購入費助成や産前・産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用負担軽減を図る経済的支援を一体として実施する事業を創設し、継続的に実施する」こととされた。
これを踏まえて伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する「出産・子育て応援交付金」が創設され、令和4年度補正予算(第2号)において必要な経費が計上された。その地方負担については、令和4年度の地方交付税の増額交付の中で対応することとされた。
令和5年度当初予算においても、「出産・子育て応援交付金」の継続実施のための経費が計上されており、その地方負担について令和5年度に所要の地方交付税措置を講じることとしている。
イ 出産育児一時金の増額
出産育児一時金については、健康保険や国民健康保険などの被保険者等が出産したときに、出産に要する経済的負担を軽減するため、一分娩当たり原則42万円が支給されているが、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月以降、出産育児一時金について現行の42万円から50万円への大幅引上げを行うこととされた。
国民健康保険の出産育児一時金については、その地方負担について地方交付税措置を講じているが、50万円への引上げ部分にも拡充し、引き続き地方交付税措置を講じることとしている。
ウ 産前産後保険料免除の創設に伴う公費による支援
国民健康保険の保険料については、国会での「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)等の附帯決議において、子育て世代の負担軽減や少子化対策等の観点を踏まえ、出産に関する保険料の配慮の必要性や在り方等について検討すべきとされており、社会保障審議会医療保険部会等において議論が行われてきた。
このような状況を踏まえ、第211回通常国会に提出されている「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」等により、令和6年1月以降、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料及び所得割保険料を免除することとされている。免除した保険料に係る公費負担が創設される予定であり、この地方負担について、新たに地方交付税措置を講じることとしている。
エ 児童虐待防止対策体制の強化
児童虐待防止対策の推進については、令和元年度から令和4年度までの児童相談所等の体制強化の目標を定めた「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)が令和4年度に終了すること等を踏まえ、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」(令和4年12月15日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定)が策定され、児童相談所において、児童福祉司を令和6年度までの2年間で約1,060名増員し、令和6年度に全国で約6,850名配置すること、児童心理司を令和8年度までの4年間で約950名増員し、令和8年度に全国で約3,300名配置することが目標とされた。
これを踏まえ、令和5年度に児童福祉司を約530名、児童心理司を約240名それぞれ増員できるよう、地方財政計画に必要な職員数を計上するとともに、地方交付税措置を講じることとしている。
上記のほか、こども・子育て政策の強化については、令和5年1月に、総理指示を受け、こども政策担当大臣の下に「こども政策の強化に関する関係府省会議」が開催され、目指すべき姿と当面加速化して進めるべき事項について集中的に検討し、同年3月末を目途に具体的なたたき台を取りまとめることとされている。その上で、令和5年4月以降、更に検討を深め、同年6月の「骨太の方針」までに、将来的なこども・子育て予算倍増に向けた大枠を提示することとされている。