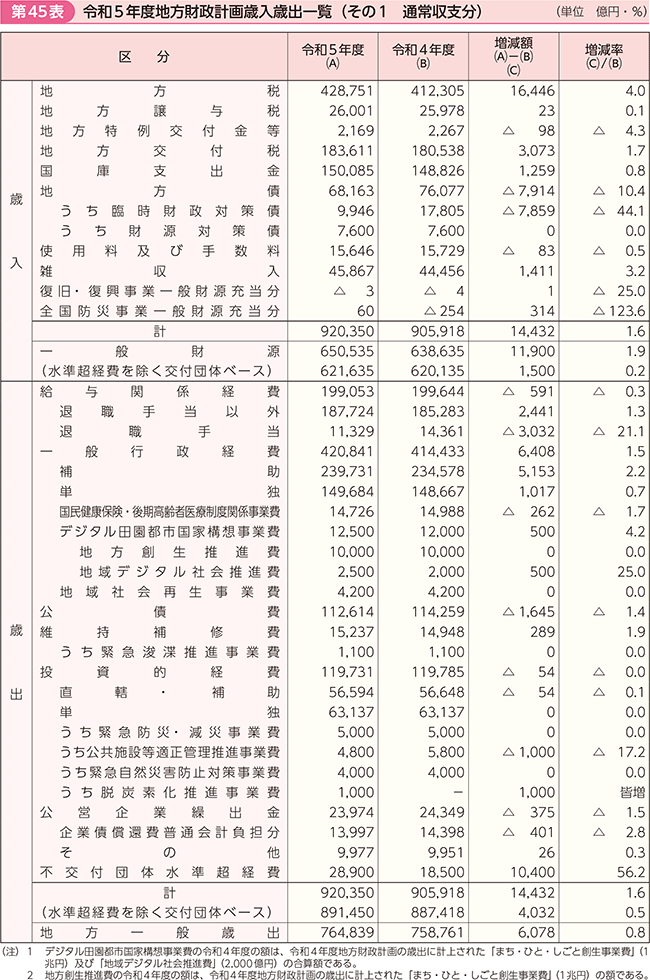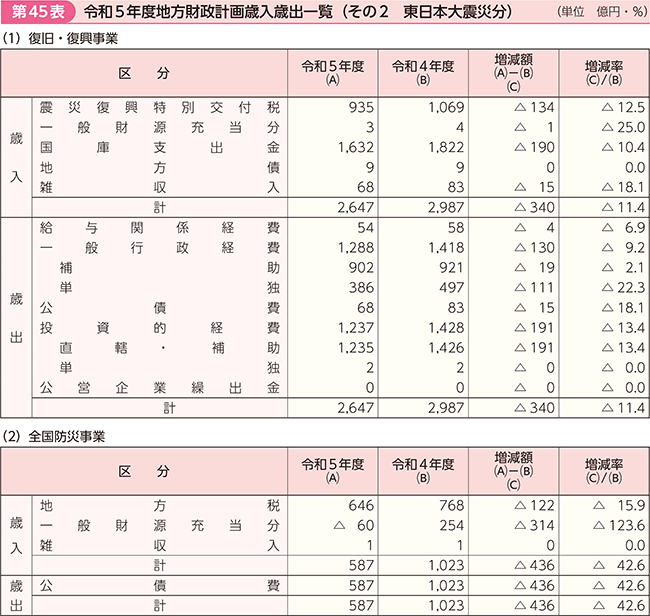2 令和5年度の地方財政
(1)令和5年度の国の予算
「令和5年度予算編成の基本方針」(令和4年12月2日閣議決定)及び「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(令和4年12月22日閣議了解、令和5年1月23日閣議決定)に基づいて、令和4年12月23日、令和5年度一般会計歳入歳出概算が閣議決定された。
令和5年度予算は、以下のような基本的な考え方により編成された。
ア 令和5年度予算の基本的な考え方
(ア)我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持ち直しが続いている。その一方で、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした国際的な原材料価格の上昇や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高騰、欧米各国の金融引締めによる世界的な景気後退懸念など、我が国経済を取り巻く環境には厳しさが増している。
(イ)こうした状況から国民生活と事業活動を守り抜くとともに、景気の下振れリスクに先手を打ち、我が国経済を民需主導の持続的な成長経路に乗せていくため、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする財政支出39.0兆円・事業規模71.6兆円の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を策定した。
これを速やかに実行に移し、経済対策の効果が最大限に発揮されるよう万全の経済財政運営を行う。
(ウ)足元の物価高を克服しつつ、新しい資本主義の旗印の下、社会課題の解決に向けた取組を成長のエンジンへと転換し、我が国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくため、以下の重点分野について、計画的で大胆な投資を官民連携の下で推進する。
まず、民主導での成長力の強化と「構造的な賃上げ」を目指し、リスキリング支援も含む「人への投資」の抜本強化と成長分野への労働移動の円滑化、地域の中小企業も含めた賃上げ等を進める。
また、科学技術・イノベーション、スタートアップ、グリーントランスフォーメーション(GX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)といった成長分野への大胆な投資を、令和4年内に取りまとめられるスタートアップ育成5か年計画やGX促進に向けた今後10年間のロードマップ等に基づき促進する。
(エ)コロナ禍において、婚姻件数・出生数が急激に減少するなど我が国の少子化は危機的な状況にある。こうした中、「こども家庭庁」を創設し、出産育児一時金の大幅増額を始めとする結婚・妊娠・出産・子育てに至るまで切れ目ないこども・若者・子育て世帯への支援など、少子化対策を含むこどもに関する必要な政策の充実を図り、強力に進めていく。
全ての人が生きがいを感じられ、多様性のある包摂社会を目指し、全世代型社会保障の構築、女性活躍、孤独・孤立対策、就職氷河期世代への支援等に取り組む。
(オ)ロシアによるウクライナ侵略も含め、国際情勢・安全保障環境が激変する中、令和5年のG7広島サミットや日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議の開催、国連安保理非常任理事国を務めることも見据え、機動的で力強い新時代リアリズム外交を展開するとともに、防衛力を5年以内に抜本的に強化する。防衛力の抜本的強化については、必要となる防衛力の内容の検討、そのための予算規模の把握及び財源の確保を一体的かつ強力に進め、令和4年末に改定される新たな「国家安全保障戦略」等に基づいて計画的に整備を進める。
(カ)国際情勢の変化に対応したサプライチェーンの再構築・強靱化が急務となる中、円安のメリットもいかし、企業の国内回帰など国内での「攻めの投資」、輸出拡大の推進により、我が国の経済構造の強靱化を図るとともに、半導体を始めとする重要な物資の安定供給の確保や先端的な重要技術の育成等による経済安全保障の推進、食料安全保障及びエネルギー安全保障の強化を図る。
(キ)新型コロナウイルス感染症対策について、ウィズコロナの下、国民の命と健康を守りながら、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る。次の感染症危機に備え、司令塔機能の強化に取り組む。
(ク)防災・減災、国土強靱化の取組を強力に推進するとともに、これまでの成果や経験をいかし、更なる取組を推進するための次期国土強靱化基本計画の検討を進め、中長期的かつ継続的に取り組む。
東日本大震災からの復興・創生、交通・物流インフラの整備、農林水産業の振興、質の高い教育の実現、観光や文化・芸術・スポーツの振興、2050年カーボンニュートラルを目指したグリーン社会の実現等に取り組み、デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組と併せて地方活性化に向けた基盤づくりを推進する。
(ケ)経済財政運営に当たっては、経済の再生が最優先課題である。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。必要な政策対応に取り組み、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組む。政策の長期的方向性や予見可能性を高めるよう、単年度主義の弊害を是正し、国家課題に計画的に取り組む。
イ 令和5年度予算編成についての考え方
(ア)令和5年度予算編成に当たっては、令和4年度第2次補正予算と一体として、上記の基本的な考え方及び「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定。以下「骨太方針2022」という。)に沿って、足元の物価高を克服しつつ、経済再生の実現に向け、人への投資、科学技術・イノベーション、スタートアップ、GX、DXといった成長分野への大胆な投資、少子化対策・こども政策の充実等を含む包摂社会の実現等による新しい資本主義の加速や、外交・安全保障環境の変化への対応、防災・減災、国土強靱化等の国民の安全・安心の確保を始めとした重要な政策課題について必要な予算措置を講じるなど、メリハリの効いた予算編成を行い、その政策効果を国民や地方の隅々まで速やかに届け、我が国経済を持続可能で一段高い成長経路に乗せていくことを目指す。
(イ)その際、骨太方針2022で示された「本方針及び骨太方針2021に基づき、経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。
(ウ)歳出の中身をより結果につながる効果的なものとするため、骨太方針2022を踏まえ、新経済・財政再生計画の改革工程表を策定し、EBPMやPDCAの取組を推進し、効果的・効率的な支出(ワイズスペンディング)を徹底する。
このような方針に基づいて編成された令和5年度一般会計歳入歳出概算の規模は114兆3,812億円で、前年度当初予算と比べると6兆7,848億円増(6.3%増)となった。
財政投融資計画の規模は16兆2,687億円で、前年度計画額と比べると2兆6,168億円減(13.9%減)となっている。
また、「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」においては、令和5年度の国内総生産は571.9兆円程度、名目成長率は2.1%程度、実質成長率は1.5%程度となるものと見込まれている。
(2)地方財政計画
令和5年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地域のデジタル化や脱炭素化の推進等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、骨太方針2022等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和4年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。
また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。
なお、地方財政審議会からは、令和4年5月25日に「活力ある持続可能な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月9日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和5年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。
以上を踏まえ、次の方針に基づき令和5年度の地方財政計画を策定している。
ア 通常収支分
(ア)地方税制については、令和5年度地方税制改正では、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し、航空機燃料譲与税の譲与割合の特例措置の見直し等の税制上の措置を講じることとしている。
(イ)地方財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。
a 地方交付税法第6条の3第2項に基づく制度改正として、令和5年度から令和7年度までの間は、令和4年度までと同様、財源不足が建設地方債(財源対策債)の増発等によってもなお残る場合には、この残余を国と地方が折半して補填することとし、国負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補填措置を講じる。臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入する。
b 令和5年度の地方財源不足見込額1兆9,900億円については、上記の考え方に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。
(a)建設地方債(財源対策債)を7,600億円増発する。
(b)地方交付税については、国の一般会計加算(地方交付税法附則第4条の2第1項の加算)により154億円増額する。
また、交付税特別会計剰余金1,200億円を活用するとともに、「地方公共団体金融機構法」(平成19年法律第64号)附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金1,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。
(c)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を9,946億円発行する。
c 交付税特別会計借入金の償還については、令和3年度の償還計画の見直しに伴い償還を繰り延べたものの一部8,000億円を増額し、1兆3,000億円の償還を実施する。
d 上記の結果、令和5年度の地方交付税については、18兆3,611億円(前年度比3,073億円、1.7%増)を確保する。
(ウ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化及び地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。
この結果、地方債計画(通常収支分)の規模は、9兆4,981億円(普通会計分6兆8,163億円、公営企業会計等分2兆6,818億円)とする。
(エ)地域のデジタル化や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、地域の脱炭素化の推進、住民に身近な社会資本の整備、社会保障施策の充実、地方公共団体の施設の光熱費高騰への対応、消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進、過疎地域の持続的発展等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。
a 「地域デジタル社会推進費」については、マイナンバーカード利活用特別分として500億円増額し、2,500億円を計上する。
また、「まち・ひと・しごと創生事業費」については、「地方創生推進費」に名称変更し、引き続き1兆円(前年度同額)計上した上で、これと「地域デジタル社会推進費」を内訳として、「デジタル田園都市国家構想事業費」を1兆2,500億円計上する。
b 「地域社会再生事業費」については、引き続き4,200億円(前年度同額)計上する。
c 投資的経費に係る地方単独事業費については、地方公共団体が、地域脱炭素の取組を計画的に実施できるよう、新たに「脱炭素化推進事業費」を1,000億円計上することとし、全体で前年度同額を計上し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。
d 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
e 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
f 一般行政経費に係る地方単独事業費については、社会保障関係費の増加や地方公共団体の施設の光熱費高騰に伴う経費の増加等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。
g 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。
h 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。
(オ)地方公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。
(カ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。
イ 東日本大震災分
(ア)復旧・復興事業
a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため、935億円を確保する。また、一般財源充当分として3億円を計上する。
b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。
この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、13億円(普通会計分9億円、公営企業会計等分4億円)とする。
c 直轄事業負担金及び補助事業費、地方自治法に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費並びに地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出等について所要の事業費2,647億円を計上する。
(イ)全国防災事業
全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として646億円を計上するとともに、一般財源充当分として60億円を減額計上する。
以上のような方針に基づいて策定した令和5年度の地方財政計画は、第45表のとおりとなっており、その規模は、通常収支分は92兆350億円で、前年度と比べると1兆4,432億円増(1.6%増)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が2,647億円で、前年度と比べると340億円減(11.4%減)、全国防災事業が587億円で、前年度と比べると436億円減(42.6%減)となっている。
また、令和5年度の地方債計画の規模は、通常収支分が9兆4,981億円(普通会計分6兆8,163億円、公営企業会計等分2兆6,818億円)で、前年度と比べると6,818億円減(6.7%減)となっている。東日本大震災分は、復旧・復興事業が13億円(普通会計分9億円、公営企業会計等分4億円)で、前年度と比べると2億円減(13.3%減)となっている。
(3)公営企業等に関する財政措置
ア 公営企業
(ア)通常収支分
公営企業については、経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図る必要がある。
このため、令和5年度においては、次のような措置を講じることとしている。
公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金については、地方財政計画において2兆3,974億円(前年度2兆4,349億円)を計上する。
公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分2兆6,818億円(前年度2兆5,722億円)を計上する。
各事業における地方財政措置のうち主なものは以下のとおりである。
a 公営企業会計の更なる適用の推進について、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業について、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行するなど、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費や、市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。
なお、簡易水道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本費対策に係る地方交付税措置について、人口3万人以上の地方公共団体は令和3年度から公営企業会計の適用を要件に加えている。
b 水道事業については、多様な広域化を推進し、持続的な経営を確保するため、都道府県が実施する広域化の推進のための調査検討に要する経費について、新たに地方交付税措置を講じるとともに、広域化に伴う施設の整備費等について、引き続き地方財政措置を講じる。
c 下水道事業については、広域化・共同化を推進し、持続的な経営を確保するため、都道府県が実施する広域化・共同化の推進のための調査検討に要する経費について、新たに地方交付税措置を講じるとともに、広域化・共同化に伴う施設の整備費等について、事務を共同で処理する際に必要なシステム整備費を対象に追加した上で、引き続き地方財政措置を講じる。
d 病院事業については、公立病院等の経営強化を推進し、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師等の確保の取組等の支援について、引き続き地方財政措置を講じる。
また、公立病院等の施設整備費に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を引き上げるとともに、令和3年度に講じた不採算地区病院等に対する特別交付税措置の拡充を令和5年度においても継続する。
(イ)東日本大震災分
公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において0.19億円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等分4億円を計上する。
イ 国民健康保険事業
国民健康保険制度については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったが、国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、国民健康保険法第72条の2に基づき、一般会計から当該都道府県国保に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の9%分)については、その所要額(5,910億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)国保被保険者のうち低所得者に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県3/4、市町村1/4)を負担することとし、その所要額(4,271億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)国保被保険者のうち未就学児に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(40億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)国保被保険者のうち子育て世代の負担軽減、次世代育成支援及び負担能力に応じた負担とする観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が産前産後期間の保険料免除相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(2億円)について地方交付税措置を講じる。
(オ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(1,344億円)について地方交付税措置を講じる。
(カ)高額医療費負担金(4,043億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、都道府県国保1/2)を負担することとし、地方負担(1,011億円)について地方交付税措置を講じる。
(キ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000億円)を講じる。
(ク)出産に直接要する費用や出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るための出産育児一時金については、令和5年4月から50万円に引き上げられるとともに、引き続き市町村が一部(市町村2/3、市町村国保1/3)を負担することとし、地方負担(187億円)について地方交付税措置を講じる。
(ケ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40歳から74歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業(388億円)に対して、国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、都道府県国保1/3)を負担することとし、地方負担(129億円)について地方交付税措置を講じる。
ウ 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度については、実施主体である後期高齢者医療広域連合の財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和を図る(均等割2割・5割・7割軽減)ため、都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く。)が負担(都道府県3/4、市町村1/4)することとし、その所要額(3,545億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)高額医療費負担金(4,103億円)については、後期高齢者医療広域連合の拠出金に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、後期高齢者医療広域連合1/2)を負担することとし、地方負担(1,026億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金(201億円)に対して国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、後期高齢者医療広域連合1/3)を負担することとし、地方負担(67億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)後期高齢者医療広域連合に対する市町村分担金、市町村(一部事務組合等を除く。)の事務経費及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。
(オ)出産育児一時金に係る費用を全世代で分かち合う観点から、その費用(公費負担部分を除く。)の一部について、後期高齢者が負担する仕組みを導入することとしており、後期高齢者医療の保険料改定のタイミングである令和6年4月から導入することとしている。