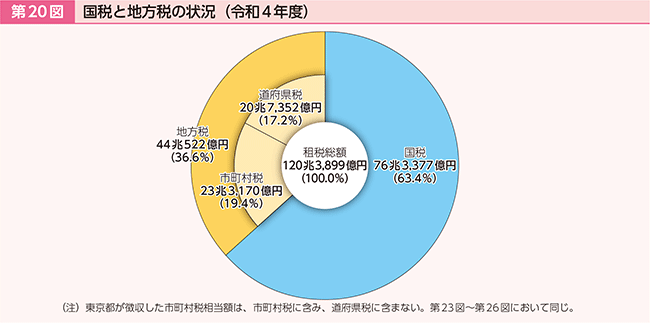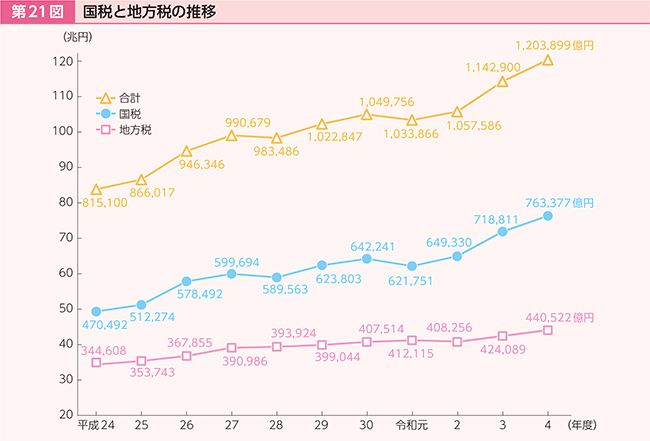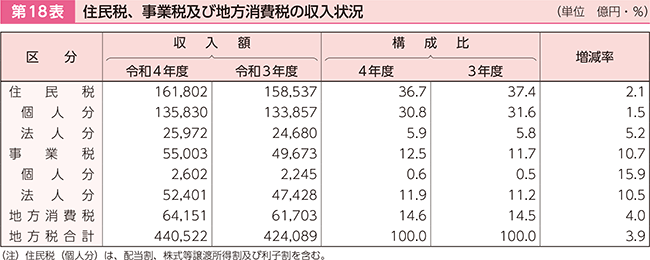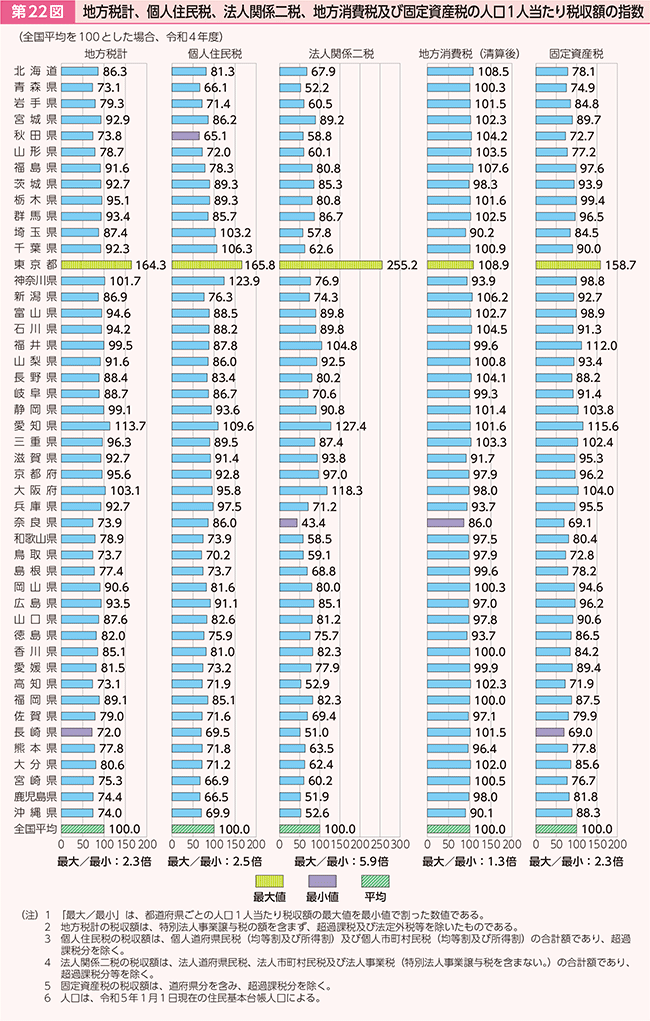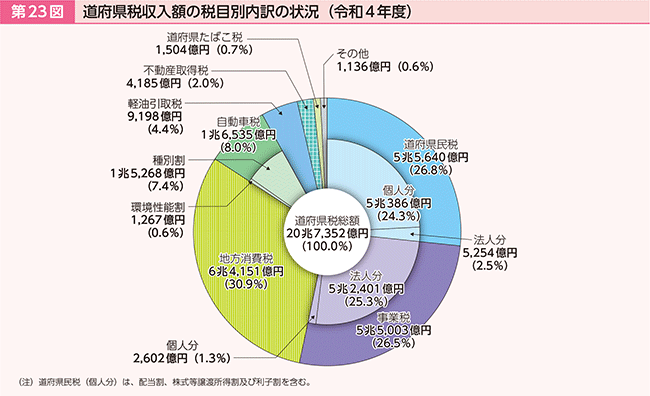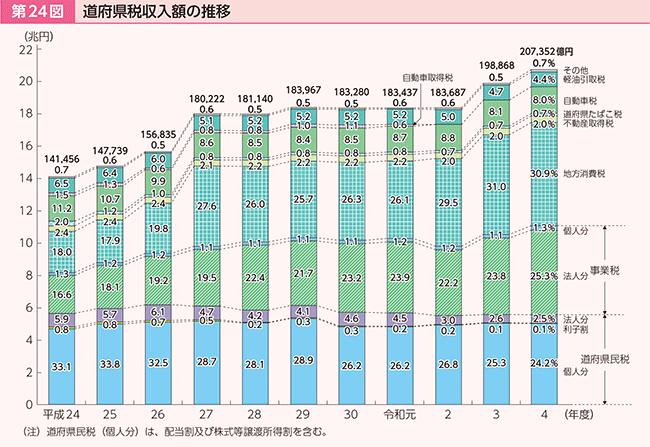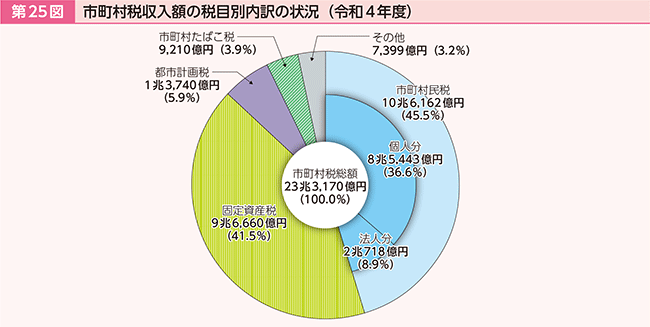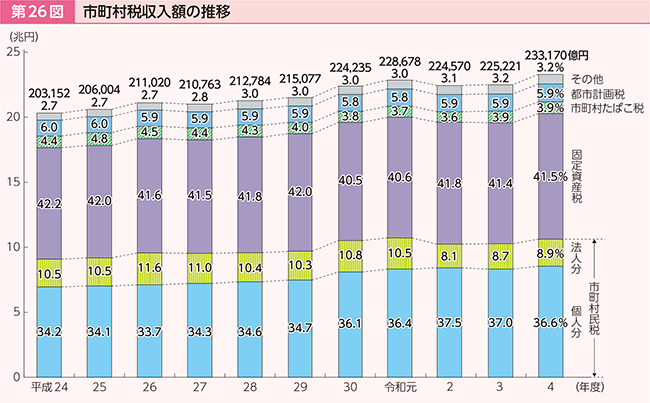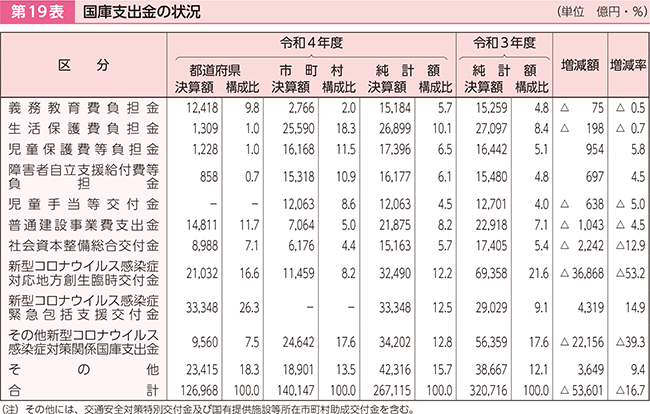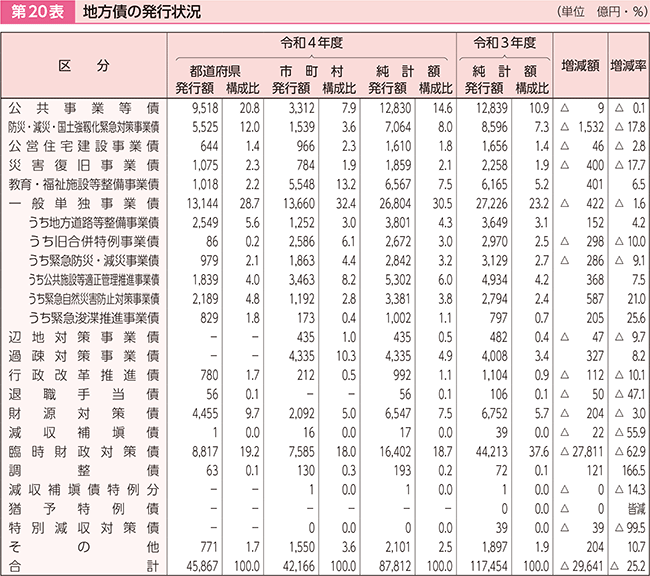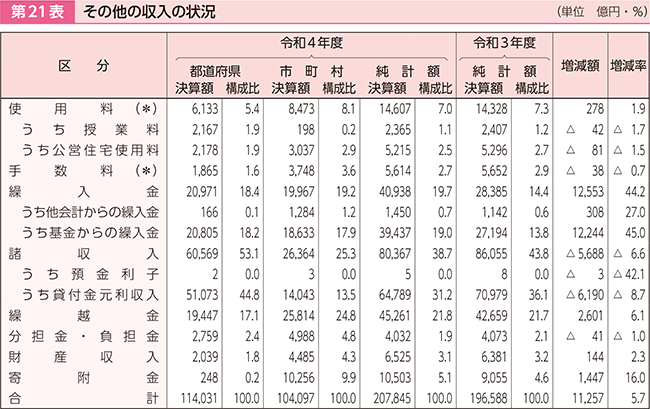3 地方財源の状況
国税と地方税を合わせた租税の状況及び地方歳入(普通会計)の状況は、以下のとおりである。
(1)租税の状況
国税と地方税を合わせた租税として徴収された額は120兆3,899億円で、前年度と比べると5.3%増となっている。
国民所得に対する租税総額の割合である租税負担率をみると、令和4年度においては、前年度と比べると0.5ポイント上昇の29.4%となっている。なお、主な諸外国の租税負担率をみると、アメリカ23.8%(2020暦年計数)、イギリス34.3%(同)、ドイツ30.3%(同)、フランス45.0%(同)となっている。
次に、国税と地方税の状況をみると、第20図のとおりであり、租税総額に占める割合は、国税63.4%(前年度62.9%)、地方税36.6%(同37.1%)となっている。また、地方交付税、地方譲与税及び地方特例交付金等を国から地方へ交付した後の租税の実質的な配分割合は、国45.5%(同43.3%)、地方54.5%(同56.7%)となっている。なお、国税と地方税の推移は第21図のとおりであり、地方税は平成24年度以降増加傾向にある。
(2)地方歳入
ア 地方税
地方税の決算額は44兆522億円で、前年度と比べると3.9%増となっている。
地方税収入額の63.8%を占める住民税、事業税及び地方消費税の収入状況は、第18表のとおりである。また、各税目の収入額を前年度と比べると、住民税は個人分の増加等により2.1%増、事業税は法人分の増加等により10.7%増、地方消費税は4.0%増となっている。なお、法人関係二税は7兆8,373億円で、前年度と比べると8.7%増となっている。
地方税計、個人住民税、法人関係二税、地方消費税及び固定資産税の人口1人当たり税収額の指数をみると、第22図のとおりであり、地方税計については、最も大きい東京都が164.3、最も小さい長崎県が72.0で、約2.3倍の格差となっている。
個別の税目ごとに比較してみると、個人住民税については、最も大きい東京都が165.8、最も小さい秋田県が65.1で、約2.5倍の格差となっている。法人関係二税については、最も大きい東京都が255.2、最も小さい奈良県が43.4で、約5.9倍の格差となっている。地方消費税については、最も大きい東京都が108.9、最も小さい奈良県が86.0で、約1.3倍の格差となっている。固定資産税については、最も大きい東京都が158.7、最も小さい長崎県が69.0で、約2.3倍の格差となっている。
このように、地方税収については、各税目とも都道府県ごとに偏在性があるが、その度合いについては、法人関係二税の格差が特に大きく、地方消費税の偏在性は比較的小さい。
(ア)道府県税の収入状況
都道府県の地方税の決算額から東京都が徴収した市町村税相当額を除いた道府県税の収入額は20兆7,352億円で、事業税、地方消費税の増加等により、前年度と比べると4.3%増となっている。
道府県税収入額の税目別内訳の状況は、第23図のとおりである。
このうち、法人関係二税は5兆7,655億円で、道府県税総額に占める割合は27.8%となっている。
道府県税収入額の推移は、第24図のとおりである。
(イ)市町村税の収入状況
市町村の地方税の決算額に東京都が徴収した市町村税相当額を加えた市町村税の収入額は23兆3,170億円で、固定資産税、市町村民税(個人分)の増加等により、前年度と比べると3.5%増となっている。
市町村税収入額の税目別内訳の状況は、第25図のとおりである。
市町村税収入額の推移は、第26図のとおりである。
(ウ)法定外普通税
地方公共団体は、「地方税法」(昭和25年法律第226号)で規定されている税目のほかに、地方公共団体ごとの特有な財政需要を充足するため、法定外普通税を設けることができる。法定外普通税の収入額は538億円で、前年度と比べると7.4%増となっている。
(エ)法定外目的税
地方公共団体は、地方税法で規定されている税目のほかに、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を設けることができる。法定外目的税の収入額は193億円で、前年度と比べると44.7%増となっている。
(オ)超過課税
地方公共団体は、地方税法で標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要がある場合に、その税率を超える税率を定めることができる。この標準税率を超えて課税された部分である超過課税による収入額は8,233億円で、前年度と比べると7.0%増となっている。
イ 地方譲与税
地方譲与税の決算額は2兆7,621億円で、特別法人事業譲与税の増加等により、前年度と比べると12.9%増となっている。
地方譲与税の主な内訳をみると、特別法人事業譲与税が2兆1,659億円(対前年度比16.9%増)、自動車重量譲与税が2,947億円(同1.8%増)となっている。
ウ 地方特例交付金等
地方特例交付金等の決算額は2,227億円で、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減少等により、前年度と比べると51.0%減となっている。
地方特例交付金等の内訳をみると、個人住民税減収補填特例交付金が2,172億円、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が55億円となっている。
エ 地方交付税
地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方の固有財源である。また、その目的は、地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を損なわずに、その財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公共団体の独立性を強化することである。
地方交付税の決算額は18兆6,310億円で、前年度と比べると4.5%減となっている。地方交付税の内訳をみると、普通交付税17兆4,376億円、特別交付税1兆1,131億円、震災復興特別交付税(*)802億円となっている。
また、団体区分別にみると、都道府県においては9兆5,298億円で、前年度と比べると6.7%減、市町村においては9兆1,012億円で、前年度と比べると2.1%減となっており、その地方交付税総額に占める割合は、都道府県においては51.2%(前年度52.3%)、市町村においては48.8%(同47.7%)となっている。
普通交付税(基準財政需要額が基準財政収入額(*)を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付されるもの)の交付状況をみると、不交付団体は、都道府県では東京都の1団体である。市町村(特別区及び一部事務組合等を除く。以下この段落において同じ。)では前年度より21団体増加し、72団体となっている。また、災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税の令和4年度の交付状況をみると、都道府県においては東京都を除く全団体に、市町村においては全1,718団体に、それぞれ交付されている。
なお、令和4年度当初において地方公共団体に交付される通常収支分の地方交付税の総額は、地方財政計画(*)において、前年度と比べると、6,153億円増(3.5%増)の18兆538億円とした。また、国の令和4年度補正予算(第2号)において、国税収入の補正等に伴い令和4年度分の地方交付税の額が1兆9,211億円の増額となったことを受け、このうち4,970億円を令和4年度に増額交付することとした。具体的には、普通交付税の調整額を復活するとともに、地方公共団体が、経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に実施するために必要な経費を算定するため、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」を創設することとした。
オ 国庫支出金
国庫支出金の状況は、第19表のとおりである。国庫支出金の決算額は26兆7,115億円で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減少等により、前年度と比べると16.7%減となっている。
国庫支出金の内訳をみると、新型コロナウイルス感染症対策関連の国庫支出金の合計は10兆40億円となり、国庫支出金総額の37.5%を占めている。
カ 都道府県支出金
市町村が都道府県から交付を受ける都道府県支出金の決算額は4兆6,987億円で、障害者自立支援給付費等負担金の増加等により、前年度と比べると2.2%増となっている。
都道府県支出金の内訳をみると、国庫財源を伴うものが65.0%、都道府県費のみのものが35.0%となっている。
キ 地方債
地方債の発行状況は、第20表のとおりである。地方債の決算額は8兆7,812億円で、臨時財政対策債の減少等により、前年度と比べると25.2%減となっている。
団体区分別にみると、都道府県においては4兆5,867億円で、前年度と比べると29.9%減、市町村においては4兆2,166億円で、前年度と比べると19.3%減となっている。また、地方債依存度(歳入総額に占める地方債の割合)は7.2%で、前年度と比べると2.0ポイント低下している。
ク その他の収入
その他の収入の状況は、第21表のとおりである。決算額は20兆7,845億円で、基金からの繰入金の増加等により、前年度と比べると5.7%増となっている。