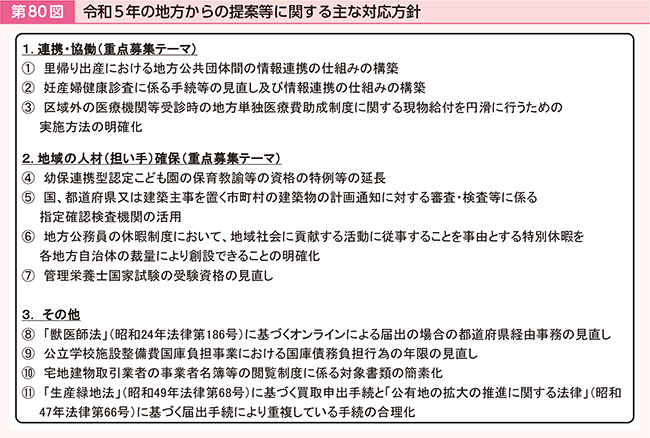8 地方行政をめぐる動向と地方分権改革の推進
(1)第33次地方制度調査会について
令和4年1月に発足した第33次地方制度調査会は、約2年に及ぶ調査審議を経て、令和5年12月21日に「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(以下「令和5年答申」という。)を内閣総理大臣に提出した。令和5年答申は、ポストコロナの経済社会に的確に対応する観点から、<1>デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応、<2>地方公共団体相互間の連携・協力及び公共私の連携、<3>大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応について提言したものであり、これを踏まえた「地方自治法の一部を改正する法律案」を第213回通常国会に提出する予定である。
(2)地方公共団体相互間の連携・協力
地方圏において少子高齢化・人口減少の局面に的確に対応していくための連携の枠組みである「連携中枢都市圏」や「定住自立圏」の形成については相当程度進捗した段階にあり、広域的な産業政策、観光振興、災害対策など、比較的連携しやすい取組から実績が積み上げられている。
さらに、令和5年答申を踏まえ、地方公共団体の経営資源が制約される中で、持続可能な形で行政サービスを提供し住民の暮らしを支えていくため、地方公共団体が、地域や組織の枠を越えて資源を融通し合い、他の地方公共団体や地域の多様な主体と連携・協働していく取組を深化する必要がある。
特に、市町村の自主的な連携による専門人材の確保等の取組が重要であり、その上でニーズに応じた都道府県等による調整・支援を促進する必要がある。
専門人材の確保については、小規模市町村を中心として、専門性を有する人材の配置が困難な状況がみられることから、技術職員やデジタル人材の確保に対する地方交付税措置に加え、都道府県等が、市町村と連携協約を締結した上で、保健師、保育士、税務職員など、当該市町村が必要とする専門性を有する人材を確保し派遣する場合の募集経費及び人件費について、令和6年度から新たに特別交付税措置を講じることとしている。
(3)地方公務員行政に係る取組
ア 会計年度任用職員制度
令和2年度に導入された会計年度任用職員制度に係る任用や給与決定などの施行状況については、任用根拠の明確化や勤務条件の改善など、概ね、制度の趣旨に沿った運用が図られているが、一部にまだ対応が十分でない地方公共団体もあり、こうした団体においては、適正化を図る必要がある。
会計年度任用職員への勤勉手当の支給については、制度導入時には、国の非常勤職員に勤勉手当の支給が広まっていなかったこと等を踏まえ、検討課題とされていたが、「地方自治法の一部を改正する法律」(令和5年法律第19号)により、令和6年度から支給が可能とされた。これを受け、令和6年度の地方財政計画においては、会計年度任用職員への勤勉手当の支給に要する経費として、1,810億円を計上している。
イ 地方公共団体の人材育成・確保
地方公共団体において、少子高齢化、デジタル社会の進展等により複雑・多様化する行政課題に対応する上で、人材育成・確保の重要性が高まっており、令和5年答申においても、都道府県等が市町村と連携して専門人材の育成・確保に取り組む視点の重要性が指摘されている。このような状況を踏まえ、総務省では、各地方公共団体が人材育成基本方針を改正等する際の新たな指針として、「人材育成・確保基本方針策定指針」(令和5年12月22日付け総務省大臣官房地域力創造審議官・自治行政局公務員部長通知)を策定し、地方公共団体に対して、新たな指針を参考として、各地方公共団体において策定されている基本方針の改正等を含め、着実に取組を推進するよう要請している。
こうした中、前述した専門人材確保に係る特別交付税措置の創設に加え、人材育成については、各地方公共団体が、改正後の人材育成基本方針において、特に重点的に取り組むとして明示した新たな政策課題に関する自団体職員向けの研修経費及び都道府県等が市町村職員を含めて開催する広域的な研修経費について、令和6年度から新たに地方交付税措置を講じることとしている。
(4)地方分権改革の推進
ア 地方からの提案に関する対応方針等
地方分権改革については、平成26年から、それまでの成果を基盤とし、地方の発意に根ざした新たな取組を推進するため、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定)により、「提案募集方式」を導入している。これまで、累次にわたる、いわゆる地方分権一括法*4により、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革が推進されている。
令和5年においては、176件の提案について調整がなされ、このうち154件についての対応方針が「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)に盛り込まれた。
本方針に盛り込まれた事項のうち、主なものは第80図のとおりであり、法律の改正により措置すべき事項については、所要の地方分権一括法案を第213回通常国会に提出することを基本とし、現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化することとされている。
また、計画策定等による地方公共団体の事務負担の増大への対応については、「計画策定等における地方分権改革の推進について〜効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド〜」(令和5年3月31日閣議決定)を着実に運用し、国・地方を通じた効率的・効果的な計画行政を推進することとされている。
今後とも、地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って、地方分権改革を着実かつ強力に進めていくこととされている。
イ 地方税財源の充実確保
地方公共団体が自らの発想で特色を持った地域づくりを進めていくためには、その基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築を進めることが重要である。
なお、令和6年度税制改正については、令和5年11月14日に、地方財政審議会から、「令和6年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」が提出されるとともに、同年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定された。
以上を踏まえ、地方税制の改正を行うため、第213回通常国会に「地方税法等の一部を改正する法律案」を提出している。
*4 提案募集方式の導入以降、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号。いわゆる「第5次地方分権一括法」。)から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第58号。いわゆる「第13次地方分権一括法」。)までの地方分権一括法が成立している。