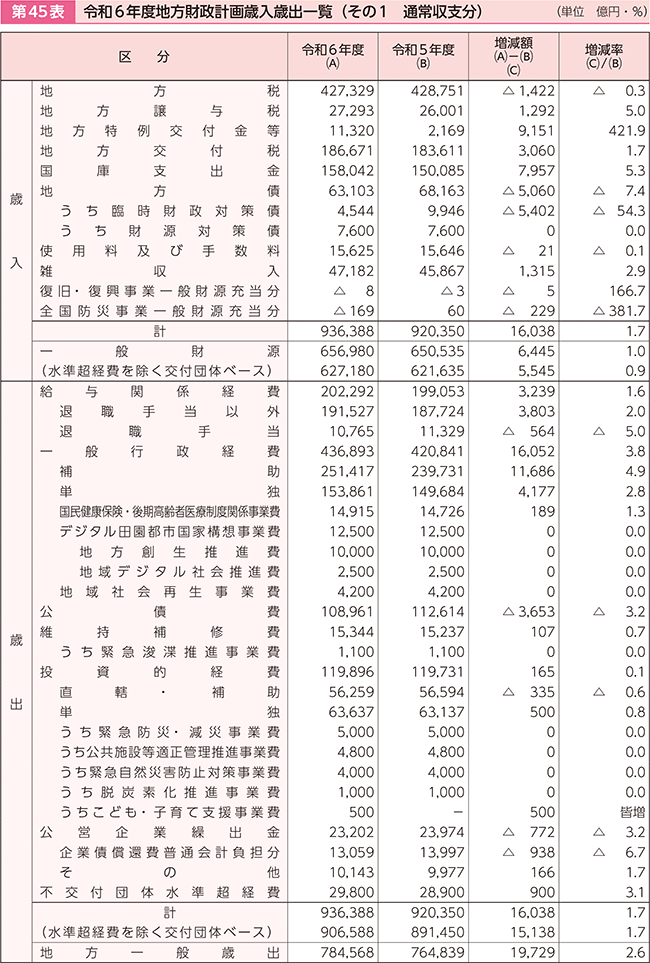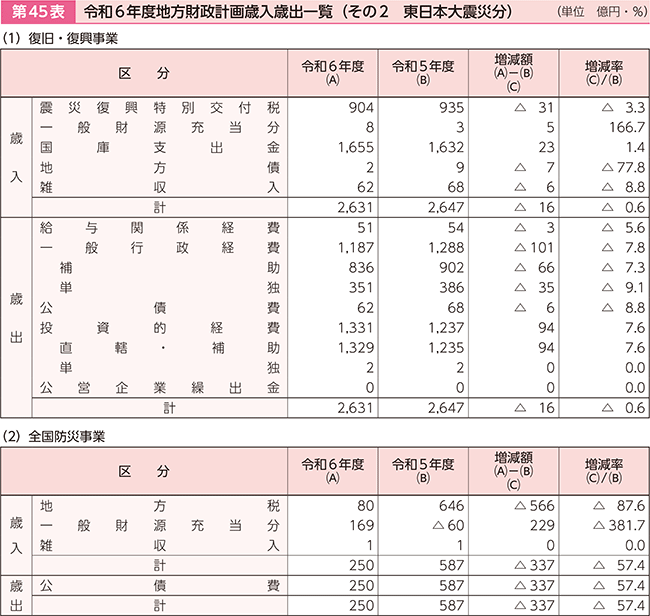2 令和6年度の地方財政
(1)地方財政計画
令和6年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、こども・子育て政策の強化等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費や民間における賃上げ等を踏まえた人件費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16 日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。
また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。
なお、地方財政審議会からは、令和5年5月25日に「活力ある多様な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月11日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和6年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。
以上を踏まえ、次の方針に基づき令和6年度の地方財政計画を策定している。
ア 通常収支分
(ア)地方税制については、令和6年度地方税制改正では、個人住民税の定額減税を実施するほか、法人事業税の外形標準課税に係る適用対象法人の見直し、令和6年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長、森林環境譲与税の譲与基準の見直し等の税制上の措置を講じることとしている。
(イ)所得税・個人住民税の定額減税に伴う減収については、次の措置を講じる。
a 個人住民税の定額減税に伴う減収9,234億円については、個人住民税減収補填特例交付金によりその全額を補填する。
b 所得税の定額減税に伴う地方交付税の減収7,620億円については、前年度からの繰越金及び自然増収による地方交付税法定率分の増1兆1,982億円により対応する。
さらに、2,076億円を、令和7年度以降、国の一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとし、当該加算額については交付税特別会計借入金の償還に充てるものとする。
(ウ)地方財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。
a 令和6年度の地方財源不足見込額1兆8,132億円については、令和5年度に講じた令和7年度までの制度改正に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。
(a)建設地方債(財源対策債)を7,600億円増発する。
(b)地方交付税については、国の一般会計加算により3,488億円(地方交付税法附則第4条の2第1項の加算額154億円及び同条第3項の加算額834億円並びに平成22年12月22日付け総務・財務両大臣覚書第3項(2)及び令和4年12月21日付け総務・財務両大臣覚書第8項に定める「乖離是正分加算額」2,500億円)増額する。
また、交付税特別会計剰余金500億円を活用するとともに、地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金2,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。
(c)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を4,544億円発行する。
b 交付税特別会計借入金の償還については、「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)附則第4条第1項に基づき、5,000億円の償還を実施する。
c 上記の結果、令和6年度の地方交付税については、18兆6,671億円(前年度比3,060億円、1.7%増)を確保する。
(エ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。
この結果、地方債計画(通常収支分)の規模は、9兆2,184億円(普通会計分6兆3,103億円、公営企業会計等分2兆9,081億円)とする。
(オ)地域のデジタル化や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、こども・子育て政策の強化、住民に身近な社会資本の整備、社会保障施策の充実、消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進、過疎地域の持続的発展等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。
a 「デジタル田園都市国家構想事業費」については、1兆2,500億円(前年度同額)計上する。
b 「地域社会再生事業費」については、4,200億円(前年度同額)計上する。
c 「こども未来戦略」(令和5年12 月22 日閣議決定)に掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」における地方負担について所要の財政措置を講じる。
d 投資的経費に係る地方単独事業費については、新たに「こども・子育て支援事業費」を500億円計上することとし、全体で前年度に比べ0.8%増額し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。
e 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
f 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、こども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
g 一般行政経費に係る地方単独事業費については、こども・子育て政策の強化等による社会保障関係費の増加や会計年度任用職員への勤勉手当の支給に要する経費等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。
h 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。
i 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。
(カ)公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。
(キ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。
イ 東日本大震災分
(ア)復旧・復興事業
a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、補助事業に係る地方負担分等を措置するため、904億円を確保する。また、一般財源充当分として8億円を計上する。
b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。
この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、7億円(普通会計分2億円、公営企業会計等分5億円)とする。
c 補助事業費、地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出、地方自治法に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費等について所要の事業費2,631億円を計上する。
(イ)全国防災事業
全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として80億円を計上するとともに、一般財源充当分として169億円を計上する。
以上のような方針に基づいて策定した令和6年度の地方財政計画は、第45表のとおりとなっており、その規模は、通常収支分は93兆6,388億円で、前年度と比べると1兆6,038億円増(1.7%増)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が2,631億円で、前年度と比べると16億円減(0.6%減)、全国防災事業が250億円で、前年度と比べると337億円減(57.4%減)となっている。
また、令和6年度の地方債計画の規模は、通常収支分が9兆2,184億円で、前年度と比べると2,797億円減(2.9%減)となっている。東日本大震災分は、復旧・復興事業が7億円で、前年度と比べると6億円減(46.2%減)となっている。
(2)公営企業等に関する財政措置
ア 公営企業
(ア)通常収支分
公営企業については、上記(1)ア(カ)の公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金として、地方財政計画において2兆3,202億円(前年度2兆3,974億円)を計上する。
公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分2兆9,081億円(前年度2兆6,818億円)を計上する。
各事業における地方財政措置のうち主なものは、以下のとおりである。
a 公営企業会計の適用の更なる推進について、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業については早急に公営企業会計を適用し、その他の事業についてはできる限り公営企業会計を適用するなど、地方公共団体において円滑に取組が実施されるよう、適用に要する経費や、市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。
b 公営企業会計の適用の進捗を踏まえ、公債費負担を適正な水準の料金収入等で賄える程度に平準化できるよう、資本費平準化債の発行可能額の算定において、過去に発行した資本費平準化債の元金償還金を新たに算定対象に加えることとしている。
c 水道事業については、広域化を推進し、持続的な経営を確保するため、広域化に伴う施設の整備費等や都道府県が実施する広域化の推進のための調査検討に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。
また、水道管路の計画的な耐震化を推進するため、水道管路耐震化事業に対する地方財政措置について、対象となる上積事業費の算出方法を見直した上で継続する。
d 下水道事業については、広域化・共同化を推進し、持続的な経営を確保するため、広域化・共同化に伴う施設の整備費等や都道府県が実施する広域化・共同化の推進のための調査検討に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。
e 病院事業については、公立病院等の経営強化を推進し、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師等の確保の取組等の支援について、引き続き地方財政措置を講じる。
また、公立病院等の施設整備費に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を引き上げるとともに、令和3年度に講じた不採算地区病院等に対する特別交付税措置の拡充を令和6年度においても継続する。
f 交通事業については、依然としてテレワークの普及等の影響を受け、新型コロナウイルス感染症による感染が拡大する前の令和元年度と比較して1割以上の減収が継続するなど構造的な課題を抱えることから、適切に経営改善に取り組む地方公共団体の資金繰りを円滑にし、経営改善を促進するため、新たに交通事業債(経営改善推進事業)を創設することとしている。
(イ)東日本大震災分
公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において0.19億円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等分5億円を計上する。
イ 国民健康保険事業
国民健康保険事業については、厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、国民健康保険法第72条の2に基づき、一般会計から当該都道府県国保に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の9%分)については、その所要額(5,883億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)国保被保険者のうち低所得者に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県3/4、市町村1/4)を負担することとし、その所要額(4,278億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)国保被保険者のうち未就学児に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(40億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)国保被保険者のうち子育て世代の負担軽減、次世代育成支援及び負担能力に応じた負担とする観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が産前産後期間の保険料免除相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(8億円)について地方交付税措置を講じる。
(オ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(1,314億円)について地方交付税措置を講じる。
(カ)高額医療費負担金(3,949億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、都道府県国保1/2)を負担することとし、地方負担(987億円)について地方交付税措置を講じる。
(キ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000億円)を講じる。
(ク)出産に直接要する費用や出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るための出産育児一時金については、引き続き市町村が一部(市町村2/3、市町村国保1/3)を負担することとし、地方負担(184億円)について地方交付税措置を講じる。
(ケ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40歳から74歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業(393億円)に対して、国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、都道府県国保1/3)を負担することとし、地方負担(131億円)について地方交付税措置を講じる。
ウ 後期高齢者医療事業
後期高齢者医療事業については、実施主体である後期高齢者医療広域連合の財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和(均等割2割・5割・7割軽減)を図るため、都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く。)が負担(都道府県3/4、市町村1/4)することとし、その所要額(3,754億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)高額医療費負担金(4,854億円)については、後期高齢者医療広域連合の拠出金に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、後期高齢者医療広域連合1/2)を負担することとし、地方負担(1,214億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金(216億円)に対して国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、後期高齢者医療広域連合1/3)を負担することとし、地方負担(72億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)後期高齢者医療広域連合に対する市町村分担金、市町村(一部事務組合等を除く。)の事務経費及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。
(オ)出産育児一時金に係る費用を全世代で分かち合う観点から、その費用(公費負担部分を除く。)の一部について、後期高齢者が負担する仕組みを導入することとしており、後期高齢者医療の保険料改定のタイミングである令和6年4月から導入することとしている。