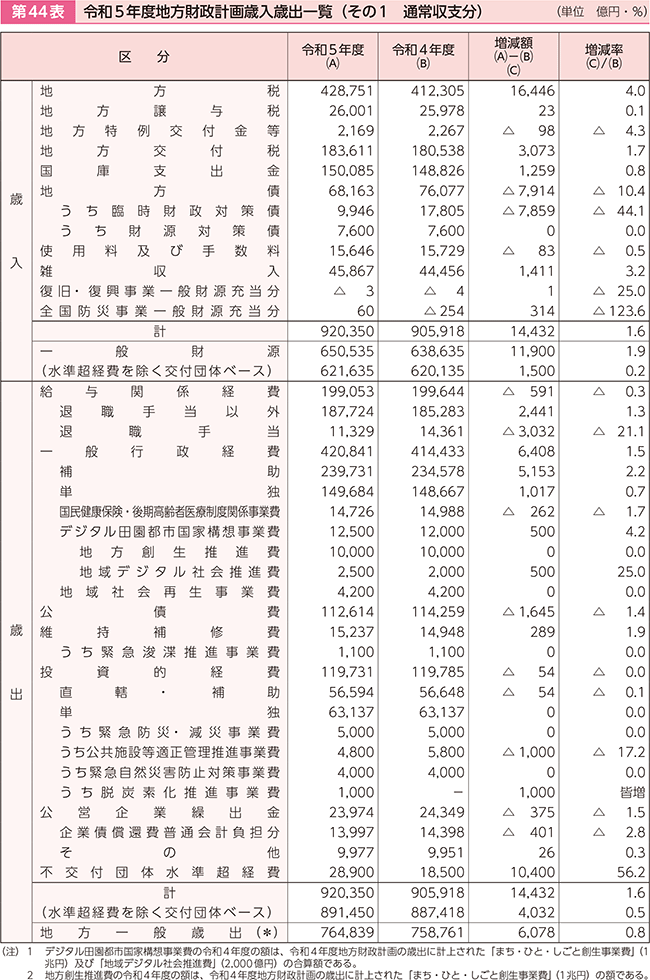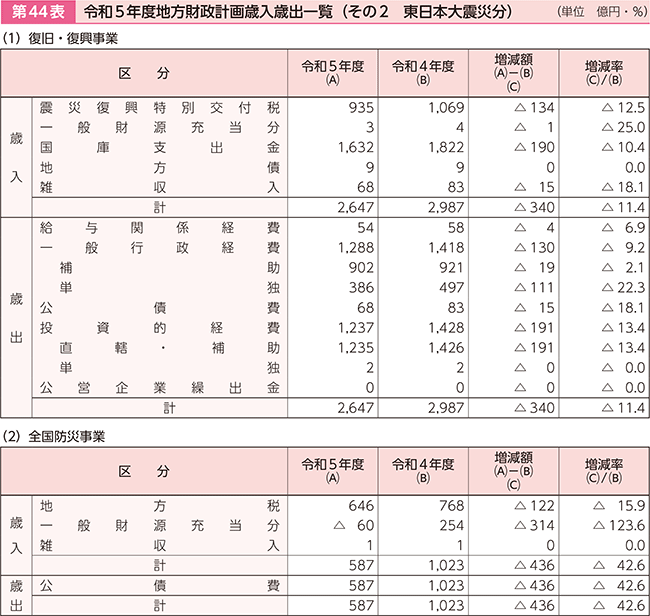第2部 令和5年度及び令和6年度の地方財政
1 令和5年度の地方財政
(1)地方財政計画
令和5年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、地域のデジタル化や脱炭素化の推進等に対応するために必要な経費を充実して計上するとともに、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととする。また、歳入面においては、「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和4年6月7日閣議決定)等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、令和4年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生じることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとする。
また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとする。
なお、地方財政審議会からは、令和4年5月25日に「活力ある持続可能な地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」及び同年12月9日に「今後目指すべき地方財政の姿と令和5年度の地方財政への対応等についての意見」が提出された。
以上を踏まえ、次の方針に基づき令和5年度の地方財政計画を策定している。
ア 通常収支分
(ア)地方税制については、令和5年度地方税制改正では、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直し、航空機燃料譲与税の譲与割合の特例措置の見直し等の税制上の措置を講じることとしている。
(イ)地方財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとし、所要の法律改正を行う。
a 「地方交付税法」(昭和25年法律第211号)第6条の3第2項に基づく制度改正として、令和5年度から令和7年度までの間は、令和4年度までと同様、財源不足が建設地方債(財源対策債)の増発等によってもなお残る場合には、この残余を国と地方が折半して補填することとし、国負担分については、国の一般会計からの加算により、地方負担分については、地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)により補填措置を講じる。臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入する。
b 令和5年度の地方財源不足見込額1兆9,900億円については、上記の考え方に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。
(a)建設地方債(財源対策債)を7,600億円増発する。
(b)地方交付税については、国の一般会計加算(地方交付税法附則第4条の2第1項の加算)により154億円増額する。
また、交付税特別会計剰余金1,200億円を活用するとともに、「地方公共団体金融機構法」(平成19年法律第64号)附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金1,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。
(c)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を9,946億円発行する。
c 交付税特別会計借入金の償還については、令和3年度の償還計画の見直しに伴い償還を繰り延べたものの一部8,000億円を増額し、1兆3,000億円の償還を実施する。
d 上記の結果、令和5年度の地方交付税については、18兆3,611億円(前年度比3,073億円、1.7%増)を確保する。
(ウ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化及び地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。
この結果、地方債計画(*)(通常収支分)の規模は、9兆4,981億円(普通会計分6兆8,163億円、公営企業会計等分2兆6,818億円)とする。
(エ)地域のデジタル化や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、地域の脱炭素化の推進、住民に身近な社会資本の整備、社会保障施策の充実、地方公共団体の施設の光熱費高騰への対応、消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進、過疎地域の持続的発展等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。
a 「地域デジタル社会推進費」については、マイナンバーカード利活用特別分として500億円増額し、2,500億円を計上する。また、「まち・ひと・しごと創生事業費」については、「地方創生推進費」に名称変更し、引き続き1兆円(前年度同額)計上した上で、これと「地域デジタル社会推進費」を内訳として、「デジタル田園都市国家構想事業費」を1兆2,500億円計上する。
b 「地域社会再生事業費」については、引き続き4,200億円(前年度同額)を計上する。
c 投資的経費に係る地方単独事業費については、地方公共団体が、地域脱炭素の取組を計画的に実施できるよう、新たに「脱炭素化推進事業費」を1,000億円計上することとし、全体で前年度同額を計上し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。
d 「人づくり革命」として、幼児教育・保育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
e 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。
f 一般行政経費(*)に係る地方単独事業費については、社会保障関係費の増加や地方公共団体の施設の光熱費高騰に伴う経費の増加等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。
g 消防力の充実、防災・減災、国土強靱化の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。
h 過疎地域の持続的発展のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。
(オ)公営企業(公営企業型地方独立行政法人を含む。以下同じ。)の経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。
(カ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、行政のデジタル化、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。
イ 東日本大震災分
(ア)復旧・復興事業
a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため、935億円を確保する。また、一般財源充当分として3億円を計上する。
b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。
この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は、13億円(普通会計分9億円、公営企業会計等分4億円)とする。
c 直轄事業負担金及び補助事業費、「地方自治法」(昭和22年法律第67号)に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費並びに地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出等について所要の事業費2,647億円を計上する。
(イ)全国防災事業
全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として646億円を計上するとともに、一般財源充当分として60億円を減額計上する。
以上のような方針に基づいて策定した令和5年度の地方財政計画は、第44表のとおりとなっており、その規模は、通常収支分は92兆350億円で、前年度と比べると1兆4,432億円増(1.6%増)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が2,647億円で、前年度と比べると340億円減(11.4%減)、全国防災事業が587億円で、前年度と比べると436億円減(42.6%減)となっている。
また、令和5年度の地方債計画の規模は、通常収支分が9兆4,981億円で、前年度と比べると6,818億円減(6.7%減)となっている。東日本大震災分は、復旧・復興事業が13億円で、前年度と比べると2億円減(13.3%減)となっている。
(2)令和5年度補正予算及び一般会計予備費の使用
ア 令和5年度補正予算(第1号)とそれに伴う財政措置等
(ア)令和5年度補正予算(第1号)
令和5年度補正予算(第1号)は、令和5年11月10日に閣議決定、同年11月20日に第212回臨時国会に提出され、同年11月29日に成立した。
この補正予算においては、歳出面で、物価高から国民生活を守る2兆7,363億円、地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する1兆3,303億円、成長力の強化・高度化に資する国内投資を促進する3兆4,375億円、人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を起動・推進する1兆3,403億円、国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心を確保する4兆2,827億円、地方交付税交付金7,820億円等が追加計上されたほか、既定経費の減額3兆5,098億円の修正減少額が計上された。また、歳入面で、税収1,710億円、税外収入7,621億円、前年度剰余金受入3兆3,911億円、公債金8兆8,750億円(建設公債2兆5,100億円及び特例公債6兆3,650億円)が追加計上された。
この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和5年度当初予算に対し、13兆1,992億円増加し、127兆5,804億円となった。
(イ)令和5年度補正予算(第1号)に係る財政措置等
この補正予算においては、国税収入の決算等に伴い地方交付税が増額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じること等から、以下のとおり措置を講じることとした。
a 地方交付税
この補正予算において、地方交付税法第6条第2項の規定に基づき増額される令和5年度分の地方交付税の額は、8,584億円(令和4年度国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額8,230億円及び令和5年度国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額354億円)である。また、令和5年度当初に行うこととしていた交付税特別会計借入金の償還については、当該償還予定額のうち3,000億円の償還を繰り延べるとともに、当該額を令和5年度当初の地方交付税の総額に加算することとし、これらの合算額1兆1,584億円については、以下のとおり措置する。
(a)以下のとおり、5,741億円を令和5年度の地方交付税総額に加算して増額交付する措置を講じる。
<1> 普通交付税の調整額を復活するとともに、国の補正予算における歳出の追加に伴う地方負担及び地方公務員の給与改定を実施する場合に必要となる経費の一部を措置するため、令和5年度の地方交付税を2,591億円(普通交付税2,436億円及び特別交付税155億円)増額交付する。
この普通交付税の増額交付に対応して、令和5年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時経済対策費」を創設するとともに、調整額を復活する。
<2> 令和6年度及び令和7年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費の財源を措置するため、令和5年度の普通交付税を3,000億円増額交付する。
これに対応して、令和5年度に限り、基準財政需要額の費目に「臨時財政対策債償還基金費」を創設する。
なお、「臨時財政対策債償還基金費」の算定額については、令和6年度及び令和7年度の「臨時財政対策債償還費」からそれぞれ当該算定額の2分の1に相当する額を控除する。
<3> 本年度の災害等の状況にかんがみ、上記<1>の155億円に加えて、令和5年度の特別交付税の総額に150億円加算する。
<4> 上記<1><2>に伴い、普通交付税の再算定を行う。
(b)令和5年度地方財政計画において「地域デジタル社会推進費」を計上するために活用することとしていた令和5年度の地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金1,000億円について、その活用時期を見直す。
(c)残余の額4,843億円については、令和6年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付する措置を講じる。
以上の措置を講じるため、「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」を第212回臨時国会に提出し、令和5年11月29日に成立した(令和5年法律第83号)。
b 追加の財政需要
この補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対しては以下のとおり財政措置を講じる。
(a)この補正予算により令和5年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担については、原則として、その100%まで地方債を充当できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の50%(当初における地方負担額に対する算入率が50%を超えるものについては、当初の算入率)を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
<1> 災害復旧事業債
I 補助災害復旧事業債
補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
II 災害対策債
(I)なりわい再建支援事業(地方公共団体が補助する経費の2/3を国が補助する場合)に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
(II)災害廃棄物処理事業については、地方負担額の80%を特別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、災害対策債の後年度における元利償還金の57%を特別交付税により措置する。
III 一般単独災害復旧事業債
一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、その47.5%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
IV 地方公営企業災害復旧事業債
地方公営企業災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、一般会計からの繰出額に応じ、その最大50%までを特別交付税により措置する。
<2> 公営企業債
当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様の方式により措置する。
<3> 一般事業債
災害援護貸付金について、資金手当として一般事業債を充当できることとする。
(b)この補正予算により令和5年度に追加されることとなる地方債の対象とならない経費については、以下のとおり財政措置を講じる。
<1> 感染症医療費負担金事業に係る地方負担については、令和4年度から繰り越された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国庫補助事業等の地方負担分)の算定対象とする。
<2> 上記<1>以外の事業に係る地方負担については、上記a(a)の地方交付税の増額交付等の中で対応する。
c 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増額等
この補正予算においては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を1兆5,592億円(うち低所得世帯支援枠分1兆592億円、推奨事業メニュー分5,000億円)増額することとされた。
このほか、全額国費により、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増額(6,143億円(医療分))、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施(887億円)等に係る事業を計上することとされた。
(ウ)地方公務員の給与改定
令和5年の国家公務員の給与改定については、国の給与関係法の公布及び施行(令和5年11月24日)に伴い、その取扱いが決定されたが、地方公務員の給与改定については、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応されるよう、また「常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いについて」(令和5年5月2日付け総務省自治行政局公務員部給与能率推進室長通知)を踏まえ、常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与について、改定の実施時期を含め、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とし、適切に対処されるよう、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和5年10月20日付け総務副大臣通知)で通知した。
なお、当該給与改定に係る一般財源所要額については、地方財政計画上の追加財政需要額(4,200億円)及び上記(イ)a(a)の地方交付税の増額交付の中で対応することとした。
イ 令和5年度一般会計予備費の使用とそれに伴う財政措置
(ア)予備費の使用
令和5年度一般会計予備費について、令和6年1月26日に1,534億円の使用が閣議決定された。
(イ)予備費の使用に係る財政措置
この予備費使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対しては以下のとおり財政措置を講じることとした。
a この予備費の使用により令和5年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担額については、原則として、その100%まで地方債充当できることとし、後年度においてその元利償還金について以下のとおり地方交付税により措置する。
(a) 災害復旧事業債
<1> 補助災害復旧事業債
補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
<2> 災害対策債
I 令和6年能登半島地震により「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)が適用された石川県並びに被災者生活再建支援法及び「災害救助法」(昭和22年法律第118号)が適用された市町村は、「災害対策基本法施行令」(昭和37年政令第288号)第43条第3項に基づき災害対策債を発行できることとする。
II なりわい再建支援事業(地方公共団体が補助する経費の2/3を国が補助する場合)及び災害廃棄物処理事業に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
III 災害救助費(特別交付税措置を講じた残余の地方負担額に限る。)に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その57%を特別交付税により措置する。
<3> 一般単独災害復旧事業債
一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、その47.5%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
(b) 補正予算債
<1> 災害関連事業
補正予算債を充当できることとし、後年度における元利償還金の80%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。
<2> 災害援護貸付金
資金手当として補正予算債を充当できることとする。
b この一般会計予備費の使用により令和5年度に追加されることとなる地方債の対象とならない経費については、以下のとおり財政措置を講じる。
(a)なりわい再建支援事業
地方公共団体が補助する経費の2/3を国が補助する場合、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。
なお、地方公共団体が事業者負担に対して総事業費の3/4以内で補助する経費の1/2を国が補助する場合、地方負担額の70%を特別交付税により措置する。
(b)災害廃棄物処理事業
災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。
(c)災害救助費
災害救助費に要する経費の40%(地方負担額を限度)に対して、特別交付税により措置する。
(d)その他
上記(a)〜(c)以外の事業に係る地方負担については、所要の特別交付税措置を講じるほか、地方公共団体が行う公共施設又は公用施設の整備事業等について、当該事業に係る通常の地方債に加え、当該地方負担の額の範囲内で地方債を充当することが可能な額を対象として、資金手当として補正予算債を充当できることとする。
(ウ)地方税等の減収に係る財政措置
歳入欠かん債の発行要件を満たす地方公共団体(上記(イ)a(a)<2>Iと同様)においては、令和6年能登半島地震に伴う地方税等の減免による減収額について、その100%まで歳入欠かん債を発行できることとし、後年度における元利償還金については、発行年度における標準税収入額に占める発行額の割合に応じ、その75%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとする。
(3)公営企業等に関する財政措置
ア 公営企業
(ア)通常収支分
公営企業については、上記(1)ア(オ)の公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金として、地方財政計画において2兆3,974億円(前年度2兆4,349億円)を計上する。
公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分2兆6,818億円(前年度2兆5,722億円)を計上する。
各事業における地方財政措置のうち主なものは、以下のとおりである。
a 公営企業会計の更なる適用の推進について、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業について、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行するなど、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費や、市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き地方財政措置を講じる。
b 水道事業については、多様な広域化を推進し、持続的な経営を確保するため、都道府県が実施する広域化の推進のための調査検討に要する経費について、新たに地方交付税措置を講じるとともに、広域化に伴う施設の整備費等について、引き続き地方財政措置を講じる。
c 下水道事業については、広域化・共同化を推進し、持続的な経営を確保するため、都道府県が実施する広域化・共同化の推進のための調査検討に要する経費について、新たに地方交付税措置を講じるとともに、広域化・共同化に伴う施設の整備費等について、事務を共同で処理する際に必要なシステム整備費を対象に追加した上で、引き続き地方財政措置を講じる。
d 病院事業については、公立病院等の経営強化を推進し、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・看護師等の確保の取組等の支援について、引き続き地方財政措置を講じる。
また、公立病院等の施設整備費に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を引き上げるとともに、令和3年度に講じた不採算地区病院等に対する特別交付税措置の拡充を令和5年度においても継続する。
(イ)東日本大震災分
公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において0.19億円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等分4億円を計上する。
イ 国民健康保険事業
国民健康保険事業については、厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、「国民健康保険法」(昭和33年法律第192号)第72条の2に基づき、一般会計から当該都道府県国保に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の9%分)については、その所要額(5,910億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)国保被保険者のうち低所得者に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県3/4、市町村1/4)を負担することとし、その所要額(4,271億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)国保被保険者のうち未就学児に係る保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(40億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)国保被保険者のうち子育て世代の負担軽減、次世代育成支援及び負担能力に応じた負担とする観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が産前産後期間の保険料免除相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(2億円)について地方交付税措置を講じる。
(オ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(1,344億円)について地方交付税措置を講じる。
(カ)高額医療費負担金(4,043億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、都道府県国保1/2)を負担することとし、地方負担(1,011億円)について地方交付税措置を講じる。
(キ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000億円)を講じる。
(ク)出産に直接要する費用や出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担の軽減を図るための出産育児一時金については、令和5年4月から50万円に引き上げられるとともに、引き続き市町村が一部(市町村2/3、市町村国保1/3)を負担することとし、地方負担(187億円)について地方交付税措置を講じる。
(ケ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40歳から74歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業(388億円)に対して、国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、都道府県国保1/3)を負担することとし、地方負担(129億円)について地方交付税措置を講じる。
ウ 後期高齢者医療事業
後期高齢者医療事業については、実施主体である後期高齢者医療広域連合の財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和(均等割2割・5割・7割軽減)を図るため、都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く。)が負担(都道府県3/4、市町村1/4)することとし、その所要額(3,545億円)について地方交付税措置を講じる。
(イ)高額医療費負担金(4,103億円)については、後期高齢者医療広域連合の拠出金に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、後期高齢者医療広域連合1/2)を負担することとし、地方負担(1,026億円)について地方交付税措置を講じる。
(ウ)財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金(201億円)に対して国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、後期高齢者医療広域連合1/3)を負担することとし、地方負担(67億円)について地方交付税措置を講じる。
(エ)後期高齢者医療広域連合に対する市町村分担金、市町村(一部事務組合等を除く。)の事務経費及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。