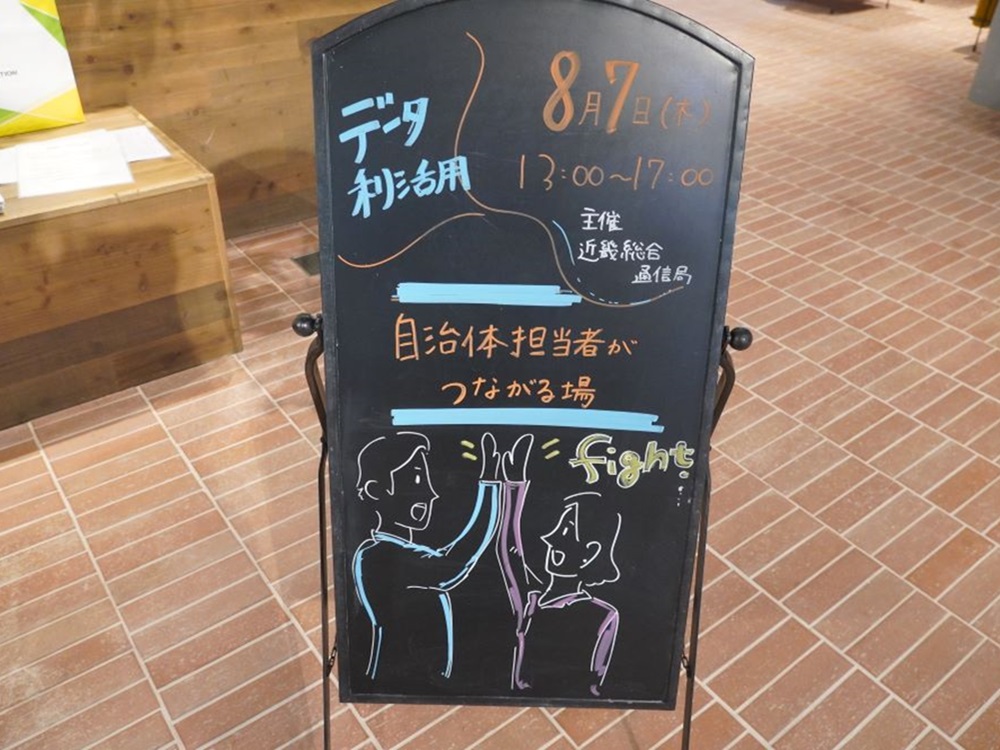近畿総合通信局は、2025年8月7日(木)、「データ利活用」をテーマとして「自治体担当者がつながる場」を大阪市内で開催し、現地・オンライン合わせて138名の方に参加いただきました。本イベントは、地方公共団体の職員がデジタルを活用して地域課題の解決を図る施策を進めるにあたり、継続して相談・情報共有等ができる関係性の構築を支援することを目的としています。第1部は講演、第2部は現地参加者と講師がグループに分かれて話し合う意見交換会を実施しました。
開催に先立ち、近畿総合通信局 武本情報通信部長が、「本イベントはまさに担当者がつながり、意見交換をする場であり、他地域の取組を参考にしつつ、活発な議論が展開されることを期待している。日々の業務の一助となり、今後の更なるご活躍の一端を担う機会となれば幸い。」と挨拶しました。

総務省統計局統計データ利活用センター 羽鳥 記章センター長から、EBPM(データなどの合理的根拠に基づく政策立案)の基本的な考え方から実践的な手法まで幅広く説明しました。特にEBPMを実践するための流れとして、PPDACサイクルを紹介するとともに、原因志向、仮説構築、調査計画策定、データの収集方針の立て方、政策効果の推定、結論の導き方など、実務に即したプロセスを丁寧に解説しました。

地域情報化アドバイザー 森 康通 氏から、これからデータ活用を始めたい方に向けて、国が公開しているオープンデータなど、すぐに利用可能なデータの紹介に加え、身近なところから取り組むためには、庁内で既に保有する数多くのデータの存在を知ることが大切であると言及されました。そして、どのようなデータを保有しているか把握するために、自部門におけるデータカタログを作成し、データ本体ではなくカタログを庁内に発信・共有すること、そこから、さらに庁内でのデータ利活用を検討するために、データカタログを公開レベルに応じて分類し、データの利用範囲を明確にすることが重要であるとお話いただきました。

宝塚市総務部業務改革推進課 吉川 達 氏、岡田 弘志 氏から、データ利活用に係る体制づくりとして、新しいアイデアや技術の獲得に熱心なイノベーターを巻き込んだ1年目の取組から、イノベーターに続く人材の発掘に挑戦された困難や苦労について具体的にご説明いただきました。また、持続可能なデータ利活用の推進には、問題解決の考え方を共有できる仲間づくりと、孤立させない仕組みが不可欠であるとお話いただきました。

第2部の意見交換会では、現地参加者と講師が複数のグループに分かれて情報交換を行いました。各グループでは、各団体が抱える共通の課題やその解決に向けた取組について、活発に意見が交わされました。
また、意見交換会終了後に名刺交換の時間を設けて、他グループの参加者とも交流していただきました。このようなネットワークの形成が、今後の情報共有や連携の促進に寄与することが期待されます。


近畿総合通信局では、今後も、地域課題の解決に向けてデジタル施策に取り組む地方公共団体を積極的に支援し、地域の皆様に寄り添った対応を継続してまいります。