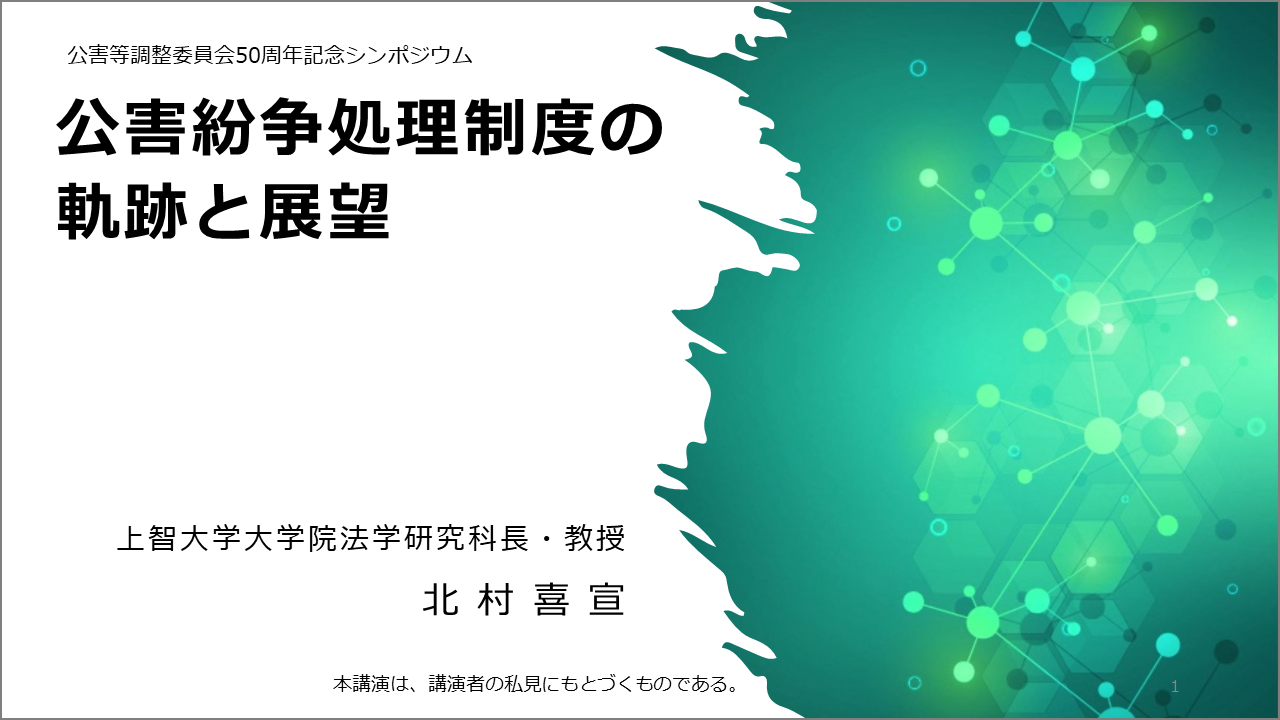【栗田奈央子(公害等調整委員会事務局次長)】
それでは、定刻になりましたので、ただいまから公害等調整委員会の設立50周年を記念したシンポジウムを開催いたします。
本日は、私、公害等調整委員会事務局次長の栗田が司会進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
それでは、まず、上智大学大学院法学研究科長・教授、北村喜宣様に基調講演をお願いいたします。北村様は、公害等調整委員会政策評価懇談会の構成員をお務めいただいています。基調講演のタイトルは「公害紛争処理制度の軌跡と展望」でございます。
それでは、北村様、よろしくお願いいたします。
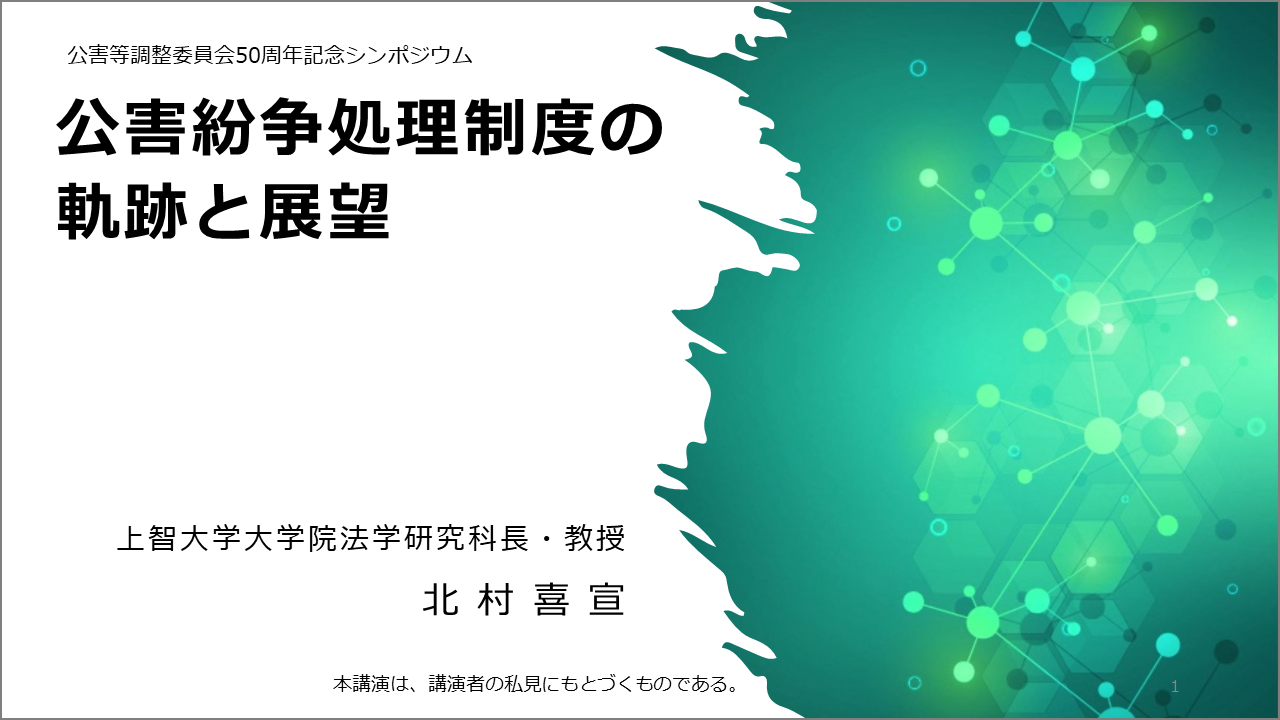
基調講演の資料はこちら[PDF 0.7MB]
【北村喜宣(上智大学大学院法学研究科長・教授)】
皆様、初めまして。上智大学大学院法学研究科長をしております北村喜宣と申します。専門は環境法学でして、本日はその観点からお話を申し上げるということになります。この50周年という記念すべき節目のときにお招きを頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。次のこういうイベントのときは恐らく75周年か100周年かでしょうから、そのときにまだ公調委が公調委であるのかということも含めて、私が今思っていることを皆様方にお伝えすることができればと考えております。
それでは、スライドに沿いましてお話を進めさせていただきます。まず最初のところ、少しこの組織の誕生の前史を振り返ってみましょう。ここに「三度目の正直」と書いておきました。実は、この公害紛争処理法、我々のこの組織の母法というものですけれども、実はすんなりとできたわけではありませんでした。このような仕組みをつくる、そのこと自体は1960年代の後半からしばしば中央政府において議論はされていました。そのときは、この紛争処理、苦情処理を担う主体は市町村を前提として考えられていたようなのです。なぜ地方だったのかというのは非常に興味深いところです。1つは、裁定という機能が全く想定されていなかったということでしょう。時折しも公害が深刻・激化していたときでした。1967年に公害対策基本法が制定されます。その21条1項で、政府に対して、公害に係る被害が生じた場合における和解の仲介、調停等の紛争処理制度を確立するため、必要な措置を講じなければならないと国会が命令したのが始まりでした。早速、中央公害対策審議会で検討がなされ、その結果、1968年に、公害に係る紛争の処理及び被害の救済の制度についての意見が出されました。その中で、簡易迅速に行政的解決を図るため、広範かつ実効性のある統一的な行政上の紛争処理制度を設けることが必要だということが提言されたのでした。公害に関するこうした紛争調整制度はあちこちにぽつぽつと散在してはいました。それをひとまとめにして、言わば横串を刺すような形で統一的な制度をつくり、国民の利用の便宜に供するということが認識されていた状況が伺われます。そうした国家的な合意があったのですけれども、この法律の案は、実は、第61回国会、第62回国会と上程はされますものの、廃案に至ったという若干気の毒な面があります。これは公害紛争処理法案の内容が悪かったのではなくて、政治日程の関係で可決・成立までたどり着かなかったということでした。しかしながら、諦めるわけではなく、再チャレンジ、再々チャレンジということで、第63回の国会において何とか成立、公布されたのです。この月に御注目ください。1970年の6月です。環境法研究者の中にも、この公害紛争処理法というのは第64回の臨時国会、いわゆる公害国会でできたのだというように何となく誤解していらっしゃる方が少なくありません。確かにそう誤解してしまいがちですね。重要な法律が改正、制定されたあの公害国会で恐らくはこの公害紛争処理法もできたはずだと思ってもしようがない面があるのですが、事実は1つ前の国会でできているということでした。
さあ、その63回国会でどういう議論がされたのか、少し議事録を見てみることにいたしましょう。ここで注目されるべきは、どういうものを対象に公害等調整委員会あるいは公害審査会、この組織が対応するのかということでした。こうした組織がないと、一般に私人間の紛争というのは、基本的に私人間で解決してくださいということになります。それがかなわなければ、裁判所に提訴してくださいということになるわけです。行政は非介入というのが基本スタンスですね。そうした中にあって、言わば法律に基づいて国家的に介入する。国家的にというのはやや大げさですけれども、中央政府が、あるいは地方政府が介入していくということになりますと、それを正当化するだけの正当性・公共性が必要になってまいります。勢い、その対象は限定せざるを得なくなってくる、これは当然のことのように見えます。そこで、しばしば言われているのでありますけれども、相隣的なものは公害の対象にしていないという答弁が繰り返しされました。それなりの社会的な広がりを持つもの、深刻化の度合いがあるもの、これを中心に公害概念を考えるということでした。この点については後で図でお示しすることにいたします。

実はこのときに、裁定制度を導入すべきであるという議論もされていました。ところが、この裁定制度の提案は野党がしたということもありまして、与党の受け入れるところにはならなかったのです。ですから、このときの答弁は、極めて裁定制度に対して冷淡です。そういうものはこの紛争処理制度の趣旨にはそぐわないのだと明言されています。調停制度を中心にやっていくのだということが言われていたのでした。当事者同士の話合いを旨とする、いわゆる互譲の精神という、我々が使っているこの制度の基本となる考え方が既にこのときに明言されていることが確認できます。この点、恐らく注意が必要なのは、互譲の精神と申しましても、一方当事者が明確に悪いと、他方当事者は被害者だけであるというところに、互譲というものは成立するはずがございません。それは極めて不正義です。この点は我々も十分に注意すべきであろうかというように考えているところです。
さあ、この制度制定後どのように展開したのかを少し見てまいりましょう。公害紛争処理法の「展開」です。歴史を振り返って実に印象的なのは、この制度は公布後、比較的短期間に数度の重大な改正を受けているということなのです。ここにお示しいたしておりますとおり、68回、72回というように、本当に、矢継ぎ早と言ってもいいほどの改正を受けています。大体こういう制度というのは、しばらくは転がしておいて、5年、10年で見直しというのがよくあるパターンなのですけれども、それを許さないような時代状況が少なくとも1970年当時にはあったのだということが推察されます。1970年のときには非常に政府は冷淡であった裁定制度についても、これを取り込む方向で議論が進められます。63回国会での附帯決議で裁定制度にかじを切るようなものが合意されたということを受けまして、68回の国会、これは公害等調整委員会の設置法ができた年でありますけれども、それによる公害紛争処理法の一部改正によって、既存の三条機関であった土地調整委員会と中央公害審査委員会の実質的な統合によりまして、この公害等調整委員会が誕生したのでした。裁定制度もここで整備されました。さらに、この公害紛争処理法が一部改正された結果、従来の和解の仲介制度があっせん制度に吸収され、調停手続も拡充されたというわけでして、現在の私どもが使っているこの制度の原形はこの1974年に整備されたという評価が可能であろうかと存じます。
さあ、制定から数年間の間に矢継ぎ早に改正を受けたこの法律ですが、その後は、客観的に申しましても、目立った改正を受けていません。改正自体は、ここに御覧いただくように、たくさんたくさんされております。しかしながら、私のような外部の者から見ますれば、この内容と申しますのは、いささか他律的事由を中心とする形式的あるいは手続的な改正が多く、実質的な内容の修正・変更を伴うものではなかったということです。黄色の吹き出しのところには、関係する法律に伴う改正も入れておきました。令和2年の地方分権一括法による改正まで含めますと、改正自体はたくさんされているのですが、実質的なところにまでは踏み込んでいないのです。これはもちろん、公害等調整委員会の事務方が改正を必要とするのかしないのかの御判断に大きく依存するところでございます。したくなかったからしなかったのか、したくてもできなかったのか、こればかりは我々外部から推しはかることはできませんけれども、国民に対しては、既存の法律で何とかやっていけるというようにお考えであったからだろうというように言えようかと思います。
50年の一つの節目として環境法研究者の観点からは指摘できると考えますのが、公害対策基本法から環境基本法へというように、そもそものこの公害紛争処理制度がよって立つ基盤となる法律が改正されたことです。基幹法の改正はやはり一つの大きな転機でありえただろうと私は考えております。後に紹介いたしますとおり、学会からも、あるいは弁護士会からも、この改正を重く見まして、それにアジャストするような対応をこの組織が取るべきではないかという提言もされています。副題に「超然とした水平移動」と書いておきました。公害対策基本法が1967年に制定されたとき、その目的には、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するというような、まさに当時における喫緊の課題への対応が宣明されておりました。そして、先ほども見ましたけれども、21条1項において、この公害紛争処理制度の根拠といいますか、こういう方向で制度化すべきだという国会の命令を確認できます。「公害」から「環境」に換わった、1993年が環境基本法の制定です。目的規定を御覧ください。現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の環境確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献するというように、射程距離が横にも時間的にも相当に広がったことが確認できますね。それを踏まえて、第2章の環境保全施策においては、健康保護、生活環境保全、自然環境保全、生物多様性確保というように、時の課題に対する対応の基本的な方針が明記されました。そうした中において、この公害紛争処理制度の根拠となる条文、これは21条1項から31条1項に変わったのですけれども、内容はどうでしょうか。主語が「政府は」から「国は」と換わっている点をまず確認できます。法令用語で「政府は」と言うと、まさに中央政府はということですが、「国は」と申しますと、三権全てを包含するというのが法令用語の使い方ですので、国会が自分自身に対して適切な措置を講じることも命じているという点をここでは確認しておきたいと考えます。にもかかわらず、やはり「公害」と書いてございまして、環境基本法2章の中においては、この31条1項と申しますのはやや浮いている感じがいたすところです。「環境の時代にまだ公害かい」というような言い方は、現に公害に苦しんでいらっしゃる患者さん、被害者の方にとっては非常に冷たい言い方に聞こえる面もございますけれども、そういう方々の救済はもちろん射程に入れつつも、現代的課題に対応すべく、この制度が進化するということもこの環境基本法の制定のメッセージであったというように一般的には受け止められています。
さて、その「公害」とは何かということを改めて考えてみましょう。環境基本法の多くの基本的な条文は、公害対策基本法の条文に影響を受けています。先ほど31条1項が浮いていると申しましたが、環境基本法の下で「公害」という文言を眺めていますと、やや据わりの悪さを感じるところでもあります。環境基本法における公害は、基本的に公害対策基本法の下での公害概念を引き継いでいます。これがそこの概念を図にしたものです。一番広くは環境保全上の支障なのですけれども、全てではなく、人為起源、人為活動起因の7事象というようになっています。しかし、それだけではございません。それだけだと先ほどの相隣関係が入ってきますので、これは国会答弁において明確に除いたということを確認しました。絞りの3つ目は相当範囲性です。相当範囲のということです。これが公害でして、公害に係る紛争というのはこの射程のものを言うわけです。紛争という局面では被害発生が要件ではないというのは、ここにいらっしゃる方は十分御存じのとおりです。おそれであってもこの制度としては受け止めるということになっている点は御案内のとおりです。ところが、概念として公害となってまいりますと、被害の発生というようにもう一絞り来るのでした。環境基本法の下では、基本的発想はやはり未然防止です。その中で、国は発生を防止するためにあれこれ対応するということですので、やや、その中にこの条文が入っているのは、据わりの悪さを感じるところです。場所的にはちょっと動かせばよかったかなと考えるのですが、このあたりは少し、いろいろな事情があったのかもしれません。
さあ、この公害紛争処理制度、ADRとして日本国が世界に紹介するに値する制度であるということは何回も指摘されています。私人間紛争への行政法的な介入をする制度です。制定以降どのように展開したのかを別の観点から振り返ってまいりましょう。冒頭、古典的な紛争モデルと申しました。私人間、とりわけ弱き私人と強き私人の間の紛争、かつ、これが重要ですけれども、当時は十分な行政法的な規制がなかったということです。もちろんその行為は、民事法的には不法行為というように、違法性をもって民事法的な責任が問われるものではありますけれども、少なくとも、行政法的にやってはいけなかったのかというと、そうではないことも少なくなかったのです。ここにいらっしゃる方は、水俣病の当時のチッソの行為が水質二法の下では特に問題なかったということは御承知であろうかと思います。しかし、このような、全面的に当事者主義に委ねることの不正義と行政法的な介入を正当化するための「社会的公共性」の存在、こういうものが次第に認識されるようになってまいります。
「相当範囲にわたる」ということで、近隣紛争のようなものは射程に入れないと宣明されていました。それにもかかわらず、運用の中でこれが徐々に緩和されてきているように見えます。いつからそうだったのかというのは難しゅうございますね。恐らく、見るところ、前例の積み重ねで概念それ自体が変容してきたと言えようかと考えます。令和2年度の年次報告においても、近隣店舗の室外機からの騒音や等々々ということで、比較的小規模な事件が目立つ傾向ということで、それに対しても公害紛争処理制度を活用した解決が求められることが多くなっているというような御認識をなさっております。そういうものはこの制度の射程外であるというような受け止め方にはなっていないという点も確認できます。
次のスライドで、違った点からも見てみましょう。裁定ということになってまいりますと、公害に係る被害ということになっておりますので、これが発生しているというのは、かなりの相当範囲要件性を満たしているなと思うところです。その裁定においても、令和2年度の年次報告に例を見れば、農業施設からの騒音だ、あるいは工事現場からの騒音だ、これの一定の範囲があるのか、あるいは近隣騒音にとどまるのかという線引きは難しいですが、そのあたりまで裁定の対象として取り上げられていることが確認できます。相当範囲というものに関しましては、例えば環境基本法の解説書において、汚染状況などが広範囲にわたっていれば、被害者は1人であってもこの法律においてはこれを公害と考えるのだと記されています。これは相当広範囲にわたっているということなのです。もう一つですが、行政として対応すべき事態に至っているかどうか等に関し問題の状況に応じて検討し、解決すべきだということで、ケース・バイ・ケースで考えていこうという柔軟な姿勢が環境基本法の所管官庁においても示されている点も確認できます。
ところで、こうした「柔軟な対応」はどのようなインパクトを及ぼすのかということを次のスライドで確認いたしとうございます。公害紛争処理制度に関する懇談会報告書が2015年にまとまっております。そこでも、相当範囲性、典型7公害以外の扱い、そして環境紛争という概念への対応ということについて試論が展開されておりますので、後に御参照くだされば幸いです。1970年の立法時には、「一方に片寄ることはいかぬとは思いますけれども、十分被害者の、そして弱いお立場を考えながら、事案の解決に運用上配慮してまいる」ということが担当大臣から宣明されている、まさに私どもの制度の基本認識と言えるものです。紛争の発生があればもちろん受けることができるわけですし、被害発生のおそれの具体的な立証があればよいのは当然でしょう。一方、やはり相隣関係の問題の除外する方針は、実は2002年の公害紛争処理法の解説においても維持されているのです。徐々に拡大して概念が変容したと先ほど申し上げましたけれども、根本としてはそうはなっていないのです。となりますと、こうしたものに関する申立てがあり、それに対して被申立人として対応を求められる人たちというのは、本来、制度の対象外の紛争なのに、それの付き合いを求められているという面がなきにしもあらずです。この点をどう考えるかは、法的には少なくともシリアスな問題かなと考えています。すなわち、自分は正当性のある制度の下で正当な申立てとして受け止められたものに相手をしているのかと。そうではなく、組織としてちょっと拡大した感じのところで相手をしているのかということです。もちろん事務方はそんなことを言うわけありませんので、そういう境界線を引かないでしょう。しかし、利用者の観点から、これは結構重要かなと考えるところです。
さあ、この仕組みの中の花形は調停であったというのは皆様方よく御存じのとおりですね。それは件数としてはかなり維持されています。都道府県の公害審査会の調停の新受件数、50年間で年平均32.7件で大体安定している傾向にあります。むしろ、昭和時代、平成時代を比べると、増加傾向にすらあるということがデータとして確認ができます。これをどう都道府県の委員会で受け止めていくのかというのは、恐らくは皆様方の大きな関心事であろうかと考えます。裁定に関しては需要が拡大しているというのも確認できるところですね。現在では中央委員会にしか権限がありませんので、これをどうするのかというのは、今後この制度の大きな議論のポイントと考えます。信頼性、権威のある決定と申しますのは、適切な手続からしか生まれないものです。そうした信頼できるもの、この制度、この手続だからしようがないよねというように納得していただける制度がつくれるのかというのは結構シリアスな問題です。それがゆえに、先ほど御紹介申し上げました2015年の報告書の中では、例えば手挙げ方式によって、その権限を都道府県の委員会が持つということの可能性も議論しております。また、都道府県の調停に当たって、原因裁定の嘱託を中央委員会が受けるとか、いろいろなことで裁定手続と調停手続の柔軟な利用というものを考えてみようではないかということも議論されています。

さて、先ほど手挙げ方式と申しました。実は、この言い方は、地方分権時代の現在、あるところに置かれている権限を違うところに移譲する、しかもそれは、押しつけではなく、自発的な意思決定によってすると、こういうのが一般化しつつあるのは御案内のとおりです。分権時代の公害紛争処理制度です。この事務、決して法律によって、やれというように命じられている事務ではないというのは、都道府県の関係者の方々はよく御存じのとおりです。もとより都道府県の審査会は任意設置です。自治体の公害苦情相談員も任意設置です。断る自由はあったのかという話になってきますと、なかなか難しゅうございますけれども、任意で設置されているという点は大きいと考えています。当時においても、1970年ですけれども、この法律の下での国の紛争処理機関と都道府県のそれとの関係は、いわゆる上・下の関係でやるものではなく、というような認識がされておる点も新鮮に映るところでございます。ただ、任意と言いつつ、この法律は、結構枠づけが強うございます。その辺は機関委任事務華やかなりし頃の法律として、その影響があるのかなという気がしないではありません。分権時代にはその手続についても、利用者の信頼性を損なうことなく、拡充する自由というのを都道府県の審査会に認めてもよろしいでしょう。恐らく公害審査会の利用状況については、ここに御参集の方々の都道府県において大きな違いがあるだろうと推測いたします。やはり自分たちの地域の利用者のニーズに合った制度にするというのが通常の発想だと思います。任意の制度なのですから、自分たちで変えていけるところは変えていく。デフォルトとして公害紛争処理法があるとしても、それは条例で自分たちに合わせていけばよいのです。ベストのモデルがあるわけでもありませんので、議論する時代になっています。「体を服に合わせる時代」から「服を体に合わせる時代」に変わっています。使い勝手をよくして、県民の福祉を向上させるという究極の目的のために何ができるのかということを、とりわけ職員の方にはお考えいただきたいということです。もちろん公調委への移送手続、事件移送がありますので、勝手なことをやって、あとはひとつよろしくというわけにはいきませんから、その辺の接合はきちんとしなくてはいけませんけれども、カスタマイズできるところはカスタマイズすることがあるのかなということです。
さて、この制度に対しては各界からの御要望も出ています。弁護士会から、学会からということで、幾つかの例を示しておきました。日本弁護士連合会は最近、公害紛争処理制度の改革を求める意見書をお出しになりました。環境紛争調整法に改称すべきだということをおっしゃっています。対象を公害だけでなく、環境への負荷に係る被害をめぐる紛争に拡大せよという主張もあります。かつて、この委員会の現職委員であった南博方教授は、現職の委員時代に、環境利益の調整の場として環境紛争処理制度を再構築すべき時期が来ているということを各所で再三にわたって御主張になっておられました。現在の環境法を代表する2つのテキストにおいて、越智教授、大塚教授それぞれが、自然環境、都市問題といったものに射程を広げるべきであるという主張をしておいでになります。どう考えるのかというのは、この組織にとっても非常に重たい課題であろうと認識しておりますし、後に述べますように、環境法学にとっても相当に重たい問題です。
例えば皆様方、国立市大学通りマンション事件を御存じでしょうか。最高裁判決が平成18年の3月にあったものです。その以前の昭和時代でありますけれども、伊達火力発電所事件がございまして、ここでは環境権というものが主張され、それに基づく対応が求められました。昭和55年の札幌地裁判決ですが、原告が主張するそのようなものは、訴訟において実現する、保護するにはふさわしくないのだということが明言されております。すぐれて、民主主義の機構を通して決定されるべきなのだ。要するに、司法判断にはなじまないというわけです。このような認識は、時代を下って、平成18年の国立事件最高裁判決にも継承されています。何が良好な景観なのかは、周辺の住民相互間や財産権者との間で見解の対立が生ずることも予想されるのであるから、第一次的には、民主的手続により定められた行政法規や当該地域の条例等によってされることが予定されている。対等当事者間の民事紛争で白黒の決着をつけるにはふさわしくない事案であるという認識なのです。
このような内容を持つ紛争を果たして受け止めることができるのかというのが問題になってまいります。紛争処理機関としての民主的な正統性という点に関わる問題です。なぜ裁判所は腰を引くのでしょうか。何が良い環境であるのか、何が良い景観であるのかに関して、裁判所は責任が持てないというわけです。民事訴訟においては、当然、どうしてはいけないのかというのがある程度示せるわけですけれども、そのよるべき規範が存在しないので、民主的機関で決めてくれとなっているわけです。もしもそれがあれば、行政は判断することも、あるいは可能でございましょう。広島地方裁判所が下した有名な差止め判決である鞆の浦世界遺産訴訟事件においては、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく広島県計画がありまして、そこでは、あの地域は保全するのだということが明言されていました。そうなりますと、環境公益と私が称するものを体現するルールの存在があった。これはやはり必要かなと感じるところです。こうした紛争は公害に関する紛争とは少々異なるものでして、少し範囲を拡大するというようにはなかなかいかないのではないかというのが私の認識です。被害者は誰なのかという点も大きくポイントになってくるところです。
ではどういうふうにすればよいのか。少し考えを進めてまいりましょう。この制度ができたのは、1つは、生命健康侵害事案を前提にしていて、裁判にのる事案であったからというのが前提にあるように見えます。もちろん、良好な環境を保全しようという意識を持って紛争の処理に当たっているとは当時の関係者の方もおっしゃっているところですが、やはり基本はそういう古典的なケースであったでしょう。何が良い自然環境か、何が良い都市環境かに関して、行政的な介入ができそうなこの環境の時代ではありますけれども、場当たり的な処理になってしまわないかという点も懸念されるところです。また、保護対象が明確な生命健康侵害事案であれば、今日おいでになっている騒音の専門家の先生が御活躍されるということもございましょうが、好みの問題、環境、景観というのは、なかなか難しゅうございましょう。国立判決の景観利益というのを認める要件として、客観的価値があること、近接に居住していること、日常的に享受していること、このような基準を満たす案件についてならば、あるいはそういうことも可能ではなかろうかとも考えるところです。
次のスライドに参りましょう。こういう認識を持てば、どのような制度設計が可能になるのかということです。先ほど申しましたとおり、環境公益というように、何らかの決定がされているものが望ましいとは考えるところです。その候補としては、例えば景観法に基づく景観計画でありますとか、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略ですとか、そういうものです。そういう法定計画あるいは条例に基づく計画で何事かの決定がされている、合意がされているというものであれば、何とかなるかなという気がいたします。裁定を前提にしませんので、三条機関である必要はございません。こうなれば、都道府県においても、公害審査会の改組によって、これを実現することは可能だというような気がいたします。現に自治体においては、環境オンブズマンというようなことを制度化しているところもありますし、あるいは現在でも、これを何とかしなさいということで、行政権限の発動に関しては、行政手続法に基づく「処分等の求め」ということも可能になっているところです。公害紛争処理法13条に基づく条例と対象を拡大した独立条例とを傘下に含む新たな総合的な環境紛争処理条例を構想することも、あるいは可能であろうかと思われます。
先を急ぎましょう。具体的な公法的な規制・規律がない行為、これに基づく環境紛争をどうするか、これが一番争点になろうかと考えます。環境に関する直接的な負荷が加わるのでございまして、必ずしも直接のインパクトが人間にはないというパターンです。法的に保護されるべき環境とそうでない環境の境界線をどうするのかということも難しゅうございます。なかなか「何でもあり」とはいかないだろうというようにも認識しておるところです。
さあ、最後のスライドで、そうした動きを受けたときに公調委は動けるのかということです。冒頭、50年後にこの組織はあるのかという不吉なことを申しましたけれども、その発展の方向性にも関わる話として収めたいと考えます。
公調委も難しゅうございます。制度を利用してくださいというように弁護士会には度々おっしゃるわけですが、弁護士会からは、ならば拡大しろと、射程を広げろと言われるわけでして、それはちょっと難しいということで、お互い動きが取れない状態になっておるわけです。現実的に政治的にこの仕組みを改正する風が吹くのか、吹いているのかというと、全く吹いていません。そうしたときに何事かを語るというのが非常に難しいのは行政的には十分に理解ができるところです。ですから、公害というものからの戦線非拡大以外の選択肢は当分はないのかなということですけれども、自治体における可能性は十分にあると私は認識しています。そこから言わばボトムアップで変えていくという戦略をつくるかどうかというのは1つあろうかということです。環境基本法の下では、将来世代、そして地球益というものも言われているところですね。これは実は環境法学にとっても、公害紛争と環境紛争の違いを深く考えるきっかけを与えているわけです。最近、オランダで、ドイツで、行政府や立法府に対して、CO2を減らせという判決が出ているのです。と申しますのも、現在世代、将来世代の健康に確実に影響を与えることだからという認識が前提にあります。日本のコートは保守的ですから、恐らくそういう判決は期待しようもない。何といっても公害というのは毒性物質に関わるものだと言うわけですので、ちょっと距離があり過ぎて茫然とするのですけれども、司法府は特にほかの国と競争していませんので、これはいいと言えばいいのですが、企業はどうでしょうか。国際的競争の下で資金調達をしている現在、ESG投資、SDGs金融というようなことが言われる。そうしたときに、一方当事者として、CO2を減らしてくださいと申立てがあったときに、冷たい態度を取っていれば、国際マーケットにおいてどのように見られるのかということも考える時代になってきそうです。そうしたときに調停の場における反論はどのように変わっていくのかというのは環境法学者としても非常に注目するところです。そうした時代の公害紛争、環境紛争の在り方というのは、環境法学の世界においても十分に検討すべき内容かなというようにも考えておるところです。
いささか駆け足になってしまいました。拙い報告で恐縮でございました。以上をもちまして、基調講演とさせていただきとう存じます。御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)
【栗田】 北村様、基調講演をありがとうございました。
次回の公害等調整委員会設立50周年記念シンポジウム「50年を迎える公害等調整委員会」(第2回)では、パネルディスカッションのテーマ(1):公害紛争処理制度の現状及び課題の紹介を予定しています。引き続きご覧ください。