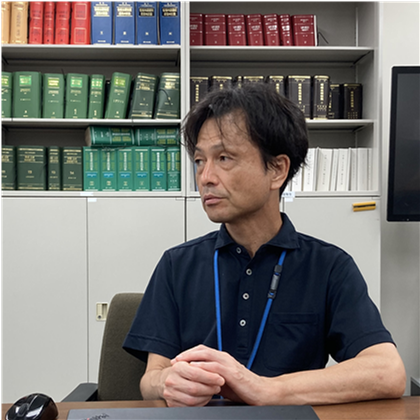(協力)
・上野 透 一般財団法人日本立地センター専務理事、元 公害等調整委員会事務局審査官
・加藤 剛 総務省大臣官房総務課管理室長、元 公害等調整委員会事務局総務課企画法規担当課長補佐、元 公害等調整委員会事務局審査官
(聞き手)
・橋本 隆介 公害等調整委員会事務局総務課課長補佐(広報担当)
〈令和5年6月30日実施〉
1.事件の紹介
◆橋本 本日は、機関誌「ちょうせい」の特集「国と地方公共団体との連携」に掲載するインタビュー記事作成のため、お集まりいただき誠にありがとうございます。
今回は、平成15年2月に東京都公害審査会より公害紛争処理法(以下「処理法」という。)第38条第1項に基づいて、公害等調整委員会が事件を引き継いだ調停事件について、当時在籍されていたお二方にお話を伺わせていただきます。
まずは、東京都地下鉄等騒音・振動被害防止調停申請事件(平成15年(調)第1号事件。以下、「地下鉄騒音事件」という。)について、その概要と処理経過について、私から紹介させていただきます。
【事件の概要】
平成13年2月27日、東京都にあるビルの区分所有者6人から、東京都及び鉄道会社を相手方(被申請人)として、東京都知事に対して調停を求める申請がありました。
被申請人らの運行する鉄道が申請人らのビルの地下を通過する際に引き起こす騒音・振動によって、申請人らは、不快感と不安を感じ、営業活動にも支障をきたしており、これらを理由として、申請人は、被申請人らに対し、鉄道の運行に伴う騒音・振動を軽減することを求めていました。
【事件の処理経過】
東京都公害審査会は、平成13年2月27日に本申請を受け付けた後、11回の調停期日を開催し、手続を進めましたが、全国的、広域的見地から解決を図ることが必要であると判断し、当事者の同意を得た上で、処理法第38条の規定に基づき、公害等調整委員会に対し事件の引継ぎについて協議を行った結果、公害等調整委員会は、東京都公害審査会の判断及び当事者の意向を踏まえ、平成15年3月10日、本事件を引き継ぎました。
公害等調整委員会は、本事件を引き継いだ後、直ちに調停委員会を設け、7回の調停期日を開催するとともに、平成15年6月5日、申請人らが主張する地下鉄駅舎の新設工事及びレール磨耗と騒音・振動との因果関係を判断するのに必要な専門的事項を調査するため、専門委員1人を選任したほか、現地調査及び騒音・振動の測定・分析調査を実施するなど、手続を進めて検討した結果、平成17年6月16日の第8回調停期日において調停が成立し、本事件は終結しました。
さて、お二方に事件についてお話しを伺う前に、自己紹介ということで、公害等調整委員会事務局に在籍されていた時のポストや業務内容について教えていただけますでしょうか。
◆上野 私は、経済産業省から出向して、平成15年から17年まで審査官として在籍しました。3年前に経済産業省を退職し、現在、一般財団法人日本立地センターに勤務しています。ここでは、都道府県や市町村、業界団体などに賛助会員になっていただいていて、地域の産業用地開発や企業誘致、地域産業振興の支援をさせていただいています。自治体での担当部署は商工担当部局ですけれども、環境に配慮した産業立地という点からは、公害審査会の業務にも関わりがあるものと思われ、今回の企画に参加させていただくことに縁を感じています。
公害等調整委員会在籍時は、今回取り上げる調停事件のほかに、地盤沈下、農薬による健康被害、工場騒音、悪臭被害などを担当しました。それから、米国の調停制度などの現地調査を行って、この「ちょうせい」にレポートを書いたこともありました。
◆加藤 私は、確か平成14年から2年ぐらいだったと思いますけれども、総務課の企画法規担当の課長補佐として在籍しておりまして、業務内容としては、事件の受付ですとかがメインになる仕事をさせていただきました。その後、ちょうど今から1年前までの3年間、審査官として再び公害等調整委員会で働くことになりまして、事件処理をやっておりました。現在は総務省の本省に戻りまして、大臣官房総務課の管理室長ということで、また違う業務をやっております。
この調停事件は、随分昔の話でありますけれども、こうして上野元審査官とお会いもできましたし、こういう機会を設けていただいて、大変ありがたいと思っております。
 上野 透 氏
上野 透 氏
2.事件の管轄と事件の引継ぎの制度について
【事件の管轄について】
◆橋本 今回取り上げる事件は、公害審査会の係属事件を公害等調整委員会が公害紛争処理法の規定に基づき引き継いだものです。事件の引継ぎの例としては、昭和62年に長野県知事から事件を引き継ぎ、昭和63年に調停が成立した「スパイクタイヤ粉じん被害等調停申請事件」などがありますが、 こういった制度があること自体、都道府県公害審査会の事務局職員の方にはご存じない方もいらっしゃるかもしれません。
まず、事件の管轄について基本的なことをご紹介させていただきます。処理法では、公害紛争を処理する機関として、国に公害等調整委員会が設置され、都道府県には都道府県公害審査会が設置されているところです。公害紛争の処理は、公害等調整委員会と都道府県公害審査会により分掌されており、両者は上下関係にはありません。
都道府県公害審査会は公害等調整委員会が管轄する紛争以外の紛争に係るあっせん、調停及び仲裁について管轄することとされていますが(処理法第24条第2項)、調停事件については、管轄の規定に対する例外として、相当と認める理由がある場合には、引継ぎ制度により、本来の管轄にかかわらず、都道府県公害審査会における係属事件を公害等調整委員会に引き継いだり、反対に公害等調整委員会における係属事件を都道府県公害審査会に引き継いだりすることができるようになっています(処理法第38条)。事件を引き継ぐ場合には、当事者の同意を得、かつ、引き継ごうとする先の機関と協議する必要があります。この事件の引継ぎの規定は、あっせん、仲裁に係る事件については置かれていません。
【事件の引継ぎについて】
◆橋本 加藤室長に事件の引継ぎ規定について伺いますが、処理法第38条第1項の「相当と認める理由」については、一般的にどういった場合を想定していると考えたらいいのでしょうか。
◆加藤 まず、処理法では、重大事件、広域処理事件及び県際事件を中央委員会(「公害等調整委員会」を指す。以下同じ。)の管轄、その他の事件を審査会等の管轄としています。しかし、それぞれの事件の実情を見ると、審査会等の事件の中にも中央委員会で処理した方が適当であると思われるものもあり、またその逆の場合もあると考えられます。例えば、形式的には中央委員会の管轄には当たらないが、実質的には人の健康又は生活環境に大きな影響を与える事件や全国的見地から解決する必要がある事件の場合が考えられます。また、逆の例としては、形式的には申請被害額が5億円以上であることから、中央委員会の管轄に当たるが、実質的には被害地域が1つの都道府県の区域内に限定されている事件などの場合が考えられます。これらの場合には、事件を引き継ぐことについて相当の理由があると認め得るものと考えます。
それから、審査会等に係属している事件において、都道府県自体が被申請人となっていることなどにより、当該審査会等に対する申請人の不信感が強い場合や、中央委員会に係属している事件において、費用面等から当事者が地元都道府県の審査会等において処理することを希望している場合などについても、事件を引き継ぐことについて相当の理由があると認める余地があるものと考えています。
いずれにしても、「相当と認める理由」については、当該調停事件を解決するためにはどの機関で処理することが最も適当であるかという視点から、それぞれの事件の実情に即して総合的に判断することが必要になると考えます。
以上の点は、コメンタールに掲載されていますが、公害審査会だけで判断できるものではないので、検討に際して悩まれることもあるのではないかと思います。そのようなときは、公害等調整委員会事務局に遠慮なくご相談いただくことも大事なように思います。幸い、コロナ禍を経てWeb会議が一般的になったので、遠隔地の公害審査会であっても容易に打合せができるようになったことですし。
なお、調停事件の引継ぎについては、「相当の理由」が必要になりますが、裁定事件は公害等調整委員会の専属管轄なので、公害審査会に係属中の調停事件について、公害等調整委員会に裁定申請することは可能です。私は実際に事件処理に当たる審査官としても公害等調整委員会に在籍しましたが、その際に、公害審査会に係属中の調停事件について、公害等調整委員会に原因裁定が申請された事件も担当しました。人事異動のため、事件終結まで携わることはできませんでしたが、因果関係について、職権調査とそれを踏まえた専門委員による科学的知見に基づく意見書を証拠として採用すること、つまり、専門委員の科学的知見に基づく見解を当事者双方に示すことが大きな契機となって、調停による解決が図られることは多数あるように思います。
公害等調整委員会の専門委員は首都圏在住の方が多いのが実情ですが、首都圏以外に在住されている方もいらっしゃることからも明らかなように、地方にも公害に関する科学的知見を有する専門家の方は多数いらっしゃいます。ですが、そういった専門家の方々の科学的知見を活かすためには、それ相応のデータを採取することが必要になるので、公害審査会の予算や人員・人材といった体制面でなかなか難しい面もあるのかもしれません。同様の事情は公害等調整委員会にもあるとは思いますが、「引継ぎ」以外の手法も含めて検討することも可能であり、そういった意味でも、遠慮なくご相談いただくことが大切ではないかと思います。
【地下鉄騒音事件の引継ぎについて】
◆橋本 平成15年2月、東京都より事件の引継ぎの協議がありました。事件の引継ぎを相当と認める理由は、どのような内容だったのでしょうか。
◆加藤 この事件は、地下鉄道の真上にあるビルの所有者が、この地下鉄道のさらに下に建設された地下鉄道の構築物工事の進捗に伴い、その上部を通過する地下鉄道の振動・騒音が悪化し被害が生じている、本件ビルの顧客、賃借人に多大な不快感と不安を与え、営業活動に著しい支障をきたしているとして、当該振動・騒音の低減を請求しているものでした。
事件の引継ぎを相当と認める理由ですが、東京都公害審査会からは「地下鉄道による振動・騒音については、全国の大都市において問題化しつつあるが、本事件においては、複数の地下構築物を伝播して地上の構築物に与える複合的影響が争点となっており、これに関しては、調査方法や対策が確立しておらず、全国的・広域的な見地から解決を図る必要があること」、そして当事者双方の同意があることが理由として挙げられていました。
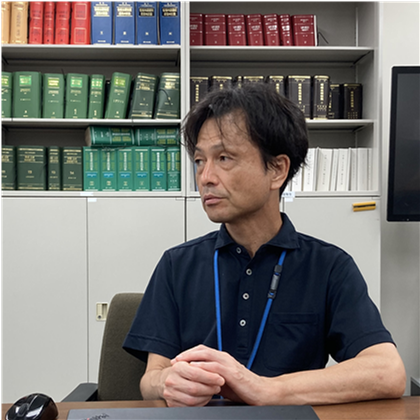 加藤 剛 氏
加藤 剛 氏
◆橋本 事件の引継ぎに当たっては、事務的に事前の連絡などはあったのでしょうか。
◆加藤 東京都公害審査会の事務局担当者から事件の引継ぎについて事前説明を受けたように記憶しております。また、その際には、東京都公害審査会の事件処理の実情をよく理解するために、事件の受付を担当している総務課だけでなく、実際に事件処理に当たり、騒音・振動の専門的知見などに通じている審査官も同席し、説明を伺ったように記憶しております。 事件の引継ぎを相当と認める理由については、事前説明を通じた東京都公害審査会と公害等調整委員会との間での共通認識の醸成を経て、東京都公害審査会において整理、検討の上、提出されたものと思います。
事前説明の場で、具体的にどのようなやりとりがあったかまでは覚えておりませんが、一般的には、まずは公害等調整委員会にご相談いただき、当該事件のこれまでの経緯や当事者の見解等について、都道府県公害審査会の事務局職員から説明をしてもらうということかと思います。
なお、これは公害等調整委員会側の問題ですが、公害審査会からの相談の段階で審査官が同席し、事件処理の実情を把握しておくことは、その後、事件を引き継いだ際にスピーディーに事件処理を進める上で有益ではないかと思います。引継ぎをスムーズに行うことは、当事者双方から信頼を得る上でも大切ではないかと思いますし。調停事件の引継ぎとは異なりますが、裁判所に係属中の事件について裁判所から原因裁定の嘱託を受ける原因裁定嘱託についても、同様のことがいえるのではないでしょうか。
3.東京都地下鉄騒音事件の調査について
◆橋本 続いて上野様にお伺いいたします。本事件は、平成15年3月に事件の引継ぎが決定され、その後、公害等調整委員会において、現地調査、測定技術検討会議、調査委託会社による現地の騒音・振動測定調査が行われ、計8回にわたる調停期日を経て、平成17年6月に調停が成立しました。
上野様は、事件の途中、第3回の期日(平成15年9月)から本事件をご担当されました。本事件では、平成16年3月に、4日間にわたって、現地での騒音測定が実施されました。測定に当たっては検討会の開催や事前測定も実施されています。本測定まで時間をかけて調整がなされていたことが伺われます。例のない大規模で複雑な騒音測定が実施されましたが、騒音測定の方針や進め方は、どなたが主導されたのでしょうか?
◆上野 私が来たときには既に、専門委員と測定を実施する調査会社は決まっていました。専門委員の石井聖光東大名誉教授は、建築音響工学と騒音制御工学の権威で、日本音響学会会長などもされた先生でした。この調停事件当時、80歳近かったと思いますが、大変お元気で、いろいろお世話になりました。今でも年賀状のやり取りをさせていただいています。この石井先生のご指導の下、調査会社の専門家と、厚生労働省から来られていた審査官と私とで、原因究明のために、どのような実験、測定、分析をしたらいいかということを当事者の意見も聞きつつ検討していきました。
◆橋本 調査の目的は何だったのでしょうか。
◆上野 本件では、申請人側のいるビルの直下に地下鉄道が通っていたのですが、その下に、新たな地下鉄道の構築物が設置されたことによって、もともとあった直下の地下鉄道の電車の通過による騒音・振動が耐えられないほど大きくなったということで、申請人側は、両地下鉄道側にその騒音・振動の軽減を求めました。しかし、新地下鉄道側は新設の構築物と騒音・振動増大とは関係ないとしていました。そこで、その新地下鉄道の構築物ができたことと、この騒音・振動増大との因果関係を分析することが調査の目的でした。
なお、騒音・振動が増大する直接の要因としては、直下の地下鉄道のレールにできる波状摩耗ということはわかっていました。申請人側のビルの直下の地下鉄道のレールが大きくカーブしているため、電車の通過が繰り返されるうちにレールに波状摩耗が点々と生じ、それによって電車の通過による騒音・振動が増大するのです。波状摩耗のあるレールを研磨して平滑にすると騒音が静かになるので、申請人側は、直接の要因である直下の地下鉄道のレールの研磨を地下鉄道側に求めていました。
◆橋本 具体的にどういった調査をされたのでしょうか。
 インタビューの様子
インタビューの様子
◆上野 まず、事前調査として、レールが平滑な時期に、申請人側のビル内で、電車の通過に伴う騒音・振動の測定をしました。その後、しばらくして、波状摩耗が出てきて騒音・振動も大きくなる頃に本調査をすることとしました。
本調査ですが、騒音・振動を発生させているビル直下の地下鉄道のトンネルの中に入り、終電の後、始発までの時間、保守に使用しているモーターカーを走行させて、トンネル内の3地点と、申請人のビル内で騒音・振動を測定するなどの大規模な実験を行いました。これには測定機器の設置準備、撤去を入れて4日間かかりました。トンネル内3地点のレールと壁面、それから申請人側のビル内に振動加速度ピックアップ、マイクロフォンを取り付けて、モーターカー走行時の騒音・振動を測定しました。上下線ともに3種類の速度で、モーターカーを行ったり来たりさせて調査を行いました。
専門委員の石井先生は、近くのホテルに宿泊され、真夜中の調査に立ち会っていただきました。トンネル内は暗く足元は不安定で、ご高齢の先生は大変だったと思うのですが、真相解明に熱心で目を輝かせながら、実験を確認しておられました。
◆橋本 こうした調査を経て、本事件では最終的に調停が成立しています。申請人らが求めていた鉄道の運行に伴う騒音・振動の軽減策について、申請人・被申請人ともに納得する形で決着することができた要因は何だったと思いますか。何かきっかけとなるようなことがあったのでしょうか。
◆上野 当初は当事者間で主張が異なる部分もありましたが、公害等調整委員会として出来る限りの調査を尽くした上で、調停委員が直接和解の方向性を各当事者に語りかけたことが、調停成立へ向かう大きな契機となったと思います。
また、調停で重要と言われる互譲の精神、本事件では三者いたわけですけれども、皆がその精神に基づいて行動していただいたということがあるのではないかと思います。
先ほどからお話をしていますとおり、権威ある専門家の知見を活用できたこと、公害等調整委員会の呼びかけのもと当事者が協力してこれだけの大規模な調査を実施することができたこと、こうした公害等調整委員会の業務におけるメリットが生かされたのではないかと思います。
◆橋本 最近は小規模な事件が増加する中で、大規模な調査を実施した本事件には、ほかの事件にはないご苦労もあったのではないでしょうか。本事件に関わる中で、大変だったことやご苦労されたことがあればお話しいただけますでしょうか。
◆上野 深夜、終電が終わってから未明にかけての調査を4日間やりましたけれども、夜出かけて朝帰る日が続き、家族はびっくりしていました。また、普通、人が入れない暗いトンネルの中に入ると、モーターカーも間近に通るものですから、少し怖かったですが、非日常的な貴重な経験ができたと思っています。
また、測定実験の後、非常に分厚い測定結果が調査会社から出てきたのですが、専門性が高く、それを分析するのはなかなか大変でした。厚生労働省出身の審査官と二人で騒音・振動の勉強をして、何回も石井先生、調査会社の専門家、審査官二人で集まって、何時間もかけて議論しながら、一般の人にも分かるように整理をしていきましたが、結構苦労しました。
4.おわりに
◆橋本 ありがとうございます。それでは最後に、各都道府県の公害審査会の事務局職員に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。
◆上野 専門委員の選定とか専門的な調査の実施、調停に当たっての当事者との調整についてはいろいろ悩ましいこともあると思います。そういったときに公害等調整委員会に相談して進めていくことが効果的な場合があると思います。それから、連絡協議会やブロック会議の場も生かしながら国と連携することも考えていただけるといいのではないかと思います。
私もこの「ちょうせい」の記事で、いろいろと自治体の方々が事件対応でご苦労されていることを拝見しています。様々なケース、事情があり、こうすればといいといった特効薬のようなものはなく、難しいところはあると思いますが、やはり、まず当事者の主張をよく聞くこと、当事者は色々なことを言われるとは思いますが、それらを傾聴した上で論点を整理していくことが必要です。そして、客観的な原因解明など行政側としてできることをやっていき、ファクトに基づいた解決策を提示し、当事者に納得していただくということではないでしょうか。それらの中で、当事者には真摯に対応して、信頼を得ていくということも調停においては不可欠と思います。
苦労の多いことと思いますが、地域のために大変重要な仕事ですので、頑張っていただければと思います。
◆橋本 ありがとうございます。それでは、インタビューを終了したいと思います。本日は貴重なお話を伺うことができました。上野様、加藤様、お忙しい中、本日はお時間をつくっていただきまして、誠にありがとうございました。
地方公共団体の皆様へ
都道府県公害審査会等の事件を公害等調整委員会に引き継ぐ方法として、今回のインタビュー記事でご紹介した事件の引継ぎ(公害紛争処理法第38条)に加えて、本年6月に開催した第53回公害紛争処理連絡協議会において、より簡易な運用として、当事者に公害等調整委員会への裁定申立を促す運用を提案させていただいています。
地域に一定の影響があり、紛争解決に公害等調整委員会の専門的リソースの活用が望まれる事案については、積極的に当事者に公害等調整委員会への裁定申立を促していただいて結構です。その際、都道府県公害審査会等で調停を打ち切る場合に限らず、事件を係属させたまま、公害等調整委員会で原因裁定を行い、その結果を利用して都道府県公害審査会等で調停を行うというバリェーションも考えられます。
公害等調整委員会としては、都道府県公害審査会等と連携して公害紛争処理制度の解決力を高めたいと考えており、都道府県公害審査会等の事務局との日頃からの意思疎通を一層図ってまいります。
公害等調整委員会事務局