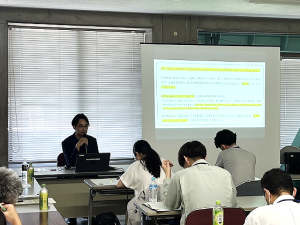�@���Q���k�́A���Q�Ɋւ�������ɔ��W����O�̒i�K�ʼn������邱�Ƃɂ��A���⑊�k�̐\���҂͂��Ƃ��A�n��Z���̌��N�Ɛ�������ێ�����Ƃ����ɂ߂ďd�v�Ȗ�����S���Ă��܂��B�܂��A���Q���k�́A���Q�����̊ȈՐv���ȉ�����ړI�Ƃ�����Q�����������x�̍L��Ȓ�ӂ��x����y��Ƃ��ċɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B
�@�啪���ł́A�ߘa6�N7��19���A�����̌��Q���k�����̐E���̉����͂̌����ړI�Ƃ��đ����E�U���E���L�����Q�����S���Ҍ��C����J�Â��܂����B���Q�������ψ�����ǂł́A�����C��Ɍ��Q�������ψ�����ǐE���y�ь��Q���k�A�h�o�C�U�[���u�t�Ƃ��Ĕh���v���܂����B
�@�{�L���ł́A�����C��̊T�v�ƂƂ��Ɍ��C��̈Ӌ`���Ɋւ�����Q���k�A�h�o�C�U�[�ւ̃C���^�r���[�̓��e�����Љ�����܂��B���C��̎�g�́A���Q���k�̓K�ȏ�������芪���l�X�ȉۑ����Q�R����Ǝs�����Ƃ̘A�g�ɓ������ĎQ�l�ɂȂ�ƍl���܂��B�{�L�����F�l�̍���̎�g�̎Q�l�ɂȂ�K���ł��B
�@���Q���k�A�h�o�C�U�[�̗����טa���i�啪�s��������ہ@�������j�ɂ����͂��������A�s���{����Â̌��C��̈Ӌ`���ɂ��āA�C���^�r���[���s���܂����B
�@��������@���Q�������ψ�����Ǒ����ۉے��⍲�i�L��S���j�@���{�@����
�y����܂ł̌o���z
�i���Q�������ψ�����Ǒ����ۉے��⍲�i�L��S���j�@���{�i�ȉ��A���{�j�j�܂��́A���S���E���Q���k�S���̂��o���ɂ��āA�����Ă��������܂��ł��傤���B
�i���Q���k�A�h�o�C�U�[�@�������i�ȉ��A�����A�h�o�C�U�[�j�j�A�E�����琅�����Ɋւ�肽���ƍl���Ă��܂����B�啪�s�̗p��ɔz�����ꂽ�̂́A���A������ł����B�����ʂ萅�����̓��X�ł��������Ƃ��L�����Ă��܂��B�������Z�p�������6�N�w��A�H��̑�C�����␅�������Ȃǂ̌��Q��s����21�N�Ԍg���A�K�������ƕ��s���đ��l�Ȍ��Q���̏����ɂ��ւ���Ă��܂����B
�i���{�j���S���z����A���Q���k�̑Ή��́A��ς������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�����ł��ˁB���������߂Čo���������́A�ꂢ�v���o����ł��B�s���ƐڐG����@��̂Ȃ������E���������Ȃ���̌���ŃR�~���j�P�[�V�����͂�������A�m���s����ւ��l�̐S�̈����ǂ߂��ɒp�����������炢�Y���Ƃ��o���Ă��܂��B �ސE���čĔC�p�E���ƂȂ��Ĉȍ~�A���ł��Ⴂ�E���ƌ���ŋ����Ɋւ���Ă��܂����A�K�X�A����̓W�J������V�i���I�̑z��Ȃǂ��A�h�o�C�X���Ă��܂��B���̂悤�Ȏ��A�ӂƎႢ�E���ȏ�ɂ��Ă̖��n�ŗ��������̂Ȃ��������g�̂��Ƃ��v���o�����Ƃ�����܂��B
�i���{�j�����āA����܂ł��Ή����ꂽ����̒��ŁA���Ɉ�ۂɎc���Ă��鎖��ɂ��ċ����Ă��������܂����B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�ʂ̎���̒��ł��A���ЁA���b���������w�r�[�Ȃ��̂�����܂����A���`��������܂��̂ōT���܂�(��)�B�����A�w�r�[�Ȃ��̂قǁA����̐�y�⓯�����ւ���Ă���ď����Ă���܂����B�ւ���Ă��ꂽ���ɑ��ẮA���ł����ӂ��Ă��܂��B����͋����͂��Ƃ�肠����ۑ�ɋ��ʂ�����̂ł͂���܂����A“�����҂���l�ɂ��Ȃ�”�Ƃ������Ƃ́A��Ȏd�g�݂��Ǝv���܂��B�����łȂ��Ă��ŋ߂̋���́A�K���ɂȂ��܂Ȃ�������A�\�}�����G�ł�������A���Ԃ�����������ƁA�S�̕��S���傫���킯�ł�����A����ɗ��邱�Ƃ͌����Ēp�����������Ƃł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�i���{�j�����ł��ˁB�������g�̌o����U��Ԃ��Ă݂Ă��A��i�⓯���Ɍb�܂�Ă���ƁA���Ƃ��撣�낤�ƁA����Ă���ꂽ�悤�Ɏv���܂��B���Q���k���܂ފ��s���ɂ����Ă��X�̎��ĂɊւ��āA�g�D�I�ɑΉ����镵�͋C���E��ɂ��邱�Ƃ��厖�ł���ˁB����ɂ́A��i���g���Z���̊F�l�Ɛڂ���E���̐S���I���S�𗝉����āA�ӎ��I�ɑg�D�������邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���̎d����ʂ��āA�C�t�������Ƃɂ��ċ����Ă��������܂����B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�w���Ƃ́A����������܂��B���̈�ɁA�����ł́A�ƂĂ���ςȂ��ƁA���̏u�Ԃ͔����ǂ���Ȃ��ƁA�ƂĂ��J�T�Ȃ��Ƃɏ��荇���܂����A�����Č��Ă݂�ƁA���N��A��N��Ɂu���̂炢�o���͈�̉��������낤���v�Ǝv�����Ƃ���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�@������́A����͎��ŗL�̂��̂�������܂��A����ȋ����̒��ł͂��̏u�Ԃ͐\���l�⌴���҂̕��ɑ��āA�l�K�e�B�u�ȐS���������Ƃ����邩������܂��A��X�̎d���̒��ŐU��Ԃ��Ă݂�ƁA���̕��X���獡�̎��g�̔��z�͂�_�͂���ĂĂ�������Ǝv���N�������Ⴊ����܂��B���X�̐h���l�X�Ȃ��Ƃ́A�ڐ���ς���Ύ���̗ƂɂȂ�Ƃ������Ƃł��傤���B
�y�m���E�Z�p�̊w�ѕ��z
�i���{�j���́A���Q���������@�ւł��萧�x�̒����ψ���Ƃ��Ēn�������c�̂Ƃ̘A�g���}���Ă�����Q�������ψ�����ǂɈٓ�����2�N�ڂɂȂ�܂����B���̈�N�A���Q���k�A�h�o�C�U�[�̊F�l�A�����Ď����̐E���̊F�l�̂��b���f���Ċ��������Ƃ́A�d���̐i�ߕ��A�����Ƃ������̂ɗB��̐����͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�m���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��m����Z�p�͂������܂��B�����A������ǂ��g���āA���Ă��ƂɈقȂ�Z���⎖�Ǝ҂ƑΉ�����̂��́A���s��������Ȃ���A�܂��ߋ��̎���⓯���Ƒ��k���Ȃ�����g�ނ����Ȃ��B�l�����邱�Ƃ���肫������ŁA�悢���ʂɂȂ�����ł����A�[�����Ă��炦�Ȃ����Ƃ����X����Ƃ������Ƃł��B�P�[�X�E�o�C�E�P�[�X�̑Ή��ŁA�F�l�{���ɂ���J����Ă���Ɗ����܂����B
�@�����ŁA���f���������̂ł����A���Q���k�̑Ή��Ɋւ��āA������“�^”�A�d���������ŕK�v�ƂȂ�y��Â���Ɋւ��āA�E���͂ǂ̂悤�Ɏ��g��悢�Ƃ��l���ł��傤���H
�i�����A�h�o�C�U�[�j�������ق��̎����Ɠ��l�ɁA��{�ƂȂ鏈���菇������܂��B���͐E��ŐV�l���C�̍ۂɂ͍��q�w���Q���k�̎�����x
1 ���g���Ă��܂��B�c�O�Ȃ��獡�͔p�łƂȂ��Ă��܂��B�����ςʼn��炩�̍H�v�����Ă��������A�����̌���Ŏs�����E�����o�C�u���Ƃ��ĕ��ՂɊ��p�ł���悤�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B������ɂ́A���̎A���꒲���A�\���l�⌴���҂Ƃ̐ڐG�A���҂̈ӌ��̂��荇�킹�A��̎��{�Ƃ��̌�̊m�F�ȂǁA���ꂼ��̗v�_���Љ��Ă��܂��B���̗v�_���ӎ������ۂ̋�����OJT��ςݏd�˂Ă����B���܂������Ȃ����Ƃ�����܂����A�ǂ̂悤�Ȍo�����ƂɂȂ�܂��̂ŁAPDCA�ō��݂�ڎw�����Ƃ��悢�Ǝv���܂��B
�@������x�̌o����ς��́A�����̒�ԏ����ł����̂��A�Ⴆ�ΎO�ҋ��c�̂����ɂ�����H�v���邱�Ƃ����ǂ�������ɂȂ���̂ł͂ȂǁA�������̎��s���낪����Ǝv���܂��B��X���悭��炳��Ă��鎖�����P�Ɠ����ł�(��)�B�����āA��y�ւ̏�����ӗ~�I�Ȑl�ވ琬�́u�?(�S�\����Z�p�̓`��)�͐l�̂��߂Ȃ炸�v���Ǝv���Ă��܂��B
�y�g�D�̊��̕ω��z
�i���{�j�m���ƋZ�p�A���ꂩ�猻��o���B���ꂼ����D��S�������Čp�����Ċw�Ԃ��ƁB�����Ċw�ё����钆�ŁA���g�̍l����s�����_��ɕς��Ă������Ƃ��厖�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B����ŁA�g�D�̐��̃X��������Ɩ��̑��l���ɂ��A���̑��̋Ɩ��Ɋ������Ԃ������Ă���A�E���͊w�Ԏ��Ԃ��Ȃ��Ƃ�����������������܂��B
�@��������k�̌������̂��傫�����邱�Ƃ͍l�����܂��A�Z������͎��̗ǂ��s���T�[�r�X�̒����߂��܂��B�S���̌��Q���k�����ł́A�\�͂������グ�邱�ƁA�w�Ԃ��ƂɊւ��āA�ۑ�������Ă���Ƃ���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̂����肢�����ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�m���ɑS���̌��Q���̏�����S�������1.1���l�̐E���́A���Q�W�@�߂̎{�s�̂ق��A�����̂ɂ���Ă͉ƒ낲�݂Ȃǂ̔p�����A���������A��������A��n�ȂǁA���l�Ȏ�������Ƃ��Ă���킯�ł����A��������A��������A�ꍇ�ɂ���Ă͂��̎d���𒆒f���āA�����ɂ��̏����ɏo�����ȂǁA�����Ƃ��������̗D��x�͍��������Ɗ����Ă��܂��B����������{���̒S�������ƕ��s���Ȃ�������ɂ��Ă�����̒m���𑝂₵�A�X�L�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���������Ԃ̂Ȃ����ł̂���J�́A�ƂĂ���ς��낤�Ǝv���Ă��܂��B
�y���k�Ή��̎p���z
�i���{�j�ߋ��̎���A���̎����̂̎��Ⴉ��w�Ԃ��Ƃ���������ŁA���܂��ɕ����Ă��鎖�ĂƂ����̂́A�����҂��Ⴆ�A���Ⴄ�B�����đΉ�����E�����g�̌o����i���Ⴄ�̂ŁA���̎���ƑS�������悤�ɑΉ��ł��邱�Ƃ͂܂��Ȃ��Ǝv���܂��B�����A�Ή�����Ƃ��̎p���Ƃ������A�S�\���ɂ��ẮA���ʂ��镔��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�E���ɑ��ăA�h�o�C�X���Ă��邱�ƂȂǂ���܂�����A�����Ă��������܂��ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�s���E���́A���܂育���g�Ɏ��o�͂Ȃ��Ǝv���܂����A�Љ�̒��ł͐ӔC���̋������̏W�c�̂悤�ȋC�����܂��B�s���ȂǑS�̂ւ̂��ǂ���d�҂Ƃ��āA���̎p���͂������厖�Ȃ��Ƃł����A�����ł͂������đ傫�ȕ��S�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�������̗͂������悢�̂�������܂���B
�@��قǂ��\���グ�܂������A���l�ȍs�������̒��ł������́A��l�ŕ������ސ����̂��̂ł͂Ȃ��A�݂�ȂŎ~�߁A�m�b���o�������A�Ƃ��ɍs�����鋤����ƂȂƍl���邱�Ƃ���ł��B�����̎葱�����~���ɐi�݁A�����đg�D�̃`�[�����[�N����������Ă����B�����̃R�~���j�P�[�V���������������A���z�I�ȐE��Â���ɂ��q����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@����ŁA���k�ł���l���g�D�̊O�ɂ��������邱�Ƃ��A�傫�ȏ����ɂȂ�܂��B�s���{����ߗs�����Ȃǂ̒S���҂Ɗ�̌�����W������A�d���C���g���͔����ŋ��̉����Ɍ����Ēm�b��������������W������Ƃ悢�Ǝv���܂��B���̃l�b�g���[�N�́A�����̏ꍇ�A�����g�̐ϋɐ��̋��x�ōL����ɍ�����������̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�l�b�g���[�N���L�����̋@��Ƃ��āA�S����2����1���x�̓s���{�����J�Â��Ă���s�����̌��Q�����S���҂�ΏۂƂ������C��́A�����̊�b�����r���������Ƃ����Ӗ��ɂ����Ă��A�ł��邾�������̓s���{���ŊJ�Â���A��������̕����Q������邱�Ƃ��]�܂����Ǝv���Ă��܂��B
�y���C�̈Ӌ`�z
�i���{�j�ߋ��̑Ή�������w�ԂƂ������Ƃł́A����̑啪����Â̌��C��̂悤�ȋ@��͂ƂĂ��厖���Ǝv���܂��B�Q���ғ��m�Ŗ��h���������āA���C���I��������Ƃ��A�l�ԂŘA�������A���k�ł���W��z�����Ƃ��ł��܂��B�s���{������Â���s�����E����ΏۂƂ������Q�����̌��C��̈Ӌ`�ɂ��āA�ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�s���{�����C��ɂ́A���⑼�̃A�h�o�C�U�[�����ꂼ��Q�����āA�����Ɋւ���u�����Ă�����������A�������������̌��C(�O���[�v���[�N)�ł̓R�����e�[�^�[�߂Ă��܂��B�Q�����ꂽ�����̎s�����E���̕�����́A���̎s�����E���ƒ��ځA�ӌ������������ʁA�u�����̃q���g���v�A�u�����Y�݂����L�ł����v�A�u�m�荇�������ƂŐS�����v�A�u���̂悤�Ȍ��C��͒���I�ɊJ�Â��Ăق����v�ȂǁA�D�ӓI�Ȋ��z�����Ă��܂��B
�@�J�Â��Ă���s���{���̍H�v�₲�z���ŁA�s�����E���������̌���ŋ��߂Ă��邱�ƂɓI�m�ɉ�����A�Ӌ`�̑傫�����C��ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���Ă��܂��B
�y���Q���k�A�h�o�C�U�[�̈Ӌ`�z
�i���{�j�����ςł́A���C�u�t�̔h���A�H�̃u���b�N��c�̊J�ÁA��N����͔N�x���߂�web�Z�~�i�[���J�Â��Ă��܂��B�����ςł́A���Q���k�̌o���̖L�x�ȕ��X�ɂ����������āA���Q���k�A�h�o�C�U�[�ɂȂ��Ă��������A�S���̌���E���̊F�l�ɑ��āA�����g�̌o���������������Q���k�Ɋւ���A�h�o�C�X��o����������̏Љ�����Ă��������Ă���܂��B���Q���k�A�h�o�C�U�[�̍u���⎖�ጤ���ɂ����鏕���A�u�]�͎Q���҂̖����x�������ł��B
�@���Q�����������x���^�p���钆���ψ���Ƃ��āA�����ς͍�������������������p�����Ă�����悤�̐��𐮂��Ă����Ȃ��Ƃ����܂��A���Q���k�A�h�o�C�U�[�̈Ӌ`�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɂ��l���ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�����A�h�o�C�U�[�Ƃ��ĈϏ����������́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃł��������ׂ����A����������܂����B�����ς̕�����ߋ��̃A�h�o�C�U�[�Ɩ��̎����Ȃǂ������������ŁA�����̂ň�ĂĂ���������Ƃ��A�����̌���Ŋ撣���Ă�����F����ɁA���Ԃ����邱�Ƃ����̖������ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�����̋����ł́A�ւ��E���͋�J�������āA�Y�蕉�S���傫���B�F����Ɋ��Y���āA�����ł��q���g����A���C�����߂��Ă��炤�A���ꂪ�A�h�o�C�U�[�̖��߂��Ǝv���Ă��܂��B
�@�����͂����Ă��A�����̎���̕ω��ƂƂ��Ɍ��Q���̂���l���ς���Ă����܂��̂ŁA�ǂ̂悤�ȃA�h�o�C�X���ӂ��킵���̂��A�����ɖ������Ƃ�����܂��B�K���A�A�h�o�C�U�[�́A�����܂߂đS����8�����Ϗ�����Ă��āA���ӕ�����Ⴂ�܂��̂ŁA�������Ƃ��͏��������ƈӌ���������Ƃ��Ă��܂��B17���ȍ~�̈ӌ�����������܂��̂ŁA�`�[�����[�N�̑���́A�����Ƒ����`�ł�(��)�B
�y�g�D�̐��z
�i���{�j�Z���⎖�Ǝ҂ȂǗl�X�Ȑl���瑊�k��咣�����ƁB�����āA������̐����ɑ��ė��������߂Ă������ƁB����́A�ƂĂ���ςȎd���ł���A�f�X�N���[�N�Ƃ͈�����X�g���X������Ǝv���܂��B�����g�������ό��Q���k�_�C�����ŁA���X�A�����̊F�l����̑��k���Ă��܂����A������ɑ��k����܂łɂ�����x�̊��ԁA�䖝����Ă������A�Y�܂�Ă������Ƃ��b�������ς��Ƃ����̂́A�o�����Ȃ��ƕ�����Ȃ��Ǝv���܂��B�T���猩�Ă���ȏ�ɐE���͔��Ă��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@���k�Ή�������E���̐��_�ʂ̃P�A���厖���Ǝv���܂����A�g�D�̐��݂̍���i�E����l��l�̕��S���y�����邽�߂̍H�v�j��Ǘ��E�A��i���ӎ������ق����ǂ����ƂȂǂ���������Ă��������B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�ŋ߂͑����̐E��ōĔC�p�E�����z�u����Ă��Ċ���Ă���Ǝv���܂��B�����ł͘V���ȐE���́A����܂Ŕ|���Ă����R�~���j�P�[�V�����͂◎�����Ȃǂ��𗧂��܂����A���������l�ނ������Ɋւ�邱�ƂŁA�ԈႢ�Ȃ����̐E���̕��S�y���Ɗw�т̋@��ɂȂ���Ǝv���܂��B
�@�܂��A���͓̎d�b�ɂ�邱�Ƃ��唼���Ǝv���܂��B���̐E��ł́A�d�b�����E���̎���̐E���������ďZ��n�}��p�ӂ��A�ߋ��̌o�߂�����p�\�R����ʂ�I�����āA�T�|�[�g����悤�ɂ��Ă��܂��B��i�́A�S���E������A���̌���ɏo�����O�ɑΉ��Ă̑��k���A���ӂƏꍇ�ɂ���Ă͒lj��̏��������āA��̊����ɂ��Ă��܂��B�Ǘ��E�́A����ɍs�����Ƃ���S���E���ɂ悭���������A�A����͘J���˂�����Ă��܂��B
�@��͂�S���E���ɂƂ��ď�i��Ǘ��E�̌��t�͉h�{�܂ł��B��i��Ǘ��E�͊��Y���S�Ɗ��ӂ̋C�����������A�����̃~�[�e�B���O�ɂ̓^�C�����[�Ɋ֗^���邱�Ƃ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�y���Q�R����̒���ɂ��āz
�i���{�j�����ςł́A���Q�����������x�̃r�W�����ƑS�̍\�z�������Ƃ���ł��B�����ς́A���Q���������@�ւƂ��Ă̖���������܂����A�����ψ���Ƃ��āA�s�撬���̌��Q���k�����A���Q�R����y�ь��Q�������ψ����Ȃ���Q�����������x�S�̂Ƃ��Ẳ����͂̑��a�����߂Ă�������������܂��B
�@�S�̂Ƃ��Ẳ����͂̑��a�����߂�Ƃ����̂��|�C���g���ƍl���Ă��܂��B���Q�����������x���ł��Ĕ����I�o���܂������A���߂ČX�̋@�ւ����̓��������o���邱�ƁA���x�S�̂Ƃ��Ď��Ă��������Ă����W���č\�z���邱�ƂŁA���Q�����������x�ʼn��������ׂ��������������̂܂ܕ��u���ꂸ�ɁA�ӂ��킵���@�ւŏ��������悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�@�����A�h�o�C�U�[�ɂ́A�ߋ��̘A�����c��ɂ����Ă��o�d���������A�s�̐E���̎��_������Q������Q���������A���Ɏs�撬���ƌ��Q�R����Ƃ̊ւ��ɂ��Ă��������������܂����B�����ł͓s���{�����Q�R����̔F�m�x���Ⴂ�Ƃ������w�E�������������Ƃ���ł��B���Q�R����̒��������ςْ̍�ɂӂ��킵�����Ă����ۂɂ��邩�ǂ����́A�s�撬���̌��Q���k�����̊F�l����Ԃ������ł��̂ŁA�����������C�̋@����������āA�s��ADR�Ƃ��Ă̌��Q�����������x�̓����Ƌ��݂ɂ��ė������Ă��炤���ƁA�ǂ����������Ă����Q�R���������ςň����Ă���̂���m���Ă��炤���Ƃ��K�v�s���ł��B�Ȃ��Ȃ������ł����ɒ��������Ă��鎖��Ȃǂ�����A���k�҂ɒ����ْ���ē����Ă��������A�\���ĂɂȂ��������Ƃ��ł���Ɨǂ��ƍl���Ă��܂��B
�@���Q���k����������Q�R���������ςւ̐\���Ă̗U���Ƃ������Ƃ��������Â̂����������C�̈Ӌ`�Ƃ����̂͂ƂĂ��傫���Ɗ����Ă��܂����������ł��傤���B
�i�����A�h�o�C�U�[�j����Â̌��C��ł́A��Î҂���K�����Q�R����ȂǕ��������̐��x�̏Љ����܂��B�����̌��Q���́A�����Ⴂ����(35�N���炢�O)�Ɣ�ׂĂ��A�����̎��Ⴊ�����Ă���悤�Ɋ����܂��B55�N�قǑO�ɂł������Q���������@�ł����A���̂悤�Ȏ���������s�����ɂƂ��čs��ADR�̓�������蔭�������V���Ȏ���w�i�̒��ŁA���̐��x�̉��l���ĕ]������邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͊����Ă��܂��B���̈Ӗ��ł��A���x�̔F�m�x�Ǝg���₷�������シ��A���ꂩ��́A�s���{���̌��Q�R����̐\�����Ⴊ�����Ă����K�R������悤�ɂ��v���Ă��܂��B
�@����ɉ����ēs���{���̌��C��ł́A�n��̋����f�ނƂ����O���[�v���[�N������܂����A�o�ȎҎQ���^�̌��C�Ƃ��čD�]�ŁA�s�����Ԃ̘A�g�̉�������������ڂƁA�s���{���Ƃ̊W�̋����ȂǁA���l�Ȍ��ʂ�ł��܂��B
�@�������������ł����A�����A�h�o�C�U�[�́A�O���[�v���[�N�Ŏ��グ���鎖��ւ̃A�v���[�`�̃q���g�Ȃǂ��A���O�̍u���ł͂��b���ł���悤�����Ɠw�͂����Ă��܂��B�����Ƃ�����ɊF����̂����ɗ��Ă�悤�Ƀu���b�V���A�b�v���ׂ��Ɠ��Ȃ����Ă��܂����B
�@�Ƃ���ŋ��́A�s�����̌���Ŕ������A���ꂪ�s���Ή��̋N�_�ƂȂ�܂��B����������ȏꍇ�́A���̌�̓s���{���Ƃ̘A�g�̗ǔہA���Ƃ̘A�g�̗ǔۂ������ɏd�v���͘_��҂��܂���B�A�h�o�C�U�[�̖ڐ��Ō���ƁA���̍ŏ��̘A�g�̃L�[�ƂȂ�s�����Ɠs���{���̊W����������ł��ߓ��Ŏ茘�����@���A�s���{���̌��C��ł���Ǝv���Ă��܂��B
�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�ł��邾�������̓s���{�����W�s�����̐E���̂��߂̌��C������I�ɊJ�Â��邱�Ƃ������܂ߑ����̃A�h�o�C�U�[���]��ł��܂��B���C���J�Â̌����ꂩ�猤�C��𗧂��グ��̂͂Ȃ��Ȃ�����J�����邩�Ǝv���܂��B�ł��̂ŁA�����������C��S���ǂ��ł��A���N�J�Â���Ă��邱�Ƃ�������̕��i�ƂȂ�悤�A�����ϑ�����s���{���̒S���҂ɘb�����������Ă��������A�K�v�ȏ�����Ă��炤���Ƃ��|�C���g�ɂȂ�܂��B�����ςɂ́A����œ��X�������Ă���E���̂��߂ɂ��A���������g�����肢�������Ǝv���܂��B���̋@��Ƃ��Ė��N�̘A�����c���H�̃u���b�N��c����������Ă͂ǂ����Ǝv���܂��B
�y�Ō�Ɂz
�i���{�j���Q�����ɏ]������Ă���S���̐E���ɑ��郁�b�Z�[�W�����肢���܂��B
�i�����A�h�o�C�U�[�j�u���b�N��c��s���{�����C��ł��悭���b�������Ă���������ł����A�u�����悻�������芴��B�����̂Ȃ�������ʂ��āA��X�͐E���Ƃ��Ĉ�̉��������̂��v�A����͑傫�ȃe�[�}���Ǝv���܂��B
�@�ł��悭�l���Ă݂�Ƌ����Ƃ́A�\�}����Ղ���́A�W�҂ƑΘb����́A����̓W�J��z�肷��́A���ӌ`����}��͂Ȃǂ���ʁA��ʂŖ�����ƂƂ�������킯�ŁA����͉��������Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A���ꂩ�炢�낢��ȐE��Ɉٓ��ɂȂ��Ă��A�ǂ̂悤�ȍs���ۑ�Ɏ��g��ł��A�E���Ƃ��Ă����镪��A��ʂŎ�����A���߂��鑍���I�ȗ͂ł���Ƃ����܂��B�傰���Ɍ����ΑސE�܂ł̍��Y�Ƃ������܂��B�ߊς���͐��܂����̂͏��Ȃ��̂ŁA�O�����ɂ��Ƃɓ���������悢�Ǝv���܂��B
�@���͏������ł����A�m����X�L����������悤�ɁA������������Ă��܂����B�������ł����̂ŁA���X�̎��Ȍ��r������Ǝv���܂��B�����Ă����Ƃ��߂ł͂Ȃ��E��ŃV�F�A���邱�Ƃ�����Ǝv���Ă��܂��B�d���͑g�D�œ�������̂ł��̂ŁA�g�D�̖{���̋����Â���ɖ𗧂��܂��B
�@�Ō�Ɉꌾ�A���_�ł����A�d���͕����ʂ�O�̃��[�N������ƍl���Ă��܂��B�t�b�g���[�N�ƃ`�[�����[�N�ƃl�b�g���[�N�ł��B�����ł́A����l�̕��S�����炷���߂ɂ��A�`�[�����[�N�ƃl�b�g���[�N���������Ă��������B����ɉ�����A�S��������߂ɁA�Ⴆ�X�|�[�c�A���s�A���y�ȂǁA�Ȃ�ł������̂Ŗ����ɂȂ��āA�傢�ɃI�t�^�C�����y����ŁA��l��l�̐S�̌��N���ɂ��Ă���������ƐS�������Ă��܂��B
�i���{�j�M�d�Ȃ��b���������Ղ��܂����B�C���^�r���[�ɂ����͂��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B�����g�A��ϕ��ɂȂ�܂������A����̃C���^�r���[�́A�����ρA�����đS���̎����̐E���̊F�l�̎Q�l�ɂȂ�Ǝv���܂��B�{���͂��Z�������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�ȏ�
1�@�w���Q���k�̎�����x (���c�@�l���{������ҁA���Q�������ψ�����NJďC�A����11�N)