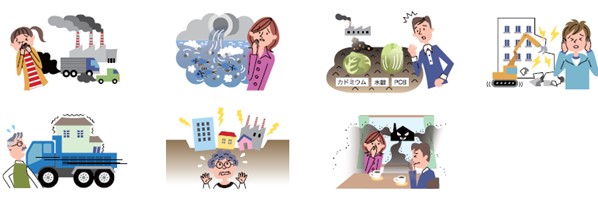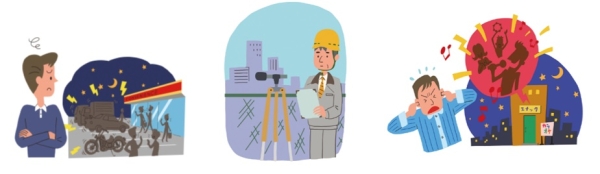公害等調整委員会事務局は、大阪府公害審査会前会長の播磨政明弁護士にインタビューを行いました。播磨弁護士からは、令和6年6月7日に開催された「第54回 公害紛争処理連絡協議会」のグループ別意見交換において、大阪府の先進的な取組の事例をご紹介いただいたところです。
インタビュー実施のきっかけは、それらの事例の中に「公害審査会の活性化」等を進めていく上でのヒントがあるのではないかと考えたからです。
そのため、播磨弁護士には改めて“大阪府公害審査会の活性化”について、在任中に取り組んでおられたことや“公害紛争処理制度全体の運営が円滑に進むために”考えておられたこと等を以下のテーマに沿ってお伺いしました。
1 公害紛争処理の調停の強み、特性
2 公害紛争処理制度と公害審査会の存在意義
3 公害審査会への申立ての誘導について
4 今後の公害紛争処理制度に期待すること
その他、日頃、公害苦情相談に従事されている職員の皆様への温かいメッセージも頂戴しました。市区町村の公害苦情相談窓口、公害審査会及び公害等調整委員会からなる公害紛争処理制度全体としての「解決力の総和」を高めるためには、公害紛争処理制度で解決されるべき紛争が未解決のまま放置されず、ふさわしい機関で処理されるように環境を整えることが重要です。本インタビュー記事が、関係者の皆様の今後の取組の参考になれば幸いです。
(令和6年11月29日 大阪府・伏見町法律事務所にて)
播磨 政明 氏
(はりま まさあき)
弁護士
大阪府公害審査会前会長
1 公害紛争処理の調停の強み、特性
(1)“大阪府公害審査会の調停の強みは、粘り強く熱意を持って進めていくというところにあります。「何とか円満解決したい」という熱意を全員が持っているんです。”
大阪府公害審査会の特色として、長期間に渡って調停を行っているということと、調停回数を多数重ねて円満解決を図るというのがあります。
全体の委員数は15人です。弁護士が5人、学者や有識者が10人いて3人でチームを組みます。弁護士が必ず調停委員長になります。ですから、あとは学者と有識者、学者の中でも専門と専門外の人を組み合わせて、その3人で委員会を構成します。弁護士である調停委員長は、弁護士会の推薦を受けていますので、非常に熱意を持っていらして、とにかく「調停を成立させたい」という強い意欲を持っています。粘り強く長期間に渡って、多数回の調停をして「何とか円満解決をしたい」という熱意を全員が持っています。そういうことで長期間、多数回の調停を重ねることになるのですね。
例えば、問題が音源である場合は、音響の専門家の方に調停委員として入っていただきますので、測定も簡易に自らやってくださいます。そのようにして方向性は大体、専門家の方が示してくれます。弁護士と専門家が一緒に頑張って進めていくという双方の兼ね合いが「熱意を持って調停を重ねていく」ということに繋がっています。
(2)“申請人、被申請人双方が相手方に対してどういうふうにお考えになっているか、その辺りを中立的に進行するということを心がけています。”
もう一つ、調停に当たり一番大事なのは、中立、公正に双方の言い分をお聞きするということです。 大阪の場合、直近5年間の統計を見ても、令和元年から令和5年までに32件申立てがあったんですが、そのうちのどちらか又は、双方に代理人の弁護士が付いているケースが23件ありました。つまり、72%の事件に代理人がついています。ついていない人もいますので、その場合は、被害事実を訴えてきたときの資料を収集して、双方が相手方に対してどういうふうにお考えになっているか、その辺りを中立的に進行するということを心がけています。 申請人ご本人から、怒られたこともありますよ。なかには、公害審査会を救済機関だと思って申請してくる方もおられます。そういった場合は、お互いに譲り合う「互譲精神」をあまり理解してくれなくて、自分たちの言い分を認めてくれるのが当然じゃないかとおっしゃって、とても怒られたことがあります。苦情を聞く場なのかどうかというところもありますけれど、なかなか難しいと思った事件があります。

代理人が申請人に対して、調停とはどういうものか十分に説明して、その上での申立てだったら良いんですが、資料も乏しく、自分たちの感情を訴えて、僕ら調停委員を説得して、相手方に譲歩を求めてもらおうというお考えを持った事件でした。そういうお考えなので、こちら側が色々聞くと怒り出すんですよね。それは、本当に困りましたね。だから、期待されるのは良いんですが、公害審査会は救済機関だから何とかしてくれると思っておられると、解決の仕方が難しい場合があります。
(3)“規制基準も超えていないし、受忍限度も超えていないとなると話合いにならない。そのような場合でも何らかの被害があれば、そういう被害があるんだということを原因者にも分ってもらい、何らかの解決を目指すということが重要なのかなというふうに思います。”
公害紛争と言っても近頃は、ご近所トラブルのような問題も多いんですね。マンションの上下で「何か気に入らん」とかね。何でそんなに気になるのかと現地調査に行ってもらうと、実は、そのマンションの周りがあまりに静かすぎて、上下の騒音がもろに耳に入るという案件でした。
こういうのは、現地に行かないと分らないことですし、行ってみたら上の階には子どもさんがいらっしゃるんですが、ちゃんと床に敷物を敷いて対応してくださっているんですよ。それでも、下の階に住んでいる人は気になって仕方無いと。そういう辺りからもやっぱり現地調査に行って見ていただくんです。典型7公害以外の問題がこれからもますます多くなるんじゃないですかね。
紛争があればそれらも含めて受け付けていますし、相手方も典型7公害とは違うと言って拒否する人はいません。そこに被害があれば、やはり何とかしようという姿勢がありますね。本当に事務局も調停委員も熱心なんですよ。紛争があれば、何とかまとめてみよう、まとめてみたいという気持ちで取り組んでいます。
それから、音に関しては日中、自宅にいらっしゃる方からの相談が多くなってきたんじゃないですかね。昼間あまり外出せずにおられる場合は、難しい場合が多いです。夜中に給湯器を使ってお風呂に入るのが23時ぐらいだから、その音がうるさいだとか生活リズムは人によって違いますよね。ずっと家にいらっしゃるか、働きに出ているのかでも全然違います。 最近では、ずっと家で仕事をしていて、何百メートルか離れたところの騒音がうるさいという申立てもあります。ご自分で測定して記録をつけている場合もあるし、業者に頼んで低周波音の測定をしてもらったという方もおられますが、その測定結果はなかなか利用しにくいことも多いんですよ。審査会の調停では、客観的に見て本当にそうかなと確認したいけれど、申請人が独自に依頼している測定結果はその点で、使えないこともあります。審査会では、証拠も客観的に扱っていますから、申請人にとってあまり良い結果に落ち着かないこともあります。だから、受忍限度を超えている、超えていないという議論になるわけですね。そして、規制基準も超えていないし、受忍限度も超えていないとなると普通は話合いにならない。そのような場合でも、何らかの被害があれば、そういう被害があるんだということを原因者にも分かってもらうということが重要なのかなというふうに思います。自分たちが思わず被害を与えてしまっていることがあるんだということが分かれば、何とかできないかなという部分もありますし。逆に隣の人がおっしゃることがよく分からないということであれば、審査会で専門家から説明してもらえば良いですし。調停委員も話を伺って、じゃあ、ここのところをこう考えてみましょうと進めていくので、柔軟な考え方ができないとなかなか難しいですよね。
柔軟性にも運用面と解決面の双方がありますが、自分の主張が全部通るわけでもないけれども、相手の主張も全部通るわけじゃ無いんだということですよね。
(4)“紛争の進展に応じて、柔軟な解決方法を模索してやっていますので、最初の申立て時から成立した時点では、解決の内容が全く違ってしまうこともあるんです。”
また、大阪の公害審査会で一般的に行っていることですが、例えば、原因者に騒音の防止措置などをしてもらうことになったとしたら、調停が終結するまでに実際、どこまで行っているのか「途中経過」を確認して、解決していることを見届けています。決して、ほったらかしにはしません。調停は、強制力があるわけではないので、執行の部分を考えると難しい部分もありますが、それでも、これまでもめたようなケースはなく、皆さん誠実に対応してくださって終結しています。
ですから、ある意味では、これも一つの特色ですが、紛争の進展に応じて、柔軟な解決方法を模索してやっていますので、最初の申立て時から成立した時点では、解決の内容が全く違ってしまうこともあるんです。

例えば、一番始めは、建設工事の騒音や振動、日照被害が問題となって申立てがあったという事件。日照被害については、調停中に様々な説明を受けていくうちに「これはやむを得ない」というコンセンサスが出来てきたんです。それが、建物が完成に近づいてくると今度は、プライバシーの問題が出てきた。つまり、その建物からのぞかれてしまうから、こちらに面している階段を全部、板で覆いを作って欲しいという全く別の要求に変わるんです。最初に訴えていた被害とは全く変質してしまったんです。でも、だからと言って、それは駄目ですよと断って打ち切るのではなく、原因者側つまり被申請人側にもこういう要求があるけれどどうですかと一定程度、非常階段の効用を無にしない程度の措置を取ってもらったりします。そして申請人には、これが限界ですね、これ以上やると建築基準法に触れてしまうので駄目ですよとしっかり説明します。
その他にも出来上がってきた建物には、廊下や階段の照明が一日中ついていて、今まで何も無かった所だったのに「光害」が起きてしまったじゃないかと、それを何とかして欲しいという要求も追加されました。これはもう、被害を訴えているお宅のカーテン代を1戸当たり何万円と算定して、申請者側にお支払いするという金銭的解決で終わりましたが、当初の申立てとは全く違う柔軟な解決方法ですよね。こういう終わり方をするケースも結構あるんです。だから、建設工事が終わったからと言って、調停を打ち切るということにはならないんですよね。申請人の要求に応じて、模索しながらも円満解決を図るということなんです。
(5)“もう一つの大阪の特色である「ロングラン調停」は、解決するというよりむしろ、話合いの場を提供する、お互いの協議の場ということで、裁判所ではなかなか出来ないようなことをしている。”
他にも、公害審査会は解決するというほかに、話し合いの場を提供することにも徹しています。成果がどこにあるのかというのはありますけれども、住民サービスという感じで取り組んでいます。弁護士の調停委員の任期は6年ずつですけど、それを継続してつながっていく「ロングラン調停」を行ってきているわけです。
つまり、安心して協議出来る場を公害審査会は提供していて、結果、長期間にわたって調停期日を重ねているけれど、それが機能しているというところだと思います。公調委からすると、何やってるんだと言うことになると思いますけれど、これは大阪府の審査会の中では意義のあることをやっているんだという意識でおります。期日を重ねると申請人の要求事項も変わっていって、苦情処理をしているような感じですね。もちろん、特殊な事件ではあるので、全国の皆さんの参考にはならないと思いますが、こういう使われ方もあるといいますか、見守り型の公害紛争処理になるんですね。
見守り型だからこそ、普通の事件であっても調停外で当事者同士が協議して、一定の措置を講じてもらった結果を次回の期日で報告してもらうということもやってもらっています。例えば、次回の期日までにこれとこれをやってくださいと「宿題」を出して、その報告を受けて、「次回はこれをやってきて」と続けていく。そこまで行くと成立することが多いですよね。次回やること、次回までに提出してもらうこととかをきちんと調書に残しています。調停委員会からの指示で、当事者に次回期日に報告を求めるということは、普通にやっていることですね。
白黒つけるというより、どっちに寄ろうと解決したら良いわけです。原因を明らかにするのは難しいところもありますし、ご本人たちも原因について裁定を求めるというよりも「解決」を求めていますので。資料だけでは白黒つけにくいんです。そこは、突き詰めすぎずに“ソフトエンディング”に持って行くという努力をしているんですね。“ロングラン調停”もそうですよ。解決を遅らせるというのではないですからね。もし、解決するとしたら、この制度であれば取り下げてもらうのかもしれないですよね。でも、それよりも覚書で今後も環境に配慮していくとかそういう和解になると思うんです。
2 公害紛争処理制度と公害審査会の存在意義
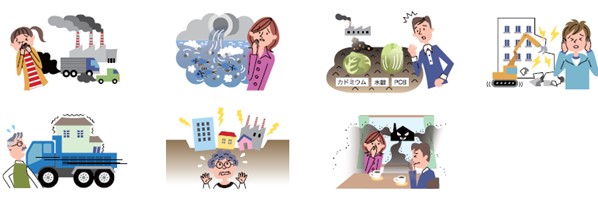
“本人の納得が非常に大きい解決ができる制度だから、精神的な満足が得られる。裁判所の調停よりも柔軟な解決ができるという点で、公害審査会は非常に存在意義が大きい。”
身近に相談できる体制としては、市町村に公害苦情相談窓口がありますが大阪の方は、結構難しいところがありまして、相談では解決できず紛争になった場合、もちろん訴訟も選択肢としてありますが、なかなか敷居が高いというところがあります。その場合の受け皿として公害審査会は非常に良い機能を果たしていると思います。
一番良いと思う点は、お互いに互譲しあって、その上で納得した解決を目指すことができるということです。裁判では、請求の趣旨が必要ですが、公害審査会では、相手方に対し、被害を無くす、あるいは軽減させるための行為を要求するものや何とかしてくれというような措置要求をするようなものが大半です。
申請人は一般の市民の方ですので、手元に資料が無いことも多いですし、専門家が近くにいらっしゃるわけでもない。つまり、どうやって資料を集めたら良いか、何をしたら良いか分らないという状態でいらっしゃる。それでも、裁判所とは違って特に請求の趣旨がはっきりしていなくても、「何とか被害を少なくしてほしい」とか「軽減してほしい」というような「措置の要求」を求めても良い制度です。金銭要求が求められても調停で相手方が、それを認めることはめったにありません。
金額で着地点を決めてしまうと、弁護士としては非常に難しい事件になってしまう。被害を金銭に換算してお金が取りにくい事件なんですね。それでも、申請人の納得が非常に大きく、解決できる制度なので精神的な満足が得られる。経済的な利益よりも、精神的な満足を得るというのは、裁判所の調停では難しいですから、柔軟な解決ができるという点では、公害審査会は非常に存在意義が大きい。
3 公害審査会への申立ての誘導について
(1)“大阪府公害審査会事務局の皆さんは、非常に誠実に当事者に対応されます。相手方に意見書の提出を依頼する場合もしっかりケアしている。そうして、当事者に応じていただけるよう水面下で相当な努力をされている。そういうところがとても大きいと思います。”
公害審査会に事件が上がってくる時点で、もう既にこじれていて、「とても話合いによる和解なんてできない」だとか、「調停しても不成立になるだけだ」というような、消極的な意見もあるようです。
でも、例えばですが市役所が実施した騒音測定で規制値を上回る結果が出ているような場合には、当事者間では、被申請人の方が市役所の指導で一定の改善策を講じていることが、結構あるんです。それでも、申請人ご本人が市役所による指導だけでは納得できない場合がありますので、どうしてもこじれてしまう。こじれているという言い方が良いのか分りませんが、例えそうだったとしても結局、調停委員3人が公正・中立の立場で膝を交えて、非公開で双方の話を聞きます。現地調査にも気軽に出かけて行きます。その場で相手方にも直接話して、申請人ご本人や他に被害を受けているお宅でも、同じように話を伺って、どういう状況なのかを理解した上で、規制値がどうあろうとも、もっと良い解決ができないか耳を傾けていくと調停中であっても、被申請人の方はもう少し、自ら費用を投じて更に軽減措置をしてくださったりすることがあるんです。
この公害調停制度では、原因者と言われる被申請人が対応してくれますし、調停に応じる、応じないというのは原因者にとっては自由ですので、嫌だったら応じなければいいわけです。でも、僕が公害審査会在任中に断った原因者はいませんでした。これは、被申請人の方が、「調停がどんなところか、行ってみよう」と思ったのか、それとも「何か言いたいことがあって行こう」と思ったのかは分かりませんが、応諾率で言えば100%じゃないですかね。
それは、被申請人に解決意欲があるというのも、もちろんあると思いますけど、多分、大阪府公害審査会事務局の皆さんが、非常に誠実に対応されていて、被申請人に意見書の提出を依頼する場合も被申請人にしっかりケアしている。そうして、応じていただけるように水面下で相当な努力をされている。そういうところがとても大きいと思います。
(2)“44%は事務局への相談が申請に結びついた事件。事務局含めて審査会全体で情報共有できています。”
大阪府の公害審査会では、市町村の担当者を集めて研修をしていますが、アンケート結果を見ても「研修を受けて良かった」という回答が多いです。もともと、基準値を超過しているような事件の場合、市町村に指導していただいていますが、指導しても状況が変わらないとか、そもそも基準値が無いような事案もありますので、そうした場合は調停の申請ができることを相談者にはご案内するんです。長期間にわたって事務局の方で相談対応しているので、その過程で相談者と事務局との間に一定の信頼関係が出来ていくことが多いようです。
最終的には、本人が決めることなので無理矢理申立てを勧めるということはもちろんありませんが、令和元年から令和5年までの5年間で事務局に相談があって、申立てに結びついた件数というのが、14件でした。内訳としては令和元年に4件、令和2年に2件、令和3年に3件、令和4年に4件、令和5年は1件となっています。
これらは全部、事務局からつながった事件です。受付件数が全体で32件だったので、そのうち44%が公害審査会の事務局に相談があって、申請に結びついたという事件なんです。
ですから、審査会の事務局は申請人、被申請人双方に上手に対応していまして、代理人が就いていないような方からの、「申請したいけれどどうしたらいいか」という相談にも誠実に対応していますし、相手方への接触も丁寧に行っているので、応諾しないというケースはここ数年では0という状況になっています。
調停制度のいいところは、ご本人とお話しして相手方を説得するという部分でもありますが、事務局もうまくやっているんだなと思っています。申請に対して、被申請人からの意見書も大体提出してもらえる。意見書の書き方についても、事務局の方で丁寧にアドバイスされているんですね。
それから、事務局からは私のところへも相談がこまめにあがってきていました。まず、事件が係属すると調停委員を誰にするのか、事件の背景を見ながら、この人とこの人どうですかと相談しに来るわけです。僕の方では、事件の内容、手持ち件数を見ながら弁護士委員の調停委員長を選任します。代理人が就いている場合には、この代理人を説得するには、どの人が一番適任か、と考えて選んでいます。
事務局からあがってくる相談は、調停委員の調整などから始まりますが大阪では、年に2回、全体委員会を開いています。委員全員で情報共有して、どこまで進んでいるのか、問題点はどこにあるのかなど、調停委員長から説明したら他の委員から意見があります。その辺りからも、事務局含めて審査会全体で情報共有できているから心配は無かったですね。それに、委員会とは違う観点の質問が事務局から出てくることもありますし、問題点や解決の方法について、調停委員会でも「これでいいのかな」と思っていることについて、質問を投げかけることもあります。

(3)“この制度は、審査会事務局の姿勢に加えて弁護士が実際に使ってくれないと、なかなか順調には進まないんじゃないかと思います。双方の代理人がきちんと解決を目指して委員会の専門家のアドバイスを受ければ、もっともっと申立てを掘り起こせるんじゃないかと思うんです。”
「都道府県の公害審査会を、活性化していくべき」という課題については、もっと早くから危機意識を持たないといけなかったと思うんですよ。今の公調委からは、一生懸命何とかしたいという意欲があふれておりますけれどね。
そういう点で言うと、危機意識に関しては、労働委員会なんかはものすごく高くて、何とかしようというのがあるんですよ。でも、公害紛争の公調委では、何とか活性化しようという雰囲気が僕が審査会会長になった最初の頃は、少なかったように感じました。最近は、6月の協議会のように闊達にご意見がでてくるようになって、良い方向に行ってるなと思うんです。その際に受付件数がゼロの審査会も相当数あると伺いましたが、公害紛争処理制度を広報して、調停制度が有用だということを訴える努力をすることが必要ですね。
協議会の後で、公調委が都道府県の弁護士会に行って説明会をされていると伺いましたが、この制度は、弁護士が実際に使ってくれないと、なかなか順調には進まないんじゃないかと思います。双方の代理人がきちんと解決を目指して専門家のアドバイスを受ければ、もっともっと掘り起こせるんじゃないかと思うんです。常設の審査会が無いところもありますから、「あなたの身近な苦情について、きちんと処理しますよ」ということを広報するとか、「自分たちはこんなことで助かりました。」というようなことをSNSなど使って発信できたら良いんだけれど。「こういう事件で、こういう解決ができますよ」という解決の事例をもっとPRする必要がありますね。「こんなに役立ちました」と。調停を進めていく過程で、最終的に解決しなくても申立て時点より良くなったケースって結構あるんですよね。
少し前に不調になったケースで、とても静かだった場所にできた施設のダンスやカラオケの音がうるさいということで、申立て時は騒音対策を求めていたものがあります。双方の代理人が一生懸命にアレンジして、何時から何時まででカラオケは止めます等、一定のところまで良くなったのに、最後のところで解決金の金額でもめてしまいまして、被申請人の方からしたら、これまでも十分対応してきたし、お金もかかっているのに更に追い打ちをかけられるというのはとんでもないとおっしゃって、成立しなかったというものがあるんです。このケースのように、非常に有用な話合いができて、相手方が一定の措置を講じてくれたとしても成立しないケースもありますし、事態が改善されても成立しないというものもあります。
大阪の場合、事件を持ってくる弁護士が何人かいるんですよ。相談を受けてこの調停制度を積極的に利用するという方がいます。有用な制度ですし費用面からもコストパフォーマンスが良いと思いますね。申立てもしやすいし、専門家の知見も得られる、たまに何かむちゃくちゃなことを言うような方がおられたとしても、事務局がアドバイスしていますし、一定のシステムに乗っているから良いんですよね。ただ、やはり好き嫌いあると思いますし、こういう事件をやりたいと思わない人も結構いらっしゃるとは思うんです。それでも、やっぱりやりたい弁護士も一定割合いますからね。
(4)“僕は、大阪の弁護士会では「公害審査会の存在意義」というのは裁判所の調停とも違う形としてはっきり認識されていると思っていますし、積極的に活用されていると考えています。”
それから、こじれていると言えばなかなかすごいのがありました。公害審査会に申請される前に、簡易裁判所で調停をして、その後、申立人と相手方が入れ替わって、再度調停をしたというケースなんですが、裁判所でうまくいかなかった事件を審査会に持ってくるという、そういう事例が大阪にはあるんですよ。
最初は、被申請人側も「簡易裁判所で調停してもだめだったんだから」と、消極的なことを言いますが、それでも拒否することなく応じてくださって、進めているうちに一定方向へ進んでいくという形もあります。裁判所で調停をして、それが成立しなかったり、あるいは調停中であっても一方が公害審査会に申し立ててきて、双方で進んで行くということもあります。だから、僕は、大阪の弁護士会では、公害審査会の存在意義というのは裁判所の調停とも違う形としてはっきり認識されていると思っていますし、積極的に活用されていると考えています。
例えば、原因者の方から裁判所ではなく、あえて公害審査会に円満解決を求めて調停を申請してくる場合もあります。自分としては、適切に一生懸命対応しているのに、理解してもらえないから「何とかしてくれ」というケースです。双方をお呼びして、「何が不満なのか」をお伺いしていく中で、争点が分かっていくこともありますし、原因者側としても「もう少しこうします」と譲歩することはありますから、そこは委員側の「何とか解決したい」という熱意にもよるんじゃないでしょうか。それに、調停に応じるよう委員側から説得されたら、やっぱり解決したいと皆さん思われるんじゃないでしょうか。
それから、公害審査会では、組織として測定にも簡易迅速に対応できるし簡易裁判所で調停不調になったものでも、新しい視点で考えるという点では、簡易裁判所よりも柔軟に出来るし、事務局もしっかりしているので、良いのかなと思います。
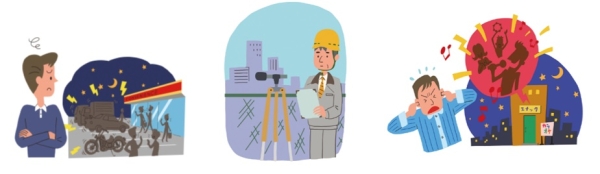
4 今後の公害紛争処理制度に期待すること
“制度全体として解決力の総和を高めるためには、上から旗を振るだけではなくて、現場から意欲が上がってこないと難しいと思います。底上げするためには、全国の公害審査会の事務局の方が自分たちの存在意義というのを意識することが重要。”
公害紛争処理制度は、解決面からもすごく良い制度ですね。少なくとも、申立て段階ではこじれていて、主に金銭賠償ではないような措置請求が主ですので、それを専門家として仲介して、訴訟と対比して時間、費用、解決方法、互譲による解決のメリットがあるということを説明する。原因者である被申請人には、法的な問題になっていないとしても、一定程度苦情の原因があることを理解してもらって、相互に信頼関係が築けるように粘り強く工夫して協議を成立させることができる制度ですので、これは是非積極的に広報されて活用されることを期待したいと思います。
その活用のためには、やっぱり弁護士の関与が重要だと思います。この制度の有用性が全国の弁護士に認知されるということが必要ですので、公調委の方も弁護士会での制度の説明というより、例えばシンポジウムを開いて公害紛争処理に関わったことのある弁護士に来てもらって、有用性を広く伝えてもらうとか工夫できると思いますね。一方的な広報ではなく年に1回くらいシンポジウムを開かれたらいいと思います。
公害紛争処理制度全体の解決力の総和を高めるためには、上から旗を振るだけではなくて、現場から意欲が上がってこないと難しいと思います。底上げするためには、全国の公害審査会の事務局の方が自分たちの存在意義というのを意識することが重要ですね。
この制度を利用してもらうためには、審査会の方達に実際の現場での進め方を理解してもらうことも重要ですよね。調停は非公開だから、なかなか難しいと思いますけれど、近畿管内とか東京管内とか、事件のあるところに他の府県の方が研修か何かで勉強できる機会があると良いですよね。やっぱり現場での進め方を理解していないと、「申立てが来ても困るな、来たらどうしよう」となってしまいます。だから、申立てが来ても安心して対応できるように、実地研修みたいなことが考えられたら良いかなと思います。調停委員が当事者とやりとりしている場とか、最初は、対立していた当事者をどう説得して事情聴取しているかとかその辺りを見てもらうとかなり勉強になると思いますよ。

大阪府の審査会では、調停調書も非常に詳細に取っていますので、読み直すだけでも勉強になります。その経過からどれを次の宿題にするかとか、その辺りも出るようになっていきますから、やはり事件を掘り起こすには、事務局に頑張ってもらわないといけないんですよね。調停委員と事務局双方の努力が必要なんです。だから、事務局で継続的な対応というか、何回もご本人と話していくうちに「申立てもありますよ」という感じでご本人の意思を確認しながら、調停の申立てに持って行くようなことは事務局も努力していますし、そもそもが公平な制度ですけれど、必要な資料なんかも、その相談の段階でしっかり指摘していますから、調停の進行自体もスムーズになるんですね。
ですから、やっぱり事務局の方の意識が高まるというのは非常に重要で、大阪の場合は、OJTが非常にしっかりできているんです。今年の4月に新人職員が入ったんですが、短い期間で立派に対応できるようになっています。初めて配置された部署が審査会ですけれど、本当にしっかりやっています。だいたい、半年もしたら十分、立派になっておられます。その前に配置された新人職員は、1年ぐらいしたら職員みんなを回していましたね。だから、本当に大阪府公害審査会のOJTはすごいと思っているんです。それだけ、事件の数が多いということもあるんでしょうけど、なによりも現場でしっかりやってるからだと思います。紛争があれば解決したいと思っていますから、双方にとって良いと思うことを何とかアドバイスして成立させたいと思って、みんな一生懸命やっています。対応の最前線にいらっしゃる方たちは、本当にすごく大変なので健康を大事に頑張っていただきたいと思います。