2016年のアメリカ大統領選などを契機とし、新型コロナウイルス感染症、ウクライナ侵攻に関するものを含め、インターネット上のフェイクニュースや偽情報が問題となっています。
総務省では、2018年10月に立ち上げられた「プラットフォームサービスに関する研究会」の中で、「インターネット上のフェイクニュースや偽情報への対応」を検討項目の一つとして議論を行い、2020年2月に最終報告書(以下「2020年報告書」という。)を取りまとめました。
2020年報告書を踏まえ、「プラットフォームサービスに関する研究会」において、プラットフォーム事業者の取組が十分かどうか、官民の取組が適切に進められているかどうか等について、プラットフォーム事業者からのヒアリング等を通じて、モニタリングと検証評価を行うとともに、2020年報告書に基づき、偽情報への対応の在り方について、多様なステークホルダーによる協力関係の構築、プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保、ファクトチェックの推進、ICT リテラシー向上の推進など、10 の方向性について、産学官民で連携を行い、取組を進めてます。
「プラットフォームサービスに関する研究会」の以下の会合において、SNS等のプラットフォーム事業者や事業者団体から偽情報対策に関するヒアリングを行いました。
その他、「プラットフォームサービスに関する研究会」の開催状況・会議資料はこちらをご参照ください。
新型コロナウイルスに関する間違った情報や誤解を招く情報(いわゆるデマ・フェイクニュース)の実態把握を行い、今後の対策を行うに当たって参考となる情報を得るため、当該情報に関する国民の接触・受容・拡散状況や、当該情報流通に関する意識について調査を行いました。
日本におけるフェイクニュースの実態について把握することを目的として、インターネット利用者が、フェイクニュースにどの程度接触しており、拡散経験があるか等の調査を行いました。
新型コロナウイルス及び米国大統領選挙に関する間違った情報や誤解を招く情報(いわゆるデマ・フェイクニュース)の実態把握を行い、今後の対策を行うに当たって参考となる情報を得るため、当該情報に関する国民の接触・受容・拡散状況や、当該情報流通に関する意識について調査を行いました。
日本における偽情報流通の実態や特徴を把握することを目的として、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国の10〜60代の男女を対象にウェブアンケートを実施し、国際比較および過去調査との時系列比較を行いました。
日本における偽・誤情報流通の実態や特徴を把握することを目的として、日本、アメリカ、イギリス、フランス、韓国の10〜60代の男女を対象にウェブアンケートを実施し、国際比較および過去調査との比較を行いました。
諸外国における偽・誤情報に関する政策動向やファクトチェックの取組の状況、メディア情報リテラシー等に関する取組状況について調査を行いました。
偽・誤情報の流通の問題の顕在化をはじめとする、インターネット上で流通する違法有害情報の問題については、こうした情報を発信する側に対する対応のみでは十分ではなく、受信するユーザーの側のメディア情報リテラシー※の向上を促すことが必須とされています。
こうした課題に対処するため、メディア情報リテラシー向上の総合的な推進に資する目的で、メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査を実施するとともに、偽・誤情報対策のための啓発教育教材とその効果検証手法を開発し、これらを用いた講座をモデル的に実施しました。
※メディアリテラシーと情報リテラシーを統合した概念であり、ニュースリテラシーやデジタルリテラシーといった他の様々な関連するリテラシーの概念を包含する。
偽・誤情報を知り、それに備えることができるようになるための教材を作成しました。本教材を活用して講座を開催される方向けに、講師用ガイドラインもご用意していますので、各種講座においてぜひご活用ください。
下記サイトにて、啓発教育教材等の概要資料、講座実施の手引きを掲載しているほか、啓発教育教材および講師用ガイドラインをパワーポイント形式にてダウンロードすることができますので、ご参照ください。
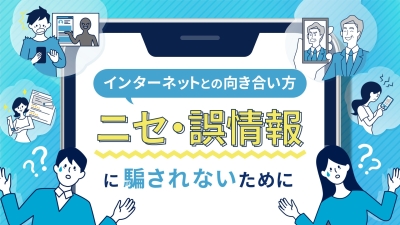
プラットフォームサービスに関する研究会の各報告書や実態調査の結果を踏まえ、民間の取組にも期待しつつ、SNS等のプラットフォーム事業者や事業者団体の取組について、モニタリングや効果検証を継続的に行っていく予定です。