 アートによる地域振興の成功事例の一つとして別府が挙げられる。数年前まではおよそ関心を持たなかったはずの若い女性がやってくる街になった。5年前、様々な文化が混浴するような街にしたいと「混浴温泉世界」をキャッチコピーとした現代アートの国際展が始まった。街並みを大幅に整備した訳ではなく、商店街の幾つかの空き店舗などの建物をリノベーションして、展示スペースやステージにしたが、それだけで街のイメージが変わった。アートをやっている街として、いろいろな雑誌やメディアで紹介され、観光雑誌で別府特集が組まれた。その結果、若い女性が訪れるようになり、経済効果ももたらした。今や温泉街のみなさんも応援してくれている。もともと温泉街や観光の再生について考えていた地域の経済人の活動の中にアートが入ったことによって一気に飛躍できたのだが、いずれにしてもアートが別府のイメージを変えた。
アートによる地域振興の成功事例の一つとして別府が挙げられる。数年前まではおよそ関心を持たなかったはずの若い女性がやってくる街になった。5年前、様々な文化が混浴するような街にしたいと「混浴温泉世界」をキャッチコピーとした現代アートの国際展が始まった。街並みを大幅に整備した訳ではなく、商店街の幾つかの空き店舗などの建物をリノベーションして、展示スペースやステージにしたが、それだけで街のイメージが変わった。アートをやっている街として、いろいろな雑誌やメディアで紹介され、観光雑誌で別府特集が組まれた。その結果、若い女性が訪れるようになり、経済効果ももたらした。今や温泉街のみなさんも応援してくれている。もともと温泉街や観光の再生について考えていた地域の経済人の活動の中にアートが入ったことによって一気に飛躍できたのだが、いずれにしてもアートが別府のイメージを変えた。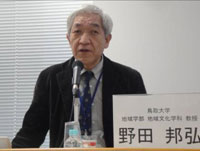 横浜市の創造都市は、1985年に始まった「欧州文化都市」をベースにしている。この取組はEUが指名した都市が1年間集中的にいろいろな文化事業を行うもので、財源はEUが負担し、都市は公募され審査を経て決定される。今は年間2都市でやっている。この事業は当初、文化や芸術の活性化のために始まったが、次第に地域再生に効果があることがわかり、次第に条件不利地を指名するようになった。この映像は2009年の欧州文化首都になったドイツのエッセンのプログラムのひとつだ。開催都市は都市を売り込む絶好のチャンスであるため、世界に向けてプロモーションビデオを作る。欧州文化首都の全てが上手くいっている訳ではないが、これをきっかけに元気になっている都市も多い。
横浜市の創造都市は、1985年に始まった「欧州文化都市」をベースにしている。この取組はEUが指名した都市が1年間集中的にいろいろな文化事業を行うもので、財源はEUが負担し、都市は公募され審査を経て決定される。今は年間2都市でやっている。この事業は当初、文化や芸術の活性化のために始まったが、次第に地域再生に効果があることがわかり、次第に条件不利地を指名するようになった。この映像は2009年の欧州文化首都になったドイツのエッセンのプログラムのひとつだ。開催都市は都市を売り込む絶好のチャンスであるため、世界に向けてプロモーションビデオを作る。欧州文化首都の全てが上手くいっている訳ではないが、これをきっかけに元気になっている都市も多い。 各地で盛んに行われているアートプロジェクトには、市民の手弁当の予算50万円くらいのものから、「越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内国際芸術祭」など10億円規模のものまで様々だ。経済効果は規模が大きければ得られる。ただし、集客には有名なアーティスト、見栄えのする作品、期間が必要となり、必然的にお金がかかる。しかし、ほとんどのアートプロジェクトは小規模で、文化イベントは首都圏でも集客はせいぜい3千人くらいだ。集客だけならアートでない方が良い。お金をかけずに行うアート活動の意義についてよく考えることが大切だ。
各地で盛んに行われているアートプロジェクトには、市民の手弁当の予算50万円くらいのものから、「越後妻有アートトリエンナーレ」や「瀬戸内国際芸術祭」など10億円規模のものまで様々だ。経済効果は規模が大きければ得られる。ただし、集客には有名なアーティスト、見栄えのする作品、期間が必要となり、必然的にお金がかかる。しかし、ほとんどのアートプロジェクトは小規模で、文化イベントは首都圏でも集客はせいぜい3千人くらいだ。集客だけならアートでない方が良い。お金をかけずに行うアート活動の意義についてよく考えることが大切だ。加藤種男氏
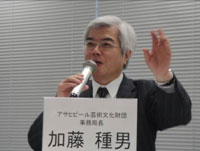 今、世の中では市場や競争だけが正しいという風潮がある反面、相互扶助も重要だという認識も強くなっている。功利的には何の効果もないが故にアートは、社会の中でみんなが助け合って生きていこうとするときには結構力強い味方になる。その一方で、先ほどの話のとおり、アートには外から人を呼ぶインパクトも秘めている。
今、世の中では市場や競争だけが正しいという風潮がある反面、相互扶助も重要だという認識も強くなっている。功利的には何の効果もないが故にアートは、社会の中でみんなが助け合って生きていこうとするときには結構力強い味方になる。その一方で、先ほどの話のとおり、アートには外から人を呼ぶインパクトも秘めている。
アートプロジェクトには、民間が主導するタイプと行政が主導するタイプがあるが、いずれにせよ、両者がうまくかみ合っているケースは、批判も含め議論を丁寧にしている。アートの一番おもしろいところは、意表を突かれるというか、まったく想定していないものが生まれてくること。これがアートの価値だ。そこを双方がキチンと議論した上で認識することが大切だ。
また、アートによる地域振興を進めるには、たとえば、行政とアーティスト、たとえば、現場の若い専門家たちと決定権のある人々など、ものの見方や価値観が異なる両者を如何につなげるが重要だ。両方の言語を駆使しながら通訳をして、双方を繋いでいくことがポイントとなろう。
野田邦弘氏
 官と民それぞれWin・Winの関係にすることが絶対に必要で、これがないと持続可能にはならない。それができない一つの理由は、行政の担当者が人事異動でどんどん変わるからだろう。当然、民間にも課題は沢山ある。その中でうまく組んでいる事例を見ると、やはり目標を共有している。目標が共有されているわけだから、成果が出なかったら交代いう約束がちゃんとできる。そういう仕組みを考えること。横浜がうまくいったのは、委員会で目標評価制度を作って、それで動かし始めた。そして、始まったらNPOや民間の人に任せてゴチャゴチャ言わない。その代わり2年、3年後にチェックさせてもらいました。制度設計をきっちりやって、目標を共有して、あとは任せて口を出さないが評価はする。これが大切な一つのポイントだと思っている。
官と民それぞれWin・Winの関係にすることが絶対に必要で、これがないと持続可能にはならない。それができない一つの理由は、行政の担当者が人事異動でどんどん変わるからだろう。当然、民間にも課題は沢山ある。その中でうまく組んでいる事例を見ると、やはり目標を共有している。目標が共有されているわけだから、成果が出なかったら交代いう約束がちゃんとできる。そういう仕組みを考えること。横浜がうまくいったのは、委員会で目標評価制度を作って、それで動かし始めた。そして、始まったらNPOや民間の人に任せてゴチャゴチャ言わない。その代わり2年、3年後にチェックさせてもらいました。制度設計をきっちりやって、目標を共有して、あとは任せて口を出さないが評価はする。これが大切な一つのポイントだと思っている。
あと、外から人を呼ぶためには、レベルの高いものがないと来ない。それには費用がかかる。観光客を呼んで経済効果を上げるにはコストがかかるという点を行政は理解することが大切だ。
熊倉純子氏
 欧米には、作品プロジェクトはあるが、行政と市民と若いアーティストたちが街を一緒に共創する文化はない。アーティストが市民と同じ目線で物を考えるという発想は日本人にしかない。これからの市民文化というのは、出し物の観客として住民を呼ぶのではなく、街でプロジェクトを一緒に行い、文化でどう地域に働きかけていくのかを一緒に考えていくスタイルが重要かと思う。その方が皆生き生きし、もっと地域とつながると考えている。
欧米には、作品プロジェクトはあるが、行政と市民と若いアーティストたちが街を一緒に共創する文化はない。アーティストが市民と同じ目線で物を考えるという発想は日本人にしかない。これからの市民文化というのは、出し物の観客として住民を呼ぶのではなく、街でプロジェクトを一緒に行い、文化でどう地域に働きかけていくのかを一緒に考えていくスタイルが重要かと思う。その方が皆生き生きし、もっと地域とつながると考えている。
一方、プロを活かす場合は、動いてもらうために、あの手この手を尽くすのがマネジメントだろう。それには街の人を必死にさせる。その前に担当者が必死になる。そして、「どうしてもやりたい」という意識をキチンと作る。
そして、やるのだったら、ちゃんと汗かいて、どこにニーズがあるのかを探る。ほかにはないプライスレスという演出を考える。おもしろいことに仕立ててくれるプロフェッショナルを企画に入れるのも一つの方法だ。


