|
4 放送サービスの拡充に向けて(1)都市型CATVの開局
CATVの新たな展開として,大規模,多チャンネルでかつ双方向機能を有する,いわゆる都市型CATV構想が進められている。 (2)国際放送の充実 我が国の国際放送は,国際理解の増進や海外在留邦人への情報提供を目的として,NHKにより「ラジオ日本」の名称で,1日延べ40時間,21の言語で全世界に向けて短波放送によって行われている。我が国の国際社会における地位の向上や経済摩擦の激化等に伴い,諸外国の我が国に対する正しい理解,認識を得る上で,国際放送の果たす役割はますます重要なものとなってきている。このため,従来から郵政省では国際放送の充実・強化に努めており,次のように主として受信状況の改善に重点を置いた取組を行っている。(第1-2-17図参照)。 (国内送信所の整備・増力) KDD八俣送信所(茨城県)の老朽化した送信設備を最新・高出力の設備にするため,59年度から4か年計画で整備・増力工事が行われている。これにより,主に東南アジア等わが国の近隣地域において受信改善が図られる予定である。 (海外中継の実施) 遠隔地域の受信改善については,海外中継によることが効果的であることから,これまでもその実施に努め,対象地域の受信改善に大きな効果をあげてきた。現在,アフリカのガボン共和国(モヤビ送信所)及びカナダ(サックビル送信所)の協力を得て国際放送の海外中継が行われている。 モヤビからの中継については59年4月より実施し,当初1日6時間であった欧州,中東,北アフリカ向けを61年4月から1日7.5時間に拡大するとともに,62年4月から南米向けに1日4時間の放送を新たに開始した。また,サックビルからの中継は,61年10月より北米向けに実施し,当初1日1時間であったものを,62年4月から1日4時間に拡大した。遠隔地域への国際放送については,南西アジア地域など一部にまだ受信状態の不安定な地域が残っているため,今後も受信状態改善への取組が必要となっている。 また,互いに相手国の送信施設を利用して国際放送の中継放送を行う,相互交換中継を我が国においても実施できるようにするため,62年6月,放送法の改正が行われた。 (映像メディアの活用) 今日極めて大きな影響力を有するテレビジョン放送等の映像メディアを諸外国への情報提供手段として活用することは,我が国に対する理解,認識を深める上で効果的であり,我が国においても関係機関で検討などを行っているところである。 (3)FM多重放送の実用化 FM多重放送は,FM放送の電波のすき間を利用して,FM放送とは別の音声や文字,図形等を送る新しい放送である。FM多重放送のうち,音声多重放送としては教育番組等の放送が考えられ,文字多重放送としては,FM放送の番組案内や音楽の曲名等の表示が考えられている。このFM多重放送を実現するため,電気通信技術審議会で技術基準の検討が行われ,合わせて,研究開発が進められてきたが,61年12月から62年2月まで行われた野外実験により,実用化の見通しが得られるに至った。 これを受けて,62年6月には,FM多重放送の実用化に対応するための放送法及び電波法の改正が行われた。郵政省では,今後,FM多重放送の早期実用化を目指して準備を進めることとしている。 (4)BS-2bによる放送開始 我が国の衛星放送については,59年5月からNHKがBS-2a(本機)を利用して,1チャンネルの試験放送を行ってきたが,61年2月にBS-2b(予備機)が打ち上げられ,同年12月から2チャンネルの試験放送が開始された。また,同年末から62年の年始にかけて特別編成による衛星放送が実施された。62年3月末における衛星放送の受信世帯数は,約13万6,600世帯(NHK調べ)である。衛星放送はテレビジョン放送の難視聴解消に大きな成果を上げてきたが,62年6月には,難視聴解消とともに衛星放送をより一層普及促進させるため,BS-2bの2チャンネルのうちの1チャンネルを利用して,衛星放送独自の番組を基本として行う放送が可能となるよう,BS-2に関する放送の免許方針の修正が行われた。 これに基づき,同年7月にNHKは新しい番組編成による試験放送を開始した。衛星放送の普及促進を図るため,今後とも番組編成上の工夫のほか,BS-2を利用した新しい放送技術の開発実験等が行われる予定である。 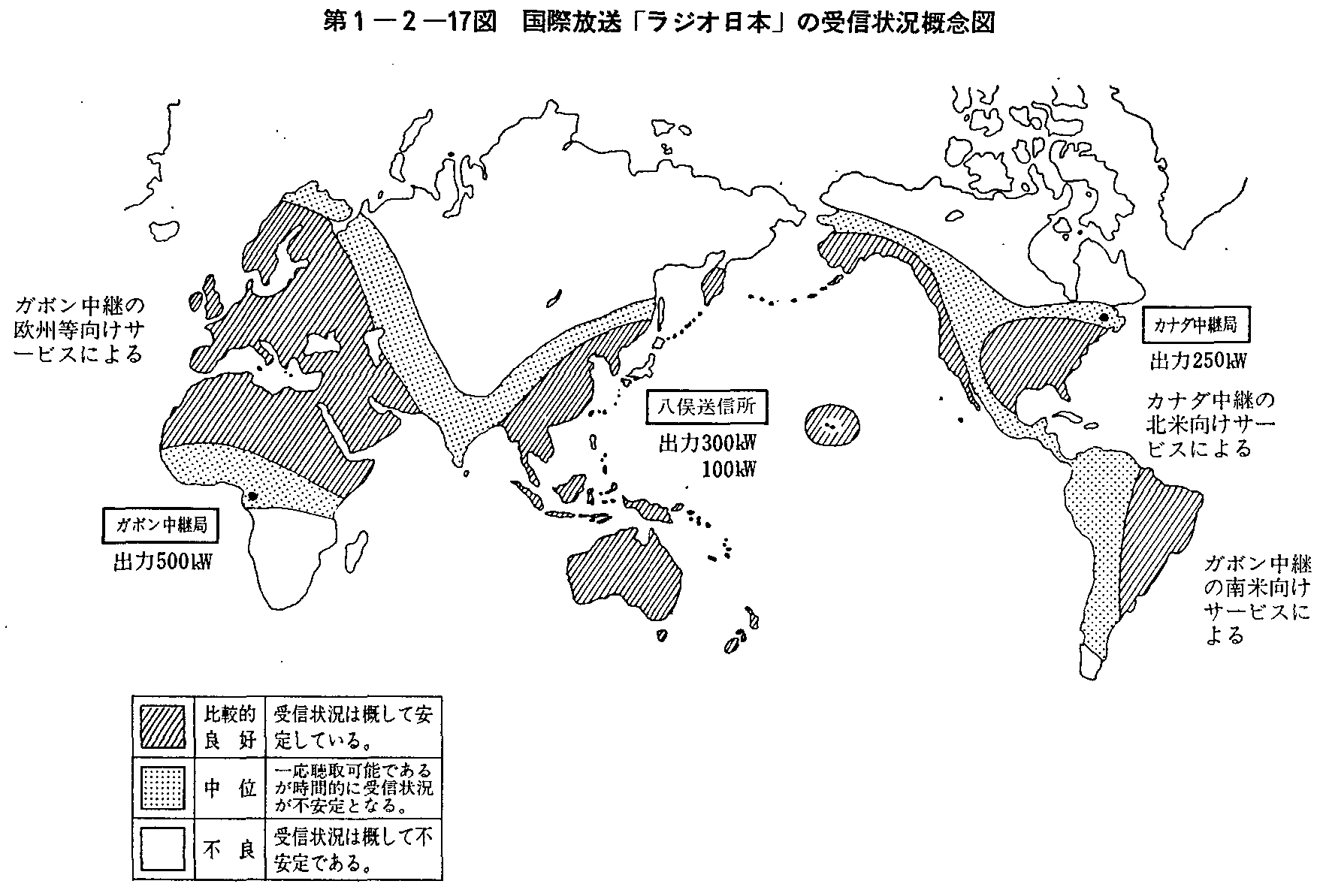
|