|
2 暮らしに対する通信の影響暮らしの中に浸透している通信は,暮らしに対して様々な影響を与えている。(郵 便) 郵便についてみると,定期刊行物の頒布,通信教育等を容易にすることによって,社会文化の啓発,向上に貢献してきている。また,年賀郵便を除いても,一世帯当たり年間約220通(60年度)もの郵便物を受けとっていることからも分かるように,郵便は,国民の暮らしに浸透している。また,郵便は,古くから文字文化ともいうべき儀礼的な文化を浸 透させてきたということができる。とりわけ,年賀状に代表される郵便のもつ儀礼性は今日においても,暮らしの中で大きな役割を果たしている。 (テレビ) テレビについてみると,62年世論調査によれば,テレビが人々に与える影響として,「政治や社会問題に対する関心を増す」,「青少年の非行や暴力行為を助長する」,「趣味や教養が豊かになる」といった回答が多く,テレビが人々の意識や行動に強い影響力をもつものとして認識されていることが分かる(第2-1-3図参照)。 (電 話) 電話についてみると,59年の世田谷電話局とう道火災では,銀行等のオンラインシステムを利用することができなくなったほか,警察,消防等の公共機関の業務にも大きな支障が出た。これは,電話が直接又は間接に国民の暮らしに大きな影響を与えていることを示すものである。 また,62年世論調査では,電話の利便性として,「わざわざ出掛けてゆく手間が省ける」という回答が72.3%に上ることから,電話は,国民の行動形態を変えている。 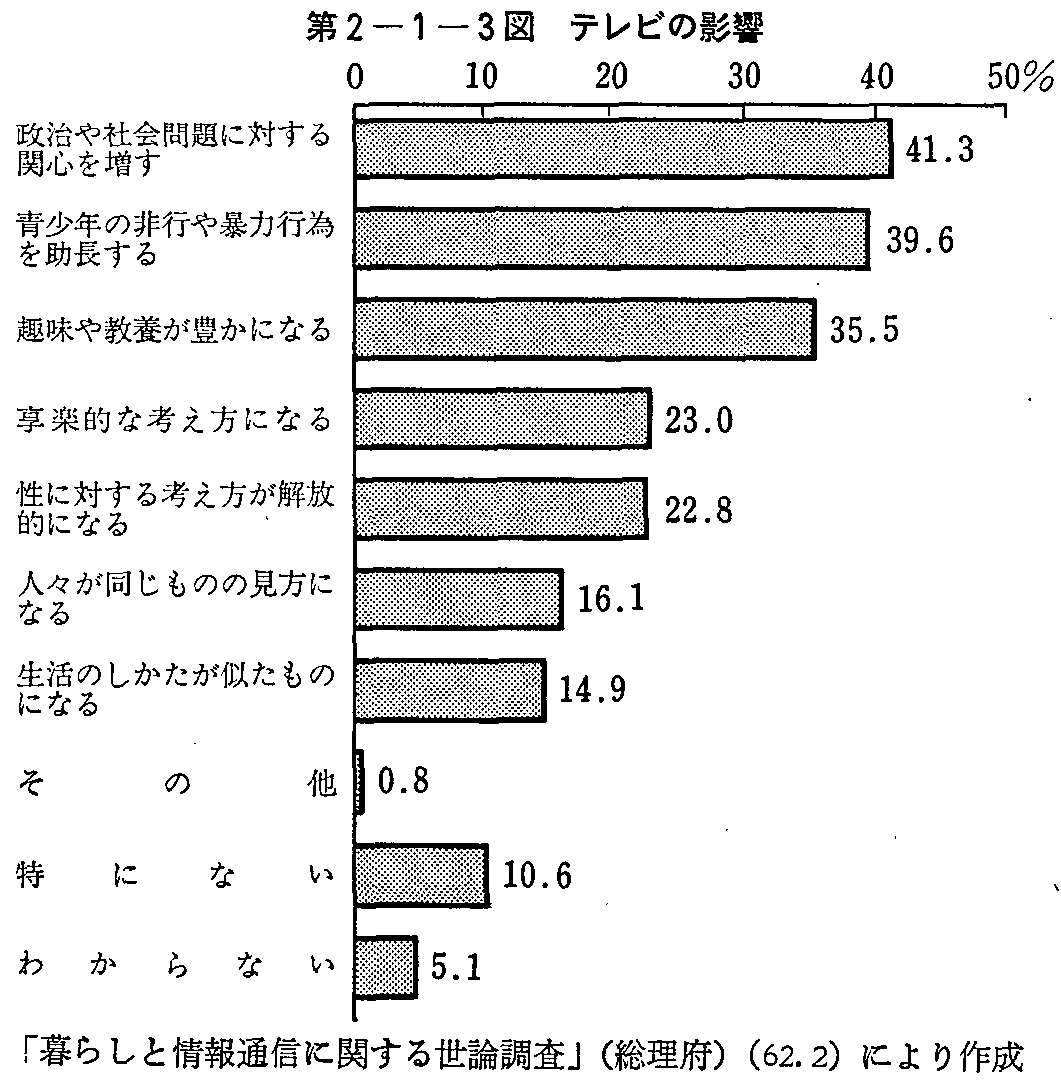
|