3 情報化の進展と地域性
地域の現状をみるため,ここでは情報化との関係が強い県民所得等の各指標の推移等について分析し,さらに,それらの指標と情報化の関連性について分析する。
(1)地域の現状
ア 県民所得
地域の経済状態を示す代表的な指標に県民所得がある。
59年度の地域別県民所得は,第3-1-17図のとおりである。
我が国の国民所得は,50年度は125兆9千億円,59年度は247兆4千億円と9年間で1.96倍となっている。
県民所得の上位3地域は,東京,大阪及び神奈川であり大都市圏に集中している。59年度の我が国の国民所得に占める割合は,東京が14.4%(50年度は14.8%),大阪が8.2%(同8.5%),神奈川が6.5%(同6.3%)と東京及び大阪のシェアが低下している。下位3地域は鳥取,高知及び島根という過疎地域である。
次に,一人当たり県民所得によって地域別所得格差をみると,30年代後半から50年代初頭までの経済成長の過程において,ほぼ一貫してその格差は縮小していた。その背景としては,[1]地方圏の社会資本の整備,政府の工場分散政策の推進等から,大都市に集中していた工場が地方圏に移り,それによって地方の雇用増と所得の向上がもたらされたこと,[2]地方交付税や公共投資等の財政による地方への所得移転が行われたことなどがある。これを変動係数でみると50年度の15.23%から徐々に低下し54年度には14.12%となった。しかし,55年度からは格差の拡大傾向が始まり,59年度には,15.98%まで拡大し,50年代で最大の格差と
なった(第3-1-18図参照)。
東京を100とした指数でみても,50年度は最低の地方でも東京の5割を超えていたが55年度,59年度と年度が進むほど格差が広がり,59年度では5割未満であった(第3-1-19表参照)。
50年代後半は,県民所得との相関が強い企業活動で主に利用される専用データ通信及びファクシミリの供給情報量が飛躍的に伸びて,通信系供給情報量の地域間格差が出るとともに,県民所得の地域間格差が拡大した時期であり,両者の相関関係を示している。
59年度の一人当たり県民所得の多い地域は,東京,大阪,愛知,神奈川等であり,通信系供給情報量の多い地域とほぼ同じである。
イ 事業所数
通信系供給情報量の大半は,主に企業で利用されているメディアによる供給情報で占められており,近年の情報化は企業の情報化を中心に進んでいる。また,民間放送のスポンサー,新聞及び雑誌の広告出稿者の大半は事業所である。このことから事業所数と情報化は密接な関係にあると考えられる。
61年の地域別事業所数は,第3-1-20図のとおりである。
全国の事業所数は,50年の559万2千事業所から61年の670万9千事業所へと20.0%増加(年平均伸び率1.7%)している。
61年の事業所数の上位3地域は,東京,大阪及び愛知であり,全国の事業所数に対する割合は東京が11.9%(50年は12.2%),大阪が8.0%(同7.9%),愛知が5.5%(同5.4%)となっており,東京のシェアがやや低下しているがシェアの変化はほとんどない。
伸び率(61年/50年)の高い地域は埼玉,千葉,沖縄,神奈川等があり,東京に隣接する地域が目立っている。これは,各種機能が東京に集中しており,それを求めて東京に進出しようとした事業所が多く,東京における活発なオフィスビルの建築にもかかわらず,それを上回る事務
所需要があり,賃料の上昇もあって東京周辺部での需要が高まっていることなどが原因と考えられる。
61年の一人当たり事業所数の多い地域は,福井,石川,山梨,東京等である。しかし,事業所当たり従業者数でみると,東京が10.0人と事業所規模が全国一大きいのに対し,他の3地域は7人以下であり事業所規模が小さいものとなっている。東京周辺の地域である埼玉,千葉及び神奈川では事業所当たりの従業者数が増加しており,徐々に規模の大きい
事業所が増加していることを示している。
一方,伸び率の低い地域には,富山,島根,新潟等の日本海沿岸の地域が多い。
ウ 人口
60年の地域別人口は,第3-1-21図のとおりである。
全国の人口は,50年の1億1,194万人から60年の1億2,105万人へと8.1%(年平均伸び率0.8%)増加している。
日本経済は二度の石油危機等により,高度成長から低成長への転換を余儀なくされた。これにつれて地方圏から大都市圏への人口集中の動きは鎮静化し,50年代に入ると,Uターン,Jターンといった大都市圏から地方圏への人口の逆流現象もみられるようになった。しかし,50年代後半以降は地方経済の低迷に伴い人口移動でも大都市圏への集中傾向が再び現れ,とりわけ東京圏への一点集中傾向が強まっている。
60年の人口社会増加数をみると,神奈川,埼玉及び千葉が圧倒的に多く全体の73.4%を占めている(第3-1-22図参照)。
人口の伸び率(60年/50年)でみても,伸び率の高い地域は千葉,埼玉,奈良,茨城,神奈川等となっており,東京圏の伸びが目立っている(第3-1-23表参照)。
工 旅客数
情報の伝達は通信メディアにおいて主に行われるが,同時に人と人との直接の接触においても行われる。ここでは,人と人との接触を示す指標として旅客数を取り上げる。
我が国の1年間の交通機関(国鉄,民鉄,自動車,旅客船及び定期航空)を利用した総旅客数は,50年度の延べ461億5千万人から60年度は538億3千万人で,76億8千万人増加(16.6%増)した。
総旅客数から定期旅客数を除いた不定期旅客数は,50年度の延べ349億7千万人から60年度は418億3千万人となっており,68億6千万人の増加(19.6%増)であった。不定期旅客数の伸びが総旅客数の伸びを上回っている。
60年度の地域別発旅客数は,第3-1-24図のとおりである。
60年度の地域別発旅客数の多い地域は,東京,大阪,神奈川等となっており,人口集中地区人口比率(人口集中地区人口/人口総数)が比較的高く経済活動が活発な地域である。逆に少ない地域は県民所得の低い過疎地域である鳥取,高知,島根等であった。
60年度の一人当たり移動回数(旅客数/人口)は,第3-1-25図のとおりである。
一人当たり年間移動回数の全国平均は,50年度に412回であったものが60年度には445回となっている。
60年度の一人当たり年間移動回数の多い地域は東京,神奈川,大阪等であった。とりわけ東京は,全国平均の2倍以上の回数であり,人と人との直接接触による情報活動が活発であることが分かる。一方,年間移動回数の少ない地域をみると愛媛,高知,徳島等であり,四国地方が目立っている。
(2)地域の現状と情報化
ここでは,地域別各情報量(総供給情報量,総消費情報量,通信系供給情報量,放送系供給情報量,放送系消費情報量,輸送・空間系供給情報量,輸送・空間系消費情報量,専用データ通信供給情報量,ファクシミリ供給情報量及び郵便供給情報量)を被説明変数とし,地域別各指標(県民所得,事業所数,人口及び旅客数)を説明変数として,単純最小二乗法により分析する。
ア 県民所得と情報量
県民所得と各情報量との相関は,ファクシミリ供給情報量を除いて高くなっている。特に,マス・メディアの影響の強い総供給情報量,放送系供給情報量,輸送・空間系供給情報量及び輸送・空間系消費情報量と県民所得との相関係数は,他の三つの説明変数との相関係数より高く
なっている。
総供給情報量,放送系供給情報量,輸送・空間系供給情報量及び輸送空間系消費情報量と県民所得との関係は第3-1-26図のとおりである。
各情報量と県民所得(X1)との関係は,総供給情報量(Y1)については,
Y1(X1)=-1.36882×1015+1.75046×109X1-12.0817X12
(t=27.40) (t=-5.94)
(R=0.99355)
放送系供給情報量(Y4)については,
Y4(X1)=-1.37135×1015+1.74455×109X1-12.1551X12
(t=27.30) (t=-5.97)
(R=0.99347)
輸送・空間系供給情報量(Y6)については,
Y6(X1)=2.17711×1012+5.91108×106X1+0.0579468X12
(t=28.10) (t=8.65)
(R=0.99762)
輸送・空間系消費情報量(Y7)については,
Y7(X1)=6.63951×1011+3.39488×106X1-0.0220634X12
(t=27.23) (t=-5.56)
(R=0.99365)
であった。総供給情報量と放送系供給情報量はX12部分の係数がマイナスを示しており,県民所得が増加してもある程度のところで情報量の増加は頭打ちとなっている。これは,両情報量ともテレビジョン放送の影響が大きく,郵政省が情報の地域間格差を是正するために積極的に周波数の割当てを進めたため,情報供給源の集中が防がれたことなどによる。
同じマス・メディアでも新聞の影響が強い輸送・空間系供給情報量では,X12部分の係数がプラスを示しており,県民所得の増加の割合以上に情報量が増加することを示して,政策的配慮がないと,経済力等の強い地域へ情報が集中することを示している。
このことは,通信系供給情報量及びその構成メディアである専用データ通信供給情報量からもいえる(第3-1-27図参照)。
両情報量と県民所得との関係は,通信系供給情報量(Y3)については,
Y3(X1)=2.86333×1011+21105X1+0.015315X12
(t=0.64) (t=14.69)
(R=0.98678)
専用データ通信供給情報量(Y8)については,
Y8(X1)=2.60585×1011-48393.9X1+0.0151221X12
(t=-1.65) (t=16.19)
(R=0.98566)
であり,X12部分の係数がいずれもプラスを示している。
イ 事業所数と情報量
事業所数と各情報量との相関は全般的に高くなっている。特に通信系供給情報量,専用データ通信供給情報量,ファクシミリ供給情報量及び郵便供給情報量と事業所数との相関係数は,他の三つの説明変数との相関係数よりも高くなっている。
専用データ通信及びファクシミリはその利用の大半は企業であること,郵便も事業所差出しが約8割であるが,その影響を裏付けたものとなっている。通信系供給情報量,専用データ通信供給情報量,ファクシミリ供給情報量及び郵便供給情報量と事業所数との関係は,第3-1-28図のとおりである。
各情報量と事業所数(X2)との関係は,通信系供給情報量(Y8)については,
Y8(X2)=1.71912×1011-60135X2+18.0559X22
(t=-0.11) (t=24.88)
(R=0.99567)
専用データ通信供給情報量(Y8)については,
Y8(X2)=1.97707×1011-2.29831×106X2+17.9078X22
(t=-4.68) (t=26.44)
(R=0.99457)
ファクシミリ供給情報量(Y9)については,
Y9(X2)=-5.11735×108+21947.2X2+0.0410504X22
(t=8.60) (t=11.66)
(R=0.99335)
郵便供給情報量(Y10)については,
Y10(X2)=2.5506×1010-1.4679×105X2+1.57001X22
(t=-3.20) (t=24.86)
(R=0.99445)
であった。
各情報量ともX22部分の係数がプラスを示しており,事業所数が増加すると,それ以上の割合で情報量が急激に増加することが分かる。
ウ 人口と情報量
人口は,特に,総消費情報量及び放送系消費情報量との相関係数が高く,他の三つの説明変数との相関係数を上回っている。
総消費情報量及び放送系消費情報量と人口との関係は,第3-1-29図のとおりである。
各消費情報量と人口(X3)との関係は,総消費情報量(Y2)については,
Y2(X3)=4.86773×1012+1.0008×108X3+0.029173X32
(t=16.91) (t=0.05)
(R=0.99249)
放送系消費情報量(Y5)については,
Y5(X3)=1.98591×1012+9.6066×107X3-0.44419X32
(t=16.11) (t=-0.78)
(R=0.99088)
であった。
各消費情報量のグラフはほぼ直線であり,人口が増加するとほぼ一定の割合で消費情報量が増加しているのが分かる。各消費情報量ともマス・メディアであるテレビジョン放送の影響が大きく,一人の人間がマス・メディアを通じて供給される情報を処理(消費)できる量には限界が
あることを示している。
供給情報量と人口との関係をみるため,比較的相関係数が高い総供給情報量と輸送・空間系供給情報量を取り上げると第3-1-30図のとおりである。
各供給情報量と人口(X3)との関係は,総供給情報量(Y1)については,
Y1(X3)=-8.29716×1014+2.62903×109X3+130.749X32
(t=9.30) (t=4.85)
(R=0.98902)
輸送・空間系供給情報量(Y6)については,
Y6(X3)=1.04774×1013+2.68712×106X3+1.76044X32
(t=2.89) (t=19.82)
(R=0.99575)
であった。
両方ともX32部分の係数がプラスを示しており,人口の増加以上の割合で供給情報量が増加しているのが分かる。
工 旅客数と情報量
旅客数と相関関係の強い情報量には,輸送・空間系供給情報量及び郵便供給情報量がある。
輸送・空間系供給情報量及び郵便供給情報量と旅客数との関係は第3-1-31図のとおりである。
各情報量と旅客数(X4)の関係は,輸送・空間系供給情報量(Y6)については,
Y6(X4)=4.86154×1012+3.12113×106X4-0.0037819X42
(t=29.94) (t=-3.52)
(R=0.99560)
郵便供給情報量(Y10)については,
Y10(X4)=1.58472×1010+2706.1X4+0.000070698X42
(t=5.20) (t=13.20)
(R=0.99052)
であった。
輸送・空間系供給情報量と旅客数のグラフはほぼ直線であり,旅客数が増加するとほぼ一定の割合で情報量が増加するのが分かる。
(一層の分析の必要性)
県民所得,人口等の説明変数については,相互に多重共線関係に立っことが予測されること,単年度の分析のみならず各年度ごとの分析,あるいは被説明変数にタイムラグを入れた場合の影響等について今後一層の分析を行う必要がある。
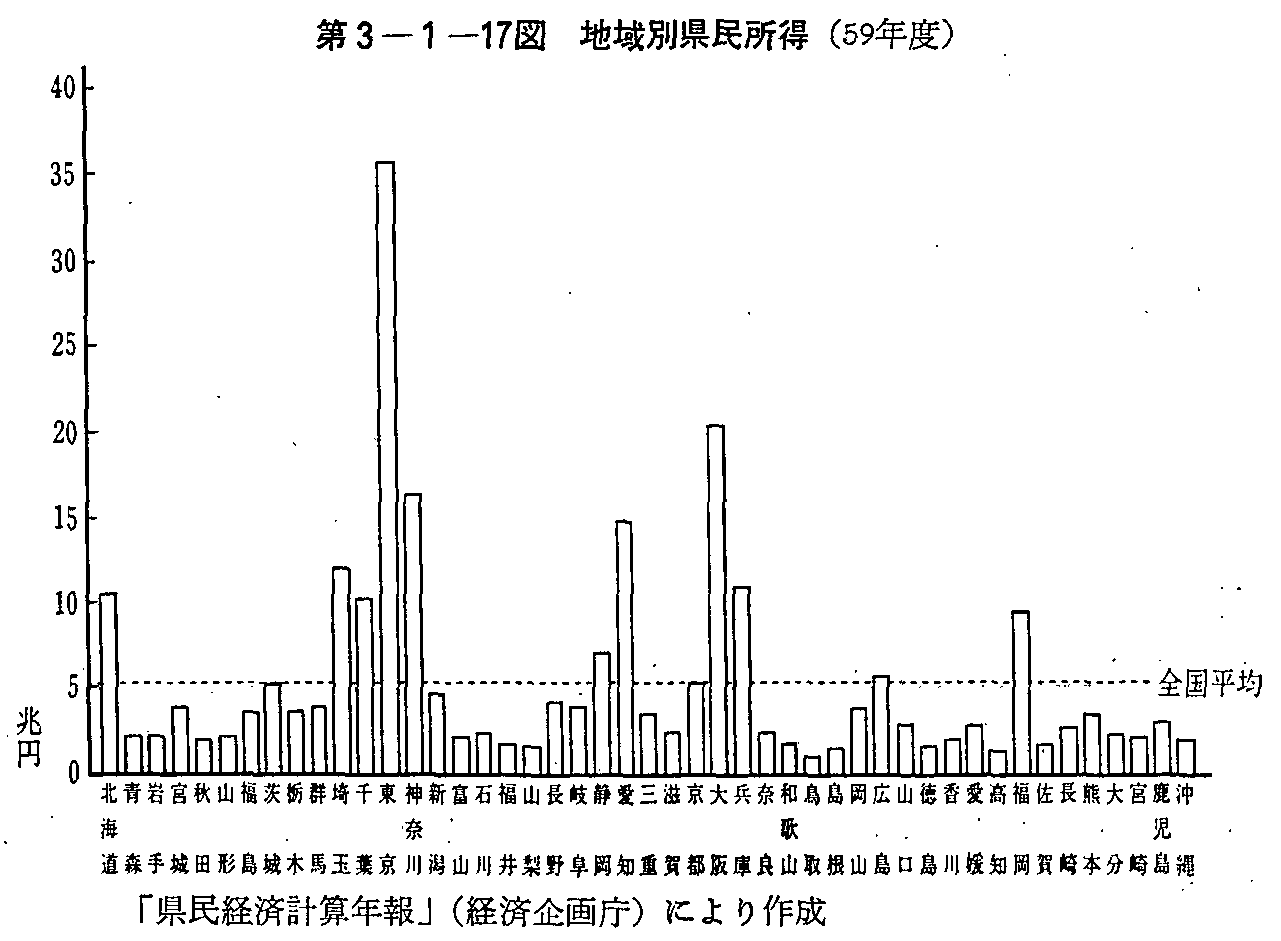
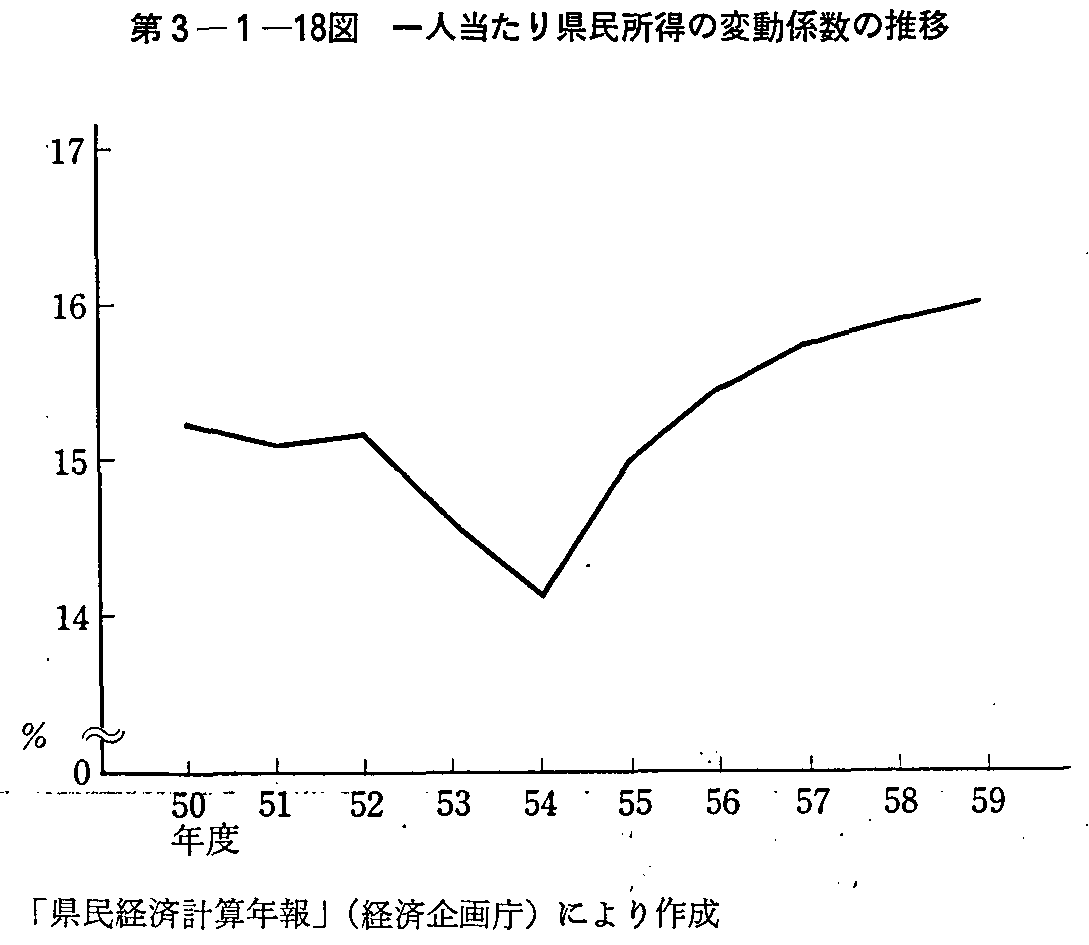
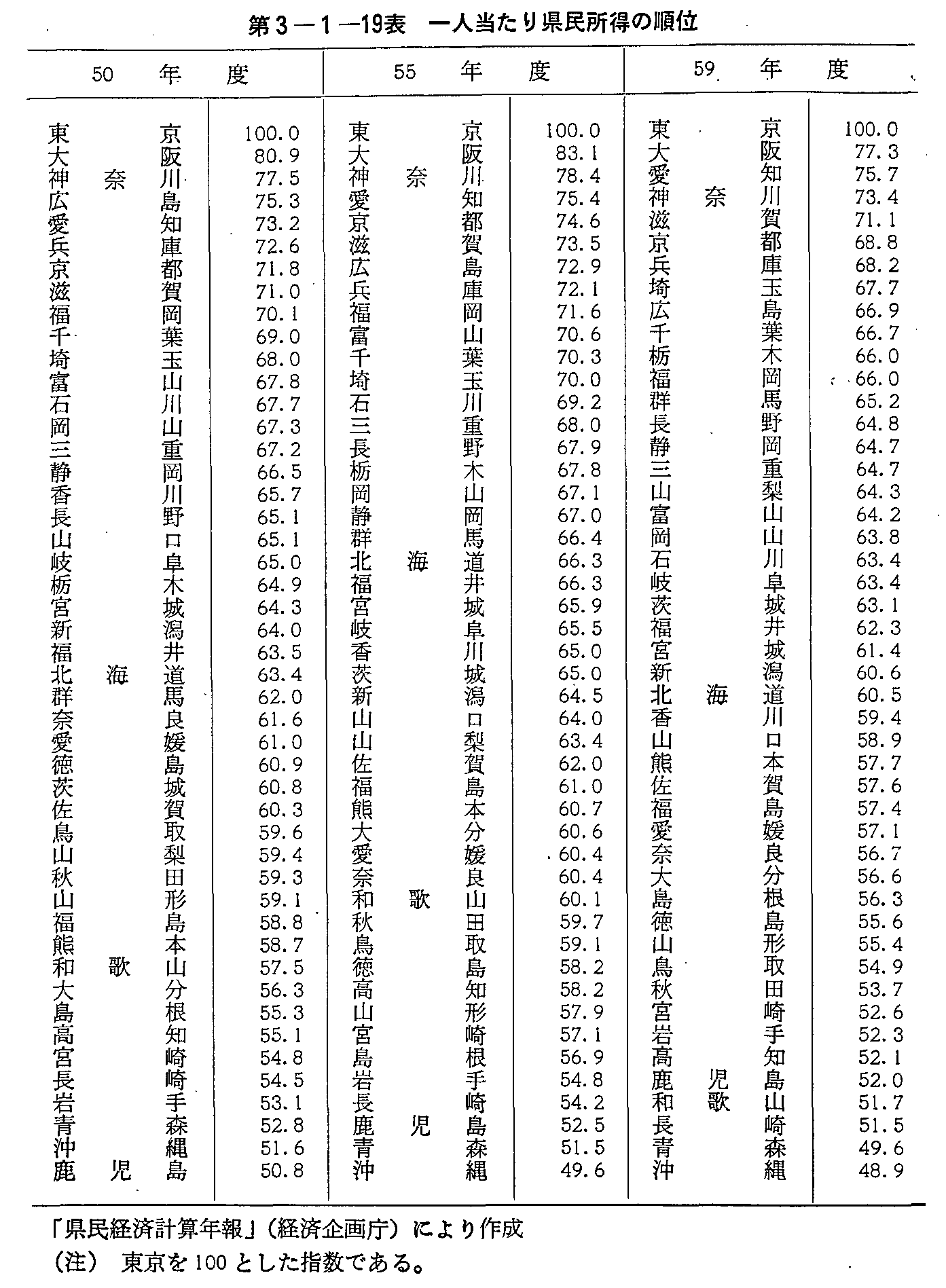
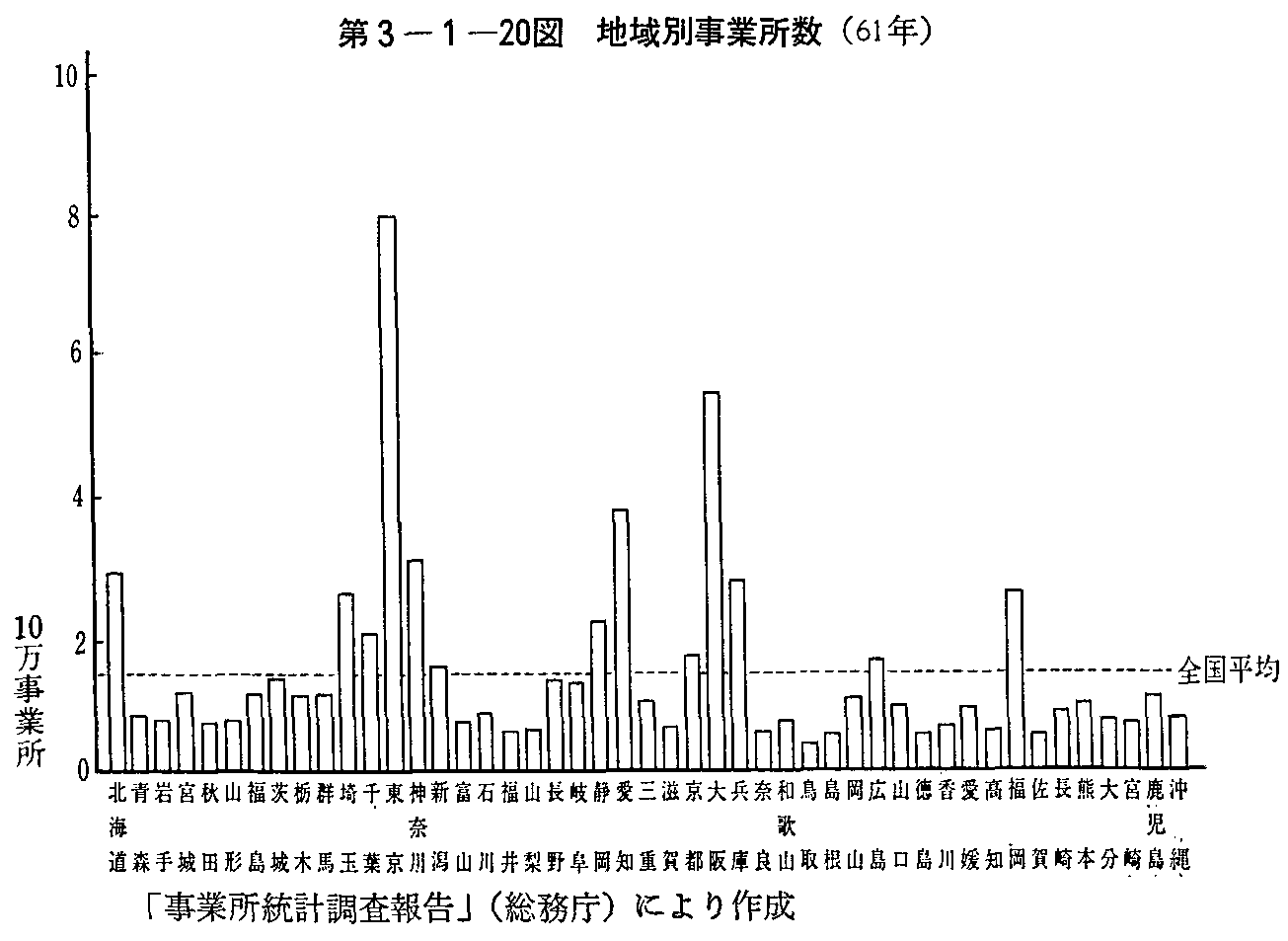
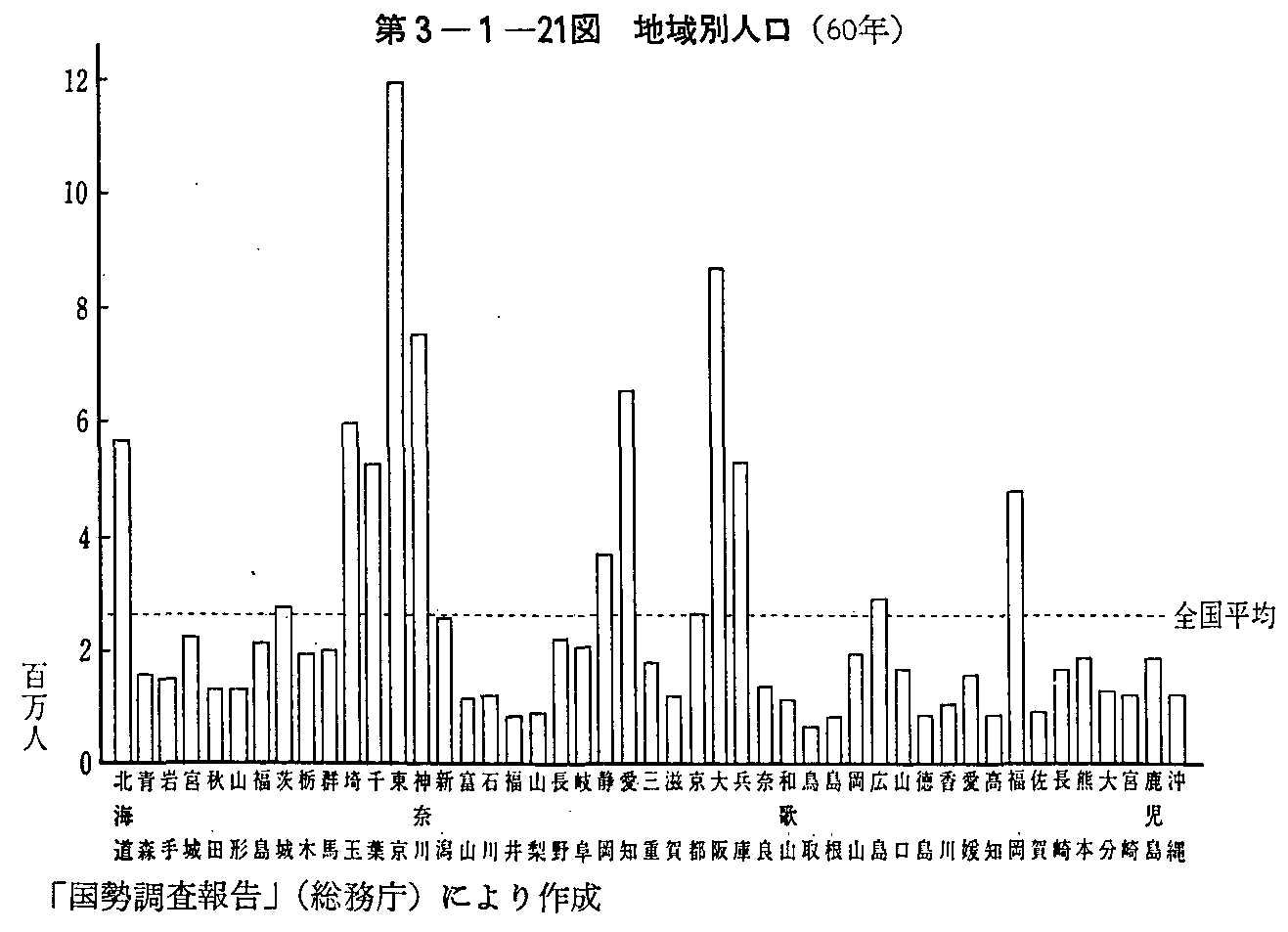
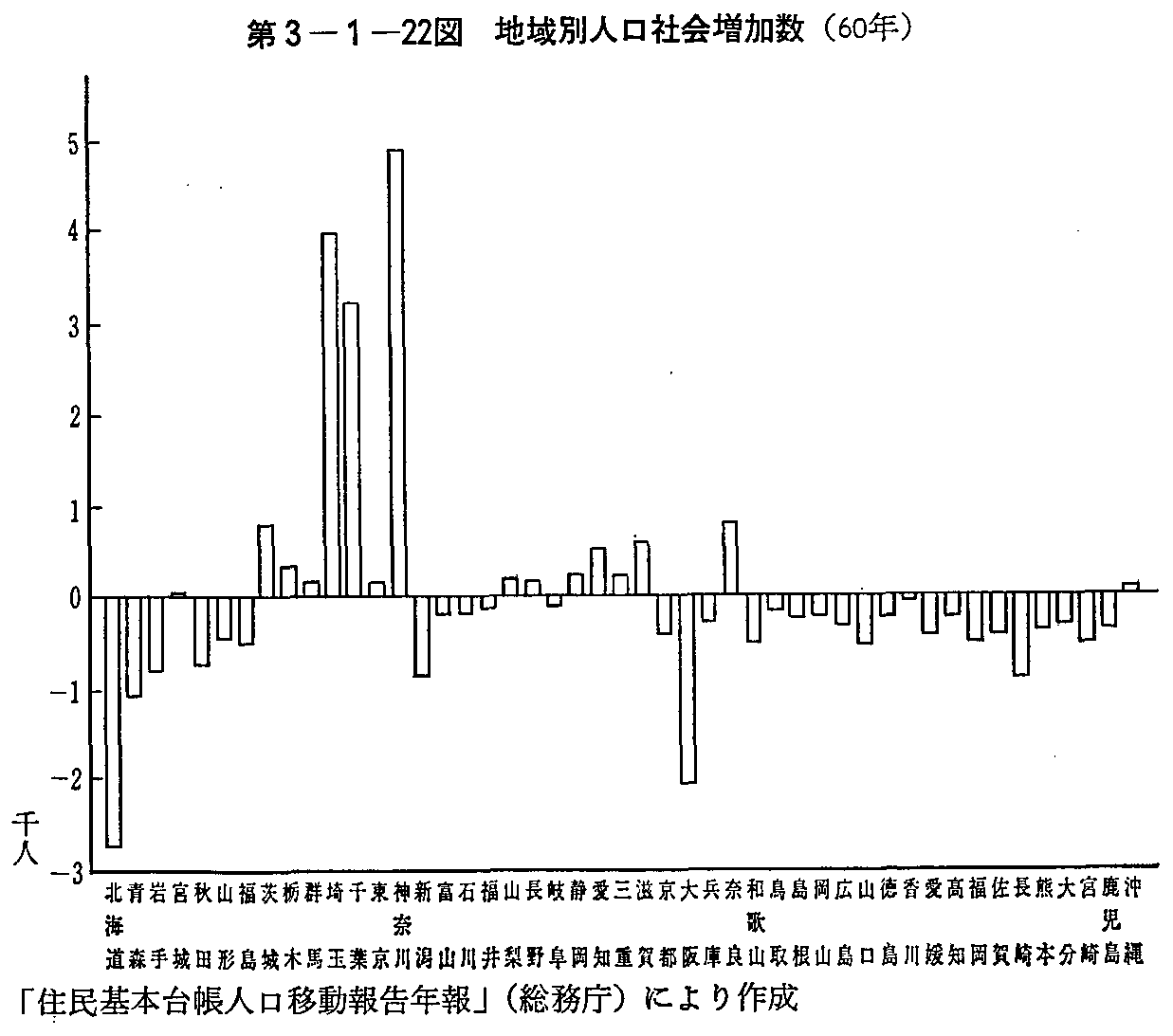
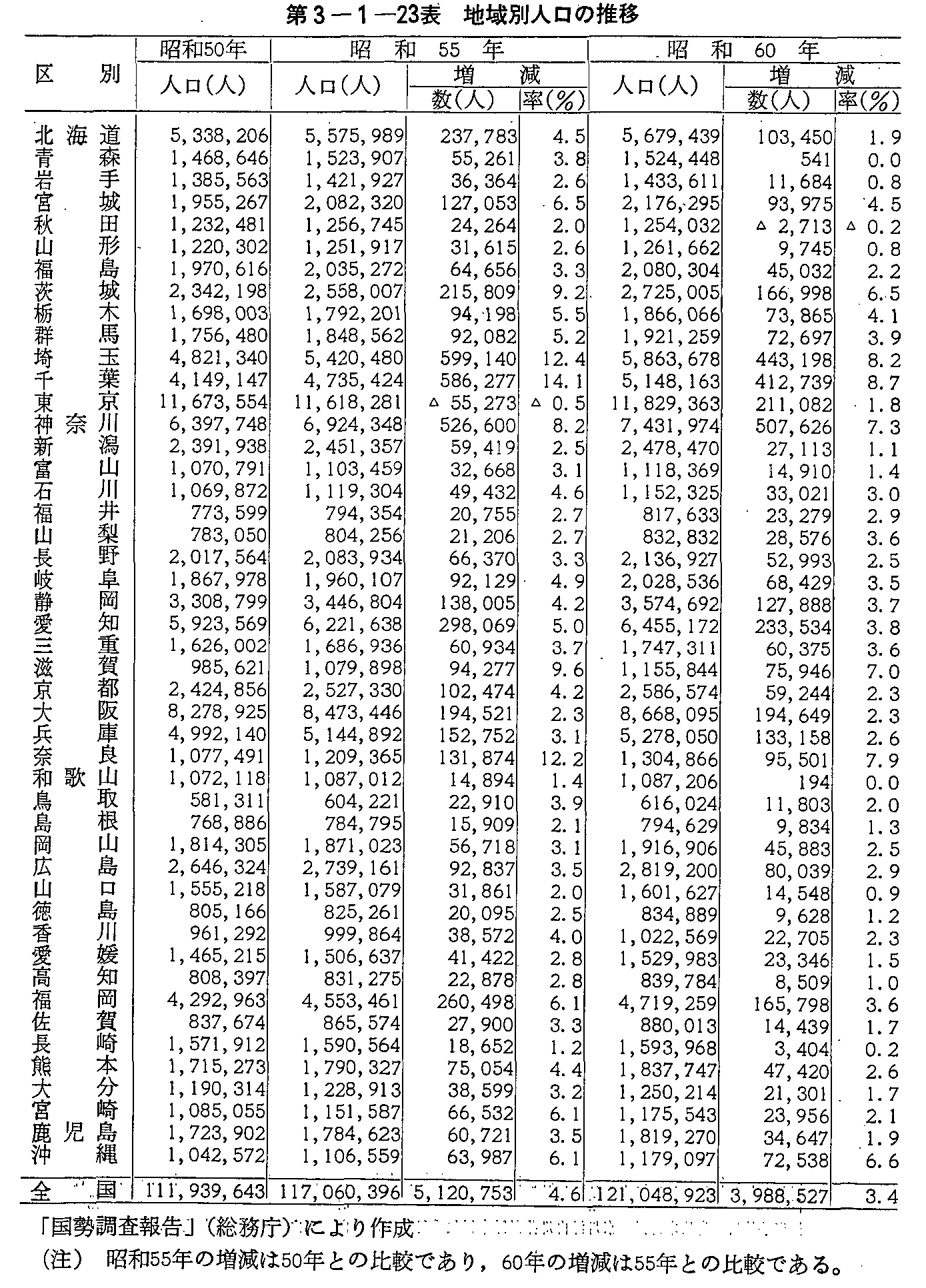
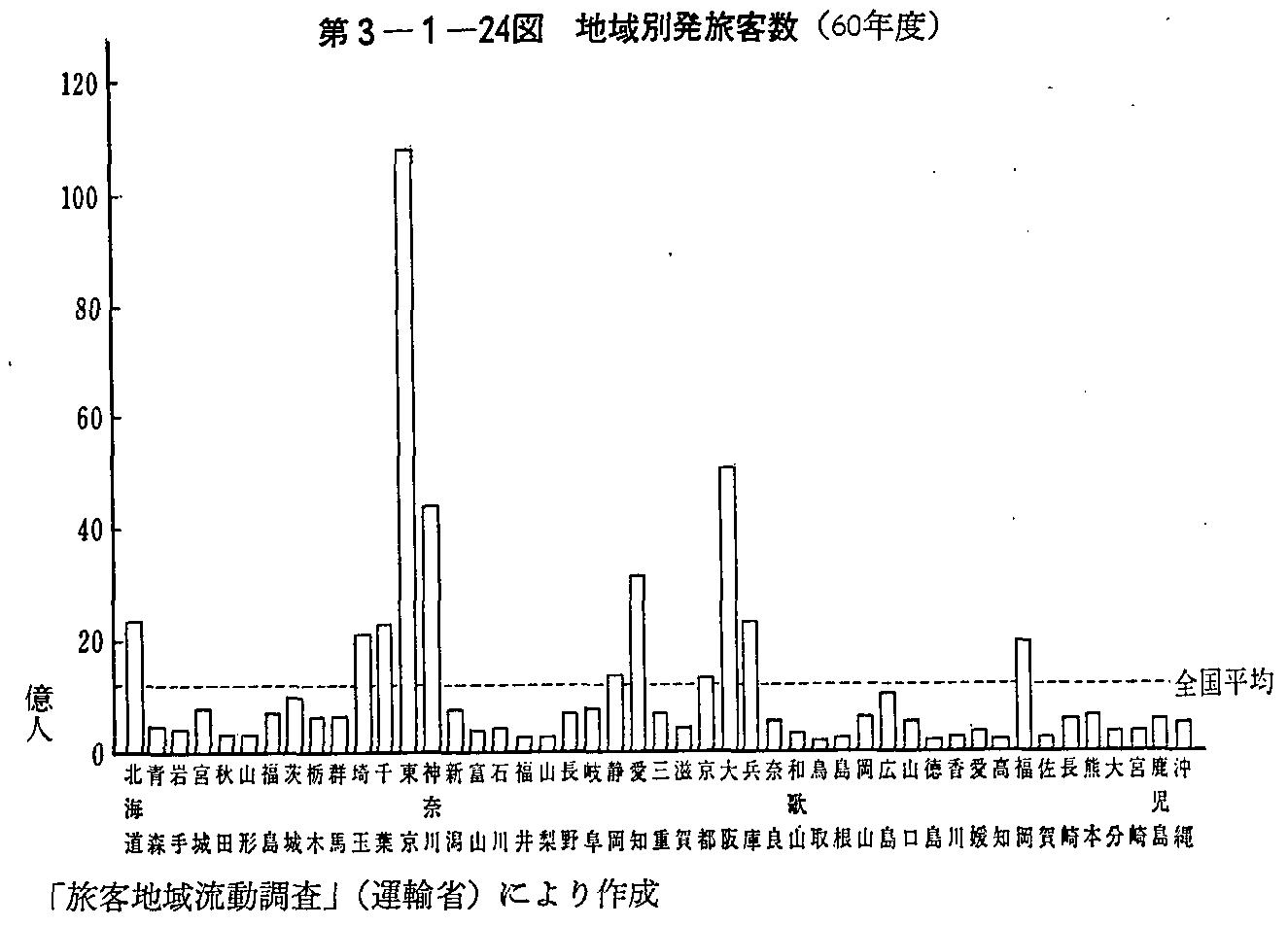
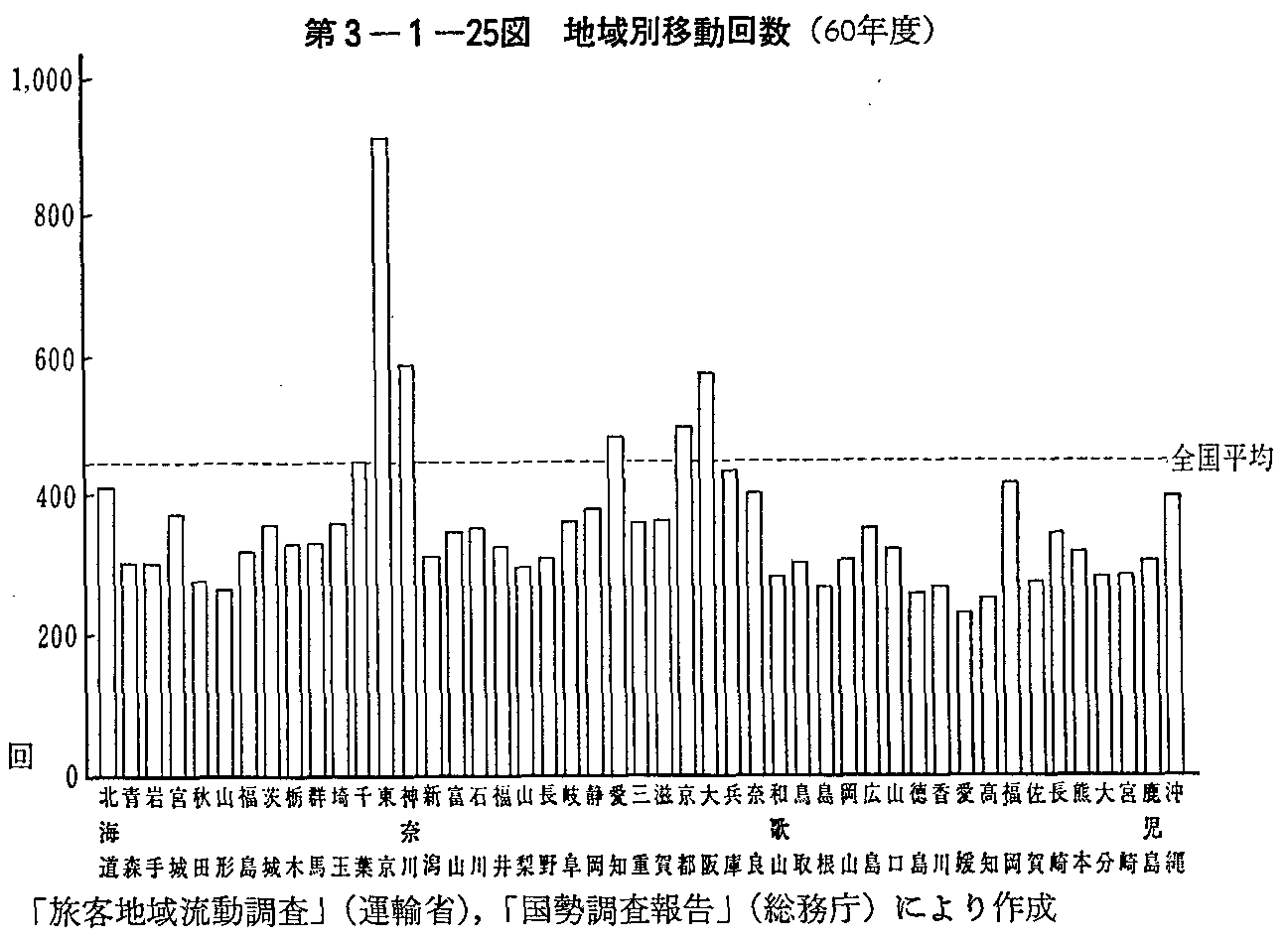
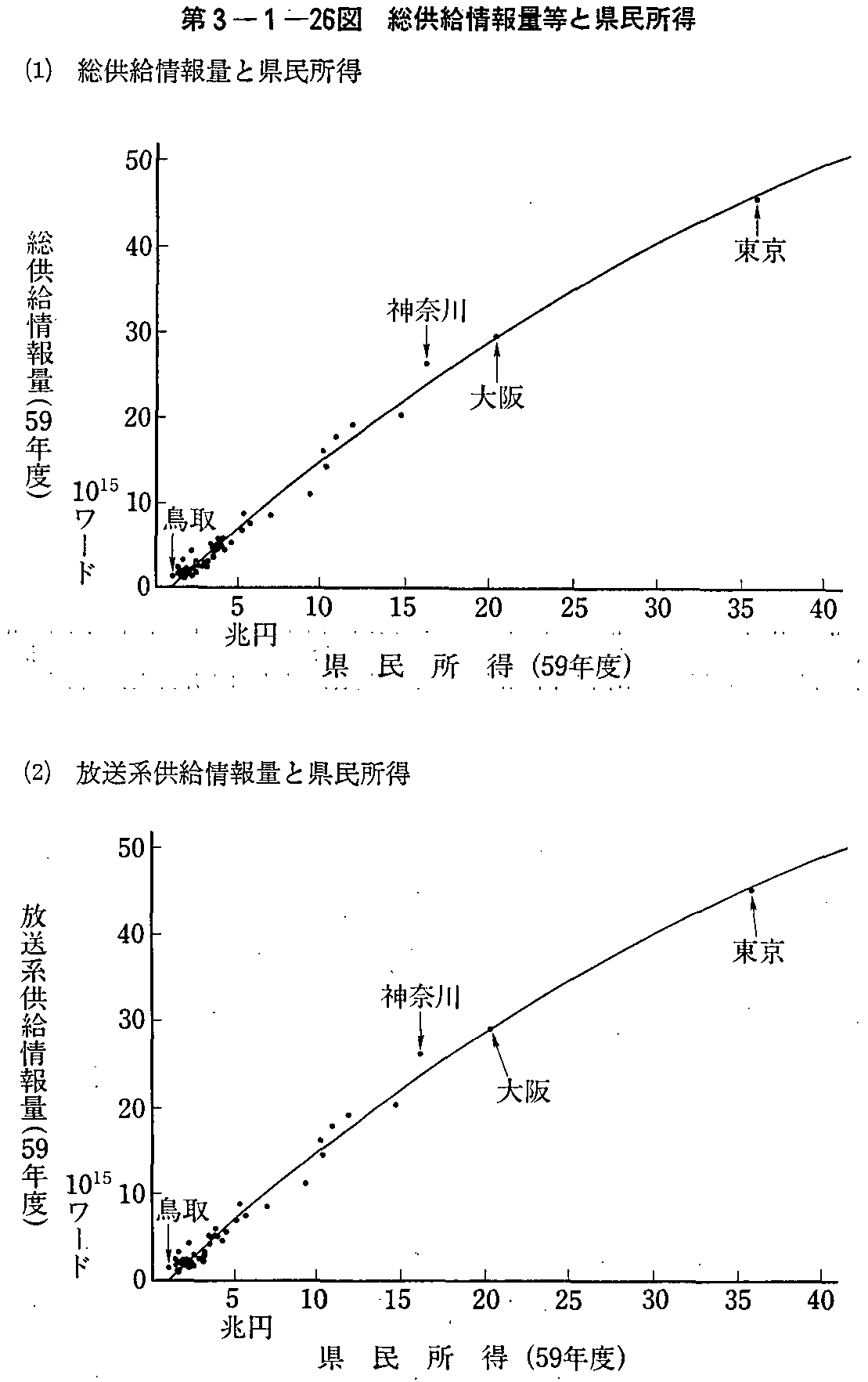
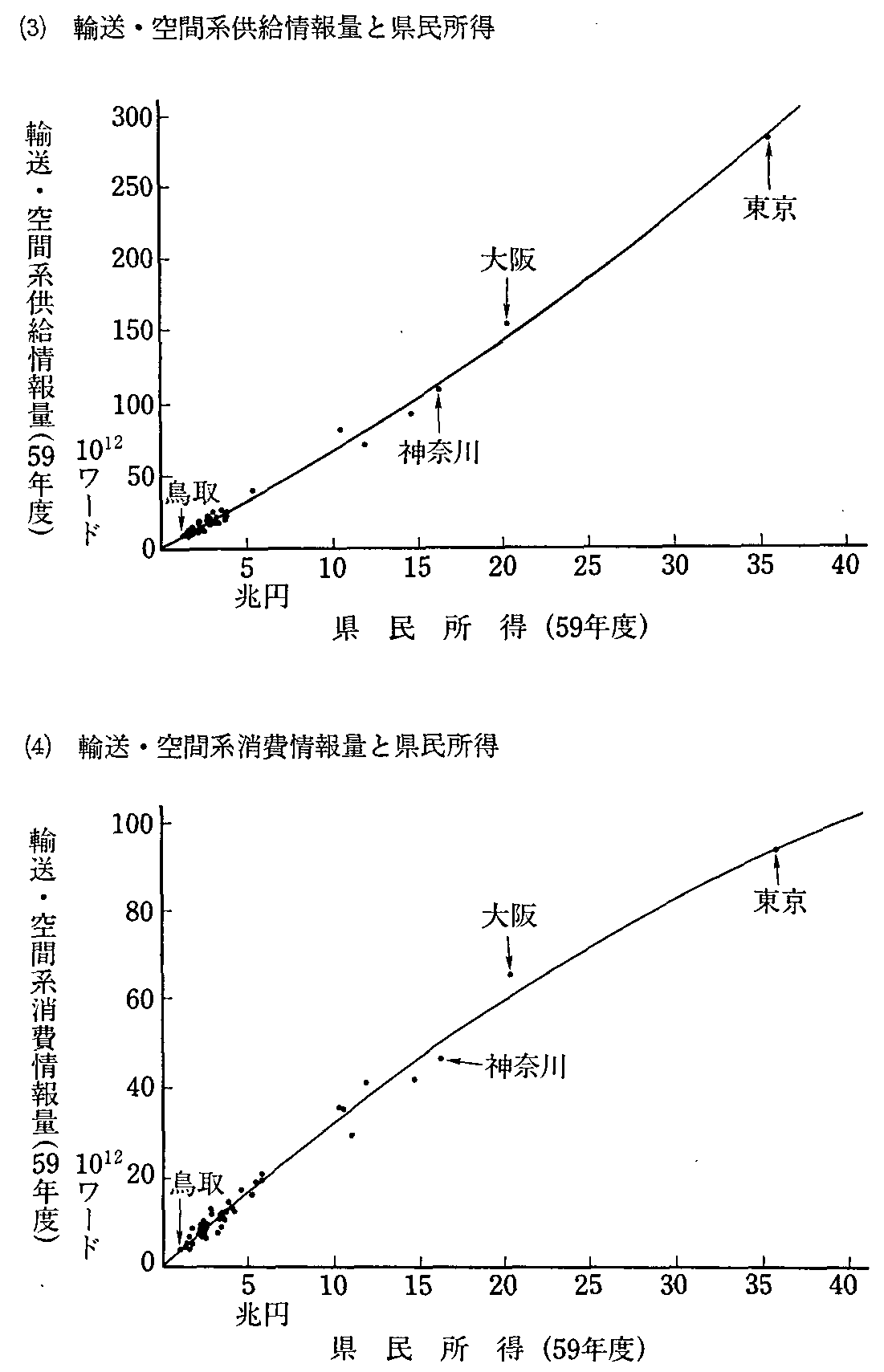
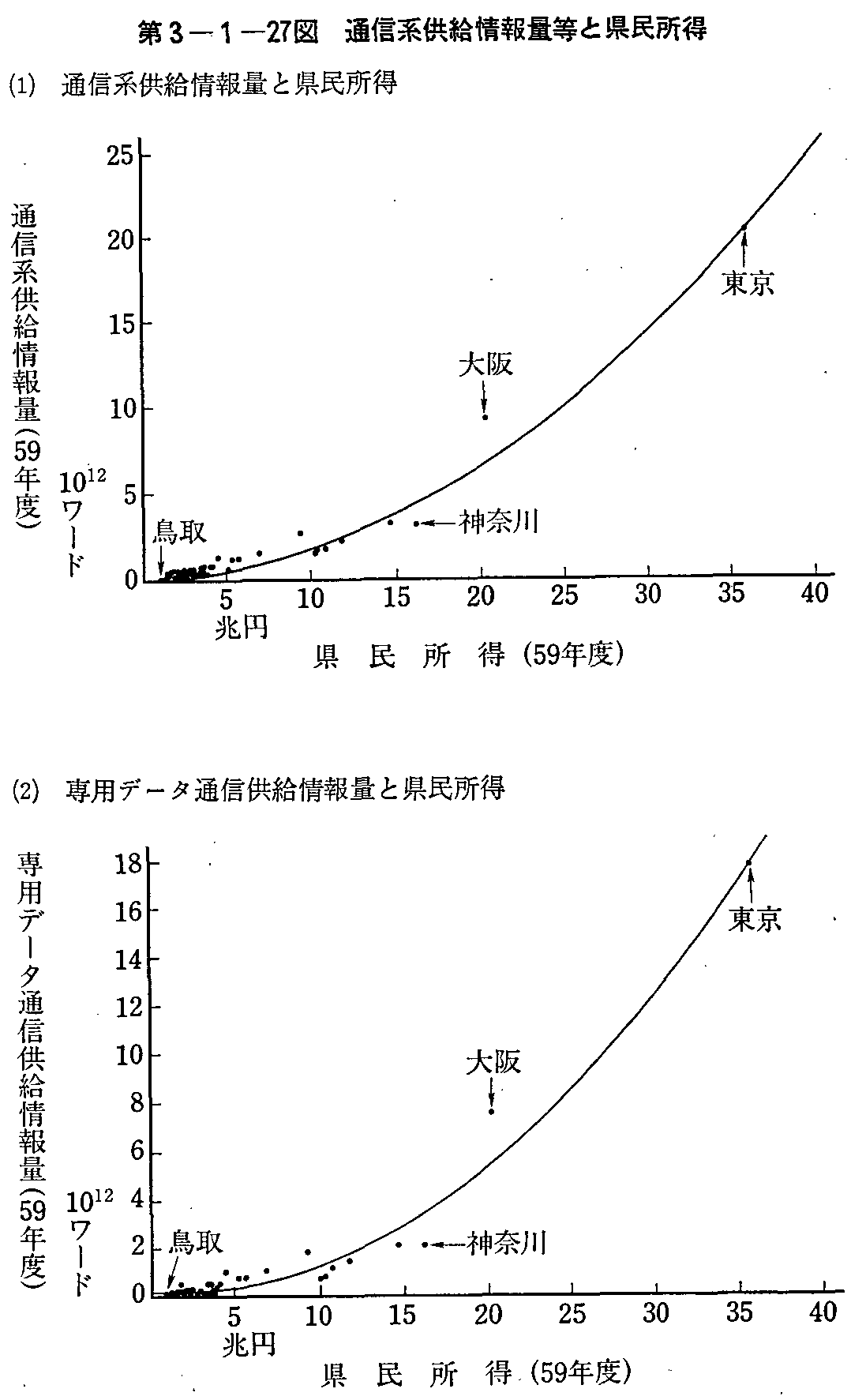
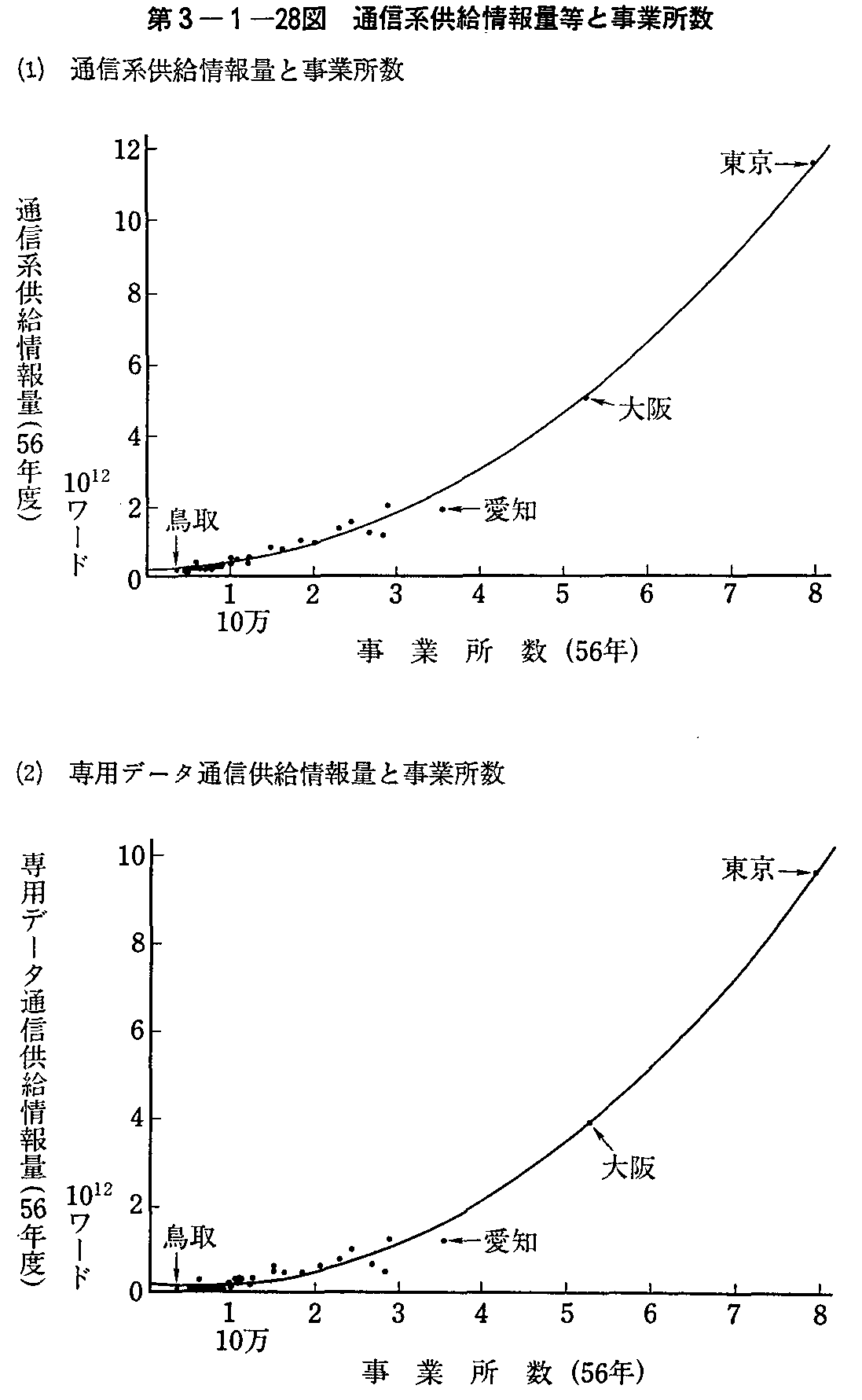
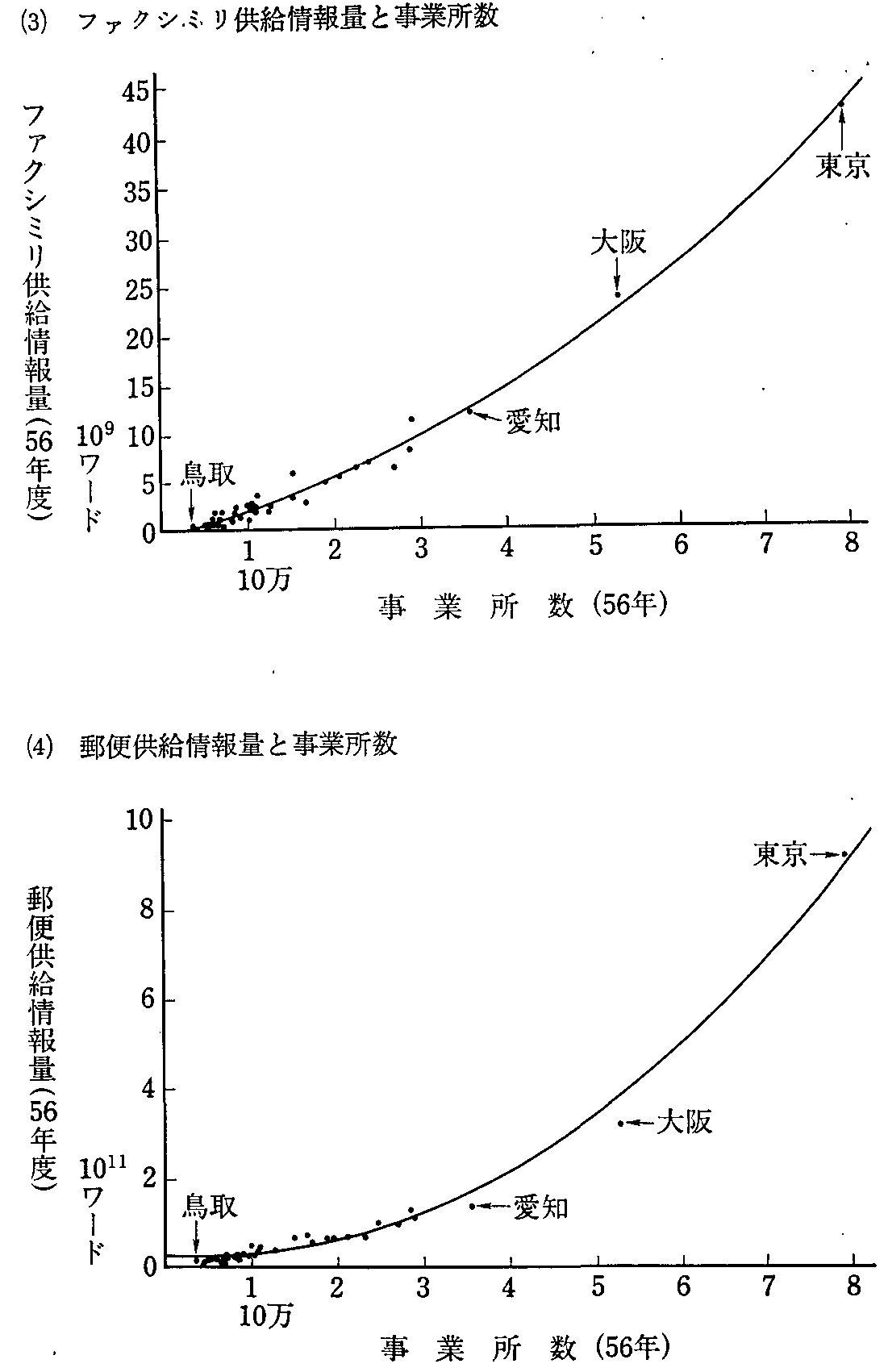
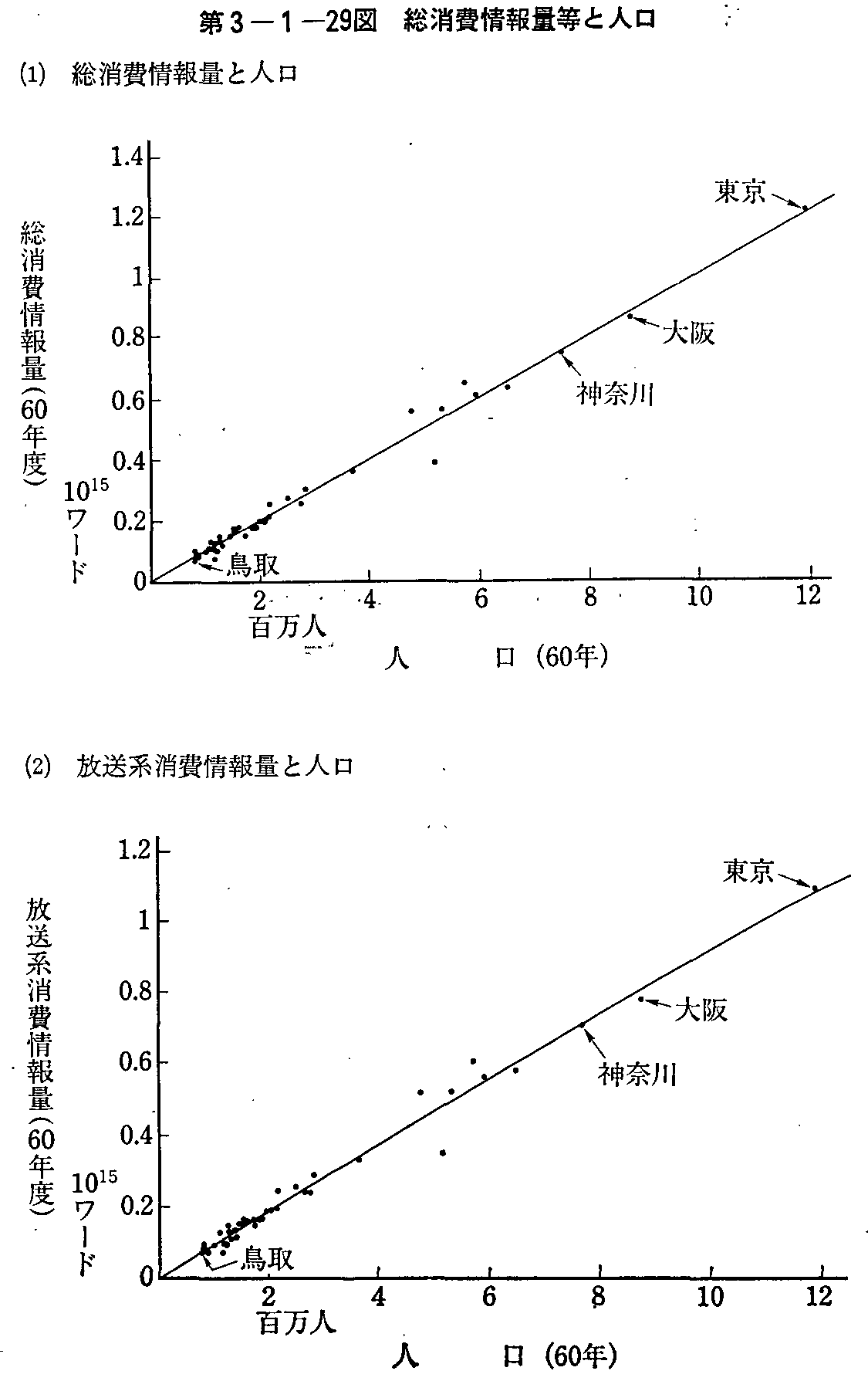
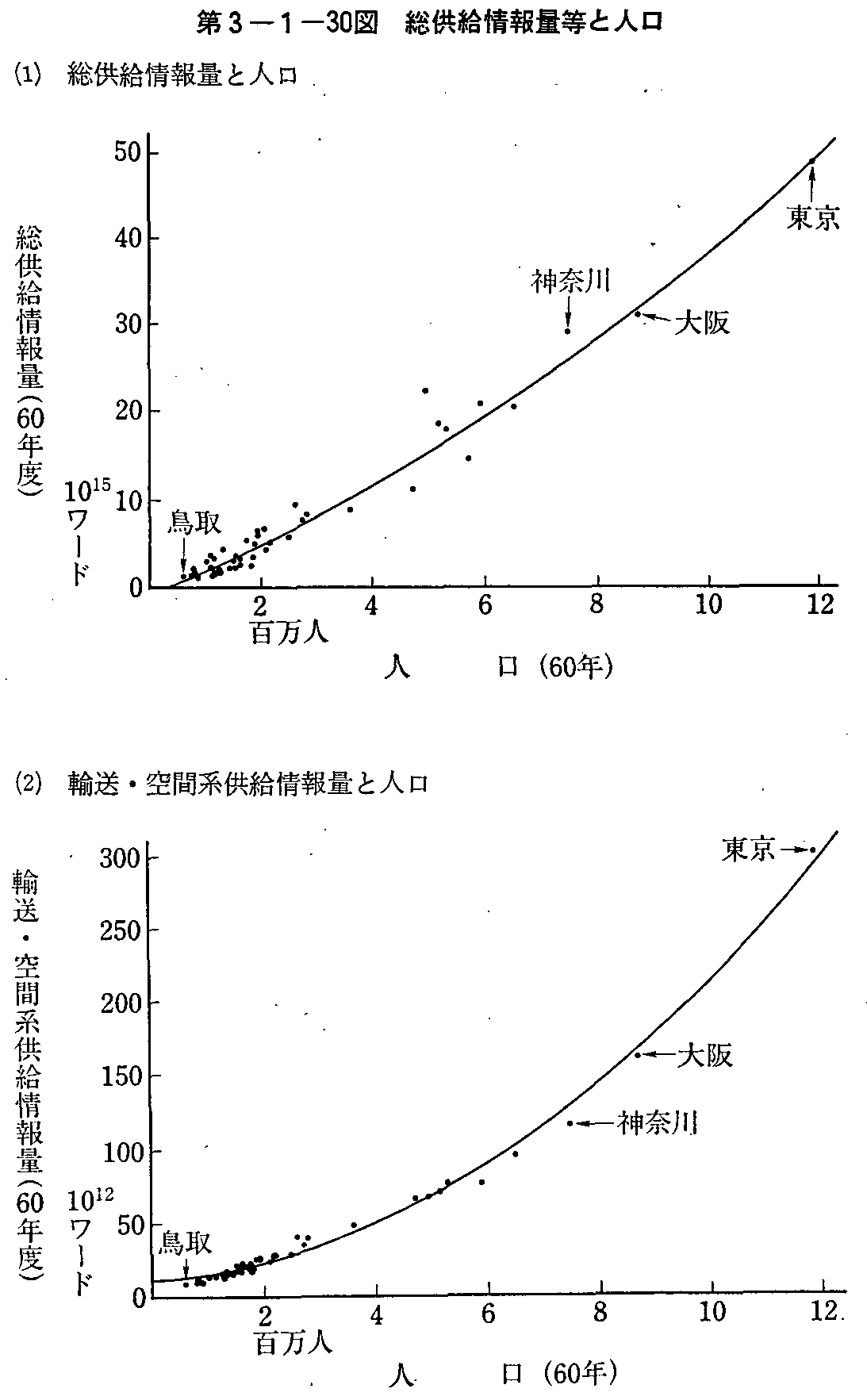
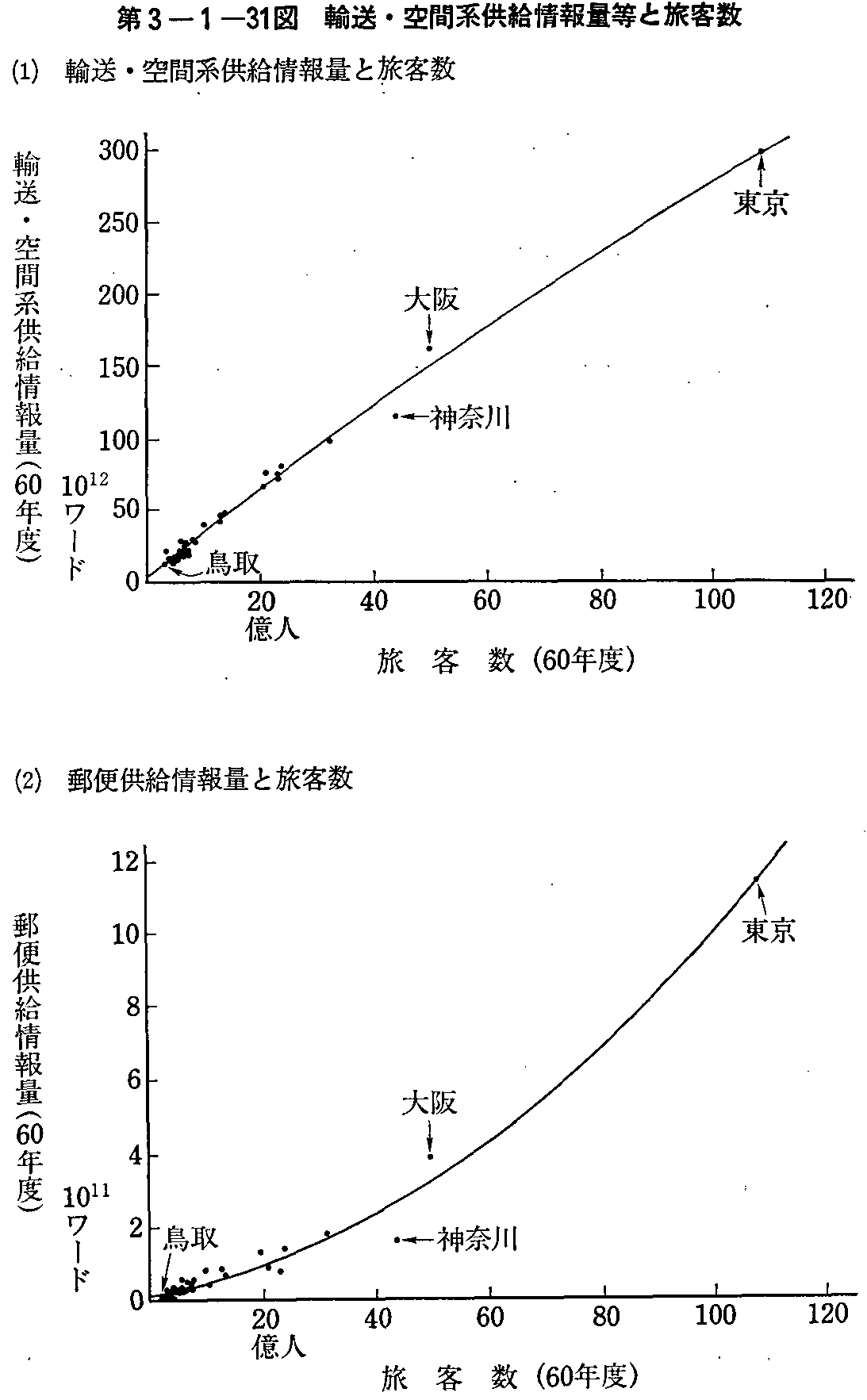
|