 第1章 昭和60年度通信の現況
 第2節 通信政策及び通信サービス
 第1節 通信を支える人間
|
5 有線放送ネットワーク
有線放送ネットワークは,ケーブル等の導体を利用して,映像や音声等の情報を伝送するものである。
(1)CATV網
CATVは,当初テレビジョン放送の難視聴を解消するためのものであった。しかし最近では,伝送路の能力を生かし,自主放送や各種の情報サービスの提供等を行うシステムとしても利用されるようになった。さらに今日では,大規模・多チャンネル・多目的ないわゆる「都市型CATV」の建設が進められている。
(CATV網の構成)
CATV網は,センター,受信端末及びこれらを結ぶ伝送路から構成されている。また網形態は,伝送路において増幅・分岐が必要なため,ツリー形である(第2-2-41図参照)。
センターの機能は,基本的にはテレビジョン放送と同様である。またセンターには,テレビジョン放送の送信アンテナに相当するヘッドエンドが設置されている。ヘッドエンドは,受信した番組や自主番組の放送波を,増幅,調整,合成して,ケーブルに送出する機能をもっている。
CATV網の伝送路には,放送型サービスに適している同軸ケーブルが用いられており,その伝送帯域は従来250MHz程度までのものがほとんどであったが,最近では,都市型CATVに代表されるように300MHzや450MHzまでの広帯域伝送が可能なものが設置又は計画されている。また,これらの都市型CATV等では,有料テレビの提供のために,伝送路は双方向伝送が可能なものになっている。
今後のCATVにおいては,この広帯域化,双方向化が急速に進行していくものと予想される。
CATV網の端末は,各家庭に設置されているテレビジョン受像機である。ただし,多チャンネル化又は双方向化に対応するためには,アダプタが必要となる。
(CATVの普及状況)
CATVの施設数及び受信契約者数の推移は第2-2-42図及び第2-2-43図のとおりである。我が国のCATVは,施設数でみると小規模施設が多いが,受信契約者数でみると大規模施設の増加が著しく,施設の大規模化の傾向がみられる。
(CATVの発展のために)
CATVの発展のためには,次の課題がある。
[1] CATVにおける無線利用
CATVの大規模化に伴い,ケーブルの敷設等が困難な箇所については無線を利用し,設備コスト等の節減を図ることが有効な手段である。このため,郵政省では,58年に23GHz帯の無線を利用する免許方針を定め,60年にはチャンネル数の拡大と利用範囲等の拡大を行った。今後,CATVの普及に向けて,無線の積極的な活用を図ることが重要である。
[2] 再送信における同意問題
放送事業者の放送をCATVで再送信する場合には,その放送事業者の同意が必要であるが,これまで放送事業者とCATV事業者の間では再送信に関する協議が整わない例もみられた。そこで61年5月に,有線テレビジョン放送法の改正が行われ,当事者間の協議が整わない場合には,郵政大臣の裁定により措置することなどができるようになった。
[3] 周波数配列
今後のCATVは,大規模化・多チャンネル化・多目的化の方向に進展すると想定されるので,多数の伝送チャンネルが確保され,かつ,伝送チャンネル相互の妨害が少ない周波数配列が必要である。これについては,61年3月に「有線テレビジョン放送技術委員会」から,望ましい周波数配列が報告された。郵政省としては,今後,この周波数配列の標準化を図る方針である。
(2)有線ラジオ放送網
有線ラジオ放送は,当初ラジオ放送を共同で聴取するために始まり,その後,農漁村において地域情報を伝達するためのもの,都市において飲食店等に音楽を放送するためのもの等が次第に発達してきた。
有線ラジオ放送は,共同聴取業務(ラジオ放送を受信して再送信するもの),告知放送業務(ラジオ放送以外の音声その他の音響を送信するもの)及び街頭放送業務(道路,広場,公園等公衆が通行し又は集合する場所で,共同聴取又は告知放送を行うもの)に分類される。有線ラジオ放送網は,第2-2-44図のとおりツリー形で,CATV網と類似した構成となっている。
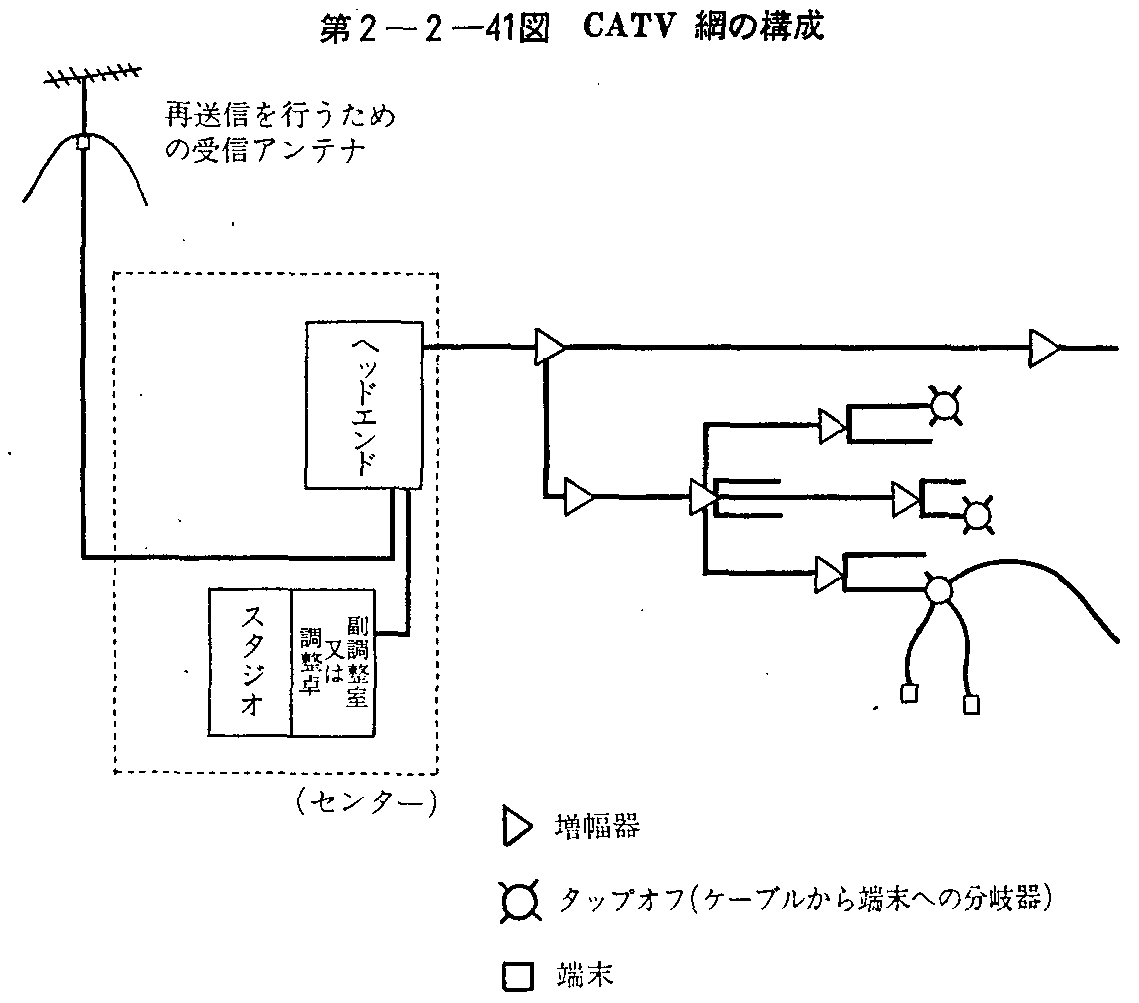
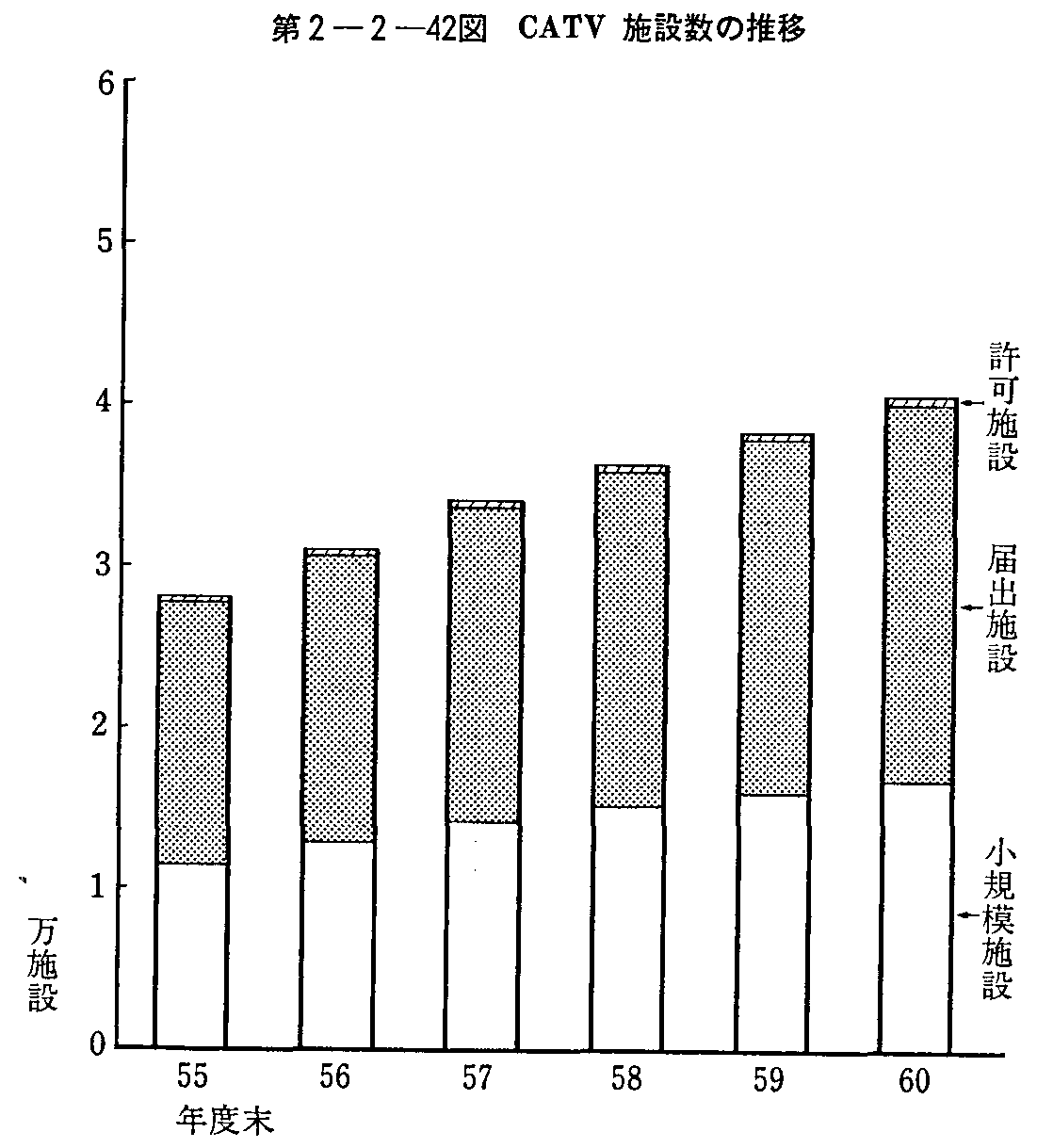
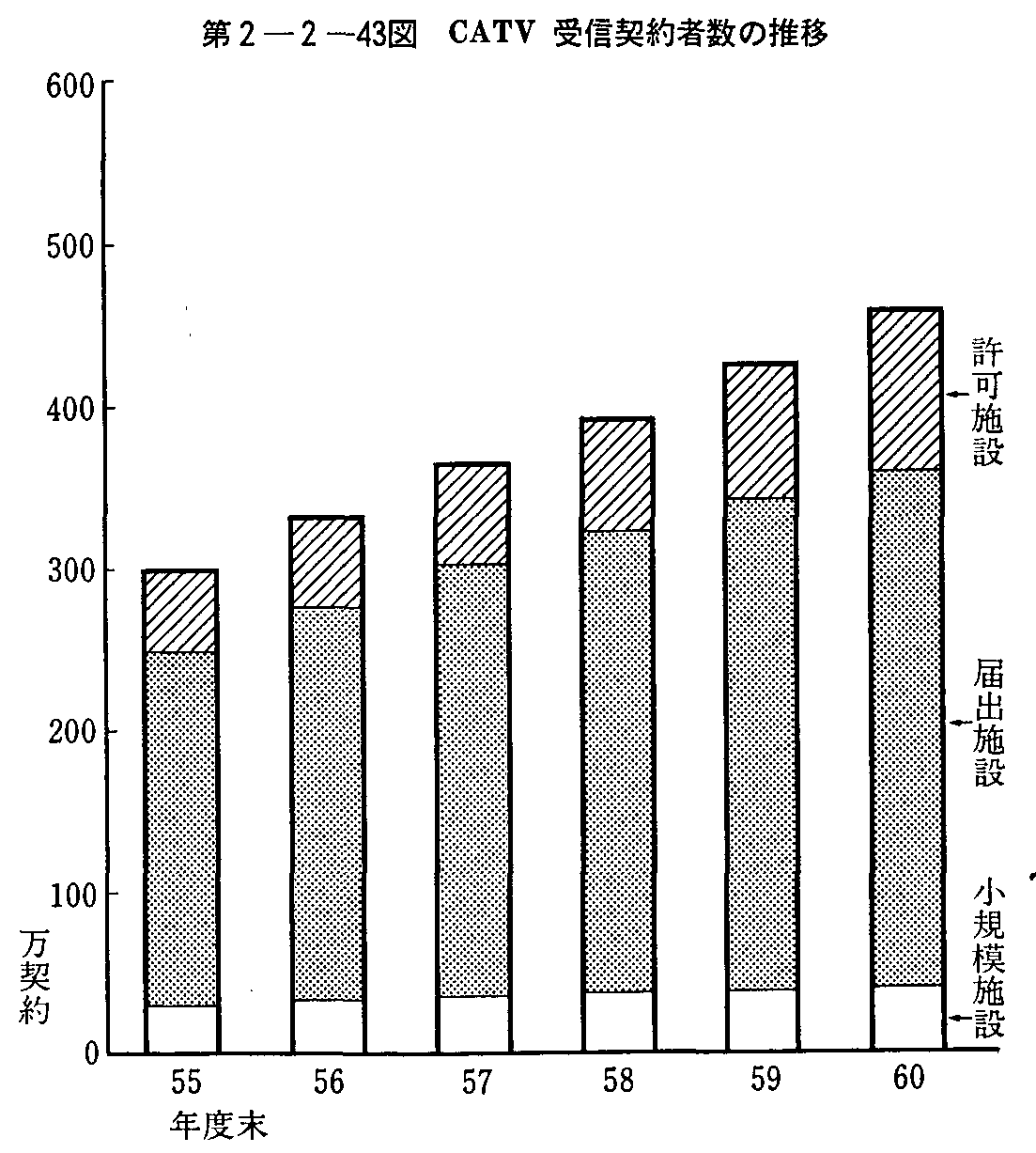
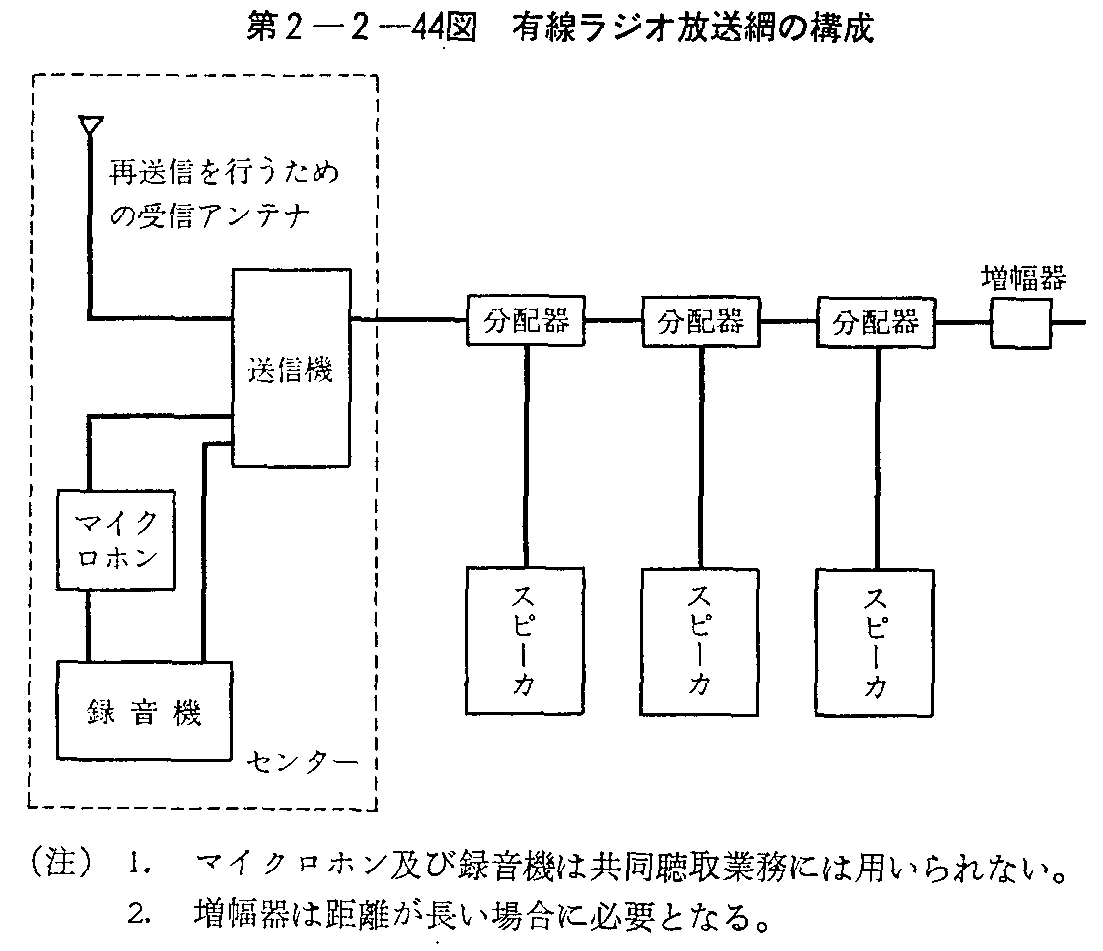
|