1-3-2 地方公共団体の情報提供事業の今後の動向
(1)地方公共団体からの情報の提供
地方が自立するためには,地方自らの情報の創造が必要である。この地方独自の情報の中でも,地域の情報化に主導的役割を果たしている地方公共団体が提供する情報は,特に重要である。
ア 今後重視して提供する情報分野
今後,地方公共団体が重視して提供したいという情報分野を示したのが<2>-1-3-20表である。
(重視される住民生活に密着した情報)
全体的にみると,地域・コミュニティ情報の74.2%をはじめとして,医療・保健情報,防災関連情報が過半数を上回るなど,住民生活に密着した情報の提供が重視されている。他方,農林漁業関連情報,観光レクリエーション関連情報,産業イベント情報のように地場産業に密着した情報あるいは誘客効果の見込める分野も比較的高くなっている。
(市区町村の別にみた重視される情報分野)
市区町村の別にみると,区部及び市部においては,地域・コミュニティ生活関連情報や高齢者・身障者福祉関連情報のような,より住民生活に密着した情報が,より重視されている。
特に,地域・コミュニティ生活関連情報は,人口規模別にみても,規模が大きくなるに従って重視する割合が高くなっている。これは,都市部においては,地域における人と人とのつながりが町村部ほど定着しておらず,生活面での情報提供に関して,地方公共団体の果たしている役割が大きいことを示している。
一方,農村漁村地域の多い町村部においては,農林漁業関連情報が特に重視されている。
イ 今後のメディアの活用意向
地方公共団体が,今後情報を提供するときに利用したいと考えているメディアは,<2>-1-3-21表のとおりである。これによれば,地方公共団体は,その属性あるいは地域性とメディアの特性を使い分けようとしていることが分かる。
まず,広報紙誌,パンフレット,回覧板等の活字メディアは,今後においても,どの市区町村においても,利用意向が高い。地域ブロック別にみても,地域間であまり差はみられず,全国的に重視されているメディアである。
ラジオ放送,テレビジョン放送については,人口30万人以上の都市がラジオ放送(30.2%)及びテレビジョン放送(37.7%),人口20万〜30万人の都市がテレビジョン放送(40.6%)と高くなっている。さらに,都道府県については,ラジオ放送が51.1%,テレビジョン放送が61.7%と利用意向が極めて高い。これは,放送が広範囲に同一の情報を提供するのに適したメディアであること及び放送区域がおおむね県域となっていることなどによる。
有線ラジオ放送,有線放送電話は,町村部において利用意向が高い。これらのメディアは,町村部という比較的小規模の地域を安価にカバーすること,これらの地域で普及していることから,地方公共団体が既存のメディアの有効活用を図ろうとする現れであるということができる。
いわゆるニューメディアの中では,CATV及びビデオテックスの利用意向が高い。その中でも,CATVは区部及び人口30万人以上の都市において利用意向が60%を超えている。都市部におけるCATVの利用意向の高さは,最近の都市型CATVの展開と軌を一にするものである。ビデオテックスは人口20〜30万人の都市において最も利用意向が高くなっている。このように,これらの二つのメディアに関しては,使い分けの傾向がみられる。
電気通信系のニューメディアの利用意向にも着実なものがみられる。特にファクシミリについては,都市規模や地域をあまり問わず,コンスタントな利用意向がみられる。これは記録を手軽に送れるということ,システムの構築に大きな負担がなく経済的であることなどの特性が評価されているためと考えられる。
また,最近普及が進みつつあるデータ通信やパソコン通信に関しても,人口30万人以上の都市でデータ通信(43.3%)及びパソコン通信(45.3%),人口20〜30万人の都市で同じく34.4%及び46.9%の利用意向が示されるなど中規模以上の都市で活用が目指されてぃる。
(2)第三セクターの設立
自治省の「地方公共団体における地域情報政策に関する調査」によれば,地域の情報化の推進に係る第三セクターの設立状況は,62年4月1日現在で106(62年度設立予定を含む。)となっている。また,サービスを開始しているものの中では,ローカルビデオテックスが最も多い。また,今後の事業拡大予定をみると,パソコン通信,ローカルビデオテックス,CATVが多くなっている。
なお,情報提供事業の促進に当たっての第三セクターの設立に対する地方公共団体の意向は,<2>-1-3-22図のとおりである。
(3)情報提供事業を実施中の市区町村の動向
現在実施中の情報提供事業の今後の動向として,拡大・拡充計画等についてみる。
ア 拡大計画
(拡大計画の動向)
事業の拡大意向についてみると,拡大する計画であるというものが約2割,できれば拡大したいというものが約4割となっている(<2>-1-3-23図参照)。
(メディア別の拡大計画)
拡大計画をメディア別についてみた場合,CATVについては,積極的な拡大意向がみられる反面,ビデオテックスについては,現状維持,縮小という動きが一部みられることが挙げられる。
イ 改良計画
一方,システム・機器・情報内容等の改良計画についてみると,改良計画があるものは,約3割となっている(<2>-1-3-24図参照)。
改良計画についてもCATVは53.3%と高く,CATVに対する地方公共団体の積極的な姿勢がうかがわれる。
改良計画の具体的な内容について,メディア別に特徴的なものをみると,以下のとおりである。CATVについては,双方向化や多チャンネル化を計画しているものが中心となっている。また,データ通信については,ホスト・コンピュータの機能向上を挙げるものが多い。さらに,ビデオテックスについては,端末機器の増配置,新規情報の追加,情報更新間隔の短縮,新規IPの獲得等の情報内容の充実,予約業務等の新機能の追加等の,量及び質の両面からの改良が計画されている。
なお無線については,拡大,改良を問わず,比較的現状維持が高いのは,これが防災を主目的とするものであり,一応その目的を達しうる水準のものが多いためと考えられる。
(4)情報提供事業を計画・構想中の市区町村の動向
事業の計画・構想には,既に実施中の地方公共団体が追加して実施するものと,未実施の地方公共団体が新たに実施するものとがあるが,ここでは,その両方を併せて,実施主体,開始予定時期等の計画・構想の概要について,現在実施中の事業と比較しながら述べる。
(実施主体)
計画・構想中の情報提供事業の実施主体については,当該市区町村が最も多く,次いで,第三セクター等,広域市区町村,都道府県,民間企業・団体等の順となっている(<2>-1-3-25図参照)。
計画・構想中の市区町村を都市規模別にみた場合,実施中のものに比べて,中小規模の市が比較的多くなっている。
これを,実施中のものと比べると,当該市区町村の割合が減少しているのに対して,第三セクター等及び広域市区町村が増加しており,情報提供事業を共同で実施していく意向の高まりを示している。
これは,一地方公共団体が単独で行うより,周辺の市町村と連携し,あるいは民間部門と提携したほうが,財政的にも人材的にも,能率的かつ容易に施策を進め得る場合が多いことによる。
(事業実施開始予定時期)
事業実施開始予定時期については,全体としては,63年が38.8%となっている。また,65年までに開始予定のものが65.2%に達している。メディア別にみた場合,ビデオテックスの早期立上がりとCATVが比較的遅いのが目立つ。これは両者の設備投資及び運営経費の差を反映しているとみられ,比較的コスト負担の低いビデオテックスからまず着手されることを示している。
(情報収集提供予定実施機関)
情報収集提供予定実施機関については,当該市区町村が90.1%と最も多くなっている。しかし,実施中の場合と同じく事業所等,商工業団体,都道府県等の地域の関係機関も広汎に参加する傾向がみられる(<2>-1-3-26図参照)。
(情報提供の予定対象地域)
情報提供の予定対象地域については,当該市区町村を対象にするものが約半数であり,次いで,広域市区町村となっている。これを実施中のものと比べると,当該市区町村がやや少なく,一方,広域市区町村が多くなっている。また,都道府県内や全国を対象とするものは比較的少なく,広域市区町村密着型の傾向が強まっている(<2>-1-3-27図参照)。これは,実施主体として相対的に広域市区町村によるケースが増えていること,全国ブロックを対象とする場合の運営経費の増嵩によるとみられる。
(情報提供に利用する予定のメディア)
情報提供に利用する予定のメディアについては,<2>-1-3-28図のとおりである。ビデオテックス,CATVが最も多くなっている。
電気通信系のメディアについては,実施中のものと同様,ビデオテックスの利用意向が高い。次いで,パソコン通信,ファクシミリ,データ通信の順となっており,実施中のものと比べて,パソコン通信,ファクシミリ,データ通信の利用意向が高い。
これらは,情報の処理,加工,あるいは記録といったものにより,単なる情報の提供から一歩進めるものとして注目される。
また,放送系のメディアについてみると,CATVが最も多い。これは,実施中のものよりも極めて高く,既に地域に密着したメディアとしてCATVを利用する意向の現れであると考えられる。反面,都市規模等の関係から,その他の放送系メディアの活用意向は低くなっている。
(情報提供事業の目的)
事業の目的については,地域産業の振興,観光・レクリエーションの振興,文化活動の振興,防災対策の改善・充実,学校教育・社会教育の充実が上位を占めている(<2>-1-3-29表参照)。実施中のものと比較すると,目的が多様化している。
(情報提供事業に要する経費等)
情報提供事業の予定構築経費は,<2>-1-3-30図に示すとおりであり,構築経費が1億円を超えるものが過半数となっている。実施中のものと比べると,高額化の傾向がみられる。さらに,情報提供事業の予定年間運営費用についても同様の傾向がみられる(<2>-1-3-31図参照)。
情報提供事業の計画・構想に携わっている職員数については,<2>-1-3-32図に示すとおりである。職員数は,実施中のものと同様,少人数となっている。
(情報提供事業の効果への期待)
事業の効果の現れ方についてみると,ある程度(5年程度)の期間が必要とするものが過半数を占めている。一方,すぐに効果が現れるのを期待するものは,約4分の1にとどまっている(<2>-1-3-33表参照)。このように,情報提供事業の効果が現れるまでの期間については,既に実施中のものと比べて,やや長い期間が必要であると考えられる傾向にある。
(5)情報提供事業が未計画の市町村の動向
(情報提供事業の検討状況)
情報提供事業を未計画の市町村は,回答があった地方公共団体の82.5%にのぼっている。また,1,688市町村(回答があった地方公共団体の71.1%)は,事業の具体的な計画を有していない。
さらに,そのうちの1,216市町村では研究,検討が行われていない。その比率は人口10万人未満の市や町村部において高くなっている。反面,市町村独自で検討,研究を行ったものも225団体ある(<2>-1-3-34図参照)。
(情報提供事業が未計画である理由)
また,事業が未計画である理由については,「研究・検討が不十分である」というもの及び「システムの構築費用等が多額となる」というものが過半数を占めている(<2>-1-3-35図参照)。このように,情報提供事業について未計画の地方公共団体に関しては,その実施に当たって,ノウハウ及び費用の両面がネックとなっている。
(6)都道府県の動向
都道府県の情報提供事業は,実施中が41都府県(103プロジェクト),計画・構想中が6道県となっている。
ア 実施中の情報提供事業の状況
(利用しているメディア)
情報提供事業に利用しているメディアは,<2>-1-3-36図のとおりである。電気通信系のメディアでは,ビデオテックスが最も多く,次いでデータ通信,ファクシミリ,パソコン通信の順である。一方,放送系のメディアでは,ラジオ放送,テレビジョン放送及び文字放送が,ほぼ同じ程度に利用されている。
(情報提供事業の目的)
清報提供事業の目的は,観光・レクリエーションの振興が最も多く,次いで,地域産業の振興,文化活動の振興となっている。特に,ビデオテックスを利用している事業について,この傾向が強い(<2>-1-3-37表参照)。
(開始時期)
事業の開始時期は,61年に開始したものが34と最も多い。また,59年以前に開始したものも28ある(<2>-1-3-38図参照)。
(実施主体)
事業の実施主体は,当該都道府県が最も多く,次いで第三セクター等,民間企業・団体等の順となっている(<2>-1-3-39図参照)。
(情報収集提供実施主体)
情報収集提供実施主体についても,当該都道府県が最も多く,次いで,市区町村,事業所・商工業者・農林漁業者等の順となっている(<2>-1-3-40図参照)。
(情報提供事業の効果)情報提供事業の効果の現れ方については,5〜10年程度の期間が必要としているものが過半数であるが,すぐに効果が現れることを期待しているものも,約4割となっている(<2>-1-3-41表参照)。
(拡大計画及び改良計画)
事業の拡大計画については,拡大する計画のあるものが約4分の1,できれば拡大したいというものが約3分のlとなっている(<2>-1-3-42図参照)。
また,改良計画については,計画のあるものとないものとが,ほぼ半々になっている(<2>-1-3-43図参照)。
イ 計画・構想中の情報提供事業の状況
(利用を計画しているメディア)
事業に利用を計画しているメディアは,<2>-1-3-44図のとおりである。電気通信系のメディアでは、ビデオテックスが最も多く,次いでデータ通信,ファクシミリ,パソコン通信の順である。一方,放送系のメディアでは,CATVを利用するというものが多くなっている。
(事業の目的)
事業の目的は,地域産業の振興が最も多く,次いで,観光・レクリエーションの振興,文化活動の振興となっている(<2>-1-3-45表参照)。
(開始予定時期)
事業の開始予定時期は,63年が12と最も多く,次いで,64年が10,65年が7という順になっている(<2>-1-3-46図参照)。
(実施予定主体)
実施予定主体は,当該都道府県が最も多く,次いで第三セクター等,民間企業・団体等の順となっている(<2>-1-3-47図参照)。
(情報収集提供実施主体)
情報収集提供実施主体についても,当該都道府県が最も多く,次いで,事業所・商工業者・農林漁業者,市区町村の順となっている(<2>-1-3-48図参照)。
(情報提供事業の効果)
事業の効果の現れ方については,5〜10年程度の期間が必要としているものが過半数となっている(<2>-1-3-49表参照)。
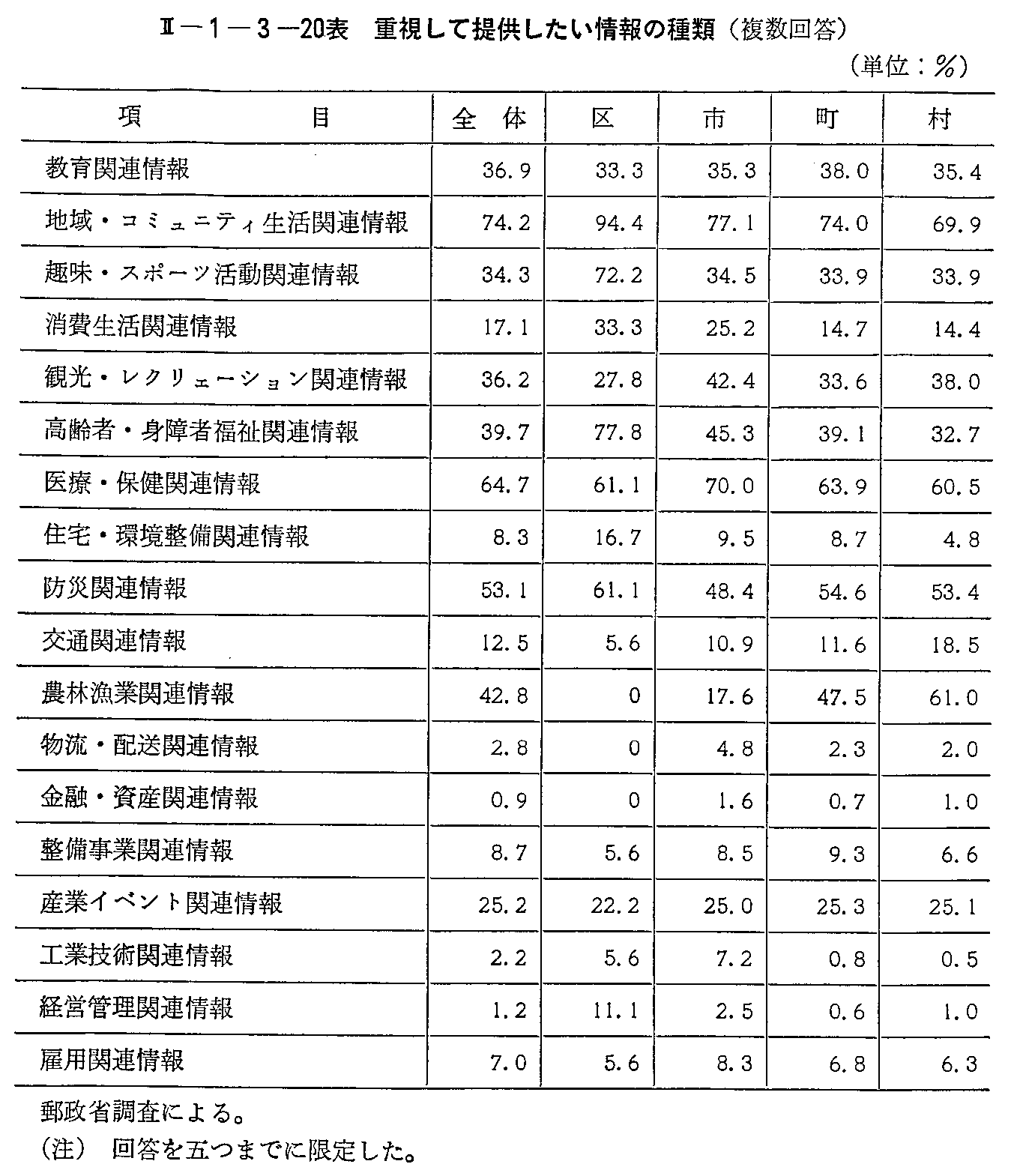
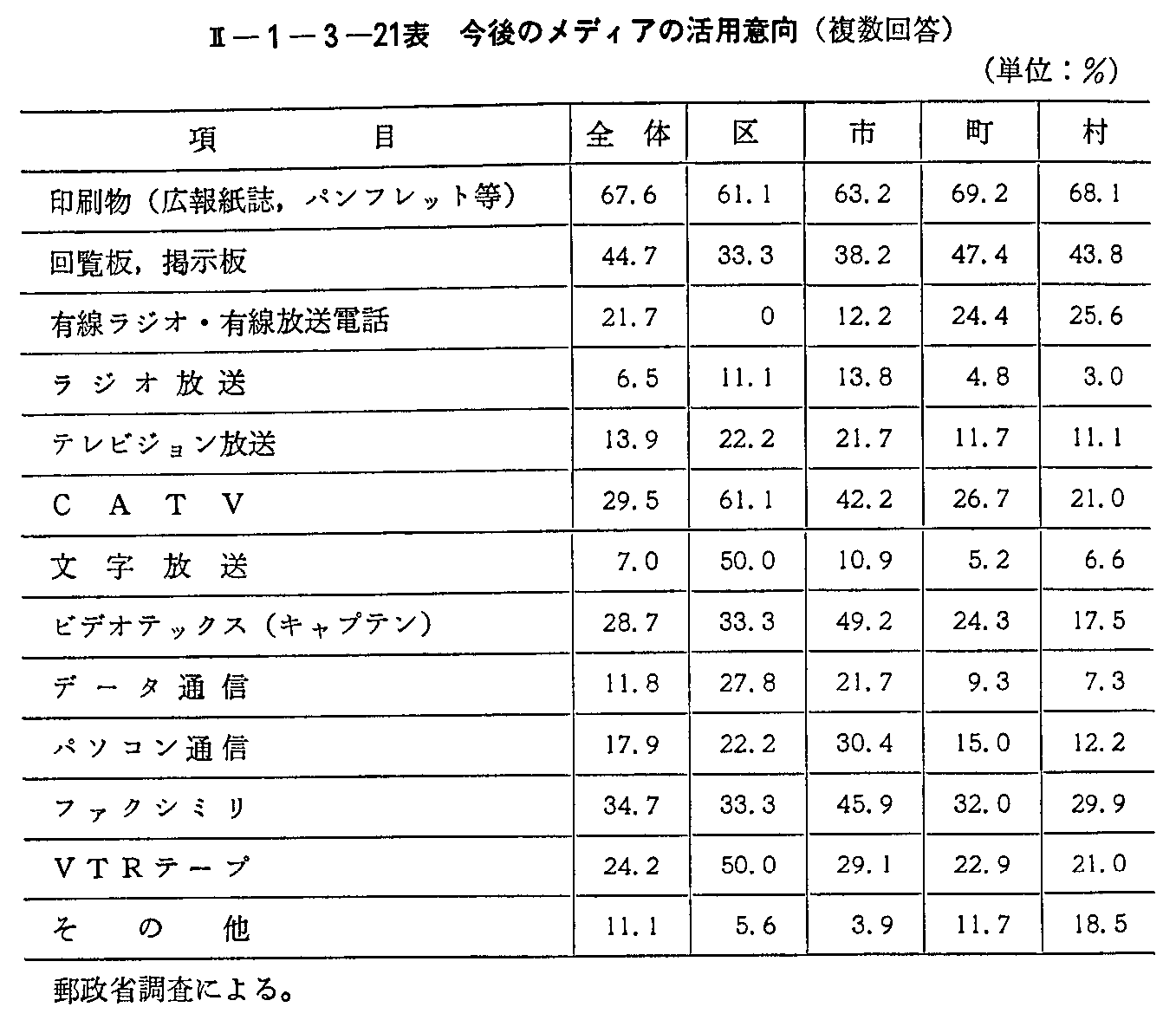
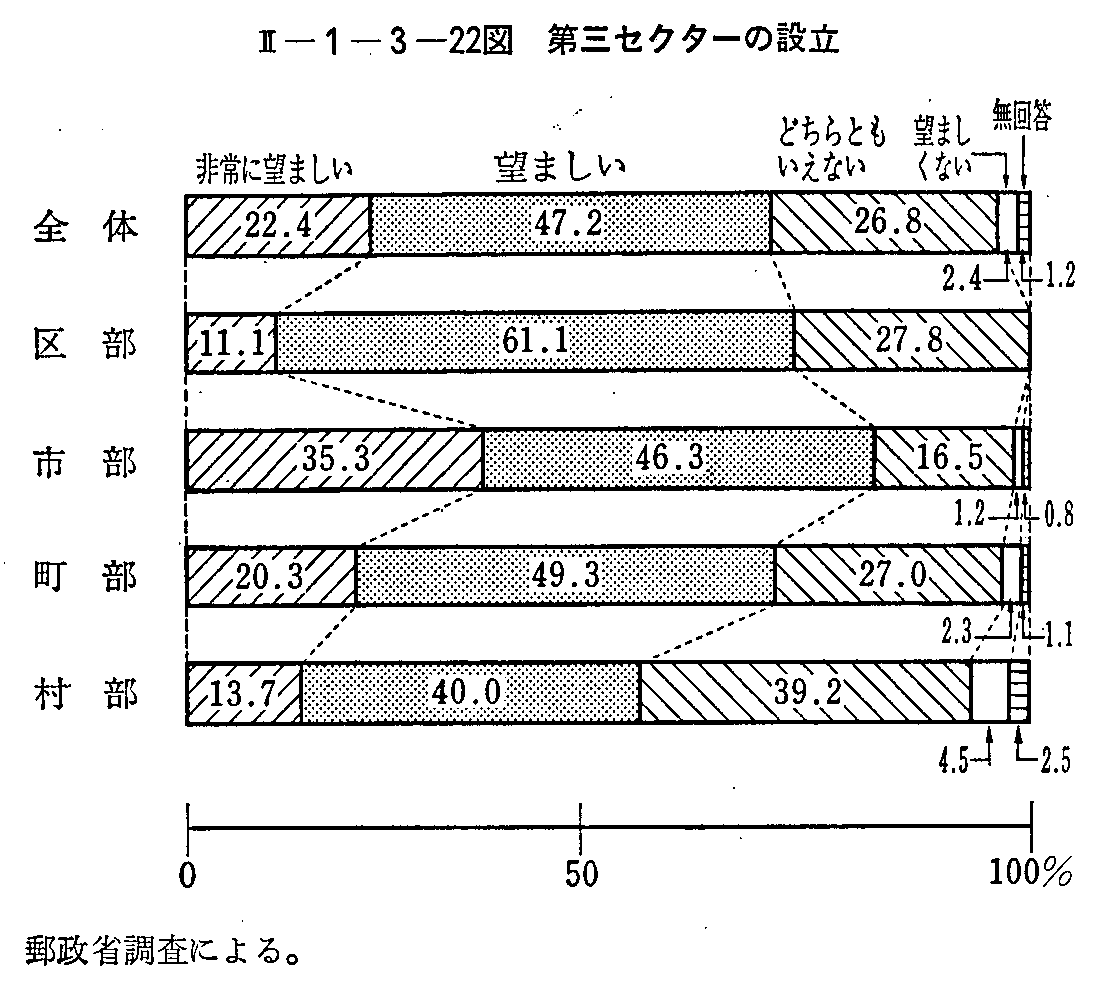
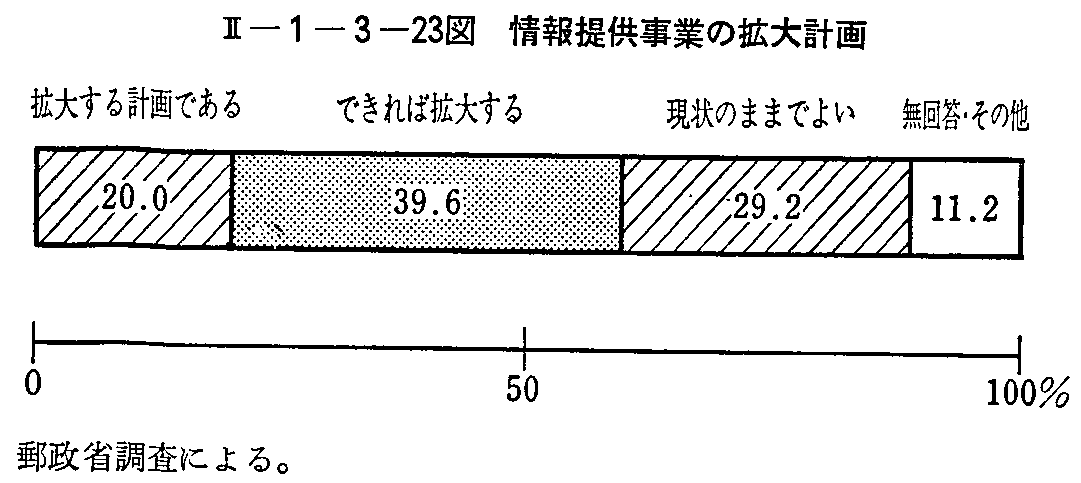
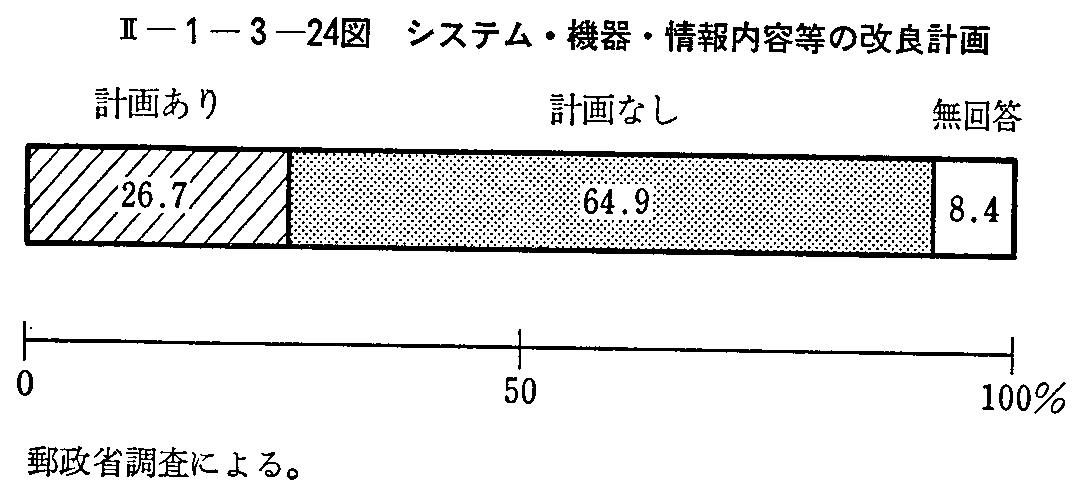
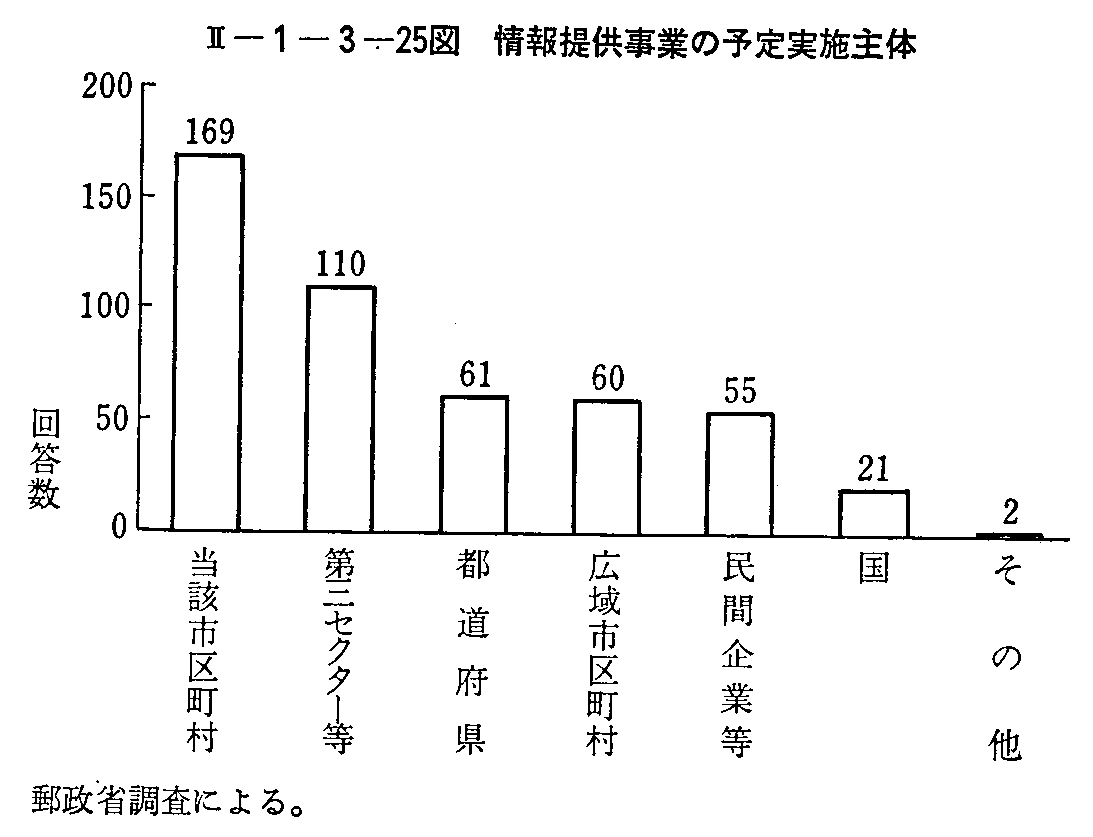
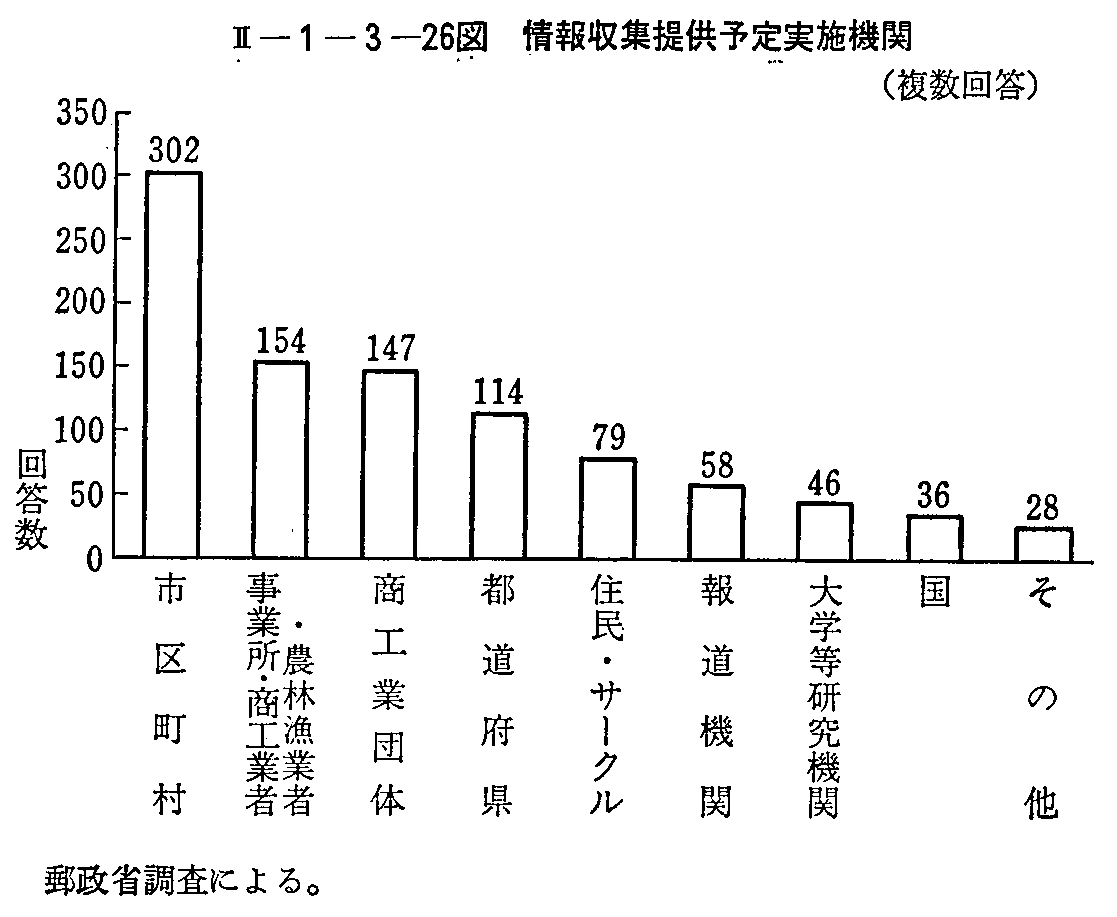
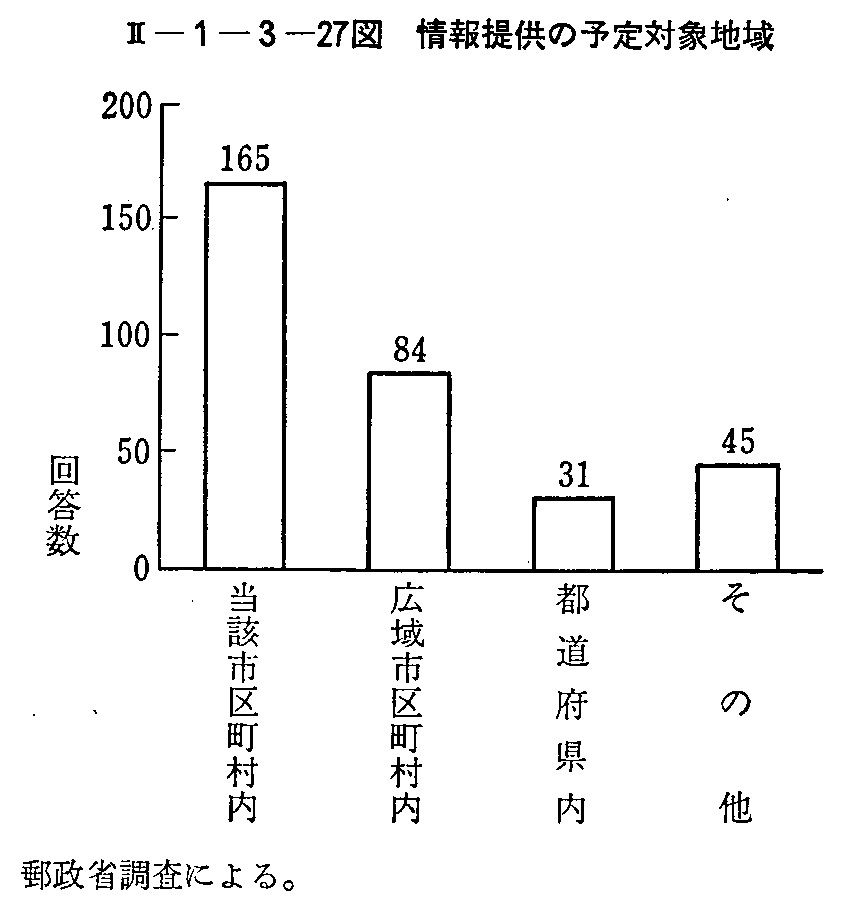
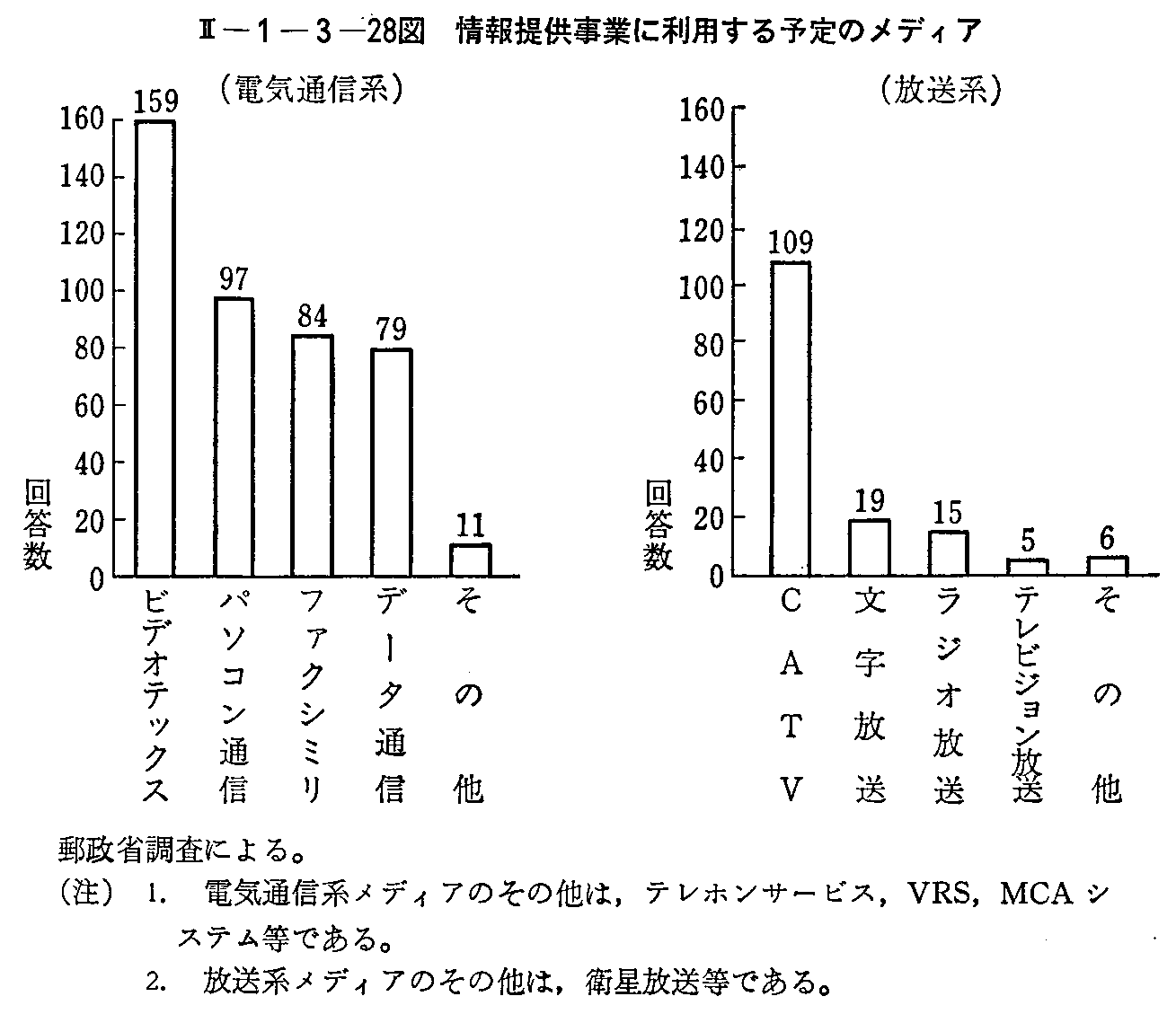
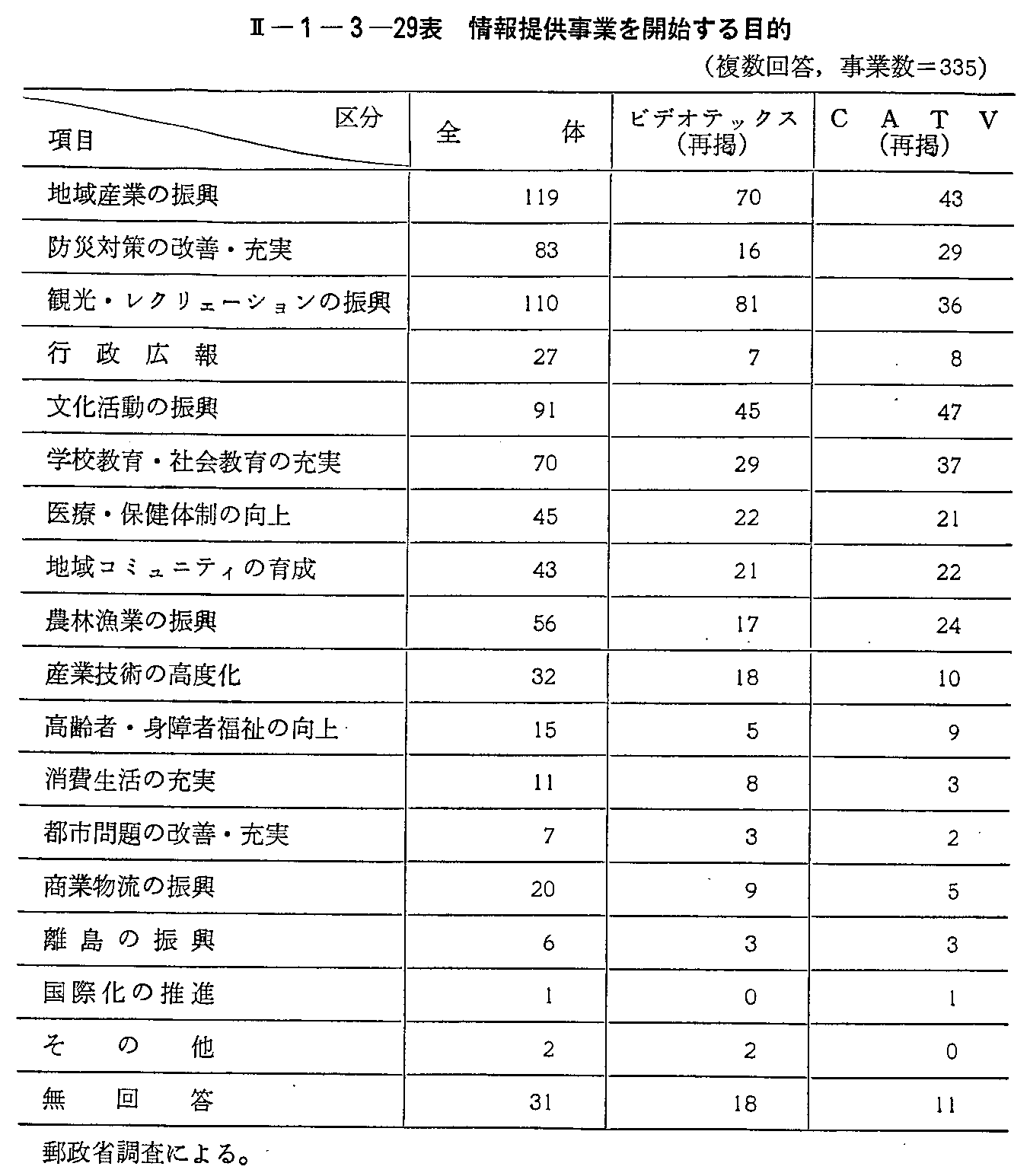
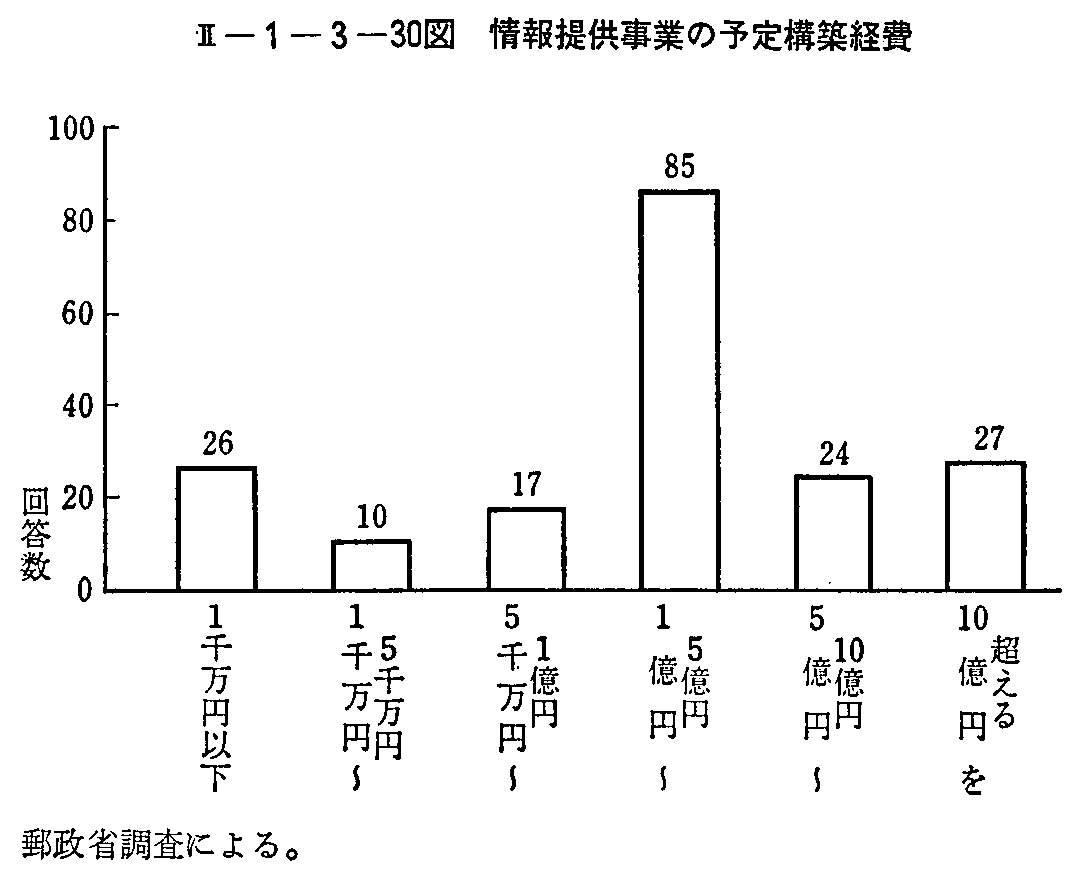
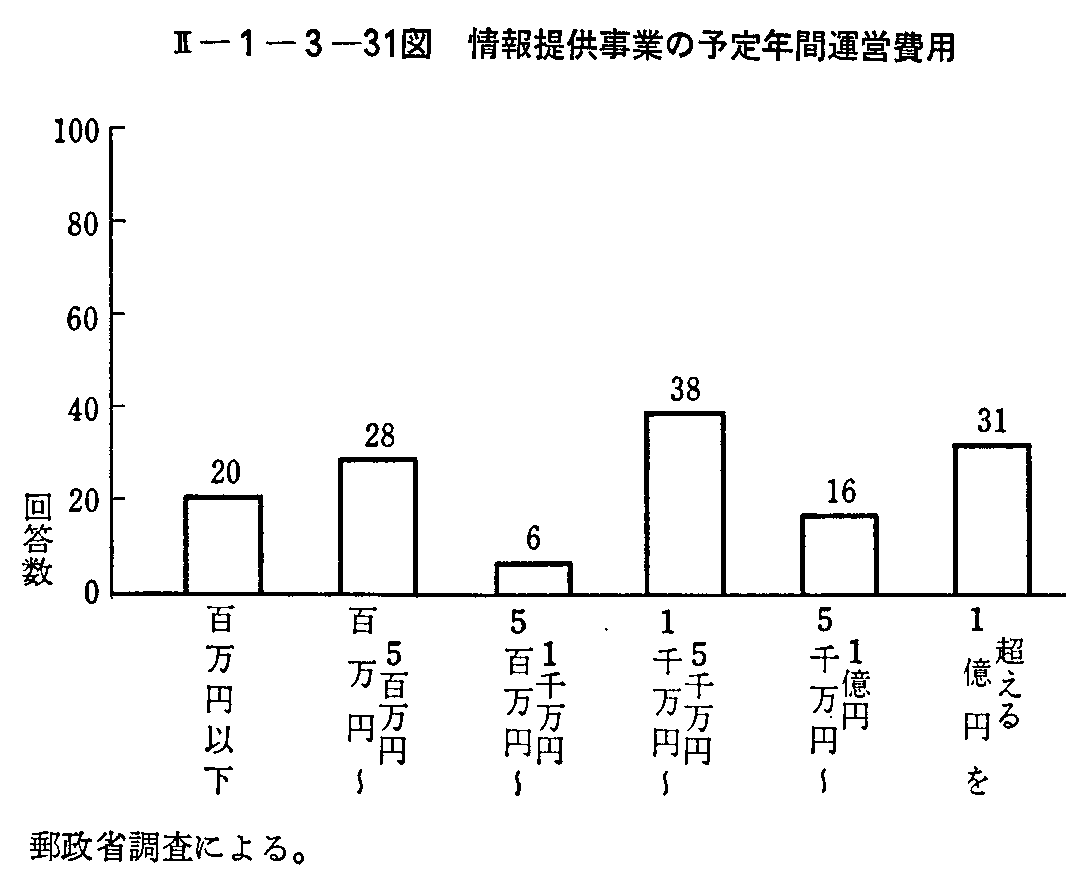
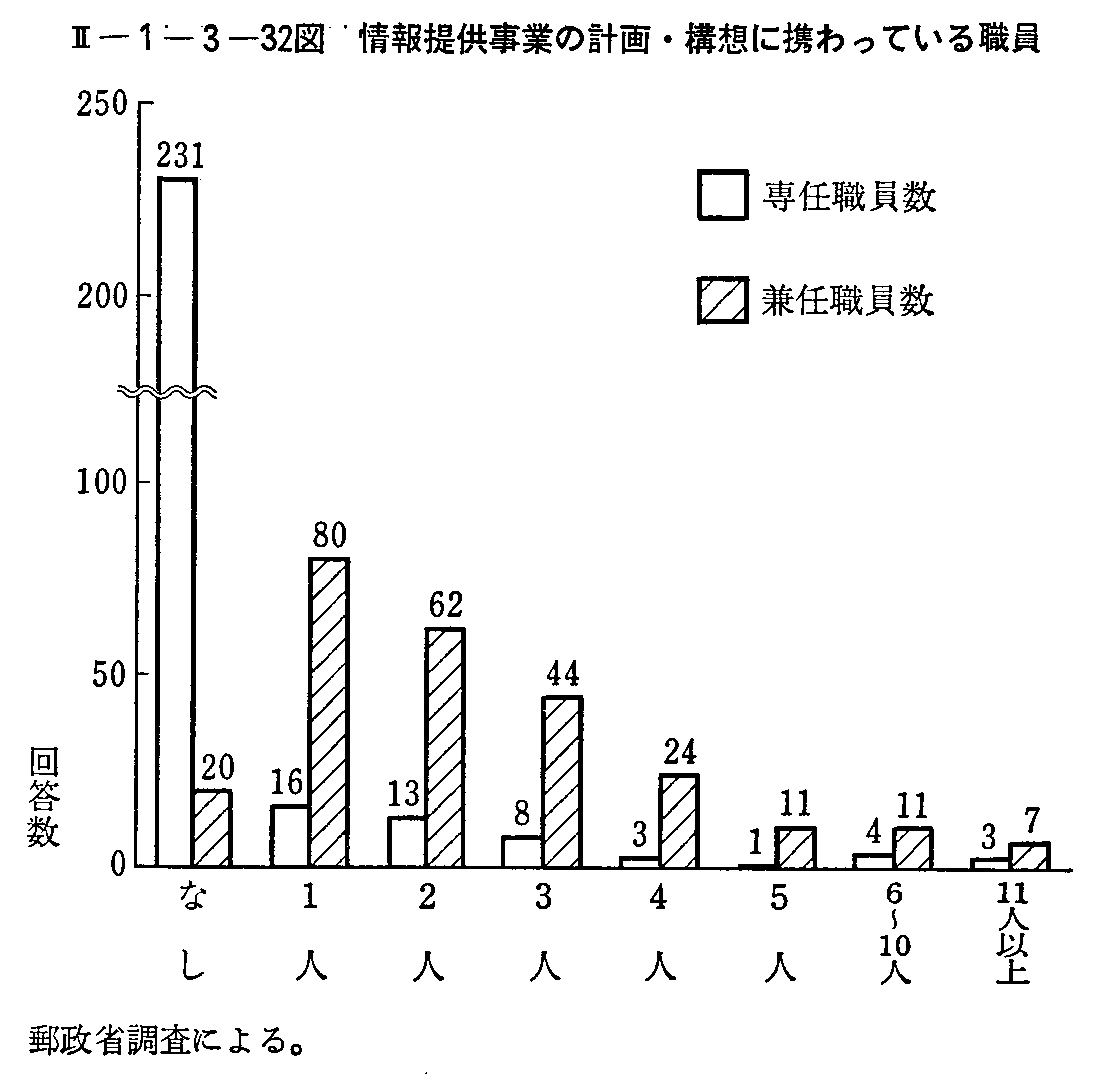
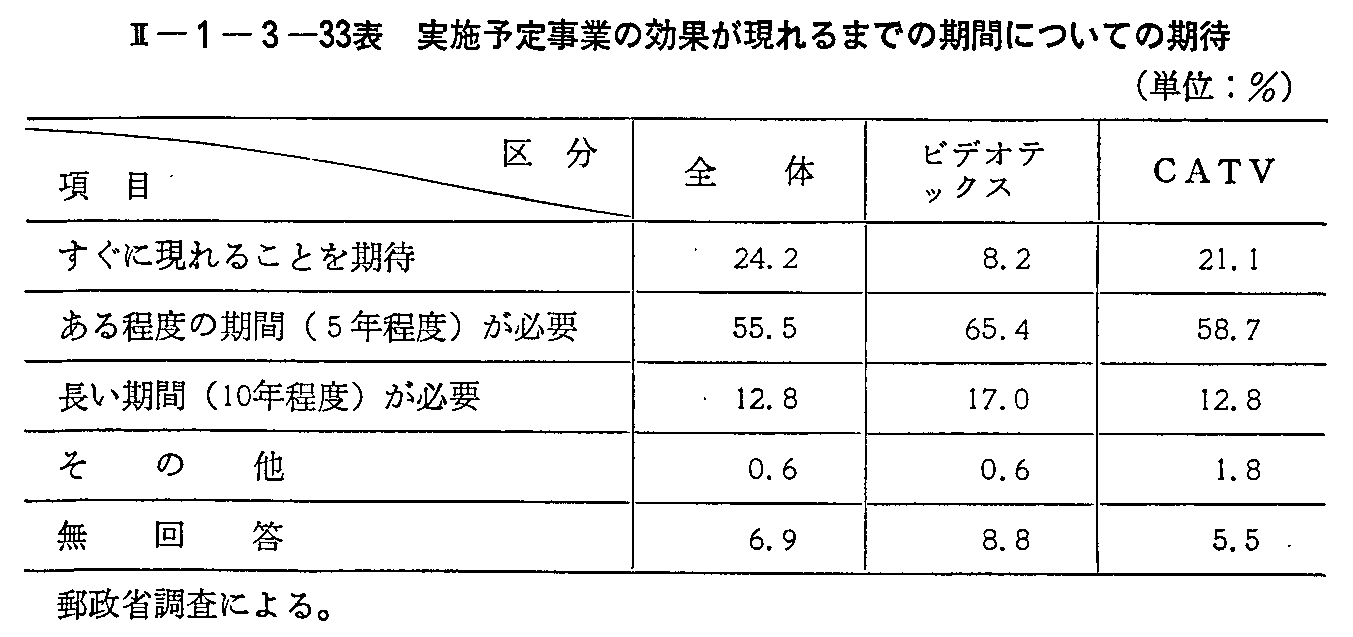
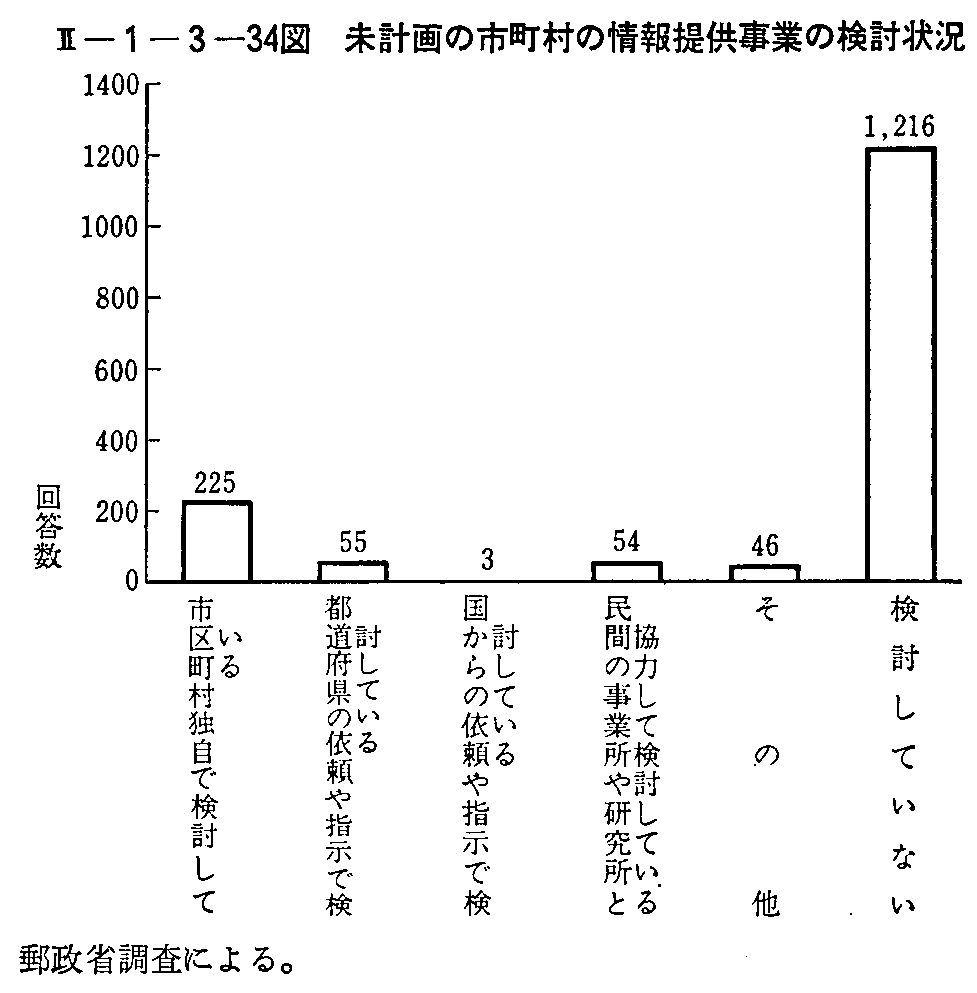
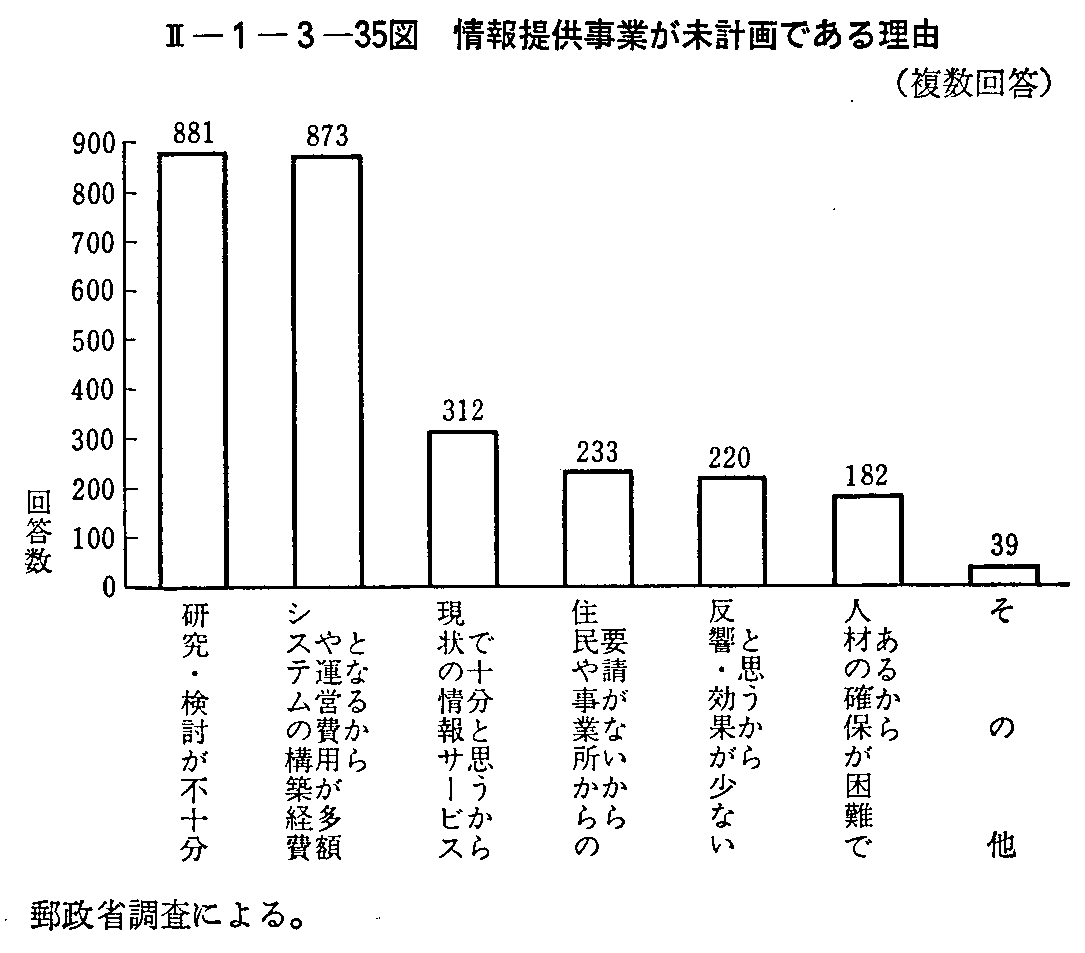
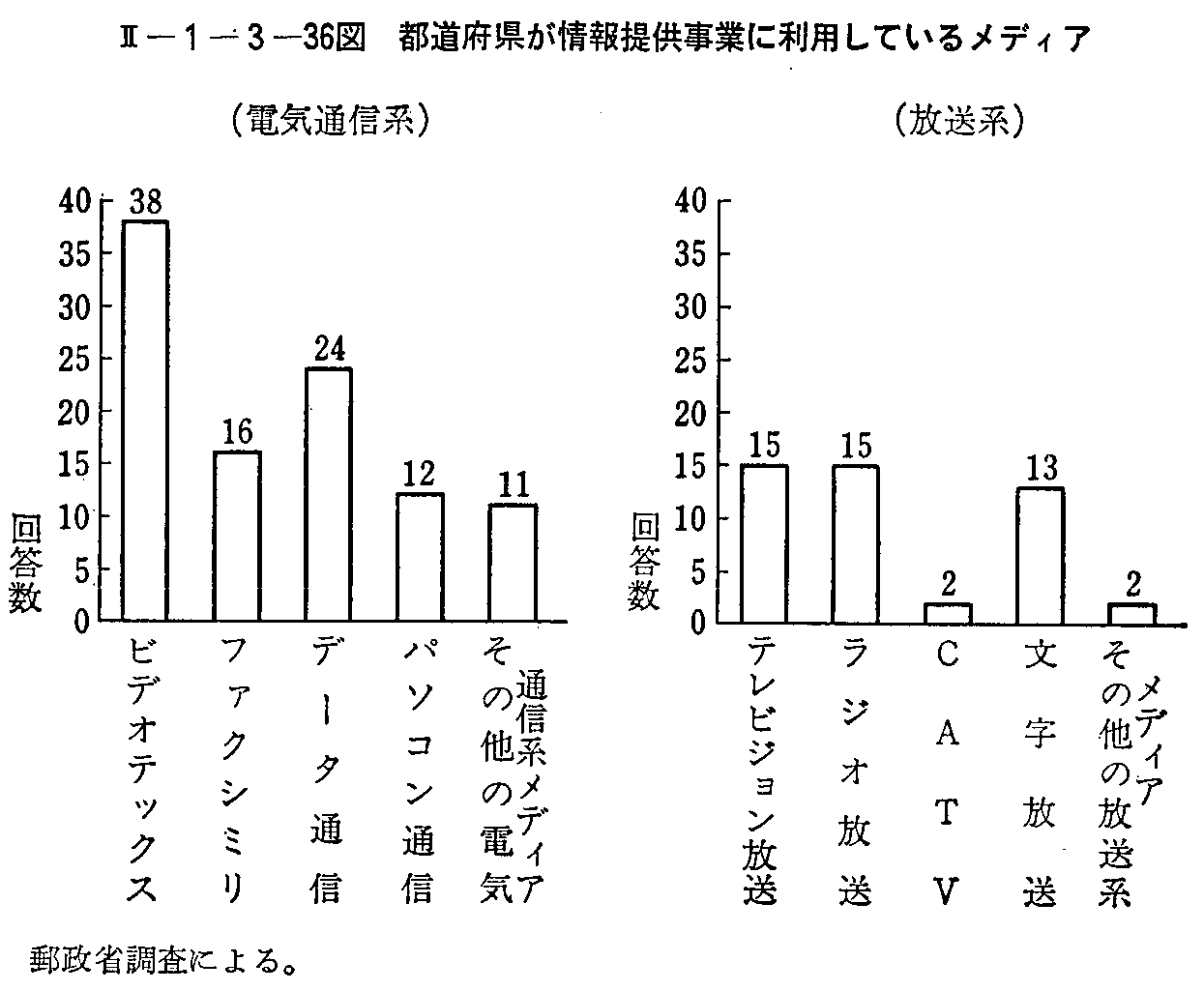
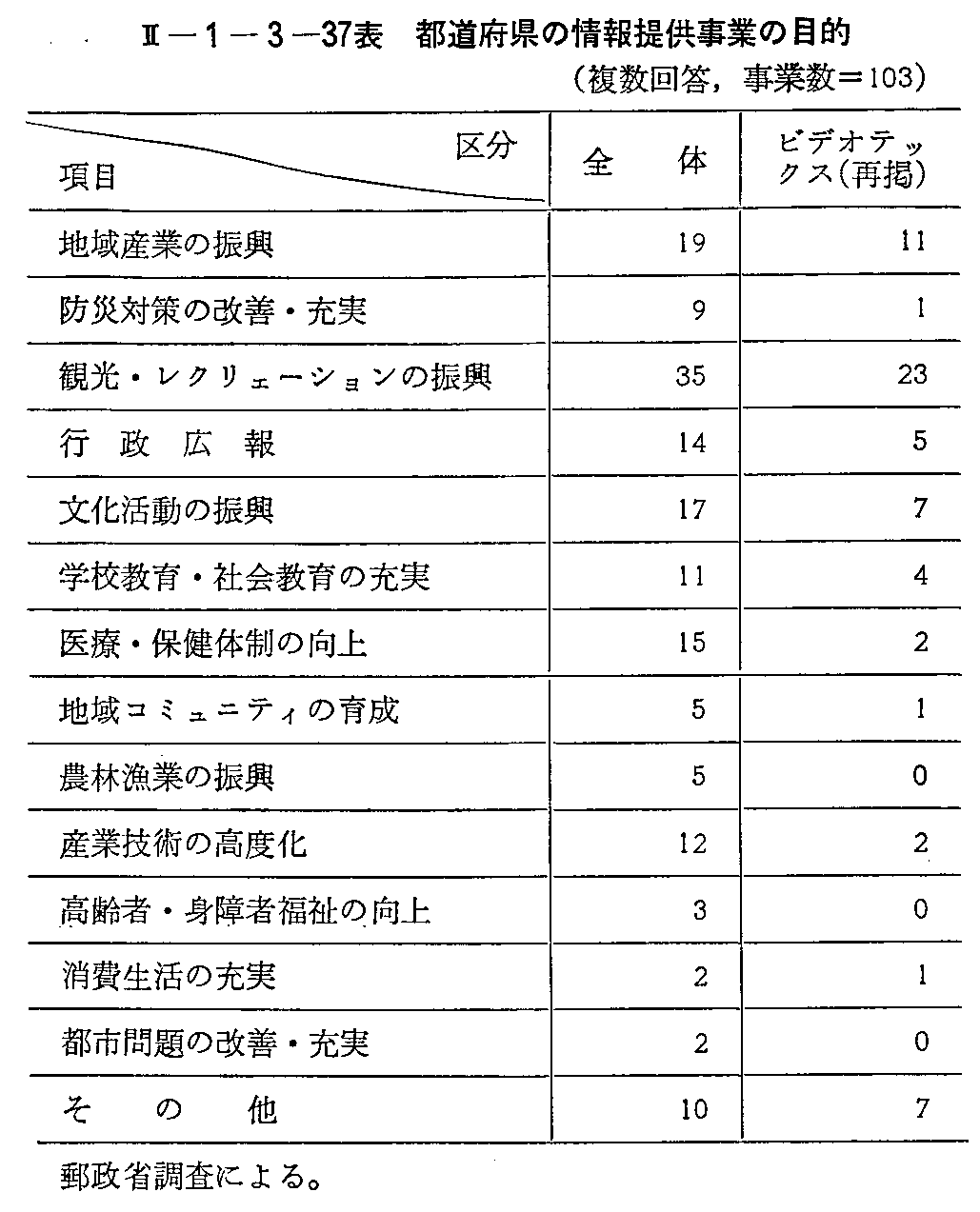
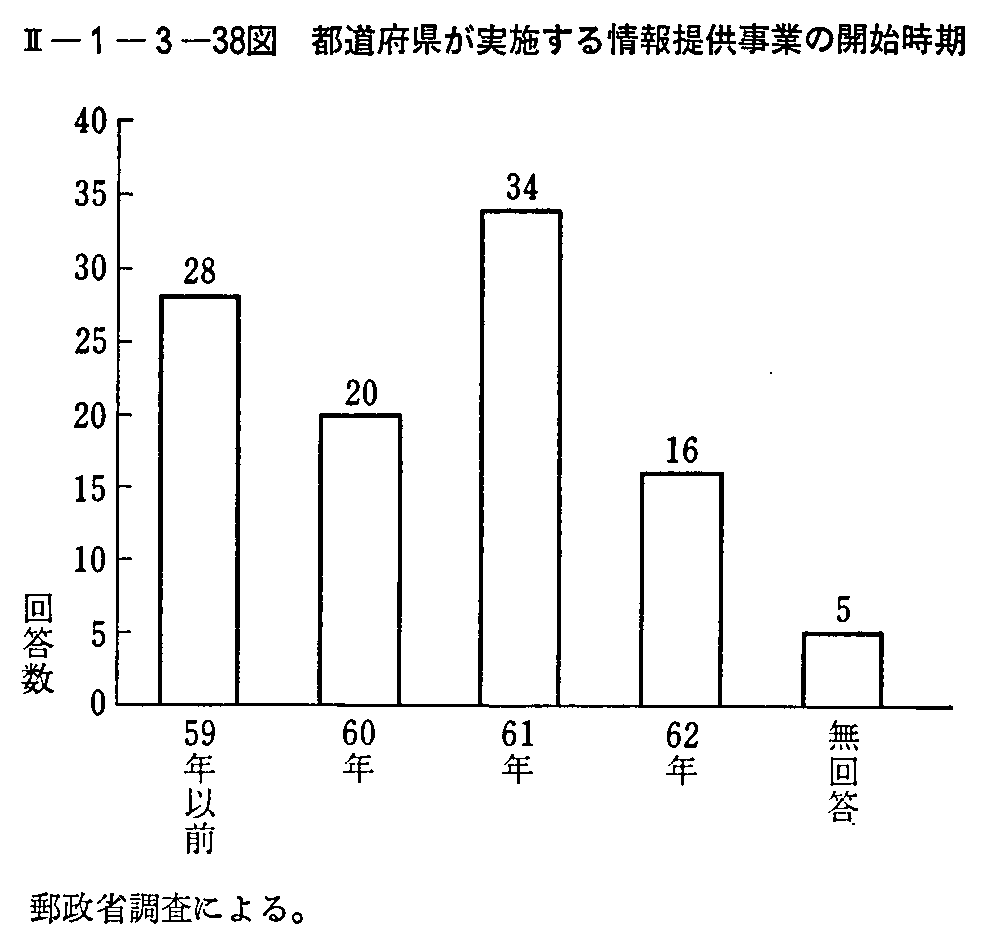
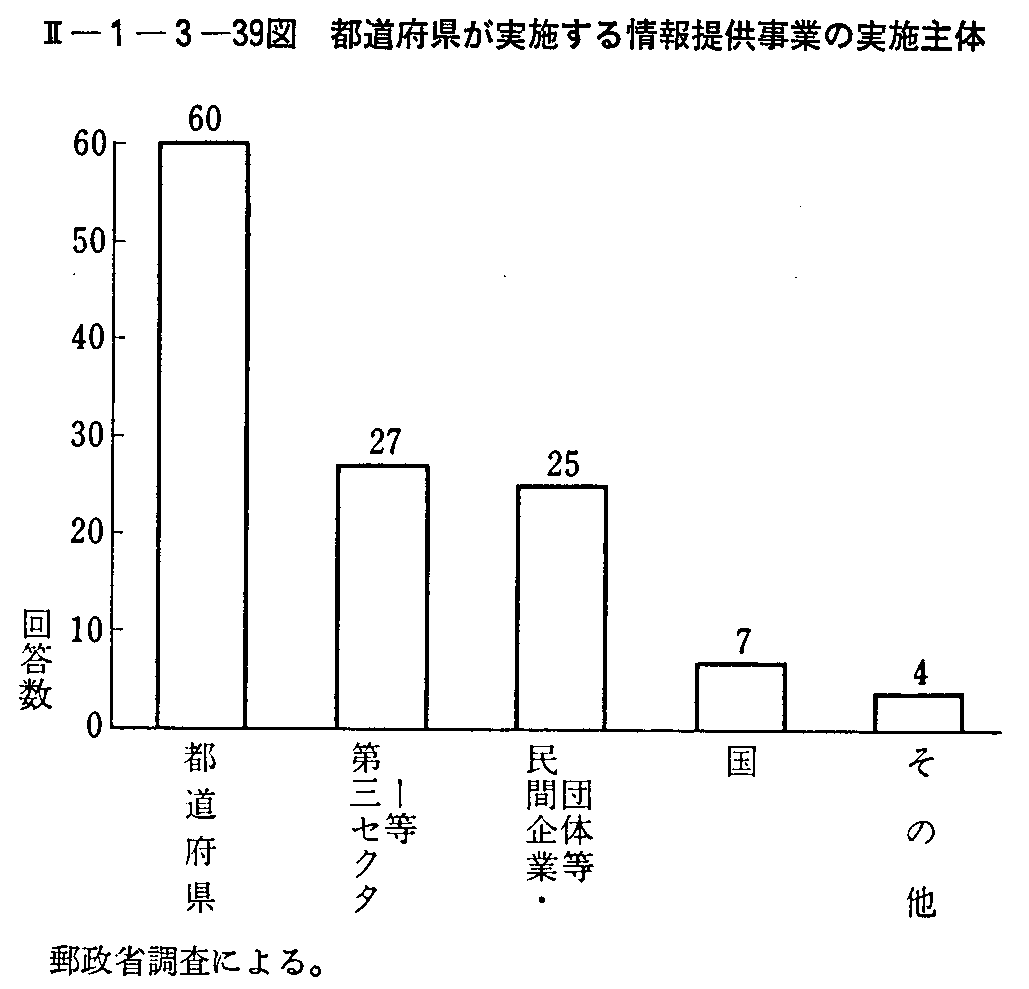
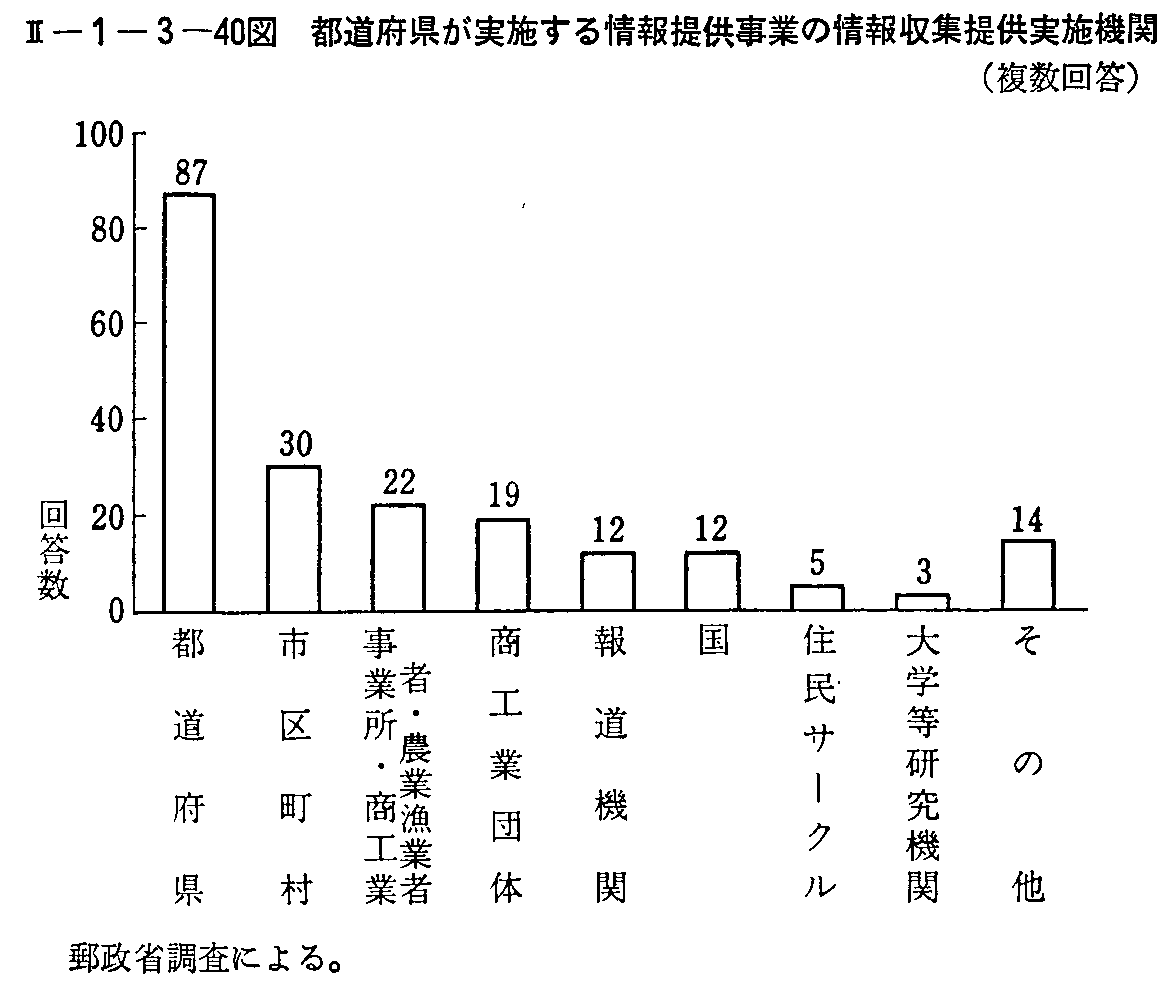
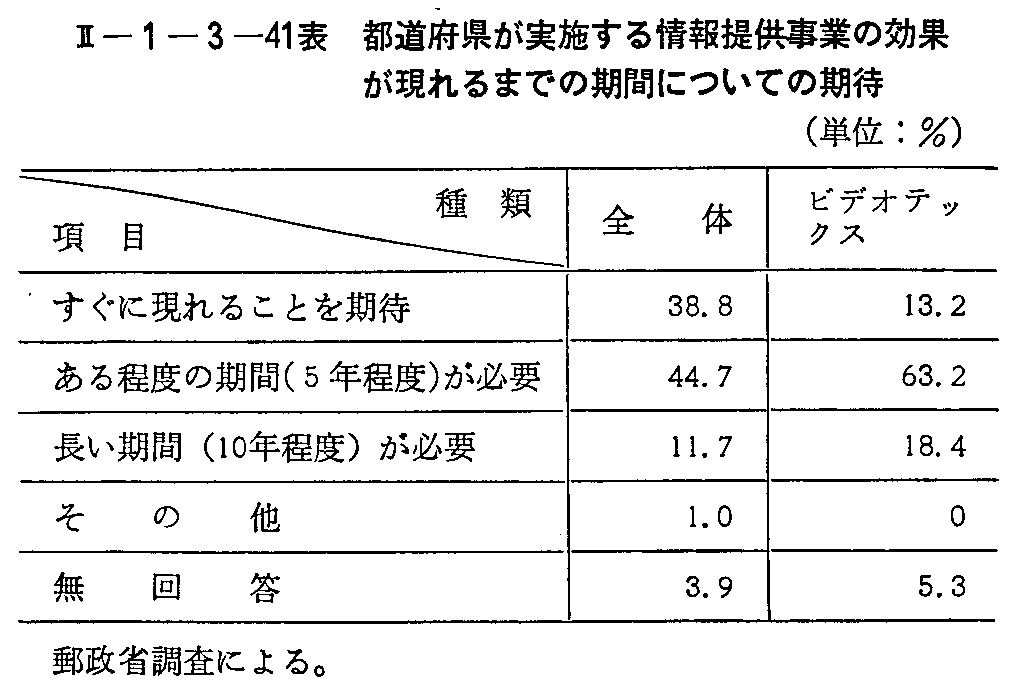
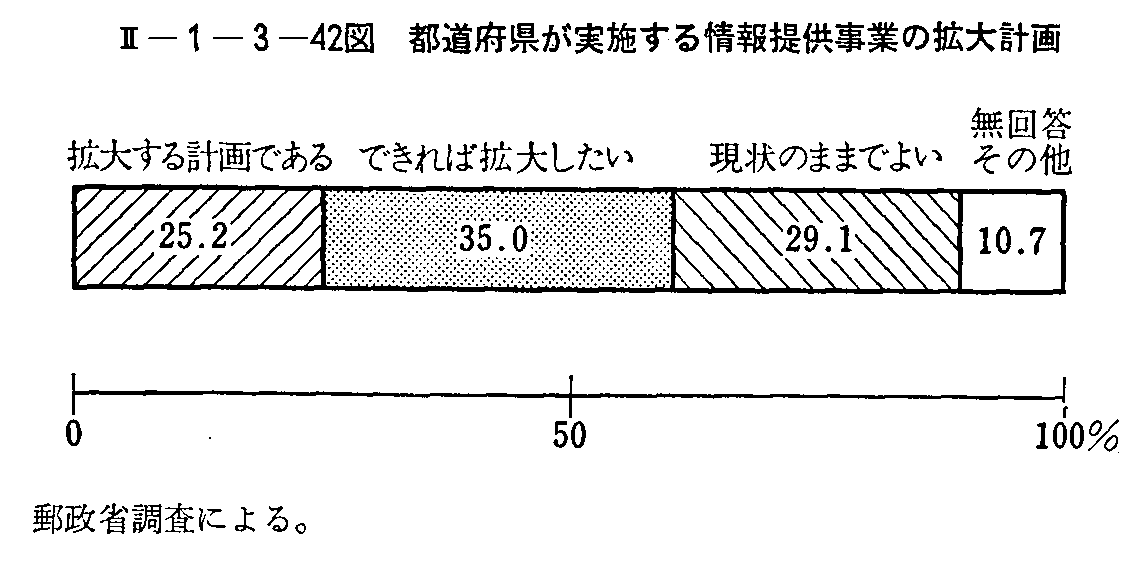
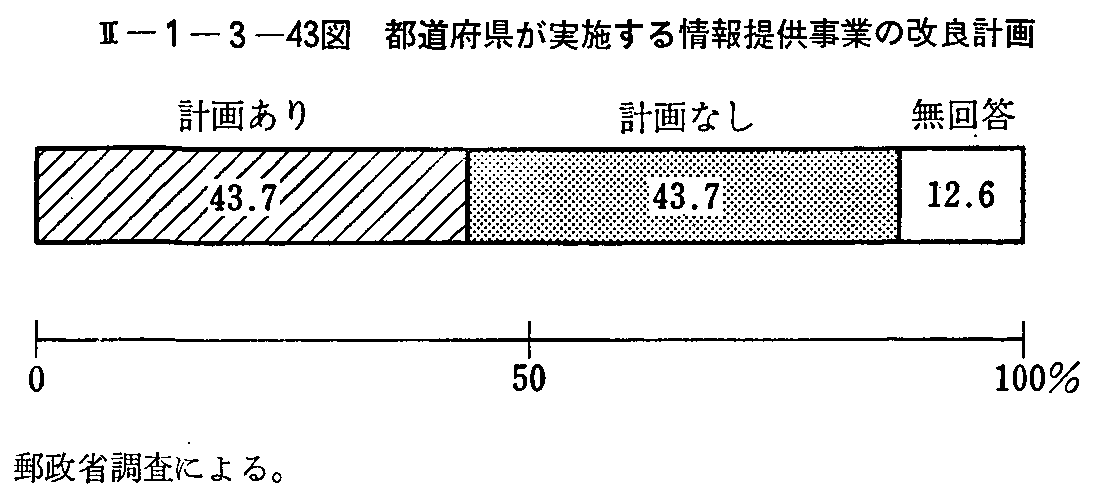
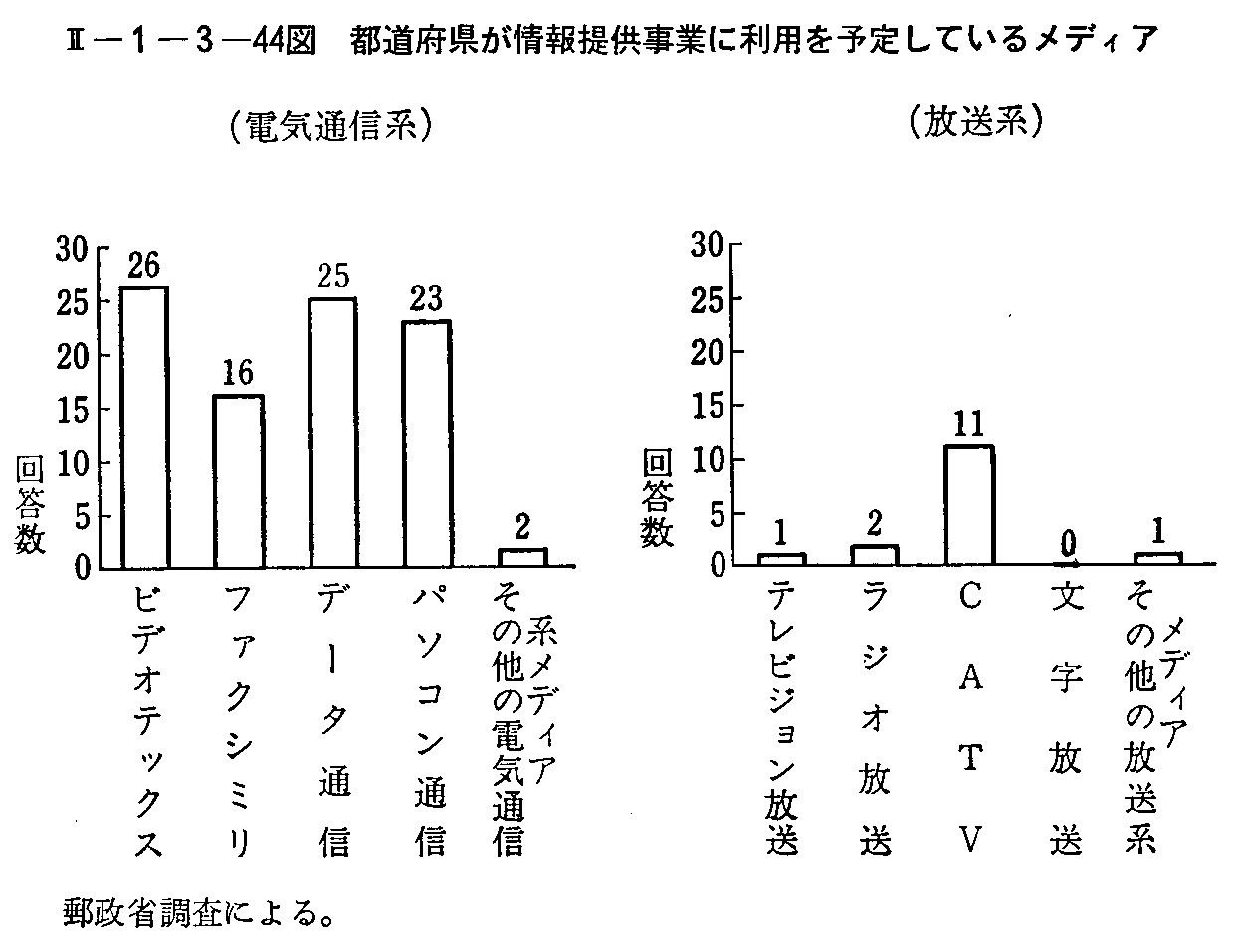
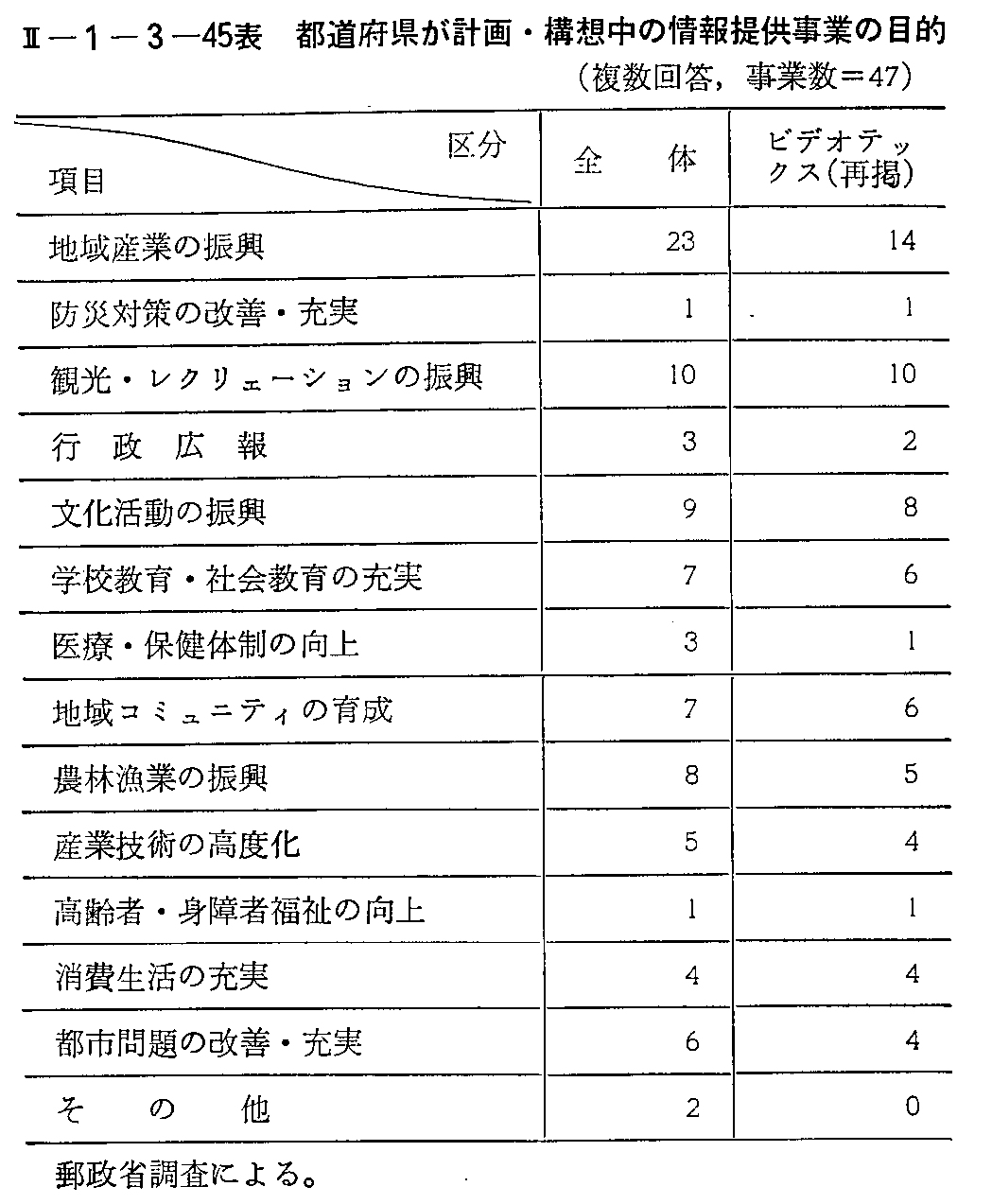
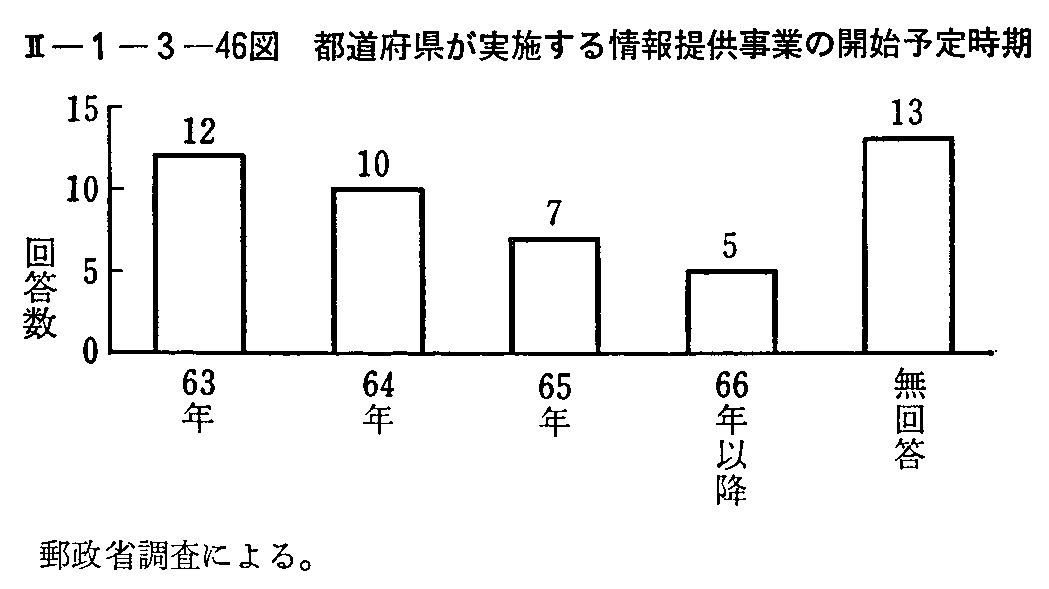
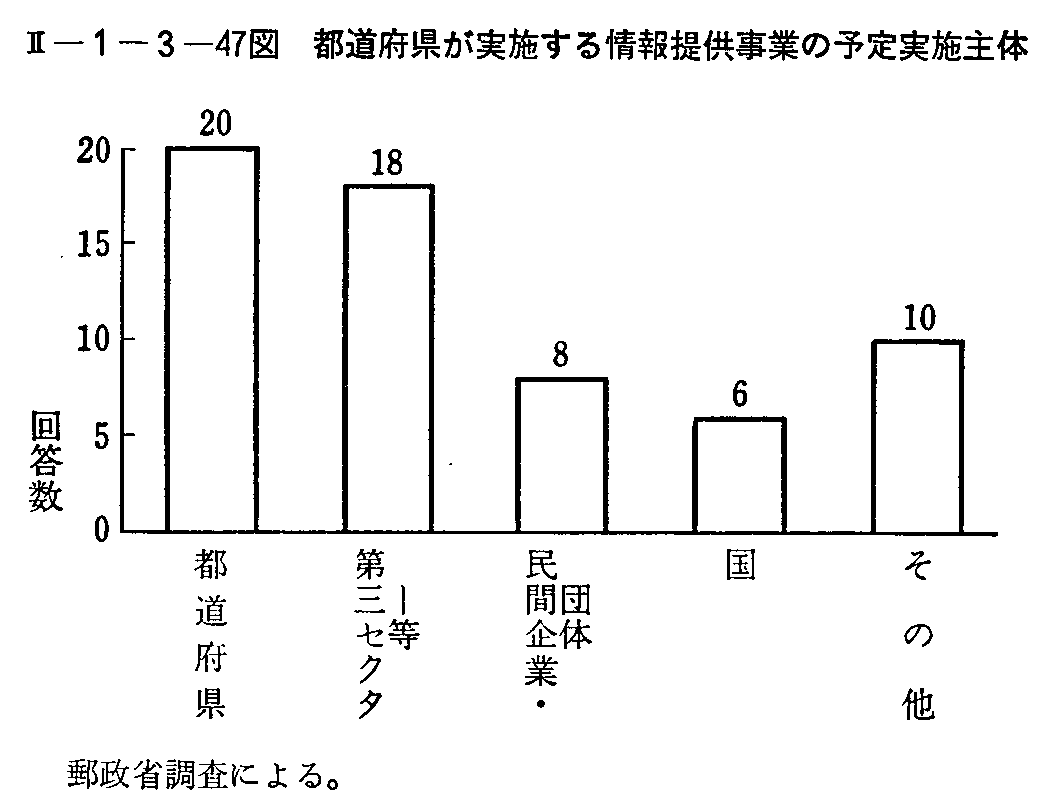
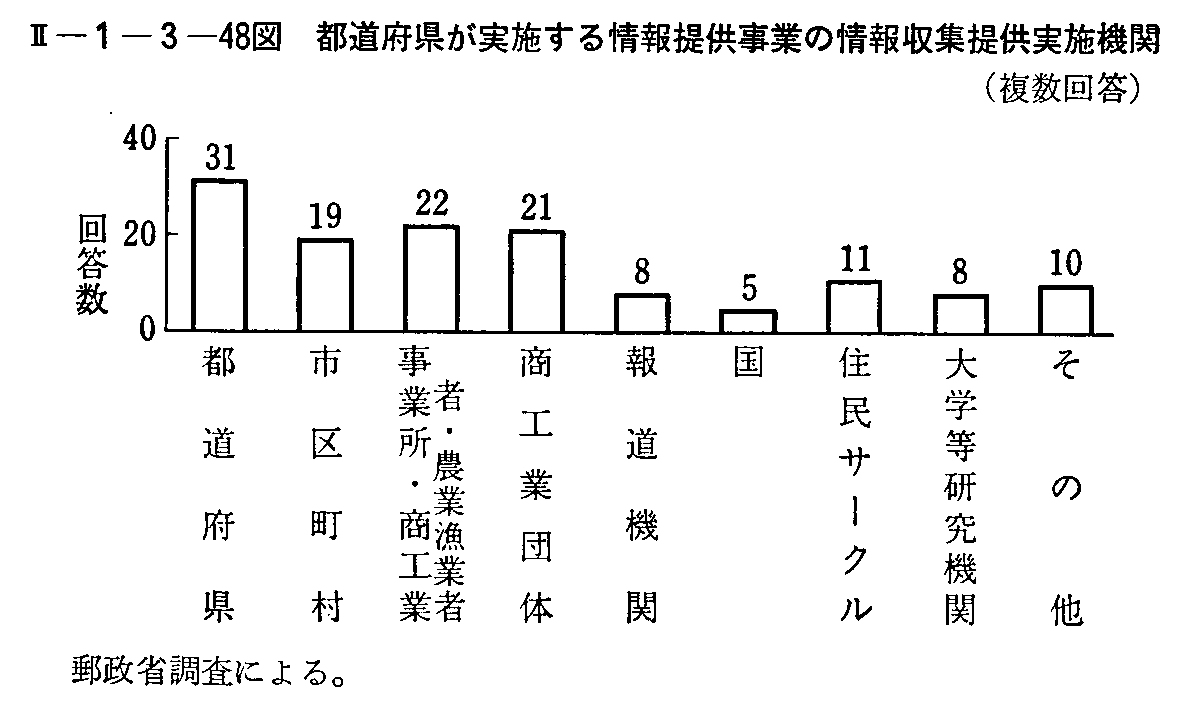
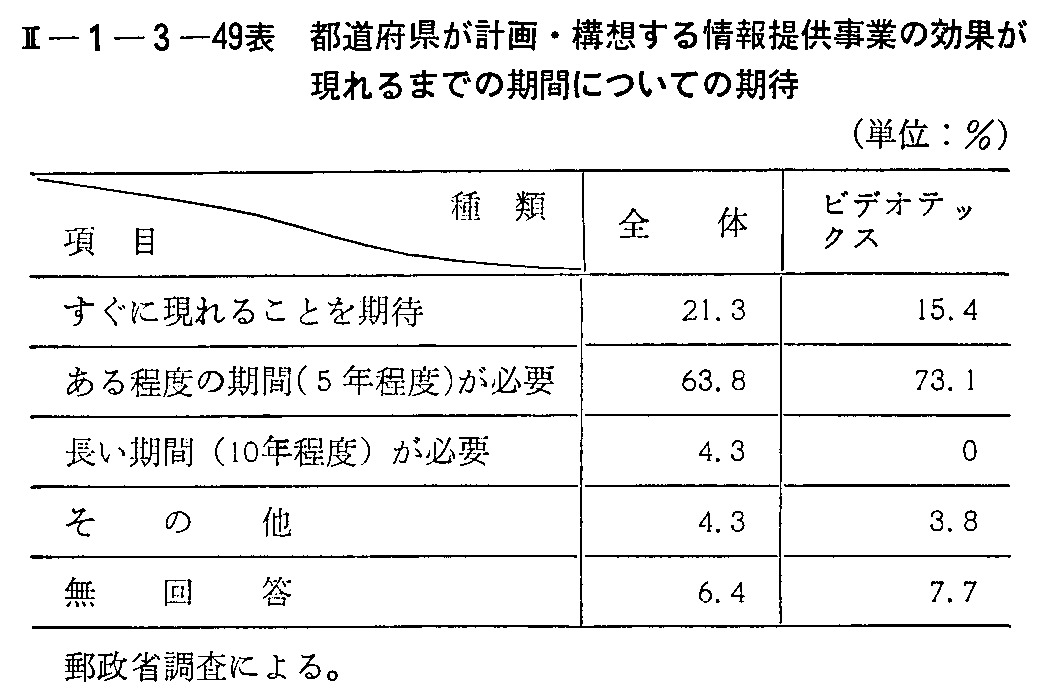
|