 第1部 総論
 第1節 昭和56年度の通信の動向  第2節 情報化の動向  第3節 諸外国における通信政策及び事業運営をめぐる動向
 第1節 通信環境の変化  第2節 通信サービスの高度化・多様化
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第2節 通信サービスの高度化・多様化
1 宇宙通信
(1)我が国の動き
ア.宇宙通信技術の開発
近年の著しい宇宙開発の進展は,通信・放送の分野における宇宙空間の実利用,宇宙通信の実用化を可能とした。
宇宙通信システムは,人工衛星を用い,広い地域を電波によりカバーする新しいメディアの通信システムであり,災害に強く,地形,建物等にょる障害を克服することができ,広帯域,高品質の長距離伝送路や広域ネットヮークを迅速かつ経済的に実現できるという特長を有している。
このため,我が国においては,昭和40年代初頭から宇宙通信について検討が開始され,実験用中容量静止通信衛星(CS「さくら」)及び実験用中型放送衛星(BS「ゆり」)を通じて各種の基礎的宇宙通信技術の開発が行われてきた。
(ア)実験用中容量静止通信衛星(CS「さくら」)による実験CS「さくら」は52年12月に静止軌道上に打ち上げられたもので,53年5月から郵政省を中心に電電公社,宇宙開発事業団等の協力の下に衛星通信に関する各種の実験が継続実施されている。これまでの実験により,準ミリ波帯等の電波を用いた電話,画像等の伝送特性が明らかになるとともに,コンピュータ・ネットワーク,統合ディジタル衛星通信システム等新しいシステムを確立するための基礎データが得られた。
また,災害通信,新聞紙面伝送等種々の利用形態に即した実験が実施され,それらが技術的に実現可能であること,その場合における技術面,運用面における諸条件等が明らかになった。
(イ)実験用中型放送衛星(BS「ゆり」)による実験
BS「ゆり」は53年4月に静止軌道上に打ち上げられたもので,53年7月から郵政省を中心にNHK,宇宙開発事業団等の協力の下に衛星放送に関する各種の実験が行われ,56年度をもって終了した。この実験により,日本の大部分の地域では直径1m程度のアンテナを,また,小笠原,南大東島等の離島では直径4.5m程度のアンテナを設置することにより良好なテレビジョン画像を受信できること,車載型の送受信局により全国各地から衛星放送用テレビジョン信号が送受信できること,などが明らかになった。
また,高精細度テレビジョン信号,高品質のステレオ音声信号,静止画放送信号等の伝送実験が実施され,貴重なデータが得られた。これらの成果によって,12GHz帯を用いた個別受信用の衛星放送システムの実用化の見通しが得られた。
イ.実用衛星の開発と利用
(ア)衛星の実用化推進のための組織体制の整備
CS「さくら」及びBS「ゆり」による実験成果を踏まえ,宇宙通信の早期実用化を図るとともに,静止軌道及び宇宙通信周波数の有効利用,資金及び技術力の集約化等を図り実用衛星の管理,運用等を一元的かつ効率的に行うための機関として,54年8月,「通信・放送衛星機構」が設立された。同機構は,宇宙通信の実用化に備え,衛星管制センターの建設等所要の準備を進めるとともに,通信・放送衛星に対する利用者機関の要望を調整し衛星の諸元に反映させるなどの役割を果たしており,我が国における宇宙通信の普及,発展に大いに貢献していくものと期待されている。)第一世代の実用衛星CS-2,BS-2の打上げ
CS「さくら」及びBS「ゆり」による実験の成果を基に,我が国では宇宙通信の実用化を積極的に推進しているが,初の実用通信衛星CS-2は電話換算約4,000チャンネルの伝送容量を有しており,CS-2aが58年1・2月期に,CS-2bが同年8・9月期に打ち上げられることとなっている(第1-2-5図参照)。
衛星通信システムは,地上の災害の影響を受けにくいこと,地形等に左右されず遠距離,広範囲な通信が可能であること,異常トラヒックに対する対応や回線設定が容易であること,などの特長があることから,CS-2は,[1]災害時の通信の疎通を図るための災害対策用通信,[2]離島に対する通信品質の向上や通信需要の増大に対処するための離島通信,[3]各種催物や事故現場等からの中継に対応するための臨時通信等に利用される予定である。
CS-2の利用機関としては,国内公衆通信業務を行う電電公社,人命・財産の保護等のための公共業務用通信を行う警察庁,消防庁,建設省,日本国有鉄道,電力会社が予定されている。
一方,我が国初の実用放送衛星BS-2は,カラーテレビジョン2チャンネルの伝送容量を有しており,BS-2aが59年1・2月期に,BS一2bが60年8・9月期にそれぞれ打ち上げられることとなってぃる(第1-2-6図参照)。
NHKでは,辺地又は離島におけるテレビジョン放送の難視聴解消が重要な課題となっており,BS-2の打上げ予定時期である58年度においてもなお40数万の難視聴世帯が残るものと推定されることから,この衛星はNHKテレビジョン放送の難視聴解消に対する抜本的解決策としての利用のほか,非常災害時における放送網の確保やテレビジョン放送の受信品質の改善にも役立つものと期待されている。
(ウ)第二世代の実用衛星CS-3,BS-3の打上げ
第一世代の実用衛星CS-2,BS-2はそれぞれ衛星寿命5年を目標としているので,昭和60年代前半には,これら第一世代の実用衛星のサービスを継続・発展させるとともに,増大かつ多様化する通信,放送
ニーズに対処するため更に大容量,長寿命の次期衛星,すなわち第二世代の実用衛星CS-3,BS-3の打上げが必要となる。
このため,郵政省では,55年度から電波利用開発調査研究会に学識経験者等からなる実用衛星部会を設け,CS-3,BS-3の利用の在り方について調査・審議を行い,CS-3については56年6月に,BS-
-3については57年3月にそれぞれ報告書の提出を受けたところである。
また,これと並行して,郵政省では最適衛星システムの技術的検討も進めており,57年度はCS-3の予備設計,BS-3の概念設計を行うこととしている。
このような状況を背景に,CS-3(伝送容量:電話換算約6,000チャンネル)については実用衛星部会の報告書を参考にするなどしてその具体的利用について検討を進めているが,現在のところ次のような利用の仕方が考えられている。
[1] CS-2により提供される非常災害対策用通信,離島通信等のサービスを継続させるとともに,利用の拡大を図る。
[2] 衛星通信は一地点から多数の地点に向けて同時に同一内容の情報を伝達するいわゆる同報通信に適していることから,この特性を生かして新聞紙面伝送,テレビ・ラジオの番組伝送等の分野へ利用を図る。
[3] 衛星通信の広域性,広帯域性を生かして,テレビ会議,高速データ通信等を行う統合ディジタル通信の分野へ利用を図る。
また,BS-3については,宇宙開発技術の進展等を踏まえ,カラーテレビジョン3チャンネルないし4チャンネルの伝送容量を有する衛星とすることを目標としており,現在のところ次のような利用の仕方が検討されている。
[1] NHKは辺地又は離島における難視聴の解消,非常災害時における放送網の確保等BS-2からのサービスを継続するとともに,併せて種々の利 用方策を検討することにより衛星の一層の有効利用を図る。
[2] 放送大学の早期全国普及を図る観点から,放送大学学園によるBS-3の利用を検討する。
[3] 地上放送との調和を図りつつ視聴者の多様なニーズにこたえるとともに 衛星放送の一層の普及を図るため,新規の一般放送事業者による放送衛星の利用を検討する。
[4] 放送需要の多様化と技術の進歩に応じて文字放送,ファクシミリ放送,PCM音声放送,高精細度テレビジョン放送等の新方式の放送の試行的実施を行う。
(2)諸外国の動き
衛星通信システムは長距離伝送を主とした国際通信の分野において最初に商用化され,発達してきた。現在では国内の通信システムにも衛星が導入されており,地域的な衛星通信システムも計画されている。また,海上移動通信システムや放送システムにも衛星が使用され始めている。
ア.国際通信システム
衛星通信サービスを提供する国際システムとしては,国際電気通信衛星機構(インテルサット),国際海事衛星機構(インマルサット)及びインタースプートニクがある。
インテルサットは,国際通信を主とした電話,テレックス,テレビジョン伝送等の通信サービスを提供しており,1982年7月現在,106か国が加盟している。1965年にアーリ・バードによりそのサービスを開始して以来,トラヒック量ほ増大の一途をたどっているため,1980年にV号系衛星が打ち上げられており,1984年には改良型の<5>-A号系衛星が打ち上げられる予定である。また,地域別のトラヒック量に関しては,大西洋地域及びインド洋地域での伸びが大きく,これらのトラヒックの増大に対処するため,1986年にはより大型のVI号系衛星を打ち上げる計画が進められている。
インマルサットは1982年2月1出米国のマリサットシステムを引き継ぎ,船舶を対象とした電話,テレックス等の通信サービスを提供しており,1982年7月現在,37か国が加盟している。このシステムを利用する船舶数及びトラヒック量は急増しており,特に大西洋においてこの煩向が著しいので,1982年5月111.容量の大きな欧州宇宙機関(ESA)の所有するマレックス衛星に置き換えられた。インド洋及び太平洋においても,マレックス衛星又はインテルサットV号系衛星に搭載された悔事通信システムに置き換えられる予定である。
インタースプートニクは,ソ連のゴリゾント衛星を使用して電話,テレビジョン等の通信サービスを提供しており,1982年7月現在,ソ連,東欧圏を中心に15か国が加盟している。
イ.国内及び地域衛星通信システム
現在,独自の衛星を打ち上げ,国内通信を行っている国は米国,カナダ,ソ連及びインドネシアであり,フランス,西独,インド等においても打上げ計画が進められている。また,ノールウェー,ブラジル,アルジェリア,チリー等では,インテルサット衛星の一部を利用して国内通信を行っている。
米国では,RCAアメリコム社,ウェスタン・ユニオン電信会社(WUT),AT&T/GTEサテライト社(GSAT),アメリカン・サテライト社(ASC)及びサテライト・ビジネス・システムズ社(SBS)の各社が衛星による通信サービスを提供しており,国内衛星通信システムが最も発達した国である。このうち,SBS社のSBSシステムはデータ,画像を統合した高速ディジタル伝送が可能な企業内ネットワークを提供する新しいシステムであり,高速データ通信やテレビ会議等の多様なサービスが可能なものとして注目されている。
カナダは人口が希薄でまばらに広がっているため積極的に宇宙開発を行ってきたが,1972年11月にアニクAを打ち上げ,世界で最初に国内衛星通信システムを持つ国となった。現在,テレサット・カナダ社により4機の衛星が運用されている。また,インドネシアも国内衛星通信システム(パラパ)を所有しており,その衛星搭載中継器の一部をマレイシ乙
タイ,フィリピン等の近隣諸国に提供している。この両国とも,近い将来次世代の衛星を打ち上げる計画がある。
地域衛星通信システムとしては,ヨーロッパでは暫定欧州電気通信衛星機構(暫定ユーテルサット)が,また,アラブ諸国ではアラブ衛星通信機構(アラブサット)が地域通信システムを運用するために設立され,現在,衛星システムの開発が進められている。(3)今後の取組
我が国において,宇宙通信は本格的な実利用の段階を迎えつつあり,今後の増大かつ多様化する通信需要を充たす新しい通信手段として一層の発展が期待されている。
衛星通信は,広い地域を一挙にカパーできることや,周波数帯域が広く高品質の回線が確保できることなどの特長を持っていることから,その特長を生かした利用方法の開拓,多様化する通信・放送需要に対処するための新たな利用技術の開発及び利用の促進を図るための宇宙通信システムの経済化が課題となっている。さらに,世界的な周波数及び静止軌道のひっ迫に対処するための技術開発が必要とされている。
固定衛星通信については,同報通信,統合ディジタル通信等の分野への本格的利用や,将来予想される大型衛星時代に備えて,限られた特定の地域に電波を発射できるマルチビームアンテナ,衛星内交換技術,新しい周波数帯の開発等が急務となっている。
一方,移動衛星通信については,現在:主として短波帯により行われている洋上の船舶との通信が,回線の品質,容量,通信可能時間等に制約が多いことや周波数帯の使用が混雑していることなど多くの問題を抱えているので,この解決策としての国内海上移動通信システムの導入の検討が進められている。将来的には,自動車,航空機等の移動体との通信にも衛星を利用することが考えられている。
このほか,衛星を利用した捜索救難通信システムは,現在運用中の地上方式によるものに比較して受信可能範囲,遭難信号の発射位置の算出,応答時間等の面で優れた機能を発揮することが考えられるため,国際海事機関(IMO)においてその導入について検討が進められており,我が国としてもその対応を検討していく必要がある。
また,衛星放送については,文字放送,ファクシミリ放送,PCM音声放送,高精細度テレビジョン放送等の新しい放送への利用を検討すること,受信用アンテナの小型化,さらにはロ-カル放送実現のための放送衛星技術の開発等が必要である。
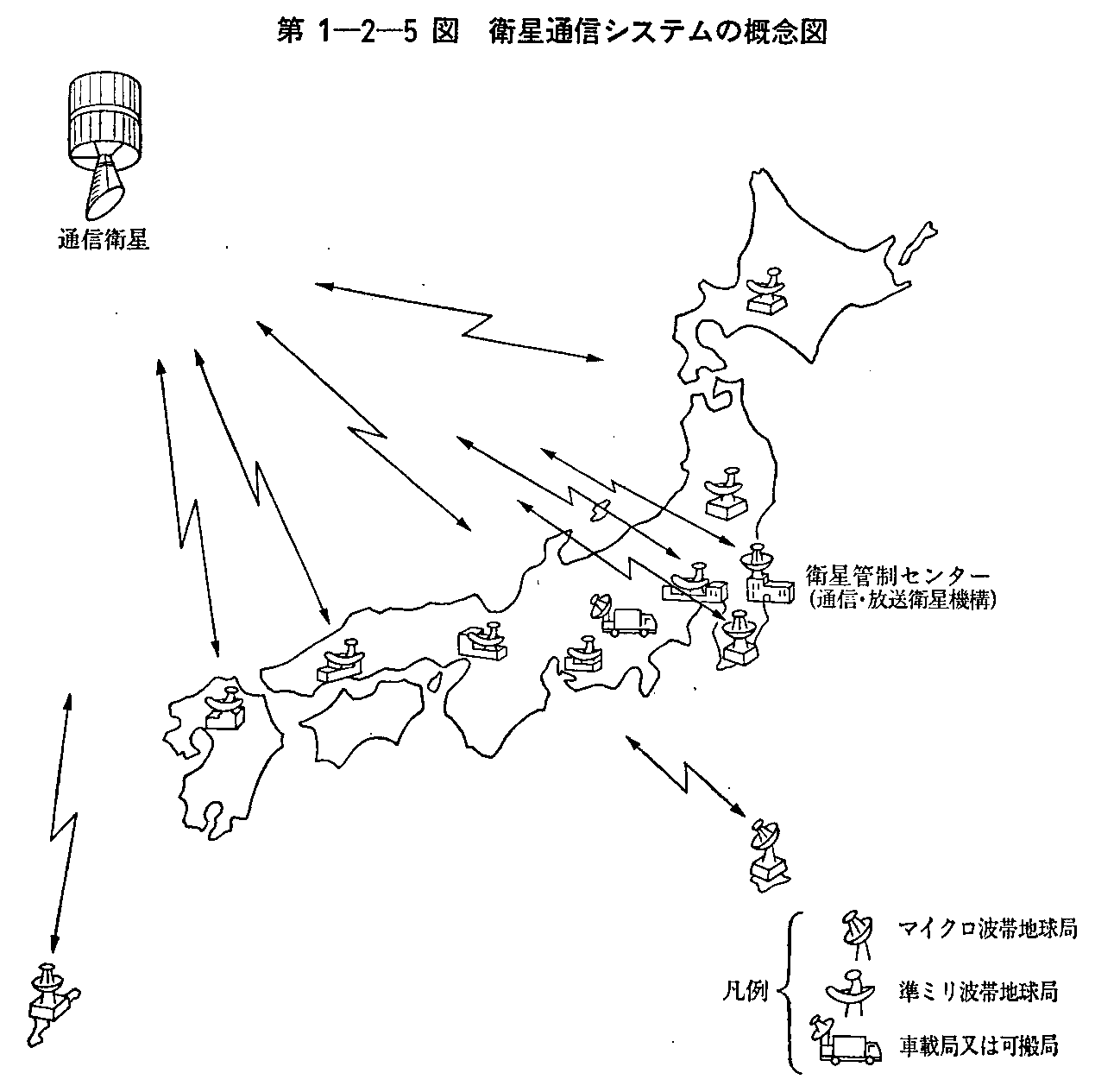
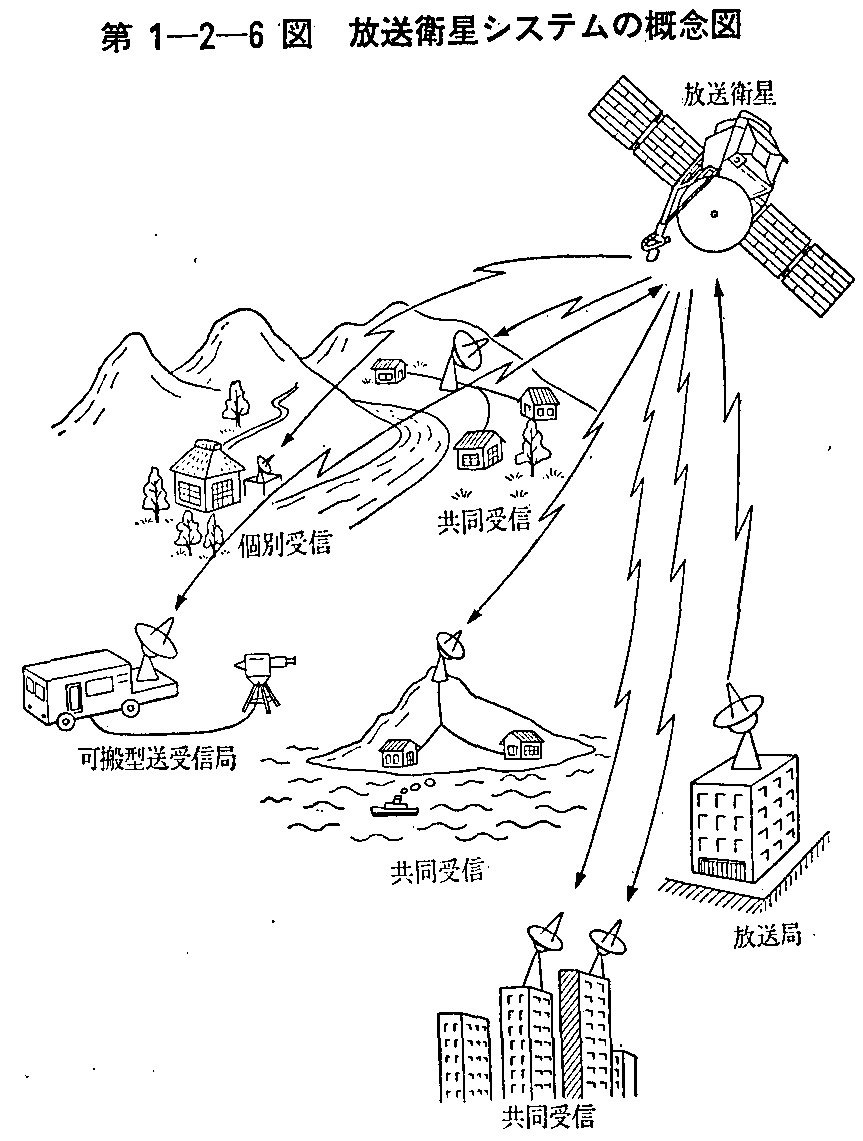
|