2 有線放送電話業務
(1) 設備の状況
ア.施 設 数
施設数は,38年度の2,649をピークに年々減少しているが52年度末における施設数は986であり,51年度末現在の1,110に比べて124(11.2%)の減である。
その減少の要因としては,農林漁業地域における公社電話の普及に伴い,通話手段としての有線放送電話を利用する者が減少することにより生じる施設の経営難や設備更改のための資金難等があげられる。
施設数の最近の年度別状況は第2-2-11表のとおりである。
施設の運営主体は,有線放送電話の基盤が農林漁業地域であることもあって,農林漁業団体が最も多く716(72.6%),次いで地方公共団体197(20.0%),
市町村や農協等の共同経営体49(5.0%),公益法人24(2.4%)となっている。
イ.規模別分布状況
有線放送電話の1施設平均端末設備数は2,008であるが,規模別の分布をみると,平均端末設備数以下により多く分布している(第2-2-12表参照)。
ウ.端末設備数
52年度末における端末設備数は197万9,431であり,51年度末の212万3,377に比べて14万3,946(6.8%)の減となっている。44年度に323万とピークに達した端末設備数は,以後年々減少しているが,これは公社電話の増加率と深い関係にあることが推測できる(第2-2-13表参照)。
エ.電電公社回線と接続しているもの
電電公社と接続通話契約を締結している施設は,52年度末において施設数で368(全施設数の37.3%),端末設備数で76万5,462(端末設備総数の38.7%)となっている。接続通話契約の種別には,第一種(市内接続通話)接続と第二種(市内,市外接続通話)接続とがあるが,ほとんど第二種接続である。
接続有線放送電話は,39年に制度化されて以来,47年度まで増加の一途をたどっていたが,48年度から減少の傾向を示している。これは,公社電話の普及に伴い,地域外との通話手段としての接続通話の利用が減少したことによるものと見られる。
オ.交換方式
ダイヤル式の自動交換方式をとっている施設は,52年度末において施設数で755(全施設数の76.6%),端末設備数で169万446(端末設備総数の85.4%)となっている。
自動交換方式の端末設備数は,47年度からほぼ横ばいとなっているが端末設備総数が減少していることもあって,有線放送電話全体における自動化率は,年々上昇している。
なお,施設の平均端末設備数は2,239であり,全施設の平均端末設備数2,008に比べ,自動交換方式をとる施設が大型であることを示している。
(2) 利用状況
ア.利 用 者
52年度末現在における利用者数は191万4,592人であり,51年度末現在の205万4,884人に比べ6.8%の減である。
イ.利 用 料
52年度における利用料は,全施設平均で688円であり,51年度の668円に比べ20円(3.0%)の増となっている。これは,人件費増が利用料に反映したものと思われる。
ウ.放送時間
有線放送電話は,放送と通話を一体として行うメディアであるが,そのうち放送の利用状況についてみると,52年度の1日平均放送時間が1時間24分となっている。
(3) 総合情報通信システムの開発調査
48年に設置された「地域通信調査会」における検討結果を踏まえ,49年度から,有線放送電話に,遠隔制御,映像伝送,情報処理などの多目的機能を付加した総合情報通信システムの開発調査を行っているが52年度は,長野県穂高町の有線放送電話施設において,水道・ガスの自動検針システムの運用実験を行った。
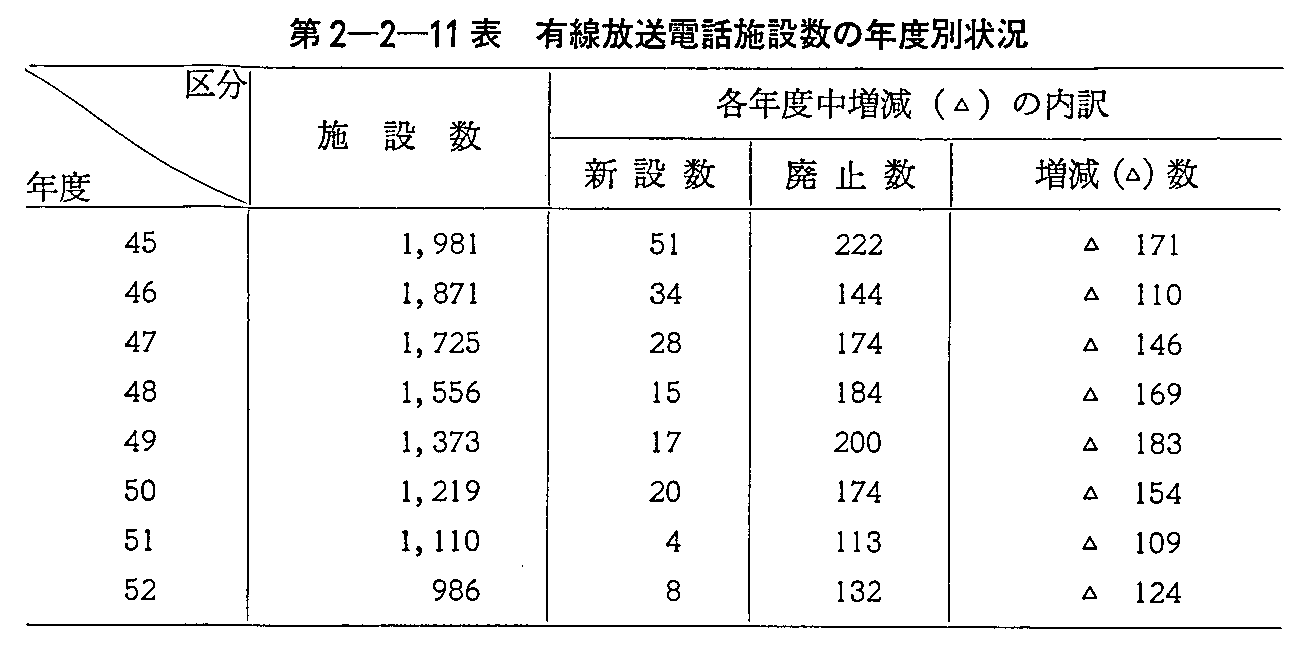
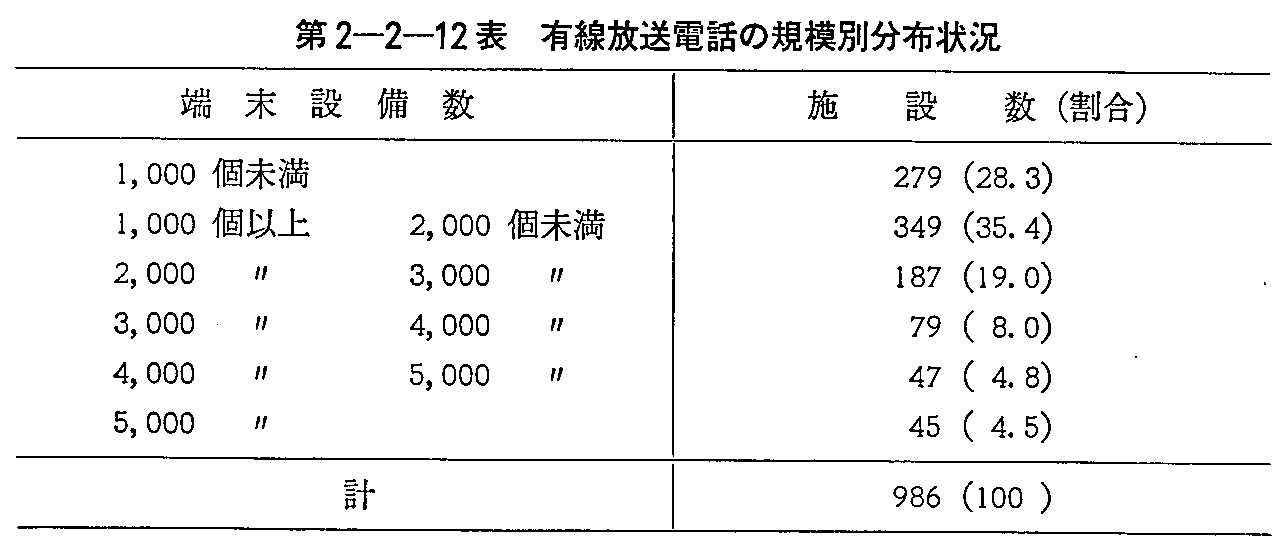
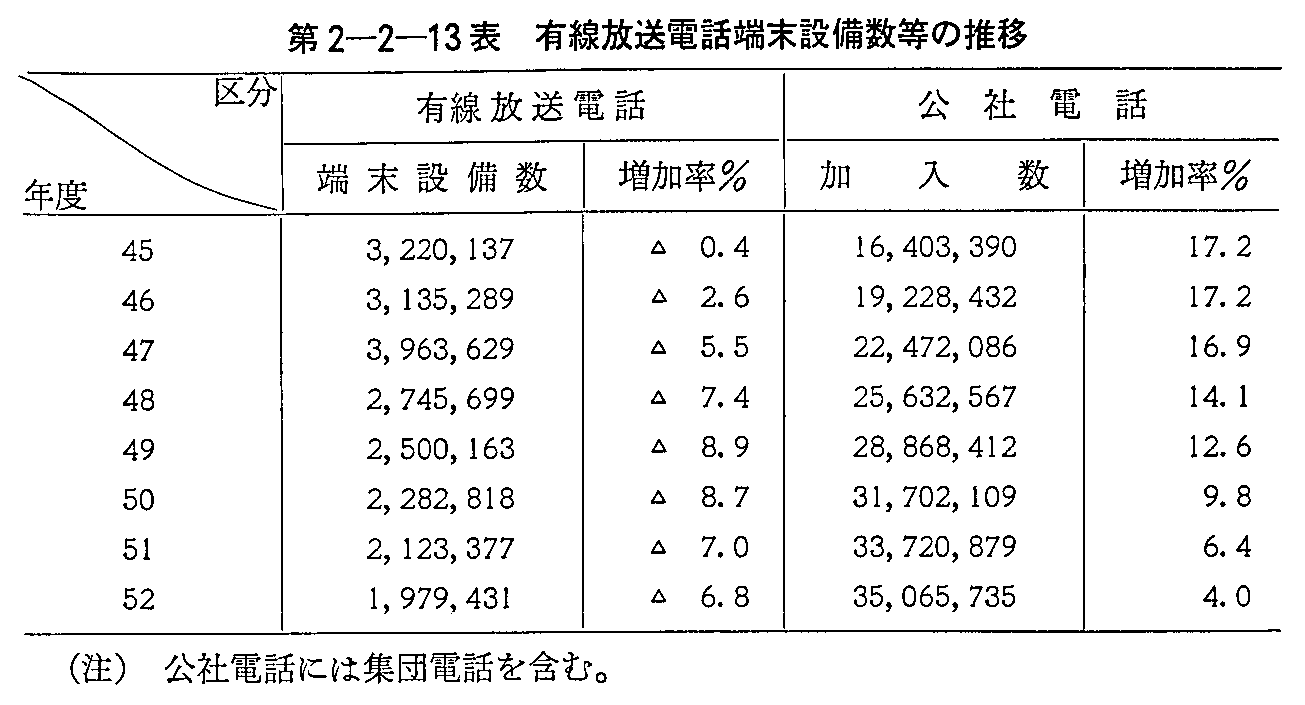
|