 第1部 総論
 第1節 昭和51年度の通信の動向
 第1節 宇宙通信発展の歩み  第2節 進展する宇宙通信の現況  第3節 宇宙通信の監理  第4節 宇宙通信の展望
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 電磁波有効利用技術  第4節 有線伝送及び交換技術  第7節 衛星通信の研究  第8節 その他の研究
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第1節 昭和51年度の通信の動向
1 通信の動向
(1) 概 況
ア.国内通信の動向
最近の国内通信の動向は,第1-1-1図のとおりである。
郵便サービスについてみると,51年度の内国郵便物数は129億通(個)で,前年度に比べ7.9%の減となり,27年度以来,24年ぶりの減少を示した。これは経済の低迷に51年1月の料金改定が加わり,利用が落ち込んだものとみられる。年賀及び選挙郵便物を除いた平常信の動きをみると,料金改定後1年間は,利用の落ち込みが目立ち,51年度年間では8.5%の減となったが,料金改定1年後の52年2月,3月は,前年同期よりそれぞれ7.7%,9.7%の増となっており,利用物数は回復の兆しがみえる。
これを郵便サービスの生産額でみると,利用物数の減少にもかかわらず,51年1月に料金を改定したこともあって,対前年度比57.2%増の7,065億円となった。
なお,利用状況を諸外国と比較すると,郵便物数(外国郵便を含む。)は49年度で米国に次いで第2位であるが,国民1人当たり差出通数は127.5通と米国の428.6通,英国の195.2通,西独の164.2通等と比べてなお相当のへだたりがある。
電信サービスについてみると,電報の発信通数は38年度の9,461万通をピークに毎年減少を続けているが,51年度においては11月の料金改定の影響もあって,4,189万通と対前年度比7.4%の減少となり,50年度の減少率2.2%をかなり上回った。利用内容をみると,電報通数の減少にもかかわらず近年微増の傾向にあった慶弔電報は2〜3倍の料金値上げが響いて,5.4%の減少を示したが,全体に占める割合は年々多くなっており51年度では65.6%を占め50年度の64.2%よりふえている。その反面「チチキトク」といった緊急内容の電報は,わずか1%を占めるにすぎない。
また,国民1人当たり利用通数は年間0.4通と少ないが,英国,西独等の0.1通と比べると高い値を示している。これは,慶弔電報の利用が多いことなどが影響しているものとみられる。
加入電信加入数は,伸び悩みの傾向をみせ,51年度末7万6千加入で,前年度に比べ2.1%の増加にとどまった。これは,景気回復の遅れと,料金改定の影響などにより,新規需要数が伸び悩んだことに加え,データ通信やファクシミリ等の他の通信メディアへの移行によるものとみられる。
51年度のこれら電信サービスの生産額は,電報通数の減少,加入電信加入数の伸び悩みにもかかわらず,料金を改定したこともあって480億円と対前年度比20.8%の増加になった。
51年度末の加入電話加入数は,3,372万加入に達した。このうち一般加入電話については,当初増設予定数260万加入に対し,景気回復の遅れ,料金改定による一時的な需要の落ち込み等により,61万加入下回り,199万加入が増設されたにとどまった。しかし,積滞電話の数は23万に減少し,需給関係は大幅に改善され,52年度末の積滞解消は目前となった。この他,地域集団電話については,9万加入が一般加入電話に変更された。
電話普及の現状をみると,人口100人当たりの加入電話普及率は,29.7加入となった。又,電話機数では米国に次いで2位,100人当たり電話機数では,米国,スウェーデン,スイス,カナダ,ニュー・ジーランド,デンマークに次いで第七位に位置している。一般加入電話に占める住宅用電話の割合は,65.0%に達し,100世帯当たり普及率も,66.1加入となった。このような住宅用電話の普及が進行しているなかで,電話に対する顧客のニーズは,高度化,多様化の傾向を強め,各種の附属装置等においても全体的に着実に増加している。特に電話ファクスについては,ファクシミリ通信の急速な普及を反映して,51年度末設置台数は5,600台と前年度の2倍となっている。また,従来からのサービスに加え,「ミニプッシュホン」,「でんわばん」(不在案内)が新たに提供されるようになった。一方,このような急速な電話の普及に伴い,いたずら電話など電話を悪用する事例が世間の注目をひいている。
電話サービスの生産額については,景気の停滞にもかかわらず,料金を改定したこともあって2兆2,373億円と対前年度比19.6%の増加となった。
なお,農林漁業地域の通信手段として利用されている有線放送電話の端末設備は,前年度に比べ7.0%減少し212万台となった。また,51年度の有線放送電話の生産額は,前年度に比べ4.7%減の200億円となった。
専用サービスは,企業の情報量の増加傾向に伴い,電話のほかデータ伝送,模写伝送等多様な用途に利用されている。
その利用動向を回線数(A〜J規格)でみると,51年度末現在26万8千回線と前年度に比べ4.8%増加した。規格別内訳では,主として通常の音声伝送に利用されるD規格が21万回線で80%近くを占めている。51年度の専用サービスの生産額は,562億円で,対前年度比12.9%増となった。
飛躍的な発展を遂げてきたデータ通信は,51年度も順調に推移し,データ通信システム数は,51年度末2,057システム(私設システムを除く。)となり,前年度に比べ39.1%増加した。51年度において新たにサービスを開始したシステムとしては,全国信用金庫システム,農林省生鮮食料品流通情報システム等がある。電子計算機のうちでこれらデータ通信に使用されている割合を示すオンライン化率は,年々上昇しており,51年度末で7.5%となっている。
データ通信回線のうち,特定通信回線は5万3千回線と前年度に比べ15.6%増加しており,公衆通信回線も8千6百回線と,対前年度比63.3%の堅実な伸びを示している。
このような状況の下で電電公社のデータ通信サービスの生産額は742億円と前年度に比べ25.8%の増加となった。
テレビジョン放送は,国民の間に広く普及しており,日本放送協会(以下「NHK」という。)の受信契約総数は,51年度末において2,706万件で,対前年度比1.9%の増となった。このうち,カラー契約は,2,331万件となり,契約総数の86.1%となったが,普及の進展とともに,年度増加数の伸びは鈍化してきている。一方ラジオ放送は,カーラジオ及び個人用ラジオ等,若い世代を中心とした需要に支えられて地道な発展を続けている。
放送サービスの生産額については,NHKでは51年6月のテレビ受信料の改定もあって対前年度比46.2%増の1,881億円となった。また,民間放送では,スポット収入を中心とする広告料収入の伸びに支えられて,19.5%増の6,566億円となっている。
イ.国際通信の動向
最近の国際通信の動向は,第1-1-3図のとおりである。
外国郵便物数(差立及び到着)は,2億663万通(個)で対前年度比2.6%の増加であった。通常郵便物の地域別交流状況をみると差立てアジア州,到着で北アメリカ州が最も多く,それぞれ29.5%,39.7%を占めている。また,より迅速なサービスを求めて航空便の占める割合は,年々上昇しており,差立及び到着を含めた外国郵便物数全体では51年度は76.3%となった。
国際電信サービスについてみると,国際電報は国際加入電信の普及等により近年停滞の傾向にあり,51年度における取扱数は,499万通で前年度に引き続き,4.9%の減少となった。地域別には,アジア州が55.9%を占めている。
国際加入電信取扱数は活発な貿易活動に支えられて,対前年度比21.4%増の1,971万度となった。また,51年度末における国際加入電信加入者数は5,874加入,電電公社の加入電信加入者で国際利用登録をしている者の数は1万3,991加入で,それぞれ順調な伸びを示している。
なお,国際電信サービスの生産額は,対前年度比16.3%増の385億円となった。
国際電話サービスについてみると,その通話度数は対前年度比19.3%増の1,022万度であり,これを生産額でみると384億円と対前年度比20.3%の増となった。対地別では,アジア州が最も多く58.3%を占めている。なお,48年3月に開始された国際ダイヤル通話は,全発信度数の4.2%を占めるにすぎないが,50年度に比べ3.7倍の急成長を遂げており,今後,外国側対地の拡張,国内利用可能地域の拡大とともに増加することが予測される。
貿易商社や銀行等で利用されている国際専用サービスにおける賃貸回線は,51年度末現在,音声級回線135回線,電信級回練489回線となり,前年度に比べ各々26.2%,7.5%の増加となった。これを,サービス生産額でみると,対前年度比10.0%増の91億円となっている。
(2) 主な動き
ア.電信電話料金の改定
利用度の低い電話の増加による収入の伸び悩みに加えて,48年秋の石油ショック以来の人件費,物件費の大幅な上昇が重なり,電電公社は49年度1,753億円の赤字を計上した。このため,電信電話料金の改定が問題となったが,50年度においては政府の物価抑制という基本方針に基づいてその改定が見送りとなったため,2,812億円の赤字となった。
このような事業財政を抜本的に立て直すため,通話料の単位料金である度数料を7円から10円に,電話基本料を2倍(51年度中は暫定的に1.5倍)に,また通常電報料を2倍にそれぞれ引き上げることなどを骨子とする「公衆電気通信法の一部を改正する法律案」が国会に提出され,第七十八回臨時国会において51年11月4日に成立し,同月17日から施行された。
これらの法定料金改定にともない,法定料金と関連の深い法定外の電信電話料金である二共同電話の電話基本料,夜間の通話料,加入電信関係料金等の改定は11月11日に郵政大臣の認可を受け11月17日から実施された。
イ.国際海事衛星機構(インマルサット)設立への動き
海上通信は主として短波により行われてきた。しかし短波通信は近年混雑が激化しているのに加え,通信品質が不安定であることなどの欠点があり,従来からその改善の必要性が指摘されてきた。このため,政府間海事協議機関(IMCO)において,世界各国が共同して,静止衛星を使う海事衛星システム及びシステムの管理,運営にあたる国際機関としての国際海事衛星機構(インマルサット)を設立することが検討されてきた。
1973年11月の第八回IMCO総会では,国際海事衛星システムの設立に関する政府間会議を開催することが決定され,1976年9月ロンドンで開かれた第三回政府間会議では「国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約」及び運用協定が採択され署名のために開放された。
同機構は,締約国で構成され,国家主催に関する事項を審議する総会,事業体の代表により構成され,機構の財政及び業務に責任を有する理事会並びに機構を法的に代表する事務局長を長とする事務局から成っている。
政府は,海事通信の改善に資するためこの条約に受諾を条件として1977年3月22日調印し,承認を求めるため国会に提出した。
なお,条約発効の最終期限は1979年9月3日であり,その60日前の7月5日までに締約国となった国の当初出資率の合計が95%以上になることが必要である。
ウ.情報処理産業における資本自由化
我が国は,39年4月に経済協力開発機構(OECD)に加盟して以来,その規約に従い数次にわたって資本自由化を実施し,48年5月には,企業の新設及び企業の同意のある経営参加については原則として100%自由化した。
その際,電子計算機又は同制御自動機構の製造販売又は賃貸業及び情報処理産業等については,猶予期限を設け,段階的に自由化するものとされ,前者については50年12月,後者については51年4月に完全自由化が達成された。
なお現在米国の大手TSS業者が米国にあるコンピュータを利用して日本で情報通信サービスを提供することを計画中である。
エ.放送衛星に関する世界無線通信主管庁会議(WARC-BS)の開催
各国に衛星放送用の電波の割当てを行うための放送衛星に関する世界無線通信主管庁会議が114か国の参加のもとに,52年1月10日から2月13日までジュネーブで開催され,第一地域(ヨーロッパ,アメリカ),第三地域(アジア,太洋州)の放送衛星用の周波数割当計画及び技術基準が作成された。我が国は当初の要求通り,8チャンネル,衛星の静止軌道位置東経110度(インドネシアのカリマリタン上空)を確保した。
これらを取り決めた最終文書は1979年1月1日から発効することとされており,さらに,同年開催予定の世界無線通信主管庁会議において,国際電気通信条約付属無線通信規則に組み入れられる予定である。なお,アメリカ,カナダ両国の属する第二地域(南北米州)については時期が延引され,1982年までに同地域だけの計画を作成することが了承されている。
放送衛星は,現在はまだ実用化されていないが各国とも関心が高く,我が国でも実用放送衛星システムの導入に必要な技術開発と技術基準を確立すること及び我が国の電波権益を確保することなどを目的として,52年度末実験用中型放送衛星(BS)を打ち上げる予定である。
オ.多重放送の動向
テレビジョン放送や超短波放送(FM放送)の電波に別の情報を重畳して同時に放送する多重放送は,情報の量的増大のみならず質的多様化をもたらすものとして注目されてきた。関係各方面での技術開発とならんで,郵政省では49年7月法律,技術の専門家等からなる「多重放送に関する調査研究会議」を設け法的制度的問題を検討してきた。
51年12月同会議は検討結果を取りまとめ,次のような内容の報告書を郵政大臣に提出した。すなわち,総論において多重放送の種類,多重放送の技術の開発の現状及び利用分野等について概説し,次に,制度上の諸問題として,放送局の免許と多重放送を行う場合の周波数の占用の関係,既存の放送番組を補完するための利用と既存の放送番組から独立した利用の関係及びファクシミリ放送について論じた上,最後に現段階で多重放送のすべての種類について全面的に実施に移すのは時期尚早であるので,技術的法律的に問題の少ないものから実験的に行い逐次実用化を進めるべきであるなどの提言を行っている。
郵政省ではこの報告書に基づき52年1月17日に電波監理局に部内の関係者を構成員とする,多重放送協議会(会長は電波監理局長)を設置し多重放送の実施に当たっての問題点等について検討を開始した。
その後,放送事業者から,テレビジョン音声多重放送についての実用化試験局開設の免許申請が提出されている。
カ.アジア太平洋電気通信共同体設立への動き
国際連合アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)は,従来遅れがちであったイラン以東のアジア・太平洋地域の電気通信の開発を促進し,さらに地域電気通信網であるアジア電気通信網の計画について,その推進をはかるため,地域的協議機関としての,アジア太平洋電気通信共同体の設立を準備してきた。
我が国は,ESCAP地域での電気通信分野における最大の先進国であり,本共同体に参加し,技術的協力を推進していくことは,同地域内各国に対する国際協力の増進の見地から極めて望ましく,かつ同地域における電気通信業務の技術的向上と拡充は,我が国との通信の向上にも資するものと考えられる。
このため我が国はアジア太平洋電気通信共同体設立の準備にあって,積極的な役割を果たしてきたところである。
アジア太平洋電気通信共同体憲章は同共同体について,その目的,任務,加盟資格,組織,経営等を規定したものであり,政府は52年3月22日に受諾を条件として調印し,承認を求めるため国会に提出した。
なお本憲章は同共同体の本部所在予定地であるタイを含む7か国以上の批准又は受諾が発効要件となっている。
キ.日中間海底ケーブルの運用開始
我が国と中国との間の通信は,従来短波によって行われてきたが,47年日中国交回復が実現したことにともない,両国間の電気通信の改善をはかる気運が盛り上がり,まず同年10月に衛星通信が開始され,さらに海底ケーブルを建設するための話し合いが開始された。
この成果を受けて,48年に日中両国間で「日本・中国間海底ケーブル建設に関する取極」が締結された。49年には日中間海底ケーブル建設計画が合意に達し,建設当事者となる国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。),上海市郵電管理局間で「日中間海底ケーブル建設保守協定」が締結され,その後工事が進められて51年7月上旬に完成し,同年10月から運用が開始された。
これは,熊本県苓北(れいほく)町と上海市南〓(なんほい)との間約850kmを結ぶ海底同軸ケーブルシステムで,電話換算480回線の容量を有し,要した建設費約60億円は日中両国で折半して負担した。
この海底ケーブルにより,衛星通信と合わせて安定した高品質の通信が確保され,日中間の経済,文化の幅広い交流の促進に貢献することが期待される。
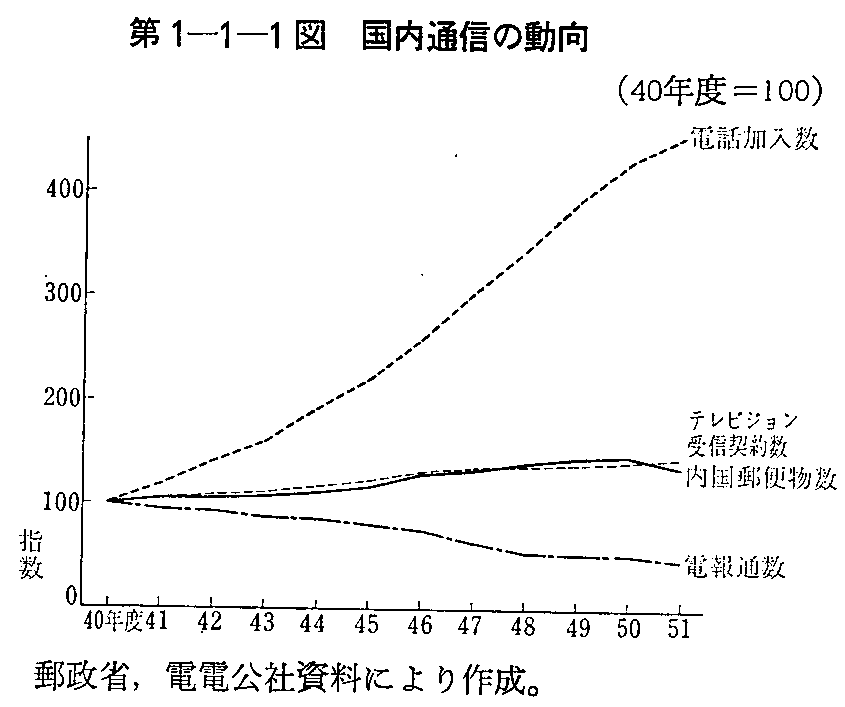
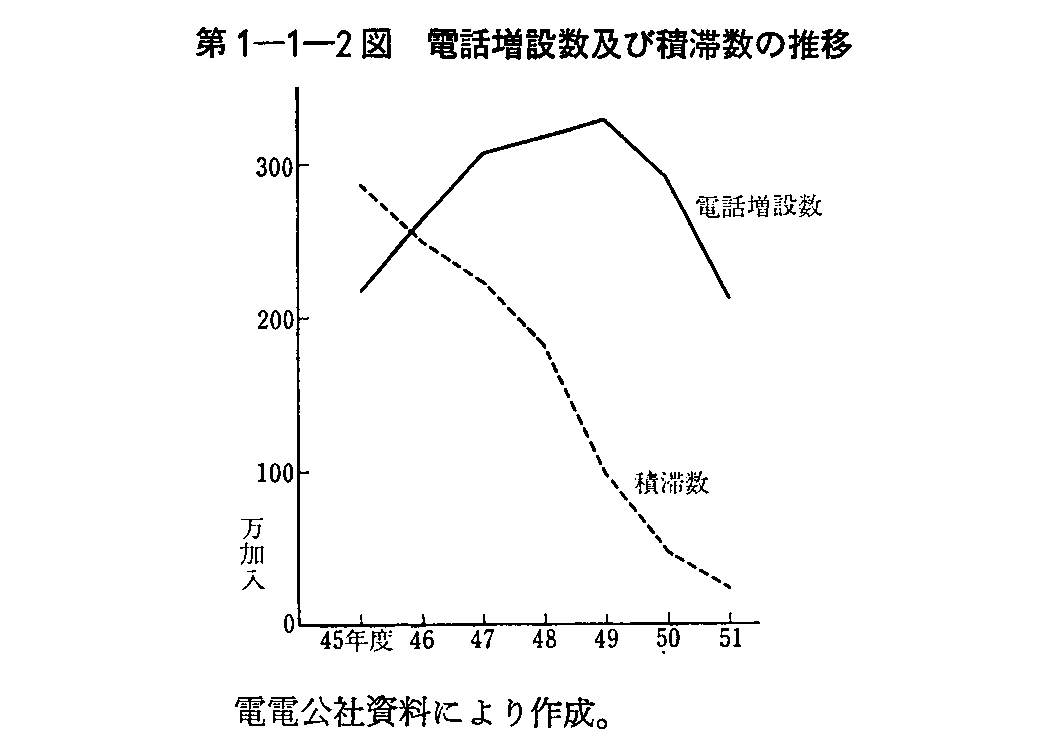
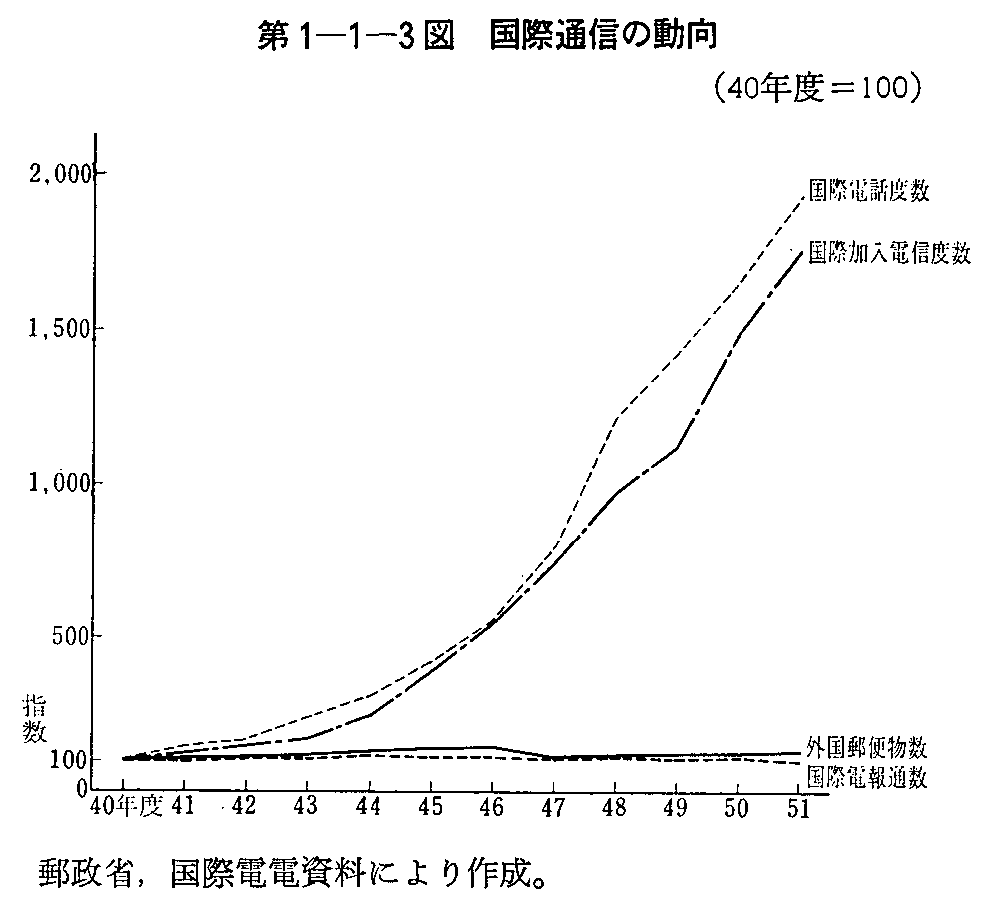
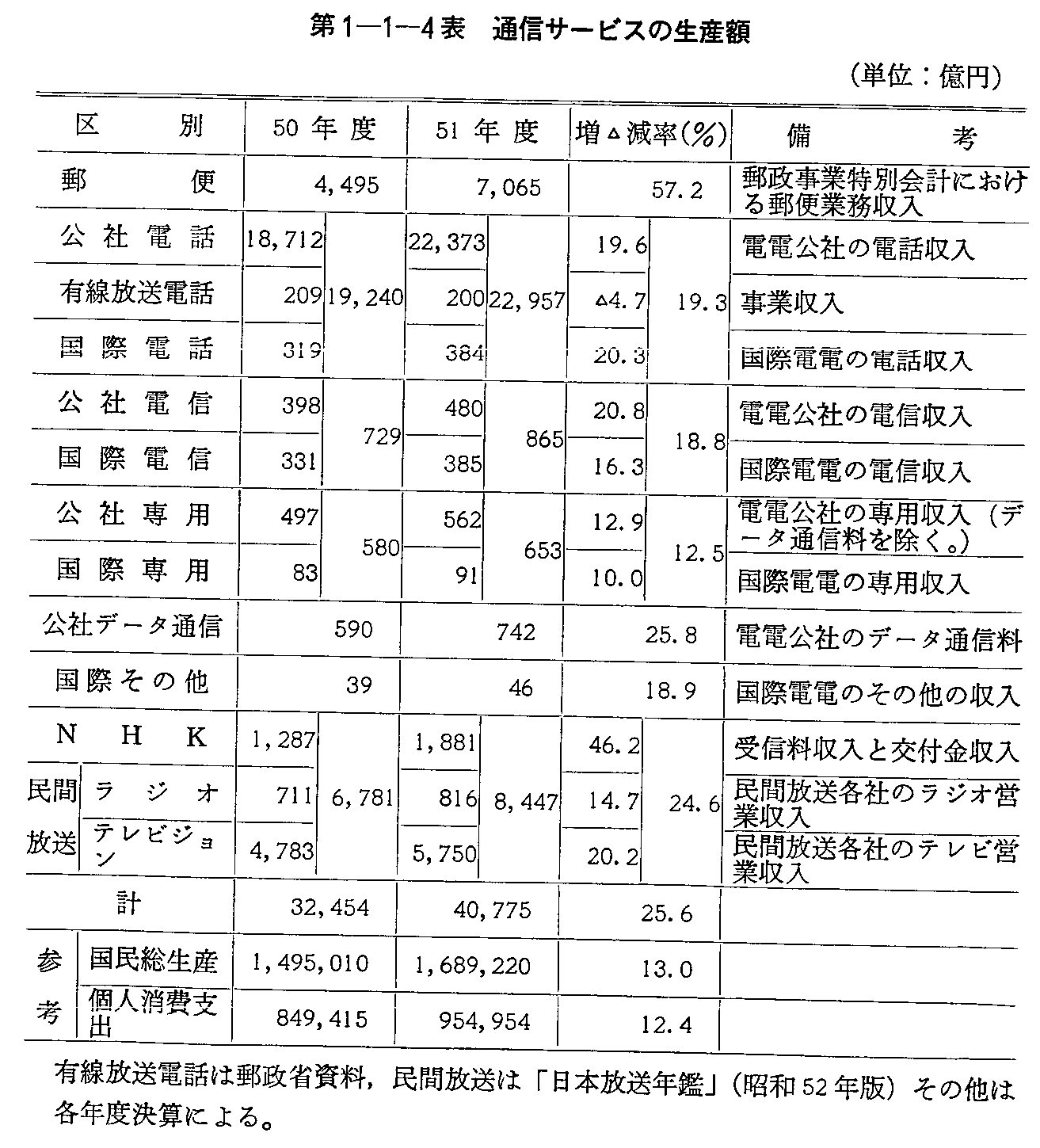
|