 第1部 総論
 第1節 昭和51年度の通信の動向
 第1節 宇宙通信発展の歩み  第2節 進展する宇宙通信の現況  第3節 宇宙通信の監理  第4節 宇宙通信の展望
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 電磁波有効利用技術  第4節 有線伝送及び交換技術  第7節 衛星通信の研究  第8節 その他の研究
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 昭和51年度の社会経済動向と通信
(1) 通信事業経営の現状
ア.通信事業の収支状況
51年度における通信事業経営は,景気回復の遅れや電電公社の料金改定法案の成立遅延等厳しい局面に置かれた状況にもあったが,全般的には収支改善の方向にあった。以下通信事業体別に51年度の収支状況を概観することとする(第1-1-5表及び第1-1-6図参照)。
郵便事業については,収入は51年1月の料金改定により7,615億円(前年度比53.9%増),支出は7,014億円(前年度比12.0%増)で差引き601億円となり,単年度収支としては47年度以来4年ぶりに黒字となった。しかし,51年度末における業務運営費財源借入金はなお1,875億円残されている。
電電公社については,収入は2兆5,182億円(前年度比19.3%増),支出は2兆6,607億円(前年度比11.3%増)で差引き1,425億円の赤字が生じた。これは料金改定が行われたがその実施が当初予定より5か月遅れ,事業収入が当初見込みより約3,000億円減少したためである。この結果,49年度から連続3か年赤字決算となった。
国際電電については,収入は961億円(前年度比18.3%増),支出は870億円(前年度比17.9%増)であり,差引き91億円の黒字となって,健全な経営を続けている。これは国際化の進展と諸活動の活発化による通信量の増加を反映しているものとみられる。
NHKについては,収入は1,923億円(前年度比45.7%増),支出は1,718億円(前年度比13.8%増)で差引き205億円となり,48年度以来3年ぶりに黒字となった。これは51年6月の受信料改定の寄与が大きいと思われる。
民間放送については,利益が前年度に比べほぼ倍増した。これは活発な広告需要に支えられて収入が大幅に増加したからである。
通信事業の人件費比率が大きいのは労働集約的性格を持っていることのためと思われる。
イ.通信事業の財務構造
51年度における各事業体の財務比率は第1-1-7表のとおりである。
郵便事業では,労働装備率が低いがこれは人力依存度の高い事業の性格によるほか,局舎借入れ,輸送の外部委託等の運営形態をとっていることによるものである。
電電公社では,総資産に占める固定資産の比率が90.6%,労働装備率が17,850千円と高い値を示しているが,これは全国的な規模の設備を有する事業の性格によるものである。固定比率が418.3%と他の通信事業に比べ著しく高いのは総資本のうち電信電話債券を主体とする固定負債が74.0%と極めて高い比率を占めており,自己資本が小さいことによる。
国際電電では,前年度とほぼ同様の財務比率を示したが,労働装備率は日中海底ケーブルの完成等により対前年度比14.7%の増を示した。
NHKでは,収支状況が黒字になったことを反映して,固定比率,固定資産対長期資本比率,負債比率が大幅に減少し,流動比率が増大している。
民間放送では,総資産に占める固定資産比率がNHKと比べるとかなり低くなっている。
ウ.通信関係設備投資の動き
通信事業は事業の性格から一般に高度な技術に裏付けられた設備を多く必要とする。事業・サービスの拡大・改善のため,毎年多額の設備投資が行われている。51年度の通信の分野における設備投資額は1兆4,952億円であり,各分野別にみると次のとおりである(第1-1-8表)。
郵便事業では老朽狭あい局舎の改善を図ったほか集配普通郵便局が4局,無集配特定郵便局が86局新設された。また郵便処理の近代化,効率化の一環として,51年度には郵便番号自動読取区分機4台,選別台付自動取りそろえ押印機16台が新たに配備され,局内作業の機械化が更に推進された。これらの設備投資額は前年度に比べ18.8%増の653億円であり,その内583億円が自己資金,70億円が財政投融資(簡保資金)からの借入金である。
電電公社においては料金改定が当初予定より5か月遅れたため,建設資金の財源不足をもたらし,支出削減措置がとられるという事態があったため50年度より若干少ない1兆3,618億円の設備投資が行われた。全国的規模において一般加入電話の積滞を解消し,すぐつく電話をめざして一般加入電話208万加入が増設された。また社会的要求の多様化にこたえるため,カラー電話76万4千個,親子電話55万3千個,プッシュホン42万7千個,ホームテレホン11万5千セット,ピンク電話5万8千個,キャッチホン4万7千個が設置された。また市外回線13万7千回線,専用線3万2千回線,データ通信回線1万5千回線,テレックス7千加入が増設された。資金調達額は2兆156億円であり,この内,内部資金は6,944億円,加入者債券,政府保証債券等の外部資金は1兆3,212億円である。
国際電電においては136億円の設備投資が行われた。51年5月には日中海底ケーブルが完成し,国際電話および国際加入電信用の電子交換機が導入され,沖縄・ルソン・香港間海底ケーブル,大阪国際電話局の建設が推進された。また音声級回線133回線,電信級回線149回線が増設された。
NHKにおいては対前年度比63.9%増の212億円の設備投資が行われた。テレビジョン放送難視聴の解消をめざしてテレビジョン放送局399局(総合199局,教育200局)を開設したほか,超短波放送局10局を開設した。
また,画質改善のためのテレビジョン放送局の整備,スタジオ設備の整備を行った。資金調達についてみると,資本勘定の規模は331億円であり,この内,内部資金は255億円,放送債券等の外部資金は76億円である。
民間放送においてはテレビジョン放送局336局を開設し,対前年度比16.4%増の333億円の設備投資が行われスタジオ及び放送設備等が拡充された。
なお,私設電気通信については,郵政省が実施した961機関の調査を基に推計した結果によれば(ただし,主要官公庁,特殊法人,従業員数300人以上の民間企業に限る。),50年度中に約540億円の 設備投資が行われた。これを設備面からみると無線通信装置の1万3千台をはじめとして,電話機の1万2千台,搬送装置の700台,ファクシミリ,印刷電信装置等の電信装置600台,留守番電話装置等の電話附属装置400台が新設された。また交換機については,自動交換機が回線容量で1万4千回線新設された。
50年度末における施設数についてみると,私設有線電気通信回線は線路延長で10万km,固定業務用無線通信回線は505万チャンネル・キロメートルに達しており,このほか電話機が46万台,無線通信装置が19万台,搬送装置が3万台,電信装置が1万4千台(うちファクシミリ8千台)等となっている。また交換機では手動交換機が4千台,自動交換機が回線容量で33万回線となっている。
(2) 通信関連産業の動向
ア.通信機械工業
51年度の通信機器の受注実績額は5,863億円で前年度に比べ5.7%の減少となった。内訳では無線通信装置が1,153億円で対前年度比12.9%減と落ち込み,有線通信機器についても4,710億円で3.8%の減少となった。
このうち電信装置をみてみると,ファクシミリが対前年度比55.8%増となっているものの印刷電信装置が42.6%減となるなど電信装置全体としては31.2%減となった。また電子交換機は11.5%増と順調な伸びを示した。
需要部門別では官公需は3,004億円と対前年度比14.7%の減少となり,民需は1,467億円で4.8%増,外需は1,392億円で7.5%増にとどまった。全体としては民需に回復の兆しが見られるものの,電電公社をはじめとする官公需の低落の影響を直接受けることとなった。
イ.電線工業
51年度の電線の受注実績額は8,395億円と前年度に比べ23.5%増となり,ここ2年の減少傾向から増加傾向へ転じた。このうち銅電線は7,564億円で20.9%増,アルミ電線は831億円で54.0%増であった。なお銅電線の通信ケーブルは1,560億円と前年度に比べ6.2%の減少となったのが注目される。
需要部門別では官公需が1,378億円で対前年度比9.8%減となったが民需は6,065億円で34.1%増,外需が952億円で27.8%増と民需の回復によって大幅な増加となった。なお官公需のうち電電公社からの受注は1,299億円で前年度に比べ10.9%の減少となった。
ウ.電子計算機製造業
51年度の電子計算機(周辺装置を含む)の納入実績は7,315億円と前年度に比べ19.1%増となり,不況にもかかわらず好調な伸びを示した。このうち国産機は4,151億円で21.1%増,外国機は3,164億円で16.6%増と国産機の健闘が目立った。また大型機,中型機はそれぞれ対前年度比23.8%,22.0%の増加となった。
エ.電気通信工事業
51年度における電電公社からの受注契約額は,電信電話料金の値上げが遅れたこともあって4,380億円となり,対前年度比0.3%減とほぼ前年並みとなった。このうち通信線路工事は3,808億円で0.6%増,伝送無線工事を含む通信機械工事は572億円で6.2%減となっている。
一方,自営PBX工事業界で組織している社団法人全国電話設備協会の会員数は51年度末で1,177となっており,このうち自営PBX工事等を行っている工事業者は1,096に達している。また自営PBX台数は約4千台増え,前年度に比べ33%の伸びとなった。
オ.情報サービス業
51年11月1日現在で情報サービス業の年間売上高は3,070億円と前年度に比べ11.6%の増加となった。これを業務の種類別にみると事務計算が34.5%,ソフトウェア開発,プログラム作成15.3%となっており要員派遣は年々30%以上の着実な伸びを示している。
また,契約先産業別にみると鉱業・製造業が23.6%,金融・保険業等が21,5%,公務が17.1%となっている。
カ.その他
51年度のポケット・ベル会社の営業収益は104億円で前年度に比べ22.2%増と順調な伸びを示した。加入者は4年連続10万台以上の伸びを示し51年度末で63万9,576加入となった。業種別に加入者をみると販売業38.3%,建設業20.3%及びサービス業16.3%となっている。
有線音楽放送業は52年1月末現在で,施設数475,加入者数16万1,611となっており,年間利用料は約78億円に達していると推定される。
テレホンサービスの提供主体は公共機関,民間企業,福祉団体等各界に及び51年度末のサービス件数は2,776件と前年度末に比べて0.8%減少したが,回線数では1万2,809回線と6.3%の増加となった。サービス件数を案内種別でみると芸能・音楽案内が9.2%,行政案内が7.7%,及び人生相談が6.3%となっており,その他多種多彩なサービスが行われている。
ニュース供給業のうち一般ニュースの51年度における情報量の一日平均は新聞向けが,18万字,放送向けが2万3千字となっており,写真はそれぞれ74枚,10枚となっている。また外電の一日平均は受信が55万語,送信が18万語である。
なお,駅前等にみられる電光表示サービスは広告の他,官公庁の広報,社会キャンペーン,ニュース速報等,地域に密着した新しい情報通信メディアとして注目されている。
(3) 家計と通信
家計における1世帯当たり年間の通信関係支出(郵便料,電報・電話料及び放送受信料)は,51年(1〜12月)において3万5,296円である(第1-1-10表参照)。51年には,郵便料,放送受信料,次いで電報・電話料の料金改定が行われたこともあって,対前年度比20.4%の増加となっている。家計における通信関係支出は全消費支出の1.7%,雑費支出の4.1%にすぎないが,この10年間に5,1倍と著しく増加している。この主な原因は,第1-1-11図で明らかなように,住宅用電話の普及に基づく電報・電話支出の急増であり,家庭通信における電話の役割は非常に大きくなっている。第1-1-12図は通信関係支出,雑費支出及び可処分所得をそれぞれに対応する消費者物価指数で実質化し,その推移を指数で比較したものである。家計における情報化の程度を表わすと考えられる雑費支出は所得とほぼ同じ率で上昇しているが,雑費のうちに含まれる通信関係支出は急激な増加を示しており,家計における言わば通信性向は所得の上昇とともにますます大きくなっている。
(4) 通信及び関連産業の国際交流
我が国と諸外国との国際交流は,貿易,文化,経済協力等多岐にわたっている。通信及び関連産業の分野においても,その範囲は,外国郵便及び国際電気通信,放送,あるいは通信機材の輸出入,技術上の交流等様々な面において,活発な交流が行われている。第1-1-13図はこれらの交流の推移を示したものである。これをみると,通信機材の輸出入額の増加率が高いのが注目される。外国郵便物数は微増の傾向であるが,国際電気通信度(通)数は貿易額の増加に加えて,外国旅行者数の増加も手伝って大きな増加率を示している。
また,諸外国との交流には必ず「出」と「入」の両面があるが,第1-1-14図は交流の分野により様々な特徴があることを示している。
国際通信の交流状況をみると,外国郵便は「到着」がわずかに多いのに対し,国際電気通信は「発信」が「着信」を上回っている。この傾向を反映して,国際電気通信料金の対外決済はここ数年赤字基調が続き,51年度においては2,600万ドルの赤字となり,これは我が国の51年度の貿易外収支の赤字61億2,700万ドルの0.4%にあたる。
放送についてみると,NHKは51年度において1日延べ37時間の国際放送を行った。このうち全世界向けのジェネラル・サービスは13時間30分,地域別放送は23時間30分となっている。一方,諸外国で行っている日本語による国際放送時間数を総計してみると1日延べ平均46時間となり,日本語以外の言語での国際放送も含めると,相当量の国際放送による情報が我が国に流入していることになる。
また,諸外国との間で相互理解と友好,親善を増進するため,放送番組の交換等が行われている。
NHKの51年度の番組交換状況をみると,テレビにおいては,海外へ提供した番組延べ45時間,海外から受け入れた番組15時間,ラジオにおいては,海外への提供延べ1,726時間,海外からの受け入れ758時間と,それぞれの提供が受け入れを上回っている。
更に,42年に財団法人NHKサービスセンターに設けられたNHKインターナショナルを通じ,諸外国の放送機関へNHK放送番組の有償頒布を行うとともに開発途上国や海外の放送機関等に番組を貸出している。51年度における実績をみると,33か国78機関に1,274本を頒布し,17か国38機関に260本を貸出しを行っている。
民間放送の教育教養番組の充実と向上を目的として43年に設立された財団法人放送番組センターも番組交流業務の一翼を担い,幅広い活動を行っており,51年度の活動状況は次のとおりである。
[1] 日米テレビ交流会議において,米国側の事務局であるJapan Society(日本協会)とそれぞれ無償で4番組4本の番組交換を行った。
[2] 同センターがこれまで制作した番組のうち12番組90本が国際交流基金に提供され国際文化交流の推進のため活用された。
[3] 米国の日本研究家グループに対し,日本研究の資料として10番組25本を有償で提供した。
[4] 外国の放送会社等との番組の売買についてみると,同センターの特別番組「JAPAN」が外国の放送会社2社に販売され,外国のテレビ番組制作会社2社から2番組78本を購入した。
次に通信機材の輸出入の状況を第1-1-15表によりみてみると,51年度における通信機材の輸出入額は2,785億円であり,我が国の貿易額の0.7%を占めている。通信機械の輸出入額を輸出,輸入別にみると,輸出額が圧倒的に多く全体の89.3%を占めている。輸出を対地別にみると,北アメリカ州が最も多く全体の32.6%を占めている(第1-1-16図参照)。最近,輸出の大黒柱として,プラント輸出が注目を集めているが,51年度における通信機械のプラント輸出額は4億1,300万ドルであり,我が国の総プラント輸出額の2.7%を占めている。通信機械のプラント輸出は,発展途上国の社会経済基盤の整備に大きな役割を果たすものであり,今後更に発展することが期待されている。
一方,通信ケーブルの51年度における輸出入額は151億円となっているが,総貿易額に占める割合は0.04%と小さい。輸出,輸入別にみると,通信機械と同様,輸出が圧倒的に多く99.0%を占めている。この輸出を対地別にみると,アジアが最も多く,全体の47.2%を占めており,通信機械の輸出において北アメリカ州が大きな割合を占めているのと好対照をなしている(第1-1-16図参照)。
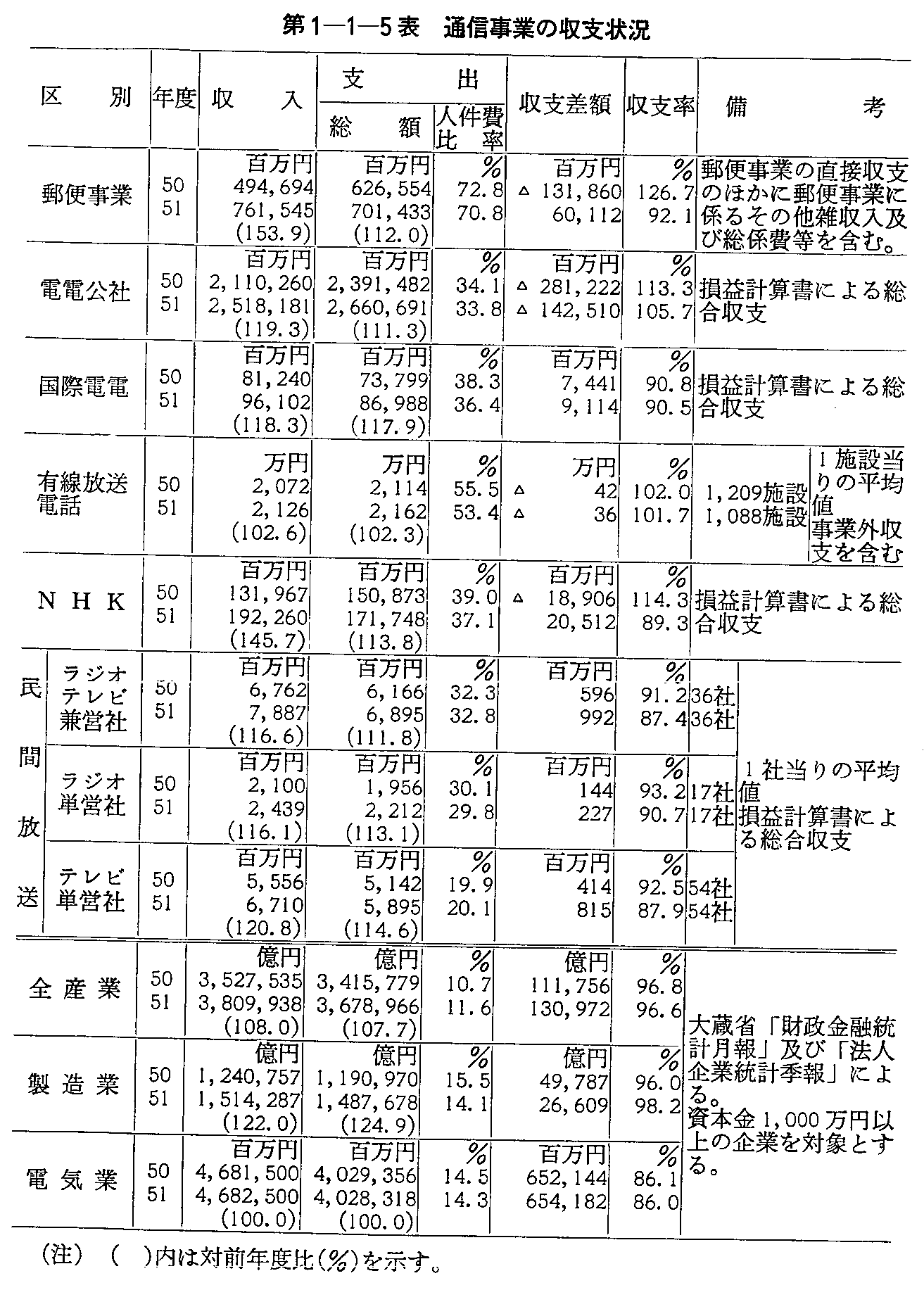
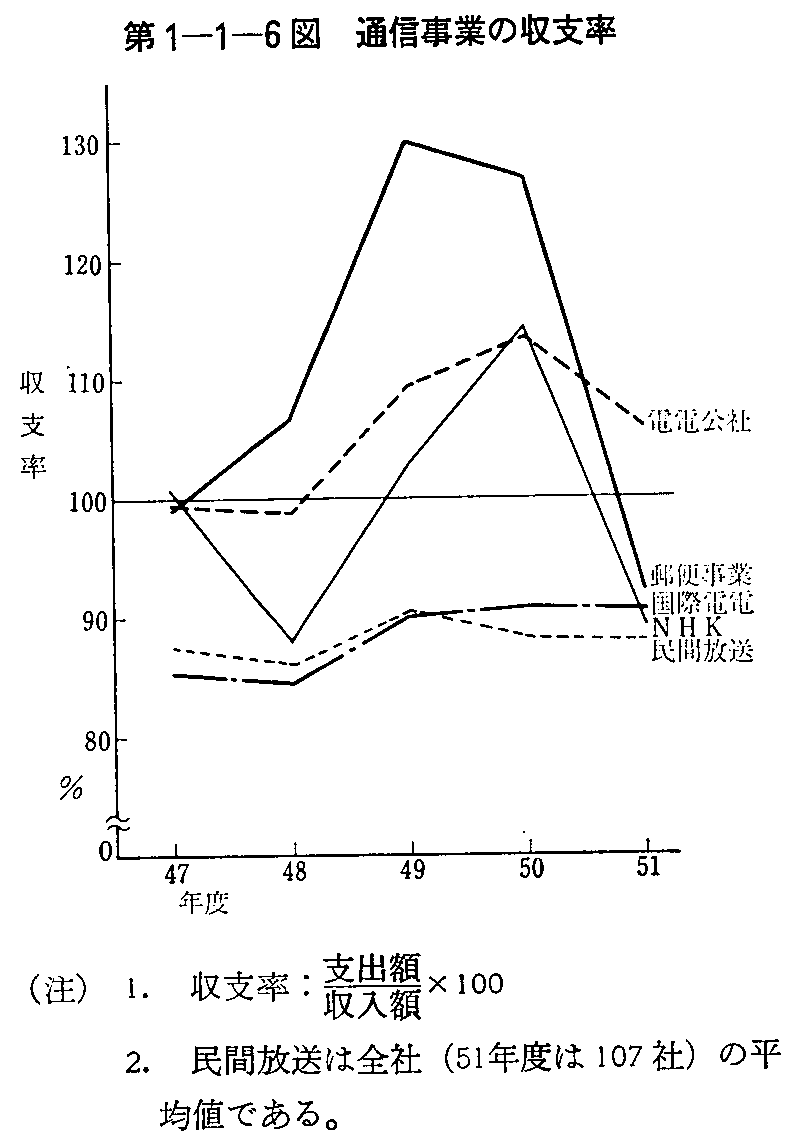
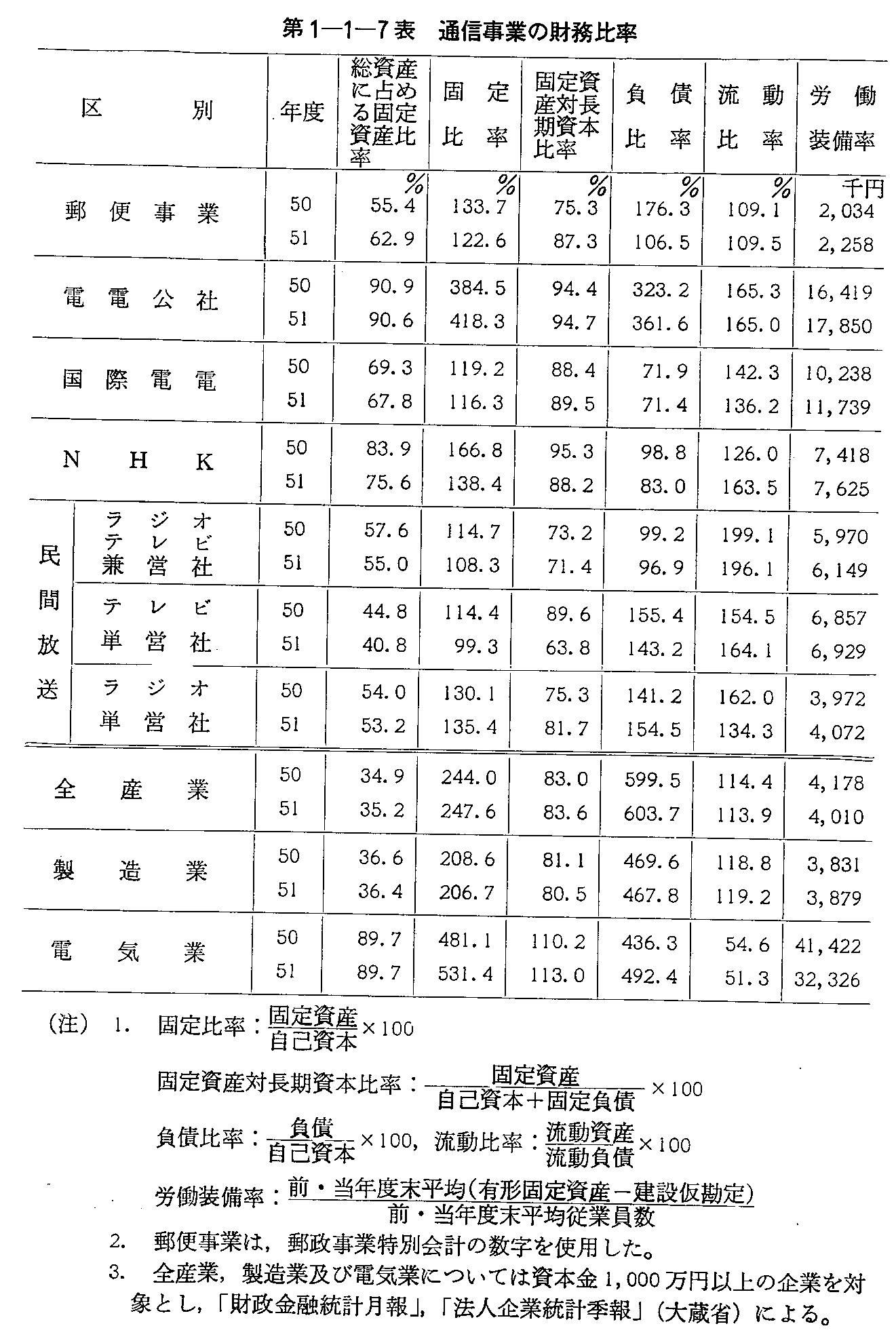
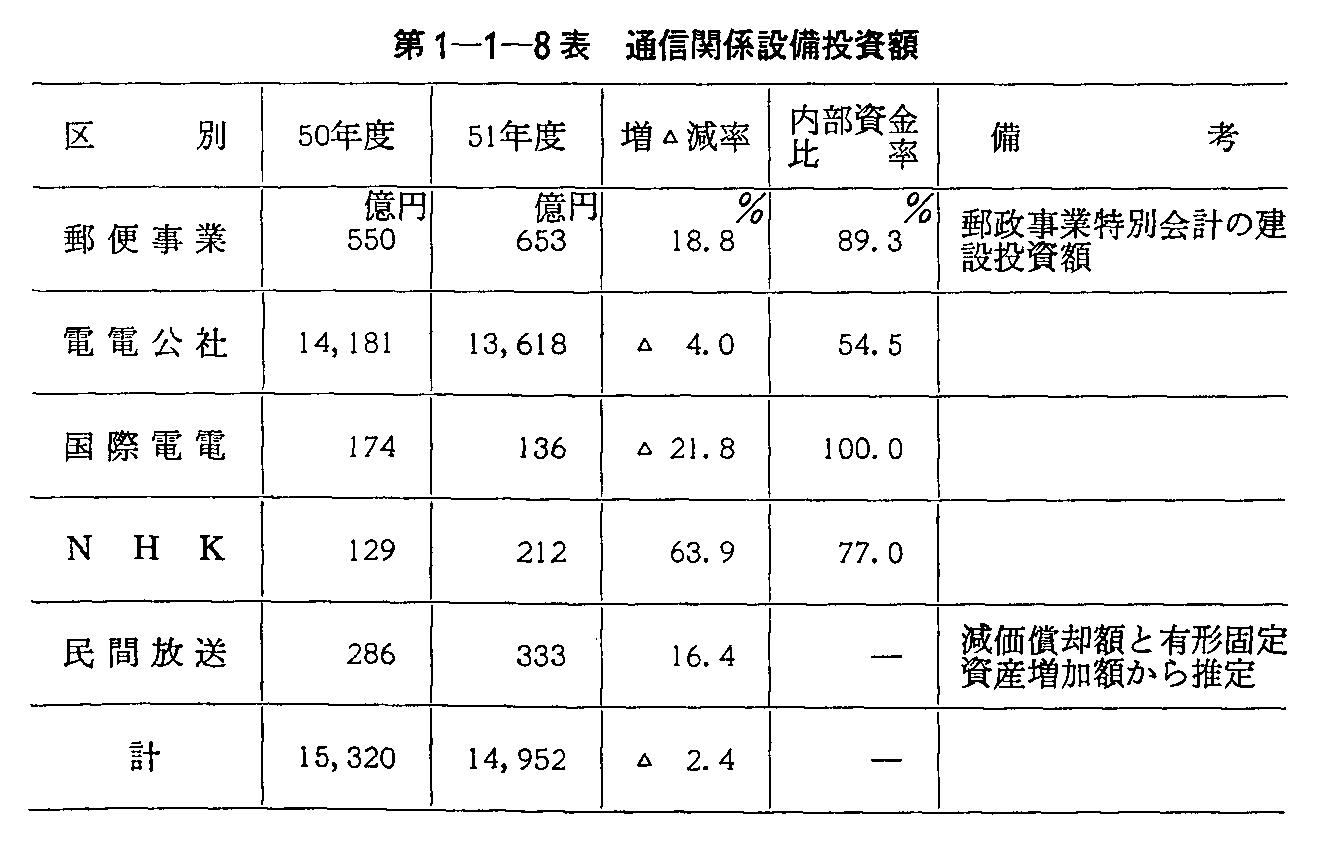
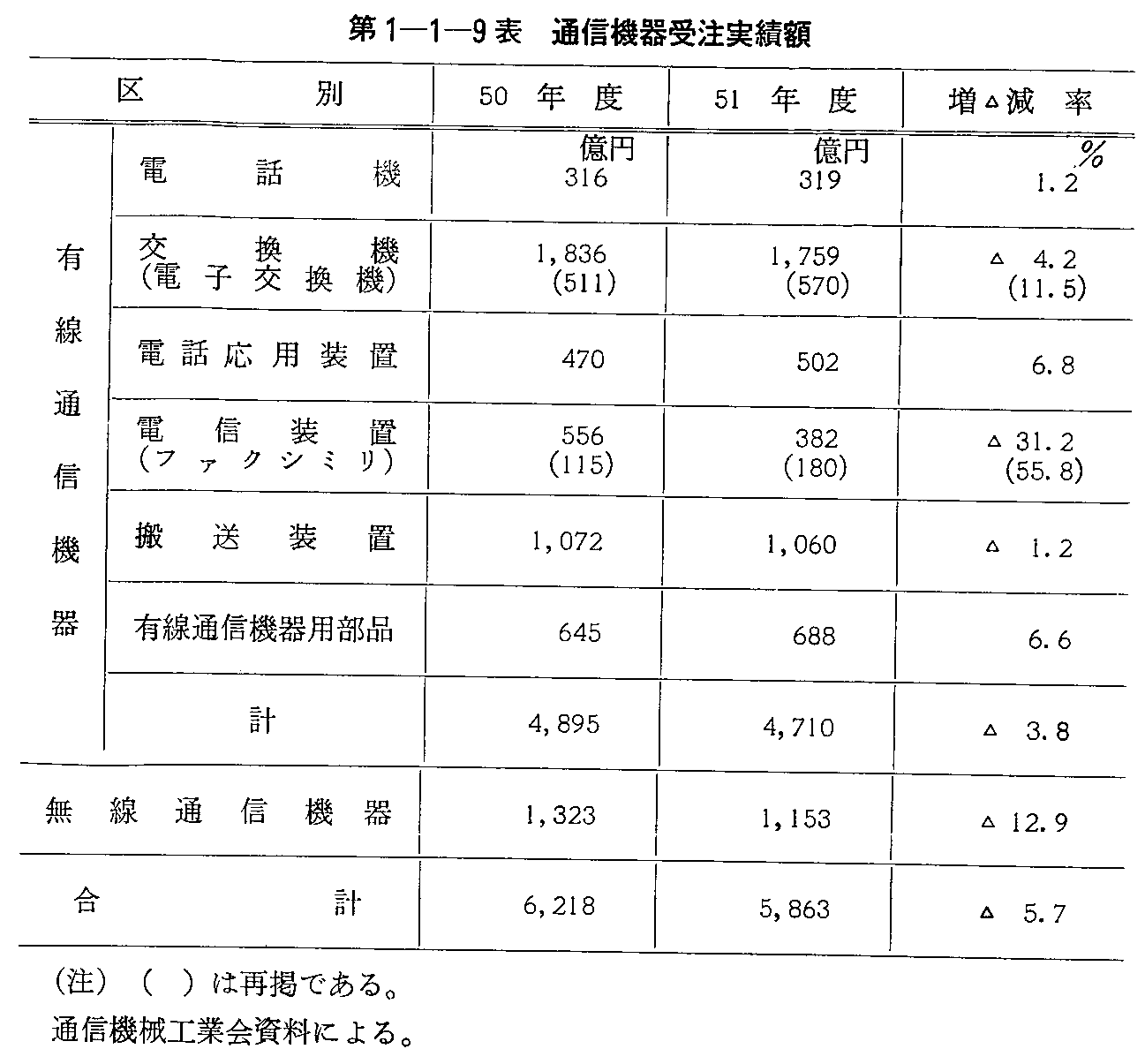
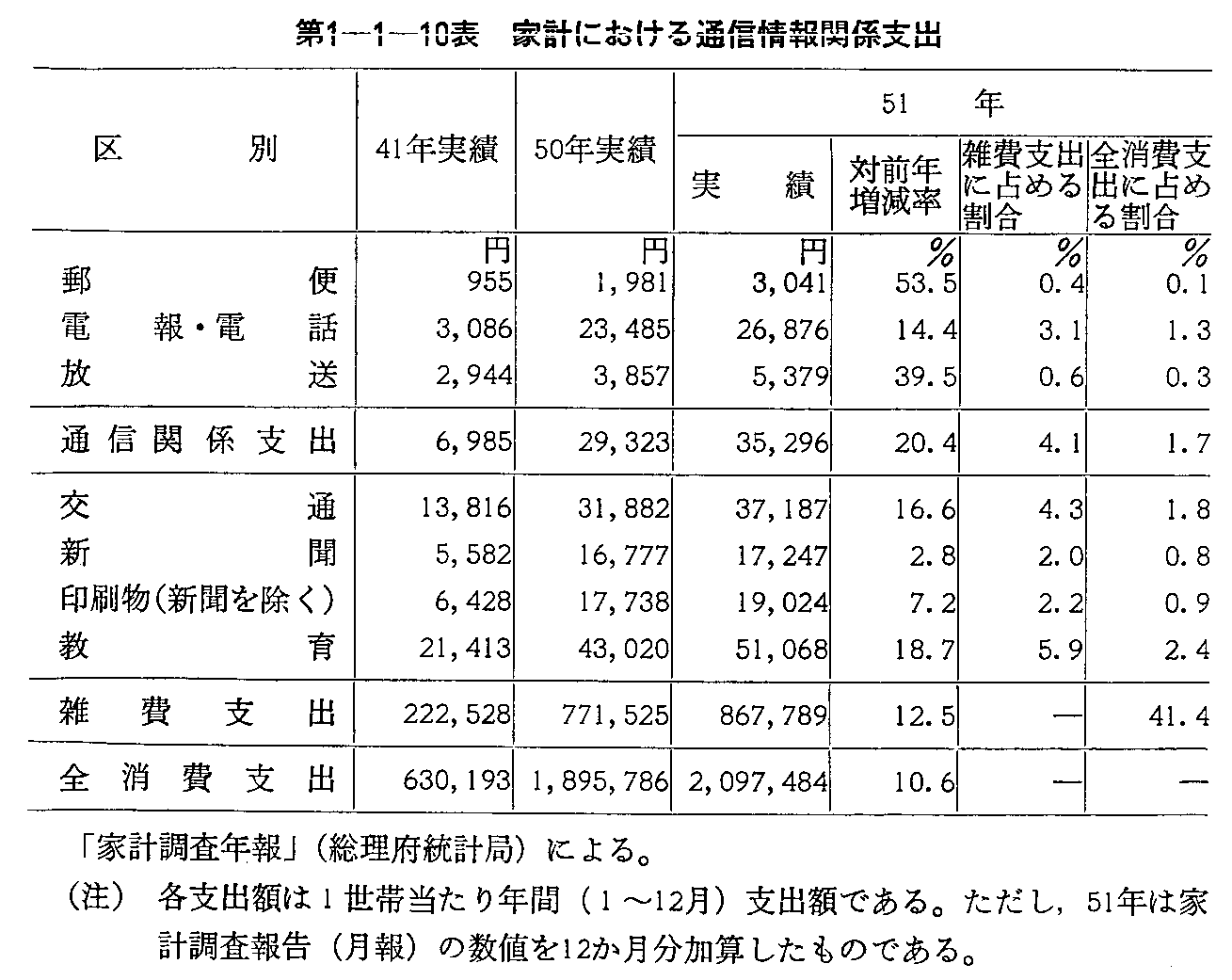
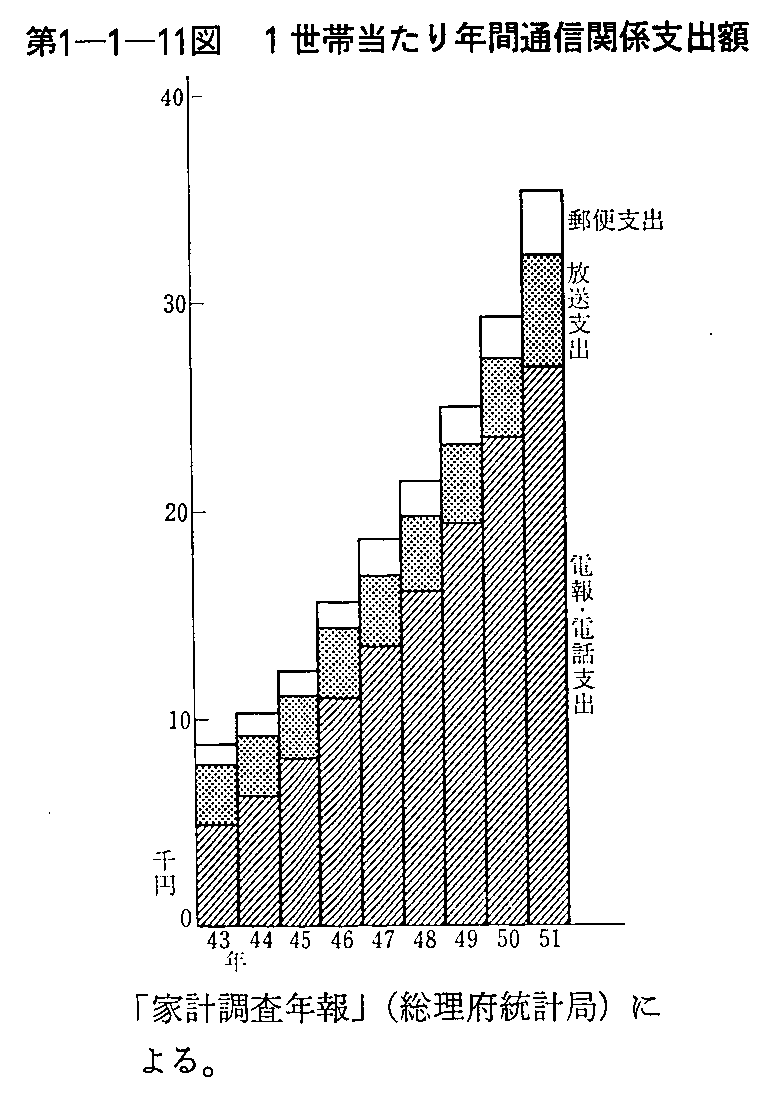
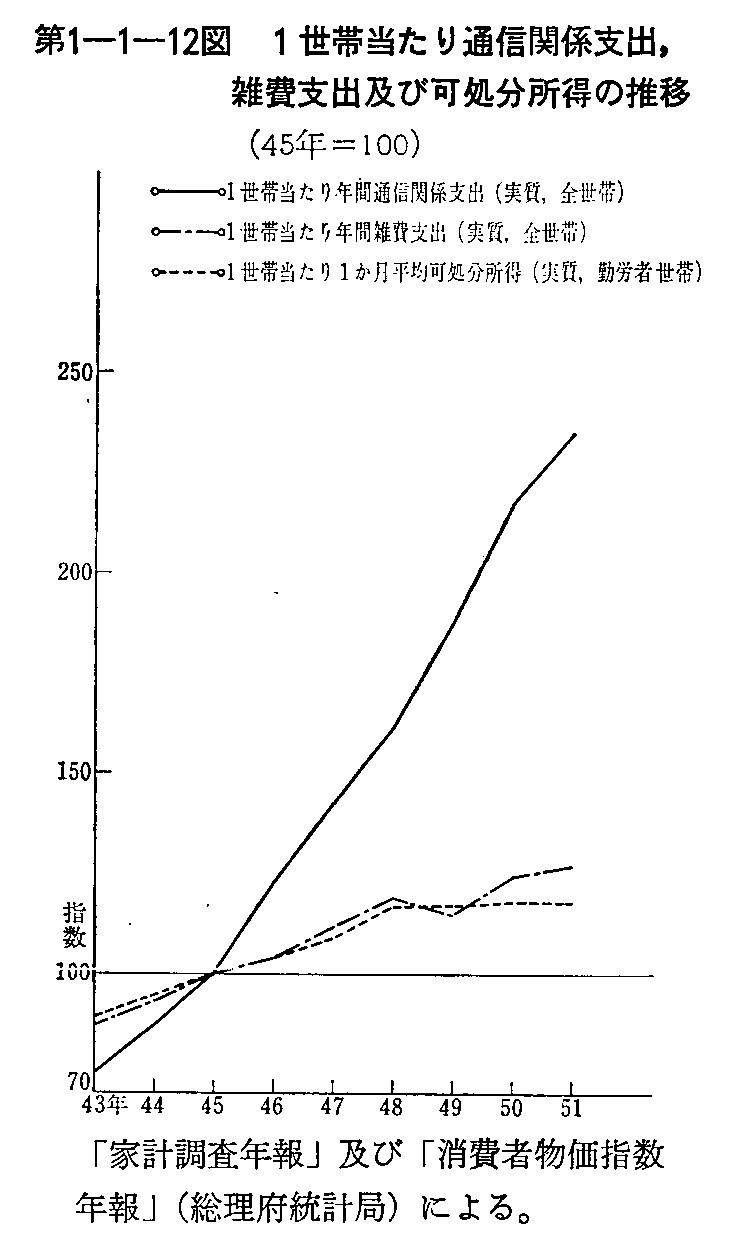
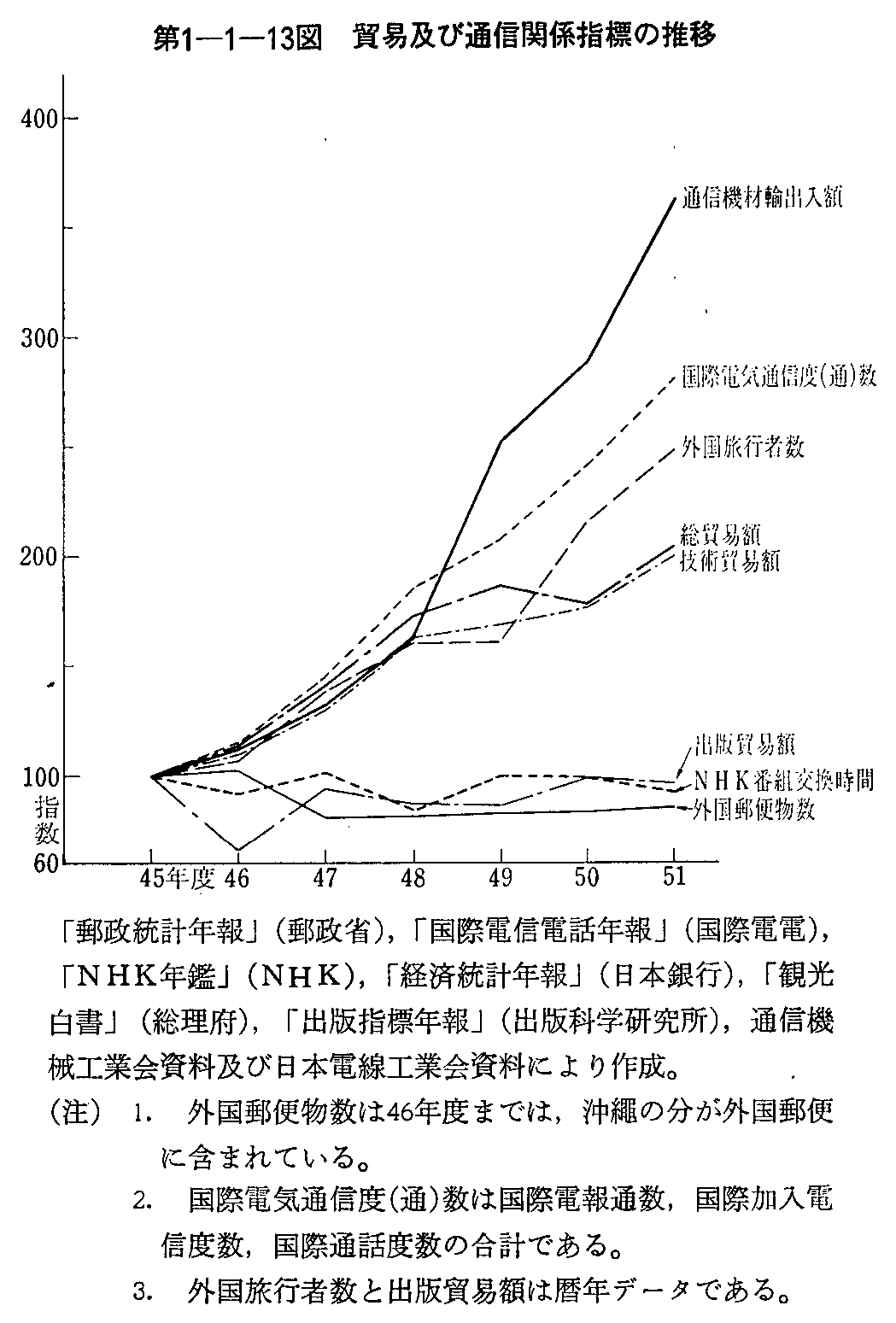
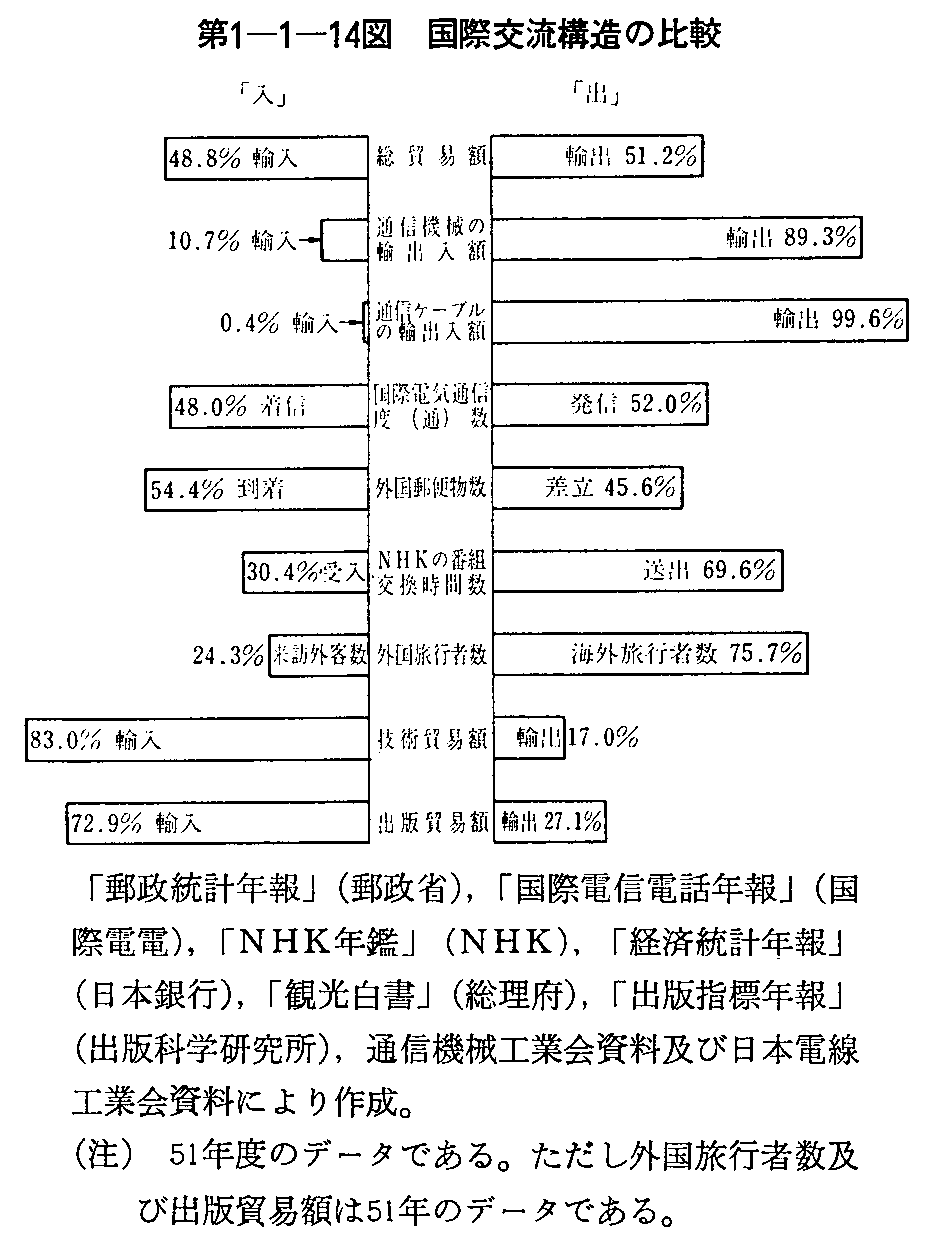
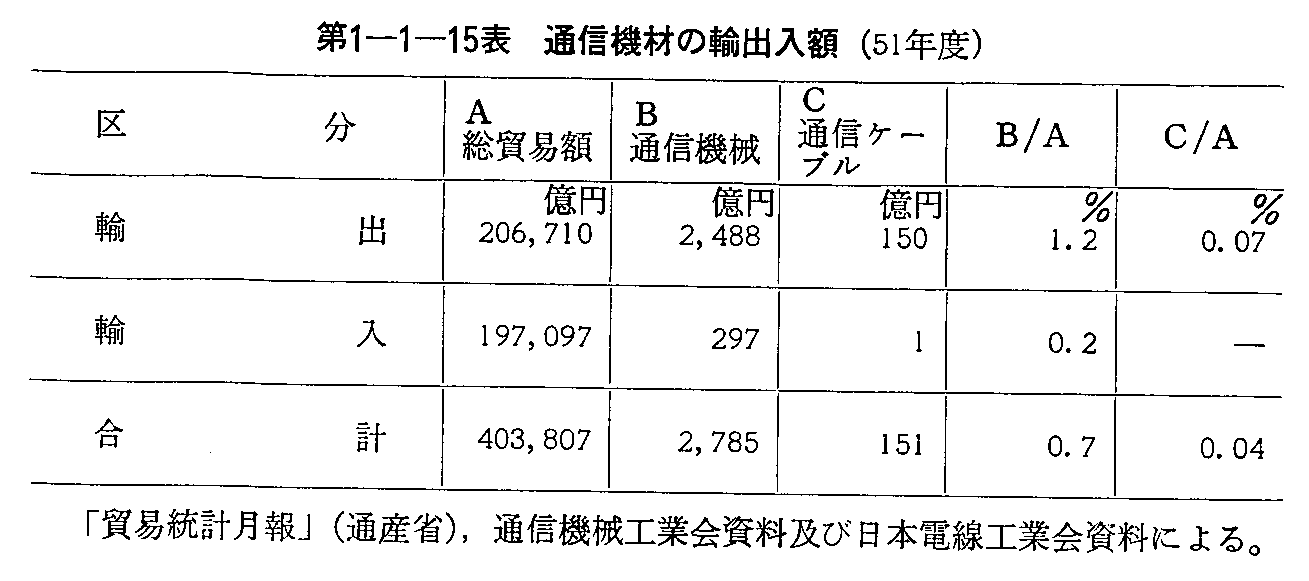
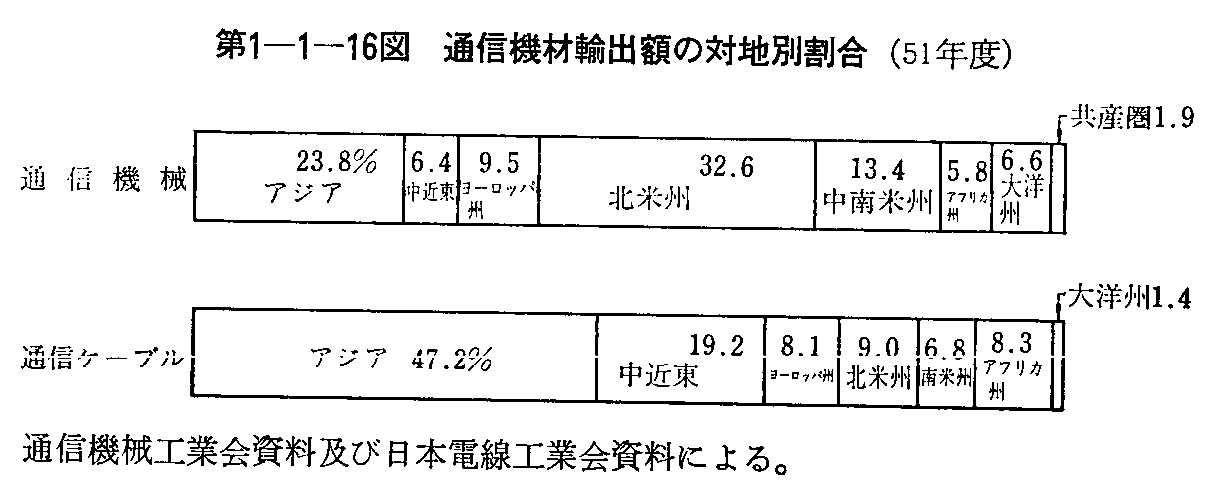
|