 第1部 総論
 第2章 通信の現況
 第1章 増大する通信の役割  第2章 情報化社会と通信
 第3部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便の利用状況  第3節 郵便事業の現況  第4節 郵便事業の近代化合理化  第5節 外国郵便
 第2章 公衆電気通信
 第2節 公衆電気通信施設の現状  第3節 公衆電気通信サービスの現状  第4節 事業経営状況  第5節 公衆電気通信事業の拡充と合理化
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況  第3節 無線従事者
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信システムの現況  第3節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理
 第3節 周波数割当
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 研究開発の課題とその状況
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 テレビの普及と市民生活
昭和28年2月にテレビジョン放送が開始されて以降この20年の間に,テレビはラジオにはない映像メディアとしての特徴を発揮し,報道,教養・教育,更には娯楽番組など多彩な放送番組を提供し,市民生活を豊かなものにしてきた。テレビの普及状況を受信契約数(NHK調べ)の推移でみると,放送開始後5年余を経過した33年5月に100万を超え,引き続きその後も急速に伸び,37年3月に1,000万,42年12月には2,000万をそれぞれ突破し,47年度末には2,443万に達した。
このようにテレビは市民の間に急速に普及したが,テレビは市民の日常生活のなかでどのような地位を占めているであろうか。
(1) テレビ視聴の動向
第2-1-8図は,NHK放送世論調査所の「国民生活時間調査」等をもとに,日本人全体の平均テレビ視聴時間の推移を示したものである。35年から40年までの5年間に国民1人当たりのテレビ視聴時間(平日)は,テレビの全国的な普及によって大幅に増えているが,40年から47年にかけては大きな変化がみられず,テレビが市民生活のなかでほぼ定着しつつあることを示している。
しかしながら,40年と45年について,性別,年代別,職業別に分けて平日におけるテレビ視聴時間をみると,かなりの変化がある(第2-1-9図参照)。すなわち,性別では,男性全体の平均テレビ視聴時間が40年から45年にかけてほぼ一定しているのに対し,女性の場合34分増え,かなりの増加となっている。しかも女性のテレビ視聴時間が男性よりも多く,45年においては男性の2時間41分に対し,女性は3時間28分となっている。
また,テレビ視聴時間を年代別にみると,年代層によって変化の状況にかなりの相違がある。特に,20代がほとんど変化していないのに対し,10代が若干減少気味であり,逆に50代,60代は大幅に増加している。これを詳細にみると,10代は40年の2時間18分に対して45年は2時間9分で,9分減少しており,一方増加が顕著な60代は,40年の3時間16分に対して45年は4時間1分となり,45分増えている。このように年代層によってテレビ視聴時間の増減傾向にかなりの差があるが,NHK放送世論調査所が行った「全国意向調査」によると,男女とも若い世代ほどテレビ放送番組に対する選択意識が強く,「見たい番組がある時に見る」比率が高いのに対して,高年齢層になるに従って「見るのが習慣になっている」比率が高く,極めて対照的である
(第2-1-10図参照)。このような年代によるテレビの見方の相違がテレビ視聴時間に少なからず影響を与えていると考えられる。
次にテレビ視聴時間の変化を職業別にみると,農林水産業,家庭婦人のテレビ視聴時間が40年から45年までの5年間に大幅に増加しており,それぞれ約40分長くなっている (第2-1-9図参照)。これに対し,管理・専門職及び事務・技術職の場合,テレビ視聴時間が逆に約10〜30分減少している。更に特徴的なのは,家庭婦人のテレビ視聴時間が断然多く,45年においては4時間30分に達し,全国民の平均テレビ視聴時間3時間5分をかなり上回っている。しかしながら,この4時間30分のうち2時間29分はいわゆる「ながら視聴」である。つまり家庭婦人の場合,炊事,洗たく,掃除などをしながらテレビを見る時間が非常に多く,このことから,テレビが主婦の家庭生活のなかに深く浸透しているのがうかがえる。
(2)テレビ視聴と余暇行動
平日における国民の生活行動のうち睡眠,食事,家事など「生活上必要な行動」の時間を除いた1余暇行動」の時間について,その時間を第2-1-11図によりみると,35年から40年にかけて国民1人当たりの余暇時間はかなり増え,テレビ視聴時間も大幅に増加している。しかしながら,40年と45年の比較では,余暇時間全体に顕著な変化が認められず,テレビ視聴時間もほぼ横ばいである。ちなみに余暇時間全体に占めるテレビ視聴時間の比率をみると,35年の19%からテレビがほぼ全国的に普及したとみられる40〜45年においては.49〜54%と大幅に伸びている。
これまで平日における国民のテレビ視聴と余暇行動についてみたが,日曜日におけるテレビ視聴の地位はどうであろうか。第2-1-12表により45年と47年のテレビ視聴時間についてみると,日曜日におけるテレビ視聴時間は,この2年間若干減少しているものの大きな変化がみられず,平日の場合と同様に,テレビ視聴が日曜日においてもほぼ定着しつつあることを示している。また,日躍日のテレビ視聴時間が45年,47年とも平日に比べてかなり大きいのが注目される。近年,余暇行動の多様化,活発化の傾向がみられ,そのテレビ視聴に与える影響が指摘されているが,上でみたようにさほど顕著な影響がみられず,テレビが日曜日においても依然として高い地位を占め続けていることがうかがえる。
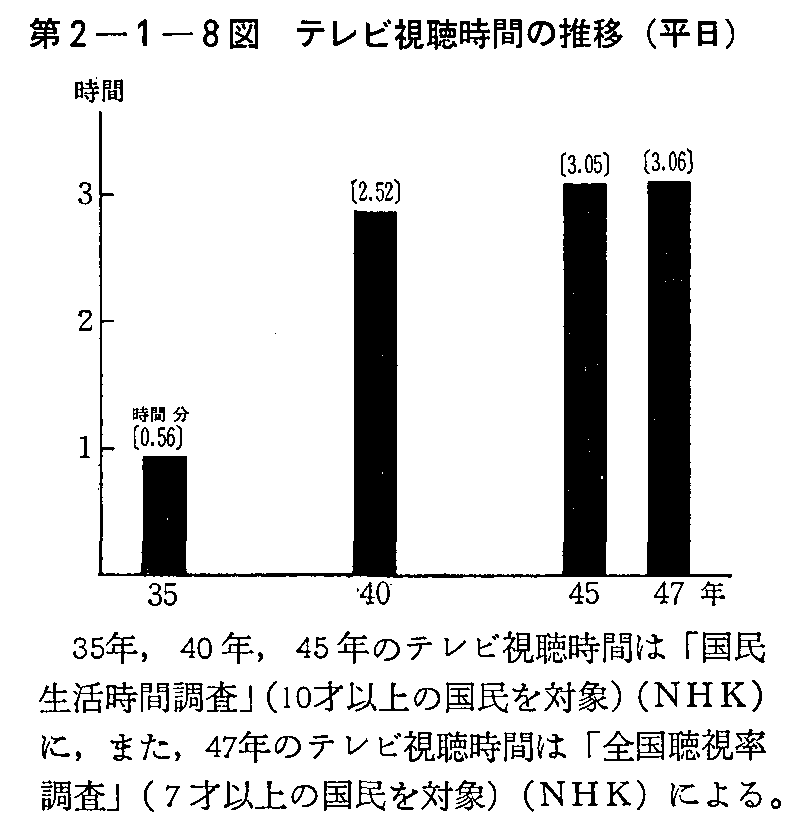
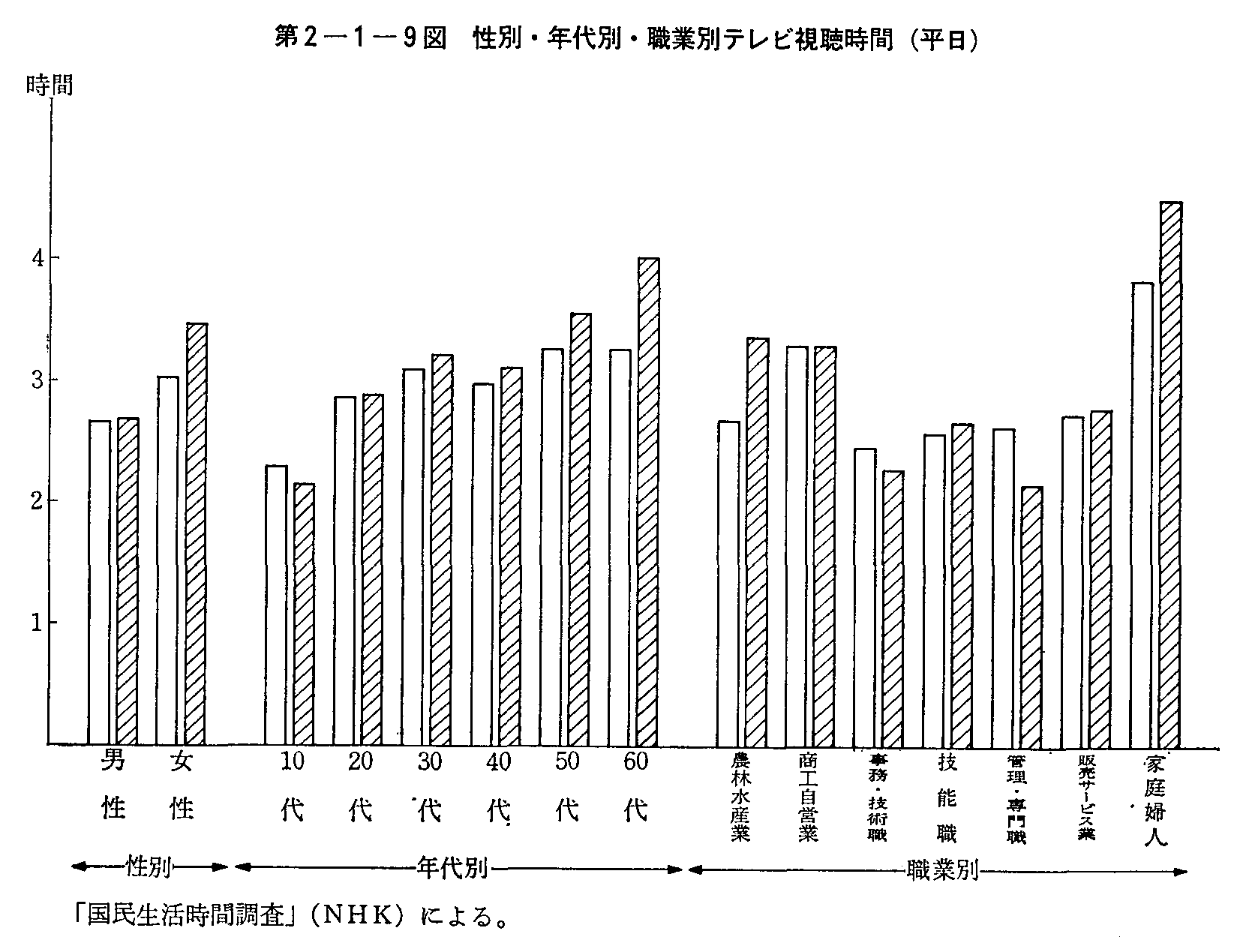
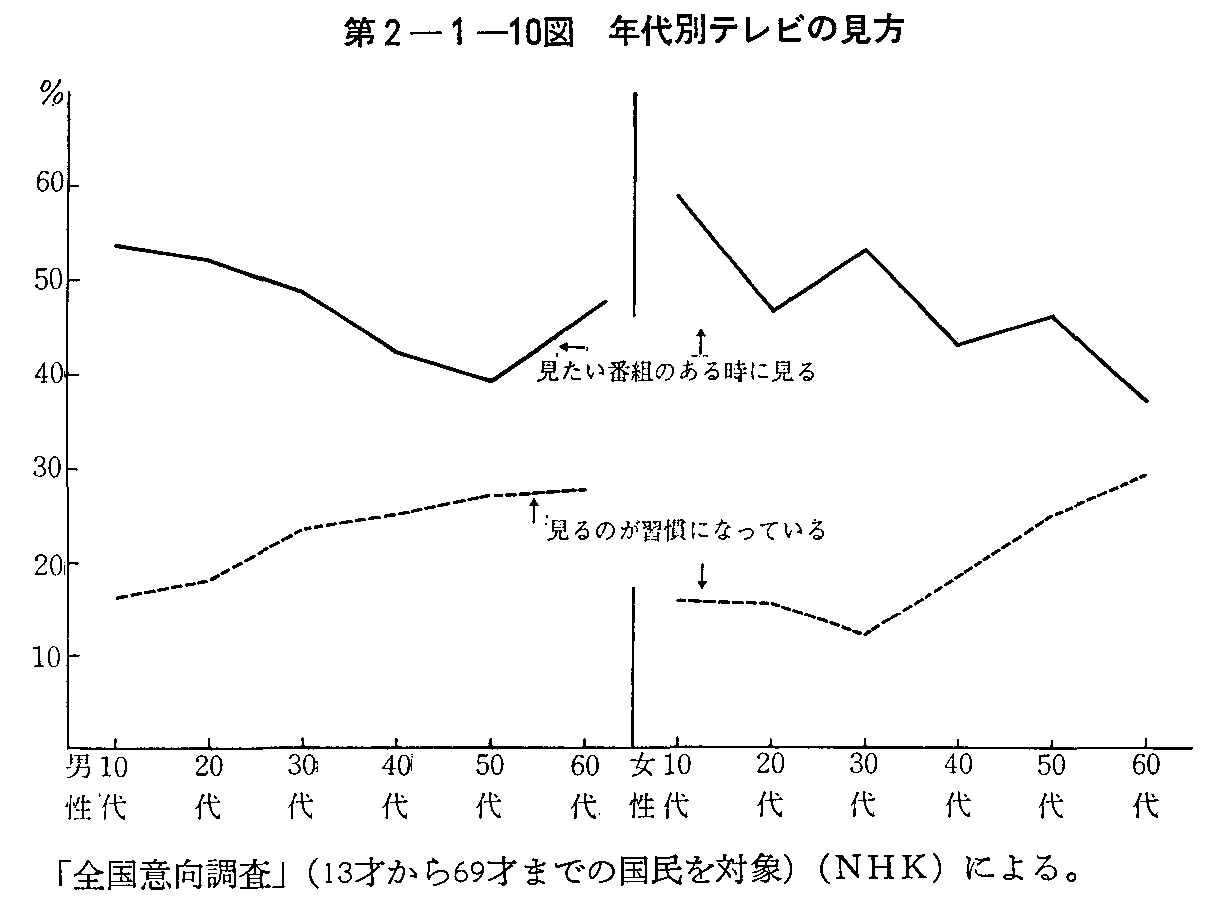
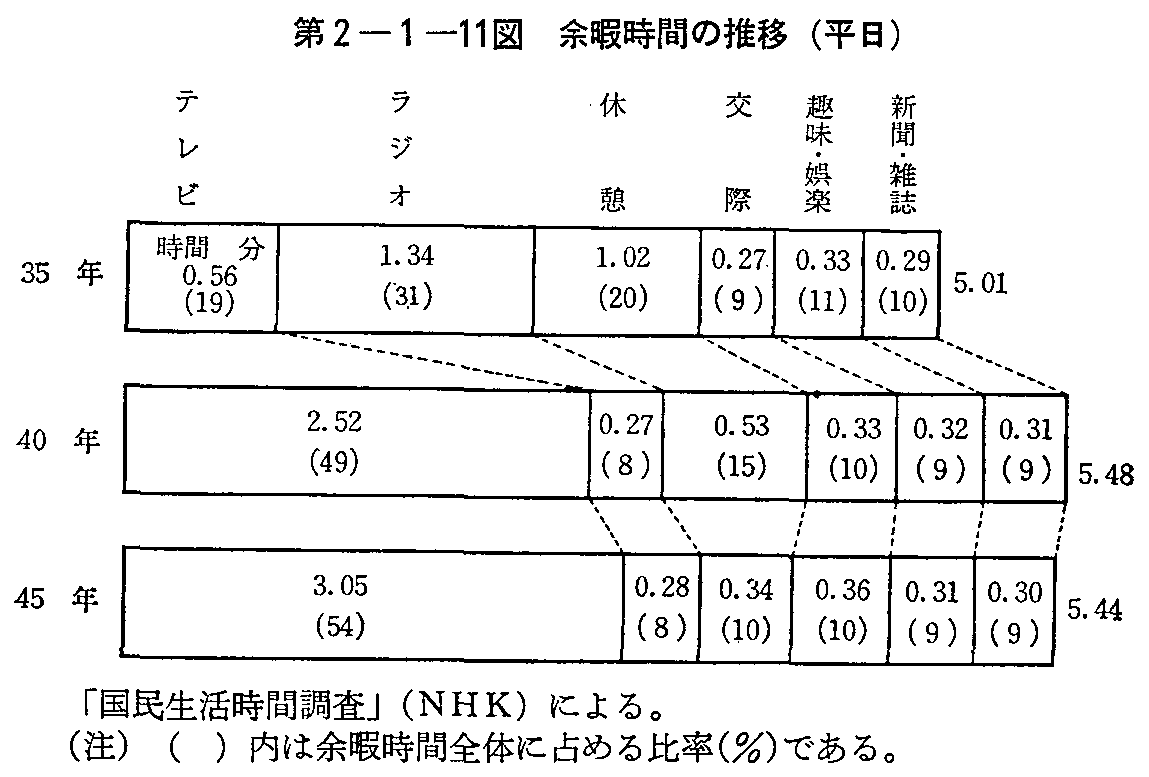
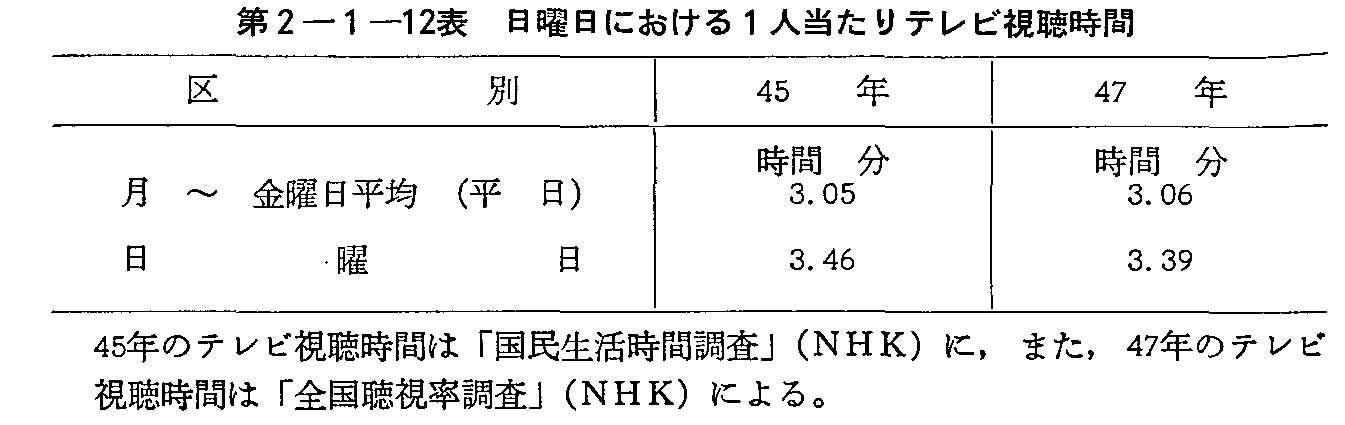
|