|
4 国際データ通信回線の利用状況(1) 利用の概要国際電電が自営システムのために提供する電気通信回線は,[1]国際特定通信回線 [2]国際公衆通信回線(加入電信の電信回線)である。 これら国際データ通信回線は国内のデータ通信回線と同様に,国際特定通信回線は46年9月1日から,国際公衆通信回線は47年11月12日から,それぞれ利用が開始されている。国際特定通信回線は,利用開始前は国際専用回線に電子計算機を接続して利用していたものが,国際特定通信回線に移行したものである。46年9月1日の移行時には18システムであったが,47年度末には25システムとなり,今後,社会経済活動の国際化,企業の海外進出に伴い国際データ通信回線に対する需要は,一層増加していくものとみもれる。 (2) 対象業務別利用状況 システム設置状況は,1利用者当たり1システム設置が通例となっているが,ただ航空会社がメッセージスイッチング・システムと座席予約システムの2システムを併設しているため,利用者数24に対しシステム数は25となっている。 25システムの対象業務別の内訳をみると,22システムがメッセージスイッチング・システムであり,このほか,気象庁の気象データ編集システム,航空会社の座席予約システム,旅行業者のホテル予約システムの3システムがある。 メッセージスイッチング・システムのなかに,商事会社が東京本社と海外支店,出張所間を結んだシステムが8あるが,これらのシステムは,海外における販売情報の収集,販売指示,海外ユーザーからの商品照会業務等に利用ざれており,この8システムで総回線数(183回線)の77.0%(141回線)を占めている。 なお,ボイスグレードの使用状況は,第3-4-19表では1回線であるが,このほか,商事会社等のシステムにおいてボイスグレード7回線が使用されている。これらはいずれも回線使用の効率化を図るため50b/s規格,75b/s規格等に分割して使用されている。 (3) 電子計算機の設置状況 電子計算機の設置場所は,日本側が13システム,外国側が12システムでおおむね半々となっている。日本側は1システム(大阪)を除きすべて東京である。外国側は1システム(フランス)を除きすべて米国の各都市に設置されている。 日本側に電子計算機を設置しているシステムは,海外の各出先機関との間に国際的なネットワークを構成しており,1システム当たり回線使用数は14.1回線となっている。これに対し,外国側に電子計算機を設置しているシステムは,外国企業が国内の支店又は合弁会社の端末機との間を接続している形態のものであるため,回線使用数は1システム当たり1回線となっている。 電子計算機の国産機,外国機別の利用状況は,日本側に設置されている電子計算機13台のうち国産機10台,外国機3台となっている。 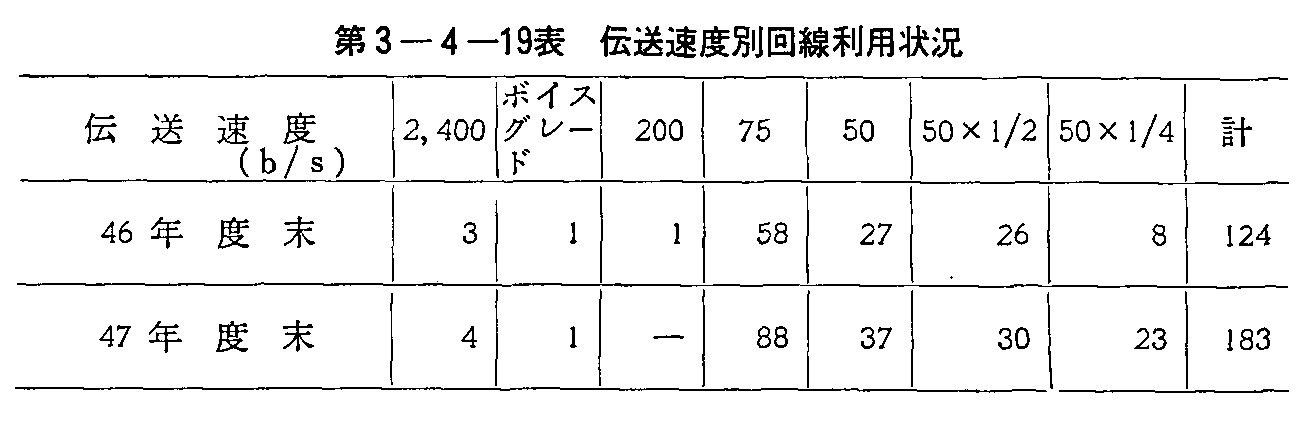
|