 第1部 総論
 第1節 昭和55年度の通信の動向  第2節 情報化の動向  第3節 諸外国における情報通信の動向
 第1節 災害対策の重要性と通信の役割  第2節 災害時における通信の役割  第3節 通信分野における災害対策  第4節 新しい通信システムの開発と今後の課題
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第1節 昭和55年度の通信の動向
1 通信の動向
(1) 概 況
ア.国内通信の動向
最近の国内通信の動向は第1-1-1図のとおりである。
郵便サービスについてみると,55年度の内国郵便物数は157億通(個)で,対前年度比3.1%の増加となり,51年度以来の低い伸び率となったが,これは56年1月に実施された料金改定の影響等によるものと考えられる。
年賀及び選挙郵便物を除いた平常信の動きをみると,127億通(個)となり,対前年度比3.6%の伸びを示している。
これを郵便サービスの生産額(外国郵便物を含む。)でみると,料金を改定したこともあり,対前年度比8.2%増の8,539億円となった。
なお,54年度の我が国の総郵便物数は153億通(個)と米国,ソ連に次ぎ世界第3位であるが,国民1人当たり差出通数についてみると,我が国は131.9通であり,米国の454.8通,フランスの240.2通,西独の224.3通,英国の185.7通等と比べて相当の隔たりがあり,世界第19位となっている。
電信サービスについてみると,電報の発信通数は38年度の9,461万通をピークに以後毎年,減少を続けてきたが,52年度以降ほぼ横ばいの状況にあり,55年度においては,4,104万通となっている。また,利用内容をみると慶弔電報の全体に占める割合が圧倒的に多く,55年度では前年度と同様73%であった。
加入電信加入数は,51年度末の7万6千加入をピークに減少傾向となり,55年度末には5万8千加入と,対前年度比8.6%の減少となった。これは,データ通信やファクシミリ等の他の通信メディアへの移行等があったためとみられる。
55年度の電信サービスの生産額は,加入電信加入数の減少等のため,640億円と対前年度比5.1%の減少となった。
55年度末の加入電話等加入数は,3,905万加入に達した。このうち,一般加入電話については,増設予定数135万加入に対し,127万加入が増設された。また,地域集団電話については,17万5千加入が一般加入電話に変更された。
電話の普及状況についてみると,人口100人当たりの加入電話普及率は33.3加入となった。
また,54年度には,電話機数では米国に次いで世界第2位,人口100人当たり電話機数では,米国,スウェーデン,スイス,カナダ,ニュー・ジーランド等に次いで第9位に位置している。
一般家庭における電話の普及及び事業所における経営効率化のための通信利用の高度化等を背景として,電話に対する国民のニーズは高度化,多様化の傾向を強め,各種の附属装置等も着実に増加している。電電公社が提供している附属装置等についてみると,親子電話は533万個,プッシュホン329万個,ホームテレホン95万セット,ビジネスホン401万個,電話ファックス1万5千台となっている。また,従来からのサービスに加え,「多機能プッシュホン」,「公衆ファックスサービス」等のサービスが新たに提供されるようになった。
電話サービスの生産額については,対前年度比3.9%増の3兆5,257億円となった。
なお,農林漁業地域の通信手段として利用されている有線放送電話の端末設備数は,前年度に比べて3.6%減少し,172万台となった。
また,有線放送電話サービスの生産額は,前年度に比べ0.1%減の180億円となった。
専用サービスは,電話のほか,データ伝送,ファクシミリ伝送等多様な用途に利用されている。
その利用動向を回線数(帯域品目のうちD〜J規格及び符号品目の回線数)でみると,55年度末現在,対前年度比1.4%増加し,30万2千回線となった。
55年度の専用サービスの生産額は,対前年度比6.5%増の916億円となった。
データ通信は,55年度も順調に推移し,データ通信システム数は,前年度に比べ25.9%増加し,5,879システム(私設システムを除く。)となった。
データ通信回線のうち,特定通信回線は10万回線と前年度に比べて20.1%増加しており,公衆通信回線も3万4千回線と対前年度比の46.1%増加となった。
このような状況の下で,電電公社のデータ通信サービスの生産額は,前年度比で16.4%増加し,1,599億円となった。
放送関係では,日本放送協会(以下「NHK」という。)のテレビジョン放送の受信契約総数は,55年度末において対前年度比1.1%増の2,926万件となった。カラー契約は,2,649万件となり,契約総数の90.5%を占めているが,カラーテレビの普及の進展とともに年度増加数の伸びは鈍化している。
一方,ラジオ放送は,カーラジオ,ラジオ・カセット等の普及を背景に,安定した発展を続けている。
放送サービスの生産額については,NHKでは受信料を改定したこともあり,対前年度比23.6%増の2,650億円となった。また,民間放送ではスポット収入を中心とする広告料収入の伸びが鈍化したこともあり,対前年度比5.3%増の9,863億円となった。
イ.国際通信の動向
最近の国際通信の動向は,第1-1-2図のとおりである。
外国郵便物数をみると,外国あてのものについては対前年度比6.4%増の1億1,163万通(個)であり,一方,外国来のものは対前年度比3.0%減の1億1,755万通(個)であった。通常郵便物の地域別交流状況をみると,差立では,アジア州が最も多く31.1%を占め,到着では北アメリカ州が37.1%と最も多い。また,航空便の占める割合は,年々上昇を続けており,差立及び到着を含めた外国郵便物数全体で,55年度は80.5%となった。
国際電信サービスについてみると,国際電報は,近年停滞の傾向にあり,55年度における取扱数は334万通と前年度に引き続き9.3%の減少となった。地域別にみると,アジア州が最も多く57.0%を占めている。
国際加入電信取扱数は対前年度比16.1%増の3,798万度となった。また,55年度末の国際加入電信加入数は7,344加入,電電公社の加入電信加入者のうち,国際利用登録者数は,2万143加入で,それぞれ順調な伸びを示している。
なお,国際電信サービスの生産額は,対前年度比4.9%増の556億円となった。
国際電話サービスについてみると,その通話度数は対前年度比19.6%増の2,343万度とケリ,これを生産額でみると,対前年度比4.0%増の709億円となった。対地別にはアジア州が最も多く,49.3%を占めている。なお,48年3月に開始された国際ダイヤル通話の利用は年々増加しており,55年度においては,全発信度数の32.3%を占め,前年度に比べ52.9%の増加となった。今後,国内利用可能地域の拡大とともに更に増加することが予想される。
国際専用回線等のサービスは,55年度末現在で音声級回線200回線,電信級回線612回線となり,前年度に比べ各々4.2%,6.3%の増加となった。
国際専用回線等のサービスの生産額は,料金の引下げを行ったこともあり,対前年度比4.1%減の107億円となった。
(2) 主な動き
ア.郵便料金の改定等
郵便法等の一部を改正をする法律が55年11月26日成立し,56年1月20日から施行された。
改正の主な内容は,[1]封書60円,葉書40円(56年3月末日までは30円)にするなど郵便料金を改定したこと,[2]郵便事業に係る累積欠損金が解消されるまでの間,一定の範囲,一定の条件の下で封書及び葉書の料金は郵政審議会に諮問した上,省令で定めるように料金決定方法を弾力化したこと,[3]新たに広告つき葉書を発行し,この葉書は一般の葉書より安く(売価35円)販売するほか,切手類の交換を葉書と葉書だけに限らず,切手と切手,切手と葉書の相互の交換もできるようにするなどサービスの改善を図ったこと,などである。
なお,この郵便法等の一部改正と併せて郵便規則の一部も改正され,第三種郵便物,第四種郵便物,書留,速達料等の料金や郵便の取扱内容の一部が改正され,1月20日から施行された。
イ.電子郵便実験サービスの開始
郵政省は,56年7月20日から電子郵便実験サービスを開始した。実験サービスの主な内容は,[1]東京,名古屋及び大阪の各中央郵便局に高速ファクシミリ送受信装置を設置する,[2]電子郵便は前記郵便局の窓口で引き受け,同装置で伝送した後,速達郵便物の例により配達する。[3]配達地域は東京23区内,名古屋市内及び大阪市内とする。[4]料金は1通につきA4判1枚500円,追加1枚ごとに300円加算となっている。
郵政省はこの実験を通じて,サービスの在り方,需要の動向,運用の経済性,機器の性能等について,詳細な検討を行うこととしている。
ウ.電気通信政策懇談会の提言
郵政省は,1980年代における我が国の電気通信政策等に関してその課題と展望を明らかにするため,55年10月,郵政大臣の私的懇談会である「電気通信政策懇談会」を設けた。
同懇談会では,[1]電気通信の分野における新しい秩序の確立,[2]公衆電気通信事業体の在り方,[3]電気通信の高度化の推進とそれに伴う問題点に対する対応,[4]国際化への対応と国際社会への貢献――4点を中心に幅広く検討を行い,56年8月24日郵政大臣に提言を行った。
この中には,緊急課題として「データ通信回線利用の自由化の問題」についての具体的な提言や,政策審議機関の拡充強化等の提言も含まれている。
郵政省は,今後,この提言の趣旨を尊重し,これを踏まえた施策を推進していくこととしている。
エ.ファクシミリ通信網サービス等の開始
電電公社は,ファクシミリ通信の大衆化のため,56年9月16日からファクシミリ通信網サービス及びミニファックスサービスを開始した。
ファクシミリ通信網サービスは,蓄積変換装置とディジタル伝送路を用いて,高速スピードで効率的にファクシミリ信号を送ることができるため,遠距離の場合でも比較的安い料金で通信ができる。
また,ミニファックスは,A5判サイズのファクシミリ端末であるが,機能の簡易化等により,低価格化,小型化を図ったもので,ファクシミリ通信網へ接続できるほか,電話網にも接続して通信することができる。
オ.遠距離通話料の引下げ等
電電公社は,遠距離通話料と近距離通話料との格差是正を図るための当面の措置として,55年11月,通話料の夜間割引制度を改正したところであるが,56年4月28日,公衆電気通信法の一部を改正する法律が成立したことに伴い,56年8月5日から遠距離通話料を500kmを超える地域について14〜17%引き下げるとともに,56年8月9日から日曜・祝日に係る料金を60kmを超える地域について約40%引き下げた。
カ.電電公社資材調達問題の解決
東京ラウンドの「政府調達に関する協定」に関する交渉において,同協定の電電公社への適用を巡り,日米間の重要交渉事項となっていた電電公社の資材調達問題は,55年12月19日,大来・アスキュー両代表間の書簡交換により解決した。
この解決措置において,電電公社は,公衆電気通信設備の特殊性を考慮しつつ,調達手続における内外無差別原則等の政府調達協定の趣旨を勘案した新しい調達手続を56年1月1日から採用し,56年6月10日,その詳細手続である「公衆電気通信設備の調達手続」を公表した。
キ.国際通信料金の改定
国際電信電話株式会社(以下「国際電電」という。)は,54年12月1日の料金引下げに続いて,55年7月1日,国際通話料金を10〜55%,国際専用回線料金を電信級については28〜35%,音声級については15〜26%それぞれ引き下げた。また,55年10月1日,国際デーテル料金を44〜54%,国際テレビジョン伝送料金を定時伝送については19〜32%,随時伝送については20〜22%それぞれ引き下げた。さらに,56年4月1日には国際加入電信料金を10〜17%,国際通話料金を17〜55%,国際専用回線料金を電信級については3〜28%,音声級については6〜46%それぞれ引き下げた。
ク.国際コンピュータ・アクセスサービス等の開始
国際電電は,55年9月8日から「国際コンピュータ・アクセスサービス(略称:ICAS)」を開始した。このサービスは,我が国の利用者の端末から外国のホストコンピュータにオンラインでアクセスし,ホストコンピュータに収容された情報をいつでも,即座に,必要な部分だけ入手できるもので,当面,我が国と米国との間で行われる通信を取り扱うこととしている。
また,55年10月1日から国際電話網を利用した加入電話相互間のファクシミリ通信及びデータ伝送の取扱いを開始した。
このサービスの取扱対地は,55年度末現在,米国,英国等29対地となっている。
ケ.放送の多様化施策の推進
郵政省は,テレビジョン音声多重放送について放送の多様化を図るため,55年12月,従来二か国語放送及びステレオホニック放送に限っていた免許方針を改正し,例えば解説放送のようにテレビジョンの主番組内容を充実させるための放送(いわゆる「補完的利用」)のすべて及び一定の条件の下での災害に関する情報の放送を認めることとした。
また,56年3月,電波技術審議会からテレビジョン文字多重放送の方式や技術基準,緊急放送システムに適した信号方式の基本について答申があったが,これらを含め,放送サービスの在り方について,現在,学識経験者等からなる「放送の多様化に関する調査研究会議」において検討が行われている。
コ.放送大学学園法の成立
放送を効果的に利用することにより,広く国民に大学教育の機会を提供するという放送大学学園法が56年6月4日成立し,56年6月11日から施行された。
法律の主な内容は,[1]放送大学学園を設立すること,[2]この放送大学学園が放送大学を設置するとともに,放送大学の教育に必要な放送を行うこと,[3]これに伴って,放送法の一部を改正し,放送大学学園の放送に関する規律を定めることなどである。
なお,この法律に基づき56年7月1日,放送大学学園が設立された。
サ.電波法の一部改正
無線局の免許申請者及び無線従事者国家試験の受験者の増加に対応し,行政事務の簡素合理化と申請者等の利便の増進を図るなどのため,電波法の一部を改正する法律が56年5月15日成立した。
改正の主な内容は,[1]無線設備の技術基準適合証明制度の創設,[2]電話級アマチュア無線技士等の資格試験実施事務の委託,[3]一定の条件の下での外国人に対するアマチュア無線局の免許の付与,[4]免許を受けずに無線局を開設した者に対する罰則の創設,などであり,[1],[2]及び[3]については56年11月23日から,[4]については58年1月1日から施行される予定である。
シ.宇宙通信実用化の促進
実験用中容量静止通信衛星(CS「さくら」)及び実験用中型放送衛星(BS「ゆり」)による各種の基本実験は53年度から行われており,多くの成果が得られている。特に「さくら」については,55年度は公共業務用衛星通信システムに関する実験(警察,国鉄関係),災害対策用衛星通信システムに関する実験等,実用化に向けての応用実験が行われた。
これらの成果を踏まえて,我が国の実用通信衛星は57年度及び58年度に,また,実用放送衛星は58年度及び60年度に,それぞれ本機,予備機を打ち上げる計画となっている。
また,60年代前半にはより大型の実用通信衛星及び放送衛星の打上げが考えられるが,これらの衛星の利用の在り方について,学識経験者等からなる「電波利用開発調査研究会(実用衛星部会)」において検討が進められており,56年6月,このうち通信衛星についての報告書がまとめられた。
ス.国際電信電話諮問委員会総会の開催
国際電信電話諮問委員会(CCITT)の第7回総会が,1980年11月10日から21日まで,ジュネーブにおいて開催された。この会議はほぼ4年ごとに開かれており,今回の総会では,光ファイバケーブルの伝送特性,ディジタル総合サービス網の基本原則,ビデオテックスのための国際情報交換,G3ファクシミリ機器の標準化,テレテックスの標準化等に関する勧告が採択された。
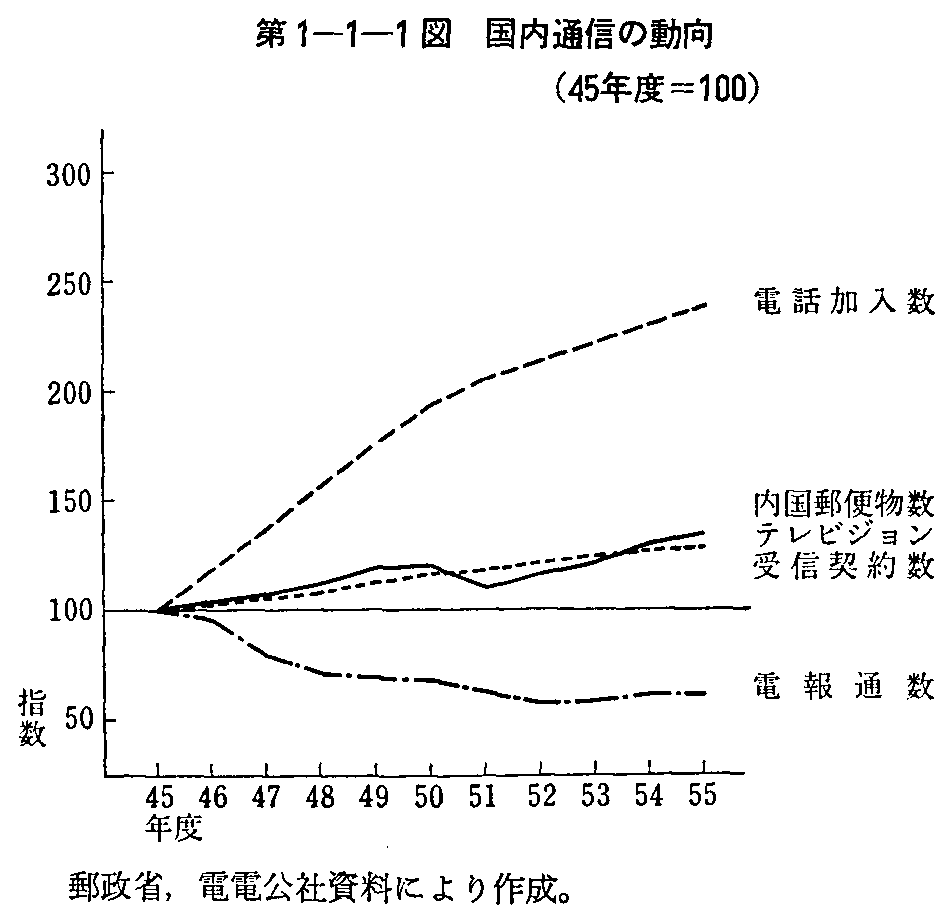
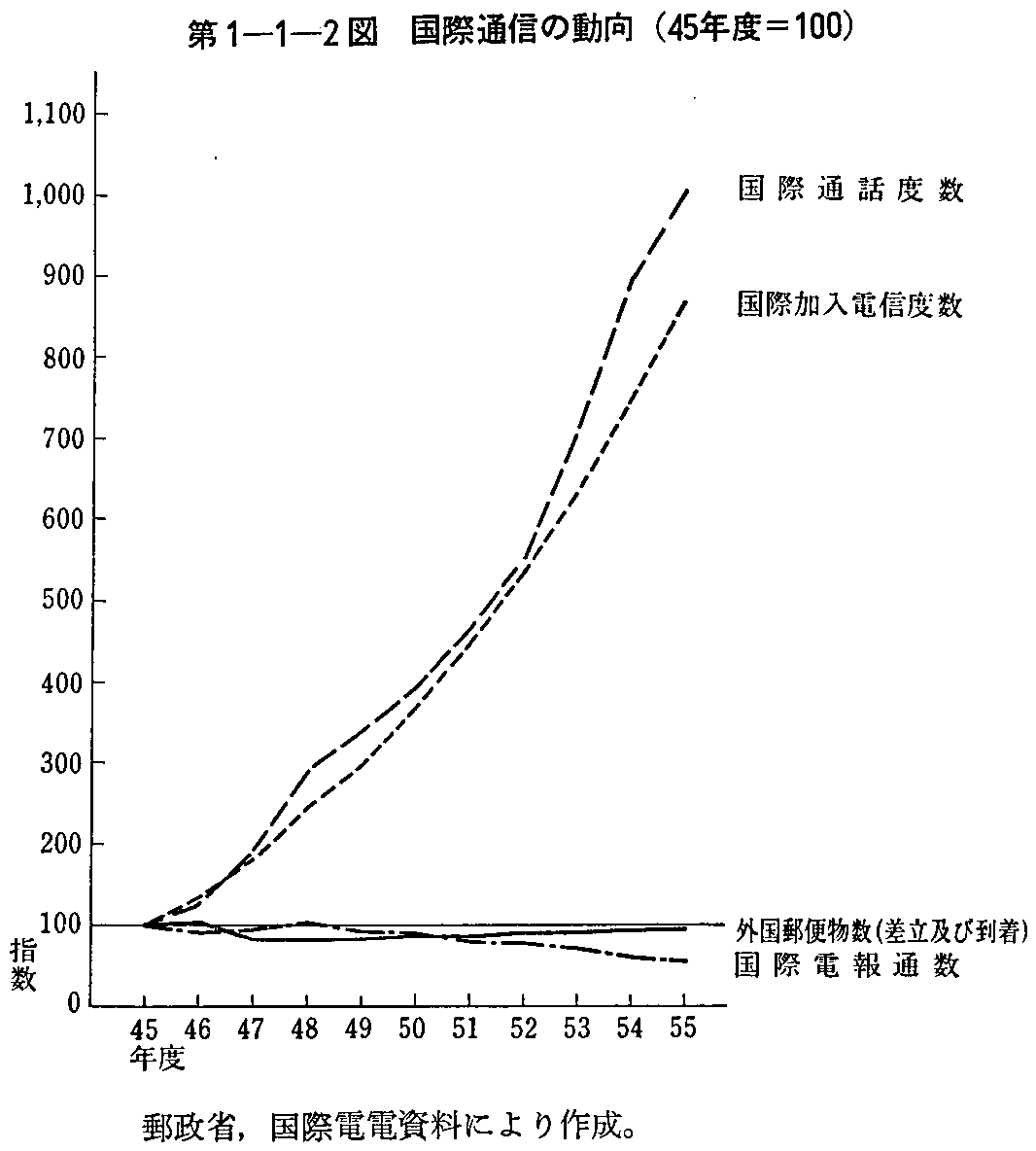
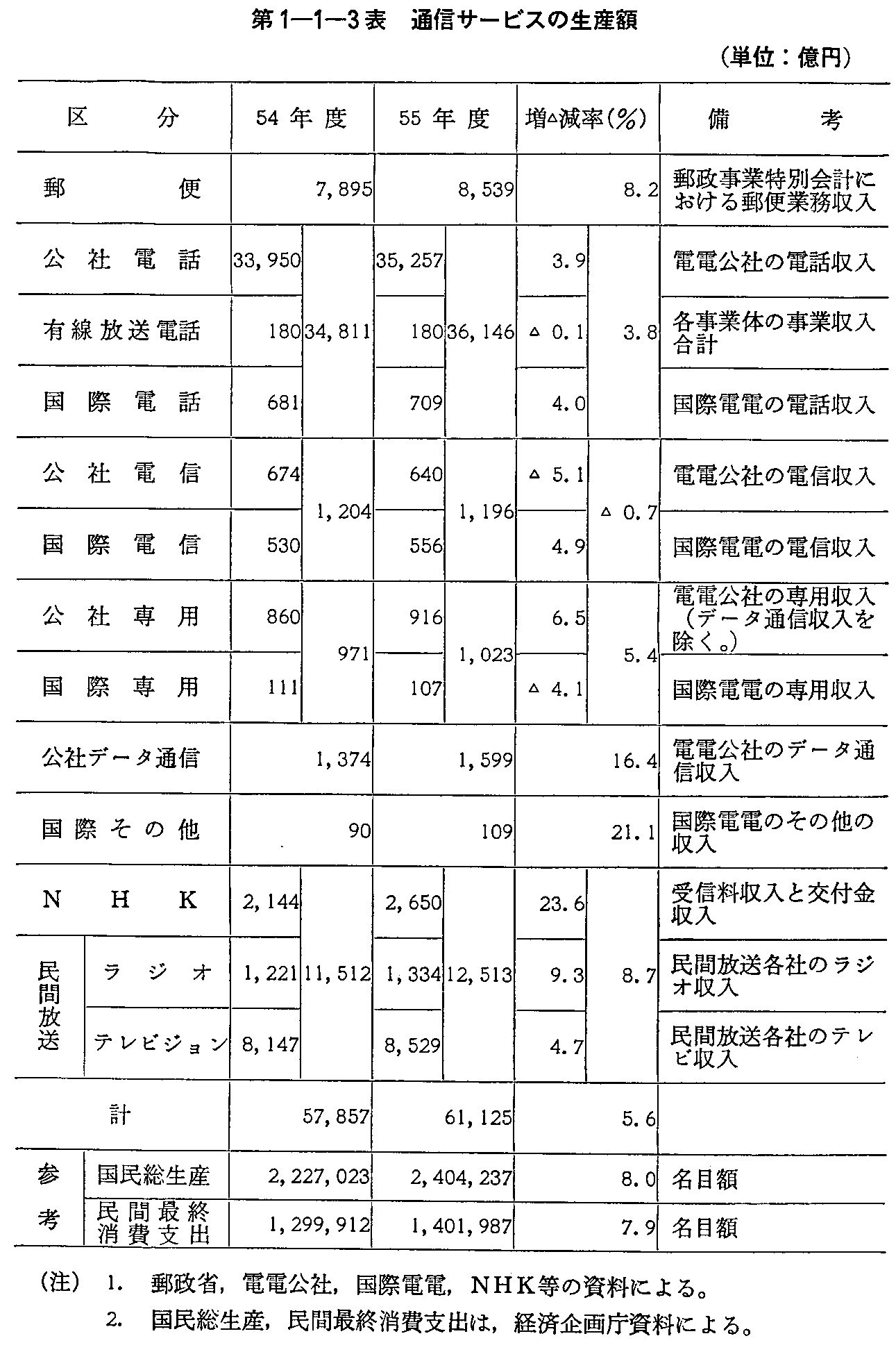
|