 第1部 総論
 第1節 昭和55年度の通信の動向  第2節 情報化の動向  第3節 諸外国における情報通信の動向
 第1節 災害対策の重要性と通信の役割  第2節 災害時における通信の役割  第3節 通信分野における災害対策  第4節 新しい通信システムの開発と今後の課題
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
第2節 国内公衆電気通信の現状
1 電電公社業務
(1)電 報
電報は,明治以来,国民一般の緊急通信手段として重要な役割を果たしてきたが,近年,加入電話の普及及びデータ通信等多様な通信手段の発展に伴い,その性格は変容してきており,電報の利用通数や利用内容等に反映している。電報通数は,38年度の9,461万通をピークとして大幅に減少してきたが,52年度以降ほぼ横ばいの傾向にあって55年度は4,104万通(国民1人当たり0.35通),となっている。その内容については,総電報通数中に占める慶弔電報の割合は,73%(3,000万通),死亡・危篤を知らせる緊急信等の一般電報は27%と前年度と同様の構成となっている(第2-2-1図参照)。
なお,新しい電報サービスとして55年8月から提供された緊急定文電報は,2万3千通の利用があった。この緊急定文電報は,個人の死亡,危篤,事故,病気,被災等に関する緊急連絡の利便化を図るもので,あらかじめ定めた文(定文)を通信文に使用し,20字以内で任意の補完文を追記でき,通信文の長短にかかわらず1通ごとに300円(通常電報の基本料相当額)となっている。
電報事業の収支状況については,利用通数の伸び悩み,人件費等諸経費の増嵩により,毎年大幅な赤字を続けている。電電公社も,電報受付局(115番取扱局)の統合,電報配達業務の民間委託の推進等業務運営の効率化を図ってきているが収支を改善する抜本的な対策にはなり得ず,電電公社の事業経営問題点の一つとなっている。
(2)加入電信
加入電信は一般にはテレックスと呼ばれ,任意の相手方と50b/sの符号伝送が可能な交換網サービスで,31年のサービス開始以来,企業における情報化指向,事務合理化の機運にマッチしその加入数は着実に伸びてきていたが,ファクシミリやデータ通信など他の通信手段への移行等の要因により,近年は減少傾向にある。55年度末加入数は,前年度末に比し約5千加入減少し,5万8千加入となった(第2-2-2図参照)。
(3)電 話
電話は,交換網を通じて任意の相手方との間に音声通信を行うことが可能な典型的なパーソナル電気通信メディアであり,日常生活や企業活動に欠くことのできない基幹的な通信手段としての地位を占めている。
現在では,電電公社発足以来の二大目標であった「積滞解消」,「全国自動即時化」がほぼ達成され,電話の需給均衡時代を迎えたが,電電公社の今後取り組むべき課題の一つは社会の進展に伴ってますます多様化・高度化する需要動向にきめ細かに対応していくことであり,今後とも安定した良質なサービスの提供に積極的に取り組んでいくことが要請される。
電電公社が提供している電話の中では,一般家庭や事業所等で使用される加入電話や,街頭や店頭に設置されて公衆の利用に供される公衆電話が代表的なものであるが,このほかにも船舶電話,列車公衆電話,自動車電話等がある。
ア.電話サービスの現状
(ア)加入電話
55年度末現在,加入電話総数は3,905万加入であり,このうち単独電話は3,629万加入,共同電話は154万加入,構内交換電話65万5千加入,事業所集団電話34万8千加入,地域集団電話21万4千加入となっており,また,地域団体加入電話組合加入回線及び有線放送電話接続回線の数は,1,021加入となっている。総数では前年度末より129万1千加入(3.4%)の増加となった(第2-2-3図参照)。
人口100人当たりの普及率は55年度末において33.3加入となり10年前に比し約2倍となった。
加入数の推移を事務用,住宅用の利用種別でみると,55年度は地域集団電話を一般加入電話に変更したものを含め,事務用が25万3千加人の増加に対し,住宅用は119万1千加入増加しており,最近の著しい傾向として住宅用電話の増加が依然続いている。
また,電話機数は,前年度末より265万個増加して5,628万個となり,人口100人当たり電話機数は,47.9個となった。
なお,54年度には電話機数では,米国に次いで世界第2位,人口100人当り電話機数では,米国,スウェーデン,スイス,カナダなどに次いで世界第9位となっている。
このような加入電話の普及にもかかわらず,地域集団電話の一般加入電話化,普通加入区域の拡大による過疎地域への電話の普及等なお解決を要する問題は残されている。
地域集団電話は,農山漁村地域等における集団的な電話需要に応じて設散されたが,多数共同電話方式であるため話中になることが多い等利用上不便であることから,生活条件の変化等による通話量の増大に伴い,一般の加入電話への変更の要望が強くなってきている。電電公社では,逐次計画的に一般加入電話への変更を実施してきており,55年度においては17万5千加入の一般加入電話化が行われた。
なお,このような地域集団電話の一般加入電話化の促進に伴い地域集団電話の加入者数が著しく減少した場合,残存する加入者にとっては,単独電話に近い利用ができることとなり,集団的な利用の態様に応じた施設と料金をもって構成されているこの制度の趣旨にそぐわないものとなるので,56年4月に成立した公衆電気通信法の一部改正により,電電公社は,加入者数が極端に減少した場合(集団電話の加入申込みに必要とされる数の10分の1未満)において交換設備の老朽化等により集団電話サービスの提供が困難となったときには,郵政大臣の認可を受けて,単独電話等へ切替えができることなった。
また,現在,普通加入区域外に設置される一般の加入電話については,通常の料金のほか特別の費用の負担を要することとなっており,このため,普通加入区域の拡大または負担の軽減について多くの要望が寄せられている。
そこで,電電公社では第6次5カ年計画(53〜57年度)において,電話加入区域を電話局から半径5kmを7kmへ拡大することとして,鋭意これを推進してきており,55年度は362区域を拡大した。この加入区域の拡大は順調に進められており,56年度は240区域を拡大する予定となっている(第2-2-4表参照)。
(イ)公衆電話等
公衆電話には,公社直営で電話ボックス等に設置されている街頭用公衆電話と,商店等に管理を委託している店頭用公衆電話(赤電話)がある。街頭用公衆電話には,10円硬貨のほか100硬貨も併用可能な100円硬貨併用公衆電話(黄電話)と10円硬貨専用公衆電話(青電話)があり,また,頭公衆電話は従来10円硬貨利用のものに限られていたが,55年8月から100円硬貨併用の公衆電話(新型赤電話)が提供され,約5千個設置された。
電電公社では,利用者の利便の向上を図るため,積極的に公衆電話の増設に努めており,55年度には黄電話が6万5千個増設され,年度末には総数88万個,人口1,000人当たり7.5個の普及率となった。
また,加入電話の一種で公衆にも利用できるように電話機に硬貨投入装置が付加されているいわゆるピンク電話もその新規需要には根強いものがあり,55年度は6万3千個の増設が行われて年度末総数は100万個となった(第2-2-5図参照)。
(ウ)移動体通信
無線を利用した移動体通信の分野では,沿岸を航行する船舶に設置されている船舶電話,国鉄新幹線に設置されている列車公衆電話,自動車に設置されている自動車電話等があり,船舶電話については54年3月から自動化が図られている。
このうち,自動車電話は,54年12月から東京23区で,また55年11月から大阪で開始された新しいサービスである。現在のサービス・エリアは,東京地域では東京23区と東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県の63市であって,おおむね都心から50km圏となっており,大阪地域では大阪府,兵庫県(56年7月開始予定),京都府,奈良県(両県は56年9月開始予定)の主要都市48市となっている。56年度末には名古屋地区で新たにサービスを提供する予定である。
この自動車電話サービスは,サービス・エリア内を走行中の場合,自動車電話と全国の電話との間はもとより,自動車電話相互間でも通話を行うことができる。
56年3月末現在,自動車電話サービスの開通数は6,406件で,順調に増加している。
(エ)各種付加サービス
社会活動の高度化に伴い国民の生活様式が変化し,電話についても,従来のようにただ単に通話ができればよいというだけでなく,より便利かつ高度な機能を備えることが求められてきている。
このような要求を満たすため,ホームテレホン,プッシュホン,電話ファックス,ビジネスホン等の各種の電話機や附属装置のほか,キャッチホン(通話中着信サービス),でんわばん(不在案内),シルバーホン(音量増幅用電話)等のサービスが提供されている(第2-2-6図参照)。
(オ)ポケットベルサービス
電話のネットワークを利用して,無線により外出している人等を呼び出す,いわゆるポケットベルについては,43年のサービス開始後急速に普及し,55年度末においては,サービス提供地域は65地域,加入数は109万加入となった(第2-2-7図参照)。
(カ)新たに提供されたサービス
55年度には,コードレスホン,料金着信払通話サービス(コレクトコール),多機能プッシュホン等の提供が開始され,56年度に入ってからは,クレジット番号通話サービス,ファクシミリ通信網サービス及びミニファックスサービス等が新たに提供された。これらの新サービスの主なものの概要は次のとおりである。
A コードレスホン
一般家庭や事業所等において電話機を自由に持ち運んで通話をしたいという要望にこたえるものであって,屋内の配線部分を無線方式にすることによって約20mの範囲内において自由に電話機を移動して通話することができるものであり,回転式とプッシュ式の2種類がある。
B 料金着信払通話サービス(コレクトコール)
発信者の請求に基づきその通話に係る料金を発信者に代わり当該通話の着信があった加入電話の加入者等が支払うこととして通話ができるサービスであって,着信者の料金支払承諾を得られた場合に取り扱うものである。
C 多機能プッシュホン
通常のプッシュホンの電話機能を拡充するとともに簡単なデータ入出力装置をも備えたものであって,付加装置である簡易プリンタを利用することにより出力データの記録もできる。この多機能プッシュホンを各種のデータ処理センタへアクセスすることにより,例えばクレジット加盟店によるクレジットカードの検証や売上処理業務,不動産業等による情報検索業務,金融機関による残高照会や入金通知業務,チェーン店等による商品発受注業務などにも利用できるものであり,これら業務の迅速化,正確化,省力化を図ることができる。
なお,多機能プッシュホンには1形と2形の2種類あるほか付加装置として簡易プリンタ等がある。
D クレジット番号通話サービス
加入電話,公衆電話等から行った通話に係る料金を加入電話加入者があらかじめ指定した加入電話に課すこととして,外出先,出張先等からどこへでもキャッシュレスで通話ができるサービスである。
E ファクシミリ通信網サービス及びミニファックスサービス
ファクシミリ通信網サービスは,必ずしも電話における会話のように同時送受信が要求されないファクシミリ通信の特徴を生かした蓄積変換方式をとっているため,[1]ディジタル化による冗長度抑圧及び長距離の高速電送等を行うことができるなど伝送路の使用効率の向上が図られ,通信料金が大幅に安くなっていること,[2]従来,端末機側で有していた自動受信機能及び同報通信機能等を網側に負担させ,多数の利用者が共用できるようにしていること,[3]不達通知機能,再呼機能,発信者番号の自動記載機能等従来のファクシミリ通信になかった便利な機能を網側が有していることなど従来の電話ファックスにはない特色を持つサービスである。
一方,ミニファックスは,A5判サイズのファクシミリ端末であるが,このファクシミリ通信網に接続して通信できるもので,大幅に低価格となっているほか小形・軽量化と操作の簡易性を図っている。また,このミニファックスは,既存の電話ファックスと同様電話網のみを利用して通信することもできる。
イ.料金明細に関する問題
郵政省及び電電公社では,電話利用者から料金について問合せや苦情があった場合,その料金内訳を的確に答えられる体制を整えておくことが必要であるとの観点から,現在,電話料金明細サービスについて,そのサービスの詳細のほか,通信の秘密の確保,プライバシー保護等実施上の諸問題について,関係各方面の意見も聴しながら慎重に検討を進めているところである。
なお,総理府が56年2月25日から3月3日まで実施した「電話利用に関する世論調査」では,料金内訳の送付を希望する人の割合は全体の66%を占め,また希望しないとするものの中でも,そのうち42%の人が電話局では料金の内訳書を保存しておくべきだとしている。
ウ.電話無料装置に関する問題
最近,電気通信システムの普及とともに電子技術が発達するにつれて,通信機能に対する妨害や犯罪の発生する可能性が大きくなってきている。55年度には,こうしたものの例として,マジックポンとかビップホンと呼ばれる不正機器が出現している。
これらの装置を加入電話機に取り付けると,その電話にかけた通話度数が登算されず,結果的に電話料金が免脱されてしまうものである。この不正機器の機能は,国際通話料金の免脱にまで及ぶものである。
郵政省及び電電公社は,事件発生以来,捜査当局の協力を得て,これら不正機器の設置,使用の発見・防止に努めている。
(4)専用サービス
電話や加入電信が,交換網によって,任意の加入者との間で自由に通信を行うサービスであるのに対し,専用サービス(公衆電気通信設備の専用)は,特定の者が,特定の地点相互間において,公衆電気通信設備を排他的に使用するサービスで料金が定額性であることから,企業,公共機関等が多量の通信を行うのに適した通信手段である。
現在,専用の制度は,使用する周波数の幅に応じてD規格からL規格までアルファベット別に分類される品目(帯域品目)と符号伝送速度に応じて50b/sから48kb/sまでに分類される品目(符号品目)とに大別される。さらに,帯域品目の各規格は伝送速度及び使用方法に応じて細分化されており,単に音声通信のみでなくデータ伝送,模写伝送,放送中継等多様な需要に応じている。また,符号品目は,最近におけるコンピュータ利用技術の高度化に伴い,データ伝送のみに利用する回線の需要増加にこたえるものであり,混合使用は認められていない。
利用状況を回線数(帯域品目のうちのD〜J規格及び符号品目の回線数)についてみると,55年度末で約30万2千回線あり,前年度に比べて約4千回線(1.4%)増加している(第2-2-8図参照)。規格別には,3.4kHzの周波数帯域を使用するD規格が約21万6千回線と全体の約72%を占めており,その中でも通常の音声伝送が可能で専用電話として利用されているD-2が約18万9千回線とD規格全体の87%を占めている。
D規格に次いで多く利用されているのは50b/sで,その回線数は,55年度末で8万3千回線となっている。その他の規格については,専用サービス全体からみれば,その利用数は極めて少ない。
また,L規格は,4MHzの周波数帯域の伝送が可能なもので,テレビジョン放送中継用としてNHK及び民間放送各社に使用されており,55年度末現在の利用状況は,474回線,延ベキロにして4万6,500kmとなっている。
なお,テレビジョン音声多重放送の開始に伴い,54年8月からテレビジョン放送中継回線の音声多重化を実施した。
(5)公衆電気通信法の一部改正
第94回通常国会に提出された「公衆電気通信法の一部を改正する法律案」は,56年4月28日に成立した。同改正は,電話の遠距離通話料を引き下げるとともに,日曜日・祝日の通話料を法律で定められている料金より割引きして定めることができるようにすることを主たる内容とするものであり,8月5日から施行された。
この改正法を提出するに至った背景については,我が国の電話の通話料が諸外国のものに比べ近距離は2分の1ないし4分の1と安くなっているのに対し,遠距離は2倍ないし3倍と高くなっていることから,遠距離通話料と近距離通話料とのいわゆる遠近格差が大きくなっており,その是正については郵政省としても重要な課題として取り組んできたところである。その一環として55年11月27日から通話料の深夜割引制度の新設(320kmを超える区域外通話料について,午後9時から翌日午前6時までは昼間の6割引とした。),夜間割引時間帯の拡大(夜間割引の対象時間帯を午後7時から翌日午前8時まで前後1時間ずつ拡大した。)を実施したが,更に遠近格差の是正措置を進めるため,公衆電気通信法の一部を改正し,特に遠距離である500kmを超える区間の昼間の通話料を引き下げるとともに,日曜日・祝日の割引制度を導入することとしたものである。
改正された事項の概要は次のとおりである。
ア.遠距離通話料の引下げ
区域外通話地域間距離が500kmを超える区域外通話の料金は第2-2-9表のとおり改められた。
これによって,遠近格差は従来の1対72が1対60に是正された。
イ.日曜日・祝日に係る通話料の割引制度の導入
区域外通話地域間距離が60kmを超える区域外通話の日曜日及び祝日(祝日の振替休日等を含む。)に係る料金について,夜間通話料金の場合と同様に,電電公社が郵政大臣の認可を受けて法定の料金より低く定めることができることとなった。
ウ.電話使用料適用の特例
電話使用料について,加入電話加入者が市町村等の法人であっても,老人福祉電話等郵政省令で定めるものに限り,住宅用が適用されることとなった。
エ.その他の法律改正事項
集団電話について,加入者数が少数となった場合に加入電話の種類を変更することができることとなったほか,ダイヤル自動化の完了に伴う所要の規定の整備を行った。
オ.郵政大臣の認可による改正事項
夜間及び深夜時間帯の通話料,100番通話料,手動即時通話料,待時通話料,自動車電話の通話料,船舶電話の通話料及び一般専用の基本回線専用料等について,法定料金の引下げ率と同じ率で引き下げられ,8月5日から実施された。また,新たに導入された日曜日・祝日に係る昼間料金の割引については,夜間割引と同様4割引とし,8月9日から実施された。
この結果,夜間料金と深夜料金については,従来と同様に改訂後の昼間料金のそれぞれ約4割引及び6割引となるので,750kmを超える区域外通話料は,夜間帯では3分間通話した場合450円が360円に,深夜帯では3分間280円が240円にそれぞれ引き下げられ,遠近格差も昼間帯の1対60に対して夜間帯では1対45,深夜帯では1対24となった。
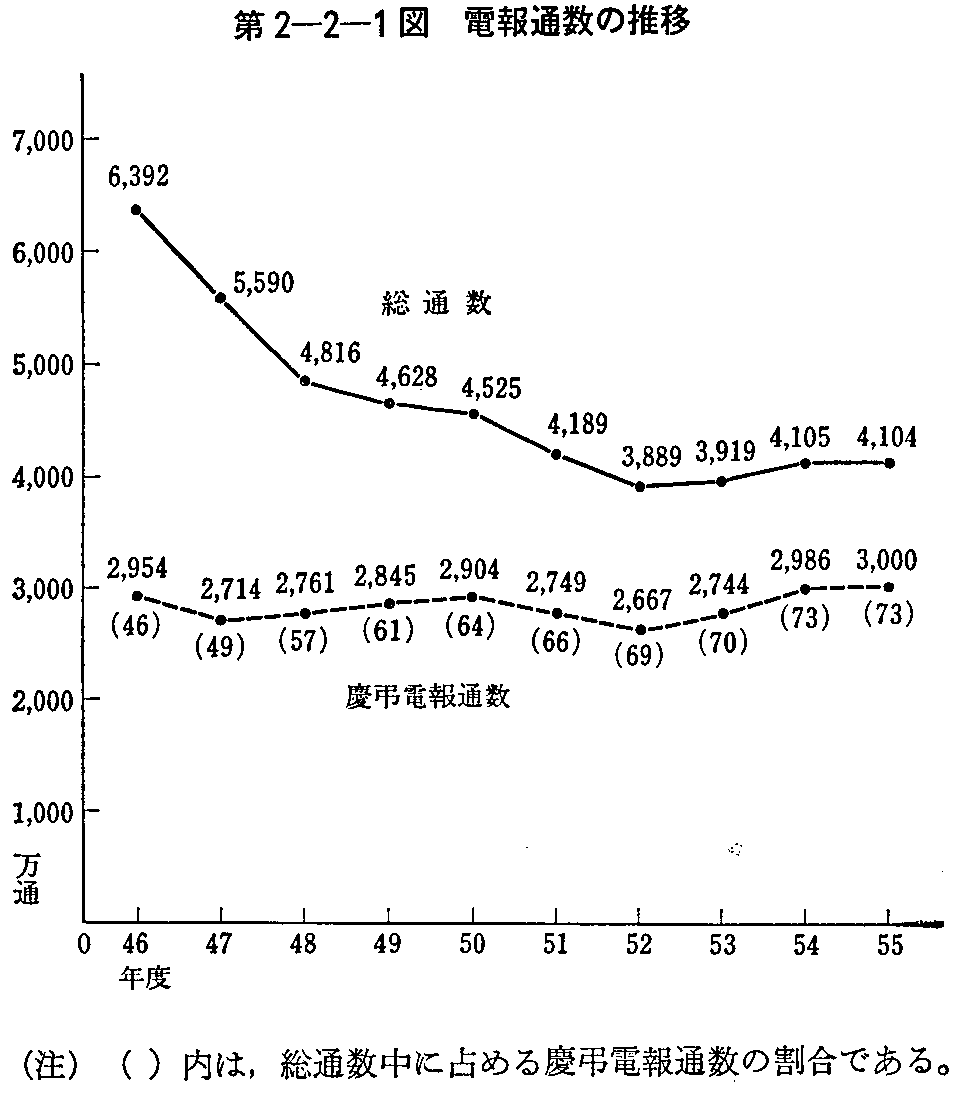
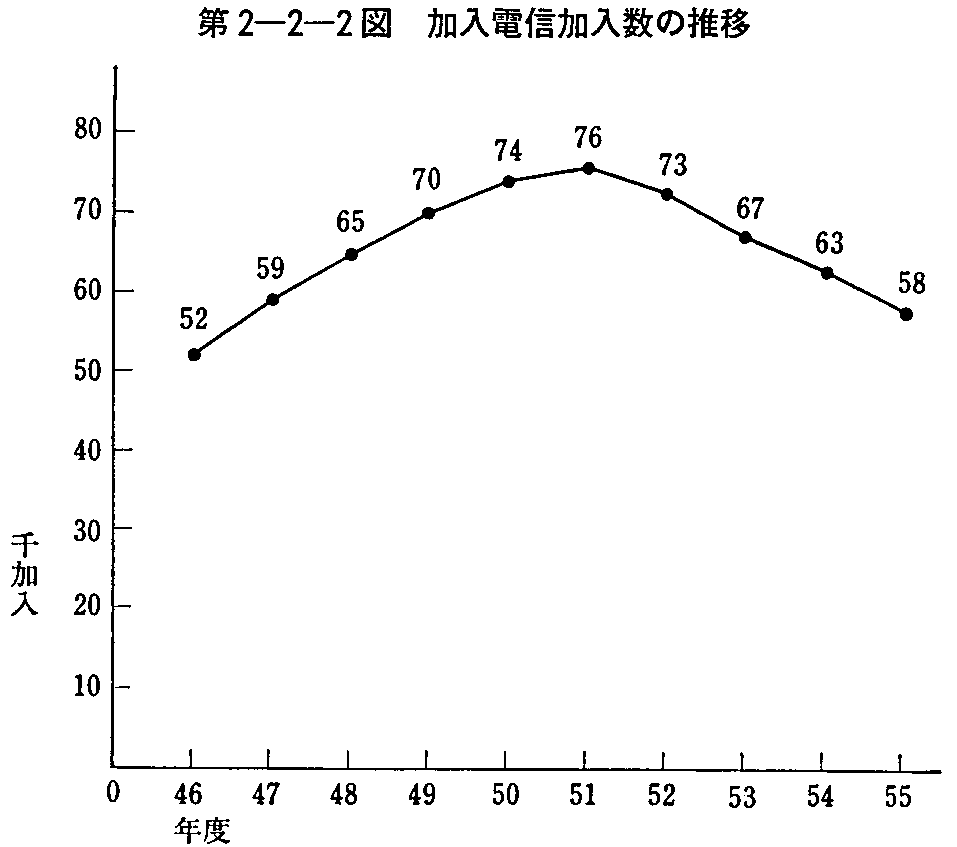
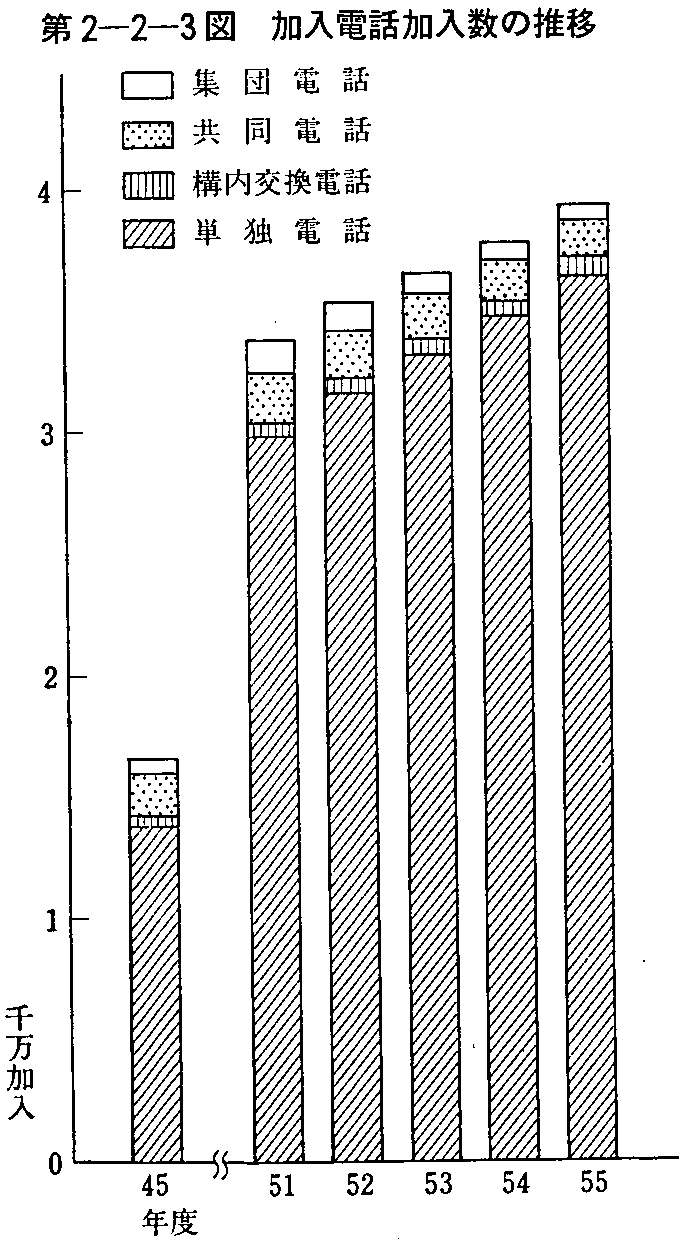
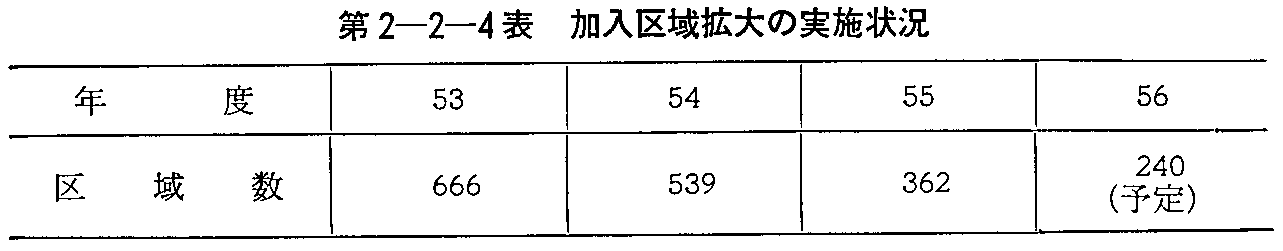
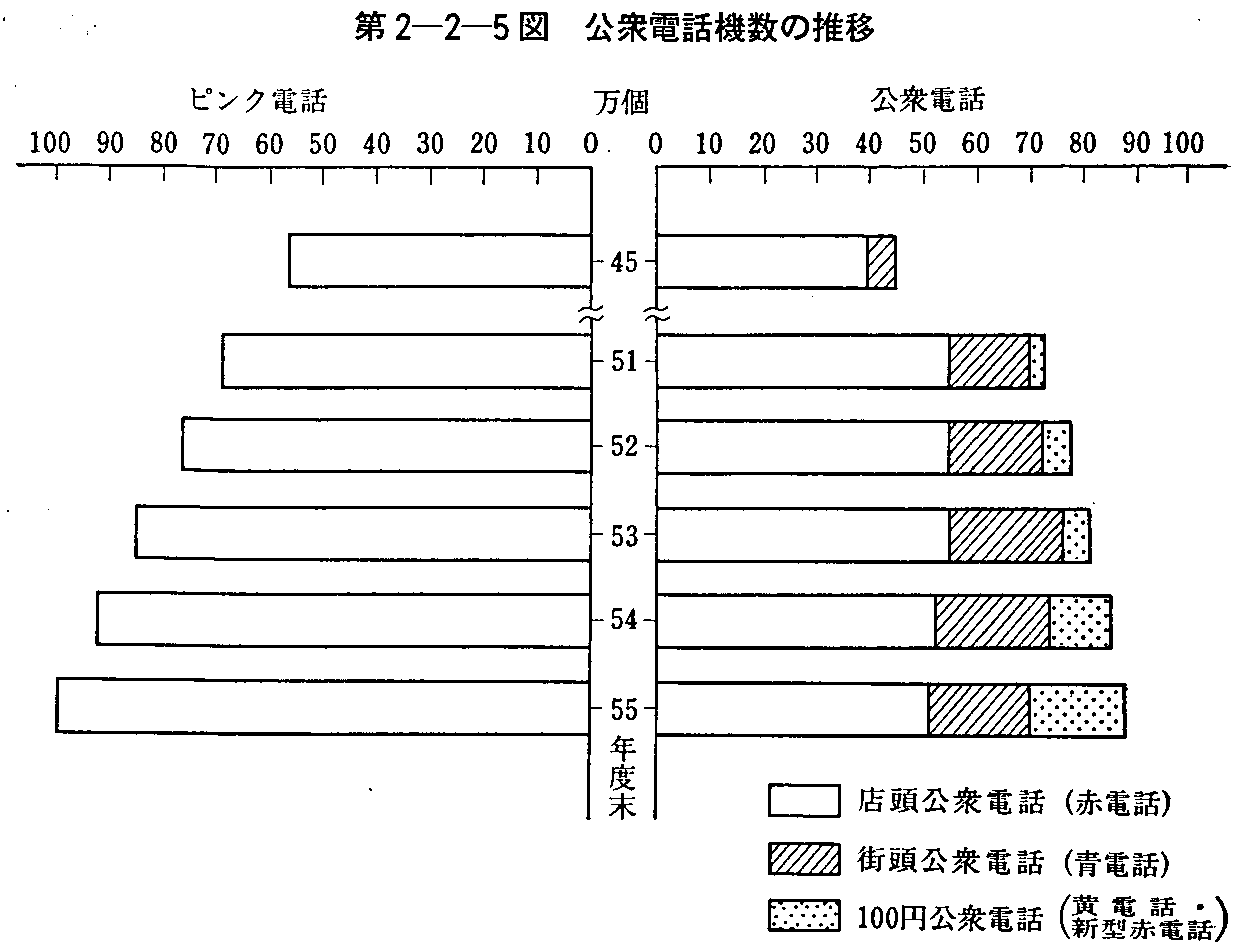
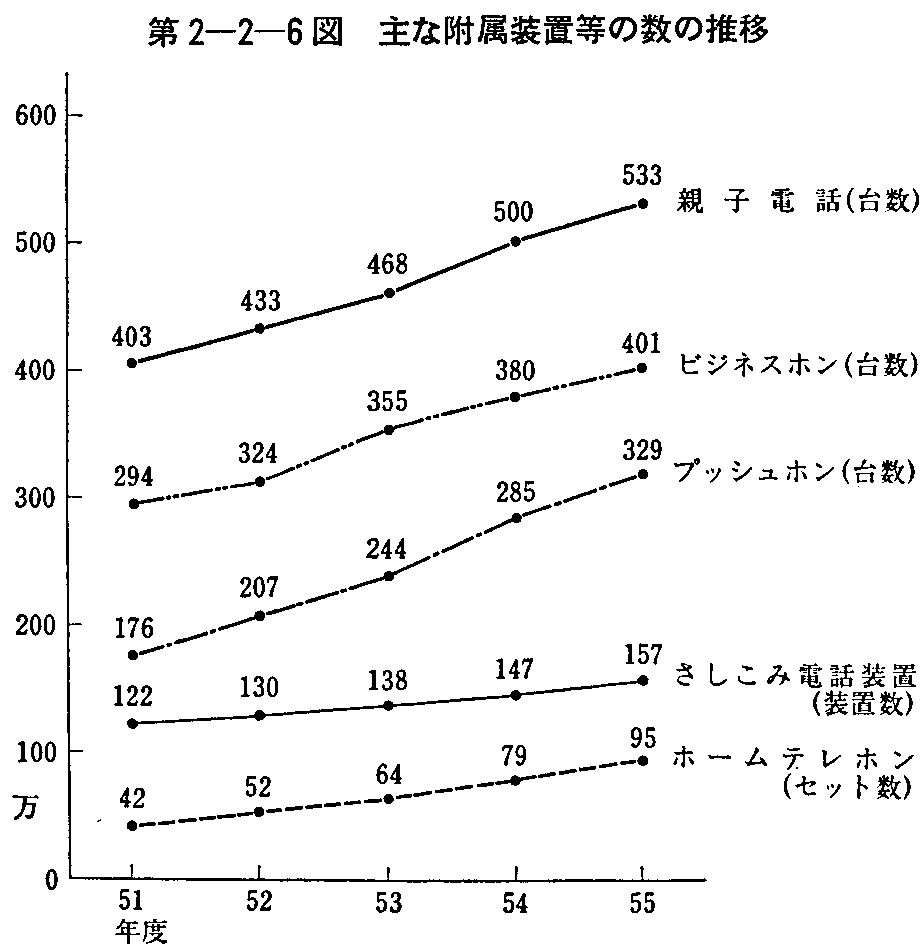
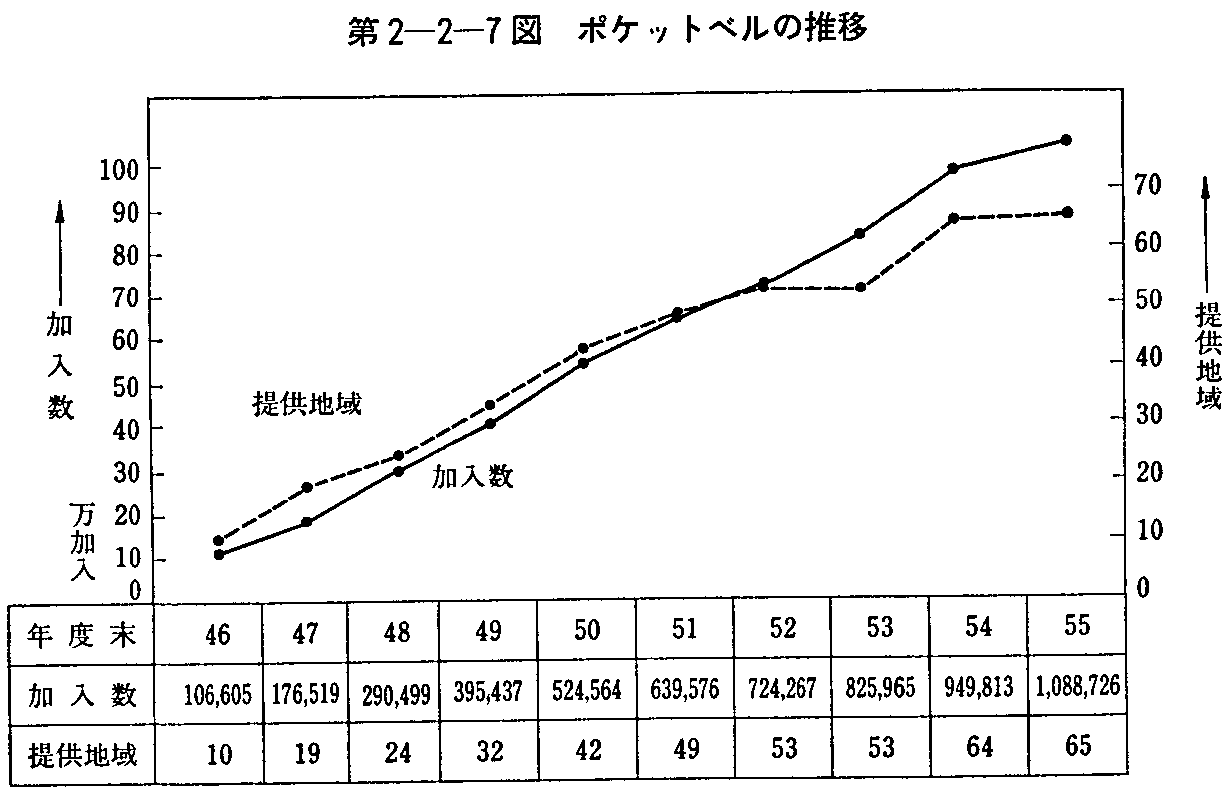
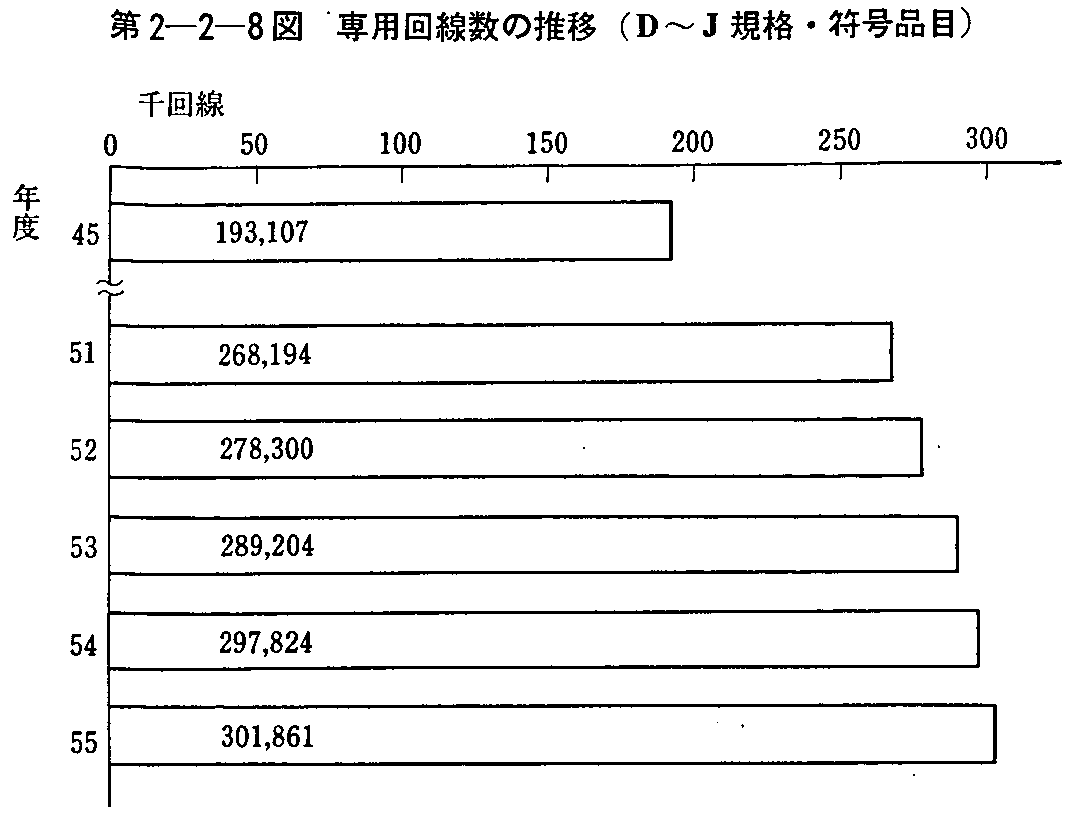
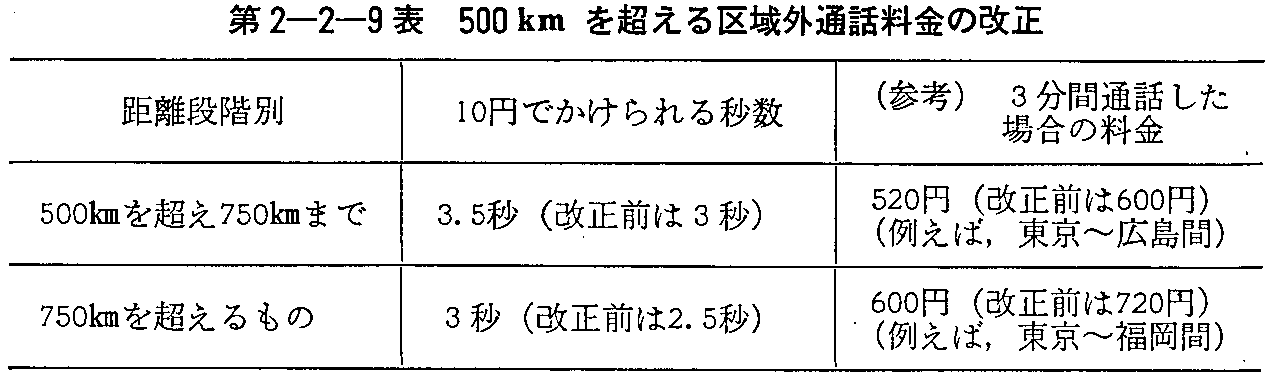
|