 第1部 総論
 第1節 昭和55年度の通信の動向  第2節 情報化の動向  第3節 諸外国における情報通信の動向
 第1節 災害対策の重要性と通信の役割  第2節 災害時における通信の役割  第3節 通信分野における災害対策  第4節 新しい通信システムの開発と今後の課題
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 情報処理技術
(1)ハードウェア
ア.本体系装置
コンピュータは,半導体技術の進歩を背景として,急速な性能向上とコストの低下を果たしており,汎用機種の場合,この15年間で演算速度は20倍に,主記憶装置のコストは70分の1になっている。
従来は主としてLSI等の素子技術の進歩により,演算速度の高速化を実現してきたが,今後は,先廻り制御,並列処理方式等の高速演算方式の開発が課題となっている。
記憶装置は,高速ICメモリと低速ICメモリとで主記憶を構成するという記憶階層方式が一般の大型機で採用されている。ここしばらくは,このような記憶階層が存続すると思われるが,ICメモリの低価格化に伴い,近い将来,高速大容量のICメモリのみで主記憶装置が構成される可能性がある。
また,主としてマイクロプログラムによりオペレーティングシステムの一部または,その他のルーチンをハードウェアとして実現するファームウェア化が進んでいる。これはハードウェアよりは機能の追加,変更に対する融通性が大きく,ソフトウェアよりは高速処理ができる特徴を有している。
コンピュータが社会経済活動のあらゆる分野に浸透してくるのに伴い,システムに対する高度の信頼性が要求されるようになりつつある。このため,ハードウェアに高度の障害検出,防止機能を持たせるとともに,オンライン中でも保守診断が可能な保守試験プログラムが開発された。
イ.通信制御処理装置及びファイル制御処理装置
情報処理機能の分散化傾向を反映し,従来,中央処理装置で行っていた通信制御機能及びファイル制御機能を個別に実行する通信制御処理装置及びファイル制御処理装置の開発が進められている。
通信制御処理装置は,メッセージレベルまでの処理を行うものであり,複数の回線を収容し,端末装置及び通信回線の制御や誤り検出・訂正を行い,メッセージのチェック,記録などの機能までを有するものである。
また,ファイル制御処理装置は,ますます大容量化するファイル系の制御を分担することにより,ファイルの効率的管理を行うほか,大規模データベースの効率的,経済的な実現に大きな威力を発揮するものと考えられる。
ウ.周辺装置
周辺装置は,大別してファイル記憶装置と入出力装置に分けられる。
ファイル記憶装置については,高速化・大容量化が進められており,1ギガバイト級の磁気ディスク記憶装置や1台当り数十〜数百ギガバイトの超大容量磁気記憶装置の実用化が進められている。また,高密度化,小型化による経済化をはかった数百メガバイト級の小型の磁気ディスク記憶装置の開発が進められている。
入出力装置は,さらに,高速化を目指すとともに,マンマシンインタフェースの改善を目指し,文字・図形・音声等による入出力装置の開発が進められており,音声応答装置及び音声認識装置が導入されつつあるほか,漢字入出力についても一層の高速化,高品質化が図られ,15,000行/分以上の高速漢字プリンタ等が出現している。
(2)ソフトウェア
ア.データベース技術
データの大容量化及び相互関係の複雑化に伴い,より効率的で使いやすい高度なデータ管理機能の必要性が高まり,複雑,大量のデータを一元的に管理して解決しようとするデータベースシステムの実用化が進んでいる。
この種システムの実現に当って,データの蓄積についての物理的配置や論理的関係づけを行うデータベース定義機能,データの検索,更新及び加工を行うデータベース操作機能等を備えたデータベース管理システム(DBMS)の開発が進められている。
イ.ソフトウェア作成及び維持管理の効率化
ソフトウェア量の飛躍的増大,保守費の急増,プログラム要員不足等の要因により,“ソフトウェアの危機”が叫ばれており,プログラムの生産性向上及び維持管理の効率化が重要となっている。
このため,システム開発用に処理効率の良い,きめ細かな処理も記述可能な高水準言語の開発を始めとして,ストラクチャードプログラミング等のプログラム開発技法,ドキュメント作成システム等の開発及び運用が行われている。また,遠隔地の端末からプログラム作成を行うリモートデバッグシステムや,1台のコンピュータで同時に複数の仮想コンピュータを作り出す仮想計算機システム(VM)が開発されている。
ウ.ネットワーク・アーキテクチャ
最近のデータ通信システムは,各種資源の分散及び共用,システム全体としての価格性能比の向上等をねらいとしたネットワーク化の進展が著しい。しかしながら,複数の計算機,端末などを通信回線で結合して効率的なデータ通信網を構築するためには,その構成方法,通信規約(プロトコル)の標準化等多くの問題を解決しなければならない。
これらの問題を個々のシステム対応ではなく,統一的に解決するネットワーク・アーキテクチャの技術開発が進められている。
この具体的な動きとして,郵政省では「汎用コンピュータ・コミュニケーション・ネットワーク・プロトコル(CCNP)」の開発を進め,55年度郵政省告示として発表した。
これはコンピュータ間通信を広く国家的立場から検討し,国際通信網との接続等も考慮した標準的なプロトコルの確立と普及とを目的としたものである。
その特徴は次のとおりである。
[1] 異機種コンピュータ及び端末相互間で資源の共用が可能である。
[2] 公衆パケット網との整合が考慮されており,公衆パケット網のもつ誤り制御機能,フロー制御機能,送達確認機能等を活用し経済化が図れる。
[3] 各レベルのプロトコルは,他のレベルのプロトコルと独立に変更,拡張が可能であり,アプリケーション指向の機能追加が容易である。
また,レベルの構成及び各プロトコルの概要を第2-7-12図,第2-7-13表に示す。
これに先立ち,電電公社では,52年度当初よりDCNA(Data Communication Network Architecture)と呼ばれる汎用ネットワーク・アーキテクチャの開発を,メーカ各社との共同研究の下に進めている。
53年度には,理論的モデルを定めた基本概念,データリンクレベル・プロトコル,トランスポートレベル・プロトコル,機能制御レベル・プロトコル及び仮想端末プロトコルがDCNA第1版としてまとめられた。54年度には,第1版の機能拡充とファイル転送/アクセス・プロトコルの追加等を行ったDCNA第2版が,更に55年度には第2版の機能拡充並びにジョブ転送プロトコル及びデータベースアクセス・プロトコルの追加を行ったDCNA第3版がまとめられ,当初予定した開発を終了した。
DCNAはさらに,将来のインフォメーション・ネットワークシステムの構築に向けて,符号,画像,音声など複数の通信形態が混在するデータ通信網に適用できるよう,55年度から機能拡充の検討が進められている。
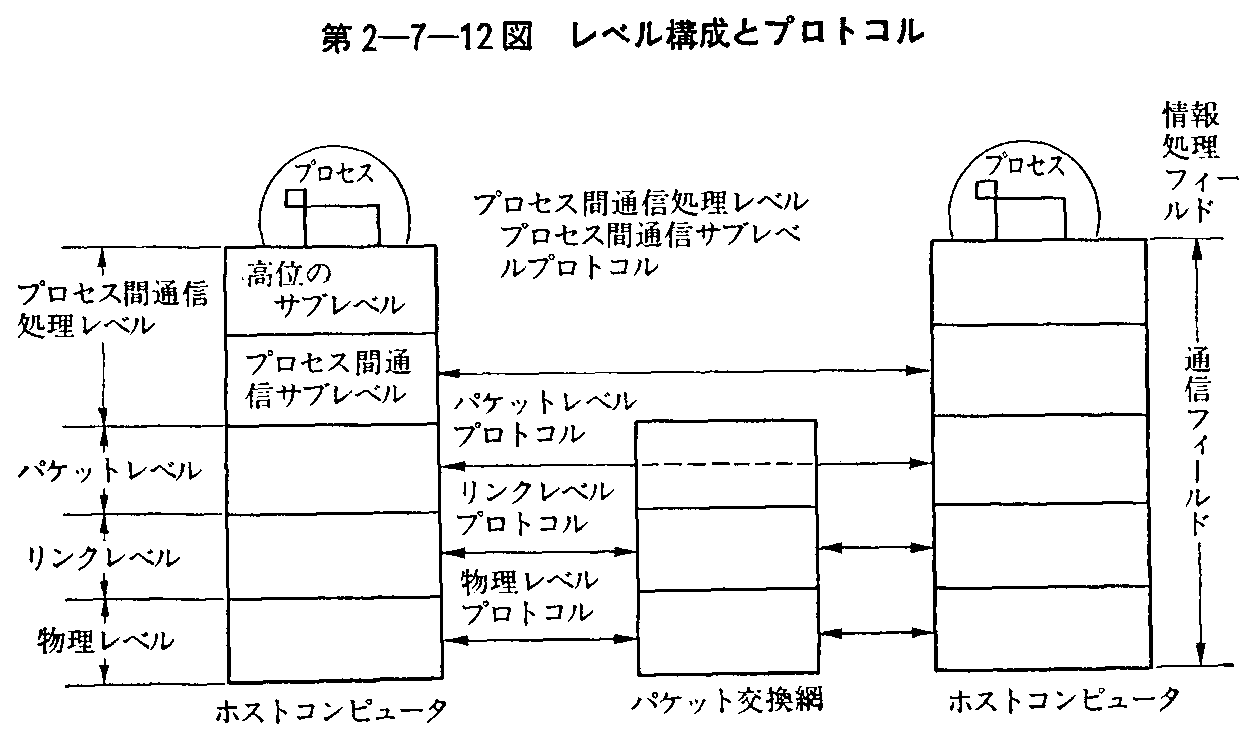
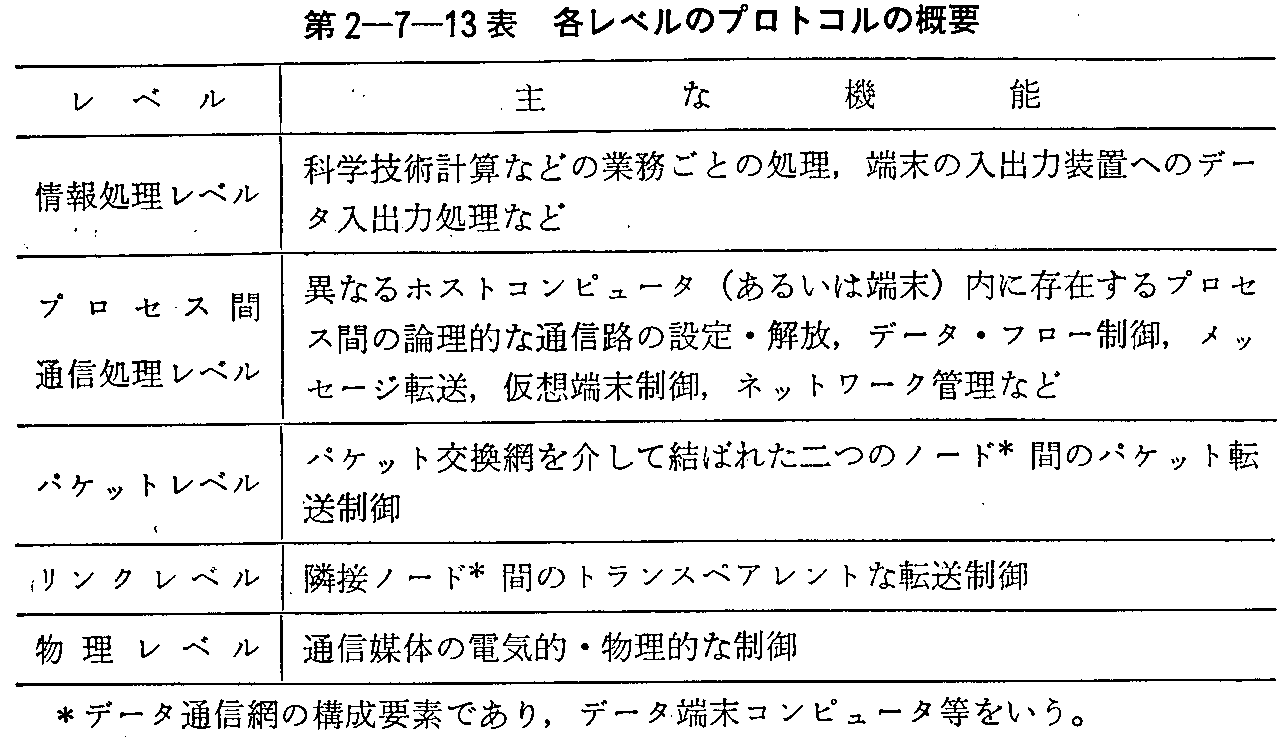
|