 第1部 総論
 第1節 昭和55年度の通信の動向  第2節 情報化の動向  第3節 諸外国における情報通信の動向
 第1節 災害対策の重要性と通信の役割  第2節 災害時における通信の役割  第3節 通信分野における災害対策  第4節 新しい通信システムの開発と今後の課題
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状  第3節 国際公衆電気通信の現状  第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況  第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況  第3節 データ通信システム  第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送  第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理  第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術  第3節 宇宙通信システム  第4節 電磁波有効利用技術  第6節 データ通信システム  第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関  第2節 国際協力
|
2 新サービスの開発計画の動向
(1) 電子郵便
近年,発達の著しい電気通信技術を用いて郵便伝送を行う電子郵便サービスは,我が国においては昭和56年7月から実験サービスを行っているところであるが,欧米諸国においても活発に開発が進められている(第1-1-20表参照)。
米国においては,米国郵便事業(USPS)が国内電子郵便サービスとして,1978年,コンピュータ発信電子郵便(ECOM)の計画を発表したが,その管轄権,システム計画等を巡り,米国通信業界はもとより,実業界に政界をも巻き込む一大論争に発展し,いまだ最終的な解決をみていない。しかし,USPSは,1982年1月にはサービスを開始したいとして,1980年8月,電子伝送サービスの設定又は廃止の管轄権を連邦通信委員会(FCC)とすることなどを内容とした郵便料金委員会(PRC)の再勧告決定(1980年4月)を基本的に受け入れ,RCA社とシステムの設計,建設の契約を締結するなど準備を進めている。なお,米国では,電子郵便を巡るさまざまな問題解決を図るため,1981年3月,電子郵便法案が下院に上程され,審議されている。
英国では,国際間のインテルポスト・サービスの拡大に対応して,1981年2月から国際電子郵便と同名のインテルポスト・サービスと呼ばれる国内電子郵便サービスを開始している。この国内インテルポスト・サービスは,英国全土の36の郵便局にG2及びG3規格のファクシミリ端末を設置し,郵便局間で伝送を行うもので, ロンドンの国際インテルポスト・センタでの再送信によって国際間のインテルポストに接続することも可能である。
西独では,1980年6月からテレブリーフ・サービスと呼ばれるファクシミリ型の電子郵便の試行サービスが開始された。このテレブリーフ・サービスは,西ベルリンを含む西独全土を対象にした試行サービスで,全国約600の郵便局にG2規格のファクシミリ端末を設置し,電話網を利用して郵便局間もしくは郵便局とテレファクス(ファクシミリ端末)利用者間の郵便伝送を行うものである。
一方,国際間の電子郵便サービスとしては,インテルポスト・サービスが,1980年6月から英国-カナダ間で開始され,その後,順次サービス地域が拡大され,現在,英国,米国,カナダ,オランダ,スイスの諸国がサービスを行っている。
(2)ビデオテックス
テレビジョン受像機と電話回線網を用い,情報検索サービス等を提供する新しい画像情報システム,ビデオテックスは,我が国では,キャプテンシステムとして,昭和54年12月から第I期実験サービスが開始され,さらに,昭和56年8月から第II期実験サービスが開始されており,昭和58年度から実用化される予定である。また,各国においても研究段階から大規模な実験サービスへ,さらには,商用化へと向かう急速な動きがみられる(第1-1-21表参照)。
世界に先駆けて,1979年3月からプレステルという商品名でビデオテックスの商用サービスを開始した英国の郵電公社(BPO)では,その後,サービス提供地域を18地域に拡大するとともに,さまざまな普及施策を講じた結果,1981年6月現在,端末機数は約1万台,提供情報画面数も約20万ページとようやく軌道に乗り始めた。また,国際間のプレステル・サービスも1981年7月から開始されているほか,写真等も伝送できるピクチャー・プレステルの開発が進められている。
フランスでは,現在,テレマティーク計画の名のもとに,郵電省(PTT)において,各種の新サービスの開発が進められており,ビデオテックスもその一つである。このうち,テレテルの実験は,1981年7月からパリ郊外のベリジー地区において開始されている。また,ビデオテックスを応用して電話番号案内を行う電子式電話帳サービスの実験は,1981年から本格的に開始され,1982年にイル・エ・ビレヌ県で商用化される予定である。
西独では,郵電省(DBP)が,英国からビューデータ方式のノウハウを購入してピルトシルムテキストという名称のビデオテックスを開発し,1980年6月からデュッセルドルフと西ベルリンで大規模な実験サービスを行っている。
カナダでは,通信省(DOC)が,テレテキストとビデオテックスを融合し,図形表示機能を高度化した独自のテリドン方式を開発しており,ベルカナダ電話会社等が,このテリドン方式を利用したビデオテックス・サービスの実験を開始している。
米国では,AT&Tが1979年8月から1980年1月までの6カ月間ニューヨーク州アルバニーでエレクトロニック・インフォメーション・サービス(EIS)という電子式電話帳サービスの小規模な実験を行った。また,AT&Tとナイト・リッダー新聞社等は,共同で1980年7月からフロリダ州でビュートロンというビデオテックスの実験サービスを開始している。
こうした各国の活発な開発競争を背景に国際電信電話諮問委員会(CCITT)では,ビデオテックスに関する国際標準化のための検討を進め,1980年11月の総会において,ビデオテックス業務に関する勧告及び会話型ビデオテックスのための国際情報交換に関する勧告を採択した。
(3)テレテキスト
我が国では,文字放送として開発が進められているテレテキストもヨーロッパ及び北米で活発な開発の動きがみられる。
ヨーロッパでは,既に実験放送あるいは定時放送を行っている英国のシーファクス及びオラクル,フランスのアンチオープ,スウェーデンのテキストテレビのほか,1980年6月から西独がビデオテキストと称するテレテキストの実験放送を開始した。また,オランダでも1980年9月からサービスが開始された。
米国では,1976年から1979年にかけて主としてテレビ会社が中心となり,実験サービスが行われてきたが,現在,その標準化が大きな問題となっている。米国連邦通信委員会(FCC)は,米国電子工業会(EIA)に特別委員会を設置し,勧告案を作成することを要請しているが,特別委員会内部で意見の対立があり,いまだいずれの方式を採用するのか勧告は行われていない。こうした中で,米国CBS社は,アンチオープ方式によるテレテキストの実験サービスを1981年4月からロスアンゼルスで行っている。
また,米国商務省電気通信情報局(NTIA)等は,カナダのテリドン方式を用いたテレテキストの実験サービスを,1981年からワシントンD.C.で行っている。
カナダでは,オンタリオ教育通信局(OECA)が,テリドン方式により,1981年8月からオンタリオ州で実験サービスを開始している。
(4)テレテックス
近年におけるマイクロ・コンピュータの急速な発達とワードプロセッサの普及を背景に,テレックス及びファクシミリ通信に加え,新たな記録通信サービスとしてテレテックスの開発が各国で検討されている。
このテレテックス・サービスは,テレックスを高速,高性能化したもので,編集,記憶機能を有するワードプロセッサに伝送機能を付加し,公衆通信網を介して,テレックスよりも高級なサービスを提供しようとするものである。
現在,最も開発が進んでいる西独では,1981年3月から西独全域で試行運用を開始しており,1982年から商用サービスを行う予定である。
このサービスは,我が国をはじめ,英国,フランス,スウェーデン,ノルウェー,イタリア,スペイン,カナダ等がそれぞれ開発を検討している。また,テレテックス・サービスの標準化も進められており,1980年11月のCCITT総会において,テレテックスの基本的な網サービス,端末及び端末プロトコルに関する勧告が行われている。
(5)ディジタル・データ網
近年,データ通信に適したネットワーク・サービスとして回線交換あるいはパケット交換方式によるディジタル・データ網サービスを提供する国が次第に増加しており,我が国では,既に電電公社が回線交換及びパケット交換方式によるディジタル・データ網サービスを提供している。
米国では,既にGTE/テレネット社,グラフネット社,タイムネット社,ITT・DTS社等の付加価値通信事業者(VAC)がパケット交換方式によるディジタル伝送サービスを行っている。一方,AT&Tは,従来から提供していたディジタル専用線であるデータホン・ディジタル・サービス(DDS)に加えて,56kb/sの回線交換方式によるデータホン・ディジタル交換サービス(DSDS)及びパケット交換方式による公衆データ網のACS(Advanced Communications Service)計画を発表し,開発を進めていたが,いまだサービス開始に至っていない。
また,サテライト・ビジネス・システムズ社(SBS)は,衛星を介してユーザ相互間を接続し,データ,画像,ファクシミリ及び音声の伝送を総合的に行うディジタル網サービスCNS-A(Communications Network Service-A)を1981年3月から開始した。
なお,衛星と地上用マイクロウェーブ技術を融合し,全国的規模のディジタル・データ網を建設する予定で,1978年以来,開発が進められてきたゼロックス社のXTEN(Xerox Telecommunications Network)計画は,1981年5月,経済的理由により中止された。
ヨーロッパにおける新たな動きをみると,英国では,郵電公社(BPO)が,1980年9月からパケット交換方式によるPSS(Public Packet Switching Service)のサービスを開始した。
西独では,郵電省(DBP)が,1975年から提供しているディジタル回線交換サービスDATEX-Lに加え,1980年8月からパケット交換サービスDATEX-Pの試行運用を開始している。
このほか,欧州共同体(EC)の国際パケット交換サービスであるユーロネット(Euronet)が,1980年2月から商用サービスを開始し,更にはEC加盟国以外のスイスへもサービスを拡大している。また,北欧4か国(デンマーク,フィンランド,ノルウェー スウェーデン)では,各国を横断する北欧公衆データ網(NPDN)サービスの提供が回線交換方式により計画されており,1981年の完成を目途に進められている。
(6)宇宙通信システム
従来,衛星通信は,国際通信分野での利用が主であったが,最近に至り各国において,国内通信や域内通信へと衛星通信システムの利用拡大が図られている。また,近年,直接放送衛星の実現への動きがみられるようになってきている。我が国でも,これまでの開発成果を踏まえて,通信衛星及び放送衛星の実用化が積極的に進められている。
米国では,国内衛星通信分野への複数参入を認めた1972年の「オープン・スカイ・ポリシー」以来,RCAアメリコム社,ウェスタン・ユニオン社(WUT),アメリカン・サテライト社(ASC),AT&T/GTEサテライト社(GSAT)が衛星を利用した国内通信サービスを提供してきたが,これらの初期参入通信事業者に加え,サテライト・ビジネス・システムズ社(SBS)が,1981年3月からサービスを開始している。
また,SBSに続き,ヒューズ・コミ.ユニケーションズ社(HCI),サザンパシフィック・コミュニケーションズ社(SPC)等の新規参入計画が相次ぎ有限な静止衛星軌道位置を巡る競争が激化してきた。このため,FCCは,1980年12月,各社から提出されていた25個の衛星製造と20個の衛星打上げの申請に対し,・一括して認可し,各社の衛星軌道位置を決定した。
今後,衛星通信サービスに対する需要の伸びや,経済性の向上,さまざまな新サービスの展開が期待されるが,一方,衛星の軌道位置の不足によって国内衛星通信事業の発展が損なわれることを回避するため,FCCは,軌道位置間隔の縮小,軌道位置の有効利用等の検討を開始している。
このほか,米国では,コムサット社の子会社であるサテライト・テレビジョン社(STC)により直接放送衛星の計画が進められている。これは,加入者の屋上に備えられた小型のパラボラ・アンテナに衛星を介して直接,有料のテレビジョン放送を行うサービスで,STCは,1980年12月,FCCに対し正式にサービス提供の申請を行っており,米国放送業界に大きな波紋を投げかけている。
フランスでは,郵電省(PTT)がテレマティーク計画の一環として,衛星通信システム,「テレコム1」計画を推進している。この計画は,[1]海外県と本国との電気通信網の充実,[2]直接通信方式による企業向け高速ディジタル・サービスの提供を主な目的とするものであり,1983年からのサービス開始を予定している。
また,フランスと西独は,共同で国内用直接放送衛星の計画をしており,西独のTV-SAT,フランスのTDF-1が,1985年からサービスを開始する予定である。直接放送衛星計画としては,このほかにルクセンブルグ等の独自の計画及び北欧5か国(デンマーク,フィンランド,ノルウェー,スウェーデン,アイスランド)共同の計画があり,1985年以降からサービスを開始する予定である。
なお,域内衛星通信計画としては,1983年サービス開始予定のヨーロッパ地域通信システム(ECS),1984年サービス開始予定のアラブサット及び東南アジア地域のパラパB等がある。
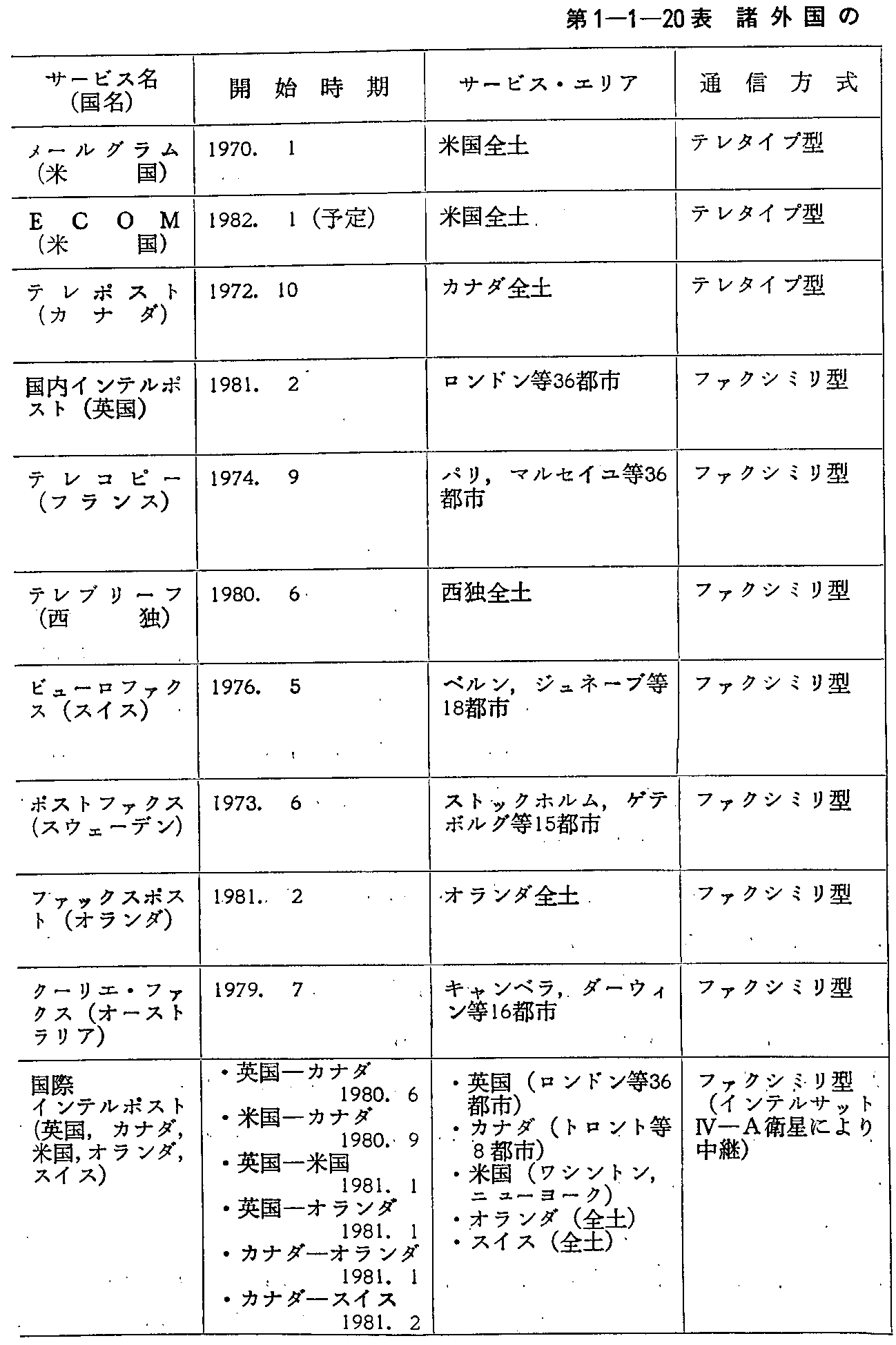
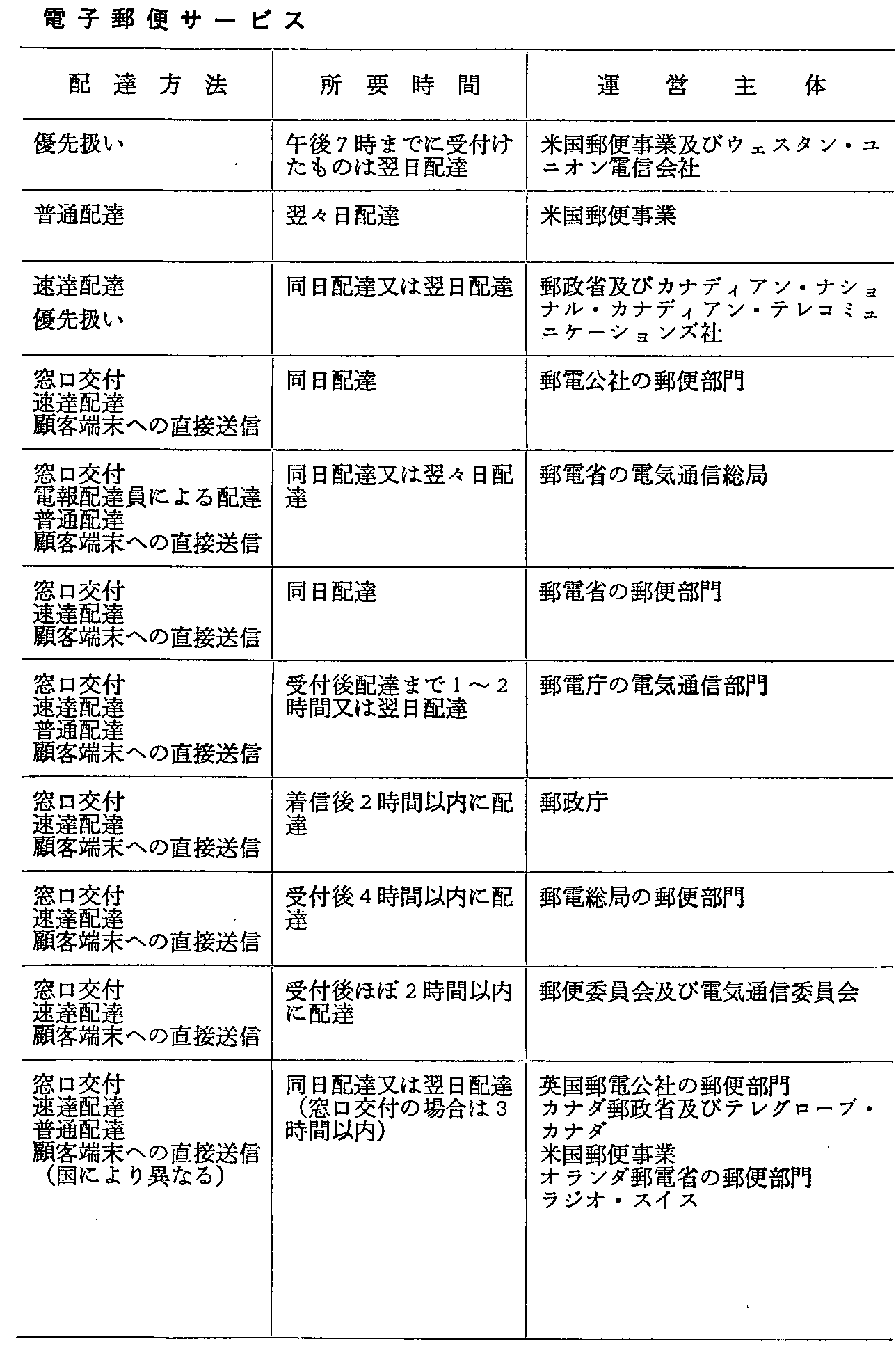
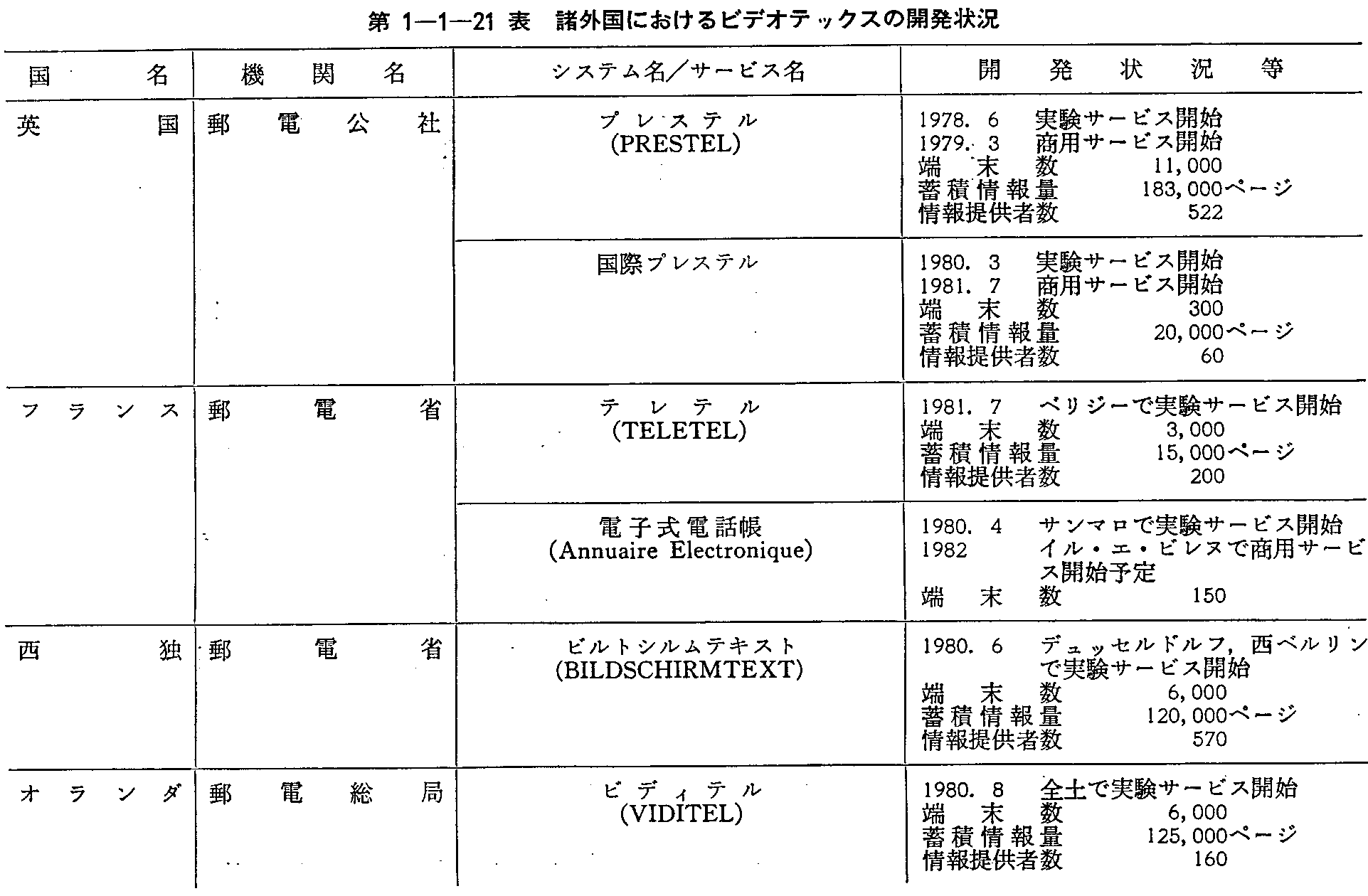
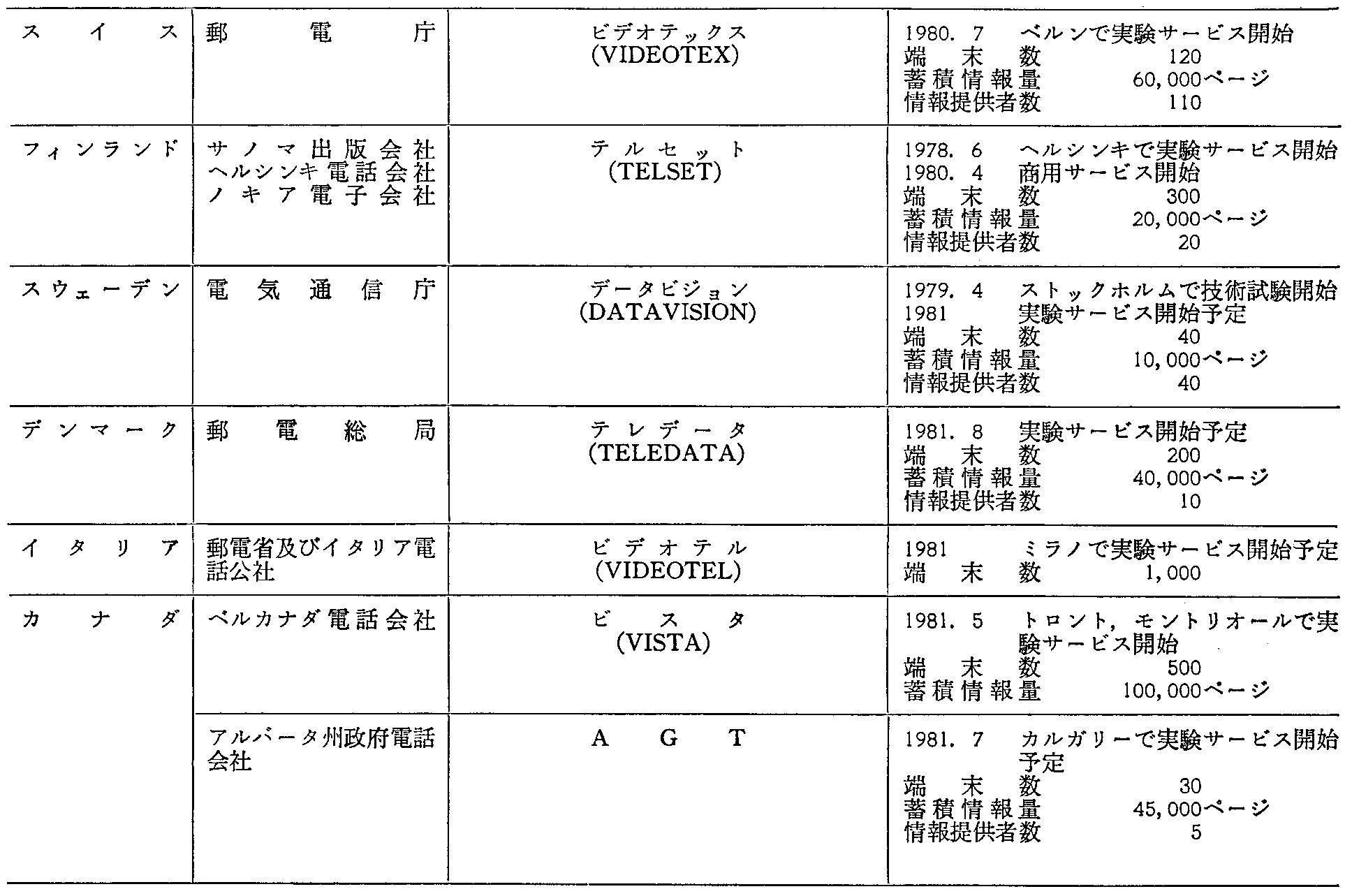
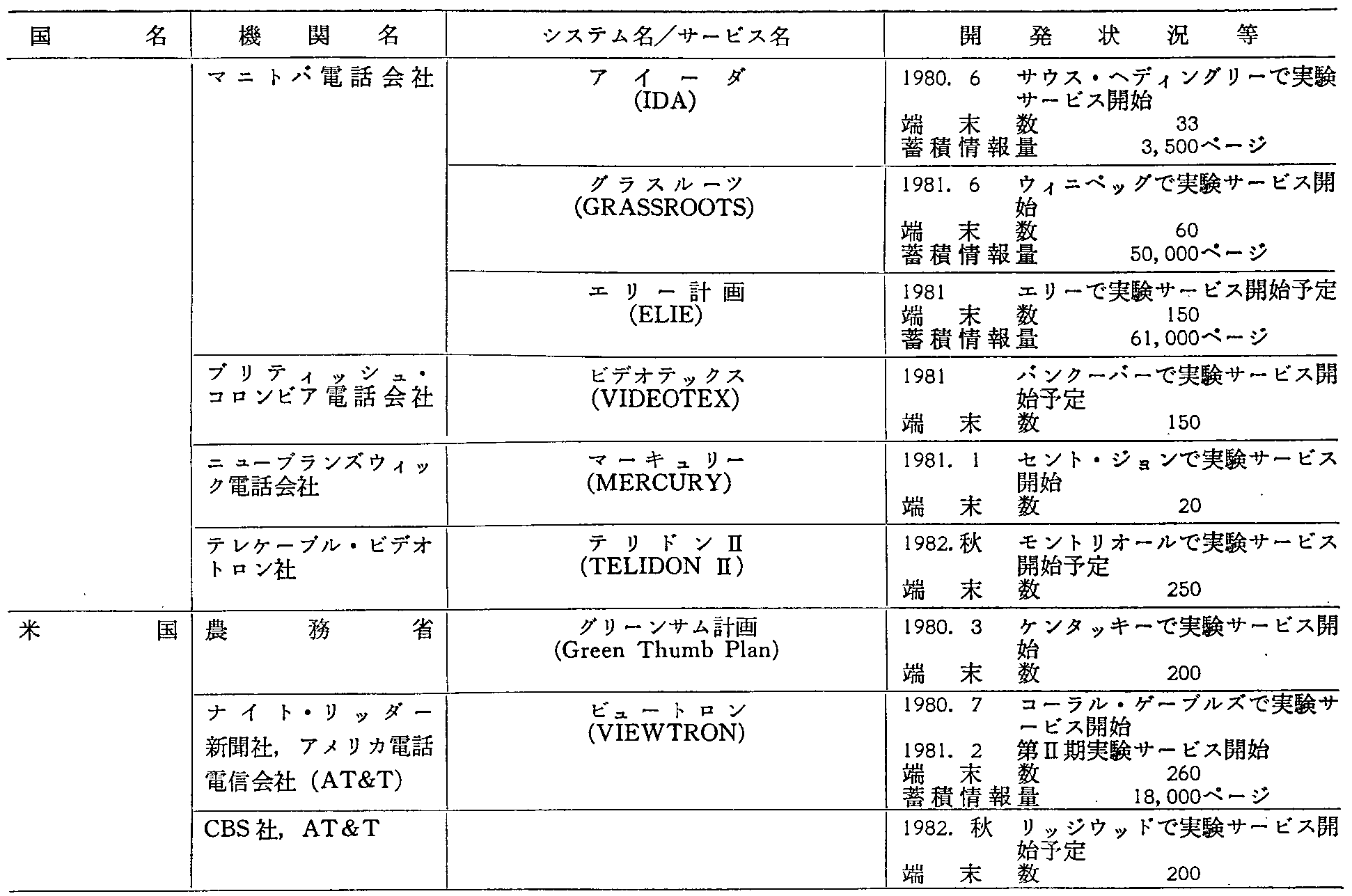
|