|
2 通信事業の財務構造50年度における各通信事業経営の状況を財務比率によってみると,第1-2-3表のとおりである。郵便事業では,収支状況が悪化しているため,借入資本への依存度が増大しており,この結果,固定比率及び負債比率が悪化した。また,郵便事業は人力依存度の大きい事業のため,労働装備率が他の通信事業や産業に比べて低い。 電電公社では,全国的な規模の設備を有する事業であることを反映して,総資産に占める固定資産の比率が約91%,労働装備率が1,642万円と高い値を示している。固定比率が384.5%と他の通信事業に比べ極めて高いが,固定資産対長期資本比率は94.4%と100%以内に納まっている。これは固定負債の額が大きいからであり,その大部分を占める電信電話債券は総資本の66.3%に達する。 国際電電では,51年1月に33億円増資を行ったことなどにより,50年度の固定比率及び固定資産対長期資本比率は前年度よりも若干好転した。また,労働装備率は対前年度比約36%増と大きな伸びを示したが,これは主として第二太平洋用ケーブルの完成によるものである。 NHKでは,郵便事業や電電公社と同様赤字決算が続いたため,負債比率の伸びが大きく,また,流動比率も大きく減少している。 民間放送では,他の通信事業や全産業平均に比べて固定比率及び固定資産対長期資本比率は低く,反対に流動比率が高い。これは民間放送事業が景気変動の影響を受けやすい放送広告に依存しているため,自己資本の充実を図ることによって経営基盤を強固にしていることによるものと考えられる。 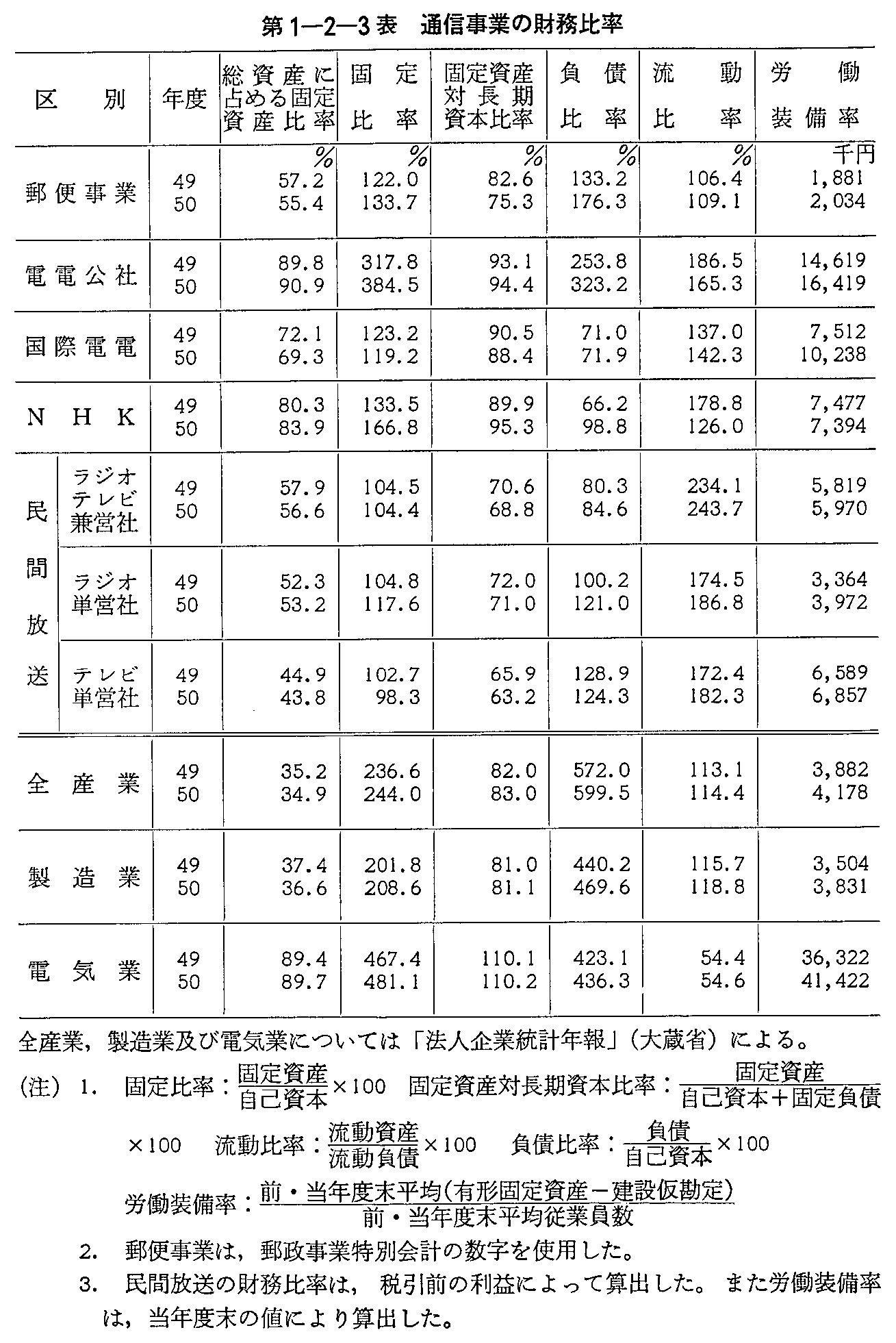
|